17 / 21
5章
3
しおりを挟む
3.ヴィクトール視点
浅い眠りに落ちては目覚めを繰り返す。後ろ手に縛られた手首がうっ血していて、痺れにも似た痛みが眠りから意識を連れ戻す。
知らない男たちに連れてこられたのは廃工場のようだった。サビだらけのベルトコンベアを背に寄りかかる俺を中心に10人ほどの男たちが銃を手に待機している。
寝たフリで盗み聞きした話によれば、俺を使って父親に身代金を要求したらしい。もうすぐその取引が始まり、これが上手く行けば彼らは幸せになれると信じて疑わない。
「俺たち野良犬が不幸なのは、このブラウンシュヴァイクとかいう奴らの管理がズサンだからなんだろ」
まるで見当違いの話をする男に、もう1人の男が頷く。
「よく知らないけど、犬の管理はコイツらがやってるらしいよな。なんで身代金なんだ?こんな小さいガキ、さっさと殺せばいいのにさ」
吐き捨てるように言うと、男は俺に近寄って腹を蹴飛ばす。内臓がせりあがるような痛みで俺は咳き込んだ。
野良犬たちには学べる場所がない。常識すらあやふやな彼らの間では、迷信じみた噂話が横行しているようで、俺たちブラウンシュヴァイク家が犬たちを不幸にしているという噂話は宗教のように一部で根付いているようだった。
うんと昔では、流行り病を魔女の仕業と信じて多くの女性を拷問の果てに殺した人間たちだ。学がなければ、そうなっても仕方ない話だろう。
夕方あたりにここへ連れてこられてから、度々理不尽な暴力があった。腹や顔を蹴られては、唾を吐きかけられたりと散々だ。今、自分がどんな顔をしているのか分からない。
「今日の取引が上手くいかなかったら、俺たちどうすんだ?」
「このガキを殺すってさ。その前にいたぶろうが犯そうが好きにして構わないらしいけど、今はとりあえず五体満足が相手からの条件らしいから、今は我慢だな」
1人が俺の前にしゃがむと、俺髪を掴んで引っ張る。
「いてぇ…やめろ」
「あんま美人じゃないけど、声はまだ子供っぽくて可愛いな。いっそ明日になるのもいいかもな」
俺の言葉など聞かずに中年の男が下品な声で笑う。
自分の意思で股を開いてきたが、さすがに浮浪者の慰みものになって死ぬのは勘弁だ。勘弁だが…あまり父親の助けを期待できないでいた。
明日までになんとかならなければ、過程はどうあれ俺が死ぬのは確定事項だ。あまりに唐突な死刑宣告で、最早涙すら出ない。
ベロアと結婚すると口約束でも、淡い未来を彼から貰ったはずが、まだ1日もたたずに取り上げるなんてあんまりじゃないか。
「そういや、そのガキが捕まえた黒人っぽい野良犬ってどうなったんだ?」
不意に眺めていた男が声を出す。彼の言葉に、俺の髪を掴んだままの中年が顔だけで振り返った。
「ああ、アイツか…金づる取り上げられて狼狽えてんじゃねえか?あんなに飼い犬になるのを拒否してたくせに、あっさりブラウンシュヴァイクの犬になるなんて所詮は金持ちに媚びたクソ野郎だ」
掴まれたまま、俺は頭を振って中年の手を払う。彼を睨みつけ、舌打ちをした。
「アイツを侮辱したら許さねえぞ」
「はあ?こんな状態で強気なもんだ」
男は俺の顔を掴み、そのまま頭突きを食らわせてくる。頭が悲鳴を上げ、脳みそがグラグラと揺れた。
「そんなにあの野良犬を信用してるのか?馬鹿じゃねえか!アイツはただの盗っ人だ、お前がどうなろうと、せびった物品持ってトンズラするに決まってる」
まだ揺れる視界の中でなんとか中年の男に焦点を合わせる。付け焼き刃で笑顔を作った。
「そんなことない。アイツはいつだって俺のヒーローだ。お前らとは違う」
首を傾け、嘲るように肩を竦め手見せる。
そうさ、ベロアはいつだって俺を助けて、守ってくれる。誰よりも愛情深く俺を愛していてくれる。
「お前の頭突きは、アイツが全力の半分で殴ったパンチの足元にも及ばねえ。筋肉ないってつれぇね」
ケタケタと声を上げて笑うと、男は立ち上がって俺の胸を足で蹴り倒し、そのままギリギリと踏みつける。
「いい度胸してんな!そんなに言うなら泣いて謝るまでボコボコにしてやろうか!五体満足ならなんでもいいんだろ!」
彼の言葉を皮切りに、他の男たちも寄ってくる。
身体のあちこちを蹴飛ばされ、踏みつけられ、痛みが引く前に次の痛みが襲う。もうどこを攻撃されているのか分からなくなる。
「死ね!お前が死ねば俺たちは幸せになれるんだ!」
「この悪魔め!」
罵倒を浴びながら俺は身体を丸めて攻撃から何とか逃れようとするが、大した防御にもならずに呻くことしか出来ない。
ベロアは俺のヒーローで、スターだ。彼を信じてはいるが、明日までに彼一人の力で俺を見つけるなんて非現実的すぎる話だろう。
多分、ベロアは来ない。きっと全力で探していてくれてる。ありがとうも言えないまま、こんな場所で惨めに死ぬのは悲しくて泣けてくる。
あのビデオは再生してもらえただろうか。色々手回ししておいて良かった。ビデオの中だけでも、ありがとうと大好きが伝えられて良かった。
腹を蹴られすぎて呼吸が出来ない。酸欠で頭が麻痺していくと、痛みも比例して薄れてゆく。
意識を失いかけたその時、天井から落ちてきた…上から叩きつけられたと言った方が正しい勢いで鉄板のようなものが落ちてきた。恐らくこの廃工場の屋根材のようで地面に叩きつけられたそれは大きくひしゃげている。
物凄い轟音に俺を囲んで痛みつけていた男たちは皆、手や足を止め、鉄板が落ちてきた方向に目を向けていた。
「テ、テメェ何モンだ!」
男たちの中の一人があげた声に、俺も痛みでギシギシする体を何とか起こして目を向ける。
抜けた天井から差し込む薄明かりに、スポットライトのように照らされた1人の男のシルエット。黒いノースリーブのベストから覗く太い手足と、フードからはみ出た揺れる長いドレッドヘアはよく知っている。
「べ…ロア…?」
やっとの思いで絞り出した声は小さくて、離れた場所に立つ彼に届くわけなんてないのに、俺の呼び掛けに答えるかのように薄明かりに照らされたヒーローは顔を上げて一瞬柔らかく微笑んだ気がした。
「こいつよく見たら、金欲しさにガキに尻尾振った恥さらしじゃねえの!」
「あ、ああ本当だ。野良犬の王だなんて持て囃されといて、こんなチビの言いなりだ。だせぇったらねえよ」
1人の嘲笑うかのような言葉を皮切りに、困惑していた彼らはまばらに笑い出す。
「どうせ大した事ねえ。こっちには武器も人数も居るんだ。だいちゅきなご主人様の目の前で嬲り殺してやろうぜ」
警棒のような武器を持った男が彼に飛び掛るのと、その男が俺の後ろに投げ飛ばされて、サビだらけのベルトコンベアがバキバキと音を立て形を崩すのがほぼ同時に思えた。
「なっ…おいテメェらボサっとしてんじゃねえぞ!」
刃物を持った男が彼にそれを振りかざし、また別の男が拳銃を向ける。
カンッという金属音で刃物を弾き回し蹴りで拳銃の男諸共蹴り飛ばされて、鋭い発砲音と共に地面に倒れた彼らはそのまま腰を抜かした様子で彼を指さす。
「な、なんだよアイツは!」
暴発した弾を受けたのか男のひとりは肩から血を流しながら怯えた様子で後ずさる。
「馬鹿野郎!相手は1人だ、一斉に仕掛けろ!!さっさと手足を切り落とすんだ!」
殺し屋にも似た風格を放つ彼に武器を持った男たちは次々に飛びかかっては、先の男たちのように簡単にねじ伏せられて地面に捨てられていく。
まるでそれは、数だけ多い敵の雑魚を次々となぎ倒していくような画面の中のヒーローショーだ。
地面に横たわって呻き声を上げる男たちの中、ついに残ったのは俺の傍にいた下品な中年の男だけ。
「は…?え…?何、なんで…こいつ使って俺たちは…」
彼は放心状態の男の胸倉を掴み床に叩きつけると、男が動かなくなるまで腹や胸を何度も何度も蹴りあげ踏みつけてから蹴り捨てた。
「…ヴィル」
多分数時間しか離れていなかったのに、彼にそう呼ばれるのが随分久しぶりに思える。
「ベロア…」
後ろ手に縛られたまま、力を振り絞って身体を起こすと、彼はすぐさま駆け寄り、俺の手を束ねていた縄をナイフで切る。俺の体を抱き支える彼を両腕で抱きしめた。
「…ごめん…ごめんヴィル…」
あんな強さを見せつけるような戦いを魅せた彼は俺を抱いたまま子供のようにボロボロと大粒の涙を流して泣き出す。
「俺こそ…ごめん」
ベロアの腕の中で自然と笑みがこぼれる。彼の体温が、いつもに増して暖かかった。
「お前、知ってたけど…めっちゃカッコイイね。今すぐぶち犯されたいくらいイケてた」
湿っぽくならないように冗談を交えながら、彼の胸に顔を埋める。
聞きたいことはたくさんあったし、なんなら死に際に見た幻という線も捨てきれないが、安堵と喜びが再び強い眠気になって俺意識を持って行こうとする。
「セックスより、今は疲れただろ」
眠気を促すような彼の優しい手つきで背中をトントンと叩かれて俺の意識は彼に吸い込まれるように闇へと落ちていった。
それからどれほど眠っていたのか分からない。筋肉痛とは違う鈍い痛みで目を開けると、そこは屋敷の自室だった。隣には見慣れた点滴ホルダーが立っていて、左手に刺さったチューブでつながっている。
ボヤける視界を反対に向けると、俺の右手を握ったまま子供のように眠るベロアの姿があった。
彼の目から頬にかけては透明な筋が残っており、目元は心做しいつもよりふっくらと赤くなっているようにみえる。
あんなにいつも強いのに、泣き腫らすほど心配してくれたのだと思うと、悪いとは思いつつ可愛いと思ってしまう。
点滴をひっぱりすぎないように彼に身を寄せる。首に顔を埋めたら、彼の匂いとほんのりと汗の匂いが香った。
ベロアの頬に自分の頬を擦り付けて、小さくキスを数回繰り返す。起こしたい気持ちもありつつ、起こすのは可哀想という気持ちの板挟みがすごい。
「ん…」
薄く開かれたまぶたの隙間から、彼の赤い瞳が覗く。
彼は瞳にぼんやりと俺の姿を映すと、手は繋いだまま勢いよく飛び起きて寝転んだままの俺をあたふたと見下ろす。
「ヴィル!大丈夫か!?体痛いよな、なんで俺寝て…いやそれより…無事で本当に…ほんとに…」
あわあわと早口で俺の心配をしたかと思えば、言葉の途中から涙ぐんで彼は目を擦って涙を誤魔化しているようだった。
「大丈夫だよ。心配してくれてありがと」
俺も彼の隣で身体を起こす。まあ痛いが、初めてベロアとセックスして抱き潰された朝と同じ程度の痛みだ。慣れっこと言えば慣れっこだった。
「アイツらの暴力なんか、お前のパンチの半分も痛くないぜ。ほら、怪我も大して…」
自分のシャツをまくると、腹がえげつない紫になっていて俺は静かにシャツで蓋をした。
「俺のはこの倍か…?」
「…うん、まあ…痛みの度合いは…。ほら、ベロアのは一撃だったけど、ちょっと回数多かったから今回は」
苦しい言い訳をしながら俺は眉を寄せて笑う。何か悔いるような顔で自分の拳を見つめる彼に、俺は誤魔化すように両腕を広げた。
「それより、ハグして!昨日ずっと1人でいて寂しかったからベロア充電!」
「体中痣だらけなのに、抱きしめなんかしたら痛いだろ…」
彼は困ったように笑うが、ガラス細工に触れるような慎重な力加減で俺を抱きしめた。
俺は力いっぱい彼を抱きしめ返す。昨日の死を覚悟したのが嘘のようで、嬉しくて気の抜けた笑い声が漏れた。
「…本当に助けてくれてありがとう。お前はやっぱり、俺の希望なんだな」
「…そんなこと」
俺の言葉に彼は少し自信なさげに言葉を返すが、少し黙り込んでから小さく笑いをこぼした。
「いや、そうだな。俺はお前の希望でスターでヒーローだ」
安心したような息を漏らす彼の胸に頬を擦り付け、温もりを堪能する。たった1日しか経っていないのに、どんなに抱きしめても足りない気がした。
「…そうだ、お前どうしてここに?」
ふと思い出して、俺は身体を少し離して彼を見上げる。
「ここは俺の屋敷だろ?なんで…ていうか、腕の怪我は?どうやって俺のことを見つけたの?」
1度口に出すと、次々に疑問が溢れ出す。まくし立てるように質問を重ねると彼は「少し落ち着け」と困ったように笑った。
「ヴィルが攫われたあと、お前の父親と会って話をした。その時、怪我の手当をしてもらったから腕は大丈夫だ」
そう言って彼は清潔な包帯が巻かれた腕を俺に見せる。
俺は彼の包帯を優しく撫でる。もしかしたら、やっぱり死にそうで夢を見ているのかと疑っていたが、この包帯の感触と傷の位置はあまりにリアルで、仄暗い気持ちが蘇ってきた。
「…ごめん、俺が足を引っ張らなければお前は怪我をすることはなかったし、俺が攫われることもなかった。面倒ばっかりかけて、本当にごめん…」
目を伏せて謝ると彼は俺の頭をガシガシと撫でる。
「面倒なんてあるか。大きな口叩いてお前を守りきれなかったのは俺の責任だ。こんなの怪我のうちにならない」
銃痕なんて普通は大怪我のうちだろうに、ベロアは包帯をパンパンと叩いて平気な顔で笑ってみせた。
「ははっ、さすが俺の大好きな狼さんだ」
その様子に笑いながら、再び彼の胸に顔をくっつける。
「…父親に会って、何か変なことされなかった?声帯取り上げるとか、殺すとか言われなかった?」
ベロアが父親に手を貸したのは、少しだけ驚いたが、そこまで大きな驚きにはならなかった。俺たち家族が仲良くあるよう願っていた彼なら、やりかねないとは思った。
問題は父親の方で、アイツがベロアをどうする気なのかだけが心配でならなかった。
「ヴィルが心配するようなことは何もなかったさ。それに、俺が思っていたほど考えのわからない奴でもない気がする」
彼は俺を安心させるように優しく背中を撫でる。
「…そうかな」
ボソボソと呟く。俺には本当に父親が何を考えているのか分からない。幼い日も、今も。どうして俺を助けたのか…あんなに見下していた野良犬という存在、今では俺の飼い犬ではあるがベロアのことなど、彼が一番毛嫌いする種類の犬のはずだ。
ベロアの手を借りてまで俺を助け出したのは、俺に新しい弱みを作る気なのか…それともベロアに?単純に資産を守りたかったなら、俺を切り捨てればいいだけの話だし、俺なんかより養子を取って跡継ぎに据えた方が余程楽だろう。
彼は俺の顔を覗き込むと、柔らかく微笑んで肩を叩く。
「人を呼んでくる、ヴィルの目が覚めたって」
そう言うと彼はベッドから立ち上がり俺の部屋から外へ出て行った。
まだ現実味に欠ける出来事が連続していて、俺はぼんやりと部屋の壁を見つめる。
ベッドから起き上がり、点滴ホルダーを手に姿見の前に立つ。額から右頬、右側の口の端を中心に顔は紫色に変色していて、口の端には血の跡がまだ少し残っている。多少は誰かが拭いてくれたのか、思いのほか清潔に見えた。
服を捲れば全身アザだらけだ。それでも、アザで済んだのだから、野良犬たちが非力であったことがよく分かる。ベロアの拳で作ったアザは触れるだけで骨が折れたのではと思うほど痛かったが、それに比べれば痛くない。
そんなことをやっていると、ノックが聞こえた。振り返ると部屋に顔を出したのは俺の母親だった。
「ヴィクター!」
彼女はいつものように目を丸くして俺に駆け寄るが、いつも以上にその目は困惑しているように見えた。
「ごめんなさい、遠方の会食に出かけていてさっき帰ったばかりなの…お父さんから聞いたわ。酷い怪我ね、痛む?」
そう言って俺の頬に優しく触れる彼女の手を、今日は振り払う気が起きなかった。
「…案外、大丈夫。見た目ほど痛くないよ」
母親の後ろからベロアが部屋に入ってくる。ベロアと母親に触れられた俺の目が合うとなぜだか彼は満足そうに笑みを浮かべる。
「私が無闇矢鱈にあなたの捜索を邪魔したせいで、あんな危険な集団と接触させてしまったんでしょう?やっぱり、もう少しお父さんに従うべきだったのかしら…」
目を伏せて母親は声を震わす。
この人は、いつも俺の父親に従う。絶対に口出ししたりしないから、俺をこうやって外に出したのは恐らく人生で初めて、父親に背いたことになるだろう。
どこか後悔を滲ませた口調のそれを聞いたベロアは彼女の背後で俺たちを見下ろす。
「そんなことはない。ヴィルはとても楽しそうだったし、オレンジが食べられるようになった。これはヴィルを守れなかった俺が悪い。母親の所為じゃない」
「オレンジが食べられる…?オレンジはあなたの好物じゃない。食べられないってどういう…」
俺の目を見つめる不安そうな母親の視線に耐えられず、俺は顔を背けて黙る。彼女はベロアに助けを求めるように振り返ると彼は不思議そうに首をかしげる。
「ヴィルは2年くらい前からお菓子以外食べられなくなったって言ってたぞ。知らないのか?」
ベロアの言葉に母親は目を見開く。再び俺に向き直って、目を背けたままの俺の肩を優しく揺すった。
「ヴィクター、本当なの?どうして早く言ってくれなかったの…みんな、あなたが好き嫌いしてご飯を残してるんだと…」
隠していたものを次々と暴露され、俺はどうしていいか分からずに黙り続ける。
本当は不意に飯を完食してやって、好き嫌いしなくなったと思わせて終わりにしてやろうと思っていたのに。
眉をひそめてベロアに視線を投げるとなにか不味いことを言ったのかと思ってるのか、少し肩をすくめて呟いた。
「…言ってなかったのか?言ったらダメか?なんでだ?」
俺は口をとがらせて俯く。もう白状するしかないようだった。
「…だって、拒食症なんて言ったらかっこ悪いし、母さんも父さんもより過保護になる。屋敷から出られなくなったりしたら困るだろ」
ブツブツと愚痴を言うように話す。
理由は本当にそのままだ。でも、あれだけ毎日トイレで吐いても誰も気にかけてくれないことに、理不尽な怒りや寂しさを感じていたのもまた事実だった。
俺みたいなのを、きっと察してちゃんと呼ぶんだろう。そう考えると、それは拒食症よりもっとかっこ悪い気がした。
「そんな、そう言ってくれたらもっと早く分かったのに…そこまで追い詰められて辛かったでしょう?気付いてあげられなくて、ごめんなさい」
母親が俺を優しく抱きしめる。ベロアよりも細くて繊細な抱擁は、小さい頃を思い出させた。
「ほらな、ちゃんと話したらすぐに仲直りできるじゃないか」
母親の背後で勝ち誇ったような笑みを浮かべる彼に俺はムッと口をへの字に曲げた。
「…別に、喧嘩してたつもりはないし」
「そういうの意地っ張りって言うんだ、テレビで見た」
ますます楽し気に笑う彼に、なんだか自分まで笑えてくるから不思議だ。
母親は顔を上げると、また優しく俺の頬を指先で撫でた。
「…本当に、ベロアさんには感謝してもしきれないわね。彼が居なければ、きっとあなたとこんなに話せる日はこなかった」
彼女は立ち上がり、ベロアに向き直ると深々と頭を下げた。
「本当にありがとうございました。あなたのことを最初は追い出そうとしてしまったこと、深くお詫びします」
「別に気にしてない。飯もうまかったしな」
「優しいのね…あなたはヴィクターにとってかけがえのない友人ね。どうかこれからも、この子の傍にいてあげて貰えないかしら」
彼女の言葉に俺は顔を上げる。
「頼まれたって離れたりしない」
そう言ってベロアは力強く頷いた。
「それって…」
そこまで言って俺は口を噤む。この先に期待の言葉を並べることに抵抗があった。いつだって期待して、叶わなくてを繰り返してきた。また、それが砕かれるのは、もうこりごりという恐怖があった。
母親は俺に振り返ると、にっこりと微笑んだ。
「私はベロアさんに正式にヴィクターの飼い犬になって欲しいと思っているの。本当は口をきいたりしてはいけないけれど、彼が話せなかったら今こうしていることも出来なかった。全部分からないままで、きっと状況はもっと悪くなっていたわ」
母親はベロアの手を控え目に取る。握手をするようにその手を握った。
「これからも、今のままのあなたでヴィクターをサポートしてあげて。お父さんには私からも頼んでみるから」
「まかせろ。母親も困ったら俺を頼るといい」
そんな話をしていると、再び部屋にノック音が響く。次に入ってきたのはスーツ姿の男…たしか宮下とかいう名前の父親専属のSPだ。
彼は深々と頭を下げて部屋に入ると、それに続いて父親が顔を出した。その背後からさらに長身の男。彼のことはよく知っている、藤崎だ。昨日の事件で大きく揉めたので、恐らく今は厳戒態勢で父親を守っているのだろう。
ついこの間、ベロアに怪我をさせた宮下はどこか気まずそうにしていたが、藤崎はいつものように父親に見えない場所に立つと、俺を見てにんまりと笑って見せた。
「…何故そんな場所で話している。怪我をしているんだから、寝ていなさい 」
お決まりの小言から始まる父親の言葉に、俺は大きくため息をついて首を横に振る。しぶしぶとベッドの中に戻って足を伸ばして座ると、父親は隣の椅子に座る。母親はベッドに腰掛け、ベロアはベッドに上がり込んで俺の隣に胡坐をかいて座った。
総勢6人もの来客に、さすがの俺の部屋もなんだか狭苦しい。
「具合はどうだ」
話し出す父親に、俺は眉をひそめて頷く。
「元気だけど」
「私の言うことを聞かずに外に飛び出すから、危険な目に遭うんだ。どうして反抗ばかりする」
父親の言葉は、さも俺だけが悪かったと言いたげで腹が立つ。最初から心配してくれてるとは思っていなかったが。
「自分の話したいことばっかり話すな。ヴィルの話はどうした。ヴィルがどうして外に出るのか、どうして反抗するのか、聞いたことあるのか」
俺を自分の胸に寄りかからせるように肩を引き寄せながら、圧の利いた声色で話す。俺を挟んでベロアと父親がにらみ合うのを感じた。
父親はベロアを暫く睨んでいたが、俺に視線を戻して鼻を鳴らした。
「反抗するのに理由があるのか」
珍しく父親が俺の話を聞こうとしている。俺がどんなに声を荒らげても聞く耳を持たないのに、ベロアは一体どんな手品を使ったのか…いや、手品を使えるほどベロアは器用じゃないから、別の手段を取ったのだろう。
「…俺は、今の奴隷制度が嫌いだ。だから、父さんのように犬を物みたいに扱うのは無理だ。跡継ぎになんかなりたくない」
目を伏せて、足の上に置いた手を弄る。父親の顔を見るのは嫌だった。
「苦しんでいる犬を助ける手段が、俺には殺すことしかなかった。殺していくのを繰り返すうちに飯が食えなくなって…このまま家にいたら死ぬと思った。だから…」
「だからベロアさんを見つけてきたのよね」
ふと、黙っていた母親が言葉の続きを汲む。顔を上げると、彼女は柔らかく微笑んでいた。
「ベロアさんは本当にいい人です。お勉強をする機会がなかったから、2階から飛び降りたり、裸で廊下を歩いたりしてましたが…それでも、全力でヴィクターを支えてくれるわ」
「もう裸で歩いたりはしなくなったものね」と彼女がベロアに言うと彼はバツが悪そうに肩をすくめて苦笑いする。
父親は訝しげに母親を見つめていたが、彼女はそれを真っ直ぐに見つめ返す。
「彼が野良犬だから、マナーに欠けるからというのはよく分かります。でも、学べば良いだけの話ではありませんか」
柔らかいその口調に、父親は毒気を抜かれたように目を丸くしたが、それでも表情を再び険しくして口を開いた。
「しかし、口をきく犬など…世間体はどうなる。ブラウンシュヴァイクの看板を背負っているんだ、粗相は許されない。大体からして、ヴィクトールと過ごした時間そのものが短いだろう。まだ我々を騙しているだけの可能性も…」
「失礼を承知で、一つだけよろしいでしょうか」
不意に、部屋の壁際に立っていた宮下が声を上げる。振り返る父親の表情がますます険しくなるが、宮下はそれに怯まずに続けた。
「彼が持つヴィクトール様への好意は本物かと思います。短い時間ではありましたが、私のような下の者まで欺けるほど、彼は知能が高いように思えません。ご主人様も彼の知能を低く思われているなら、そこは共感頂けるのではないかと感じております」
宮下が手話で藤崎に「彼は頭が悪いが、愛は立派だ。そうだよな?」と伝えると、藤崎は言葉にならない言葉を発しながら「わかる、いい人」と口を開けて笑っていた。
直訳すればベロアを馬鹿だと言っているのだが、父親には効きそうな理由付けだ。俺は苦笑いしながら手話で2人に「ありがとう」と伝える。
「…お前、手話できるのか?」
俺の手を見て、父親が眉を寄せる。彼に目線を合わせ、俺は小さく頷いた。
「そうだけど…できないと藤崎と会話できないじゃん。通訳できる人間は多い方がいい。父さんはあまり人の話聞かないから、必要ないのかもしれないけど」
俺の言葉に父親はしばらく目を開いたまま黙っていたが、深いため息を吐いて首を振った。
「ヴィクトールこそ、あまり人のことを考えない配慮の欠けた子だと思っていたよ。あんなにだらしない関係の友人ばかり作って…」
だらしない関係の友人とは、おそらくセフレのことだろう。それに関しては耳が痛いが、配慮が欠けているとは心外だ。
「ヴィルはすごく優しいし頭もいいぞ、それに軽くて肌がすべすべだ」
少し前のめりで口を開いた彼から、簡単な言葉ばかりではあったが擁護が飛び出す。肌と軽さは関係ないが、良い場所を挙げてくれてるには変わりない。
「俺が子供たちよりも食器を使うのが上手くなくて悔しかったときは食べさせてくれたし、練習だって付き合ってくれた。俺たちが困らないようにって文字の読み方と書き方も教えてくれた。凛は女の子だからって、特別にいい匂いシャンプーだって買ってくれた」
子供たちという言葉に父親は訝しげに目を細めたが、とりあえず聞く気はあるようで黙っていた。
こんなに長いこと自分の言葉を話さない父親を俺は久しぶりに見たような気がする。
「俺がわがまま言っても叶えてくれる。俺が約束破ったこと、怒ったけど最後はちゃんと許してくれた。そんなこいつが俺が必要だって言った。だから俺はヴィルを守るって決めてる。だからずっと恋人やるって結婚もするって約束した」
「おい、結婚の話までせんでも… 」
恋人と結婚のワードまで飛び出し、俺は思わず彼の胸を叩いて苦笑いする。恐る恐る父親の顔を見ると案の定、渋い顔で俺たちを見つめていた。
「…この家業をしながら、犬と籍を入れることの重大さは分かって言っているのか?売り物に恋愛感情を抱いて結婚するなんて、頭がイカれた人間と思われても仕方ない」
「ベロアは売り物じゃない。身分なんか俺は気にしてないし、同じ人間って生き物であることには変わりないだろ」
父親に反論しながら、俺はベロアを見上げる。ベロアは俺の顔を見ると愛おしそうに微笑んで、俺の頬を撫でた。
「相手が金持ちじゃないといけないってルールはないだろ。ベロアは世界に1人しかいないし、ベロア以上の人間なんか地上もひっくるめて世界中探してもどこにもいない。俺は…ベロアがいい」
深くシワを刻み込む父親の顔を睨む。
「ベロアじゃないと嫌だ。そうじゃないなら、誰もいらない」
俺たちの話を静かに聞いていた母親は驚いたように口に手を当ててベロアを見る。
ベロアはあくまで堂々と俺を抱き寄せたまま、いつものように俺の頬に自身の頬を擦り付けた。
「恋人同士だったのね、ちょっと驚いちゃったけど…ヴィクターが選んだ人なのよね?」
目を丸くしたままの母親に俺は頷いて見せる。彼女の驚いた表情は次第に柔らかい笑みになり、彼女はゆっくりと頷いた。
「…お付き合いしてみたらいいじゃない。それで本当に2人が幸せになれるなら、結婚しなさい」
「お前!なんてこと…」
「私、恋愛結婚って憧れだったのよ。素敵な人がいて、自分で選べるなんて本当に幸せよ」
母親に父親がくってかかるが、母親の言葉にバツが悪そうに目を伏せた。
母親と父親は政略結婚だ。母親は一流のブリーダーの娘、父親はブラウンシュヴァイクの跡継ぎ。互いのことをまるで知らずに結婚したと聞く。
そんな母親から恋愛結婚が良かったと聞くのは、さすがに胸にきたのかもしれない。
母親は父親の手を握り、彼の目を優しく見つめた。
「誤解しないで、あなたと結婚したのを不幸とは思っていないし、私は幸せよ。でも、ヴィクターには好きな人がいて、思いあえているなら、その夢を砕くのはあなただって心が痛いでしょう?」
父親は口を曲げるが、黙り込む。俺はてっきり、母親が父親の言いなりなのだと思っていたが、もしかすると本当は逆なのかもしれなかった。
「私はあまり頭が良くないから…あなたの言うことに従う方がヴィクターを幸せにできると思っていたのよ。だけど、ベロアさんからちゃんとお話を聞いて、ヴィクターの様子を見ていて、2人を離すことは賛成できないと感じたの。だから、まずは様子を見たっていいじゃない」
母親は父親の手を撫でながら、俺たちに振り返る。彼女は困ったように笑って首を傾けた。
「私たち、話す機会があまりに少なかったわ。お父さんだってヴィクターのことを沢山考えているの。それだけは分かって?」
俺は口をへの字に曲げて、視線だけでベロアを見る。
「次は母親と父親が話してくれる。そうやって納得できるまでたくさん話すといい」
大丈夫だと言いたげに彼は強めに俺を抱きしめた。
なんだよ、こんな時ばっかり大人っぽく振舞ってさ。なんて、やっかみにも似た感情が湧き上がるが、ベロアの言うことは最もだ。最もだし、なんならベロアがいなければこうはならなかった。俺はため息をつきながら、口元で笑みを作った。
「…分かった」
俺の言葉に母親はにっこりと笑うと、父親を引っ張って立たせる。立ち上がった父親はまだ不満そうに俺を見ていたが、ベロアに視線を投げる。
「条件がある。息子と結婚を前提に付き合うのなら、屋敷に戻りなさい。その…子供?お前の連れ子なのかなんなのか知らんが、仮にも息子の婚約者を名乗るなら最低限の常識くらい勉強しなさい」
そこまで言ってから扉の前に立ち、父親はもう一度振り返る。
「お前たちが危険にさらされたら、ヴィクトールがまた家出する。お前たちのためでなく、息子のためだ。勘違いするな」
まるで捨て台詞のように言って部屋を出た父親を見て、母親は困ったように笑いながらついて行く。
ずっと壁際で手話をしていた宮下と藤崎は笑って手話で俺たちに言葉を伝え、その後に続いた。
「なんて言ったんだ?」
「ご結婚おめでとうってさ。ウケんね」
宮下と藤崎が残した言葉に笑いながらベロアに通訳する。
「ウケるのか?結婚するんだからおめでとうでいいじゃないか」
彼はにやりと笑って後ろから抱きしめたまま俺の首元にキスをした。
首元は弱いので、ムラムラしないように笑って彼を優しく押し返す。
「ところで、父親があんなこと言ってるけど…子供たち、どうする?信用できる?」
俺はまだ信用しきれてはいないが、あれだけ俺の意見を受け入れる父親は初めて見た。検討するべきだとは俺も思ってはいる。
「いいって言うならいいんじゃないのか?子供たちとも、お前の両親とも近くで暮らせるのは、すごく幸せなことだと思うぞ」
何も心配していないという様子で「また引っ越ししないとだな」と彼は笑った。
「それなら連れてきて貰うべきかな…なんか知らないけど、俺って今よく分からない連中に狙われてるんだろ?子供たちも巻き込まれたりしないかな」
昨日の集団がきちんと捕まるなり、解散するなりしていれば安心できるのだが、父親が家の中までSPを連れているのを見てしまうと、あまり解決しているようには思えなかった。
「それじゃあ俺が出かけてる間は誰がヴィルを守るんだ?」
訝し気に目を細めて彼は俺を抱きしめる腕に少し力を入れる。
「まあ…お前がいない間はきっと別の護衛がつくよ。この様子じゃ屋敷中、見張りだらけだろうし…子供たちを放っておくわけにもいかないだろ?」
心配してくれるのはとても嬉しいが、もし彼らがビデオレターを再生してたりしたら、完全に遺言だ。早く元気な姿を見せて安心させるべきだろう。
「それは…そうだけども…」
ベロアは子供たちが心配な反面、ますます俺に対して過保護になっているようで一向に煮え切らない様子で唸る。
「絶対に攫われたり殺されたり、殴られたりしないって約束できるんだな?」
「絶対…絶対かあ…」
彼の言葉に苦笑いしか出ない。実際、俺には戦う術がなくて、足を引っ張ったあげくに全身アザだらけだ。守れない約束に「絶対」と言う枕詞は付けられない。
「絶対じゃないのか?」
じっとりと睨むような彼の視線に目を逸らし、ふと思いつく。
「…てか、親公認なら車出して貰えばいいじゃん」
今までベロアとの関係はどこまでも親に秘密として通していたが、もう親の目を気にする必要がないなら、使用人に頼ったっていいだろう。
「俺、あんまり今は動き回れる自信ないけど、何かあっても大丈夫?絶対、足引っ張るよ」
ただでさえ足でまといなのに、こんなに身体が痛くては一層に足でまといだ。俺が彼を見つめると、彼は俺の頬に顔をぐりぐりと押し付けて答える。
「絶対大丈夫だ。もう二度とこの手は放さない」
しっかりと握られた手を撫でるように親指を動かす彼の手を、俺はそっと握り返す。
「じゃあ、そうしよ。迎えに行こうか」
俺がベッドから立ち上がろうとすると、床に足が付くより先に身体が持ち上げられる。
「動くと父親に怒られるぞ」
俺を抱き上げたベロアは、悪いことを企むようなにやりと笑う。
こうやって抱き上げられる機会が多いベロアとの時間は、なんだか自分が小動物にでもなった気分になるが、嬉しいのでそれに甘えておく。
使用人に頼んで車を手配してもらい、家にある犬用の首輪を3つ、荷物に入れた。子供たちを飼い犬扱いはしたくないが、野良犬状態で連れていくよりよっぽと安全だろう。
父親は俺が出かけると知って無言で宮下と藤崎を俺たちにつけ、目立たないように用意されたお忍び用のワゴン車に乗り込んだ。
藤崎とベロアはいつの間にか肘で小突きあう友人のような関係になっていて驚いた。宮下は運転で忙しかったので主に俺が通訳をしたが、体術や格闘技の話をしていて、俺にはちんぷんかんぷんだった。
車をあの小さな平屋の前に停めると、窓の外を覗いていた小さな顔が慌てた様子で引っ込むのが見えた。
俺とベロアが車から降りて家に近づくと、また恐る恐る覗いた顔がパッと明るくなる。窓を開け三人が飛び出して駆け寄ってきた。
「ヴィクター!!」
「ヴィーおにーちゃん!」
子供たちは驚いたり、泣きそうだったりいろんな表情を見せるが、3人とも嬉しそうに俺の足にしがみつく。
「ごめんごめん、心配かけたな」
しゃがんで1人ずつ頭を撫でたり、抱きしめたりすると、ようやく生還したんだなという実感が湧いてくる。
俺の顔や腕に出来た擦り傷やアザを見て、3人はまだ少し心配しているようではあったが、初めて出会った時も顔に青あざを作った状態だったせいか、すぐに気を取り直してくれた。
「これからみんな、俺の家に引っ越して欲しいんだ」
俺を囲んでいた子供たちは皆目を丸くして互いに顔を見合わせる。
彼らに首輪を見せる。本当は付けたくないし、嫌われそうで嫌だが、言うしかない。
「…嫌かもしれないんだけど、みんなの安全のために俺の飼い犬になって欲しい。ベロアみたいに自由にしてていいから」
笑みを浮かべたまま目を伏せる。
「うん、いいよ」
最初に声を上げたのは颯だった。俺が持っていた首輪のうち赤い首輪を取り上げて二ッと笑って見せる。
「俺赤がいい!赤はヒーローの色だもん!」
「じゃあ僕、青がいい」
颯に続いて匙も青い首輪を指さして、大きな目で俺を見つめる。
2人の様子に俺はほっと息をつく。颯に赤い首輪を付け、匙には青い首輪。苦しくないように様子を見ながらサイズを調整する。
「私は…」
颯と匙に首輪をつけてやっている一歩後ろで、凛が暗い顔をしてうつむいていた。黙り込んでしまった凜にベロアが近づき頭を撫でた。
「ヴィルなら大丈夫だ」
「…うん…わかってるの」
彼女は俺の手に余った最後の一つを見つめて下唇を噛み締める。凛が何におびえているのかはわからなかったが、あまりいい思い出でないことは確かのようだ。
「ごめんな。本当は俺も付けたくないんだ。でも、何もないままはぐれた時が1番怖い。協力してもらっていいか?」
凛を招き寄せ、彼女の小さな手を握る。何があったのかは分からないが、野良犬をやっているくらいだから辛い思い出の1つや2つあって当たり前だろう。
不安にならないように俯いた彼女に俺は微笑みかける。
「することはいつもと変わらない。みんなと遊んで、美味い飯を食べて、たまに勉強する。首輪があれば、外にだって出掛けられる。俺はみんなと一緒に街を歩きたいな」
凛は俺とベロアを交互に見て不安そうに眉を下げる。ベロアが彼女の背中を優しく押すと、凛は改めて俺を見つめて首輪がつけやすいように少し背伸びをした。
「私も…お外歩きたい」
「うん、一緒に可愛い服とか買いに行こうな」
凛に黄色い首輪を先の二人と同様、苦しくないようにつけてやった。
彼女は付けられた首輪を確認するように撫でて、安堵の溜息を吐いた。
「ヴィクトール様、家具などの運搬は他の者に頼みますので、彼らを連れてお車へ」
背後にいた宮下が俺の傍に歩み寄って頭を下げる。それに立ち上がって頷き、凛の手を引いて車へとゆっくり歩き出す。
「ベロアは他の2人を」
俺の指示でベロアがいつものように匙と颯を両腕に抱き上げた。先に彼らが乗り込むのを見届け、凛に笑いかける。
「もっと綺麗な家に行くだけだ。心配するな、なんかあれば俺たちが守るから」
「…うん、ありがとうヴィーおにーちゃん…!」
不安そうな事には変わりないが、それでも彼女は精いっぱいの笑顔を作って見せた。
ベロアたちは1番後ろの列の座席へ、俺たちは真ん中の座席に座る。車に乗り込み、不安そうに身体を縮こまらせていた凛に、助手席の藤崎がポテトチップスを笑って彼女に差し出した。
藤崎は聞き取るのが難しい発音で彼女に声をかける。凛は驚いたように俺の腕にギュッとしがみついて身を引いた。
「彼は耳が聞こえないんだ。でも、怖い人じゃない。おひとつどーぞって言ってるよ」
俺が通訳すると凛は恐る恐る彼の差し出したポテトチップスに手を伸ばし手に取った。
きゅっと目を閉じてそれを口に入れると、安堵と喜びの混ざったような控えめな笑顔をこぼした。
「おいしい…ありがとう、おっきいおにーちゃん…!」
凛の笑顔に親指を立てて藤崎は豪快にわらう。車の中はコンソメの匂いでいっぱいだった。
屋敷に着き、庭先に車を置いて中へ入る。行く先々にいる大勢の監視役が俺たちに頭を下げる様に子供たちはぽかんと呆気にとられる。
今日は会食から帰ってきて時間があるのか、庭先で花を弄っていた母親が俺たちの帰宅を聞きつけて、後ろから顔を出した。
「あら!小さいお客様ね!」
彼女は土のついた手袋をエプロンのポケットにしまうと、1番近くにいた颯の前でしゃがんだ。
「え、だ、だ、だれ…!?」
俺たちに振り返る彼に俺は肩を竦める。
「俺の母親だ」
母親はその隣にいた匙に手招きをし、頭を撫でる。
「やだあ、可愛い!小さい頃のヴィクターを思い出すわ。みんな、中庭でお茶でもどう?この間、植えた向日葵が咲いたのよ。とても立派だから見ていかない?」
懐かしがるように匙の頬をこね、颯の手を撫でたりと忙しくはしゃぐ彼女に俺は苦笑いする。
「お茶…あ、それ知ってる!おやつの時間って意味だ!」
「おやつ…!」
母親の周りをはしゃいで跳ねまわる少年たちとは対照的に凛は俺の後ろに身を隠したまま出てこない。
「おやつなら俺も食べたい」
子供たちに混ざってベロアまで混ざって母親を囲むようにうろうろと歩き回っている。
「みんなでおやつだって」
凛の頭を撫でながら笑いかけると、彼女もおずおずと母親の前に歩き出る。
その様子はまるで少し前に、俺が初めて子供たちに出会った時に似ていた。
「あら!ヴィクターの後ろに可愛い子がいるわ。一緒にお茶はどう?昨日貰ってきた美味しいクッキーがあるの」
母親は凛を見付けると、おいでと言うように両手を控えめに開いた。
凛はゆっくり母親に近づいて、彼女の手にそっと自分の手をのせて、握る。
「あ!いーなー!!俺も俺も!!」
「僕も、僕も…!」
母親の両手を奪い合うように空いた手に颯と匙が群がって手をつなぐ。
母親が子供好きなのは知っていたが、久しぶりに訪れたモテ期に顔を綻ばせている。随分と楽しそうだ。
彼等が楽し気に中庭に向かう後ろ姿を見ながらベロアが俺に寄ってくる。
「子供たちもお前の母親も楽しそうだ。連れてこられてよかった」
「思っていた以上にどちらも順応してて、むしろ俺が置いてけぼりだ」
肩を竦めて笑い、俺たちも母親と子供たちを追って歩き出す。
「…ああいうのを見てると、昔を思い出すよ。うんと小さい頃は、俺も母親が好きだった」
いつからか母親がそばに居る時間が減って、話すことも分からなくなって、何を考えてるのかすら分からなくなって、ただ父親に従う彼女がいつからか嫌いになっていた。
「母親が変わったんだと思っていたけど、ああして見ると案外昔と変わらないもんだ」
「また好きになれる。いや、好きって言えるようになるさ。きっとヴィルだってホントは昔と変わらない」
彼は俺の頬を撫でて微笑んだ。遠目に母親と子供たちを見つめる彼の瞳は満足げな反面、どこか寂しそうに見えた。
彼の言葉に、俺も笑って彼の手を握る。親離れしていく子供の親は、こんな気持ちなんだろうか。
「…お前の母親にも会ってみたかったな」
ふと、独り言のような言葉が口から漏れる。ベロアの母親はもういない。いや、生みの親が生きていたとして、姿を見せない母親にはあまり期待できない気もする。そう考えると、死んでしまった母親に会えないのは酷く残念に思えた。
「ああ、俺も…会いたいし、会ってみたい」
期待していない願いほど、案外口に出すのは簡単だったりする。笑って呟いた彼の言葉もきっとそうだったんだろう。
俺は彼の母親を探すと約束したのに、何も足取りが掴めていない。こんなに目立つ容姿とは言え、ベロアはやっぱり1人の野良犬に過ぎない。それも、今なら話は別だろうが、何も特技のない幼い日の彼だ。目撃情報はあれど、どこで見掛けたとか、何を盗んだとか、精々その程度の情報しかない。
その事実をベロアに伝えるのは、彼のそんな願いを完全に壊してしまうようで、口に出すのをはばかられる。
母親と子供たちと一緒に俺たちも茶会に参加することになった。広い中庭を囲むように植えられた向日葵は随分と背が高くなっていて、子供たちたちよりも大きかった。
広い中庭で颯と匙はオヤツ片手にはしゃいで走り回り、凛は母親の話に耳を傾けている。
ベロアと一緒に走り回る少年たちを見ながら、俺と母親、凛はのんびりとクッキーを齧る。俺に小さい頃読んだ絵本を引っ張り出し、母親は凛にオズの魔法使いを読んで聞かせていた。
彼女たちの傍で水を飲みながら、俺は丸一日チェックしていなかったメールを確認する。
今回依頼した情報屋からもベロアに対する手がかりはなかった。何度目とも分からない落胆に小さく肩を落とすが、それとは別の者からメッセージが届いていた。
花籠だ。彼には先日、恋人の情報が手に入らなすぎて泣きそうだと泣き言を言ったばかりで、その返信を読むのはちょっと恥ずかしい気持ちになる。
「恋人の出生を調べるなんて愛情深いんですね!ホーネットさんがそこまで想う恋人がどんな方なのかボクも気になります。なんなら、ボクがお調べいたしましょうか?」
そんな素人が簡単に調べられるような内容だったら苦労しない。花籠の楽観的な言葉は失笑を呼んだ。
「そんな簡単には見つからないんですよ。情報屋にも25人ほど当たりましたが、有益な情報はゼロです。もうラプラスに頼むくらいしか思いつきません。そんなの無理ですけどね!」
軽くジョークを交えながら返信を返す。
そう、ラプラスは都市を管理するスーパーコンピューターだ。膨大なそのデータさえ閲覧できれば、きっとどこかにベロアの情報が見つかるだろう。
でも、ラプラスにアクセスを許されているのはSだけだ。俺たちブラウンシュヴァイク家も、頼み倒してアクセスを許される場合はあるが、あれは父親の権限。父親に頼んだところで、くだらない内容でSの手を煩わせるなと言われるだけだ。
不意にまた腕時計がバイブする。随分と早い返信、花籠からだった。
「はい!話が早くて助かります♪ラプラスにアクセスしてその恋人さんのデータを調べてみませんか?」
俺はメールの内容に目を丸くする。花籠はそんな上層部の人間なのか?こんなしがない同人小説のファンをやってる人間が?
いや、そんなことを言ったら俺だって同じだ。ブラウンシュヴァイク家の跡継ぎがネットに同人小説を上げているだなんて、誰も思わないだろう。
花籠からたまにおひねりと称されて、同人活動費が振り込まれることがある。スピンオフを書いてくれとか、続編を作ってくれとか、そんなささいなリクエストに答えた時だ。その金額は確かに正気を疑うほどの金額で、俺ですら受け取るのが申し訳なくなるほどだった。
そんな財力を持つ花籠なら、上層部の人間だとしても何もおかしくはない。
「お願いしたいです!自分はどうすればいいですか?」
手早くメールを返信。間を空けずに返信が返ってくる。
「了解しました♪では明日、ご都合のよろしいときにメインタワーの最上階にてお待ちしております( *´艸`)ゲートではこちらの通行許可書をお使いくださいね!もし何か質問されるようでしたら『ピンクホーネット』と名乗っていただければ大丈夫なよう手筈を整えておきますね!貴方に会えるのを楽しみにしています♪」
メールに添付されたファイルには何やら小難しそうな書類ファイルが入っている。
可愛らしい顔文字がついているが、書いてある内容はガチもんだ。これで嘘だったら、随分と規模の大きい悪趣味なドッキリだが、信ぴょう性はあるように感じられた。
「このファイルを使用する場所があるんですかね?多分なんとかなると思います。いつも色々と手を尽くして頂いて感謝が尽きません。明日はよろしくお願いします!」
メールを送信し、思わず顔が綻ぶ。これが叶えば、ベロアの希望が叶うんだ。
「……ヴィル」
名前を呼ばれて顔を上げると、先ほどまで母親の読む絵本に食い入ってたベロアが不機嫌そうな顔で俺を見ていた。
「またメール見てたな…俺は怒った」
ふてくされた様子でそっぽを向く彼の肩を掴み、俺は椅子に座ったまま跳ねる。
「違うんだよベロア!お前の家族が分かるかもしれない!それも明日!明日だよ!」
新しい絵本に釘付けの子供たちと母親の隣で珍しく声を上げてはしゃぐ俺に彼は拍子抜けした顔で振り返る。
「俺の…?それも明日だなんてそんな急に…?」
「そう!俺もびっくり!なあ、明日連れてってよ!こんなチャンス、きっともうないよ!」
戸惑った様子ではしゃぐ俺を見ながら彼は眉をひそめる。
「まだ怪我が酷いだろ。それに、お前を攫った犯人がまだ見つかってないから外は危険だって宮下が言っていたからダメだ」
「なんでだよ!じゃあお前1人で行くのかよ!今日だって、俺を守りたいからって一緒に外行っただろ!」
喜んでくれると思っていたベロアの否定的な対応に、俺は思わず文句をぶつける。なんでそんな嬉しそうじゃないんだよ。
「一人で行くなんて言ってないだろ。俺はお前の傍にいる、何処も行ったりしない」
「じゃあ行かないってこと?お前の家族の事わかるかもしれないのに!」
俺の言葉に彼は首を横に振る。
「それは俺のわがままだ。そのためにこんな危ないときに外に行くのは良いって言えない」
ベロアの言葉に俺は口をへの字に曲げる。じっと彼の顔を睨むように見つめる。
「じゃあ、俺もベロアのこと知りたいから明日行く!これは俺のワガママだから、お前の意見じゃないです!」
「そ、それはむちゃくちゃじゃないのか!」
「俺の願いは何でも叶えたいんだろ!叶えてよ!一緒に行こうよ!」
もう自分が言ってることがめちゃくちゃなのは俺もよく分かってるが、こんなところで引き下がれない。幼い子供のように駄々をこねていると、不意に視線を感じて後ろを振り返る。
「…また喧嘩?」
匙がいつの間にか俺の後ろからじっとこちらを見つめていた。
周囲を見れば、匙だけでなくみんながこちらを見ている。
「恋人に痴話喧嘩は付き物だけど、お部屋でしてきたら?」
少し怒ったように眉を釣り上げる母親に、俺は身体を縮ませる。
「子供たちには新しいお部屋と家具を用意するわ。あとは私が面倒見ておくから、よく話し合ってね」
ティーセットの乗った盆を手に彼女が立ち上がると、すっかり警戒心が解けた子供たちがぞろぞろとついていく。
取り残された俺とベロアは2人で顔を見合わせた。
「…とりま、部屋戻る?」
「…そうするか」
彼も母親に怒られた子供のように肩をすくめて静かに答えた。
2人で自室に戻ると、最近の生活ですっかり籠に戻らなくなったハチドリたちが俺たちに群がる。ハチドリたちに餌をやりながらベッドに腰掛けると、ベロアも頭にサタデーを乗せたまま隣に座る。
「…なんでそんなダメなの?俺もベロアの生まれた経緯知りたいよ」
俯いたまま静かに尋ねる。本当になんで引越しは良くてベロアの過去を知るのがダメなのかがわからなかったのだ。
「だから…俺はお前が心配で…」
「ほんとにそれだけ?俺のこと言い訳にしてないよね?」
視線を泳がせる彼に詰め寄ると、彼は困ったように眉をひそめて俺を見る。
「そ…それは…なんというか…」
口ごもる彼に、目を細めてじっとりとした視線を送り続けると彼は観念したようにため息をついた。
「怖いだろ…俺がそれまで信じていた母親が、本当の母親じゃなかったとしても、本当の母親だったとしても…もし本当の母親じゃなかったとして、本当の母親がどうなったのか、なんで俺を手放したのか、生きてるのか死んでるのか父親はどこに行ったのか…全部わからない。俺は何も知らない…」
気まずそうに語られた彼の話に、俺は顔を上げる。
「…それならそうと言ってくれ。分からないよ」
ベロアの気持ちはもっともだ。誰にでもある不安だろう。
それが彼のような強い人間も考えることなのかどうかまでは、俺にはわからなかった。彼が望んでいるのだから、叶えたら喜ぶのだろうとここまでやってきたが、そうなれば無理強いするものでもないだろう。
「俺のことが心配だから諦めるとか、俺のせいでって話じゃないなら、お前が自ら進んでそれを選ぶなら無理に行く必要もないし、怒らないよ」
しょんぼりと肩を落としたままの彼の手に自分の手を重ねる。
思い返せば、ベロアは出会った時よりも随分と人間らしくなった気がする。もしかしたら、人間らしくなったのではなく、俺が彼のことをよく知っただけなのかもしれないが、ベロアも悩むし、悲しんだりする。俺と何も変わらないのだと感じることが増えた。
「ただ、お前の出生について調べるのは、実は凄く難しいんだ。今日手に入れたツテは、明日を逃せばもう二度と手に入らないかもしれない。だから、時間を置いて整理がついたら改めて探す…ってのは、ちょっと難しいかもしれない」
ベロアの顔を覗き込み、俺は口元で笑みを作る。
「だから、本当に大丈夫かよく考えてくれ。その場限りの逃げ口実とかじゃなくて」
「…わかった、ありがとう」
彼はそう答えると俯いて目を閉じる、少しそうして考えてからゆっくりと口を開いた。
「…明日、ヴィルと一緒に行く。俺が何を知ることになっても、俺が何者でも…そばに居てくれるんだよな?」
「当たり前だ。お前がとんでもない殺人鬼の血を引いてたり、実は地上の人間だったり、もはや人間じゃなかったとしてもずっと一緒だ」
ベロアの脇に腕を通して抱きしめる。
彼はそれに答えるように俺の体を抱きしめて「愛してる」と小さく呟いた。
あの後久しぶりに食堂で母親と子供たち3人とベロアの6人で夕食を食べた。
歳相応に食器を扱えるようになっていた子供たちは母親に褒められて嬉しそうに俺が教えてくれたのだと話す。
相変わらずのベロアは俺に食べさせてほしそうにしていたので、ついつい食べさせていたら母親から「2人の時にしなさい」と柔らかくたしなめられたので、ベロアはしぶしぶ慣れない食器での食事を始めた。
子供たちに屋敷の環境について、親の目がない場所でこっそり本音リサーチをしたが、思いのほか好評なようで、凛には多少の不安は残っているものの時にまだ不満はないようだった。むしろ、楽しいという意見が8割を占めていて、俺は密かに胸を撫で下ろした。
その夜は久しぶりに子供たちがいない俺の部屋で、ベロアと一緒にキングサイズのベッドで寝たが、さすがに身体が心配なのかベロアは手を出す様子もなく、傍に寄り添って眠りについた。俺は手を出してもらうことを期待していたので、ちょっと拍子抜けだが、彼の優しさが嬉しかったので素直に従った。
一晩死線を潜ったせいか、ベロアの温もりとベッドの柔らかさは殺人級の眠気をもたらした。
「うーっ、いってぇ…」
「でもこれやらないと治りが遅くなる」
朝から上半身裸でベッドに座る俺の肩に消毒液の染み込んだガーゼからぽたぽたとたれた雫が垂れる。
「液つけすぎだって」
「沢山つけた方が効くかと思ってる」
面倒くさがって、ベロアに頼んだ俺がいけなかったのだ。使用人か、せめて凛に頼めばもう少し優しく消毒してくれたことだろう。
消毒を済ませ新しい包帯を巻いてくれる彼の手つきは手馴れているのに、消毒に関してはこんなに雑だとは思っていなかった。
「これが済んだら、もう行くのか?」
「うん。取引相手には話はつけてあるし、やっぱり人目の少ない時間の方がいいだろ」
ベッドに畳んで置かれたシャツに袖を通し身支度を整える。
今日も出掛けると伝えると、「車で行きなさい」と仕事でいない父親の代わりに母親が言っていたが、ベロアがいるから大丈夫と説得した。大体からして都市のど真ん中にあるメインタワーに車で向かう方が目立つような気がするし、花籠にもあまり警戒されたくなかった。
最初の頃によく2人で乗っていたバイクを引っ張り出し、ベロアを後ろに乗せる。なんだか少し前に時間が巻き戻ったような錯覚すら起きるが、前よりもベロアの身体が近いのが嬉しく思えた。
「デカいな」
塔の前にバイクを止め、一足先に降りたベロアが感心したように呟いた。
地下の1番中心となる都心、その中央にそびえ立つメインタワー、通称「ラプラスの塔」。
この建物の最上階にスーパーコンピューターラプラスは存在し、この地下の全てのデータがそこにあるという噂だ。
塔のゲートにはベロアに負けず劣らずの屈強な男が数人、厳しい顔で警備に当たっている。
別にやましいことなどしていないし、むしろ手違いでなければ招かれた身だ。堂々としていればいいのだが彼等の圧に思わず縮こまりそうな思いで、ゲートにもうけられた監視室の窓に顔を出す。
「ご用件は?」
これまたガタイのいい男が営業スマイルなど一切ない威圧的な態度で俺を見下ろす。
背後のベロアが彼に対して威嚇するようにガンを飛ばしていた。頼むからこんなところで騒ぎを起こさないでくれと俺は彼の手をトントンとなだめるように叩く。
「えっと、ピンクホーネットって聞いてないですかね…?」
「ピンクホーネット様…お話は伺っております。通行許可証をお持ちですよね、拝見させていただきたいのですが」
男に言われて俺は、昨日花籠から送られてきたデータをゲートに設けられた端末に送る。
「…はい、確かに」
男は俺とベロアに首から下げるタイプのICカードのようなものをそれぞれ渡されゲートを開く。
「奥のエレベーターホール前でお待ちください。案内の者が参りますので」
俺たちはゲートをくぐり建物の内部へと進んでいく。
「すげえ…本当に入れた」
「簡単には入れないとこなのか?」
首に下げたICカードをいじりながらベロアが首をかしげる。
「そりゃな。この地下都市のいわば脳みそみたいな所だ。関係者以外は入れないし、関係者でもめったに入れねえって話だぜ」
実際、このメインタワーはこれだけの大きな建物でありながら、その内部や使用用途について、公開されていない部分がかなり多い。
このタワー丸々ラプラスのコンピューターだとか、人造人間の研究所だとかそれらしい推察から根も葉もない噂話まで飛び交っているほどだ。
長く飾り気のない広い通路を進んでいくと、ゲートの警備員が言っていたエレベーターホールらしき場所に出た。
エレベーターの扉が3つと申し訳程度のベンチソファがあるだけの殺風景な広間には、ここまでの道のり含めて全く人気が無かった。
「ここで待ってろって話だったか…」
ベンチソファに座って案内の者とやらを待つ。その案内人が花籠だったりするのだろうか。
一体どんな人なのだろう。上層部の人間だとしたら、それなりの大人だろうと思うが…あんな可愛い顔文字でおっさんが来たら凄い驚く。顔に出さないように気をはらなければ。
ベロアも緊張からかあまり言葉を発さず、静かに俺の隣に座って辺りをしきりに見まわしていた。
数分ほどそこで待っていると目の前のエレベーターのランプが点灯する。
上から降りてきているであろう人物の姿に思いを馳せていると、静かにその戸は開かれた。
中にいたのは二つの人影。小柄で黒髪の眼鏡をかけたスーツ姿の男性と、彼にリードでつながれた大きな身体の灰毛の男性。しかし大きな方は写真で見た猫のような締まった瞳孔に逆立った獣のような耳、作り物には見えない尻尾など異様な空気を放っている。
「ピンクホーネット様でお間違いないですか」
「あっ、はい。あなたが案内の…?」
淡々とどこか面倒くさそうな口調で問いかける彼に俺は警戒しながらも、出来るだけ好意的に答える。
小柄な男の背後に立つ大きな男は、猫背であることを考えれば身長はベロアよりも大きいだろうか。彼の放つ殺気にも似た異様な空気にベロアは威嚇するように小さな唸り声を上げる。
「ベロア、大丈夫だって」
彼をなだめる正面で小柄の男もつないだリードを軽く引いて男の気を向けさせる。
「Max stay.(マックス、待てだ)」
彼の呼び声に大きな男は一見無反応のように見えたが、彼から放たれていたピリピリとした殺気が消えるのを感じた。
「では、こちらに。ラプラスの元までご案内します」
彼に促されて俺たちはエレベーターに乗り込む。小柄な男は慣れた手つきでパネルを操作し扉を閉じる。
大柄の男二人が詰め込まれても広々としたエレベーター内で、特に話をすることもなくドア上の階を表すランプが上に登っていくのをただ眺める。
彼が花籠なのかと思っていたが、口調や仕草からするとあまりそうとは思えない。彼の様子を横目でチラチラと確認するが、彼は俺たちのことなどまるで興味がないのか見向きもしなかった。
暫くするとエレベータが停止しドアが開く。階を表すランプは最上階を示していた。
「こちらです」
小柄の男は薄暗い廊下を歩き出す。配管や配線がむき出しになったような壁にガラス張りの床、いつか映画で見たSFの宇宙船を思い出させるような廊下の先に重そうな鉄の扉が鎮座していた。
「ラプラス。連れてきた」
男が扉をノックして声をかける。
てっきり音声操作でも行うための「ラプラス」という枕詞を用いたのかと思いきや、中から「どーぞー」と気の抜けた少年のような声が返される。
ラプラスはスーパーコンピューターであるという認識が一般的だが、これではまるでラプラスが人間だとでも言うようだ。いや、まだ少年の声がコンピューターのものという線もある。過度な期待はよそう。
小柄な男が扉を押し開く。が、俺も人の事は言えないが小柄な彼では重い扉を開けるのにかなり力がいるようで、少し苦しそうに呻きながら扉を肩で押そうと踏ん張っている。
隣の大柄な男はまるで気にしていない様子で大きな欠伸をしていた。
「Max!!」
小柄の男が苛立った様子で彼を呼ぶと、「しょーがねーなー」というセリフが似合いそうなもったりとした動きで、額で扉を押して開く。
「では…自分は…これで…」
肩で息をしながら男は咳払いをし、リードを引いて廊下を戻っていく。
「あの…その変わった耳、本物ですか?」
興味に負けて男について行こうとする、大柄な男に声をかける。彼は犬のような耳をピコピコと動かしながら首を傾げたが、小柄な男がリードを催促するように小さく引っ張った。
「ただのコスプレですよ。ケモナーって日本人は言うんでしたっけ。彼はそういうのに憧れてて」
小柄な男はいかにも愛想笑いと言うような、ギクシャクとした歪な笑顔を浮かべて答える。多分、本当は笑うのが苦手なのだろうと、見ているだけで分かる不格好さだ。
エレベーターに男が乗り込み、背の高い男もそれに続く。
「なので、他言無用でお願いします」
エレベーターが閉まる際に小柄な男の声だけが残される。エレベーターが下っていく音を聞きながら、しばらくそれを呆然と見送ってしまった。
「ホーネットさん。どうぞ奥へ」
背中からあの少年のような声で呼ばれて、俺は扉に振り返る。ベロアと目を合わせて頷き、中へと踏み込む。
中は真っ暗と言っても過言ではないほど暗く、奥に進めば完全に先が見えなくなりそうに思えた。手探りで奥へと足を進めると、あの重そうな扉をベロアが進んで閉めてくれる。
扉が閉じると同時に部屋中に張り巡らされた配線が赤やオレンジ色に光り部屋の中を照らした。
子供たちと住んでいた家のリビングルームくらいの広さの空間に古めかしいソファとテーブル。壁をくりぬいたような広いベッドはクッションや毛布がぐちゃぐちゃに散らかっており床にはレーションの包み紙のようなものがいくつか落ちている。
何より印象的だったのは前面の壁一面はモニターが敷き詰められ、地下中の街の様子と思われる映像が映し出されていた。
そのモニターの前には高そうな革張りのオフィスチェアに膝を抱え込むように座った炎のような赤い髪の男が両手で顔を覆った状態で鎮座していた。
「お待ちしてました、ピンクホーネットさんとその想い人さん」
両眼を隠したまま彼は口元だけでにんまりと笑みを浮かべた。
「…花籠さんか?」
脳での情報処理が色々と追いつかないまま、目の前の男に問いかける。見えていないような気もするが、俺も被っていた帽子を取り、笑みを作って頭を下げた。
「はじめまして、ピンクホーネット…本名ヴィクトール=ブラウンシュヴァイクです」
名乗るか少し迷いながら、ハンドルネームに本名を添える。こんな場所まで招かれておいて名乗らないのは無礼だろう。
「ブラウンシュヴァイク?」
両眼を覆った彼は俺の言葉に驚いたような声でその手を避ける。ベロアとはまた違った鮮血のような赤い瞳で俺をまじまじと見てその背後のベロアにも目を向ける。
「おやおや!おやおやおやあ!これはこれは!どうせなら直前までおたのしみと思って目を覆っていたんですけど、まさかピンクホーネットさんがあの超有名なブラウンシュヴァイクのご子息様だったとは!」
彼は心底楽しそうに笑うと椅子から立ち上がって俺に手を差し出す。
明かりがついたとはいえまだ薄暗い室内で、先ほどまでは気づかなかったが、彼の両腕と両足にはリングのような機械が枷のようにはめられており、そこから伸びたコードが壁の機械へとつながっている。
「花籠、改めラプラスと申します。よろしくお願いしますね!」
差し出された手と彼の顔を交互に見つめ、笑顔を浮かべたまま握手をかわす。
なんでもない様な顔をしているつもりだが、ちょっと現実味が湧かない。ラプラスを人間であるとする説は確かに地下にはあるが、確率は相当低かった。それが、現にラプラスを名乗り、実際に塔の最上階にいる。これを嘘の一文字で片付ける方が無理があった。
「ラプラスなんて、俺よりよっぽど有名人だと思うけど」
メールの印象通りフランクなラプラスに、俺も砕けた言葉で感想を述べる。
「ンフフ。でもボクは人だと思われてませんからね~、有名人って言えるかどうか?知名度って言うならちょっと自信ありますよ!」
変わった笑い声を漏らしながら俺を舐めるように見つめた。
「ということは一昨日の誘拐騒ぎ、アレかなり手酷くやられてたじゃないですか大丈夫でした?」
まるで現場を直接見ていたかのような口ぶりに俺は感心に目を丸くする。これだけ詳しいあたり、ラプラスというのはやはり本当なのだろう。
「やっぱり知ってるんだな。恥ずかしいところ見せた」
「貴方に遠慮なく申し上げると、映画のワンシーンみたいでボクは楽しかったですよー?でも被害者が良き友人であったとわかると急に腹が立ちますねー…」
不満げに口をとがらせて足で地面をいじると彼はベロアに向き直る。
「しかし驚きました。ボクの推し作家のホーネットさんの想い人が貴方だったとは。巨人の落とし物よ」
オフィスチェアに座りなおす彼は肘掛に頬杖をついてにんまりと笑う。ベロアは訝しげに眉をひそめた。
「巨人…?」
「ああ、これは愛称ですよ。先代のラプラスは貴方の事を大変気に入っていたんです。その呼び名を考えたのも彼女です」
くるくるとオフィスチェアを回しながら話すラプラスに俺は首を傾げる。
「先代?ラプラスもやっぱり人間だから、世代交代するのか?」
よく始末屋であったり、掃除屋であったり、何かしら看板を掲げる地下の人間たちは、よく次の世代に家業を継ぐ。俺もそうであるからには、ラプラスも例外ではないだろう。
「ええまあ、人の命は有限であり、ラプラスは絶えるわけにはいきませんからね。世代交代は必要不可欠ですよ。ただ…ラプラスになれる人間はとても貴重なので必ずしも子が継ぐというわけではありませんがねぇ」
回していた椅子を止めて彼は自分の頭を人差し指でちょんちょんと指して見せた。
「さて、ボクの話よりも彼の話ですよね。巨人の子…名前は確かー…ベロアでしたっけね」
ラプラスの様子にベロアは少し緊張した様子で後ずさる。
下がってくる背中に優しく手を添えて、俺はベロアに笑いかける。
「大丈夫、一緒にいるから」
「…ああ」
少しだけ緊張のほぐれた顔で彼は微笑んだ。
「彼の何を調べたいんですか?生い立ち?血縁者?」
片手でパネルやキーボードをカチカチと操作しながらラプラスは俺達に目を向ける。
「…産みの親と…それからその親とどうして離れたのか。本当の両親が…どうしているのか…」
「はーい、じゃあ聞くより見た方が早いと思うので記録をお出ししますね。あ、そこのソファ使っていいですよ、ちょっと古いですけど掃除はしてるんで」
ラプラスに言われて指定されたソファに腰を掛ける。随分と使い込まれているようで、革張りの表面には細かい亀裂が無数に入っており、酷く軋む。
「年代物使ってんね」
あまり座り心地のよくないそれを手で押したりしながら感触を確かめる。ラプラスともあろう人間が、随分と質素な生活を送っているもんだ。
「それ、ボロって言うんですよ~?」
「身も蓋もねぇな」
せっかくオブラートに包んで表現したのに、本人に核心を突かれて俺は思わず笑う。俺に続いて隣にベロアも腰を下ろした。
「おふたりは『巨人』をご存知ですか?」
にんまりと笑みを称えたまま首を傾げるラプラスにベロアは首を横に振る。
俺はその名前には少し聞き覚えがあったが、ベロアの様子を見て、あえて何もリアクションをしないでおいた。
「聞いたことは無い。絵本のそれとは違うだろ」
「ええまあ、意味合いは同じですけどね。『巨人』って言うのは今から十数年前にちょっと流行ってた始末屋さんですよ。体が大きいから巨人。安易な看板の割にそこそこ売れっ子だったとか」
ラプラスの背後にある大きなモニターが切り替わり映像が流れ始めた。
どこかの市場のような場所で買い物をする若い女性。背は低く日本人のように見える彼女は身重らしくお腹は大きく膨らんでいる。
「彼女の名前はナツミ・ガーリブ。彼女はもうすぐ母親になろうとしていました」
映像の中の女性が重そうな紙袋を抱えて歩き出すと、後ろから大きな腕がそれを取り上げる。
腕の主は紙袋を抱え直すと、彼女を愛おしげに撫で額にキスを落とす。
その大柄な男の姿に俺は息を飲んだ。
浅黒い肌にルビーのような瞳、厚い唇とふっくらした涙袋はベロアと瓜二つだ。
「こちらの彼はもうすぐ父親になろうとしてました。名前はアースィブ。始末屋『巨人』であり、彼女の配偶者です」
女性が市場で買い物をし、商品を受け取る。それを男が受け取り微笑み合う。その短い映像が繰り返し流れる。
「身重の妻を想って、彼は1匹の犬を買いました。これから生まれる我が子と母になる妻に手を貸してもらうための労働犬、これが彼らの運命を大きく変えることになってしまった」
ラプラスの背後の映像が切り替わる。郊外の広い庭のある一軒家。その庭に置かれたゆりかごにまだ生後間もない赤ん坊が眠っていた。傍らには子供を寝かしつけていたのであろう母親もうたた寝している。
「彼らの家に買われた犬は、アースィブに恋をしていたようですね。好きな相手がすぐ側で別の女を愛して、子を育てるのを彼女はどんな思いで見ていたのかボクにはわかりませんね」
隣に座るベロアに目を向けると、彼は画面を食い入るように見つめている。
限りなく部外者に近い俺からすれば、一つの映画を見せられているようだった。色々な憶測が膨らむが、ベロアの感性を無視して面白半分に話していいものではない。俺も黙ってモニターへと視線を戻した。
「嫉妬に狂った犬は彼らの産まれたばかりの赤ん坊を奪って逃げたんです。もちろん彼らは直ぐに赤ん坊を探して犬を追ったことでしょう、でも…」
モニターが切り替わる。雨が降る夜の街中に倒れる赤ん坊を盗んだ犬、彼女の腹からは大量の血が流れ道を染めていた。
「逃げるのに夢中で慌てすぎちゃったんでしょうね。車にぶつかってあの有様です。GPSを頼りに追いかけてきた両親が見たものは、道端でぐちゃぐちゃになった犬の死体。さぁて赤ん坊はどこへやら…」
本来なら、地下の人間たちには全員マイクロチップが入れられている。それは、地上から攫われてきた人間であれば、誘拐されてきたその日に。地下で生まれ育った人間なら、1歳の誕生日に。施術が出来る医師に依頼、または施術専門の施設に子供を連れていくことで痛みもなく埋め込むことが出来る。それは自分の身分を証明する証として生涯機能する。
チップを持たないのは、それが出来ない野良犬だけ。ベロアも飼い犬登録をした時に入れた。
しかし、このような事件があった場合も、人間であるはずなのにマイクロチップを入れられなかった事になる。つまり…人間なのに、野良犬と変わらない状態になってしまったということだろう。
ベロアの両親は犬の死体を目の当たりにし、赤ん坊がいない事実に泣き崩れる母親とやり切れない表情で唇を噛む父親を映し出していた。
「少し時間を戻しましょうか」
ラプラスがそう言うと画面の映像は逆再生され赤ん坊を抱えた犬が車に跳ねられた直後を映し出す。
まだ辛うじて意識を持つ犬に駆け寄るひとつの影。フードから覗く金色の髪と青い目は、以前ベロアが話していた母親の特徴と一致する。
「あれは…」
それを肯定するようにベロアは言葉を漏らした。
金髪の女性は自身が纏っていたローブで、地面に転がった赤ん坊を雨から守るように包み抱き上げる。
赤ん坊を連れて横たわる犬に近づくも、しばらく経つとその場を立ち去っていく。
「あれが…俺と…母親…」
その後映像がベロアの本当の両親がたどり着く場面を映し出したのを見て彼は目を細めた。
「あれが…本当の」
彼の声に画面の映像は元の地下世界の映像に切り替わった。
「どうですか?知りたいことは知ることが出来ました?」
下を向いたまま困惑しているベロアにラプラスは首を傾げて問いかける。
「あれ、なんか納得いかない感じですか?質問あるなら受け付けますよ?」
俺はベロアの背中をさすりながら、ラプラスに小さく手を上げる。
「ベロアはつまり、人間だったってことだよな。飼い犬登録で、犬としてマイクロチップを埋め込んでしまったんだ。これを人間に書き換えるのって、手続きをすれば可能なのか?」
ベロアは恐らく、まだ混乱しているだろう。俺からも聞きたいことはいくつかあるので、彼が頭を整理する時間を作るためにも先に質問を繰り出す。
「出来なくはないですけどー…正式にやるならそれはあなたではなく、彼の両親か血縁者が行わなければいけません。血液検査などで血の繋がりを証明して、人間であると確定させる必要もあります。人間である証明と親や親戚に当たる人物からの申し出。そのふたつがないと難しいかと?」
ラプラスはイスをクルクルと回転させながら楽しげに答えた。
「なるほど、やろうと思えば何とかなりそうだ」
ここまでの情報があれば、巨人を探し出すのはベロアほど難しくないだろう。幸い、彼の顔も、顔どころか父親のやることなすことベロアに生き写しだ。存在そのものが証明みたいなものだろう。
「もう一つ聞いておきたいんだけど、巨人たちは今もまだこの地区周辺にいる?答えるのが難しければ、情報屋を洗うから断ってくれていい」
ダメもとで追加の質問を投げると、ラプラスはにまっと笑みを浮かべて回転させていたイスを止める。
「本当は他人の情報勝手に売るのあんま良くないとおもってるんですよー?でもホーネットさんは特別です!なーんたってボクの最推し作家さんですからね!」
ラプラスがコンピュータのパネルに触れると画面は切り替わり地図を映し出す。
「南方の小さな街の集まるエリア、今はそこに住んでいます。住所は見てのとおりで…あ、なんならあなたの端末に送りましょうか?サービスですよー?」
もじもじと機嫌良さげに笑う彼に俺は頷く。
こんな地下の神にも等しいラプラスから最推し作家の称号を得てしまうなんて、いい気にならないわけがない。
「お願いしてもいい?代わりに最新作の続編、力入れて書くから」
「ほんっとですか!?ボクあれすーっごく好きで楽しみにしていたんです~!!」
無邪気に喜ぶ彼がパネルを操作すると、花籠からのメッセージに、巨人の住処のデータが添付されてきた。
「ありがと。大事にするし、今日のことは絶対に秘密にする。約束だ」
腕時計から顔を上げて笑うと、指切りをしようと小指を差し出す。
それをラプラスは不思議そうに見つめて首を傾げた。
「あっ…もう指切りとかこの年齢じゃ、普通しないか」
最近はベロアや子供たちの相手をしていたから、ついこういうことがすぐに行動に出てしまう。
「ああ!指切りでしたか!はい、知ってますよぉ!」
彼は思い出したように自身の小指を立てて俺に差し出す。それに俺の小指を引っ掛けて固く指を結んだ。
後ろでソファに座ったままになっていたベロアも立ち上がって、眉を下げで困ったような笑みを浮かべる。
「…ありがとう、とりあえず平気だ」
ラプラスと小指を切り、ベロアを見上げる。
「大丈夫?ラプラスになんて、滅多に会えないかもしれないぜ?」
「えー?ボク毎日暇なんでいつでも遊びに来てくださいよー!」
俺とベロアの会話に割り込むように飛んできたラプラスの言葉に俺は思わず声を出して笑う。
「そんなことあるー?遊びに来ていいならまた来るけどさ」
「ええ、暇すぎて同人小説とか読み耽る今日この頃ですからね?」
思っていた以上にラプラスが親近感のある存在だったのは驚きだが、心強い味方に変わりはない。俺はそれに笑って頷いた。
「じゃあ、また来る。ラプラスも暇な時はうちにも遊びに来いよ」
ベロアの手を引いて、出口へ向かう。やけに静かなのは、まだベロアも悩むことがたくさんあるからだろう。それなら、家でゆっくり休ませてやりたかった。
ラプラスは俺たちに手を振って見送る。それに手を振り返し、メインタワーを後にした。
浅い眠りに落ちては目覚めを繰り返す。後ろ手に縛られた手首がうっ血していて、痺れにも似た痛みが眠りから意識を連れ戻す。
知らない男たちに連れてこられたのは廃工場のようだった。サビだらけのベルトコンベアを背に寄りかかる俺を中心に10人ほどの男たちが銃を手に待機している。
寝たフリで盗み聞きした話によれば、俺を使って父親に身代金を要求したらしい。もうすぐその取引が始まり、これが上手く行けば彼らは幸せになれると信じて疑わない。
「俺たち野良犬が不幸なのは、このブラウンシュヴァイクとかいう奴らの管理がズサンだからなんだろ」
まるで見当違いの話をする男に、もう1人の男が頷く。
「よく知らないけど、犬の管理はコイツらがやってるらしいよな。なんで身代金なんだ?こんな小さいガキ、さっさと殺せばいいのにさ」
吐き捨てるように言うと、男は俺に近寄って腹を蹴飛ばす。内臓がせりあがるような痛みで俺は咳き込んだ。
野良犬たちには学べる場所がない。常識すらあやふやな彼らの間では、迷信じみた噂話が横行しているようで、俺たちブラウンシュヴァイク家が犬たちを不幸にしているという噂話は宗教のように一部で根付いているようだった。
うんと昔では、流行り病を魔女の仕業と信じて多くの女性を拷問の果てに殺した人間たちだ。学がなければ、そうなっても仕方ない話だろう。
夕方あたりにここへ連れてこられてから、度々理不尽な暴力があった。腹や顔を蹴られては、唾を吐きかけられたりと散々だ。今、自分がどんな顔をしているのか分からない。
「今日の取引が上手くいかなかったら、俺たちどうすんだ?」
「このガキを殺すってさ。その前にいたぶろうが犯そうが好きにして構わないらしいけど、今はとりあえず五体満足が相手からの条件らしいから、今は我慢だな」
1人が俺の前にしゃがむと、俺髪を掴んで引っ張る。
「いてぇ…やめろ」
「あんま美人じゃないけど、声はまだ子供っぽくて可愛いな。いっそ明日になるのもいいかもな」
俺の言葉など聞かずに中年の男が下品な声で笑う。
自分の意思で股を開いてきたが、さすがに浮浪者の慰みものになって死ぬのは勘弁だ。勘弁だが…あまり父親の助けを期待できないでいた。
明日までになんとかならなければ、過程はどうあれ俺が死ぬのは確定事項だ。あまりに唐突な死刑宣告で、最早涙すら出ない。
ベロアと結婚すると口約束でも、淡い未来を彼から貰ったはずが、まだ1日もたたずに取り上げるなんてあんまりじゃないか。
「そういや、そのガキが捕まえた黒人っぽい野良犬ってどうなったんだ?」
不意に眺めていた男が声を出す。彼の言葉に、俺の髪を掴んだままの中年が顔だけで振り返った。
「ああ、アイツか…金づる取り上げられて狼狽えてんじゃねえか?あんなに飼い犬になるのを拒否してたくせに、あっさりブラウンシュヴァイクの犬になるなんて所詮は金持ちに媚びたクソ野郎だ」
掴まれたまま、俺は頭を振って中年の手を払う。彼を睨みつけ、舌打ちをした。
「アイツを侮辱したら許さねえぞ」
「はあ?こんな状態で強気なもんだ」
男は俺の顔を掴み、そのまま頭突きを食らわせてくる。頭が悲鳴を上げ、脳みそがグラグラと揺れた。
「そんなにあの野良犬を信用してるのか?馬鹿じゃねえか!アイツはただの盗っ人だ、お前がどうなろうと、せびった物品持ってトンズラするに決まってる」
まだ揺れる視界の中でなんとか中年の男に焦点を合わせる。付け焼き刃で笑顔を作った。
「そんなことない。アイツはいつだって俺のヒーローだ。お前らとは違う」
首を傾け、嘲るように肩を竦め手見せる。
そうさ、ベロアはいつだって俺を助けて、守ってくれる。誰よりも愛情深く俺を愛していてくれる。
「お前の頭突きは、アイツが全力の半分で殴ったパンチの足元にも及ばねえ。筋肉ないってつれぇね」
ケタケタと声を上げて笑うと、男は立ち上がって俺の胸を足で蹴り倒し、そのままギリギリと踏みつける。
「いい度胸してんな!そんなに言うなら泣いて謝るまでボコボコにしてやろうか!五体満足ならなんでもいいんだろ!」
彼の言葉を皮切りに、他の男たちも寄ってくる。
身体のあちこちを蹴飛ばされ、踏みつけられ、痛みが引く前に次の痛みが襲う。もうどこを攻撃されているのか分からなくなる。
「死ね!お前が死ねば俺たちは幸せになれるんだ!」
「この悪魔め!」
罵倒を浴びながら俺は身体を丸めて攻撃から何とか逃れようとするが、大した防御にもならずに呻くことしか出来ない。
ベロアは俺のヒーローで、スターだ。彼を信じてはいるが、明日までに彼一人の力で俺を見つけるなんて非現実的すぎる話だろう。
多分、ベロアは来ない。きっと全力で探していてくれてる。ありがとうも言えないまま、こんな場所で惨めに死ぬのは悲しくて泣けてくる。
あのビデオは再生してもらえただろうか。色々手回ししておいて良かった。ビデオの中だけでも、ありがとうと大好きが伝えられて良かった。
腹を蹴られすぎて呼吸が出来ない。酸欠で頭が麻痺していくと、痛みも比例して薄れてゆく。
意識を失いかけたその時、天井から落ちてきた…上から叩きつけられたと言った方が正しい勢いで鉄板のようなものが落ちてきた。恐らくこの廃工場の屋根材のようで地面に叩きつけられたそれは大きくひしゃげている。
物凄い轟音に俺を囲んで痛みつけていた男たちは皆、手や足を止め、鉄板が落ちてきた方向に目を向けていた。
「テ、テメェ何モンだ!」
男たちの中の一人があげた声に、俺も痛みでギシギシする体を何とか起こして目を向ける。
抜けた天井から差し込む薄明かりに、スポットライトのように照らされた1人の男のシルエット。黒いノースリーブのベストから覗く太い手足と、フードからはみ出た揺れる長いドレッドヘアはよく知っている。
「べ…ロア…?」
やっとの思いで絞り出した声は小さくて、離れた場所に立つ彼に届くわけなんてないのに、俺の呼び掛けに答えるかのように薄明かりに照らされたヒーローは顔を上げて一瞬柔らかく微笑んだ気がした。
「こいつよく見たら、金欲しさにガキに尻尾振った恥さらしじゃねえの!」
「あ、ああ本当だ。野良犬の王だなんて持て囃されといて、こんなチビの言いなりだ。だせぇったらねえよ」
1人の嘲笑うかのような言葉を皮切りに、困惑していた彼らはまばらに笑い出す。
「どうせ大した事ねえ。こっちには武器も人数も居るんだ。だいちゅきなご主人様の目の前で嬲り殺してやろうぜ」
警棒のような武器を持った男が彼に飛び掛るのと、その男が俺の後ろに投げ飛ばされて、サビだらけのベルトコンベアがバキバキと音を立て形を崩すのがほぼ同時に思えた。
「なっ…おいテメェらボサっとしてんじゃねえぞ!」
刃物を持った男が彼にそれを振りかざし、また別の男が拳銃を向ける。
カンッという金属音で刃物を弾き回し蹴りで拳銃の男諸共蹴り飛ばされて、鋭い発砲音と共に地面に倒れた彼らはそのまま腰を抜かした様子で彼を指さす。
「な、なんだよアイツは!」
暴発した弾を受けたのか男のひとりは肩から血を流しながら怯えた様子で後ずさる。
「馬鹿野郎!相手は1人だ、一斉に仕掛けろ!!さっさと手足を切り落とすんだ!」
殺し屋にも似た風格を放つ彼に武器を持った男たちは次々に飛びかかっては、先の男たちのように簡単にねじ伏せられて地面に捨てられていく。
まるでそれは、数だけ多い敵の雑魚を次々となぎ倒していくような画面の中のヒーローショーだ。
地面に横たわって呻き声を上げる男たちの中、ついに残ったのは俺の傍にいた下品な中年の男だけ。
「は…?え…?何、なんで…こいつ使って俺たちは…」
彼は放心状態の男の胸倉を掴み床に叩きつけると、男が動かなくなるまで腹や胸を何度も何度も蹴りあげ踏みつけてから蹴り捨てた。
「…ヴィル」
多分数時間しか離れていなかったのに、彼にそう呼ばれるのが随分久しぶりに思える。
「ベロア…」
後ろ手に縛られたまま、力を振り絞って身体を起こすと、彼はすぐさま駆け寄り、俺の手を束ねていた縄をナイフで切る。俺の体を抱き支える彼を両腕で抱きしめた。
「…ごめん…ごめんヴィル…」
あんな強さを見せつけるような戦いを魅せた彼は俺を抱いたまま子供のようにボロボロと大粒の涙を流して泣き出す。
「俺こそ…ごめん」
ベロアの腕の中で自然と笑みがこぼれる。彼の体温が、いつもに増して暖かかった。
「お前、知ってたけど…めっちゃカッコイイね。今すぐぶち犯されたいくらいイケてた」
湿っぽくならないように冗談を交えながら、彼の胸に顔を埋める。
聞きたいことはたくさんあったし、なんなら死に際に見た幻という線も捨てきれないが、安堵と喜びが再び強い眠気になって俺意識を持って行こうとする。
「セックスより、今は疲れただろ」
眠気を促すような彼の優しい手つきで背中をトントンと叩かれて俺の意識は彼に吸い込まれるように闇へと落ちていった。
それからどれほど眠っていたのか分からない。筋肉痛とは違う鈍い痛みで目を開けると、そこは屋敷の自室だった。隣には見慣れた点滴ホルダーが立っていて、左手に刺さったチューブでつながっている。
ボヤける視界を反対に向けると、俺の右手を握ったまま子供のように眠るベロアの姿があった。
彼の目から頬にかけては透明な筋が残っており、目元は心做しいつもよりふっくらと赤くなっているようにみえる。
あんなにいつも強いのに、泣き腫らすほど心配してくれたのだと思うと、悪いとは思いつつ可愛いと思ってしまう。
点滴をひっぱりすぎないように彼に身を寄せる。首に顔を埋めたら、彼の匂いとほんのりと汗の匂いが香った。
ベロアの頬に自分の頬を擦り付けて、小さくキスを数回繰り返す。起こしたい気持ちもありつつ、起こすのは可哀想という気持ちの板挟みがすごい。
「ん…」
薄く開かれたまぶたの隙間から、彼の赤い瞳が覗く。
彼は瞳にぼんやりと俺の姿を映すと、手は繋いだまま勢いよく飛び起きて寝転んだままの俺をあたふたと見下ろす。
「ヴィル!大丈夫か!?体痛いよな、なんで俺寝て…いやそれより…無事で本当に…ほんとに…」
あわあわと早口で俺の心配をしたかと思えば、言葉の途中から涙ぐんで彼は目を擦って涙を誤魔化しているようだった。
「大丈夫だよ。心配してくれてありがと」
俺も彼の隣で身体を起こす。まあ痛いが、初めてベロアとセックスして抱き潰された朝と同じ程度の痛みだ。慣れっこと言えば慣れっこだった。
「アイツらの暴力なんか、お前のパンチの半分も痛くないぜ。ほら、怪我も大して…」
自分のシャツをまくると、腹がえげつない紫になっていて俺は静かにシャツで蓋をした。
「俺のはこの倍か…?」
「…うん、まあ…痛みの度合いは…。ほら、ベロアのは一撃だったけど、ちょっと回数多かったから今回は」
苦しい言い訳をしながら俺は眉を寄せて笑う。何か悔いるような顔で自分の拳を見つめる彼に、俺は誤魔化すように両腕を広げた。
「それより、ハグして!昨日ずっと1人でいて寂しかったからベロア充電!」
「体中痣だらけなのに、抱きしめなんかしたら痛いだろ…」
彼は困ったように笑うが、ガラス細工に触れるような慎重な力加減で俺を抱きしめた。
俺は力いっぱい彼を抱きしめ返す。昨日の死を覚悟したのが嘘のようで、嬉しくて気の抜けた笑い声が漏れた。
「…本当に助けてくれてありがとう。お前はやっぱり、俺の希望なんだな」
「…そんなこと」
俺の言葉に彼は少し自信なさげに言葉を返すが、少し黙り込んでから小さく笑いをこぼした。
「いや、そうだな。俺はお前の希望でスターでヒーローだ」
安心したような息を漏らす彼の胸に頬を擦り付け、温もりを堪能する。たった1日しか経っていないのに、どんなに抱きしめても足りない気がした。
「…そうだ、お前どうしてここに?」
ふと思い出して、俺は身体を少し離して彼を見上げる。
「ここは俺の屋敷だろ?なんで…ていうか、腕の怪我は?どうやって俺のことを見つけたの?」
1度口に出すと、次々に疑問が溢れ出す。まくし立てるように質問を重ねると彼は「少し落ち着け」と困ったように笑った。
「ヴィルが攫われたあと、お前の父親と会って話をした。その時、怪我の手当をしてもらったから腕は大丈夫だ」
そう言って彼は清潔な包帯が巻かれた腕を俺に見せる。
俺は彼の包帯を優しく撫でる。もしかしたら、やっぱり死にそうで夢を見ているのかと疑っていたが、この包帯の感触と傷の位置はあまりにリアルで、仄暗い気持ちが蘇ってきた。
「…ごめん、俺が足を引っ張らなければお前は怪我をすることはなかったし、俺が攫われることもなかった。面倒ばっかりかけて、本当にごめん…」
目を伏せて謝ると彼は俺の頭をガシガシと撫でる。
「面倒なんてあるか。大きな口叩いてお前を守りきれなかったのは俺の責任だ。こんなの怪我のうちにならない」
銃痕なんて普通は大怪我のうちだろうに、ベロアは包帯をパンパンと叩いて平気な顔で笑ってみせた。
「ははっ、さすが俺の大好きな狼さんだ」
その様子に笑いながら、再び彼の胸に顔をくっつける。
「…父親に会って、何か変なことされなかった?声帯取り上げるとか、殺すとか言われなかった?」
ベロアが父親に手を貸したのは、少しだけ驚いたが、そこまで大きな驚きにはならなかった。俺たち家族が仲良くあるよう願っていた彼なら、やりかねないとは思った。
問題は父親の方で、アイツがベロアをどうする気なのかだけが心配でならなかった。
「ヴィルが心配するようなことは何もなかったさ。それに、俺が思っていたほど考えのわからない奴でもない気がする」
彼は俺を安心させるように優しく背中を撫でる。
「…そうかな」
ボソボソと呟く。俺には本当に父親が何を考えているのか分からない。幼い日も、今も。どうして俺を助けたのか…あんなに見下していた野良犬という存在、今では俺の飼い犬ではあるがベロアのことなど、彼が一番毛嫌いする種類の犬のはずだ。
ベロアの手を借りてまで俺を助け出したのは、俺に新しい弱みを作る気なのか…それともベロアに?単純に資産を守りたかったなら、俺を切り捨てればいいだけの話だし、俺なんかより養子を取って跡継ぎに据えた方が余程楽だろう。
彼は俺の顔を覗き込むと、柔らかく微笑んで肩を叩く。
「人を呼んでくる、ヴィルの目が覚めたって」
そう言うと彼はベッドから立ち上がり俺の部屋から外へ出て行った。
まだ現実味に欠ける出来事が連続していて、俺はぼんやりと部屋の壁を見つめる。
ベッドから起き上がり、点滴ホルダーを手に姿見の前に立つ。額から右頬、右側の口の端を中心に顔は紫色に変色していて、口の端には血の跡がまだ少し残っている。多少は誰かが拭いてくれたのか、思いのほか清潔に見えた。
服を捲れば全身アザだらけだ。それでも、アザで済んだのだから、野良犬たちが非力であったことがよく分かる。ベロアの拳で作ったアザは触れるだけで骨が折れたのではと思うほど痛かったが、それに比べれば痛くない。
そんなことをやっていると、ノックが聞こえた。振り返ると部屋に顔を出したのは俺の母親だった。
「ヴィクター!」
彼女はいつものように目を丸くして俺に駆け寄るが、いつも以上にその目は困惑しているように見えた。
「ごめんなさい、遠方の会食に出かけていてさっき帰ったばかりなの…お父さんから聞いたわ。酷い怪我ね、痛む?」
そう言って俺の頬に優しく触れる彼女の手を、今日は振り払う気が起きなかった。
「…案外、大丈夫。見た目ほど痛くないよ」
母親の後ろからベロアが部屋に入ってくる。ベロアと母親に触れられた俺の目が合うとなぜだか彼は満足そうに笑みを浮かべる。
「私が無闇矢鱈にあなたの捜索を邪魔したせいで、あんな危険な集団と接触させてしまったんでしょう?やっぱり、もう少しお父さんに従うべきだったのかしら…」
目を伏せて母親は声を震わす。
この人は、いつも俺の父親に従う。絶対に口出ししたりしないから、俺をこうやって外に出したのは恐らく人生で初めて、父親に背いたことになるだろう。
どこか後悔を滲ませた口調のそれを聞いたベロアは彼女の背後で俺たちを見下ろす。
「そんなことはない。ヴィルはとても楽しそうだったし、オレンジが食べられるようになった。これはヴィルを守れなかった俺が悪い。母親の所為じゃない」
「オレンジが食べられる…?オレンジはあなたの好物じゃない。食べられないってどういう…」
俺の目を見つめる不安そうな母親の視線に耐えられず、俺は顔を背けて黙る。彼女はベロアに助けを求めるように振り返ると彼は不思議そうに首をかしげる。
「ヴィルは2年くらい前からお菓子以外食べられなくなったって言ってたぞ。知らないのか?」
ベロアの言葉に母親は目を見開く。再び俺に向き直って、目を背けたままの俺の肩を優しく揺すった。
「ヴィクター、本当なの?どうして早く言ってくれなかったの…みんな、あなたが好き嫌いしてご飯を残してるんだと…」
隠していたものを次々と暴露され、俺はどうしていいか分からずに黙り続ける。
本当は不意に飯を完食してやって、好き嫌いしなくなったと思わせて終わりにしてやろうと思っていたのに。
眉をひそめてベロアに視線を投げるとなにか不味いことを言ったのかと思ってるのか、少し肩をすくめて呟いた。
「…言ってなかったのか?言ったらダメか?なんでだ?」
俺は口をとがらせて俯く。もう白状するしかないようだった。
「…だって、拒食症なんて言ったらかっこ悪いし、母さんも父さんもより過保護になる。屋敷から出られなくなったりしたら困るだろ」
ブツブツと愚痴を言うように話す。
理由は本当にそのままだ。でも、あれだけ毎日トイレで吐いても誰も気にかけてくれないことに、理不尽な怒りや寂しさを感じていたのもまた事実だった。
俺みたいなのを、きっと察してちゃんと呼ぶんだろう。そう考えると、それは拒食症よりもっとかっこ悪い気がした。
「そんな、そう言ってくれたらもっと早く分かったのに…そこまで追い詰められて辛かったでしょう?気付いてあげられなくて、ごめんなさい」
母親が俺を優しく抱きしめる。ベロアよりも細くて繊細な抱擁は、小さい頃を思い出させた。
「ほらな、ちゃんと話したらすぐに仲直りできるじゃないか」
母親の背後で勝ち誇ったような笑みを浮かべる彼に俺はムッと口をへの字に曲げた。
「…別に、喧嘩してたつもりはないし」
「そういうの意地っ張りって言うんだ、テレビで見た」
ますます楽し気に笑う彼に、なんだか自分まで笑えてくるから不思議だ。
母親は顔を上げると、また優しく俺の頬を指先で撫でた。
「…本当に、ベロアさんには感謝してもしきれないわね。彼が居なければ、きっとあなたとこんなに話せる日はこなかった」
彼女は立ち上がり、ベロアに向き直ると深々と頭を下げた。
「本当にありがとうございました。あなたのことを最初は追い出そうとしてしまったこと、深くお詫びします」
「別に気にしてない。飯もうまかったしな」
「優しいのね…あなたはヴィクターにとってかけがえのない友人ね。どうかこれからも、この子の傍にいてあげて貰えないかしら」
彼女の言葉に俺は顔を上げる。
「頼まれたって離れたりしない」
そう言ってベロアは力強く頷いた。
「それって…」
そこまで言って俺は口を噤む。この先に期待の言葉を並べることに抵抗があった。いつだって期待して、叶わなくてを繰り返してきた。また、それが砕かれるのは、もうこりごりという恐怖があった。
母親は俺に振り返ると、にっこりと微笑んだ。
「私はベロアさんに正式にヴィクターの飼い犬になって欲しいと思っているの。本当は口をきいたりしてはいけないけれど、彼が話せなかったら今こうしていることも出来なかった。全部分からないままで、きっと状況はもっと悪くなっていたわ」
母親はベロアの手を控え目に取る。握手をするようにその手を握った。
「これからも、今のままのあなたでヴィクターをサポートしてあげて。お父さんには私からも頼んでみるから」
「まかせろ。母親も困ったら俺を頼るといい」
そんな話をしていると、再び部屋にノック音が響く。次に入ってきたのはスーツ姿の男…たしか宮下とかいう名前の父親専属のSPだ。
彼は深々と頭を下げて部屋に入ると、それに続いて父親が顔を出した。その背後からさらに長身の男。彼のことはよく知っている、藤崎だ。昨日の事件で大きく揉めたので、恐らく今は厳戒態勢で父親を守っているのだろう。
ついこの間、ベロアに怪我をさせた宮下はどこか気まずそうにしていたが、藤崎はいつものように父親に見えない場所に立つと、俺を見てにんまりと笑って見せた。
「…何故そんな場所で話している。怪我をしているんだから、寝ていなさい 」
お決まりの小言から始まる父親の言葉に、俺は大きくため息をついて首を横に振る。しぶしぶとベッドの中に戻って足を伸ばして座ると、父親は隣の椅子に座る。母親はベッドに腰掛け、ベロアはベッドに上がり込んで俺の隣に胡坐をかいて座った。
総勢6人もの来客に、さすがの俺の部屋もなんだか狭苦しい。
「具合はどうだ」
話し出す父親に、俺は眉をひそめて頷く。
「元気だけど」
「私の言うことを聞かずに外に飛び出すから、危険な目に遭うんだ。どうして反抗ばかりする」
父親の言葉は、さも俺だけが悪かったと言いたげで腹が立つ。最初から心配してくれてるとは思っていなかったが。
「自分の話したいことばっかり話すな。ヴィルの話はどうした。ヴィルがどうして外に出るのか、どうして反抗するのか、聞いたことあるのか」
俺を自分の胸に寄りかからせるように肩を引き寄せながら、圧の利いた声色で話す。俺を挟んでベロアと父親がにらみ合うのを感じた。
父親はベロアを暫く睨んでいたが、俺に視線を戻して鼻を鳴らした。
「反抗するのに理由があるのか」
珍しく父親が俺の話を聞こうとしている。俺がどんなに声を荒らげても聞く耳を持たないのに、ベロアは一体どんな手品を使ったのか…いや、手品を使えるほどベロアは器用じゃないから、別の手段を取ったのだろう。
「…俺は、今の奴隷制度が嫌いだ。だから、父さんのように犬を物みたいに扱うのは無理だ。跡継ぎになんかなりたくない」
目を伏せて、足の上に置いた手を弄る。父親の顔を見るのは嫌だった。
「苦しんでいる犬を助ける手段が、俺には殺すことしかなかった。殺していくのを繰り返すうちに飯が食えなくなって…このまま家にいたら死ぬと思った。だから…」
「だからベロアさんを見つけてきたのよね」
ふと、黙っていた母親が言葉の続きを汲む。顔を上げると、彼女は柔らかく微笑んでいた。
「ベロアさんは本当にいい人です。お勉強をする機会がなかったから、2階から飛び降りたり、裸で廊下を歩いたりしてましたが…それでも、全力でヴィクターを支えてくれるわ」
「もう裸で歩いたりはしなくなったものね」と彼女がベロアに言うと彼はバツが悪そうに肩をすくめて苦笑いする。
父親は訝しげに母親を見つめていたが、彼女はそれを真っ直ぐに見つめ返す。
「彼が野良犬だから、マナーに欠けるからというのはよく分かります。でも、学べば良いだけの話ではありませんか」
柔らかいその口調に、父親は毒気を抜かれたように目を丸くしたが、それでも表情を再び険しくして口を開いた。
「しかし、口をきく犬など…世間体はどうなる。ブラウンシュヴァイクの看板を背負っているんだ、粗相は許されない。大体からして、ヴィクトールと過ごした時間そのものが短いだろう。まだ我々を騙しているだけの可能性も…」
「失礼を承知で、一つだけよろしいでしょうか」
不意に、部屋の壁際に立っていた宮下が声を上げる。振り返る父親の表情がますます険しくなるが、宮下はそれに怯まずに続けた。
「彼が持つヴィクトール様への好意は本物かと思います。短い時間ではありましたが、私のような下の者まで欺けるほど、彼は知能が高いように思えません。ご主人様も彼の知能を低く思われているなら、そこは共感頂けるのではないかと感じております」
宮下が手話で藤崎に「彼は頭が悪いが、愛は立派だ。そうだよな?」と伝えると、藤崎は言葉にならない言葉を発しながら「わかる、いい人」と口を開けて笑っていた。
直訳すればベロアを馬鹿だと言っているのだが、父親には効きそうな理由付けだ。俺は苦笑いしながら手話で2人に「ありがとう」と伝える。
「…お前、手話できるのか?」
俺の手を見て、父親が眉を寄せる。彼に目線を合わせ、俺は小さく頷いた。
「そうだけど…できないと藤崎と会話できないじゃん。通訳できる人間は多い方がいい。父さんはあまり人の話聞かないから、必要ないのかもしれないけど」
俺の言葉に父親はしばらく目を開いたまま黙っていたが、深いため息を吐いて首を振った。
「ヴィクトールこそ、あまり人のことを考えない配慮の欠けた子だと思っていたよ。あんなにだらしない関係の友人ばかり作って…」
だらしない関係の友人とは、おそらくセフレのことだろう。それに関しては耳が痛いが、配慮が欠けているとは心外だ。
「ヴィルはすごく優しいし頭もいいぞ、それに軽くて肌がすべすべだ」
少し前のめりで口を開いた彼から、簡単な言葉ばかりではあったが擁護が飛び出す。肌と軽さは関係ないが、良い場所を挙げてくれてるには変わりない。
「俺が子供たちよりも食器を使うのが上手くなくて悔しかったときは食べさせてくれたし、練習だって付き合ってくれた。俺たちが困らないようにって文字の読み方と書き方も教えてくれた。凛は女の子だからって、特別にいい匂いシャンプーだって買ってくれた」
子供たちという言葉に父親は訝しげに目を細めたが、とりあえず聞く気はあるようで黙っていた。
こんなに長いこと自分の言葉を話さない父親を俺は久しぶりに見たような気がする。
「俺がわがまま言っても叶えてくれる。俺が約束破ったこと、怒ったけど最後はちゃんと許してくれた。そんなこいつが俺が必要だって言った。だから俺はヴィルを守るって決めてる。だからずっと恋人やるって結婚もするって約束した」
「おい、結婚の話までせんでも… 」
恋人と結婚のワードまで飛び出し、俺は思わず彼の胸を叩いて苦笑いする。恐る恐る父親の顔を見ると案の定、渋い顔で俺たちを見つめていた。
「…この家業をしながら、犬と籍を入れることの重大さは分かって言っているのか?売り物に恋愛感情を抱いて結婚するなんて、頭がイカれた人間と思われても仕方ない」
「ベロアは売り物じゃない。身分なんか俺は気にしてないし、同じ人間って生き物であることには変わりないだろ」
父親に反論しながら、俺はベロアを見上げる。ベロアは俺の顔を見ると愛おしそうに微笑んで、俺の頬を撫でた。
「相手が金持ちじゃないといけないってルールはないだろ。ベロアは世界に1人しかいないし、ベロア以上の人間なんか地上もひっくるめて世界中探してもどこにもいない。俺は…ベロアがいい」
深くシワを刻み込む父親の顔を睨む。
「ベロアじゃないと嫌だ。そうじゃないなら、誰もいらない」
俺たちの話を静かに聞いていた母親は驚いたように口に手を当ててベロアを見る。
ベロアはあくまで堂々と俺を抱き寄せたまま、いつものように俺の頬に自身の頬を擦り付けた。
「恋人同士だったのね、ちょっと驚いちゃったけど…ヴィクターが選んだ人なのよね?」
目を丸くしたままの母親に俺は頷いて見せる。彼女の驚いた表情は次第に柔らかい笑みになり、彼女はゆっくりと頷いた。
「…お付き合いしてみたらいいじゃない。それで本当に2人が幸せになれるなら、結婚しなさい」
「お前!なんてこと…」
「私、恋愛結婚って憧れだったのよ。素敵な人がいて、自分で選べるなんて本当に幸せよ」
母親に父親がくってかかるが、母親の言葉にバツが悪そうに目を伏せた。
母親と父親は政略結婚だ。母親は一流のブリーダーの娘、父親はブラウンシュヴァイクの跡継ぎ。互いのことをまるで知らずに結婚したと聞く。
そんな母親から恋愛結婚が良かったと聞くのは、さすがに胸にきたのかもしれない。
母親は父親の手を握り、彼の目を優しく見つめた。
「誤解しないで、あなたと結婚したのを不幸とは思っていないし、私は幸せよ。でも、ヴィクターには好きな人がいて、思いあえているなら、その夢を砕くのはあなただって心が痛いでしょう?」
父親は口を曲げるが、黙り込む。俺はてっきり、母親が父親の言いなりなのだと思っていたが、もしかすると本当は逆なのかもしれなかった。
「私はあまり頭が良くないから…あなたの言うことに従う方がヴィクターを幸せにできると思っていたのよ。だけど、ベロアさんからちゃんとお話を聞いて、ヴィクターの様子を見ていて、2人を離すことは賛成できないと感じたの。だから、まずは様子を見たっていいじゃない」
母親は父親の手を撫でながら、俺たちに振り返る。彼女は困ったように笑って首を傾けた。
「私たち、話す機会があまりに少なかったわ。お父さんだってヴィクターのことを沢山考えているの。それだけは分かって?」
俺は口をへの字に曲げて、視線だけでベロアを見る。
「次は母親と父親が話してくれる。そうやって納得できるまでたくさん話すといい」
大丈夫だと言いたげに彼は強めに俺を抱きしめた。
なんだよ、こんな時ばっかり大人っぽく振舞ってさ。なんて、やっかみにも似た感情が湧き上がるが、ベロアの言うことは最もだ。最もだし、なんならベロアがいなければこうはならなかった。俺はため息をつきながら、口元で笑みを作った。
「…分かった」
俺の言葉に母親はにっこりと笑うと、父親を引っ張って立たせる。立ち上がった父親はまだ不満そうに俺を見ていたが、ベロアに視線を投げる。
「条件がある。息子と結婚を前提に付き合うのなら、屋敷に戻りなさい。その…子供?お前の連れ子なのかなんなのか知らんが、仮にも息子の婚約者を名乗るなら最低限の常識くらい勉強しなさい」
そこまで言ってから扉の前に立ち、父親はもう一度振り返る。
「お前たちが危険にさらされたら、ヴィクトールがまた家出する。お前たちのためでなく、息子のためだ。勘違いするな」
まるで捨て台詞のように言って部屋を出た父親を見て、母親は困ったように笑いながらついて行く。
ずっと壁際で手話をしていた宮下と藤崎は笑って手話で俺たちに言葉を伝え、その後に続いた。
「なんて言ったんだ?」
「ご結婚おめでとうってさ。ウケんね」
宮下と藤崎が残した言葉に笑いながらベロアに通訳する。
「ウケるのか?結婚するんだからおめでとうでいいじゃないか」
彼はにやりと笑って後ろから抱きしめたまま俺の首元にキスをした。
首元は弱いので、ムラムラしないように笑って彼を優しく押し返す。
「ところで、父親があんなこと言ってるけど…子供たち、どうする?信用できる?」
俺はまだ信用しきれてはいないが、あれだけ俺の意見を受け入れる父親は初めて見た。検討するべきだとは俺も思ってはいる。
「いいって言うならいいんじゃないのか?子供たちとも、お前の両親とも近くで暮らせるのは、すごく幸せなことだと思うぞ」
何も心配していないという様子で「また引っ越ししないとだな」と彼は笑った。
「それなら連れてきて貰うべきかな…なんか知らないけど、俺って今よく分からない連中に狙われてるんだろ?子供たちも巻き込まれたりしないかな」
昨日の集団がきちんと捕まるなり、解散するなりしていれば安心できるのだが、父親が家の中までSPを連れているのを見てしまうと、あまり解決しているようには思えなかった。
「それじゃあ俺が出かけてる間は誰がヴィルを守るんだ?」
訝し気に目を細めて彼は俺を抱きしめる腕に少し力を入れる。
「まあ…お前がいない間はきっと別の護衛がつくよ。この様子じゃ屋敷中、見張りだらけだろうし…子供たちを放っておくわけにもいかないだろ?」
心配してくれるのはとても嬉しいが、もし彼らがビデオレターを再生してたりしたら、完全に遺言だ。早く元気な姿を見せて安心させるべきだろう。
「それは…そうだけども…」
ベロアは子供たちが心配な反面、ますます俺に対して過保護になっているようで一向に煮え切らない様子で唸る。
「絶対に攫われたり殺されたり、殴られたりしないって約束できるんだな?」
「絶対…絶対かあ…」
彼の言葉に苦笑いしか出ない。実際、俺には戦う術がなくて、足を引っ張ったあげくに全身アザだらけだ。守れない約束に「絶対」と言う枕詞は付けられない。
「絶対じゃないのか?」
じっとりと睨むような彼の視線に目を逸らし、ふと思いつく。
「…てか、親公認なら車出して貰えばいいじゃん」
今までベロアとの関係はどこまでも親に秘密として通していたが、もう親の目を気にする必要がないなら、使用人に頼ったっていいだろう。
「俺、あんまり今は動き回れる自信ないけど、何かあっても大丈夫?絶対、足引っ張るよ」
ただでさえ足でまといなのに、こんなに身体が痛くては一層に足でまといだ。俺が彼を見つめると、彼は俺の頬に顔をぐりぐりと押し付けて答える。
「絶対大丈夫だ。もう二度とこの手は放さない」
しっかりと握られた手を撫でるように親指を動かす彼の手を、俺はそっと握り返す。
「じゃあ、そうしよ。迎えに行こうか」
俺がベッドから立ち上がろうとすると、床に足が付くより先に身体が持ち上げられる。
「動くと父親に怒られるぞ」
俺を抱き上げたベロアは、悪いことを企むようなにやりと笑う。
こうやって抱き上げられる機会が多いベロアとの時間は、なんだか自分が小動物にでもなった気分になるが、嬉しいのでそれに甘えておく。
使用人に頼んで車を手配してもらい、家にある犬用の首輪を3つ、荷物に入れた。子供たちを飼い犬扱いはしたくないが、野良犬状態で連れていくよりよっぽと安全だろう。
父親は俺が出かけると知って無言で宮下と藤崎を俺たちにつけ、目立たないように用意されたお忍び用のワゴン車に乗り込んだ。
藤崎とベロアはいつの間にか肘で小突きあう友人のような関係になっていて驚いた。宮下は運転で忙しかったので主に俺が通訳をしたが、体術や格闘技の話をしていて、俺にはちんぷんかんぷんだった。
車をあの小さな平屋の前に停めると、窓の外を覗いていた小さな顔が慌てた様子で引っ込むのが見えた。
俺とベロアが車から降りて家に近づくと、また恐る恐る覗いた顔がパッと明るくなる。窓を開け三人が飛び出して駆け寄ってきた。
「ヴィクター!!」
「ヴィーおにーちゃん!」
子供たちは驚いたり、泣きそうだったりいろんな表情を見せるが、3人とも嬉しそうに俺の足にしがみつく。
「ごめんごめん、心配かけたな」
しゃがんで1人ずつ頭を撫でたり、抱きしめたりすると、ようやく生還したんだなという実感が湧いてくる。
俺の顔や腕に出来た擦り傷やアザを見て、3人はまだ少し心配しているようではあったが、初めて出会った時も顔に青あざを作った状態だったせいか、すぐに気を取り直してくれた。
「これからみんな、俺の家に引っ越して欲しいんだ」
俺を囲んでいた子供たちは皆目を丸くして互いに顔を見合わせる。
彼らに首輪を見せる。本当は付けたくないし、嫌われそうで嫌だが、言うしかない。
「…嫌かもしれないんだけど、みんなの安全のために俺の飼い犬になって欲しい。ベロアみたいに自由にしてていいから」
笑みを浮かべたまま目を伏せる。
「うん、いいよ」
最初に声を上げたのは颯だった。俺が持っていた首輪のうち赤い首輪を取り上げて二ッと笑って見せる。
「俺赤がいい!赤はヒーローの色だもん!」
「じゃあ僕、青がいい」
颯に続いて匙も青い首輪を指さして、大きな目で俺を見つめる。
2人の様子に俺はほっと息をつく。颯に赤い首輪を付け、匙には青い首輪。苦しくないように様子を見ながらサイズを調整する。
「私は…」
颯と匙に首輪をつけてやっている一歩後ろで、凛が暗い顔をしてうつむいていた。黙り込んでしまった凜にベロアが近づき頭を撫でた。
「ヴィルなら大丈夫だ」
「…うん…わかってるの」
彼女は俺の手に余った最後の一つを見つめて下唇を噛み締める。凛が何におびえているのかはわからなかったが、あまりいい思い出でないことは確かのようだ。
「ごめんな。本当は俺も付けたくないんだ。でも、何もないままはぐれた時が1番怖い。協力してもらっていいか?」
凛を招き寄せ、彼女の小さな手を握る。何があったのかは分からないが、野良犬をやっているくらいだから辛い思い出の1つや2つあって当たり前だろう。
不安にならないように俯いた彼女に俺は微笑みかける。
「することはいつもと変わらない。みんなと遊んで、美味い飯を食べて、たまに勉強する。首輪があれば、外にだって出掛けられる。俺はみんなと一緒に街を歩きたいな」
凛は俺とベロアを交互に見て不安そうに眉を下げる。ベロアが彼女の背中を優しく押すと、凛は改めて俺を見つめて首輪がつけやすいように少し背伸びをした。
「私も…お外歩きたい」
「うん、一緒に可愛い服とか買いに行こうな」
凛に黄色い首輪を先の二人と同様、苦しくないようにつけてやった。
彼女は付けられた首輪を確認するように撫でて、安堵の溜息を吐いた。
「ヴィクトール様、家具などの運搬は他の者に頼みますので、彼らを連れてお車へ」
背後にいた宮下が俺の傍に歩み寄って頭を下げる。それに立ち上がって頷き、凛の手を引いて車へとゆっくり歩き出す。
「ベロアは他の2人を」
俺の指示でベロアがいつものように匙と颯を両腕に抱き上げた。先に彼らが乗り込むのを見届け、凛に笑いかける。
「もっと綺麗な家に行くだけだ。心配するな、なんかあれば俺たちが守るから」
「…うん、ありがとうヴィーおにーちゃん…!」
不安そうな事には変わりないが、それでも彼女は精いっぱいの笑顔を作って見せた。
ベロアたちは1番後ろの列の座席へ、俺たちは真ん中の座席に座る。車に乗り込み、不安そうに身体を縮こまらせていた凛に、助手席の藤崎がポテトチップスを笑って彼女に差し出した。
藤崎は聞き取るのが難しい発音で彼女に声をかける。凛は驚いたように俺の腕にギュッとしがみついて身を引いた。
「彼は耳が聞こえないんだ。でも、怖い人じゃない。おひとつどーぞって言ってるよ」
俺が通訳すると凛は恐る恐る彼の差し出したポテトチップスに手を伸ばし手に取った。
きゅっと目を閉じてそれを口に入れると、安堵と喜びの混ざったような控えめな笑顔をこぼした。
「おいしい…ありがとう、おっきいおにーちゃん…!」
凛の笑顔に親指を立てて藤崎は豪快にわらう。車の中はコンソメの匂いでいっぱいだった。
屋敷に着き、庭先に車を置いて中へ入る。行く先々にいる大勢の監視役が俺たちに頭を下げる様に子供たちはぽかんと呆気にとられる。
今日は会食から帰ってきて時間があるのか、庭先で花を弄っていた母親が俺たちの帰宅を聞きつけて、後ろから顔を出した。
「あら!小さいお客様ね!」
彼女は土のついた手袋をエプロンのポケットにしまうと、1番近くにいた颯の前でしゃがんだ。
「え、だ、だ、だれ…!?」
俺たちに振り返る彼に俺は肩を竦める。
「俺の母親だ」
母親はその隣にいた匙に手招きをし、頭を撫でる。
「やだあ、可愛い!小さい頃のヴィクターを思い出すわ。みんな、中庭でお茶でもどう?この間、植えた向日葵が咲いたのよ。とても立派だから見ていかない?」
懐かしがるように匙の頬をこね、颯の手を撫でたりと忙しくはしゃぐ彼女に俺は苦笑いする。
「お茶…あ、それ知ってる!おやつの時間って意味だ!」
「おやつ…!」
母親の周りをはしゃいで跳ねまわる少年たちとは対照的に凛は俺の後ろに身を隠したまま出てこない。
「おやつなら俺も食べたい」
子供たちに混ざってベロアまで混ざって母親を囲むようにうろうろと歩き回っている。
「みんなでおやつだって」
凛の頭を撫でながら笑いかけると、彼女もおずおずと母親の前に歩き出る。
その様子はまるで少し前に、俺が初めて子供たちに出会った時に似ていた。
「あら!ヴィクターの後ろに可愛い子がいるわ。一緒にお茶はどう?昨日貰ってきた美味しいクッキーがあるの」
母親は凛を見付けると、おいでと言うように両手を控えめに開いた。
凛はゆっくり母親に近づいて、彼女の手にそっと自分の手をのせて、握る。
「あ!いーなー!!俺も俺も!!」
「僕も、僕も…!」
母親の両手を奪い合うように空いた手に颯と匙が群がって手をつなぐ。
母親が子供好きなのは知っていたが、久しぶりに訪れたモテ期に顔を綻ばせている。随分と楽しそうだ。
彼等が楽し気に中庭に向かう後ろ姿を見ながらベロアが俺に寄ってくる。
「子供たちもお前の母親も楽しそうだ。連れてこられてよかった」
「思っていた以上にどちらも順応してて、むしろ俺が置いてけぼりだ」
肩を竦めて笑い、俺たちも母親と子供たちを追って歩き出す。
「…ああいうのを見てると、昔を思い出すよ。うんと小さい頃は、俺も母親が好きだった」
いつからか母親がそばに居る時間が減って、話すことも分からなくなって、何を考えてるのかすら分からなくなって、ただ父親に従う彼女がいつからか嫌いになっていた。
「母親が変わったんだと思っていたけど、ああして見ると案外昔と変わらないもんだ」
「また好きになれる。いや、好きって言えるようになるさ。きっとヴィルだってホントは昔と変わらない」
彼は俺の頬を撫でて微笑んだ。遠目に母親と子供たちを見つめる彼の瞳は満足げな反面、どこか寂しそうに見えた。
彼の言葉に、俺も笑って彼の手を握る。親離れしていく子供の親は、こんな気持ちなんだろうか。
「…お前の母親にも会ってみたかったな」
ふと、独り言のような言葉が口から漏れる。ベロアの母親はもういない。いや、生みの親が生きていたとして、姿を見せない母親にはあまり期待できない気もする。そう考えると、死んでしまった母親に会えないのは酷く残念に思えた。
「ああ、俺も…会いたいし、会ってみたい」
期待していない願いほど、案外口に出すのは簡単だったりする。笑って呟いた彼の言葉もきっとそうだったんだろう。
俺は彼の母親を探すと約束したのに、何も足取りが掴めていない。こんなに目立つ容姿とは言え、ベロアはやっぱり1人の野良犬に過ぎない。それも、今なら話は別だろうが、何も特技のない幼い日の彼だ。目撃情報はあれど、どこで見掛けたとか、何を盗んだとか、精々その程度の情報しかない。
その事実をベロアに伝えるのは、彼のそんな願いを完全に壊してしまうようで、口に出すのをはばかられる。
母親と子供たちと一緒に俺たちも茶会に参加することになった。広い中庭を囲むように植えられた向日葵は随分と背が高くなっていて、子供たちたちよりも大きかった。
広い中庭で颯と匙はオヤツ片手にはしゃいで走り回り、凛は母親の話に耳を傾けている。
ベロアと一緒に走り回る少年たちを見ながら、俺と母親、凛はのんびりとクッキーを齧る。俺に小さい頃読んだ絵本を引っ張り出し、母親は凛にオズの魔法使いを読んで聞かせていた。
彼女たちの傍で水を飲みながら、俺は丸一日チェックしていなかったメールを確認する。
今回依頼した情報屋からもベロアに対する手がかりはなかった。何度目とも分からない落胆に小さく肩を落とすが、それとは別の者からメッセージが届いていた。
花籠だ。彼には先日、恋人の情報が手に入らなすぎて泣きそうだと泣き言を言ったばかりで、その返信を読むのはちょっと恥ずかしい気持ちになる。
「恋人の出生を調べるなんて愛情深いんですね!ホーネットさんがそこまで想う恋人がどんな方なのかボクも気になります。なんなら、ボクがお調べいたしましょうか?」
そんな素人が簡単に調べられるような内容だったら苦労しない。花籠の楽観的な言葉は失笑を呼んだ。
「そんな簡単には見つからないんですよ。情報屋にも25人ほど当たりましたが、有益な情報はゼロです。もうラプラスに頼むくらいしか思いつきません。そんなの無理ですけどね!」
軽くジョークを交えながら返信を返す。
そう、ラプラスは都市を管理するスーパーコンピューターだ。膨大なそのデータさえ閲覧できれば、きっとどこかにベロアの情報が見つかるだろう。
でも、ラプラスにアクセスを許されているのはSだけだ。俺たちブラウンシュヴァイク家も、頼み倒してアクセスを許される場合はあるが、あれは父親の権限。父親に頼んだところで、くだらない内容でSの手を煩わせるなと言われるだけだ。
不意にまた腕時計がバイブする。随分と早い返信、花籠からだった。
「はい!話が早くて助かります♪ラプラスにアクセスしてその恋人さんのデータを調べてみませんか?」
俺はメールの内容に目を丸くする。花籠はそんな上層部の人間なのか?こんなしがない同人小説のファンをやってる人間が?
いや、そんなことを言ったら俺だって同じだ。ブラウンシュヴァイク家の跡継ぎがネットに同人小説を上げているだなんて、誰も思わないだろう。
花籠からたまにおひねりと称されて、同人活動費が振り込まれることがある。スピンオフを書いてくれとか、続編を作ってくれとか、そんなささいなリクエストに答えた時だ。その金額は確かに正気を疑うほどの金額で、俺ですら受け取るのが申し訳なくなるほどだった。
そんな財力を持つ花籠なら、上層部の人間だとしても何もおかしくはない。
「お願いしたいです!自分はどうすればいいですか?」
手早くメールを返信。間を空けずに返信が返ってくる。
「了解しました♪では明日、ご都合のよろしいときにメインタワーの最上階にてお待ちしております( *´艸`)ゲートではこちらの通行許可書をお使いくださいね!もし何か質問されるようでしたら『ピンクホーネット』と名乗っていただければ大丈夫なよう手筈を整えておきますね!貴方に会えるのを楽しみにしています♪」
メールに添付されたファイルには何やら小難しそうな書類ファイルが入っている。
可愛らしい顔文字がついているが、書いてある内容はガチもんだ。これで嘘だったら、随分と規模の大きい悪趣味なドッキリだが、信ぴょう性はあるように感じられた。
「このファイルを使用する場所があるんですかね?多分なんとかなると思います。いつも色々と手を尽くして頂いて感謝が尽きません。明日はよろしくお願いします!」
メールを送信し、思わず顔が綻ぶ。これが叶えば、ベロアの希望が叶うんだ。
「……ヴィル」
名前を呼ばれて顔を上げると、先ほどまで母親の読む絵本に食い入ってたベロアが不機嫌そうな顔で俺を見ていた。
「またメール見てたな…俺は怒った」
ふてくされた様子でそっぽを向く彼の肩を掴み、俺は椅子に座ったまま跳ねる。
「違うんだよベロア!お前の家族が分かるかもしれない!それも明日!明日だよ!」
新しい絵本に釘付けの子供たちと母親の隣で珍しく声を上げてはしゃぐ俺に彼は拍子抜けした顔で振り返る。
「俺の…?それも明日だなんてそんな急に…?」
「そう!俺もびっくり!なあ、明日連れてってよ!こんなチャンス、きっともうないよ!」
戸惑った様子ではしゃぐ俺を見ながら彼は眉をひそめる。
「まだ怪我が酷いだろ。それに、お前を攫った犯人がまだ見つかってないから外は危険だって宮下が言っていたからダメだ」
「なんでだよ!じゃあお前1人で行くのかよ!今日だって、俺を守りたいからって一緒に外行っただろ!」
喜んでくれると思っていたベロアの否定的な対応に、俺は思わず文句をぶつける。なんでそんな嬉しそうじゃないんだよ。
「一人で行くなんて言ってないだろ。俺はお前の傍にいる、何処も行ったりしない」
「じゃあ行かないってこと?お前の家族の事わかるかもしれないのに!」
俺の言葉に彼は首を横に振る。
「それは俺のわがままだ。そのためにこんな危ないときに外に行くのは良いって言えない」
ベロアの言葉に俺は口をへの字に曲げる。じっと彼の顔を睨むように見つめる。
「じゃあ、俺もベロアのこと知りたいから明日行く!これは俺のワガママだから、お前の意見じゃないです!」
「そ、それはむちゃくちゃじゃないのか!」
「俺の願いは何でも叶えたいんだろ!叶えてよ!一緒に行こうよ!」
もう自分が言ってることがめちゃくちゃなのは俺もよく分かってるが、こんなところで引き下がれない。幼い子供のように駄々をこねていると、不意に視線を感じて後ろを振り返る。
「…また喧嘩?」
匙がいつの間にか俺の後ろからじっとこちらを見つめていた。
周囲を見れば、匙だけでなくみんながこちらを見ている。
「恋人に痴話喧嘩は付き物だけど、お部屋でしてきたら?」
少し怒ったように眉を釣り上げる母親に、俺は身体を縮ませる。
「子供たちには新しいお部屋と家具を用意するわ。あとは私が面倒見ておくから、よく話し合ってね」
ティーセットの乗った盆を手に彼女が立ち上がると、すっかり警戒心が解けた子供たちがぞろぞろとついていく。
取り残された俺とベロアは2人で顔を見合わせた。
「…とりま、部屋戻る?」
「…そうするか」
彼も母親に怒られた子供のように肩をすくめて静かに答えた。
2人で自室に戻ると、最近の生活ですっかり籠に戻らなくなったハチドリたちが俺たちに群がる。ハチドリたちに餌をやりながらベッドに腰掛けると、ベロアも頭にサタデーを乗せたまま隣に座る。
「…なんでそんなダメなの?俺もベロアの生まれた経緯知りたいよ」
俯いたまま静かに尋ねる。本当になんで引越しは良くてベロアの過去を知るのがダメなのかがわからなかったのだ。
「だから…俺はお前が心配で…」
「ほんとにそれだけ?俺のこと言い訳にしてないよね?」
視線を泳がせる彼に詰め寄ると、彼は困ったように眉をひそめて俺を見る。
「そ…それは…なんというか…」
口ごもる彼に、目を細めてじっとりとした視線を送り続けると彼は観念したようにため息をついた。
「怖いだろ…俺がそれまで信じていた母親が、本当の母親じゃなかったとしても、本当の母親だったとしても…もし本当の母親じゃなかったとして、本当の母親がどうなったのか、なんで俺を手放したのか、生きてるのか死んでるのか父親はどこに行ったのか…全部わからない。俺は何も知らない…」
気まずそうに語られた彼の話に、俺は顔を上げる。
「…それならそうと言ってくれ。分からないよ」
ベロアの気持ちはもっともだ。誰にでもある不安だろう。
それが彼のような強い人間も考えることなのかどうかまでは、俺にはわからなかった。彼が望んでいるのだから、叶えたら喜ぶのだろうとここまでやってきたが、そうなれば無理強いするものでもないだろう。
「俺のことが心配だから諦めるとか、俺のせいでって話じゃないなら、お前が自ら進んでそれを選ぶなら無理に行く必要もないし、怒らないよ」
しょんぼりと肩を落としたままの彼の手に自分の手を重ねる。
思い返せば、ベロアは出会った時よりも随分と人間らしくなった気がする。もしかしたら、人間らしくなったのではなく、俺が彼のことをよく知っただけなのかもしれないが、ベロアも悩むし、悲しんだりする。俺と何も変わらないのだと感じることが増えた。
「ただ、お前の出生について調べるのは、実は凄く難しいんだ。今日手に入れたツテは、明日を逃せばもう二度と手に入らないかもしれない。だから、時間を置いて整理がついたら改めて探す…ってのは、ちょっと難しいかもしれない」
ベロアの顔を覗き込み、俺は口元で笑みを作る。
「だから、本当に大丈夫かよく考えてくれ。その場限りの逃げ口実とかじゃなくて」
「…わかった、ありがとう」
彼はそう答えると俯いて目を閉じる、少しそうして考えてからゆっくりと口を開いた。
「…明日、ヴィルと一緒に行く。俺が何を知ることになっても、俺が何者でも…そばに居てくれるんだよな?」
「当たり前だ。お前がとんでもない殺人鬼の血を引いてたり、実は地上の人間だったり、もはや人間じゃなかったとしてもずっと一緒だ」
ベロアの脇に腕を通して抱きしめる。
彼はそれに答えるように俺の体を抱きしめて「愛してる」と小さく呟いた。
あの後久しぶりに食堂で母親と子供たち3人とベロアの6人で夕食を食べた。
歳相応に食器を扱えるようになっていた子供たちは母親に褒められて嬉しそうに俺が教えてくれたのだと話す。
相変わらずのベロアは俺に食べさせてほしそうにしていたので、ついつい食べさせていたら母親から「2人の時にしなさい」と柔らかくたしなめられたので、ベロアはしぶしぶ慣れない食器での食事を始めた。
子供たちに屋敷の環境について、親の目がない場所でこっそり本音リサーチをしたが、思いのほか好評なようで、凛には多少の不安は残っているものの時にまだ不満はないようだった。むしろ、楽しいという意見が8割を占めていて、俺は密かに胸を撫で下ろした。
その夜は久しぶりに子供たちがいない俺の部屋で、ベロアと一緒にキングサイズのベッドで寝たが、さすがに身体が心配なのかベロアは手を出す様子もなく、傍に寄り添って眠りについた。俺は手を出してもらうことを期待していたので、ちょっと拍子抜けだが、彼の優しさが嬉しかったので素直に従った。
一晩死線を潜ったせいか、ベロアの温もりとベッドの柔らかさは殺人級の眠気をもたらした。
「うーっ、いってぇ…」
「でもこれやらないと治りが遅くなる」
朝から上半身裸でベッドに座る俺の肩に消毒液の染み込んだガーゼからぽたぽたとたれた雫が垂れる。
「液つけすぎだって」
「沢山つけた方が効くかと思ってる」
面倒くさがって、ベロアに頼んだ俺がいけなかったのだ。使用人か、せめて凛に頼めばもう少し優しく消毒してくれたことだろう。
消毒を済ませ新しい包帯を巻いてくれる彼の手つきは手馴れているのに、消毒に関してはこんなに雑だとは思っていなかった。
「これが済んだら、もう行くのか?」
「うん。取引相手には話はつけてあるし、やっぱり人目の少ない時間の方がいいだろ」
ベッドに畳んで置かれたシャツに袖を通し身支度を整える。
今日も出掛けると伝えると、「車で行きなさい」と仕事でいない父親の代わりに母親が言っていたが、ベロアがいるから大丈夫と説得した。大体からして都市のど真ん中にあるメインタワーに車で向かう方が目立つような気がするし、花籠にもあまり警戒されたくなかった。
最初の頃によく2人で乗っていたバイクを引っ張り出し、ベロアを後ろに乗せる。なんだか少し前に時間が巻き戻ったような錯覚すら起きるが、前よりもベロアの身体が近いのが嬉しく思えた。
「デカいな」
塔の前にバイクを止め、一足先に降りたベロアが感心したように呟いた。
地下の1番中心となる都心、その中央にそびえ立つメインタワー、通称「ラプラスの塔」。
この建物の最上階にスーパーコンピューターラプラスは存在し、この地下の全てのデータがそこにあるという噂だ。
塔のゲートにはベロアに負けず劣らずの屈強な男が数人、厳しい顔で警備に当たっている。
別にやましいことなどしていないし、むしろ手違いでなければ招かれた身だ。堂々としていればいいのだが彼等の圧に思わず縮こまりそうな思いで、ゲートにもうけられた監視室の窓に顔を出す。
「ご用件は?」
これまたガタイのいい男が営業スマイルなど一切ない威圧的な態度で俺を見下ろす。
背後のベロアが彼に対して威嚇するようにガンを飛ばしていた。頼むからこんなところで騒ぎを起こさないでくれと俺は彼の手をトントンとなだめるように叩く。
「えっと、ピンクホーネットって聞いてないですかね…?」
「ピンクホーネット様…お話は伺っております。通行許可証をお持ちですよね、拝見させていただきたいのですが」
男に言われて俺は、昨日花籠から送られてきたデータをゲートに設けられた端末に送る。
「…はい、確かに」
男は俺とベロアに首から下げるタイプのICカードのようなものをそれぞれ渡されゲートを開く。
「奥のエレベーターホール前でお待ちください。案内の者が参りますので」
俺たちはゲートをくぐり建物の内部へと進んでいく。
「すげえ…本当に入れた」
「簡単には入れないとこなのか?」
首に下げたICカードをいじりながらベロアが首をかしげる。
「そりゃな。この地下都市のいわば脳みそみたいな所だ。関係者以外は入れないし、関係者でもめったに入れねえって話だぜ」
実際、このメインタワーはこれだけの大きな建物でありながら、その内部や使用用途について、公開されていない部分がかなり多い。
このタワー丸々ラプラスのコンピューターだとか、人造人間の研究所だとかそれらしい推察から根も葉もない噂話まで飛び交っているほどだ。
長く飾り気のない広い通路を進んでいくと、ゲートの警備員が言っていたエレベーターホールらしき場所に出た。
エレベーターの扉が3つと申し訳程度のベンチソファがあるだけの殺風景な広間には、ここまでの道のり含めて全く人気が無かった。
「ここで待ってろって話だったか…」
ベンチソファに座って案内の者とやらを待つ。その案内人が花籠だったりするのだろうか。
一体どんな人なのだろう。上層部の人間だとしたら、それなりの大人だろうと思うが…あんな可愛い顔文字でおっさんが来たら凄い驚く。顔に出さないように気をはらなければ。
ベロアも緊張からかあまり言葉を発さず、静かに俺の隣に座って辺りをしきりに見まわしていた。
数分ほどそこで待っていると目の前のエレベーターのランプが点灯する。
上から降りてきているであろう人物の姿に思いを馳せていると、静かにその戸は開かれた。
中にいたのは二つの人影。小柄で黒髪の眼鏡をかけたスーツ姿の男性と、彼にリードでつながれた大きな身体の灰毛の男性。しかし大きな方は写真で見た猫のような締まった瞳孔に逆立った獣のような耳、作り物には見えない尻尾など異様な空気を放っている。
「ピンクホーネット様でお間違いないですか」
「あっ、はい。あなたが案内の…?」
淡々とどこか面倒くさそうな口調で問いかける彼に俺は警戒しながらも、出来るだけ好意的に答える。
小柄な男の背後に立つ大きな男は、猫背であることを考えれば身長はベロアよりも大きいだろうか。彼の放つ殺気にも似た異様な空気にベロアは威嚇するように小さな唸り声を上げる。
「ベロア、大丈夫だって」
彼をなだめる正面で小柄の男もつないだリードを軽く引いて男の気を向けさせる。
「Max stay.(マックス、待てだ)」
彼の呼び声に大きな男は一見無反応のように見えたが、彼から放たれていたピリピリとした殺気が消えるのを感じた。
「では、こちらに。ラプラスの元までご案内します」
彼に促されて俺たちはエレベーターに乗り込む。小柄な男は慣れた手つきでパネルを操作し扉を閉じる。
大柄の男二人が詰め込まれても広々としたエレベーター内で、特に話をすることもなくドア上の階を表すランプが上に登っていくのをただ眺める。
彼が花籠なのかと思っていたが、口調や仕草からするとあまりそうとは思えない。彼の様子を横目でチラチラと確認するが、彼は俺たちのことなどまるで興味がないのか見向きもしなかった。
暫くするとエレベータが停止しドアが開く。階を表すランプは最上階を示していた。
「こちらです」
小柄の男は薄暗い廊下を歩き出す。配管や配線がむき出しになったような壁にガラス張りの床、いつか映画で見たSFの宇宙船を思い出させるような廊下の先に重そうな鉄の扉が鎮座していた。
「ラプラス。連れてきた」
男が扉をノックして声をかける。
てっきり音声操作でも行うための「ラプラス」という枕詞を用いたのかと思いきや、中から「どーぞー」と気の抜けた少年のような声が返される。
ラプラスはスーパーコンピューターであるという認識が一般的だが、これではまるでラプラスが人間だとでも言うようだ。いや、まだ少年の声がコンピューターのものという線もある。過度な期待はよそう。
小柄な男が扉を押し開く。が、俺も人の事は言えないが小柄な彼では重い扉を開けるのにかなり力がいるようで、少し苦しそうに呻きながら扉を肩で押そうと踏ん張っている。
隣の大柄な男はまるで気にしていない様子で大きな欠伸をしていた。
「Max!!」
小柄の男が苛立った様子で彼を呼ぶと、「しょーがねーなー」というセリフが似合いそうなもったりとした動きで、額で扉を押して開く。
「では…自分は…これで…」
肩で息をしながら男は咳払いをし、リードを引いて廊下を戻っていく。
「あの…その変わった耳、本物ですか?」
興味に負けて男について行こうとする、大柄な男に声をかける。彼は犬のような耳をピコピコと動かしながら首を傾げたが、小柄な男がリードを催促するように小さく引っ張った。
「ただのコスプレですよ。ケモナーって日本人は言うんでしたっけ。彼はそういうのに憧れてて」
小柄な男はいかにも愛想笑いと言うような、ギクシャクとした歪な笑顔を浮かべて答える。多分、本当は笑うのが苦手なのだろうと、見ているだけで分かる不格好さだ。
エレベーターに男が乗り込み、背の高い男もそれに続く。
「なので、他言無用でお願いします」
エレベーターが閉まる際に小柄な男の声だけが残される。エレベーターが下っていく音を聞きながら、しばらくそれを呆然と見送ってしまった。
「ホーネットさん。どうぞ奥へ」
背中からあの少年のような声で呼ばれて、俺は扉に振り返る。ベロアと目を合わせて頷き、中へと踏み込む。
中は真っ暗と言っても過言ではないほど暗く、奥に進めば完全に先が見えなくなりそうに思えた。手探りで奥へと足を進めると、あの重そうな扉をベロアが進んで閉めてくれる。
扉が閉じると同時に部屋中に張り巡らされた配線が赤やオレンジ色に光り部屋の中を照らした。
子供たちと住んでいた家のリビングルームくらいの広さの空間に古めかしいソファとテーブル。壁をくりぬいたような広いベッドはクッションや毛布がぐちゃぐちゃに散らかっており床にはレーションの包み紙のようなものがいくつか落ちている。
何より印象的だったのは前面の壁一面はモニターが敷き詰められ、地下中の街の様子と思われる映像が映し出されていた。
そのモニターの前には高そうな革張りのオフィスチェアに膝を抱え込むように座った炎のような赤い髪の男が両手で顔を覆った状態で鎮座していた。
「お待ちしてました、ピンクホーネットさんとその想い人さん」
両眼を隠したまま彼は口元だけでにんまりと笑みを浮かべた。
「…花籠さんか?」
脳での情報処理が色々と追いつかないまま、目の前の男に問いかける。見えていないような気もするが、俺も被っていた帽子を取り、笑みを作って頭を下げた。
「はじめまして、ピンクホーネット…本名ヴィクトール=ブラウンシュヴァイクです」
名乗るか少し迷いながら、ハンドルネームに本名を添える。こんな場所まで招かれておいて名乗らないのは無礼だろう。
「ブラウンシュヴァイク?」
両眼を覆った彼は俺の言葉に驚いたような声でその手を避ける。ベロアとはまた違った鮮血のような赤い瞳で俺をまじまじと見てその背後のベロアにも目を向ける。
「おやおや!おやおやおやあ!これはこれは!どうせなら直前までおたのしみと思って目を覆っていたんですけど、まさかピンクホーネットさんがあの超有名なブラウンシュヴァイクのご子息様だったとは!」
彼は心底楽しそうに笑うと椅子から立ち上がって俺に手を差し出す。
明かりがついたとはいえまだ薄暗い室内で、先ほどまでは気づかなかったが、彼の両腕と両足にはリングのような機械が枷のようにはめられており、そこから伸びたコードが壁の機械へとつながっている。
「花籠、改めラプラスと申します。よろしくお願いしますね!」
差し出された手と彼の顔を交互に見つめ、笑顔を浮かべたまま握手をかわす。
なんでもない様な顔をしているつもりだが、ちょっと現実味が湧かない。ラプラスを人間であるとする説は確かに地下にはあるが、確率は相当低かった。それが、現にラプラスを名乗り、実際に塔の最上階にいる。これを嘘の一文字で片付ける方が無理があった。
「ラプラスなんて、俺よりよっぽど有名人だと思うけど」
メールの印象通りフランクなラプラスに、俺も砕けた言葉で感想を述べる。
「ンフフ。でもボクは人だと思われてませんからね~、有名人って言えるかどうか?知名度って言うならちょっと自信ありますよ!」
変わった笑い声を漏らしながら俺を舐めるように見つめた。
「ということは一昨日の誘拐騒ぎ、アレかなり手酷くやられてたじゃないですか大丈夫でした?」
まるで現場を直接見ていたかのような口ぶりに俺は感心に目を丸くする。これだけ詳しいあたり、ラプラスというのはやはり本当なのだろう。
「やっぱり知ってるんだな。恥ずかしいところ見せた」
「貴方に遠慮なく申し上げると、映画のワンシーンみたいでボクは楽しかったですよー?でも被害者が良き友人であったとわかると急に腹が立ちますねー…」
不満げに口をとがらせて足で地面をいじると彼はベロアに向き直る。
「しかし驚きました。ボクの推し作家のホーネットさんの想い人が貴方だったとは。巨人の落とし物よ」
オフィスチェアに座りなおす彼は肘掛に頬杖をついてにんまりと笑う。ベロアは訝しげに眉をひそめた。
「巨人…?」
「ああ、これは愛称ですよ。先代のラプラスは貴方の事を大変気に入っていたんです。その呼び名を考えたのも彼女です」
くるくるとオフィスチェアを回しながら話すラプラスに俺は首を傾げる。
「先代?ラプラスもやっぱり人間だから、世代交代するのか?」
よく始末屋であったり、掃除屋であったり、何かしら看板を掲げる地下の人間たちは、よく次の世代に家業を継ぐ。俺もそうであるからには、ラプラスも例外ではないだろう。
「ええまあ、人の命は有限であり、ラプラスは絶えるわけにはいきませんからね。世代交代は必要不可欠ですよ。ただ…ラプラスになれる人間はとても貴重なので必ずしも子が継ぐというわけではありませんがねぇ」
回していた椅子を止めて彼は自分の頭を人差し指でちょんちょんと指して見せた。
「さて、ボクの話よりも彼の話ですよね。巨人の子…名前は確かー…ベロアでしたっけね」
ラプラスの様子にベロアは少し緊張した様子で後ずさる。
下がってくる背中に優しく手を添えて、俺はベロアに笑いかける。
「大丈夫、一緒にいるから」
「…ああ」
少しだけ緊張のほぐれた顔で彼は微笑んだ。
「彼の何を調べたいんですか?生い立ち?血縁者?」
片手でパネルやキーボードをカチカチと操作しながらラプラスは俺達に目を向ける。
「…産みの親と…それからその親とどうして離れたのか。本当の両親が…どうしているのか…」
「はーい、じゃあ聞くより見た方が早いと思うので記録をお出ししますね。あ、そこのソファ使っていいですよ、ちょっと古いですけど掃除はしてるんで」
ラプラスに言われて指定されたソファに腰を掛ける。随分と使い込まれているようで、革張りの表面には細かい亀裂が無数に入っており、酷く軋む。
「年代物使ってんね」
あまり座り心地のよくないそれを手で押したりしながら感触を確かめる。ラプラスともあろう人間が、随分と質素な生活を送っているもんだ。
「それ、ボロって言うんですよ~?」
「身も蓋もねぇな」
せっかくオブラートに包んで表現したのに、本人に核心を突かれて俺は思わず笑う。俺に続いて隣にベロアも腰を下ろした。
「おふたりは『巨人』をご存知ですか?」
にんまりと笑みを称えたまま首を傾げるラプラスにベロアは首を横に振る。
俺はその名前には少し聞き覚えがあったが、ベロアの様子を見て、あえて何もリアクションをしないでおいた。
「聞いたことは無い。絵本のそれとは違うだろ」
「ええまあ、意味合いは同じですけどね。『巨人』って言うのは今から十数年前にちょっと流行ってた始末屋さんですよ。体が大きいから巨人。安易な看板の割にそこそこ売れっ子だったとか」
ラプラスの背後にある大きなモニターが切り替わり映像が流れ始めた。
どこかの市場のような場所で買い物をする若い女性。背は低く日本人のように見える彼女は身重らしくお腹は大きく膨らんでいる。
「彼女の名前はナツミ・ガーリブ。彼女はもうすぐ母親になろうとしていました」
映像の中の女性が重そうな紙袋を抱えて歩き出すと、後ろから大きな腕がそれを取り上げる。
腕の主は紙袋を抱え直すと、彼女を愛おしげに撫で額にキスを落とす。
その大柄な男の姿に俺は息を飲んだ。
浅黒い肌にルビーのような瞳、厚い唇とふっくらした涙袋はベロアと瓜二つだ。
「こちらの彼はもうすぐ父親になろうとしてました。名前はアースィブ。始末屋『巨人』であり、彼女の配偶者です」
女性が市場で買い物をし、商品を受け取る。それを男が受け取り微笑み合う。その短い映像が繰り返し流れる。
「身重の妻を想って、彼は1匹の犬を買いました。これから生まれる我が子と母になる妻に手を貸してもらうための労働犬、これが彼らの運命を大きく変えることになってしまった」
ラプラスの背後の映像が切り替わる。郊外の広い庭のある一軒家。その庭に置かれたゆりかごにまだ生後間もない赤ん坊が眠っていた。傍らには子供を寝かしつけていたのであろう母親もうたた寝している。
「彼らの家に買われた犬は、アースィブに恋をしていたようですね。好きな相手がすぐ側で別の女を愛して、子を育てるのを彼女はどんな思いで見ていたのかボクにはわかりませんね」
隣に座るベロアに目を向けると、彼は画面を食い入るように見つめている。
限りなく部外者に近い俺からすれば、一つの映画を見せられているようだった。色々な憶測が膨らむが、ベロアの感性を無視して面白半分に話していいものではない。俺も黙ってモニターへと視線を戻した。
「嫉妬に狂った犬は彼らの産まれたばかりの赤ん坊を奪って逃げたんです。もちろん彼らは直ぐに赤ん坊を探して犬を追ったことでしょう、でも…」
モニターが切り替わる。雨が降る夜の街中に倒れる赤ん坊を盗んだ犬、彼女の腹からは大量の血が流れ道を染めていた。
「逃げるのに夢中で慌てすぎちゃったんでしょうね。車にぶつかってあの有様です。GPSを頼りに追いかけてきた両親が見たものは、道端でぐちゃぐちゃになった犬の死体。さぁて赤ん坊はどこへやら…」
本来なら、地下の人間たちには全員マイクロチップが入れられている。それは、地上から攫われてきた人間であれば、誘拐されてきたその日に。地下で生まれ育った人間なら、1歳の誕生日に。施術が出来る医師に依頼、または施術専門の施設に子供を連れていくことで痛みもなく埋め込むことが出来る。それは自分の身分を証明する証として生涯機能する。
チップを持たないのは、それが出来ない野良犬だけ。ベロアも飼い犬登録をした時に入れた。
しかし、このような事件があった場合も、人間であるはずなのにマイクロチップを入れられなかった事になる。つまり…人間なのに、野良犬と変わらない状態になってしまったということだろう。
ベロアの両親は犬の死体を目の当たりにし、赤ん坊がいない事実に泣き崩れる母親とやり切れない表情で唇を噛む父親を映し出していた。
「少し時間を戻しましょうか」
ラプラスがそう言うと画面の映像は逆再生され赤ん坊を抱えた犬が車に跳ねられた直後を映し出す。
まだ辛うじて意識を持つ犬に駆け寄るひとつの影。フードから覗く金色の髪と青い目は、以前ベロアが話していた母親の特徴と一致する。
「あれは…」
それを肯定するようにベロアは言葉を漏らした。
金髪の女性は自身が纏っていたローブで、地面に転がった赤ん坊を雨から守るように包み抱き上げる。
赤ん坊を連れて横たわる犬に近づくも、しばらく経つとその場を立ち去っていく。
「あれが…俺と…母親…」
その後映像がベロアの本当の両親がたどり着く場面を映し出したのを見て彼は目を細めた。
「あれが…本当の」
彼の声に画面の映像は元の地下世界の映像に切り替わった。
「どうですか?知りたいことは知ることが出来ました?」
下を向いたまま困惑しているベロアにラプラスは首を傾げて問いかける。
「あれ、なんか納得いかない感じですか?質問あるなら受け付けますよ?」
俺はベロアの背中をさすりながら、ラプラスに小さく手を上げる。
「ベロアはつまり、人間だったってことだよな。飼い犬登録で、犬としてマイクロチップを埋め込んでしまったんだ。これを人間に書き換えるのって、手続きをすれば可能なのか?」
ベロアは恐らく、まだ混乱しているだろう。俺からも聞きたいことはいくつかあるので、彼が頭を整理する時間を作るためにも先に質問を繰り出す。
「出来なくはないですけどー…正式にやるならそれはあなたではなく、彼の両親か血縁者が行わなければいけません。血液検査などで血の繋がりを証明して、人間であると確定させる必要もあります。人間である証明と親や親戚に当たる人物からの申し出。そのふたつがないと難しいかと?」
ラプラスはイスをクルクルと回転させながら楽しげに答えた。
「なるほど、やろうと思えば何とかなりそうだ」
ここまでの情報があれば、巨人を探し出すのはベロアほど難しくないだろう。幸い、彼の顔も、顔どころか父親のやることなすことベロアに生き写しだ。存在そのものが証明みたいなものだろう。
「もう一つ聞いておきたいんだけど、巨人たちは今もまだこの地区周辺にいる?答えるのが難しければ、情報屋を洗うから断ってくれていい」
ダメもとで追加の質問を投げると、ラプラスはにまっと笑みを浮かべて回転させていたイスを止める。
「本当は他人の情報勝手に売るのあんま良くないとおもってるんですよー?でもホーネットさんは特別です!なーんたってボクの最推し作家さんですからね!」
ラプラスがコンピュータのパネルに触れると画面は切り替わり地図を映し出す。
「南方の小さな街の集まるエリア、今はそこに住んでいます。住所は見てのとおりで…あ、なんならあなたの端末に送りましょうか?サービスですよー?」
もじもじと機嫌良さげに笑う彼に俺は頷く。
こんな地下の神にも等しいラプラスから最推し作家の称号を得てしまうなんて、いい気にならないわけがない。
「お願いしてもいい?代わりに最新作の続編、力入れて書くから」
「ほんっとですか!?ボクあれすーっごく好きで楽しみにしていたんです~!!」
無邪気に喜ぶ彼がパネルを操作すると、花籠からのメッセージに、巨人の住処のデータが添付されてきた。
「ありがと。大事にするし、今日のことは絶対に秘密にする。約束だ」
腕時計から顔を上げて笑うと、指切りをしようと小指を差し出す。
それをラプラスは不思議そうに見つめて首を傾げた。
「あっ…もう指切りとかこの年齢じゃ、普通しないか」
最近はベロアや子供たちの相手をしていたから、ついこういうことがすぐに行動に出てしまう。
「ああ!指切りでしたか!はい、知ってますよぉ!」
彼は思い出したように自身の小指を立てて俺に差し出す。それに俺の小指を引っ掛けて固く指を結んだ。
後ろでソファに座ったままになっていたベロアも立ち上がって、眉を下げで困ったような笑みを浮かべる。
「…ありがとう、とりあえず平気だ」
ラプラスと小指を切り、ベロアを見上げる。
「大丈夫?ラプラスになんて、滅多に会えないかもしれないぜ?」
「えー?ボク毎日暇なんでいつでも遊びに来てくださいよー!」
俺とベロアの会話に割り込むように飛んできたラプラスの言葉に俺は思わず声を出して笑う。
「そんなことあるー?遊びに来ていいならまた来るけどさ」
「ええ、暇すぎて同人小説とか読み耽る今日この頃ですからね?」
思っていた以上にラプラスが親近感のある存在だったのは驚きだが、心強い味方に変わりはない。俺はそれに笑って頷いた。
「じゃあ、また来る。ラプラスも暇な時はうちにも遊びに来いよ」
ベロアの手を引いて、出口へ向かう。やけに静かなのは、まだベロアも悩むことがたくさんあるからだろう。それなら、家でゆっくり休ませてやりたかった。
ラプラスは俺たちに手を振って見送る。それに手を振り返し、メインタワーを後にした。
0
お気に入りに追加
32
あなたにおすすめの小説

膀胱を虐められる男の子の話
煬帝
BL
常におしがま膀胱プレイ
男に監禁されアブノーマルなプレイにどんどんハマっていってしまうノーマルゲイの男の子の話
膀胱責め.尿道責め.おしっこ我慢.調教.SM.拘束.お仕置き.主従.首輪.軟禁(監禁含む)
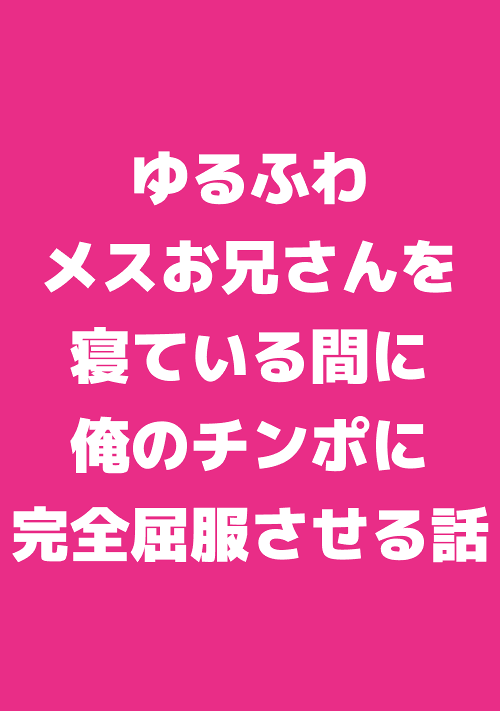
ゆるふわメスお兄さんを寝ている間に俺のチンポに完全屈服させる話
さくた
BL
攻め:浩介(こうすけ)
奏音とは大学の先輩後輩関係
受け:奏音(かなと)
同性と付き合うのは浩介が初めて
いつも以上に孕むだのなんだの言いまくってるし攻めのセリフにも♡がつく

山本さんのお兄さん〜同級生女子の兄にレ×プされ気に入られてしまうDCの話〜
ルシーアンナ
BL
同級生女子の兄にレイプされ、気に入られてしまう男子中学生の話。
高校生×中学生。
1年ほど前に別名義で書いたのを手直ししたものです。


【BL-R18】変態ドM勇者の淫乱一人旅
ぬお
BL
※ほぼ性的描写です
とある世界に、一人旅をする勇者がいた。
その勇者は気ままな旅をしながら立ち寄った村、町、都市で人々を救っている。
救われた人々は皆、感謝の言葉を口にして勇者を賞賛した。
時には、涙を流して喜ぶ人々もいる。
・・・だが、そんな勇者には秘密の悪癖があったのだった。

淫紋付けたら逆襲!!巨根絶倫種付けでメス奴隷に堕とされる悪魔ちゃん♂
朝井染両
BL
お久しぶりです!
ご飯を二日食べずに寝ていたら、身体が生きようとしてエロ小説が書き終わりました。人間って不思議ですね。
こういう間抜けな受けが好きなんだと思います。可愛いね~ばかだね~可愛いね~と大切にしてあげたいですね。
合意のようで合意ではないのでお気をつけ下さい。幸せラブラブエンドなのでご安心下さい。
ご飯食べます。


『僕は肉便器です』
眠りん
BL
「僕は肉便器です。どうぞ僕を使って精液や聖水をおかけください」その言葉で肉便器へと変貌する青年、河中悠璃。
彼は週に一度の乱交パーティーを楽しんでいた。
そんな時、肉便器となる悦びを悠璃に与えた原因の男が現れて肉便器をやめるよう脅してきた。
便器でなければ射精が出来ない身体となってしまっている悠璃は、彼の要求を拒むが……。
※小スカあり
2020.5.26
表紙イラストを描いていただきました。
イラスト:右京 梓様
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















