3 / 14
第一章
2話 怪異を背負う人
しおりを挟む
「お疲れ様です」
そう声をかけて、バイト先である居酒屋の休憩室のドアを開ける。部屋の奥で事務作業をしていたらしい店長が、椅子ごとこちらを振り返った。
「おつかれー早坂くん。今日はもうあがりだっけ?」
「はい。明日は大学の方に顔出さないといけないんで」
長期休暇中はいつも閉店時間の午前二時まで勤務しているのだが、明日は大学での集中講義に参加するため、日付が変わる前にあがらせてもらったのだった。
「がんばるねえキミも。アタシが言えた義理じゃないけど、あんま無理しないのよ?なんか最近顔色良くないし……早坂くんに倒れられると、うちとしても困るのよね。学生でがっつり働いてくれる子って貴重だから」
「はは……そうですね。気をつけます」
咄嗟に笑って誤魔化したが、内心では冷や汗をかいていた。うまく隠してきたつもりだったが、店長にはバレつつあるのかも知れない。逃げるように更衣室に駆け込んで着替えを済ませ、店長に軽く挨拶をして店を出る。
扉を閉める寸前に見えた、彼女の肩にまとわりつく黒い靄に、気づかないふりをしながら。
真っ暗な夜道を、自転車に乗って帰路に着く。
例の肝試しの夜から一週間ほどが経った。そう。思い返せばあの日からだ。いろんな事が、おかしくなってしまったのは。
できる限り周囲の暗闇に目を向けないようにしながら、無心で自転車を漕ぐ。けれどそんな努力も虚しく、ほんの数メートル先に佇む街灯の下に、それはいた。
それに気づいた瞬間、早坂は慌ててブレーキを握りしめた。甲高いブレーキの音が、静かな住宅街に響く。
頼りなく明滅する灯りの下に、何かがいる。
それは、一見ごく普通の人影のように見えた。だが、よく見ると明らかにおかしい。
なぜ、手や顔があるはずの場所まで真っ黒なんだろう。逆光のせい?灯りの真下にいるのに?
手のひらに汗がにじむ。怖いのに目が離せない。しかし、ほんの一瞬まばたきをした直後、それは跡形もなく消えていた。
そんな馬鹿な、どこに行ったんだ。慌てて視線をさまよわせるが、影はどこにもいない。
本当に消えてしまったのだろうか。
けれど、そうだとしても、あの街灯の下を通る気には到底なれない。仕方なく自転車を反転させて、別の道に向かおうとした。その時。
ついさっき通り過ぎてきた、別の街灯の下に同じ影が佇んでいた。今さっきと寸分違わぬ姿で、ただそこに立っている。
早坂は考えるよりも先に、灯りのない脇道へと飛び込んでいた。
自転車のライトだけが照らす薄暗がりの中、必死で自転車を漕ぎながら、頭のなかでは同じ言葉がぐるぐると回っている。
「なんなんだよ……!」
どうして、なぜこんなものが見えるんだ。しかも日を追うごとに、どんどん見える数が増えている。
頭がおかしくなりそうだった。いや、もしかしてとっくに自分は狂っているのか。だからこんなものが見えるのか。
こんなこと、誰にも相談できない。ある日突然化け物が見えるようになったなんて、どんな顔をして言えばいい?
……いや、もしかすると優也なら話を聞いてくれるかも知れない。けれど、話したからといって何になる。
それに、こんなことを話しておかしなやつだと思われて嫌われたら……そんなはずはないと分かっていても、それがなにより怖かった。
どうにか辿り着いたアパートの駐輪場へ乱暴に自転車を停めて、部屋へと駆け込む。
自宅の中では、まだあの化け物たちを見ていない。それだけが唯一の救いだった。けれど、それもいつまで持つか分からない。
「どうしたらいいんだよ……」
問いかけても、一人の部屋に答える者はいなかった。
*
翌日。眠れない夜を過ごした早坂は、それでも予定通り大学へ向かって講義を受けた。といっても、全くと言っていいほど集中できなかったが。
精神を蝕まれるような恐怖を感じながらも、その反面で単位だとか卒業だとか、そんな現実的なことにも頭を悩ませている自分がひどく滑稽だった。いや、むしろそうやって、無理矢理現実から目を逸らそうとしているのかもしれない。
(一人に、なりたくないな……)
一人でいると、また何かおかしな物が見えてしまうかもしれない。バイト先での件もあるから、誰かといれば見えなくなるといった物ではないのだろうが、それでも気持ちの上では幾分かマシだ。
(そうだ、安曇さんなら今日もいるかも)
ふと脳裏に浮かんだのは、あのボサボサ頭の先輩の顔だった。彼なら長期休暇中だろうがお構い無しで資料室に居座っている可能性が高い。
どうせ今日はこの後の予定なんて何もないのだ。会いに行ってみよう。あの世捨て人のような先輩に。
光都大学の四号館。敷地の端に位置するこの建物は、もともとフロア全てが資料館として使われていたのだが、二号館の図書室が増設された際にほとんどの蔵書が移されてしまい、今は利用する者もいなくなってしまった。そこに目をつけて勝手に居座っているのが安曇清春である。
四号館が取り壊されるのが早いか、安曇が大学を出るのが早いか。もっとも安曇の方にまともに卒業する気があるのかどうか、怪しいものだが。
「安曇さん、いますか」
声はかけたものの、応答を待たずに早坂は四号館の一室に足を踏み入れた。いようがいまいが、安曇が返事を返してきたことなんてないからだ。
一度は空になった本棚は、安曇が持ち込んだ本が乱雑に詰め込まれて再び満杯になっている。そんなスチール製の密林の奥に、見慣れたぼさぼさ頭がちらりと見えた。思った通り、今日も今日とて文字通り本に埋もれていたらしい。閲覧スペースの椅子に腰掛けて頬杖をついていた安曇は、早坂に気づいて顔をあげた。
「やあ早坂くん、久しぶり。元気……ではなさそうだね。まるで死人のような顔をしている」
「いきなりずいぶんな挨拶ですね」
ムッと言い返して早坂はその向かいの席に腰を下ろした。そこが早坂の定位置である。
安曇は読みかけの本を手に持ったままで、目を眇めて早坂の顔を見つめる。ちらりと見えた本のタイトルは、スティーブン・キングの『シャイニング』だった。先月までは筒井康隆を片っ端から読み漁っていたように記憶しているが、もう全て読み終えてしまったのだろうか。
「よくそんな怖い話とか気持ち悪い話ばっかり好き好んで読みますよね」
呆れつつ発した早坂の言葉を安曇は鼻で笑って、
「酔狂は君も同じだろう?わざわざ肝試しなんてものに参加して、案の定"もらってきて"しまったのではないかい」
見透かすような口調で、そう言った。
いつもなら、からかわないでくれと怒るところだが、今は黙って目を逸らすことしかできない。認めたくはないが、早坂にとって思い当たることが多すぎた。
「やれやれ……無茶と無謀は若人の特権だが、今回は少々軽率に過ぎたようだね。いったいどうするつもりだい?」
「どうするって……」
握っていた手に、知らず力がこもった。どうにかできるものならとっくにやっている。原因も解決策も、何も分からない。ここでこうしているのだって、問題を先送りしているだけ。要するにただの現実逃避だ。
黙り込む早坂を前に、安曇も何も言わない。馬鹿にするでもなく、嘲るでもなく、黙ってこちらを見つめている。
その視線に居心地の悪さを感じて、わずかに顔を伏せた。安っぽい造りの机の下に、履き古したスニーカーと白い手が見える。
…………手?
高校時代から愛用している、履き慣れた黒いスニーカー。その爪先に縋るように、ボロボロにひび割れた指が張り付いている。血の気の失せたそれは、まるで巨大な白い蜘蛛のようで……
「うわあああああああっ」
脳がそれを認識するより前に、体が反応していた。弾かれるように椅子から飛び退いて、机の下から足を引き抜く。弾き飛ばされたパイプ椅子が、床に叩きつけられてけたたましい音を立てた。
「早坂くん?」
さしもの安曇もぎょっとした顔でこちらを見ている。だが早坂の方にそれを気にする余裕はない。
慌てて足を引いたおかげで、手はスニーカーから離れたようだった。だが、手首までしか見えていなかったはずのそれは、気づけば肘までが顕になり、異常なまでに長い腕が、まるで蛇のように身をくねらせて、机の下から這い出そうとしている。
それ以上はもう、耐えられなかった。
脇目もふらずに部屋を飛び出す。四号館の近くを通りかかった学生達は、必死の形相で走り出てきた早坂をなんだと思っただろう。いや、それよりも安曇は?
想像していた最悪の事態になってしまったと、そう気がついたのは、どうにか自宅に帰りついてからのことだった。
「最悪だ……」
畳の上に力なく崩れ落ちる。
何もない場所を見て悲鳴をあげて逃げ出すなんて、逆の立場なら気が触れたとしか思えない。次からどんな顔をして安曇に会えばいいのだろう。
この先のことを思うだけで目眩がする。深くため息を吐き出した直後、突如部屋の中に響き渡ったインターホンの音に文字通り飛び上がった。
「奏太!奏太いる?」
続いて聞こえた親友の声に慌てて立ち上がる。
「優也?」
なぜこのタイミングで。一瞬躊躇ったが、扉の前から優也が立ち去る気配がないのでやむなくドアノブに手をかけた。
「あ、いたいた。よかった、帰ってたんだな」
アパートの外廊下には、タンクトップに高校時代のジャージという、明らかに部屋着と思われる格好に身を包んだ優也が立っていた。
「なんだよ、突然どうした?」
早坂が訊くと、優也は無言でスマホの画面を見せてきた。そこに表示されていたのは、何の変哲もないLINEのトーク画面のようだったが、よく見ると、驚いたことにトーク相手の名前が「安曇先輩」になっている。いつの間に安曇とLINE交換なんてしていたのだろう。そもそも早坂は安曇がLINEをやっていたことを今知った。一年以上同じサークルで過ごしてきたというのに。
いや、そんなことよりも。
「……安曇さんに聞いたのか」
優也は黙ったままで頷いた。苦い思いが広がる。あんなに隠したいと思っていたのに、結局優也にまで知られてしまった。
「あのさ。もしかして奏太、なんか変なもの見えてる?」
率直な優也の問いに、答えることができない。これはどちらの意味で聞かれているのだろう。幻覚を見ていると思われているのか、それともいつもの霊的な話か。
黙り込む早坂を、優也は困った顔で見上げてくる。
「それってさ……やっぱ、あの肝試しのせいだったりする?」
その一言で、優也がここに来た理由に察しがついた。
「……そんなこと分からないし、そうだとしても、俺が自分から行くって言ったんだよ」
だから優也が気に病む必要はない。言外に、そういう意図を込めたつもりだった。
けれど優也の表情は晴れない。
「……あのさ。奏太はこういうの嫌かもしんないけど、一回この人に相談してみないか?おれの好奇心とか都合とか置いといて、ホントにこれしか思いつかないからさ」
そういって、優也は財布の中から小さなカードを取り出した。
「名刺?」
優也に渡されたその名刺は、名前と住所だけが書かれたシンプルなものだった。白地に黒い明朝体で書かれた名前は、“井ノ原圭”。
「もしかして、この人……」
「そう。その人が、前に話した霊媒師だよ」
もう一度、素っ気ないデザインの名刺に目を落とす。優也の言う通り、普段の早坂ならこんな誘いは受けないだろう。けれど、今は藁にもすがりたい心境だった。
なにしろ今も優也の背後で、アパートの上階からぶら下がる逆さまの女が、こちらを見つめているのだから。
*
そうして優也に案内されて訪れたのは、大学がある表通りからは少し離れた裏通りだった。
近代的なオフィスの隣に古びた商店がある、そんな時間の狭間のような奇妙な通りに、それはあった。
「ほら、ここだよ」
一度帰宅して、普段着に着替え直した優也が指したのは、通りの中でも一層古い門扉を構える小さな寺……ではなく、その隣にある薄汚れたコンクリートの建物だった。
二階建てのその建物は、一階に仏具店が入っていて、その脇の狭い階段には黒い紙に白い文字で『↖霊障相談』とだけ書かれた、やる気のない貼り紙がされている。なるほど、たしかに目的地はここで間違いないようだが。
もともとこの辺りは寺社の多い土地柄なので、このような抹香臭い立地もさして珍しいわけではない。なのに、なぜだろう。とてつもない胡散臭さを感じるのは。
「……やっぱり、やめといた方がいいかな」
思わず漏れた本音に、優也が慌てて早坂の腕を掴んで引き止める。
「ちょ、ここまで来てそれはないだろ?!大丈夫だって、相談するだけなら金かかんないし!」
「いや、そういう問題じゃなくて……ていうか、なんでそんな詳しいんだよ」
よくよく考えてみれば、あの名刺もいつ貰ったんだ。早坂の疑問に、優也はあっけらかんとして答えた。
「前来た時に、ここの霊媒師を偶然見かけたって話したろ?そん時に、どうにか仲良くなりたくて、いろいろ話しかけてたら教えてくれた」
「お前のその異常なコミュ力、ホントなんなんだよ……」
何をどうしたら、初対面の霊媒師相手にナンパまがいのことをしようという気になるのだろう。早坂が呆れて踵を返そうとした時、不意に後ろに現れた人影にぶつかりそうになった。
「あ、すみません」
「いえ、こちらこそ……もしかして、ご依頼の方でしょうか」
依頼?その言葉に、はっとして視線を下げた。
真っ黒な影。その人物を見て、真っ先に浮かんできたのは、そんなイメージだった。束ねた長い黒髪に、同じく真っ黒なスーツ、そして真っ黒なハイヒール。全身を黒に包まれたその人は、まっすぐに早坂を見上げていた。
「あっ、井ノ原さん!」
優也が嬉しそうに声をあげる。ということは、やっぱりこの人物が噂の霊媒師か。
見たところ、年齢はおそらく二十代半ば。ヒールの分を抜きにしても、おそらく優也より背が高い。なるほど、この容姿なら優也が騒ぐのも頷ける。
花耶が日本人形なら、井ノ原はさしずめ西洋のビスクドールのように整った顔立ちをしていた。大きな猫目に、鋭い彫刻刀で削り出したように完璧なラインの鼻筋。おまけに身にまとった服とはどこまでも対照的に白い肌。優也が言っていた「すげー美人」は決して大げさな表現ではなかった。
「私の顔になにか?」
「あ、いえ……」
井ノ原に訝しげな視線を向けられ、慌てて目を逸らす。初めて会う人に対して不躾な態度だったかもしれない。
「井ノ原さん、お久しぶりです!おれのこと覚えてますか!」
早坂の後ろから顔を出した優也が食い気味に尋ねる。井ノ原は、そんな優也に視線を移したのち、にっこりと笑って言った。
「もちろんです。樋山さん、でしたよね」
井ノ原に名を呼ばれた途端、優也がパッと目を輝かせた。彼が犬なら千切れんばかりに尻尾を振っていることだろう。
「あの!今日はおれの友達のことで相談があって」
そういって、優也が早坂の腕を再びがっしりと掴む。
逃げるタイミングを完全に失ったと気がついたのは、そのまま井ノ原の事務所に案内されてからのことだった。
*
「どうそ、そちらにお掛けください」
井ノ原に勧められるまま、革張りのソファに腰掛ける。
井ノ原の事務所は綺麗に整頓されていて、外観から感じた胡散臭さとは無縁の、ごく一般的なオフィスだった。ブラインドが降りた窓の手前には事務机とノートパソコンが置かれていて、左右の棚には色分けされたバインダーが整然と並んでいる。井ノ原は几帳面な性格のようだ。
デスク前の応接スペースから室内を見回していると、井ノ原が三人分のコーヒーを持って戻ってきた。それぞれの前にカップを置いて、井ノ原も二人の向かいに腰をおろす。
「さて、それではお話を伺いましょうか。そちらのご友人……早坂さん、でしたね」
そういって、井ノ原は早坂に視線を向けた。正面から見据えられて、思わず口ごもってしまいそうになるが、ここまで来て黙っていても仕方ない。目の前の人物を信頼してもいいのかどうか。それだって、話してみなければ分からないのだから。
「……先週、ここにいる優也と他の友人達の四人で、近くの心霊スポットに行ったんです。その日から、おかしなものが見えるようになって」
「おかしなもの、とは?」
一瞬、隣の優也を横目で見やる。知られたくないと思ってしまうのも、今さらだ。
「最初は、影とか靄みたいなものだったんです。それが段々、人の形になって、それで……」
思い出しただけで、全身に鳥肌が立つ。幸いアパートからここに来るまでは、変わったものは見ていない。優也と話している間は忘れたふりをしていられたが、今になってまた怖くなってきた。
青ざめる早坂を見て、井ノ原はすっと目を細めて、そして驚くようなことを言った。
「あなた方が行った心霊スポットというのは、もしかして黒河トンネルですか」
「え……?」
優也が話したのかと思い、咄嗟に彼の方を振り返ったが、当の優也も目を丸くして驚いている様子だった。それはそうだろう、優也が初めてここを訪れたのは、肝試しを実行する前のはずだ。
「……なんで、分かるんですか」
警戒を顕に早坂が尋ねると、井ノ原はおかしそうに笑って答えた。
「そのくらい、よく観察すれば分かることです……と言いたいところですが、生憎私はシャーロック・ホームズではありませんので、見たままを言っただけですよ。早坂さんの中にいるんです、黒河の辺りにいたはずの、痩せぎすな若い男が」
井ノ原の言葉に、今度は別の意味で鳥肌が立った。
黒河トンネルは、この辺りの心霊スポットとしてはかなり有名だ。若者が面白半分で行きそうな場所として、適当にアタリをつけて言っただけの可能性もある。
だが、黒河トンネルに伝わる怪談話に登場する幽霊は、全て"女"のはずだ。それなのになぜ、あの夜早坂が夢で見たのと同じ、痩せぎすな若い男という単語が出てくるのか。
「中にいるって、どういうことですか」
それまで黙っていた優也が、おもむろにそう言った。これまでに見たこともないくらい、真剣な顔で井ノ原に向き合っている。
「優也……」
「それって、良くないものなんですか。奏太は……奏太はどうなるんですか」
「落ち着いてください、樋山さん」
身を乗り出して問う優也を片手で制して、井ノ原が悠然と微笑む。この人が浮かべる表情は、どれもとらえどころが無くて不気味だ。なまじ顔立ちが整っているだけに、余計そう感じるのかもしれない。
長い足をゆったりと組んで、井ノ原は先を続けた。
「霊なんてものはね、細菌やウイルスと同じです。目には見えないくともそこら中にいるし、多少体に入ってきたところで、大抵の場合は何の影響もない」
そこで一瞬言葉を切って、なぜか井ノ原は早坂に意味深な視線を投げる。
「……とはいえ、長く入り込まれれば、重篤な問題を引き起こす可能性があるのもまた同じ。率直に言いますが早坂さん。このままだと貴方……最悪死にますよ」
優也が息を呑む気配があった。しかし、早坂は井ノ原から……正確には井ノ原の背後から、目を逸らすことが出来ずにいた。
「さて。私の見立てはこんなところですが……どうしますか?ご依頼いただけるのであれば、貴方の中から、その男を追い出すことも可能ですが」
「……その前にひとつ訊きたいんですけど」
自分で思っていた以上に、掠れた声が出たのを自覚する。井ノ原が目線で応えたのを見とって、早坂は言った。
「あなたの背中にいるそれは……“何の影響もない”ものなんですか」
早坂のその言葉を聞いた瞬間、井ノ原はわずかに口角を上げて、
「ああ……貴方、これが見えるんですね」
とても愉快げに、そう言った。
井ノ原の体には、先ほどからずっと、無数の手がしがみついていた。肩に、腕に、腰に、大きさも爪の長さもバラバラで、それでいて揃って血の気の失せた手が、井ノ原のジャケットに絡みついているのだ。
「見えますよ。さっきからずっと見えてます……そいつが、あなたの中から出てきた時からずっと」
あまりにも自然な動作で、それは井ノ原の背中から生えてきたように見えた。そして、元々そういう生き物だったと言わんばかりに、当たり前の顔をしてそこにいる。
握った拳の中に汗が滲む。ひどく喉が乾いていたが、目の前のコーヒーに口をつける気にはならなかった。
怖い。今日までに見た、どんな化け物よりも。
「……井ノ原さん。あなた、本当に人間ですか」
沈黙が落ちる。
井ノ原は不意に右手で自分の顔を覆った。いくつもの手が貼りついたままの肩が震える。
井ノ原は笑っていた。心の底から楽しそうに、笑っていた。
「ふ、はは……っ、いいですねぇ早坂さん。貴方、とてもいいですよ。とても……面白い」
「……っ、ふざけないでください!」
勢いよく立ち上がった拍子に、テーブルに膝がぶつかり、コーヒーカップが硬い音を立てた。
「お、おい。奏太……」
「もういいです、あなたに相談することなんてありません。帰ります」
「そうですか?それは残念です。気が変わったら、いつでもいらしてくださいね」
「ありえませんから!」
言い捨てて事務所を飛び出す。少し遅れて、慌てた様子で優也も後を追ってきた。
「ちょっと待てって奏太!どうしたんだよ急に!」
事務所から少し離れた場所で立ち止まり、追いついてきた優也を振り返る。
「優也。悪いこと言わないから、あの人はやめとけ。上手く説明できないけど、絶対やばいから」
井ノ原の中に何かが居るのか、それとも井ノ原自身が化け物なのか。どちらにせよ、どう考えてもまともではない。
見えないからこそ、優也にはもう関わって欲しくなかった。
「奏太……」
「ごめんな、せっかく連れてきてくれたのに。けど、もう帰るわ」
そういって、優也の返事を待たずに早坂は事務所に背を向けた。結局、事態は何も解決していないし、いよいよ打つ手もなくなってしまった。
けれど、それでもあの井ノ原圭という霊媒師に頼ろうとは思えない。だってそうだろう。怪異と共存している者が、どうやって怪異を祓えるというのか。見えているのは本当なのかもしれないが、やっぱり霊媒師なんて嘘っぱちだ。
もう、誰にも頼らない。
そう声をかけて、バイト先である居酒屋の休憩室のドアを開ける。部屋の奥で事務作業をしていたらしい店長が、椅子ごとこちらを振り返った。
「おつかれー早坂くん。今日はもうあがりだっけ?」
「はい。明日は大学の方に顔出さないといけないんで」
長期休暇中はいつも閉店時間の午前二時まで勤務しているのだが、明日は大学での集中講義に参加するため、日付が変わる前にあがらせてもらったのだった。
「がんばるねえキミも。アタシが言えた義理じゃないけど、あんま無理しないのよ?なんか最近顔色良くないし……早坂くんに倒れられると、うちとしても困るのよね。学生でがっつり働いてくれる子って貴重だから」
「はは……そうですね。気をつけます」
咄嗟に笑って誤魔化したが、内心では冷や汗をかいていた。うまく隠してきたつもりだったが、店長にはバレつつあるのかも知れない。逃げるように更衣室に駆け込んで着替えを済ませ、店長に軽く挨拶をして店を出る。
扉を閉める寸前に見えた、彼女の肩にまとわりつく黒い靄に、気づかないふりをしながら。
真っ暗な夜道を、自転車に乗って帰路に着く。
例の肝試しの夜から一週間ほどが経った。そう。思い返せばあの日からだ。いろんな事が、おかしくなってしまったのは。
できる限り周囲の暗闇に目を向けないようにしながら、無心で自転車を漕ぐ。けれどそんな努力も虚しく、ほんの数メートル先に佇む街灯の下に、それはいた。
それに気づいた瞬間、早坂は慌ててブレーキを握りしめた。甲高いブレーキの音が、静かな住宅街に響く。
頼りなく明滅する灯りの下に、何かがいる。
それは、一見ごく普通の人影のように見えた。だが、よく見ると明らかにおかしい。
なぜ、手や顔があるはずの場所まで真っ黒なんだろう。逆光のせい?灯りの真下にいるのに?
手のひらに汗がにじむ。怖いのに目が離せない。しかし、ほんの一瞬まばたきをした直後、それは跡形もなく消えていた。
そんな馬鹿な、どこに行ったんだ。慌てて視線をさまよわせるが、影はどこにもいない。
本当に消えてしまったのだろうか。
けれど、そうだとしても、あの街灯の下を通る気には到底なれない。仕方なく自転車を反転させて、別の道に向かおうとした。その時。
ついさっき通り過ぎてきた、別の街灯の下に同じ影が佇んでいた。今さっきと寸分違わぬ姿で、ただそこに立っている。
早坂は考えるよりも先に、灯りのない脇道へと飛び込んでいた。
自転車のライトだけが照らす薄暗がりの中、必死で自転車を漕ぎながら、頭のなかでは同じ言葉がぐるぐると回っている。
「なんなんだよ……!」
どうして、なぜこんなものが見えるんだ。しかも日を追うごとに、どんどん見える数が増えている。
頭がおかしくなりそうだった。いや、もしかしてとっくに自分は狂っているのか。だからこんなものが見えるのか。
こんなこと、誰にも相談できない。ある日突然化け物が見えるようになったなんて、どんな顔をして言えばいい?
……いや、もしかすると優也なら話を聞いてくれるかも知れない。けれど、話したからといって何になる。
それに、こんなことを話しておかしなやつだと思われて嫌われたら……そんなはずはないと分かっていても、それがなにより怖かった。
どうにか辿り着いたアパートの駐輪場へ乱暴に自転車を停めて、部屋へと駆け込む。
自宅の中では、まだあの化け物たちを見ていない。それだけが唯一の救いだった。けれど、それもいつまで持つか分からない。
「どうしたらいいんだよ……」
問いかけても、一人の部屋に答える者はいなかった。
*
翌日。眠れない夜を過ごした早坂は、それでも予定通り大学へ向かって講義を受けた。といっても、全くと言っていいほど集中できなかったが。
精神を蝕まれるような恐怖を感じながらも、その反面で単位だとか卒業だとか、そんな現実的なことにも頭を悩ませている自分がひどく滑稽だった。いや、むしろそうやって、無理矢理現実から目を逸らそうとしているのかもしれない。
(一人に、なりたくないな……)
一人でいると、また何かおかしな物が見えてしまうかもしれない。バイト先での件もあるから、誰かといれば見えなくなるといった物ではないのだろうが、それでも気持ちの上では幾分かマシだ。
(そうだ、安曇さんなら今日もいるかも)
ふと脳裏に浮かんだのは、あのボサボサ頭の先輩の顔だった。彼なら長期休暇中だろうがお構い無しで資料室に居座っている可能性が高い。
どうせ今日はこの後の予定なんて何もないのだ。会いに行ってみよう。あの世捨て人のような先輩に。
光都大学の四号館。敷地の端に位置するこの建物は、もともとフロア全てが資料館として使われていたのだが、二号館の図書室が増設された際にほとんどの蔵書が移されてしまい、今は利用する者もいなくなってしまった。そこに目をつけて勝手に居座っているのが安曇清春である。
四号館が取り壊されるのが早いか、安曇が大学を出るのが早いか。もっとも安曇の方にまともに卒業する気があるのかどうか、怪しいものだが。
「安曇さん、いますか」
声はかけたものの、応答を待たずに早坂は四号館の一室に足を踏み入れた。いようがいまいが、安曇が返事を返してきたことなんてないからだ。
一度は空になった本棚は、安曇が持ち込んだ本が乱雑に詰め込まれて再び満杯になっている。そんなスチール製の密林の奥に、見慣れたぼさぼさ頭がちらりと見えた。思った通り、今日も今日とて文字通り本に埋もれていたらしい。閲覧スペースの椅子に腰掛けて頬杖をついていた安曇は、早坂に気づいて顔をあげた。
「やあ早坂くん、久しぶり。元気……ではなさそうだね。まるで死人のような顔をしている」
「いきなりずいぶんな挨拶ですね」
ムッと言い返して早坂はその向かいの席に腰を下ろした。そこが早坂の定位置である。
安曇は読みかけの本を手に持ったままで、目を眇めて早坂の顔を見つめる。ちらりと見えた本のタイトルは、スティーブン・キングの『シャイニング』だった。先月までは筒井康隆を片っ端から読み漁っていたように記憶しているが、もう全て読み終えてしまったのだろうか。
「よくそんな怖い話とか気持ち悪い話ばっかり好き好んで読みますよね」
呆れつつ発した早坂の言葉を安曇は鼻で笑って、
「酔狂は君も同じだろう?わざわざ肝試しなんてものに参加して、案の定"もらってきて"しまったのではないかい」
見透かすような口調で、そう言った。
いつもなら、からかわないでくれと怒るところだが、今は黙って目を逸らすことしかできない。認めたくはないが、早坂にとって思い当たることが多すぎた。
「やれやれ……無茶と無謀は若人の特権だが、今回は少々軽率に過ぎたようだね。いったいどうするつもりだい?」
「どうするって……」
握っていた手に、知らず力がこもった。どうにかできるものならとっくにやっている。原因も解決策も、何も分からない。ここでこうしているのだって、問題を先送りしているだけ。要するにただの現実逃避だ。
黙り込む早坂を前に、安曇も何も言わない。馬鹿にするでもなく、嘲るでもなく、黙ってこちらを見つめている。
その視線に居心地の悪さを感じて、わずかに顔を伏せた。安っぽい造りの机の下に、履き古したスニーカーと白い手が見える。
…………手?
高校時代から愛用している、履き慣れた黒いスニーカー。その爪先に縋るように、ボロボロにひび割れた指が張り付いている。血の気の失せたそれは、まるで巨大な白い蜘蛛のようで……
「うわあああああああっ」
脳がそれを認識するより前に、体が反応していた。弾かれるように椅子から飛び退いて、机の下から足を引き抜く。弾き飛ばされたパイプ椅子が、床に叩きつけられてけたたましい音を立てた。
「早坂くん?」
さしもの安曇もぎょっとした顔でこちらを見ている。だが早坂の方にそれを気にする余裕はない。
慌てて足を引いたおかげで、手はスニーカーから離れたようだった。だが、手首までしか見えていなかったはずのそれは、気づけば肘までが顕になり、異常なまでに長い腕が、まるで蛇のように身をくねらせて、机の下から這い出そうとしている。
それ以上はもう、耐えられなかった。
脇目もふらずに部屋を飛び出す。四号館の近くを通りかかった学生達は、必死の形相で走り出てきた早坂をなんだと思っただろう。いや、それよりも安曇は?
想像していた最悪の事態になってしまったと、そう気がついたのは、どうにか自宅に帰りついてからのことだった。
「最悪だ……」
畳の上に力なく崩れ落ちる。
何もない場所を見て悲鳴をあげて逃げ出すなんて、逆の立場なら気が触れたとしか思えない。次からどんな顔をして安曇に会えばいいのだろう。
この先のことを思うだけで目眩がする。深くため息を吐き出した直後、突如部屋の中に響き渡ったインターホンの音に文字通り飛び上がった。
「奏太!奏太いる?」
続いて聞こえた親友の声に慌てて立ち上がる。
「優也?」
なぜこのタイミングで。一瞬躊躇ったが、扉の前から優也が立ち去る気配がないのでやむなくドアノブに手をかけた。
「あ、いたいた。よかった、帰ってたんだな」
アパートの外廊下には、タンクトップに高校時代のジャージという、明らかに部屋着と思われる格好に身を包んだ優也が立っていた。
「なんだよ、突然どうした?」
早坂が訊くと、優也は無言でスマホの画面を見せてきた。そこに表示されていたのは、何の変哲もないLINEのトーク画面のようだったが、よく見ると、驚いたことにトーク相手の名前が「安曇先輩」になっている。いつの間に安曇とLINE交換なんてしていたのだろう。そもそも早坂は安曇がLINEをやっていたことを今知った。一年以上同じサークルで過ごしてきたというのに。
いや、そんなことよりも。
「……安曇さんに聞いたのか」
優也は黙ったままで頷いた。苦い思いが広がる。あんなに隠したいと思っていたのに、結局優也にまで知られてしまった。
「あのさ。もしかして奏太、なんか変なもの見えてる?」
率直な優也の問いに、答えることができない。これはどちらの意味で聞かれているのだろう。幻覚を見ていると思われているのか、それともいつもの霊的な話か。
黙り込む早坂を、優也は困った顔で見上げてくる。
「それってさ……やっぱ、あの肝試しのせいだったりする?」
その一言で、優也がここに来た理由に察しがついた。
「……そんなこと分からないし、そうだとしても、俺が自分から行くって言ったんだよ」
だから優也が気に病む必要はない。言外に、そういう意図を込めたつもりだった。
けれど優也の表情は晴れない。
「……あのさ。奏太はこういうの嫌かもしんないけど、一回この人に相談してみないか?おれの好奇心とか都合とか置いといて、ホントにこれしか思いつかないからさ」
そういって、優也は財布の中から小さなカードを取り出した。
「名刺?」
優也に渡されたその名刺は、名前と住所だけが書かれたシンプルなものだった。白地に黒い明朝体で書かれた名前は、“井ノ原圭”。
「もしかして、この人……」
「そう。その人が、前に話した霊媒師だよ」
もう一度、素っ気ないデザインの名刺に目を落とす。優也の言う通り、普段の早坂ならこんな誘いは受けないだろう。けれど、今は藁にもすがりたい心境だった。
なにしろ今も優也の背後で、アパートの上階からぶら下がる逆さまの女が、こちらを見つめているのだから。
*
そうして優也に案内されて訪れたのは、大学がある表通りからは少し離れた裏通りだった。
近代的なオフィスの隣に古びた商店がある、そんな時間の狭間のような奇妙な通りに、それはあった。
「ほら、ここだよ」
一度帰宅して、普段着に着替え直した優也が指したのは、通りの中でも一層古い門扉を構える小さな寺……ではなく、その隣にある薄汚れたコンクリートの建物だった。
二階建てのその建物は、一階に仏具店が入っていて、その脇の狭い階段には黒い紙に白い文字で『↖霊障相談』とだけ書かれた、やる気のない貼り紙がされている。なるほど、たしかに目的地はここで間違いないようだが。
もともとこの辺りは寺社の多い土地柄なので、このような抹香臭い立地もさして珍しいわけではない。なのに、なぜだろう。とてつもない胡散臭さを感じるのは。
「……やっぱり、やめといた方がいいかな」
思わず漏れた本音に、優也が慌てて早坂の腕を掴んで引き止める。
「ちょ、ここまで来てそれはないだろ?!大丈夫だって、相談するだけなら金かかんないし!」
「いや、そういう問題じゃなくて……ていうか、なんでそんな詳しいんだよ」
よくよく考えてみれば、あの名刺もいつ貰ったんだ。早坂の疑問に、優也はあっけらかんとして答えた。
「前来た時に、ここの霊媒師を偶然見かけたって話したろ?そん時に、どうにか仲良くなりたくて、いろいろ話しかけてたら教えてくれた」
「お前のその異常なコミュ力、ホントなんなんだよ……」
何をどうしたら、初対面の霊媒師相手にナンパまがいのことをしようという気になるのだろう。早坂が呆れて踵を返そうとした時、不意に後ろに現れた人影にぶつかりそうになった。
「あ、すみません」
「いえ、こちらこそ……もしかして、ご依頼の方でしょうか」
依頼?その言葉に、はっとして視線を下げた。
真っ黒な影。その人物を見て、真っ先に浮かんできたのは、そんなイメージだった。束ねた長い黒髪に、同じく真っ黒なスーツ、そして真っ黒なハイヒール。全身を黒に包まれたその人は、まっすぐに早坂を見上げていた。
「あっ、井ノ原さん!」
優也が嬉しそうに声をあげる。ということは、やっぱりこの人物が噂の霊媒師か。
見たところ、年齢はおそらく二十代半ば。ヒールの分を抜きにしても、おそらく優也より背が高い。なるほど、この容姿なら優也が騒ぐのも頷ける。
花耶が日本人形なら、井ノ原はさしずめ西洋のビスクドールのように整った顔立ちをしていた。大きな猫目に、鋭い彫刻刀で削り出したように完璧なラインの鼻筋。おまけに身にまとった服とはどこまでも対照的に白い肌。優也が言っていた「すげー美人」は決して大げさな表現ではなかった。
「私の顔になにか?」
「あ、いえ……」
井ノ原に訝しげな視線を向けられ、慌てて目を逸らす。初めて会う人に対して不躾な態度だったかもしれない。
「井ノ原さん、お久しぶりです!おれのこと覚えてますか!」
早坂の後ろから顔を出した優也が食い気味に尋ねる。井ノ原は、そんな優也に視線を移したのち、にっこりと笑って言った。
「もちろんです。樋山さん、でしたよね」
井ノ原に名を呼ばれた途端、優也がパッと目を輝かせた。彼が犬なら千切れんばかりに尻尾を振っていることだろう。
「あの!今日はおれの友達のことで相談があって」
そういって、優也が早坂の腕を再びがっしりと掴む。
逃げるタイミングを完全に失ったと気がついたのは、そのまま井ノ原の事務所に案内されてからのことだった。
*
「どうそ、そちらにお掛けください」
井ノ原に勧められるまま、革張りのソファに腰掛ける。
井ノ原の事務所は綺麗に整頓されていて、外観から感じた胡散臭さとは無縁の、ごく一般的なオフィスだった。ブラインドが降りた窓の手前には事務机とノートパソコンが置かれていて、左右の棚には色分けされたバインダーが整然と並んでいる。井ノ原は几帳面な性格のようだ。
デスク前の応接スペースから室内を見回していると、井ノ原が三人分のコーヒーを持って戻ってきた。それぞれの前にカップを置いて、井ノ原も二人の向かいに腰をおろす。
「さて、それではお話を伺いましょうか。そちらのご友人……早坂さん、でしたね」
そういって、井ノ原は早坂に視線を向けた。正面から見据えられて、思わず口ごもってしまいそうになるが、ここまで来て黙っていても仕方ない。目の前の人物を信頼してもいいのかどうか。それだって、話してみなければ分からないのだから。
「……先週、ここにいる優也と他の友人達の四人で、近くの心霊スポットに行ったんです。その日から、おかしなものが見えるようになって」
「おかしなもの、とは?」
一瞬、隣の優也を横目で見やる。知られたくないと思ってしまうのも、今さらだ。
「最初は、影とか靄みたいなものだったんです。それが段々、人の形になって、それで……」
思い出しただけで、全身に鳥肌が立つ。幸いアパートからここに来るまでは、変わったものは見ていない。優也と話している間は忘れたふりをしていられたが、今になってまた怖くなってきた。
青ざめる早坂を見て、井ノ原はすっと目を細めて、そして驚くようなことを言った。
「あなた方が行った心霊スポットというのは、もしかして黒河トンネルですか」
「え……?」
優也が話したのかと思い、咄嗟に彼の方を振り返ったが、当の優也も目を丸くして驚いている様子だった。それはそうだろう、優也が初めてここを訪れたのは、肝試しを実行する前のはずだ。
「……なんで、分かるんですか」
警戒を顕に早坂が尋ねると、井ノ原はおかしそうに笑って答えた。
「そのくらい、よく観察すれば分かることです……と言いたいところですが、生憎私はシャーロック・ホームズではありませんので、見たままを言っただけですよ。早坂さんの中にいるんです、黒河の辺りにいたはずの、痩せぎすな若い男が」
井ノ原の言葉に、今度は別の意味で鳥肌が立った。
黒河トンネルは、この辺りの心霊スポットとしてはかなり有名だ。若者が面白半分で行きそうな場所として、適当にアタリをつけて言っただけの可能性もある。
だが、黒河トンネルに伝わる怪談話に登場する幽霊は、全て"女"のはずだ。それなのになぜ、あの夜早坂が夢で見たのと同じ、痩せぎすな若い男という単語が出てくるのか。
「中にいるって、どういうことですか」
それまで黙っていた優也が、おもむろにそう言った。これまでに見たこともないくらい、真剣な顔で井ノ原に向き合っている。
「優也……」
「それって、良くないものなんですか。奏太は……奏太はどうなるんですか」
「落ち着いてください、樋山さん」
身を乗り出して問う優也を片手で制して、井ノ原が悠然と微笑む。この人が浮かべる表情は、どれもとらえどころが無くて不気味だ。なまじ顔立ちが整っているだけに、余計そう感じるのかもしれない。
長い足をゆったりと組んで、井ノ原は先を続けた。
「霊なんてものはね、細菌やウイルスと同じです。目には見えないくともそこら中にいるし、多少体に入ってきたところで、大抵の場合は何の影響もない」
そこで一瞬言葉を切って、なぜか井ノ原は早坂に意味深な視線を投げる。
「……とはいえ、長く入り込まれれば、重篤な問題を引き起こす可能性があるのもまた同じ。率直に言いますが早坂さん。このままだと貴方……最悪死にますよ」
優也が息を呑む気配があった。しかし、早坂は井ノ原から……正確には井ノ原の背後から、目を逸らすことが出来ずにいた。
「さて。私の見立てはこんなところですが……どうしますか?ご依頼いただけるのであれば、貴方の中から、その男を追い出すことも可能ですが」
「……その前にひとつ訊きたいんですけど」
自分で思っていた以上に、掠れた声が出たのを自覚する。井ノ原が目線で応えたのを見とって、早坂は言った。
「あなたの背中にいるそれは……“何の影響もない”ものなんですか」
早坂のその言葉を聞いた瞬間、井ノ原はわずかに口角を上げて、
「ああ……貴方、これが見えるんですね」
とても愉快げに、そう言った。
井ノ原の体には、先ほどからずっと、無数の手がしがみついていた。肩に、腕に、腰に、大きさも爪の長さもバラバラで、それでいて揃って血の気の失せた手が、井ノ原のジャケットに絡みついているのだ。
「見えますよ。さっきからずっと見えてます……そいつが、あなたの中から出てきた時からずっと」
あまりにも自然な動作で、それは井ノ原の背中から生えてきたように見えた。そして、元々そういう生き物だったと言わんばかりに、当たり前の顔をしてそこにいる。
握った拳の中に汗が滲む。ひどく喉が乾いていたが、目の前のコーヒーに口をつける気にはならなかった。
怖い。今日までに見た、どんな化け物よりも。
「……井ノ原さん。あなた、本当に人間ですか」
沈黙が落ちる。
井ノ原は不意に右手で自分の顔を覆った。いくつもの手が貼りついたままの肩が震える。
井ノ原は笑っていた。心の底から楽しそうに、笑っていた。
「ふ、はは……っ、いいですねぇ早坂さん。貴方、とてもいいですよ。とても……面白い」
「……っ、ふざけないでください!」
勢いよく立ち上がった拍子に、テーブルに膝がぶつかり、コーヒーカップが硬い音を立てた。
「お、おい。奏太……」
「もういいです、あなたに相談することなんてありません。帰ります」
「そうですか?それは残念です。気が変わったら、いつでもいらしてくださいね」
「ありえませんから!」
言い捨てて事務所を飛び出す。少し遅れて、慌てた様子で優也も後を追ってきた。
「ちょっと待てって奏太!どうしたんだよ急に!」
事務所から少し離れた場所で立ち止まり、追いついてきた優也を振り返る。
「優也。悪いこと言わないから、あの人はやめとけ。上手く説明できないけど、絶対やばいから」
井ノ原の中に何かが居るのか、それとも井ノ原自身が化け物なのか。どちらにせよ、どう考えてもまともではない。
見えないからこそ、優也にはもう関わって欲しくなかった。
「奏太……」
「ごめんな、せっかく連れてきてくれたのに。けど、もう帰るわ」
そういって、優也の返事を待たずに早坂は事務所に背を向けた。結局、事態は何も解決していないし、いよいよ打つ手もなくなってしまった。
けれど、それでもあの井ノ原圭という霊媒師に頼ろうとは思えない。だってそうだろう。怪異と共存している者が、どうやって怪異を祓えるというのか。見えているのは本当なのかもしれないが、やっぱり霊媒師なんて嘘っぱちだ。
もう、誰にも頼らない。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

怪異探偵の非日常
村井 彰
ホラー
大学生の早坂奏太は、ごく普通の学生生活を送りながら、霊媒師の元でアルバイトをしている。ある日そんな彼らの事務所を尋ねてきたのは、早坂にとっては意外な人物で。……「心霊現象はレンズの向こうに」
霊媒師である井ノ原圭の元に持ち込まれたのは、何の変哲もない猫探しの依頼だった。それを一任された助手の早坂奏太は、必死に猫を探すうち奇妙な路地裏に迷い込む。……「失せ物探しは専門外」
その幽霊は、何度も何度も死に続けているのだという。
井ノ原の事務所を訪ねたのは、そんな不可解な怪異に悩まされる少女だった。……「落ちる」
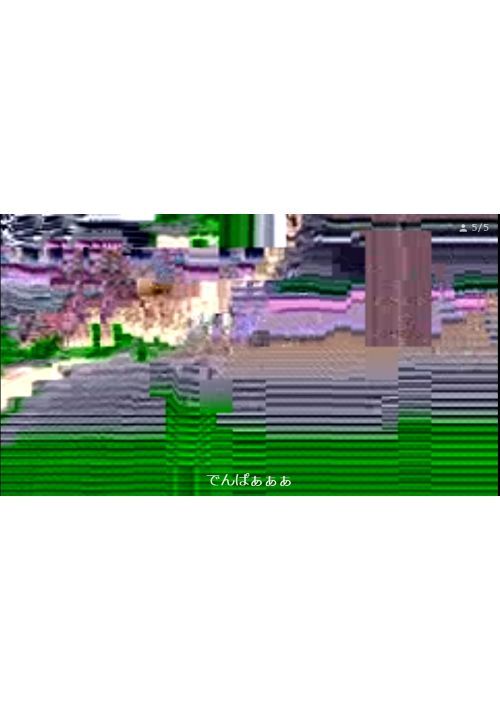


寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

煩い人
星来香文子
ホラー
陽光学園高学校は、新校舎建設中の間、夜間学校・月光学園の校舎を昼の間借りることになった。
「夜七時以降、陽光学園の生徒は校舎にいてはいけない」という校則があるのにも関わらず、ある一人の女子生徒が忘れ物を取りに行ってしまう。
彼女はそこで、肌も髪も真っ白で、美しい人を見た。
それから彼女は何度も狂ったように夜の学校に出入りするようになり、いつの間にか姿を消したという。
彼女の親友だった美波は、真相を探るため一人、夜間学校に潜入するのだが……
(全7話)
※タイトルは「わずらいびと」と読みます
※カクヨムでも掲載しています

葬鐘
猫町氷柱
ホラー
とある心霊番組の心霊スポット巡り企画で訪れることになったとある廃墟。
中に入るなり起こる耳鳴り、おかしくなるスタッフ、腐臭。襲いかかる怪異。明らかにまずい状況に退散を命じるAD美空だが消息不明となってしまう。
行方不明になった姉を探しに一人訪れた美海。だが、その時、館内に鐘の音が鳴り響き絶望の歯車が回りだす。襲い掛かる脅威、戦慄の廃墟に姉を見つけ出し無事出られるのか。

初めてお越しの方へ
山村京二
ホラー
全ては、中学生の春休みに始まった。
祖父母宅を訪れた主人公が、和室の押し入れで見つけた奇妙な日記。祖父から聞かされた驚愕の話。そのすべてが主人公の人生を大きく変えることとなる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















