3 / 3
3
しおりを挟む
国語で習った。
代名詞というもの。
アレ、とか、ソレ、とか。名前を使わないで、物を呼ぶときに使うことばだ。
ふだんの生活の中で、そういうことばはいくらでも使う。
ふつうの会話の中で、ありふれているのだ。
「さっきさー、アレとぶつかっちゃってさ。マジでさいあくー」
とある女子が、そんなことを言っている。
わたしは教室の前の方の席だから、その女子のことは見えない。でもきっと、わたしの方をじっとにらみながら言っているんだと思う。
「うわ、さいあくじゃん。におい、うつってんじゃないの」
「ちょ、やめてよ」
「んー、どれどれ……。あはっ、くさいよ!」
「はあ? まじでさいあくなんだけど!」
そんなことを言って、笑っている。
うしろは見えなくても、声で、だれが言っているのかは分かる。
ナニかとぶつかった、といやそうに言っていたのは、いつもクラスの中心にいる明るい女の子。わたしはさっき、その子とすれちがうとき、少しだけ肩がぶつかってしまった。
だから、代名詞をつかわれていても、それがわたしのことだと分かる。
ううん、べつに、たしかにさっきぶつかったのはわたしだから……なんて考える必要もない。
このクラスの中で、アレ、とか、ソレ、とか言って笑っているときは、たいてい、わたしのことを言っているんだ。
いつの日からか、そうなっていた。
それまでも、わたしのことをコソコソと……いや、べつに隠そうとすることもなく、わたしに聞こえるような大きい声ででも、わたしを悪く言って笑うようなことは毎日のようにあった。
そのたびに胸のところがヒヤっとして、消えたくなる気持ちになっていた。
そうやってわたしを悪く言うとき、はっきり名前で呼ぶか、そうじゃないときは何かいやなあだ名をつけて言うのがふつうだった。
でも、今はちがう。
わたしの名前は呼ばれない。
わたしは、アレ。
わたしは、ソレ。
わたしのことを笑っているのはたしかだから、やっぱり心がいたむのはまちがいないんだけど……でも、前までよりも、それは軽いような気もする。
アレとかソレとか言われていると、なんだか他人ごとみたい。
みんなが、わたしのことを笑う。
そのたびに、どろどろして重たい気持ちが胸の中にわくけど、名前で呼ばれないから他人ごとのような気がして、その気持ちから目をそむけられた。
でも、だからって暗い気持ちはきえない。
それどころか、ずっと目をそむけ続けているものだから、いっそう大きくなって、たまっていく。
胸が、重い。
体が重い。
朝なんか、とっても体が重たくて、起き上がるのがたいへんだ。
通学路を歩く、その一歩一歩が、とてもつらい。足をふみ出すたびに、ぎしぎし、って、ほねがきしんでいるみたい。
このままポキって折れちゃうんじゃないかって思う。
正直、そうなってくれた方がいいかもしれない。骨折したら学校を休めるし。……。
毎日、ずっと、みんながわたしのことを笑う。
でも、アレとかソレとか、わたしをモノのように言うのだ。
心がとても重たくて、胸の中からどろりと落ちてしまいそう。もし黒くてどろどろしたモノが道ばたに落ちていたら、それ、たぶんわたしのだ。
家に帰って、また、ベッドにぼふんと体をしずめる。
顔を深くうずめていて、息が出来なくなっていることに、気づかなかった。顔をよこに向けたときに、すうっと空気が入ってきて、今、息をしていなかったと気づいたのだ。
けっこう長く、息をしていなかったはずなのに、でも苦しいとは感じなかった。
また、卓上ミラーが立ったままだ。
鏡と、目が合う。
その向こうにいる人と、目が合う。
ソレが、こちらを見ている。
…………。
アレはだれだろう。
鏡の向こうから、じっとこちらを見る、アレ。
黒くどんよりとして、にごった瞳。その目がまっすぐわたしを見ているけど、でも、べつにいやな気分にはならない。
まさに死人の目が、私のことを見ている。
ただそれだけのことで、何も特別な感慨は湧かない。
ソレは、そのまま体を動かすこともなく、ベッドに体を埋めた状態で数時間を過ごしていた。棺に納められた死人みたいだ、と、私は思った。
「さっきの授業、笑ったよねー」
「ああ、アレね。また宿題忘れてきてせんせーに怒られてたね」
「バカだよねー、アレ。あははっ」
教室の後方で集まった女子が、愉しそうに笑う。
彼女らが指すのは、前列の席でじっと坐り、独り虚しく次の授業を待つアレだ。
ソレは、自分のことを言われているのだと察して、びくりと肩を震わせた。その様子を見て、明るい女子たちは吹き出す。
笑い声ははっきりと聞こえるが、前に座るソレには、女子たちが愉しげに笑う様は見えない。
ただ、細い針で背中をちくちくと刺すような声と視線を感じ、畏縮するばかり。女子らにはその背中が滑稽に見えるのだ。
――確かに、ソレは、滑稽だ。
私にもそう思えた。
一日が終えられ、ソレは、重い足取りで帰路に就く。
踏み出す度に足の骨がぎしりと軋むのを感じながら、ソレは家路を歩む。
「にゃあ」
道中、猫の鳴き声が不意に聞こえ、ソレははっとして辺りを見回した。
だが、すでに猫はそばの茂みに潜り、立ち並ぶ家の塀と塀の細い隙間へと入り込んで行っていた。その姿を目にできなかったのを残念がり、ソレは、溜め息とともに顔を伏せた。
私はその小さな背中を追って見ていたが、やはり愛くるしい。
実に気ままで、人間のことをなど歯牙にもかけないというような堂々とした振る舞い。私は猫が好きだ。
暗鬱とした日々を、ソレは過ごす。
長い時が経ったのか。
短いのか。
どちらだろう。私にはわからない。
その日は、曇天。
鈍色の分厚い雲が太陽を遮り、地上に暗い影を落とす。
カーン、カーン、カーン、カーン。
赤いランプの明滅。支柱は黄色と黒。ゆっくりと、バーが降りる。
死人が一人。
水平に降りきったバーの下を、ひょいと、潜り抜ける。
カーン、カーン、カーン、カーン。
けたたましく響くのは、鐘の音を再現した電子音。
無機質なその音は、まるで死を運ぶ音みたいだと、私はかねてより感じていた。
だからソレは、今、ここにいる。
屈み込み、足を抱く。自身への抱擁ではない。逃がさぬ、と、抱き留めているのだ。
表情はない。死んでいるから。
甲高いブレーキ音。
だが幸い、接触が免れることはなかった。
小さな体は、突き飛ばされるのではなく、車体の底部に巻き込まれた。
レールと車輪に挟まれ、転がされる。
たちどころに、体の各部が引き伸ばされて、ちぎれる。ちぎれてなお、すり潰れてミンチになっていく。
艶のない髪は車輪に絡まり、頭皮ごともっていかれた。
頭は何回転もしながらレールや車体の鋭い角にぶつかり、へこみ、擦り切れ、細かなく頭蓋骨は砂利に混ざる。
あるいは体各部の骨片も同様に砂利に混ざるほか、車体の隙間に入り込んでしまって、それは果たして回収されるのか。
一面の赤。
ソレは見るも無残な光景だ。気分が悪くて、私は、目を背けた。
代名詞というもの。
アレ、とか、ソレ、とか。名前を使わないで、物を呼ぶときに使うことばだ。
ふだんの生活の中で、そういうことばはいくらでも使う。
ふつうの会話の中で、ありふれているのだ。
「さっきさー、アレとぶつかっちゃってさ。マジでさいあくー」
とある女子が、そんなことを言っている。
わたしは教室の前の方の席だから、その女子のことは見えない。でもきっと、わたしの方をじっとにらみながら言っているんだと思う。
「うわ、さいあくじゃん。におい、うつってんじゃないの」
「ちょ、やめてよ」
「んー、どれどれ……。あはっ、くさいよ!」
「はあ? まじでさいあくなんだけど!」
そんなことを言って、笑っている。
うしろは見えなくても、声で、だれが言っているのかは分かる。
ナニかとぶつかった、といやそうに言っていたのは、いつもクラスの中心にいる明るい女の子。わたしはさっき、その子とすれちがうとき、少しだけ肩がぶつかってしまった。
だから、代名詞をつかわれていても、それがわたしのことだと分かる。
ううん、べつに、たしかにさっきぶつかったのはわたしだから……なんて考える必要もない。
このクラスの中で、アレ、とか、ソレ、とか言って笑っているときは、たいてい、わたしのことを言っているんだ。
いつの日からか、そうなっていた。
それまでも、わたしのことをコソコソと……いや、べつに隠そうとすることもなく、わたしに聞こえるような大きい声ででも、わたしを悪く言って笑うようなことは毎日のようにあった。
そのたびに胸のところがヒヤっとして、消えたくなる気持ちになっていた。
そうやってわたしを悪く言うとき、はっきり名前で呼ぶか、そうじゃないときは何かいやなあだ名をつけて言うのがふつうだった。
でも、今はちがう。
わたしの名前は呼ばれない。
わたしは、アレ。
わたしは、ソレ。
わたしのことを笑っているのはたしかだから、やっぱり心がいたむのはまちがいないんだけど……でも、前までよりも、それは軽いような気もする。
アレとかソレとか言われていると、なんだか他人ごとみたい。
みんなが、わたしのことを笑う。
そのたびに、どろどろして重たい気持ちが胸の中にわくけど、名前で呼ばれないから他人ごとのような気がして、その気持ちから目をそむけられた。
でも、だからって暗い気持ちはきえない。
それどころか、ずっと目をそむけ続けているものだから、いっそう大きくなって、たまっていく。
胸が、重い。
体が重い。
朝なんか、とっても体が重たくて、起き上がるのがたいへんだ。
通学路を歩く、その一歩一歩が、とてもつらい。足をふみ出すたびに、ぎしぎし、って、ほねがきしんでいるみたい。
このままポキって折れちゃうんじゃないかって思う。
正直、そうなってくれた方がいいかもしれない。骨折したら学校を休めるし。……。
毎日、ずっと、みんながわたしのことを笑う。
でも、アレとかソレとか、わたしをモノのように言うのだ。
心がとても重たくて、胸の中からどろりと落ちてしまいそう。もし黒くてどろどろしたモノが道ばたに落ちていたら、それ、たぶんわたしのだ。
家に帰って、また、ベッドにぼふんと体をしずめる。
顔を深くうずめていて、息が出来なくなっていることに、気づかなかった。顔をよこに向けたときに、すうっと空気が入ってきて、今、息をしていなかったと気づいたのだ。
けっこう長く、息をしていなかったはずなのに、でも苦しいとは感じなかった。
また、卓上ミラーが立ったままだ。
鏡と、目が合う。
その向こうにいる人と、目が合う。
ソレが、こちらを見ている。
…………。
アレはだれだろう。
鏡の向こうから、じっとこちらを見る、アレ。
黒くどんよりとして、にごった瞳。その目がまっすぐわたしを見ているけど、でも、べつにいやな気分にはならない。
まさに死人の目が、私のことを見ている。
ただそれだけのことで、何も特別な感慨は湧かない。
ソレは、そのまま体を動かすこともなく、ベッドに体を埋めた状態で数時間を過ごしていた。棺に納められた死人みたいだ、と、私は思った。
「さっきの授業、笑ったよねー」
「ああ、アレね。また宿題忘れてきてせんせーに怒られてたね」
「バカだよねー、アレ。あははっ」
教室の後方で集まった女子が、愉しそうに笑う。
彼女らが指すのは、前列の席でじっと坐り、独り虚しく次の授業を待つアレだ。
ソレは、自分のことを言われているのだと察して、びくりと肩を震わせた。その様子を見て、明るい女子たちは吹き出す。
笑い声ははっきりと聞こえるが、前に座るソレには、女子たちが愉しげに笑う様は見えない。
ただ、細い針で背中をちくちくと刺すような声と視線を感じ、畏縮するばかり。女子らにはその背中が滑稽に見えるのだ。
――確かに、ソレは、滑稽だ。
私にもそう思えた。
一日が終えられ、ソレは、重い足取りで帰路に就く。
踏み出す度に足の骨がぎしりと軋むのを感じながら、ソレは家路を歩む。
「にゃあ」
道中、猫の鳴き声が不意に聞こえ、ソレははっとして辺りを見回した。
だが、すでに猫はそばの茂みに潜り、立ち並ぶ家の塀と塀の細い隙間へと入り込んで行っていた。その姿を目にできなかったのを残念がり、ソレは、溜め息とともに顔を伏せた。
私はその小さな背中を追って見ていたが、やはり愛くるしい。
実に気ままで、人間のことをなど歯牙にもかけないというような堂々とした振る舞い。私は猫が好きだ。
暗鬱とした日々を、ソレは過ごす。
長い時が経ったのか。
短いのか。
どちらだろう。私にはわからない。
その日は、曇天。
鈍色の分厚い雲が太陽を遮り、地上に暗い影を落とす。
カーン、カーン、カーン、カーン。
赤いランプの明滅。支柱は黄色と黒。ゆっくりと、バーが降りる。
死人が一人。
水平に降りきったバーの下を、ひょいと、潜り抜ける。
カーン、カーン、カーン、カーン。
けたたましく響くのは、鐘の音を再現した電子音。
無機質なその音は、まるで死を運ぶ音みたいだと、私はかねてより感じていた。
だからソレは、今、ここにいる。
屈み込み、足を抱く。自身への抱擁ではない。逃がさぬ、と、抱き留めているのだ。
表情はない。死んでいるから。
甲高いブレーキ音。
だが幸い、接触が免れることはなかった。
小さな体は、突き飛ばされるのではなく、車体の底部に巻き込まれた。
レールと車輪に挟まれ、転がされる。
たちどころに、体の各部が引き伸ばされて、ちぎれる。ちぎれてなお、すり潰れてミンチになっていく。
艶のない髪は車輪に絡まり、頭皮ごともっていかれた。
頭は何回転もしながらレールや車体の鋭い角にぶつかり、へこみ、擦り切れ、細かなく頭蓋骨は砂利に混ざる。
あるいは体各部の骨片も同様に砂利に混ざるほか、車体の隙間に入り込んでしまって、それは果たして回収されるのか。
一面の赤。
ソレは見るも無残な光景だ。気分が悪くて、私は、目を背けた。
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説
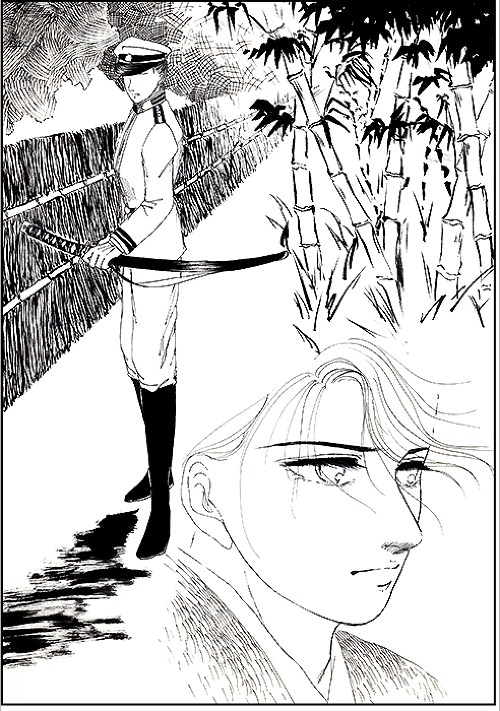
あやかしのうた
akikawa
ホラー
あやかしと人間の孤独な愛の少し不思議な物語を描いた短編集(2編)。
第1部 虚妄の家
「冷たい水底であなたの名を呼んでいた。会いたくて、哀しくて・・・」
第2部 神婚
「一族の総領以外、この儀式を誰も覗き見てはならぬ。」
好奇心おう盛な幼き弟は、その晩こっそりと神の部屋に忍び込み、美しき兄と神との秘密の儀式を覗き見たーーー。
虚空に揺れし君の袖。
汝、何故に泣く?
夢さがなく我愁うれう。
夢通わせた君憎し。
想いとどめし乙女が心の露(なみだ)。
哀しき愛の唄。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

風の音
月(ユエ)/久瀬まりか
ホラー
赤ん坊の頃に母と死に別れたレイラ。トマスとシモーヌ夫婦に引き取られたが、使用人としてこき使われている。
唯一の心の支えは母の形見のペンダントだ。ところがそのペンダントが行方不明の王女の証だとわかり、トマスとシモーヌはレイラと同い年の娘ミラを王女にするため、レイラのペンダントを取り上げてしまう。
血などの描写があります。苦手な方はご注意下さい。

ねえ知ってる?この噂を聞くとね、
下菊みこと
ホラー
ある夏の日のこと。
なっちゃんは、伝染系の怖い噂を耳にした。
なっちゃんは一人でお留守番の時に、ドアのチャイムを鳴らされる。
なっちゃんは無事にやり過ごせるだろうか。
小説家になろう様でも投稿しています。

僕と幼馴染と死神と――この世に未練を残す者、そして救われない者。
されど電波おやぢは妄想を騙る
ホラー
学校の帰り道に巻き込まれた悲惨な事故。
幼馴染の死を目の当たりにした僕は、自責の念と後悔の念に埋もれていた――。
だがしかし。
そこに現れる奇妙な存在――死神。
交換条件を持ち掛けられた僕は、それを了承するか思案し、結局は承諾することになる。
そして真っ赤な色以外を失い、閉ざされた僕の世界に新たな色を描き、物語を紡いでいくこととなった――。

何カガ、居ル――。
されど電波おやぢは妄想を騙る
ホラー
物書きの俺が執筆に集中できるよう、静かな環境に身を置きたくて引っ越した先は、眉唾な曰くつきのボロアパート――世間一般で言うところの『事故物件』ってやつだった。
元から居た住人らは立地条件が良いにも関わらず、気味悪がって全員引っ越してしまっていた。
そう言った経緯で今現在は、俺しか住んでいない――筈なんだが。
“ 何かが、居る―― ”
だがしかし、果たして――。“ 何か ”とは……。

少年少女怪奇譚 〜一位ノ毒~
しょこらあいす
ホラー
これは、「無能でも役に立ちますよ。多分」のヒロインであるジュア・ライフィンが書いたホラー物語集。
ゾッとする本格的な話から物悲しい話まで、様々なものが詰まっています。
――もしかすると、霊があなたに取り憑くかもしれませんよ。
お読みになる際はお気をつけて。
※無能役の本編とは何の関係もありません。

雪鉄
鳥丸唯史(とりまるただし)
ホラー
職場と家族問題で悩んでいる「私」。彼は子どものためにかまくらを作る。すると真夜中に謎の老人が現れて、切符を残して消えた。職場でトラブルに巻き込まれた「私」は帰りにその切符を使って「雪国電鉄」に乗ってしまう。全7話。
※小説家になろうに修正前があります。変化は微々。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















