お気に入りに追加
148
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る


食事届いたけど配達員のほうを食べました
ベータヴィレッジ 現実沈殿村落
BL
なぜ自転車に乗る人はピチピチのエロい服を着ているのか?
そう思っていたところに、食事を届けにきたデリバリー配達員の男子大学生がピチピチのサイクルウェアを着ていた。イケメンな上に筋肉質でエロかったので、追加料金を払って、メシではなく彼を食べることにした。


壁穴奴隷No.19 麻袋の男
猫丸
BL
壁穴奴隷シリーズ・第二弾、壁穴奴隷No.19の男の話。
麻袋で顔を隠して働いていた壁穴奴隷19番、レオが誘拐されてしまった。彼の正体は、実は新王国の第二王子。変態的な性癖を持つ王子を連れ去った犯人の目的は?
シンプルにドS(攻)✕ドM(受※ちょっとビッチ気味)の組合せ。
前編・後編+後日談の全3話
SM系で鞭多めです。ハッピーエンド。
※壁穴奴隷シリーズのNo.18で使えなかった特殊性癖を含む内容です。地雷のある方はキーワードを確認してからお読みください。
※No.18の話と世界観(設定)は一緒で、一部にNo.18の登場人物がでてきますが、No.19からお読みいただいても問題ありません。
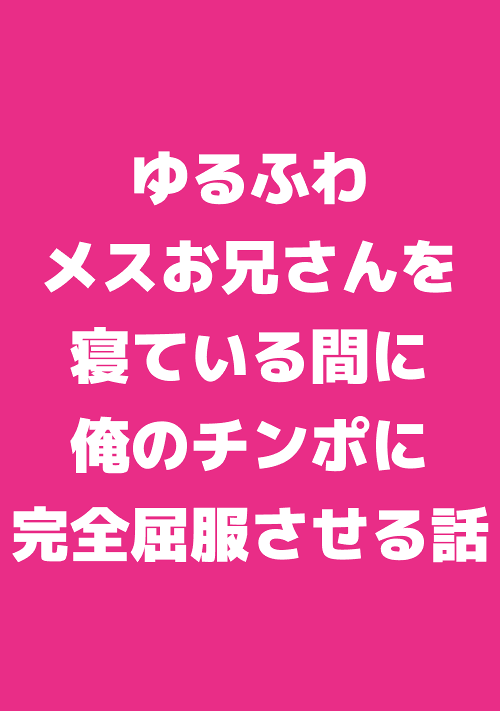
ゆるふわメスお兄さんを寝ている間に俺のチンポに完全屈服させる話
さくた
BL
攻め:浩介(こうすけ)
奏音とは大学の先輩後輩関係
受け:奏音(かなと)
同性と付き合うのは浩介が初めて
いつも以上に孕むだのなんだの言いまくってるし攻めのセリフにも♡がつく

ある宅配便のお兄さんの話
てんつぶ
BL
宅配便のお兄さん(モブ)×淫乱平凡DKのNTR。
ひたすらえっちなことだけしているお話です。
諸々タグ御確認の上、お好きな方どうぞ~。
※こちらを原作としたシチュエーション&BLドラマボイスを公開しています。

淫らに壊れる颯太の日常~オフィス調教の性的刺激は蜜の味~
あいだ啓壱(渡辺河童)
BL
~癖になる刺激~の一部として掲載しておりましたが、癖になる刺激の純(痴漢)を今後連載していこうと思うので、別枠として掲載しました。
※R-18作品です。
モブ攻め/快楽堕ち/乳首責め/陰嚢責め/陰茎責め/アナル責め/言葉責め/鈴口責め/3P、等の表現がございます。ご注意ください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















