26 / 26
【ゾンビの章】第11幕「驚愕の真相」
【ゾンビの章】第11幕「驚愕の真相」
しおりを挟む
【再び2月1日 町田】
頭がひどく混乱していた。
幾つもの事実が一本の線でつながりそうなのだが、うまく整理できない。
樹海に首と腕を埋めに行ったあの日以来、酒は断っていたが、飲まずにはいられない気分になった。ふみえが冷蔵庫に入れたままのビールでもよかったが、今はもっと強い酒が欲しい・・・。
そうだ。
達仁の部屋にウィスキーのボトルが残っていたはずだ。
亡くなった義父にはすまないが、あれを飲ませてもらおう。
家にある強い酒は、あのウィスキーだけだ。
夕刊を抱えたまま二階へと上がった。部屋の棚に置かれた未開封のマッカランの瓶とグラスを手に取る。義父の和机に座り、もどかしく封を引きちぎって、コルクのキャップをあけた。バカラのグラスに琥珀色の液体を注ぐ。マッカラン独特のシェリーの香りが鼻腔を甘くくすぐった。
一気に喉に流し込んだ。久しぶりの強いアルコールが食道を焼き、胃を焦がす。立て続けに2杯あおり、叩きつけるようにグラスを机の上に置いた。その衝撃で、机に飾ってあった写真立てのひとつが、パタンと音をたてて倒れた。
裏返しになった写真立てを元の位置に直すと、ふみえが高校に入学した時の写真だった。初々しいセーラー服姿のふみえが、満開の桜の下で笑っていた。
その時、ふと思った。
なぜ達仁は、この写真をいつも机の上に飾っておいたのだろう。
飾ってあったのは、この写真と、ふみえが生まれた時の写真だけだ。
つきあい始めた頃、確か、ふみえはこう言っていた。
自分が生まれてから毎年、桜が満開の季節になると父親が記念写真を撮ってくれた、と。
その習慣は二十歳(はたち)になるまで続いた、と。
なのに、なぜ、この2枚だけなのだ?
0歳から二十歳までは「21枚」の写真があるはずだ。なのに、達仁は何故この2枚だけを選んで飾っていたのだろう・・・・。
不意に、ある考えがひらめき、脳が震えた。
私は義父の部屋を飛び出し、階段を駆け下りた。
確かめたいことがあった。向かったのは、一階の和室だ。
和箪笥の一番下の開き戸を開ける。家族のアルバムがしまってある場所だ。
全部を外に引っ張り出し、目的のものを捜した。見るのは初めてだったが、それだとすぐにわかった。ひときわ立派なアルバムだったし、表紙に桜の花の刺繍がほどこされていたからだ。
最初のページに貼られていたのは、達仁の机にあったのと同じ1枚だった。
生まれたばかりのふみえが、母親に抱かれて写っている。
ページをめくる。1歳になった時は白いおくるみに包まれて、やはり母親に抱かれていた。2歳の時には花柄のワンピースを着て、3歳になると七五三の晴れ着姿で桜の下にひとりで立っていた。母親はふみえが1歳の時に亡くなっているからだ。
赤いランドセルを背負っているのは、小学校入学の年だ。それが中学のセーラー服に変わり、中2ではテニスウエア、卒業の年には桜の花びらが舞い散る中で卒業証書を広げて笑っていた。
そして、あの写真だ。
16歳。高校入学。真新しいセーラー服に身を包んだふみえは、満開の桜に負けないほど生気に満ち、弾けるような美しさだった。私は次のページをめくった。
そして、我が目を疑った。
そんなことが・・・。
次のページに、写真はなかった。
さらに次のページにも。
その次のページにも。
あとは白紙のページが続くだけだった。
どういうことだ・・・・。
ふみえの話では、達仁が1年に1枚ずつ撮影してくれたという「満開の桜の下の成長記録」は、二十歳になるまで続いたはずだ。写真は全部で21枚あるはずだった。
それなのに、記念写真は17枚しかない。
16歳で終わっているのだ。
なぜ、ふみえは21枚あるなどと嘘をついたのだ?
それよりも、桜の下での記念写真を「カメラマンとして自分ができる唯一のプレゼント」と言っていたという達仁が撮影を止めてしまったのは何故だ?
生まれた時の写真と16歳の時の写真だけを机の上に飾っていたのも妙だ。
誕生の年の写真はわかる。だが、もう一枚が高校に入学した時のものというのはわからない。
おそらく、ふみえが16歳の時、「よほどの何か」があったのだ。
達仁があれほど大切に思っていた記念写真を撮るのをやめてしまうほどの何かが・・。
ふみえが16歳の時のことを知る人物を捜すことだ。
まず、浮かんだのは達仁の妹、咲恵だ。部屋の子機を使って、自宅に電話をかけた。
しかし、留守番電話だった。保険会社の慰安旅行で、二泊三日の箱根旅行に出かけているという応答メッセージが流れた。出しゃばりなくせに肝心の時に役に立たない女だ。
電話を切って、考え込んでしまった。
達仁の両親はすでに亡くなっていたので、ふみえの親戚はもう咲恵しかいなかった。他にふみえの16歳の頃を知る人間に心当たりがない。
しばらく思い悩んでいると、ある事を思い出した。
達仁の部屋で「黒い手」を見つけた時に、ふみえが言っていた一言だ。
高校1年の時に足を骨折して入院した、とふみえは言っていた。たしか入院先は・・・、そう、北沢大学付属病院だ。
手術を担当した医者がグレゴリー・ペックそっくりの二枚目だった、とも言っていた。
だが、名前が思い出せなかった。
必死で、あの時の会話を思い出そうとした。
あの時、私はこう言ったはずだ。「歌舞伎の女形みたいにナヨナヨした奴だったんじゃないのか」。
そして、秀明がちゃちゃを入れたのだ。アンパンマン顔のタレントの名をあげて。
坂東玉三郎に、板東英二・・・。
そうだ。
主治医の名字を、はっきり思い出した。
「バンドウ」だ。
間違いない。
北沢大付属病院の代表番号は電話帳で調べて、すぐにわかった。私はわらをもすがる思いで、プッシュホンを押した。
電話口に出たのは病院の総合案内の女性だった。
「あの・・、そちらに、バンドウ先生というお医者様はいらっしゃいますか。字はわからないんですが」
相手は事務的な口調で言った。
「ちょっとお待ちください」
1分ほど待たされて、再び相手が出た。
「阪東敏昭先生のことですか。この病院には、阪東という名前の医師は一人しかいませんから」
「かなり昔からいらっしゃるんですか?」
「今は副医院長ですが、ここに病院ができた当時からいらっしゃると伺っているので、古くからいるのは間違いありませんけど」
相手の口調に、こちらを不審に思い始めている様子が感じられた。
「実は、以前にうちの家内がお世話になりまして、近くまで出てきたものですから、先生の時間が許せば、ひと目お会いしてお礼をと思いまして」
咄嗟にそう言うと受付の女性の声から懐疑的な響きが消えた。
「ああ、そうなんですか。それでは、脳外科におつなぎします」
脳外科だって・・・?
ふみえは足の骨折で入院した時の主治医だった、と言っていた。てっきり、整形外科の医者だと思っていたのに・・・・。
考え込んでいると、電話口から男の声が響いた。
「もしもし、阪東ですが」
人当たりの良い感じの柔らかい声だった。
「かなり昔の事なので、もう覚えてないかもしれませんが」と前置きして、宮守ふみえと達仁という親子の事を覚えていないか、と尋ねた。
少しの沈黙の後、受話器の向こうで阪東医師が言った。
「ああ、あの・・・」
「思い出しましたか?」
「思い出すも何も、私も四十年近く、医者をやっていますが、あんな経験をしたのは、最初で最後でしたからね」
「あんな経験?」
受話器を握る手が急に汗ばむのを感じた。
「妻は先生が主治医だったと言っていましたが」
「ええ、たしかに私が執刀しました」
「執刀?手術をうけたんですか?脳外科の?」
驚きだった。ふみえから、そんな話は一度も聞いたことがない。
「病名はなんだったんです?」
「急性の硬膜下血腫ですよ」
「こうまくか・・、けっしゅ?」
「頭部にひどい外傷を受けたせいで、脳と表皮の間の血管が切れて大量出血したんです。病院に運ばれてきた時には、もう意識がなく、昏睡状態でした」
「救急車で来たんですか?」
「たしか、そう記憶していますよ。高校生の娘さんが階段から落ちたという話でした。お父さんが付き添ってね。最初に診た時に、もう駄目かな、とは思いました。経験でね、これは助からないなと。でも一応、開頭手術は行いました。手術しても回復は難しいと説明したんですが、お父さんがどうしてもと言うのでね。頭を開いてみて、やっぱり駄目だと思いました。出血は多いし、脳の腫れもひどくて」
そんなに、ひどい状態だったのか。
しかし、今のふみえには後遺症も何も残っていない。なぜだろう?
「それで、先生は?」
「やるだけのことはやって、頭を閉じました。そのまま昏睡状態が続いて、三日後に」
一拍間をおいてから、阪東医師は受話器の向こうで、言った。
「亡くなりました」
頭の中でぐわんと大きな音が鳴った。
天井がぐるぐると回り出した。
「死んだ?そんなはずはない!ふみえは、私の妻として現に今も生きている!」
受話器の向こうで、相手がため息をついたのがわかった。
「ですから、そのあとなんですよ。あんな経験は初めてだと私が言ったのは」
「何が起きたというんですか?」
「集中治療室で、彼女の心臓が止まって、私が臨終を宣告すると、父親が叫び声をあげながら外に飛び出していったんです。死なせないぞ、自分が必ず生き返らせてやる、というような事を口走ってね」
まるで目の前で見ているように情景が浮かんだ。
「それで・・・?」
自分の声が震えているのがわかった。
「死亡宣告してから二十四時間以上たっていたのに、突然、心臓が動き出したんですよ。つまり、生き返ったんです」
阪東は続けた。
「もう心臓マッサージも人工呼吸もやめていたのにですよ。私を含めたスタッフ全員が、何をしても無駄だとわかっていたからです。それほど、ひどい状態だった。なのに、彼女は蘇生したんです」
一度死んで、生き返った・・・。
まるで、秀明と同じではないか。私の頭に、恐ろしい推測が浮かんだ。
「その時父親は、なにかを持ってはいませんでしたか」
「そういえば・・・、ボストンバックのようなカバンを持ってましたね。治療の間中、肌身離さず抱えてるから、何だろうと思っていました」
「どのくらいの大きさのカバンですか」
「うーん・・・、四十センチくらいだったかなあ」
『黒い手』を入れるには充分な大きさだ。
間違いない。
達仁は、あの三本指の手を持って病院に行ったのだ。
万が一の場合に、「最後の手段」として使うために!
「驚いた事に、次の日に精密検査をしてみると、脳の血腫がきれいさっぱり消えていたんです。あんなことは普通、ありえませんよ」
茫然として、私は受話器を耳から離した。受話器からは阪東の声がまだ聞こえていた。だが、もうこれ以上、聞く必要はなかった。そのまま、受話器を置き、電話を切った。
義父が2度、『黒い手』に願をかけていたのはわかっていた。一度目も、二度目も、スクープ写真を願い、その度に前代未聞のスクープをものにした。新聞社の後輩だった平は、こう言っていた。
「先輩はきっと、3つ目の願いを取っておいたんじゃないかと思います。もう一度、決定的なスクープ写真をものにするためにね」
私も、あの時はそう思った。しかし、間違っていた。
達仁は『願わなかった』のではなく、『願えなかった』のだ。
なぜなら、もう三つ目の願いを使ってしまっていたから。
16歳で死んだ愛娘の蘇りを、あの手に願っていた。
突然、頭の中に2枚の絵がフラッシュバックした。
「アルノルフィーニ夫妻の肖像」とヤン・ファン・エイクの「自画像」だ。
頭の中でこんがらかっていた謎の断片が、不意に一本の糸でつながった気がした。
「アルノルフィーニ夫妻の肖像」にヤン・ファン・エイクが込めた意味は「婚約の証」だ。だが、秀明はこの絵の中に置かれた品々が表すという「隠された意味」を自分なりに解釈したに違いない。それ故に「アルノルフィーニ夫妻の肖像」に魅了された。その呪縛から逃れられなくなった。しかし、だからこそ、絵の中に自分を呪縛から解放する術(すべ)を仕込んだのではないだろうか。
秀明が2つの絵を通して、私に伝えたかったのはこういうことではないのか。
消えてしまう直前に秀明が指さしたのはヤン・ファン・エイクの「自画像」だった。
アルノルフィーニ夫妻が立つ背後の壁には「ヤン・ファン・エイクここにありき」という文字が書かれている。では、絵の中でエイクはどこにいた?
そう、鏡の中だ。
壁に掛けられた鏡に映っている人物の1人がエイク本人だと言われているのだ。
必死で思い出してみる。
達仁の部屋の壁に飾られた鏡。太陽のような、ひまわりのような形をしているあの鏡は「アルノルフィーニ夫妻の肖像」に描かれた鏡によく似ている。しかも、あれは秀明がプレゼントしたものだ。
だとすれば、あの鏡の中に映っているものにこそ、意味があるのだ。
達仁の部屋で鏡の正面に立ってみた時、あの鏡に映っていたのは・・・・。
「とうさん、たのんだよ」と秀明が私に託したかったのは、もしかしたら・・・。
だとすれば、秀明がP国に何度も渡って探していたのは・・・。
そして、それを隠してあるのは、おそらく・・・・・。
そこまで宮守幸彦が話した時だった。
ビデオカメラの液晶モニターの中で、椅子の背にもたれながら、床を見つめて語り続けていた幸彦が、少し驚いた表情を浮かべて、顔をあげた。
そこには、「誰か」がいた。
頭がひどく混乱していた。
幾つもの事実が一本の線でつながりそうなのだが、うまく整理できない。
樹海に首と腕を埋めに行ったあの日以来、酒は断っていたが、飲まずにはいられない気分になった。ふみえが冷蔵庫に入れたままのビールでもよかったが、今はもっと強い酒が欲しい・・・。
そうだ。
達仁の部屋にウィスキーのボトルが残っていたはずだ。
亡くなった義父にはすまないが、あれを飲ませてもらおう。
家にある強い酒は、あのウィスキーだけだ。
夕刊を抱えたまま二階へと上がった。部屋の棚に置かれた未開封のマッカランの瓶とグラスを手に取る。義父の和机に座り、もどかしく封を引きちぎって、コルクのキャップをあけた。バカラのグラスに琥珀色の液体を注ぐ。マッカラン独特のシェリーの香りが鼻腔を甘くくすぐった。
一気に喉に流し込んだ。久しぶりの強いアルコールが食道を焼き、胃を焦がす。立て続けに2杯あおり、叩きつけるようにグラスを机の上に置いた。その衝撃で、机に飾ってあった写真立てのひとつが、パタンと音をたてて倒れた。
裏返しになった写真立てを元の位置に直すと、ふみえが高校に入学した時の写真だった。初々しいセーラー服姿のふみえが、満開の桜の下で笑っていた。
その時、ふと思った。
なぜ達仁は、この写真をいつも机の上に飾っておいたのだろう。
飾ってあったのは、この写真と、ふみえが生まれた時の写真だけだ。
つきあい始めた頃、確か、ふみえはこう言っていた。
自分が生まれてから毎年、桜が満開の季節になると父親が記念写真を撮ってくれた、と。
その習慣は二十歳(はたち)になるまで続いた、と。
なのに、なぜ、この2枚だけなのだ?
0歳から二十歳までは「21枚」の写真があるはずだ。なのに、達仁は何故この2枚だけを選んで飾っていたのだろう・・・・。
不意に、ある考えがひらめき、脳が震えた。
私は義父の部屋を飛び出し、階段を駆け下りた。
確かめたいことがあった。向かったのは、一階の和室だ。
和箪笥の一番下の開き戸を開ける。家族のアルバムがしまってある場所だ。
全部を外に引っ張り出し、目的のものを捜した。見るのは初めてだったが、それだとすぐにわかった。ひときわ立派なアルバムだったし、表紙に桜の花の刺繍がほどこされていたからだ。
最初のページに貼られていたのは、達仁の机にあったのと同じ1枚だった。
生まれたばかりのふみえが、母親に抱かれて写っている。
ページをめくる。1歳になった時は白いおくるみに包まれて、やはり母親に抱かれていた。2歳の時には花柄のワンピースを着て、3歳になると七五三の晴れ着姿で桜の下にひとりで立っていた。母親はふみえが1歳の時に亡くなっているからだ。
赤いランドセルを背負っているのは、小学校入学の年だ。それが中学のセーラー服に変わり、中2ではテニスウエア、卒業の年には桜の花びらが舞い散る中で卒業証書を広げて笑っていた。
そして、あの写真だ。
16歳。高校入学。真新しいセーラー服に身を包んだふみえは、満開の桜に負けないほど生気に満ち、弾けるような美しさだった。私は次のページをめくった。
そして、我が目を疑った。
そんなことが・・・。
次のページに、写真はなかった。
さらに次のページにも。
その次のページにも。
あとは白紙のページが続くだけだった。
どういうことだ・・・・。
ふみえの話では、達仁が1年に1枚ずつ撮影してくれたという「満開の桜の下の成長記録」は、二十歳になるまで続いたはずだ。写真は全部で21枚あるはずだった。
それなのに、記念写真は17枚しかない。
16歳で終わっているのだ。
なぜ、ふみえは21枚あるなどと嘘をついたのだ?
それよりも、桜の下での記念写真を「カメラマンとして自分ができる唯一のプレゼント」と言っていたという達仁が撮影を止めてしまったのは何故だ?
生まれた時の写真と16歳の時の写真だけを机の上に飾っていたのも妙だ。
誕生の年の写真はわかる。だが、もう一枚が高校に入学した時のものというのはわからない。
おそらく、ふみえが16歳の時、「よほどの何か」があったのだ。
達仁があれほど大切に思っていた記念写真を撮るのをやめてしまうほどの何かが・・。
ふみえが16歳の時のことを知る人物を捜すことだ。
まず、浮かんだのは達仁の妹、咲恵だ。部屋の子機を使って、自宅に電話をかけた。
しかし、留守番電話だった。保険会社の慰安旅行で、二泊三日の箱根旅行に出かけているという応答メッセージが流れた。出しゃばりなくせに肝心の時に役に立たない女だ。
電話を切って、考え込んでしまった。
達仁の両親はすでに亡くなっていたので、ふみえの親戚はもう咲恵しかいなかった。他にふみえの16歳の頃を知る人間に心当たりがない。
しばらく思い悩んでいると、ある事を思い出した。
達仁の部屋で「黒い手」を見つけた時に、ふみえが言っていた一言だ。
高校1年の時に足を骨折して入院した、とふみえは言っていた。たしか入院先は・・・、そう、北沢大学付属病院だ。
手術を担当した医者がグレゴリー・ペックそっくりの二枚目だった、とも言っていた。
だが、名前が思い出せなかった。
必死で、あの時の会話を思い出そうとした。
あの時、私はこう言ったはずだ。「歌舞伎の女形みたいにナヨナヨした奴だったんじゃないのか」。
そして、秀明がちゃちゃを入れたのだ。アンパンマン顔のタレントの名をあげて。
坂東玉三郎に、板東英二・・・。
そうだ。
主治医の名字を、はっきり思い出した。
「バンドウ」だ。
間違いない。
北沢大付属病院の代表番号は電話帳で調べて、すぐにわかった。私はわらをもすがる思いで、プッシュホンを押した。
電話口に出たのは病院の総合案内の女性だった。
「あの・・、そちらに、バンドウ先生というお医者様はいらっしゃいますか。字はわからないんですが」
相手は事務的な口調で言った。
「ちょっとお待ちください」
1分ほど待たされて、再び相手が出た。
「阪東敏昭先生のことですか。この病院には、阪東という名前の医師は一人しかいませんから」
「かなり昔からいらっしゃるんですか?」
「今は副医院長ですが、ここに病院ができた当時からいらっしゃると伺っているので、古くからいるのは間違いありませんけど」
相手の口調に、こちらを不審に思い始めている様子が感じられた。
「実は、以前にうちの家内がお世話になりまして、近くまで出てきたものですから、先生の時間が許せば、ひと目お会いしてお礼をと思いまして」
咄嗟にそう言うと受付の女性の声から懐疑的な響きが消えた。
「ああ、そうなんですか。それでは、脳外科におつなぎします」
脳外科だって・・・?
ふみえは足の骨折で入院した時の主治医だった、と言っていた。てっきり、整形外科の医者だと思っていたのに・・・・。
考え込んでいると、電話口から男の声が響いた。
「もしもし、阪東ですが」
人当たりの良い感じの柔らかい声だった。
「かなり昔の事なので、もう覚えてないかもしれませんが」と前置きして、宮守ふみえと達仁という親子の事を覚えていないか、と尋ねた。
少しの沈黙の後、受話器の向こうで阪東医師が言った。
「ああ、あの・・・」
「思い出しましたか?」
「思い出すも何も、私も四十年近く、医者をやっていますが、あんな経験をしたのは、最初で最後でしたからね」
「あんな経験?」
受話器を握る手が急に汗ばむのを感じた。
「妻は先生が主治医だったと言っていましたが」
「ええ、たしかに私が執刀しました」
「執刀?手術をうけたんですか?脳外科の?」
驚きだった。ふみえから、そんな話は一度も聞いたことがない。
「病名はなんだったんです?」
「急性の硬膜下血腫ですよ」
「こうまくか・・、けっしゅ?」
「頭部にひどい外傷を受けたせいで、脳と表皮の間の血管が切れて大量出血したんです。病院に運ばれてきた時には、もう意識がなく、昏睡状態でした」
「救急車で来たんですか?」
「たしか、そう記憶していますよ。高校生の娘さんが階段から落ちたという話でした。お父さんが付き添ってね。最初に診た時に、もう駄目かな、とは思いました。経験でね、これは助からないなと。でも一応、開頭手術は行いました。手術しても回復は難しいと説明したんですが、お父さんがどうしてもと言うのでね。頭を開いてみて、やっぱり駄目だと思いました。出血は多いし、脳の腫れもひどくて」
そんなに、ひどい状態だったのか。
しかし、今のふみえには後遺症も何も残っていない。なぜだろう?
「それで、先生は?」
「やるだけのことはやって、頭を閉じました。そのまま昏睡状態が続いて、三日後に」
一拍間をおいてから、阪東医師は受話器の向こうで、言った。
「亡くなりました」
頭の中でぐわんと大きな音が鳴った。
天井がぐるぐると回り出した。
「死んだ?そんなはずはない!ふみえは、私の妻として現に今も生きている!」
受話器の向こうで、相手がため息をついたのがわかった。
「ですから、そのあとなんですよ。あんな経験は初めてだと私が言ったのは」
「何が起きたというんですか?」
「集中治療室で、彼女の心臓が止まって、私が臨終を宣告すると、父親が叫び声をあげながら外に飛び出していったんです。死なせないぞ、自分が必ず生き返らせてやる、というような事を口走ってね」
まるで目の前で見ているように情景が浮かんだ。
「それで・・・?」
自分の声が震えているのがわかった。
「死亡宣告してから二十四時間以上たっていたのに、突然、心臓が動き出したんですよ。つまり、生き返ったんです」
阪東は続けた。
「もう心臓マッサージも人工呼吸もやめていたのにですよ。私を含めたスタッフ全員が、何をしても無駄だとわかっていたからです。それほど、ひどい状態だった。なのに、彼女は蘇生したんです」
一度死んで、生き返った・・・。
まるで、秀明と同じではないか。私の頭に、恐ろしい推測が浮かんだ。
「その時父親は、なにかを持ってはいませんでしたか」
「そういえば・・・、ボストンバックのようなカバンを持ってましたね。治療の間中、肌身離さず抱えてるから、何だろうと思っていました」
「どのくらいの大きさのカバンですか」
「うーん・・・、四十センチくらいだったかなあ」
『黒い手』を入れるには充分な大きさだ。
間違いない。
達仁は、あの三本指の手を持って病院に行ったのだ。
万が一の場合に、「最後の手段」として使うために!
「驚いた事に、次の日に精密検査をしてみると、脳の血腫がきれいさっぱり消えていたんです。あんなことは普通、ありえませんよ」
茫然として、私は受話器を耳から離した。受話器からは阪東の声がまだ聞こえていた。だが、もうこれ以上、聞く必要はなかった。そのまま、受話器を置き、電話を切った。
義父が2度、『黒い手』に願をかけていたのはわかっていた。一度目も、二度目も、スクープ写真を願い、その度に前代未聞のスクープをものにした。新聞社の後輩だった平は、こう言っていた。
「先輩はきっと、3つ目の願いを取っておいたんじゃないかと思います。もう一度、決定的なスクープ写真をものにするためにね」
私も、あの時はそう思った。しかし、間違っていた。
達仁は『願わなかった』のではなく、『願えなかった』のだ。
なぜなら、もう三つ目の願いを使ってしまっていたから。
16歳で死んだ愛娘の蘇りを、あの手に願っていた。
突然、頭の中に2枚の絵がフラッシュバックした。
「アルノルフィーニ夫妻の肖像」とヤン・ファン・エイクの「自画像」だ。
頭の中でこんがらかっていた謎の断片が、不意に一本の糸でつながった気がした。
「アルノルフィーニ夫妻の肖像」にヤン・ファン・エイクが込めた意味は「婚約の証」だ。だが、秀明はこの絵の中に置かれた品々が表すという「隠された意味」を自分なりに解釈したに違いない。それ故に「アルノルフィーニ夫妻の肖像」に魅了された。その呪縛から逃れられなくなった。しかし、だからこそ、絵の中に自分を呪縛から解放する術(すべ)を仕込んだのではないだろうか。
秀明が2つの絵を通して、私に伝えたかったのはこういうことではないのか。
消えてしまう直前に秀明が指さしたのはヤン・ファン・エイクの「自画像」だった。
アルノルフィーニ夫妻が立つ背後の壁には「ヤン・ファン・エイクここにありき」という文字が書かれている。では、絵の中でエイクはどこにいた?
そう、鏡の中だ。
壁に掛けられた鏡に映っている人物の1人がエイク本人だと言われているのだ。
必死で思い出してみる。
達仁の部屋の壁に飾られた鏡。太陽のような、ひまわりのような形をしているあの鏡は「アルノルフィーニ夫妻の肖像」に描かれた鏡によく似ている。しかも、あれは秀明がプレゼントしたものだ。
だとすれば、あの鏡の中に映っているものにこそ、意味があるのだ。
達仁の部屋で鏡の正面に立ってみた時、あの鏡に映っていたのは・・・・。
「とうさん、たのんだよ」と秀明が私に託したかったのは、もしかしたら・・・。
だとすれば、秀明がP国に何度も渡って探していたのは・・・。
そして、それを隠してあるのは、おそらく・・・・・。
そこまで宮守幸彦が話した時だった。
ビデオカメラの液晶モニターの中で、椅子の背にもたれながら、床を見つめて語り続けていた幸彦が、少し驚いた表情を浮かべて、顔をあげた。
そこには、「誰か」がいた。
0
お気に入りに追加
6
この作品は感想を受け付けておりません。
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

特殊捜査官・天城宿禰の事件簿~乙女の告発
斑鳩陽菜
ミステリー
K県警捜査一課特殊捜査室――、そこにたった一人だけ特殊捜査官の肩書をもつ男、天城宿禰が在籍している。
遺留品や現場にある物が残留思念を読み取り、犯人を導くという。
そんな県警管轄内で、美術評論家が何者かに殺害された。
遺体の周りには、大量のガラス片が飛散。
臨場した天城は、さっそく残留思念を読み取るのだが――。
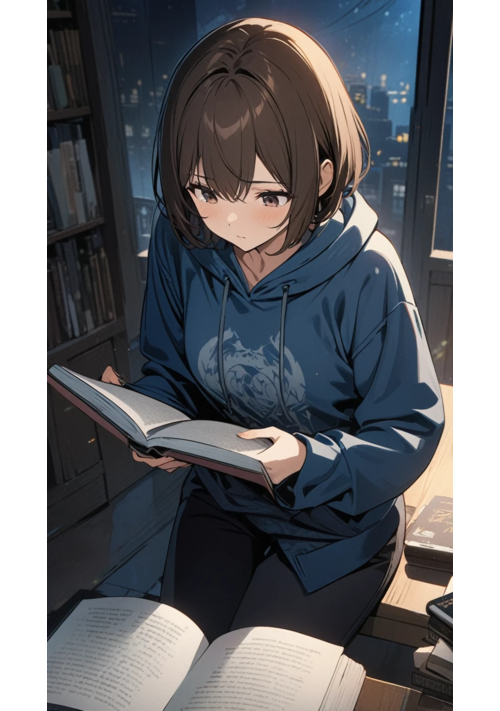
声の響く洋館
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、友人の失踪をきっかけに不気味な洋館を訪れる。そこで彼らは、過去の住人たちの声を聞き、その悲劇に導かれる。失踪した友人たちの影を追い、葉羽と彩由美は声の正体を探りながら、過去の未練に囚われた人々の思いを解放するための儀式を行うことを決意する。
彼らは古びた日記を手掛かりに、恐れや不安を乗り越えながら、解放の儀式を成功させる。過去の住人たちが解放される中で、葉羽と彩由美は自らの成長を実感し、新たな未来へと歩み出す。物語は、過去の悲劇を乗り越え、希望に満ちた未来を切り開く二人の姿を描く。

冷凍少女 ~切なくて、会いたくて~
星野 未来
ミステリー
21歳の青年『健(タケル)』は、未来に希望を見出せず、今日死のうと決めていた。この最後の配達の仕事が終わったら、全て終わりにするはずだった。
でも、その荷物をある館に住む老人に届けると、その老人が君に必要と言って家に持ち帰るように話す。理解ができなかったが、健の住むアパートで荷物を解くと、そこには、冷凍になった16歳の少女『日和(ひより)』の姿があた。
健と日和は、どこかふたりとも淋しい者同士。いつしか一緒に生活するようになり、心が打ち解けて行く。そして、ふたりの間に淡い『恋』が生まれる。
しかし、ある日、健が出張で外泊した時に、一人留守番をしていた日和に事件が起こる。その凄まじい光景に、健は天に叫んだ……。
切なく、儚いふたりの恋と、日和の秘密と謎、そして、あの老人『西園寺』という男とは…。
このミステリーの謎は、あなたの心の中に答えがある……。
君はなぜこの世界に生まれてきたの…?
僕はなぜ君に出会ってしまったんだろう…。
この冷たい世界でしか、生きられないのに…。
切なくて……、会いたくて……。
感動のラストシーンは、あなたの胸の中に……。
表紙原画イラストは、あままつさんです。
いつもありがとうございます♪(*´◡`*)
文字入れ、装飾、アニメーションは、miraii♪ です。

伏線回収の夏
影山姫子
ミステリー
ある年の夏。俺は十五年ぶりに栃木県日光市にある古い屋敷を訪れた。某大学の芸術学部でクラスメイトだった岡滝利奈の招きだった。かつての同級生の不審死。消えた犯人。屋敷のアトリエにナイフで刻まれた無数のXの傷。利奈はそのなぞを、ミステリー作家であるこの俺に推理してほしいというのだ。俺、利奈、桐山優也、十文字省吾、新山亜沙美、須藤真利亜の六人は、大学時代にこの屋敷で共に芸術の創作に打ち込んだ仲間だった。グループの中に犯人はいるのか? 俺の脳裏によみがえる青春時代の熱気、裏切り、そして別れ。懐かしくも苦い思い出をたどりながら事件の真相に近づく俺に、衝撃のラストが待ち受けていた。
《あなたはすべての伏線を回収することができますか?》

密室島の輪舞曲
葉羽
ミステリー
夏休み、天才高校生の神藤葉羽は幼なじみの望月彩由美とともに、離島にある古い洋館「月影館」を訪れる。その洋館で連続して起きる不可解な密室殺人事件。被害者たちは、内側から完全に施錠された部屋で首吊り死体として発見される。しかし、葉羽は死体の状況に違和感を覚えていた。
洋館には、著名な実業家や学者たち12名が宿泊しており、彼らは謎めいた「月影会」というグループに所属していた。彼らの間で次々と起こる密室殺人。不可解な現象と怪奇的な出来事が重なり、洋館は恐怖の渦に包まれていく。

双極の鏡
葉羽
ミステリー
神藤葉羽は、高校2年生にして天才的な頭脳を持つ少年。彼は推理小説を読み漁る日々を送っていたが、ある日、幼馴染の望月彩由美からの突然の依頼を受ける。彼女の友人が密室で発見された死体となり、周囲は不可解な状況に包まれていた。葉羽は、彼女の優しさに惹かれつつも、事件の真相を解明することに心血を注ぐ。
事件の背後には、視覚的な錯覚を利用した巧妙なトリックが隠されており、密室の真実を解き明かすために葉羽は思考を巡らせる。彼と彩由美の絆が深まる中、恐怖と謎が交錯する不気味な空間で、彼は人間の心の闇にも触れることになる。果たして、葉羽は真実を見抜くことができるのか。

どんでん返し
あいうら
ミステリー
「1話完結」~最後の1行で衝撃が走る短編集~
ようやく子どもに恵まれた主人公は、家族でキャンプに来ていた。そこで偶然遭遇したのは、彼が閑職に追いやったかつての部下だった。なぜかファミリー用のテントに1人で宿泊する部下に違和感を覚えるが…
(「薪」より)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















