お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

特殊捜査官・天城宿禰の事件簿~乙女の告発
斑鳩陽菜
ミステリー
K県警捜査一課特殊捜査室――、そこにたった一人だけ特殊捜査官の肩書をもつ男、天城宿禰が在籍している。
遺留品や現場にある物が残留思念を読み取り、犯人を導くという。
そんな県警管轄内で、美術評論家が何者かに殺害された。
遺体の周りには、大量のガラス片が飛散。
臨場した天城は、さっそく残留思念を読み取るのだが――。
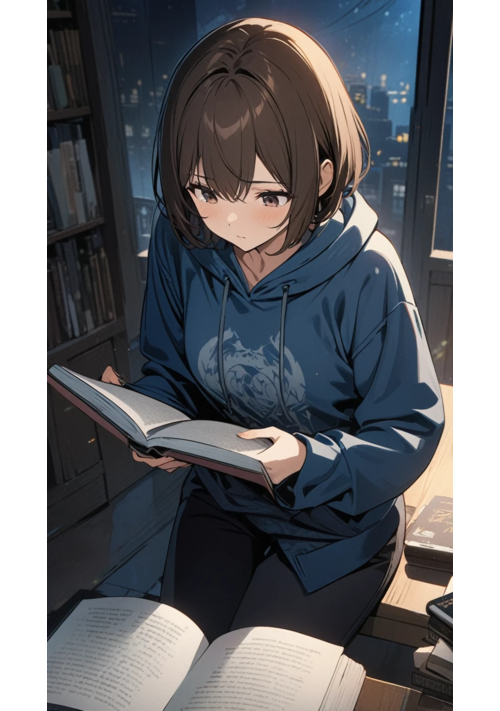
声の響く洋館
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、友人の失踪をきっかけに不気味な洋館を訪れる。そこで彼らは、過去の住人たちの声を聞き、その悲劇に導かれる。失踪した友人たちの影を追い、葉羽と彩由美は声の正体を探りながら、過去の未練に囚われた人々の思いを解放するための儀式を行うことを決意する。
彼らは古びた日記を手掛かりに、恐れや不安を乗り越えながら、解放の儀式を成功させる。過去の住人たちが解放される中で、葉羽と彩由美は自らの成長を実感し、新たな未来へと歩み出す。物語は、過去の悲劇を乗り越え、希望に満ちた未来を切り開く二人の姿を描く。

伏線回収の夏
影山姫子
ミステリー
ある年の夏。俺は十五年ぶりに栃木県日光市にある古い屋敷を訪れた。某大学の芸術学部でクラスメイトだった岡滝利奈の招きだった。かつての同級生の不審死。消えた犯人。屋敷のアトリエにナイフで刻まれた無数のXの傷。利奈はそのなぞを、ミステリー作家であるこの俺に推理してほしいというのだ。俺、利奈、桐山優也、十文字省吾、新山亜沙美、須藤真利亜の六人は、大学時代にこの屋敷で共に芸術の創作に打ち込んだ仲間だった。グループの中に犯人はいるのか? 俺の脳裏によみがえる青春時代の熱気、裏切り、そして別れ。懐かしくも苦い思い出をたどりながら事件の真相に近づく俺に、衝撃のラストが待ち受けていた。
《あなたはすべての伏線を回収することができますか?》

冷凍少女 ~切なくて、会いたくて~
星野 未来
ミステリー
21歳の青年『健(タケル)』は、未来に希望を見出せず、今日死のうと決めていた。この最後の配達の仕事が終わったら、全て終わりにするはずだった。
でも、その荷物をある館に住む老人に届けると、その老人が君に必要と言って家に持ち帰るように話す。理解ができなかったが、健の住むアパートで荷物を解くと、そこには、冷凍になった16歳の少女『日和(ひより)』の姿があた。
健と日和は、どこかふたりとも淋しい者同士。いつしか一緒に生活するようになり、心が打ち解けて行く。そして、ふたりの間に淡い『恋』が生まれる。
しかし、ある日、健が出張で外泊した時に、一人留守番をしていた日和に事件が起こる。その凄まじい光景に、健は天に叫んだ……。
切なく、儚いふたりの恋と、日和の秘密と謎、そして、あの老人『西園寺』という男とは…。
このミステリーの謎は、あなたの心の中に答えがある……。
君はなぜこの世界に生まれてきたの…?
僕はなぜ君に出会ってしまったんだろう…。
この冷たい世界でしか、生きられないのに…。
切なくて……、会いたくて……。
感動のラストシーンは、あなたの胸の中に……。
表紙原画イラストは、あままつさんです。
いつもありがとうございます♪(*´◡`*)
文字入れ、装飾、アニメーションは、miraii♪ です。

密室島の輪舞曲
葉羽
ミステリー
夏休み、天才高校生の神藤葉羽は幼なじみの望月彩由美とともに、離島にある古い洋館「月影館」を訪れる。その洋館で連続して起きる不可解な密室殺人事件。被害者たちは、内側から完全に施錠された部屋で首吊り死体として発見される。しかし、葉羽は死体の状況に違和感を覚えていた。
洋館には、著名な実業家や学者たち12名が宿泊しており、彼らは謎めいた「月影会」というグループに所属していた。彼らの間で次々と起こる密室殺人。不可解な現象と怪奇的な出来事が重なり、洋館は恐怖の渦に包まれていく。

双極の鏡
葉羽
ミステリー
神藤葉羽は、高校2年生にして天才的な頭脳を持つ少年。彼は推理小説を読み漁る日々を送っていたが、ある日、幼馴染の望月彩由美からの突然の依頼を受ける。彼女の友人が密室で発見された死体となり、周囲は不可解な状況に包まれていた。葉羽は、彼女の優しさに惹かれつつも、事件の真相を解明することに心血を注ぐ。
事件の背後には、視覚的な錯覚を利用した巧妙なトリックが隠されており、密室の真実を解き明かすために葉羽は思考を巡らせる。彼と彩由美の絆が深まる中、恐怖と謎が交錯する不気味な空間で、彼は人間の心の闇にも触れることになる。果たして、葉羽は真実を見抜くことができるのか。

どんでん返し
あいうら
ミステリー
「1話完結」~最後の1行で衝撃が走る短編集~
ようやく子どもに恵まれた主人公は、家族でキャンプに来ていた。そこで偶然遭遇したのは、彼が閑職に追いやったかつての部下だった。なぜかファミリー用のテントに1人で宿泊する部下に違和感を覚えるが…
(「薪」より)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















