4 / 15
第四話「悪魔の誘いは断れない」
しおりを挟む
ーー第四話「悪魔の誘いは断れない」
久々津は尋ねる。「君の名前は?」
「Oze」と彼は答えた。
「オズ、そうか君はオズというのか」久々津は頷きながら言う。「私は久々津という。君の主人だ」
「主人」彼の瞳が赤く光る。
「そうだ」
「おまえが、私の主人であるわけがない。矮小な人間。お前は契約者だ。オズはお前が契約した者の名前だ。おまえに、君などと呼ばれたことは腹立たしい、それ以上に、一瞬たりともおまえが私に対して優位な態度を取ったことが腹立たしい。だが、契約は締結された。お前のたったひとつの望みを叶えよう」
彼は自らの胸に手を当てて、宙に何かを刻み始めた。赤い光が降り注いでいた。久々津はその光景に目を奪われていた。契約の対価など気にする暇などなかった。
次の日、彼のアンドロイドは驚くほど正常に動作した。久々津が望む通りの動作をしていた。その話をどこで聞きつけたか、根津が訪ねてきた。「久々津先生、成功されたとか」
「あぁ」久々津は隠す様子も見せない。その過程についてこの根津とやらは知っている。「信じられないよ、これほどまでに精巧なアンドロイドが完成するなんて、まるで魔法のようだ」
「まるで」根津はそこで言葉を区切って笑う。「まるでじゃないですよ、本当に魔の力なのです。これでようやく研究が鉄の道に乗りましたね」
「あぁ、おかげさまで、この知識は司馬にしかないだろう。どの学術書にも載っていない。私は、この成果を早く発表したい。これで科研費がとれる。基盤Aも夢じゃない」
「よぅござんす。よぅござんす。それで、私たちのラボにはいつ頃来られるのでしょうか?」
「ちょっと待っていてくれ、論文誌に投稿する。あと一年は待っていて欲しい。そうすれば、司馬のもとに行こう。この『陣』の恩をしなければならない。いや、論文を書いている間にも着想は出来る。司馬の求めているモノ、その要求事項についてまとめて送ってくれないか」
「かしこまりました。すべては司馬さまのために」そう言って、根津は研究室のドアから外へといなくなっていった。久々津の端末にはダイレクトメールが数十件溜まっていた。久々津はそれよりも今が日曜日の二五時であることに驚き、急いで近くのホテルをとった。
「おはようございます」そのアンドロイドは、便宜上【クアン(KUgutsu-ANdroid)】と呼ばれた。「教授、本日の実験はどのようなものなのでしょうか?」
「今日はクアンの認知についての実験であり、音楽のリズム、メロディ、コードについて認識できるかというものだ」
「リズム、メロディ、コード、音楽にとって重要な要素であることは知っていますが、実際どのようなものかわかりません。私には難しいと思います」
「それでもやるんだ。すべてデータを取って、一本の論文にまとめる。他のアンドロイドとの違いを見せつけなければならない。これはそのために必要な一歩なんだよ」
「はい」クアンは少し首を傾けながらうなづいた。
・・・
「おはよう」扉の先には水守がいた。「今日、退院するそうだな」
「はい、お世話になります」
「あぁ、よろしく頼む」
御堂は水守が運転する車で、西新宿、都庁前にある魔導警備本社へと向かっていった。御堂はその間、窓の外に移る景色を眺めていた。
(別に珍しくもないだろうに)水守はそう思いながら、煙草をふかしていた。水守は御堂が煙草に関して文句を言わないことを少しばかり評価した。最近の若者は煙草のことをすぐ悪く言う。
「タバコ、お好きなんですか?」御堂が尋ねる。
「あぁ、好きでなければ吸わない」
「一本くれませんか、次の信号でいいので」
「あぁ、わかった」
信号で止まると、水守は御堂に一本とライターを渡した。「ありがとうございます」と御堂は言い、慣れた手つきで煙草に火をつけた。
「アメスピですか?」
「あぁ」
「ありがとうございます。病院では吸えなかったので」
「あぁ」水守は息を漏らすように言い、ハンドルを切る。「吸う人間が増えてよかったよ」
魔導警備本社は、気持ちばかりの木々に囲まれていた。建物の南側に、エレベーターが走っているのが見える。水守らは地下の駐車場に車を止めて、エレベーターで十一階へと向かっていた。
「一応、俺の班の部屋があるんだが、そこではなるべく煙草を吸うな、うるさい人間がいる」
「わかりました。水守さんが吸っていようとも吸いません」
「そうしてくれ」(年下のお前が煙草を吸っているのを見たら卒倒するかもしれん)。
特別班とだけ書かれた部屋はその階の東の隅にあった。開くと窓からの明かりが部屋の中を眩しいくらいに照らしていた。
「戻った」水守がそう言うと、「おかえりなさい」と江良が返した。
「御堂君も退院おめでとう。親御さんたちには挨拶できた?」
「ありがとうございます。それが、少し予定が合わなくて」
「それは、残念。けど、ここに配属されればいつでも会えるからね」
「おい、江良。変な希望を持たせるんじゃない。まだ適性検査が終わっていない。どこに配置されるかはそれ次第だ」そう江良をたしなめ、御堂の顔を見る。「だが、俺はお前が班に来てくれることを祈っている」
「ありがとうございます、水守さん。それでは、行ってきます。終わったら、ここに戻ってくればいいんですよね」
「あぁ」水守はそう言って、胸ポケットの箱を叩いた。御堂はそれを見て笑みをつくって頷いた。
・・・
適性検査の結果が出るまでの期間は、社員寮に部屋を一つ取ってもらえることになっていた。御堂はそのベッドの上で、天井の染みを眺めていた。時々、左手首を眺めたりしていた。その思案気な時間に飽きると、ベッドから起き上がりテレビの電源を入れた。その時間は、どの局も情報番組を流していた。彼は適当なチャンネルに合わせ、ぼんやりとその画面の移ろいを眺めていた。
「誰も知らない」御堂はそうつぶやく。「やはり、ここは違う世界、時間軸なのだ。だが、確かに御堂という人間は存在している。戸籍もあるし、親族も実在しているし、ぼくの意識以外の問題が全くない。これは本当に現実なのだろうか。いや、夢に違いない。魔法など、あり得るわけがないのだ」
「だが」テレビの画面の向こうでは、魔法犯罪についての議論がなされている。日野という男が専門家として話に加わっている。彼が言うには、魔法犯罪は確かに憎むべきものであるが、魔法を発現したことによる精神の失調も考慮すべきである。一度犯した罪ですべてを終わらせるのではなく、その者に機会を与えることが大事であり、国は制度としてそれを保証すべき、らしい。
(聞こえはいいが、それは遺族には聞き入れられない話ではないか)御堂は思う。(精神の失調も考慮すべき、とか、機会を与える、とかそういう言葉はいらない。持つべき者は、どれほど後ろ指をさされようとも、石を投げられようとも、その身を賭して与えられた運命に従わなければならない)
御堂は背をベッドに預けた。そして、思考の続きをイメージと共に繰り広げていたら、夢と現実のはざまが曖昧になり、そのまま眠りについてしまった。
それは夢にしてはいやに実感のある夢だった。
「たすけて」と願う声は、聞き覚えのあるものだった。「ぼくは、大学の研究室にいる、助けて」実体のない魂が叫んでいた。黒い靄が立ち込め、御堂の身体を覆いつくした。
「君は」そこに御堂の意思はない。
「ぼくは、御堂メグルだ」
「君が御堂メグル。君はどこにいる、いまどういう状況にある」
「ぼくは、大学の研究室にいる。君が行っていた大学と同じ大学だ。研究室も同じ。久々津に囚われているんだ。くれぐれも気を付けてくれ、久々津は悪魔だ!」
この短い夢の目覚めには、頬を伝う涙があった。
「俺が助けなければならない」御堂は水守に電話をかけた。
久々津は尋ねる。「君の名前は?」
「Oze」と彼は答えた。
「オズ、そうか君はオズというのか」久々津は頷きながら言う。「私は久々津という。君の主人だ」
「主人」彼の瞳が赤く光る。
「そうだ」
「おまえが、私の主人であるわけがない。矮小な人間。お前は契約者だ。オズはお前が契約した者の名前だ。おまえに、君などと呼ばれたことは腹立たしい、それ以上に、一瞬たりともおまえが私に対して優位な態度を取ったことが腹立たしい。だが、契約は締結された。お前のたったひとつの望みを叶えよう」
彼は自らの胸に手を当てて、宙に何かを刻み始めた。赤い光が降り注いでいた。久々津はその光景に目を奪われていた。契約の対価など気にする暇などなかった。
次の日、彼のアンドロイドは驚くほど正常に動作した。久々津が望む通りの動作をしていた。その話をどこで聞きつけたか、根津が訪ねてきた。「久々津先生、成功されたとか」
「あぁ」久々津は隠す様子も見せない。その過程についてこの根津とやらは知っている。「信じられないよ、これほどまでに精巧なアンドロイドが完成するなんて、まるで魔法のようだ」
「まるで」根津はそこで言葉を区切って笑う。「まるでじゃないですよ、本当に魔の力なのです。これでようやく研究が鉄の道に乗りましたね」
「あぁ、おかげさまで、この知識は司馬にしかないだろう。どの学術書にも載っていない。私は、この成果を早く発表したい。これで科研費がとれる。基盤Aも夢じゃない」
「よぅござんす。よぅござんす。それで、私たちのラボにはいつ頃来られるのでしょうか?」
「ちょっと待っていてくれ、論文誌に投稿する。あと一年は待っていて欲しい。そうすれば、司馬のもとに行こう。この『陣』の恩をしなければならない。いや、論文を書いている間にも着想は出来る。司馬の求めているモノ、その要求事項についてまとめて送ってくれないか」
「かしこまりました。すべては司馬さまのために」そう言って、根津は研究室のドアから外へといなくなっていった。久々津の端末にはダイレクトメールが数十件溜まっていた。久々津はそれよりも今が日曜日の二五時であることに驚き、急いで近くのホテルをとった。
「おはようございます」そのアンドロイドは、便宜上【クアン(KUgutsu-ANdroid)】と呼ばれた。「教授、本日の実験はどのようなものなのでしょうか?」
「今日はクアンの認知についての実験であり、音楽のリズム、メロディ、コードについて認識できるかというものだ」
「リズム、メロディ、コード、音楽にとって重要な要素であることは知っていますが、実際どのようなものかわかりません。私には難しいと思います」
「それでもやるんだ。すべてデータを取って、一本の論文にまとめる。他のアンドロイドとの違いを見せつけなければならない。これはそのために必要な一歩なんだよ」
「はい」クアンは少し首を傾けながらうなづいた。
・・・
「おはよう」扉の先には水守がいた。「今日、退院するそうだな」
「はい、お世話になります」
「あぁ、よろしく頼む」
御堂は水守が運転する車で、西新宿、都庁前にある魔導警備本社へと向かっていった。御堂はその間、窓の外に移る景色を眺めていた。
(別に珍しくもないだろうに)水守はそう思いながら、煙草をふかしていた。水守は御堂が煙草に関して文句を言わないことを少しばかり評価した。最近の若者は煙草のことをすぐ悪く言う。
「タバコ、お好きなんですか?」御堂が尋ねる。
「あぁ、好きでなければ吸わない」
「一本くれませんか、次の信号でいいので」
「あぁ、わかった」
信号で止まると、水守は御堂に一本とライターを渡した。「ありがとうございます」と御堂は言い、慣れた手つきで煙草に火をつけた。
「アメスピですか?」
「あぁ」
「ありがとうございます。病院では吸えなかったので」
「あぁ」水守は息を漏らすように言い、ハンドルを切る。「吸う人間が増えてよかったよ」
魔導警備本社は、気持ちばかりの木々に囲まれていた。建物の南側に、エレベーターが走っているのが見える。水守らは地下の駐車場に車を止めて、エレベーターで十一階へと向かっていた。
「一応、俺の班の部屋があるんだが、そこではなるべく煙草を吸うな、うるさい人間がいる」
「わかりました。水守さんが吸っていようとも吸いません」
「そうしてくれ」(年下のお前が煙草を吸っているのを見たら卒倒するかもしれん)。
特別班とだけ書かれた部屋はその階の東の隅にあった。開くと窓からの明かりが部屋の中を眩しいくらいに照らしていた。
「戻った」水守がそう言うと、「おかえりなさい」と江良が返した。
「御堂君も退院おめでとう。親御さんたちには挨拶できた?」
「ありがとうございます。それが、少し予定が合わなくて」
「それは、残念。けど、ここに配属されればいつでも会えるからね」
「おい、江良。変な希望を持たせるんじゃない。まだ適性検査が終わっていない。どこに配置されるかはそれ次第だ」そう江良をたしなめ、御堂の顔を見る。「だが、俺はお前が班に来てくれることを祈っている」
「ありがとうございます、水守さん。それでは、行ってきます。終わったら、ここに戻ってくればいいんですよね」
「あぁ」水守はそう言って、胸ポケットの箱を叩いた。御堂はそれを見て笑みをつくって頷いた。
・・・
適性検査の結果が出るまでの期間は、社員寮に部屋を一つ取ってもらえることになっていた。御堂はそのベッドの上で、天井の染みを眺めていた。時々、左手首を眺めたりしていた。その思案気な時間に飽きると、ベッドから起き上がりテレビの電源を入れた。その時間は、どの局も情報番組を流していた。彼は適当なチャンネルに合わせ、ぼんやりとその画面の移ろいを眺めていた。
「誰も知らない」御堂はそうつぶやく。「やはり、ここは違う世界、時間軸なのだ。だが、確かに御堂という人間は存在している。戸籍もあるし、親族も実在しているし、ぼくの意識以外の問題が全くない。これは本当に現実なのだろうか。いや、夢に違いない。魔法など、あり得るわけがないのだ」
「だが」テレビの画面の向こうでは、魔法犯罪についての議論がなされている。日野という男が専門家として話に加わっている。彼が言うには、魔法犯罪は確かに憎むべきものであるが、魔法を発現したことによる精神の失調も考慮すべきである。一度犯した罪ですべてを終わらせるのではなく、その者に機会を与えることが大事であり、国は制度としてそれを保証すべき、らしい。
(聞こえはいいが、それは遺族には聞き入れられない話ではないか)御堂は思う。(精神の失調も考慮すべき、とか、機会を与える、とかそういう言葉はいらない。持つべき者は、どれほど後ろ指をさされようとも、石を投げられようとも、その身を賭して与えられた運命に従わなければならない)
御堂は背をベッドに預けた。そして、思考の続きをイメージと共に繰り広げていたら、夢と現実のはざまが曖昧になり、そのまま眠りについてしまった。
それは夢にしてはいやに実感のある夢だった。
「たすけて」と願う声は、聞き覚えのあるものだった。「ぼくは、大学の研究室にいる、助けて」実体のない魂が叫んでいた。黒い靄が立ち込め、御堂の身体を覆いつくした。
「君は」そこに御堂の意思はない。
「ぼくは、御堂メグルだ」
「君が御堂メグル。君はどこにいる、いまどういう状況にある」
「ぼくは、大学の研究室にいる。君が行っていた大学と同じ大学だ。研究室も同じ。久々津に囚われているんだ。くれぐれも気を付けてくれ、久々津は悪魔だ!」
この短い夢の目覚めには、頬を伝う涙があった。
「俺が助けなければならない」御堂は水守に電話をかけた。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

特殊部隊の俺が転生すると、目の前で絶世の美人母娘が犯されそうで助けたら、とんでもないヤンデレ貴族だった
なるとし
ファンタジー
鷹取晴翔(たかとりはると)は陸上自衛隊のとある特殊部隊に所属している。だが、ある日、訓練の途中、不慮の事故に遭い、異世界に転生することとなる。
特殊部隊で使っていた武器や防具などを召喚できる特殊能力を謎の存在から授かり、目を開けたら、絶世の美女とも呼ばれる母娘が男たちによって犯されそうになっていた。
武装状態の鷹取晴翔は、持ち前の優秀な身体能力と武器を使い、その母娘と敷地にいる使用人たちを救う。
だけど、その母と娘二人は、
とおおおおんでもないヤンデレだった……
第3回次世代ファンタジーカップに出すために一部を修正して投稿したものです。


果てしなき宇宙の片隅で 序章 サラマンダー
緋熊熊五郎
SF
果てしなき宇宙の片隅で、未知の生物などが紡ぐ物語
遂に火星に到達した人類は、2035年、入植地東キャナル市北東35キロの地点で、古代宇宙文明の残滓といえる宇宙船の残骸を発見した。その宇宙船の中から古代の神話、歴史、物語とも判断がつかない断簡を発掘し、それを平易に翻訳したのが本物語の序章、サラマンダーである。サラマンダーと名付けられた由縁は、断簡を納めていた金属ケースに、羽根を持ち、火を吐く赤い竜が描かれていたことによる。


日本国転生
北乃大空
SF
女神ガイアは神族と呼ばれる宇宙管理者であり、地球を含む太陽系を管理して人類の歴史を見守ってきた。
或る日、ガイアは地球上の人類未来についてのシミュレーションを実施し、その結果は22世紀まで確実に人類が滅亡するシナリオで、何度実施しても滅亡する確率は99.999%であった。
ガイアは人類滅亡シミュレーション結果を中央管理局に提出、事態を重くみた中央管理局はガイアに人類滅亡の回避指令を出した。
その指令内容は地球人類の歴史改変で、現代地球とは別のパラレルワールド上に存在するもう一つの地球に干渉して歴史改変するものであった。
ガイアが取った歴史改変方法は、国家丸ごと転移するもので転移する国家は何と現代日本であり、その転移先は太平洋戦争開戦1年前の日本で、そこに国土ごと上書きするというものであった。
その転移先で日本が世界各国と開戦し、そこで起こる様々な出来事を超人的な能力を持つ女神と天使達の手助けで日本が覇権国家になり、人類滅亡を回避させて行くのであった。

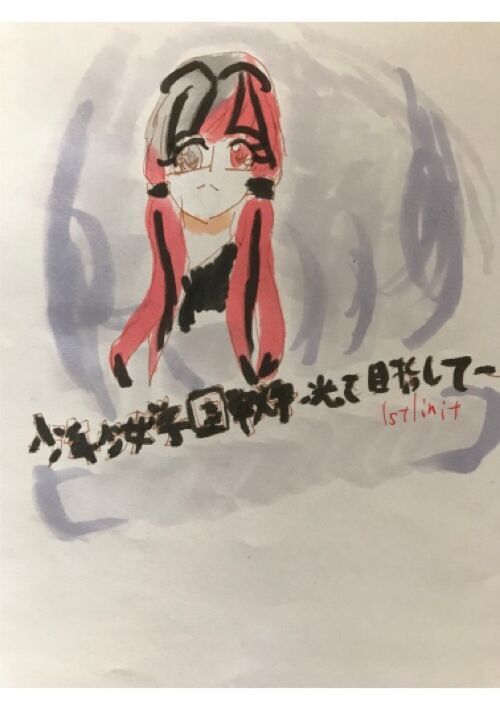
少年少女学園戦争-光を目指して-
白波光里
SF
2060年4月、令和の世も終わりつつあるが、そんな中姫川市立南光中学に入学した少女柊イズミ(ひいらぎいずみ)は同級生の越ヶ原悠司(こえがはらゆうじ)や笹原リンド(ささはらりんど)、焼美色(やきみいろ)が南光区を白姫教会(ホワイトプリンセスチャッチ)から守る為に彼ら彼女らは能力(チカラ)を手に取る!

Imposter
Primrose
SF
2026年、ある少年は未来を見通す力を持っていた。そして同時に、彼の力を狙う者もいた。少年はいままでなんとか逃げてきたが、ある少女との出会いがきっかけとなり、物語は急展開を迎える。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















