16 / 38
15
しおりを挟む
石積町は、県境の山あいにある人口7千人の小さな町だ。谷山の景色は素晴らしく、夏には登山やキャンプの客で賑わう観光地だが、冬の降雪は凄まじく、2階の窓からでないと家の外に出られない日もある。そのあまりにも酷い雪害に対応すべく、東海道新幹線の路線で唯一スプリンクラーが設置されているほどだ。
直井高校にも15年前には各学年に10人ほどの生徒が通っていたが、大雪の日は石積町管内の生徒のみ遅刻や休みが認められていた。そのせいで男子生徒の多くは、大雪が降ると高原夏美の姿が見られないことを残念がった。
しかし、直接その姿を見に訪れた男子はいただろうか? いま目の前に、彼女が育った家がある。30年以上前に分譲された、20区画のなかの1軒だ。木造2階建て建坪約30坪のこぢんまりした家で、庭も3歩進めば隣の敷地に届きそうだ。一文字葺きの屋根はサビだらけで、モルタル壁には所々ヒビが入っている。
「本当にここなのか? 表札も出てないぞ」芳田が訝しげに言った。
「たぶん間違いない。このカーナビは2年目だが、誤差はせいぜい4メートルくらいだ」そういう継人も激しい違和感を覚えていた。
制服姿の高原夏美の可憐で清楚なイメージが余りにも鮮烈すぎたせいだ。ましてや田野倉家のコンクリートの城を見たあとでは、余計にみずぼらしく見える。ただ、玄関のまえに駐まっている1台の黒いアウディだけが、周囲から浮いていた。
「本人の車かな?」芳田が社内を覗き込もうとするが、スモークフィルムが張ってあり、持ち主の性別を特定できる情報は得られそうもない。
「とにかく行ってみるしかないな」
継人はSUVを少し離れた小公園に移動して、そこから歩くことにした。お盆の最中なら、他県ナンバーでも帰省した誰かの車だと思うだろう。
むしろ怪しいのは芳田だった。物陰から襲撃者が襲って来るのを想定して、左右を見ながら時々妙な構えをしている。
「2人で行くと警戒されるかも知れん。とりあえずオレ1人で行く」
「わかった」継人が先を歩くと、芳田は拳を握りしめた。たぶん、ポケットにはナックルダスターを忍ばせているのだろう。
継人は玄関の前で大きく深呼吸をしてから、チャイムを鳴らした。
しかし、20秒経っても誰も出てくる気配はない。さらにもう1度押す。15秒が過ぎて留守かと諦めかけた、その時、カギを解錠するカチャという音が聞こえた。
「どなたですかぁ」
眠たげな女性の声とともに玄関ドアが開いていく。継人は息を呑んだ。佇まいを直し、勇気を振り絞って名乗った。
「直井高校の同級生で、同じ美術部だった栗村継人です」
涙目になりながら何とか言葉を搾り出すと、目のまえのジャージ姿の女性はキョトンとしている。
継人は落胆した表情を悟られまいと、なんとかぎこちない笑顔を作ったが、間にあわなかった。確かに旧日の面影があるといえばそんな気もするが、もしこの場に居なければ、誰も本人だと気付かないだろう。体重が大幅に増えたことを割り引いても、あまりにも残酷な変貌ぶりだった。
「ああ、夏美ならここには居ないわよ」女性は腰をボリボリ掻きながら、ドアを閉めようとする。
「あのぉ、お姉さんですか?」継人の顔がパッと明るくなった。少なくとも本人ではなかったようだ。
「そうよ。よく腹違いじゃないかって言われるけど」
姉と名乗った女性は憮然とした。勘違いをされたのは初めてではないのだろう。夏美でないことが分かって相手がホッとするのを嫌というほど見てきたに違いない。
「妹さんが何処におられるのかご存知ないですか?」
「それを知って、どうなさりたいの?」女性は身を乗り出して、外を見やった。芳田が急いで身を隠したが、すでに遅かった。「ほかにもお友達がおいでになるようだけど」
継人は頭を下げた。「すいません。決して怪しい理由じゃないんです。直接会ってお話したいだけなんです」
「まあいいわ。じゃあ夕方の6時にこの場所に来て」そう言うと、女性は下駄箱の上の樹脂ケースから名刺を2枚引っ張り出して継人に渡した。ラメ入り加工がされた紙に大きく『スナック 咲恵』、その下に『高原咲恵』とある。
「それ、源氏名じゃなくて私の本名なの。じゃあ、お連れさんにもよろしくね」
「あのぉ」継人が何か言いかけたが、手のひらを出して制した。
「はい、そこまで。太陽が高い時のバンパイアはまだ就寝中なの。話は活動時間になってからね」そう言って、高原咲恵は玄関のドアを閉めた。
継人は成す術も無く、玄関に立ちすくんだ。
車に戻ると、芳田はラメ入りの名刺をヒラヒラさせた。「弱みがあると見るや営業を仕掛けてくるとは、プロだな」
「誰かさんが顔を出さなきゃ、上手く行ってたかもしれん」
「自惚れるな。どうせカモが1人減っただけの話だ」
芳田が笑い飛ばすと、継人は舌打ちした。「でも、とりあえず糸口は掴んだ。場代を払えば妹のことも何か喋るだろう」
継人は、ハンドルをさらに西に向けた。
しばらく山間部を走ると、湖岸町に入った。ほとんどが山と谷ばかりの石積町とは違って、数十キロ先が見通せる平野部の多い町だ。近代的な工場群と古い城下町が融合した佇まいは、地方都市のかく有るべき姿を見るようで気持ちがいい。
ただ、今日は少し様子が違った。微かに琵琶湖の一部が確認できるが、真夏なのに重い雲が立ち込め、色彩を失っているように見える。市街地に背を向けるようにして伊吹山地の麓に辿り着くと、また同じような里山風景に変わった。
やがてある集落に入ったところで、芳田が「あっ」と声を上げた。
小さな集落のいちばん高台に、4軒分がまるごと入りそうな広い長屋門が見える。
「あの家だ。親父は、瓦葺きになまこ壁の大きな門が目印の家だと言ってた」
「でかいな。この辺りの大名主じゃないのか」
密集した民家群を抜けた先に姿を現わした漆喰の門は、さながら領民を見下ろす城壁のようだ。入り口には“麻倉”と薬研彫りされた檜の表札が掛けられ、その向こう側には壮麗な入母屋造りの大屋根が見える。
継人はその威容に息を呑んだ。麻倉恵子の気高さと美しさを育んだ源流がここにあるような気がした。田野倉家の邸宅が住環境の未来を指し示しているとすれば、麻倉家は歴史の記憶のなかに存在している印象すら受ける。
「ここは一緒に行こう」芳田の提案に継人も頷いた。
SUVを門の脇に駐めて、2人は中央の両開きの分厚い大扉の前に立った。芳田がその真ん中を強く押してみたが、内部から閂が掛かっておりビクともしない。
「こっちだ」継人が両脇にある潜り戸の右側にインターホンを発見し、芳田に譲った。「じゃあ頼む」
「任せろ」芳田は1度咳払いをして、ボタンを押した。
4回目のコールで、男性の声がした。
〈どちら様ですかな?〉
いかにも見識の高そうな年配者の声だ。芳田は露骨に顔をしかめると、出来るだけ丁寧な口調で続けた。
「先代のお嬢様の古い友人で、芳田と申します。現在のご当主の方とお会いしたいのですが?」
この言葉の意味が分かるのなら、何らかの反応をするはずだ。移動中に継人と打ち合わせた通りだ。
〈はて、お嬢様に該当する者はここにはおりませんが〉
「そのはずです。私たちが殺してしまったのですから」
しばらく間があった。対応を考えているのだろう。継人が小声で指示すると、芳田はさらに続けた。
「もう1人の共犯者も一緒です」
〈分かりました。とりあえず、いまお話になっている側の潜り戸からお入りなさい〉
芳田は親指を立てると、継人も同じ動作で返した。
潜り戸の鍵は最初から開いていたようだ。
2人は敷地のなかに入った瞬間、唖然とした。門の外側から見えた大屋根は近くから見ると苔だらけで、露出した野地板からは雀が出入りしている。建物のすべての窓には遮光カーテンが引かれ、土壁は所々崩れていた。400坪を超える広い庭も、瓦塀から見える高木以外の植栽は一切なく、殆どが家庭菜園と化している。
敷石の上を歩いて玄関に辿り着き、芳田がまさに引き戸に手を触れようとした瞬間、母屋の右側にある土蔵から眼鏡をかけた60歳代の男が姿を現わした。青いコットン地のワイシャツに、仕立ての良さそうなスラックスをベージュのサスペンダーで吊っている。
「そちらには誰も住んでおりませんよ」
「あっ、はい」芳田が振り返ると、蔵の入り口に一般住宅用の玄関ドアがはめ込まれているのに気が付いた。
「大きな家に1人住まいでは何かと不便が生じるものでね。土蔵を住居用にリフォームしたというわけです。どうぞこちらへ」
促されるままに2人は土蔵の中に入って、もう一度驚いた。中2階と吹き抜けを上手く融合させ、採光の取り入れが殆ど出来なくとも密閉感がない快適な空間を造り出している。となりの朽ち果てた武家屋敷とはまったく真逆のモダンな隠れ家といった風情だ。男の佇まいもその空気に溶け込んでいるように見える。
「お2人ともずいぶんお若いようにお見受けするが、どうやらご当人ではないようですな」
「父は数年前に亡くなりました」継人は苦笑しつつ、自己紹介した。「栗村と申します」
男は自嘲気味に微笑んだ。「実は、私もここの人間ではありません。元成年後見人の根乃井修一といいます」そう言ってダイニングチェアに腰掛けるようすすめた。
『成年後見人』つまり、判断能力を失った主人に代わって財産管理をする人のことだ。家庭裁判所が選任するため、肉親や親族であるとは限らない。苗字が違うところをみると、赤の他人である可能性もある。
芳田はずっと内装に見惚れてまったく喋る気配すら見せない。継人はため息をついて、先に切り出した。
「ここのご家族の方々は現在どうされているのですか?」
「誰もおりませんよ。ここ以外にも。あなた方が血脈を絶ってしまったお陰でね」根乃井はわざとらしく訂正した。「失礼。あなた方がお生まれになる前の話でしたな」
「つまり、麻倉家は断絶してしまったということですか?」
根乃井は鼻から息を漏らした。「あなた方が『先代のお嬢様』とおっしゃる麻倉恵子は、この家の当主であった麻倉一朗のひとり娘でね。麻倉家は代々流通と不動産で財を築いた地元の名士だったが、あの事件が起きたあと妻の幸子が亡くなり、一朗もその18年後に脳梗塞を患い重度の痴呆になってね。やがて事業も立ち行かなくなり、甥にあたる私が後見人に選ばれたというわけですよ」
「一朗さんにはご兄弟はいなかったんですか?」
「4人いましたかな。どれも情の薄いものばかりでね。本来なら叔父が亡くなった後に分割協議を行なって私の仕事もそこで終わるはずだったが、なんと全員が遺産を放棄したので、私が引き続き管理するはめになったわけです」
「しっかし、大変なお屋敷ですね」芳田は感嘆したように言った。「これだけの歴史ある建物なら重要文化財に指定されていてもおかしくない」
「よくご観察しておられるようだ」根井の表情が一瞬、曇った。「実際に文化庁から何度も打診はあったが、麻倉はすべて断っていましたがね」
芳田は挑発するように言った。「それは勿体ない。修理代や税金の補助なしに維持していくのは大変だったでしょう」
根乃井は鬱陶しそうに答えた。「叔父は、住環境は時代とともに変えていくものだという考えでね。改装のたびに許可を求める文化庁のやり方には私も納得できなかった。いま考えれば正しい判断だったといえるでしょうね。そもそも誰も住むことのなくなった家に手を入れる理由などないですから」
「ごもっともです」芳田はにっこり笑った。継人はその飄々とした態度が気になった。何かを掴んだ、そんな顔だ。
トゥルルルルルルルルッ
突然、携帯が鳴った。
「ちょっと失礼」根乃井は席を立って、奥の厨房まで歩いて行った。2人に背を向けたまま30秒ほど話すと、根乃井は鼻の頭を掻きながら戻って来た。「申し訳ないが、小用で出かけなければならないようだ。せっかくの機会だったのに、実に残念ですがね」
「いえ、とんでもない。こちらこそ突然の訪問で失礼しました」継人がそう言って頭を下げると、芳田もそれに続いた。
2人は再び潜り戸をぬけて外へ出た。継人はそこから見える景色に眼を奪われた。湖に立ち込めていたどんよりした雲は消え、水面はキラキラと輝いている。悠久の時の流れに翻弄されることなく、ただ静かに人間の営みを見つめ続けてきたその崇高さにあらためて圧倒された。
「諸行無常とはこのことだな」継人は溜息をついてから、エンジンをかけた。「麻倉家が完全に終わっているとは思わなかった。過去と現在が繋がっていたなんていう話は、結局オレの幼稚な妄想だったってわけだ」
「本当にそう思うか?」芳田は眉を動かした。
「ずいぶん確信ありげだな」
「じつはあの馬鹿でかい母屋の玄関を開けようとしたとき、建物の脇からブーンっていう音が聞こえたんだ。あれはエアコンか何かの室外機の音だ。間違いない」
「でもあの男は、母屋には誰も住んでないって言ってたじゃないか」
「住んでいるかいないかじゃない。問題は今も使っているかどうかだ。だからオレは登録文化財の話を持ち出してカマをかけたんだ。登録を見送った理由は一応筋は通ってるが、あの男は“誰もいない家に手を入れる理由はない”と言い切った」
「つまり、ウソをついてるってことか」
「きっと、あの屋敷の中になにか秘密があるんだ。ひょっとすると、おまえさんの言ってる糸だってあそこにあるかもしれんぞ」
直井高校にも15年前には各学年に10人ほどの生徒が通っていたが、大雪の日は石積町管内の生徒のみ遅刻や休みが認められていた。そのせいで男子生徒の多くは、大雪が降ると高原夏美の姿が見られないことを残念がった。
しかし、直接その姿を見に訪れた男子はいただろうか? いま目の前に、彼女が育った家がある。30年以上前に分譲された、20区画のなかの1軒だ。木造2階建て建坪約30坪のこぢんまりした家で、庭も3歩進めば隣の敷地に届きそうだ。一文字葺きの屋根はサビだらけで、モルタル壁には所々ヒビが入っている。
「本当にここなのか? 表札も出てないぞ」芳田が訝しげに言った。
「たぶん間違いない。このカーナビは2年目だが、誤差はせいぜい4メートルくらいだ」そういう継人も激しい違和感を覚えていた。
制服姿の高原夏美の可憐で清楚なイメージが余りにも鮮烈すぎたせいだ。ましてや田野倉家のコンクリートの城を見たあとでは、余計にみずぼらしく見える。ただ、玄関のまえに駐まっている1台の黒いアウディだけが、周囲から浮いていた。
「本人の車かな?」芳田が社内を覗き込もうとするが、スモークフィルムが張ってあり、持ち主の性別を特定できる情報は得られそうもない。
「とにかく行ってみるしかないな」
継人はSUVを少し離れた小公園に移動して、そこから歩くことにした。お盆の最中なら、他県ナンバーでも帰省した誰かの車だと思うだろう。
むしろ怪しいのは芳田だった。物陰から襲撃者が襲って来るのを想定して、左右を見ながら時々妙な構えをしている。
「2人で行くと警戒されるかも知れん。とりあえずオレ1人で行く」
「わかった」継人が先を歩くと、芳田は拳を握りしめた。たぶん、ポケットにはナックルダスターを忍ばせているのだろう。
継人は玄関の前で大きく深呼吸をしてから、チャイムを鳴らした。
しかし、20秒経っても誰も出てくる気配はない。さらにもう1度押す。15秒が過ぎて留守かと諦めかけた、その時、カギを解錠するカチャという音が聞こえた。
「どなたですかぁ」
眠たげな女性の声とともに玄関ドアが開いていく。継人は息を呑んだ。佇まいを直し、勇気を振り絞って名乗った。
「直井高校の同級生で、同じ美術部だった栗村継人です」
涙目になりながら何とか言葉を搾り出すと、目のまえのジャージ姿の女性はキョトンとしている。
継人は落胆した表情を悟られまいと、なんとかぎこちない笑顔を作ったが、間にあわなかった。確かに旧日の面影があるといえばそんな気もするが、もしこの場に居なければ、誰も本人だと気付かないだろう。体重が大幅に増えたことを割り引いても、あまりにも残酷な変貌ぶりだった。
「ああ、夏美ならここには居ないわよ」女性は腰をボリボリ掻きながら、ドアを閉めようとする。
「あのぉ、お姉さんですか?」継人の顔がパッと明るくなった。少なくとも本人ではなかったようだ。
「そうよ。よく腹違いじゃないかって言われるけど」
姉と名乗った女性は憮然とした。勘違いをされたのは初めてではないのだろう。夏美でないことが分かって相手がホッとするのを嫌というほど見てきたに違いない。
「妹さんが何処におられるのかご存知ないですか?」
「それを知って、どうなさりたいの?」女性は身を乗り出して、外を見やった。芳田が急いで身を隠したが、すでに遅かった。「ほかにもお友達がおいでになるようだけど」
継人は頭を下げた。「すいません。決して怪しい理由じゃないんです。直接会ってお話したいだけなんです」
「まあいいわ。じゃあ夕方の6時にこの場所に来て」そう言うと、女性は下駄箱の上の樹脂ケースから名刺を2枚引っ張り出して継人に渡した。ラメ入り加工がされた紙に大きく『スナック 咲恵』、その下に『高原咲恵』とある。
「それ、源氏名じゃなくて私の本名なの。じゃあ、お連れさんにもよろしくね」
「あのぉ」継人が何か言いかけたが、手のひらを出して制した。
「はい、そこまで。太陽が高い時のバンパイアはまだ就寝中なの。話は活動時間になってからね」そう言って、高原咲恵は玄関のドアを閉めた。
継人は成す術も無く、玄関に立ちすくんだ。
車に戻ると、芳田はラメ入りの名刺をヒラヒラさせた。「弱みがあると見るや営業を仕掛けてくるとは、プロだな」
「誰かさんが顔を出さなきゃ、上手く行ってたかもしれん」
「自惚れるな。どうせカモが1人減っただけの話だ」
芳田が笑い飛ばすと、継人は舌打ちした。「でも、とりあえず糸口は掴んだ。場代を払えば妹のことも何か喋るだろう」
継人は、ハンドルをさらに西に向けた。
しばらく山間部を走ると、湖岸町に入った。ほとんどが山と谷ばかりの石積町とは違って、数十キロ先が見通せる平野部の多い町だ。近代的な工場群と古い城下町が融合した佇まいは、地方都市のかく有るべき姿を見るようで気持ちがいい。
ただ、今日は少し様子が違った。微かに琵琶湖の一部が確認できるが、真夏なのに重い雲が立ち込め、色彩を失っているように見える。市街地に背を向けるようにして伊吹山地の麓に辿り着くと、また同じような里山風景に変わった。
やがてある集落に入ったところで、芳田が「あっ」と声を上げた。
小さな集落のいちばん高台に、4軒分がまるごと入りそうな広い長屋門が見える。
「あの家だ。親父は、瓦葺きになまこ壁の大きな門が目印の家だと言ってた」
「でかいな。この辺りの大名主じゃないのか」
密集した民家群を抜けた先に姿を現わした漆喰の門は、さながら領民を見下ろす城壁のようだ。入り口には“麻倉”と薬研彫りされた檜の表札が掛けられ、その向こう側には壮麗な入母屋造りの大屋根が見える。
継人はその威容に息を呑んだ。麻倉恵子の気高さと美しさを育んだ源流がここにあるような気がした。田野倉家の邸宅が住環境の未来を指し示しているとすれば、麻倉家は歴史の記憶のなかに存在している印象すら受ける。
「ここは一緒に行こう」芳田の提案に継人も頷いた。
SUVを門の脇に駐めて、2人は中央の両開きの分厚い大扉の前に立った。芳田がその真ん中を強く押してみたが、内部から閂が掛かっておりビクともしない。
「こっちだ」継人が両脇にある潜り戸の右側にインターホンを発見し、芳田に譲った。「じゃあ頼む」
「任せろ」芳田は1度咳払いをして、ボタンを押した。
4回目のコールで、男性の声がした。
〈どちら様ですかな?〉
いかにも見識の高そうな年配者の声だ。芳田は露骨に顔をしかめると、出来るだけ丁寧な口調で続けた。
「先代のお嬢様の古い友人で、芳田と申します。現在のご当主の方とお会いしたいのですが?」
この言葉の意味が分かるのなら、何らかの反応をするはずだ。移動中に継人と打ち合わせた通りだ。
〈はて、お嬢様に該当する者はここにはおりませんが〉
「そのはずです。私たちが殺してしまったのですから」
しばらく間があった。対応を考えているのだろう。継人が小声で指示すると、芳田はさらに続けた。
「もう1人の共犯者も一緒です」
〈分かりました。とりあえず、いまお話になっている側の潜り戸からお入りなさい〉
芳田は親指を立てると、継人も同じ動作で返した。
潜り戸の鍵は最初から開いていたようだ。
2人は敷地のなかに入った瞬間、唖然とした。門の外側から見えた大屋根は近くから見ると苔だらけで、露出した野地板からは雀が出入りしている。建物のすべての窓には遮光カーテンが引かれ、土壁は所々崩れていた。400坪を超える広い庭も、瓦塀から見える高木以外の植栽は一切なく、殆どが家庭菜園と化している。
敷石の上を歩いて玄関に辿り着き、芳田がまさに引き戸に手を触れようとした瞬間、母屋の右側にある土蔵から眼鏡をかけた60歳代の男が姿を現わした。青いコットン地のワイシャツに、仕立ての良さそうなスラックスをベージュのサスペンダーで吊っている。
「そちらには誰も住んでおりませんよ」
「あっ、はい」芳田が振り返ると、蔵の入り口に一般住宅用の玄関ドアがはめ込まれているのに気が付いた。
「大きな家に1人住まいでは何かと不便が生じるものでね。土蔵を住居用にリフォームしたというわけです。どうぞこちらへ」
促されるままに2人は土蔵の中に入って、もう一度驚いた。中2階と吹き抜けを上手く融合させ、採光の取り入れが殆ど出来なくとも密閉感がない快適な空間を造り出している。となりの朽ち果てた武家屋敷とはまったく真逆のモダンな隠れ家といった風情だ。男の佇まいもその空気に溶け込んでいるように見える。
「お2人ともずいぶんお若いようにお見受けするが、どうやらご当人ではないようですな」
「父は数年前に亡くなりました」継人は苦笑しつつ、自己紹介した。「栗村と申します」
男は自嘲気味に微笑んだ。「実は、私もここの人間ではありません。元成年後見人の根乃井修一といいます」そう言ってダイニングチェアに腰掛けるようすすめた。
『成年後見人』つまり、判断能力を失った主人に代わって財産管理をする人のことだ。家庭裁判所が選任するため、肉親や親族であるとは限らない。苗字が違うところをみると、赤の他人である可能性もある。
芳田はずっと内装に見惚れてまったく喋る気配すら見せない。継人はため息をついて、先に切り出した。
「ここのご家族の方々は現在どうされているのですか?」
「誰もおりませんよ。ここ以外にも。あなた方が血脈を絶ってしまったお陰でね」根乃井はわざとらしく訂正した。「失礼。あなた方がお生まれになる前の話でしたな」
「つまり、麻倉家は断絶してしまったということですか?」
根乃井は鼻から息を漏らした。「あなた方が『先代のお嬢様』とおっしゃる麻倉恵子は、この家の当主であった麻倉一朗のひとり娘でね。麻倉家は代々流通と不動産で財を築いた地元の名士だったが、あの事件が起きたあと妻の幸子が亡くなり、一朗もその18年後に脳梗塞を患い重度の痴呆になってね。やがて事業も立ち行かなくなり、甥にあたる私が後見人に選ばれたというわけですよ」
「一朗さんにはご兄弟はいなかったんですか?」
「4人いましたかな。どれも情の薄いものばかりでね。本来なら叔父が亡くなった後に分割協議を行なって私の仕事もそこで終わるはずだったが、なんと全員が遺産を放棄したので、私が引き続き管理するはめになったわけです」
「しっかし、大変なお屋敷ですね」芳田は感嘆したように言った。「これだけの歴史ある建物なら重要文化財に指定されていてもおかしくない」
「よくご観察しておられるようだ」根井の表情が一瞬、曇った。「実際に文化庁から何度も打診はあったが、麻倉はすべて断っていましたがね」
芳田は挑発するように言った。「それは勿体ない。修理代や税金の補助なしに維持していくのは大変だったでしょう」
根乃井は鬱陶しそうに答えた。「叔父は、住環境は時代とともに変えていくものだという考えでね。改装のたびに許可を求める文化庁のやり方には私も納得できなかった。いま考えれば正しい判断だったといえるでしょうね。そもそも誰も住むことのなくなった家に手を入れる理由などないですから」
「ごもっともです」芳田はにっこり笑った。継人はその飄々とした態度が気になった。何かを掴んだ、そんな顔だ。
トゥルルルルルルルルッ
突然、携帯が鳴った。
「ちょっと失礼」根乃井は席を立って、奥の厨房まで歩いて行った。2人に背を向けたまま30秒ほど話すと、根乃井は鼻の頭を掻きながら戻って来た。「申し訳ないが、小用で出かけなければならないようだ。せっかくの機会だったのに、実に残念ですがね」
「いえ、とんでもない。こちらこそ突然の訪問で失礼しました」継人がそう言って頭を下げると、芳田もそれに続いた。
2人は再び潜り戸をぬけて外へ出た。継人はそこから見える景色に眼を奪われた。湖に立ち込めていたどんよりした雲は消え、水面はキラキラと輝いている。悠久の時の流れに翻弄されることなく、ただ静かに人間の営みを見つめ続けてきたその崇高さにあらためて圧倒された。
「諸行無常とはこのことだな」継人は溜息をついてから、エンジンをかけた。「麻倉家が完全に終わっているとは思わなかった。過去と現在が繋がっていたなんていう話は、結局オレの幼稚な妄想だったってわけだ」
「本当にそう思うか?」芳田は眉を動かした。
「ずいぶん確信ありげだな」
「じつはあの馬鹿でかい母屋の玄関を開けようとしたとき、建物の脇からブーンっていう音が聞こえたんだ。あれはエアコンか何かの室外機の音だ。間違いない」
「でもあの男は、母屋には誰も住んでないって言ってたじゃないか」
「住んでいるかいないかじゃない。問題は今も使っているかどうかだ。だからオレは登録文化財の話を持ち出してカマをかけたんだ。登録を見送った理由は一応筋は通ってるが、あの男は“誰もいない家に手を入れる理由はない”と言い切った」
「つまり、ウソをついてるってことか」
「きっと、あの屋敷の中になにか秘密があるんだ。ひょっとすると、おまえさんの言ってる糸だってあそこにあるかもしれんぞ」
0
お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説
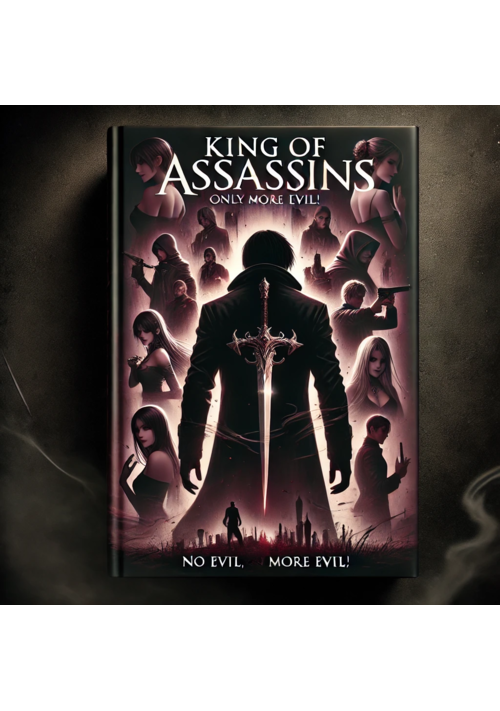

友よ、お前は何故死んだのか?
河内三比呂
ミステリー
「僕は、近いうちに死ぬかもしれない」
幼い頃からの悪友であり親友である久川洋壱(くがわよういち)から突如告げられた不穏な言葉に、私立探偵を営む進藤識(しんどうしき)は困惑し嫌な予感を覚えつつもつい流してしまう。
だが……しばらく経った頃、仕事終わりの識のもとへ連絡が入る。
それは洋壱の死の報せであった。
朝倉康平(あさくらこうへい)刑事から事情を訊かれた識はそこで洋壱の死が不可解である事、そして自分宛の手紙が発見された事を伝えられる。
悲しみの最中、朝倉から提案をされる。
──それは、捜査協力の要請。
ただの民間人である自分に何ができるのか?悩みながらも承諾した識は、朝倉とともに洋壱の死の真相を探る事になる。
──果たして、洋壱の死の真相とは一体……?

【毎日20時更新】アンメリー・オデッセイ
ユーレカ書房
ミステリー
からくり職人のドルトン氏が、何者かに殺害された。ドルトン氏の弟子のエドワードは、親方が生前大切にしていた本棚からとある本を見つける。表紙を宝石で飾り立てて中は手書きという、なにやらいわくありげなその本には、著名な作家アンソニー・ティリパットがドルトン氏とエドワードの父に宛てた中書きが記されていた。
【時と歯車の誠実な友、ウィリアム・ドルトンとアルフレッド・コーディに。 A・T】
なぜこんな本が店に置いてあったのか? 不思議に思うエドワードだったが、彼はすでにおかしな本とふたつの時計台を巡る危険な陰謀と冒険に巻き込まれていた……。
【登場人物】
エドワード・コーディ・・・・からくり職人見習い。十五歳。両親はすでに亡く、親方のドルトン氏とともに暮らしていた。ドルトン氏の死と不思議な本との関わりを探るうちに、とある陰謀の渦中に巻き込まれて町を出ることに。
ドルトン氏・・・・・・・・・エドワードの親方。優れた職人だったが、職人組合の会合に出かけた帰りに何者かによって射殺されてしまう。
マードック船長・・・・・・・商船〈アンメリー号〉の船長。町から逃げ出したエドワードを船にかくまい、船員として雇う。
アーシア・リンドローブ・・・マードック船長の親戚の少女。古書店を開くという夢を持っており、謎の本を持て余していたエドワードを助ける。
アンソニー・ティリパット・・著名な作家。エドワードが見つけた『セオとブラン・ダムのおはなし』の作者。実は、地方領主を務めてきたレイクフィールド家の元当主。故人。
クレイハー氏・・・・・・・・ティリパット氏の甥。とある目的のため、『セオとブラン・ダムのおはなし』を探している。

学園ミステリ~桐木純架
よなぷー
ミステリー
・絶世の美貌で探偵を自称する高校生、桐木純架。しかし彼は重度の奇行癖の持ち主だった! 相棒・朱雀楼路は彼に振り回されつつ毎日を過ごす。
そんな二人の前に立ち塞がる数々の謎。
血の涙を流す肖像画、何者かに折られるチョーク、喫茶店で奇怪な行動を示す老人……。
新感覚学園ミステリ風コメディ、ここに開幕。
『小説家になろう』でも公開されています――が、検索除外設定です。


幻影のアリア
葉羽
ミステリー
天才高校生探偵の神藤葉羽は、幼馴染の望月彩由美と共に、とある古時計のある屋敷を訪れる。その屋敷では、不可解な事件が頻発しており、葉羽は事件の真相を解き明かすべく、推理を開始する。しかし、屋敷には奇妙な力が渦巻いており、葉羽は次第に現実と幻想の境目が曖昧になっていく。果たして、葉羽は事件の謎を解き明かし、屋敷から無事に脱出できるのか?

パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。

ラストグリーン
桜庭かなめ
恋愛
「つばさくん、だいすき」
蓮見翼は10年前に転校した少女・有村咲希の夢を何度も見ていた。それは幼なじみの朝霧明日香も同じだった。いつか咲希とまた会いたいと思い続けながらも会うことはなく、2人は高校3年生に。
しかし、夏の始まりに突如、咲希が翼と明日香のクラスに転入してきたのだ。そして、咲希は10年前と同じく、再会してすぐに翼に好きだと伝え頬にキスをした。それをきっかけに、彼らの物語が動き始める。
20世紀最後の年度に生まれた彼らの高校最後の夏は、平成最後の夏。
恋、進路、夢。そして、未来。様々なことに悩みながらも前へと進む甘く、切なく、そして爽やかな学園青春ラブストーリー。
※完結しました!(2020.8.25)
※お気に入り登録や感想をお待ちしています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















