1 / 4
兄弟
しおりを挟む
護院 清方は車から降りると古いマンションを見上げた。ここに本当に探していた、彼の兄がいるのだろうか?恋人、成瀬 雫の部下 良岑 貴之の情報は間違っていた事がない。
日曜日の午前10時。普通のサラリーマンの彼は自分の部屋にいる筈だ。梅雨時期のどんよりした曇り空の下、清方はマンションの入口へと歩き出した。
「あの…それで、弟の事って…どこにいるのですか?」
彼は戸惑いながらも、清方を部屋へ入れた。
本庄 真也、本庄 直也の3歳上の兄だ。
「直也君はアメリカである誘拐事件に関与して保護されました。現在は私が嘱託を勤める病院で入院しています」
「誘拐事件?入院?弟は…直也は病気なんですか?」
「順を追って説明します。直也君を最後に買い取った人間は医師でした。その医師は彼を人体実験に使用した挙げ句に、誘拐事件の手助けに利用されたのです」
真也は清方の言葉に震えた。本庄家はそれなりの家格を持った家だった。戦後の高度成長期に先代が興した企業がかなり成功し一角の資産家になっていた。直也は幼い頃から優秀で祖父のお気に入りだった事から、紫霄学院の中等部に編入させられ期待に応えて特待生になった。ところが直也の編入の数ヶ月後、祖父が倒れて寝た切りになった。もとより余り折り合いが良くなかった兄弟の父親が仕方なく企業を継いだ。そこで景気が一気に悪化した。経験もやる気もない社長の下で、会社が踏みとどまれる訳もなく倒産。先祖伝来の家屋敷から別荘などを処分したが、なおも数億円の借財が残った。
そのタイミングで多々良 正恒の事件が起こったのだ。被害者の一人である直也は、紫霄を退学して両親の元へ帰った。これまでの生活と真逆な古く狭いアパートでの暮らしに。それでも借金の取り立ては来る。お坊ちゃん育ちの父親もお嬢さん育ちの母親も貧しさに勝てなかった。佐田川の誘いに乗ってしまったのだ。
直也は競売にかけられ、その金で借金は返済された。僅かばかり残った金で、両親は山奥に古い民家を購入して、今も自ら田畑を耕して暮らしている。
真也は途中から両親と別れ、アルバイトと奨学金で高校と大学を卒業、現在は小さな商社に勤めている。
「真也君は過酷な環境に、心を蝕まれてしまっています。彼を従わせる為に投与された薬剤の影響で、現在も強い幻覚や神経系統の異常を引き起こしています」
直也が無気力、無感情から回復してから出現した症状は、どこか武の発作と似て来ていた。
「あの…それで今日は…?弟の治療費でしたら、僕にも両親にも到底用意出来ません」
真也が受けた奨学金は返済するタイプで、それと日々の生活で精一杯だった。
「いえ、入院費などは今までと同じく、ある方々が出される事になっています」
入院費や治療費はアメリカにいる麗以外の第81代生徒会のメンバーが全面的に支払っていた。帰国後、夕麿が武の許可を得て身元引受に復帰。清方が主治医として、精神疾患の治療に当たっている。直也は現在、内臓にもトラブルを抱えていた為、内科的な治療も併用されていた。だがここで限界に突き当たった。発作を起こした武の為のデータ集めにも、直也に対してもっと細かい検査が必要になり、内臓疾患の手術が必要となった。
確かに身元引受の夕麿のサインでもそれらは行える。だが直也の家族が生存している限り、法律上はその許可が必要とされるのだ。直也は治療の結果、現在、感情を取り戻しつつある。家族の誰かが面会する事で、更なる回復が考えられた。
そういった事情を真也に説明する。
「両親ではなく、私にですか?」
「申し訳ありませんがご両親は一度、直也君を金銭に変える味を知っています。現在の生活状況から判断しても、また何だかの形で金銭を得ようとされる可能性が判断されました」
全てを失って慎ましい生活をしてはいる。だが彼らはその生活を抜けて、元の生活を取り戻す幻想を捨てていなかった。それは真也がよく知っている事だった。
「両親は…直也を売った事を後悔はしています。でも有り得ない幻想も持っているのです。直也が裕福な人物の元で幸せになって、いつか自分たちを助けてくれるかもしれないと…」
夕麿たちが耳にしたら怒るだろう。実の両親に売られた直也は自分を救い出してくれる、誰かはいないと一切を諦めて生きていたのだ。だからこそかつての想い人に、夕麿に執着し幻想を抱いた。自分は彼の身代わりとして売られ、それを知った夕麿が救い出してくれる。当然ながら夕麿は雫が事件の資料などから、直也が売られた事情を知って知らせるまで、何も知らなかったし居所も知りようがなかった。
「では私は何をすればよろしいのでしょうか」
「まずは直也君の治療費を払っている、かつての同級生の方々と会っていただきます。その上で彼と面会して欲しいのです」
真也が兄として精神的な意味で弟を救いたいと望むかどうかの判断が欲しいと清方は思っていた。もし彼に肉親としての情が認められないならば、別の方法を模索しなければならない。検査の承諾ならば夕麿のサインでも構わない。しかし清方は直也を治療したいのだ、医師として。
「私は勤めを休む事は出来ません。土・日しか都合がつかないのですが、それで構わないなら…弟に会いたいです」
幾分、戸惑いながら真也は答えた。無理もない、事件から10年以上の時間が流れていた。突然に見知らぬ医師が訪ねて来て、弟の現状を知らされたのだ。当惑して当たり前だ。
「では土・日の都合が良い日をお知らせください」
考える時間を与えよう。
清方はそう考えていた。 もしこのまま彼から連絡が来なくても仕方がない事だ。 誰も責める事は出来ない。 直也の事は彼には、一つの心の傷になっている筈だ。 だから彼は両親から離れて、自力で学校を卒業して一人で生活してる。
今回の件は最初、雫と貴之が来る事を望んだ。二人は警察官としての訪問の方が、真也が受け入れると考えたからだ。しかしそれは清方が拒否した。真也を強制的に動かす事になる。それでは直也に面会する事が義務になる。真也が自分で弟の現状を理解して、決断しなければ意味はないのだ。出来れば彼に弟の治療に協力して欲しい。
それにはもう一つ理由があった。感情を取り戻しつつある直也は、性嗜好異常障害を示し始めたのだ。男性色情症と呼ばれるもので、しかも直也はドン・ファン型と呼ばれる特定の人間に異常な性衝動反応を示していた。
直也にとって特別な人間とはかつての片想いの相手である夕麿だった。小柄な直也が夕麿を犯そうとする。その事実は今のところ武にだけは秘密にしてある。知れば武が激怒して、病院から追い出す可能性もあるからだ。
サチリアジスは基本的に治療法はない。直也の場合、原因は彼が性的な事を強制され続けた結果と判断される。夕麿の身代わりとなる事で想いを貫く。恋しい人の身代わりが事実であってもなくても、直也には関係がなかった筈だ。ただそれを信じる事で、自分がおかれた境遇に耐えた。縋って耐えるしか道がなかったのだ。
精神疾患と投与された薬剤による脳障害が引き起こしたものであった。
数日後、真也から連絡が入り次の日曜日の午後に面会する予定になった。
病院の受付で清方と待ち合わせ、特別病棟の応接室へ案内した。病院の一角には似つかわしくない部屋に真也は中を見回した。部屋の中には義勝と雅久がいた。二人は真也を見て立ち上がった。それぞれが挨拶を交わし、ソファをすすめられた。
雅久が立ち上がって、お茶の用意を始めた。
「あの…まだ始めないのですか?」
「他の方々がまだこちらに来られていないです」
約束の時間が守られない。真也はその事に苛立っていた。
「申し訳ありません、本庄さん。前の予定がずれたらしく今、こちらへ向かっていると連絡が入ってますのでもう少しお待ちください」
雅久がお茶を出しながら、謝罪の言葉を口にした。余裕を持ったスケジュールを組んでおいたのに、相手方の都合で時間がずれ込んだらしい。3人は貴之の指示で、空いている道を急いでいるらしい。
雅久の携帯が鳴った。3人が到着した連絡だった。
「まもなく上がって来られます」
その言葉通りに数分後、ドアが叩かれた。雅久が立ち上がって開け、まず貴之が入室し榊が入った。全員が立ち上がるのを見て、真也もそれに従った。全員が頭を垂れる中、夕麿が入って来た。清方が席に案内し彼が座るのを待って全員が順番に座った。
真也とて身分ある一族の出身。これが何を意味するのか、わからない訳ではない。彼は夕麿の顔を知っている気がした。
「あの、間違いでしたらお許しください。六条 夕麿さまであらしゃいますか?」
直也が帰宅する度に、紫霄の同級生たちの写真を見せてくれた。その中で好きな人だと言って、夕麿の写真を特別大切にしていたのだ。あの写真の面影がある。そう思ったから尋ねてみた。『あらしゃる』などという貴族言葉も、ずっと使った事がなかった。
夕麿は真也の問いかけに微笑んだ。
「はい、六条 夕麿です。現在は御園生姓になっています」
「え?」
真也が弟から聞いたのでは、夕麿は六条家の嫡男だった筈だ。何故、姓が変わっている?
「自己紹介をお願いいたします」
見かねた清方が口を開いた。
「では、私から」
雅久が夕麿の前に紅茶を置いて顔を上げた。
「御園生 雅久と申します。現在、御園生ホールディングスで経営者ルームの秘書長をいたしております」
直也が『天から舞い降りた』と表現していた同級生、それが彼だと理解する。
「御園生 義勝です。現在、この病院で精神科の研修医として勤務しています」
白衣の理由を納得する。
「良岑 貴之です。現在、警察省に所属しております」
「天羽 榊です。御園生ホールディングスで夕麿さまの専属秘書をしてます」
確かに彼らには昔見せられた、直也の同級生の写真の面影があった。
「あともう二人特待生の同級生がおりますが、直也君の事に関わっておりません」
貴之が言った。そこへ周と保、脳神経科医が来た。彼らも武の治療に関わっている為、状態の説明や今後の計画について話に加わる。
「彼らは直也君の治療を行う医師たちです。まず、脳神経科医の呉羽都志樹副院長。その隣が外科医の慈園院 保先生。そして総合医の久我 周先生です」
呉羽医師は以前は大学病院の医局長だった人物で、現在はこの病院の副院長を務めている。有人の高校時代の友人の一人でもある。まだ新米医師である義勝と周には良い教師だった。
「副院長、説明を御願いします」
「うむ」
レントゲン写真を示しながら、現在の直也の状態を呉羽は説明していく。
次第に真也の顔から血の気が引いていく。直也は内臓にかなりの問題を抱えていた。薬剤の人体実験を行われた時の副作用と、ストレスの双方が原因だと考えられた。
「まずは肝臓の手術を行います。執刀は慈園院先生がされます。彼は若いですがUCLAで学ばれた後、メディカルセンターで研鑽を詰まれた名医です」
呉羽はここで手術の承諾書を提示した。さすがにこれには真也は素直にサインをした。
「手術と脳障害の治療の為、徹底した精密検査を行う必要があります。何分にも同じ状態の方は、世界中を探しても3人しかいません」
「弟の他にも同じ目にあった人がいるのですか!?」
それは真也を驚かせるには十分だった。
「一人は…俺たちの弟だ」
義勝が搾り出すように言った。
「ロサンジェルスで誘拐されたのはその方なのです」
貴之が言葉を継いだ。
「もう一人はアメリカで収監されています。また、使用した医師もアメリカで逮捕されましたが、裁判中に自らの生命を絶ちました」
かつての紫霄学院高等部校医 佐久間 章雄は、何も語らず記録も残さずに死んだ。薬剤の出所である研究者も行方不明になっていた。清方たちが手に入れたのは、研究者が残していたデータだけだった。しかし直也のように長時間続けて投与された例や、武のように致死量の半分以上を一度に投与された例は存在してはいない。脳障害を起こした例も存在してはいない。研究者が残した成分表と二人が投与された薬剤は、アメリカでの分析結果によると違う部分がある。
「弟の治療の為だけに私たちは御願いしている訳ではありません」
雅久が身を乗り出すようにして言った。
「俺たちにとって本庄君は大切な同級生です」
義勝が言った。
「直也は、弟は中等部に1年数ヶ月在校していただけです。あんな事件があって…いなくなった者に、何ゆえにそこまでされるのですか?私から見たら弟さんの為だけに感じるのですが?」
彼らが弟と呼ぶ人間の為に、直也が再び人体実験されるのではないのか。真也は言外にそれを匂わせていた。
「私も…あの事件の被害者の一人です。またここにいらっしゃる慈園院 保さんの弟さんも被害者でした」
搾り出すような声で言葉を吐いて夕麿は唇を噛み締めた。保も俯いて拳を握り締めた。
「弟の司は高等部卒業後に…恋人と心中しました」
確かに武を治療したい。彼らにとっては切なる願いだ。だがそれだけならば身元引き受けを今更、肉親に求めなくても良い方法は幾らでもある。実の兄と対面させて精神面の治療など考えずに、実験体扱いも出来たのだ。だが夕麿たちは直也にも普通の生活が出来るように、自分の人生を歩いて行ける様になって欲しかったのだ。
特に夕麿はそう思っていた。
「わかりました……」
あの事件の被害者にこれ以上、不幸になって欲しくない。全員の居所がわからないだけに、せめて直也を社会に出られるようにまで回復させたい。
彼らのそんな想いが真也にもヒシヒシと伝わって来た。夕麿が六条家から出たのも、あの事件が原因かもしれない。細かい事情を何も知らない彼はとっさにそう思った。
夕麿は今、幸せなのだろうか?巨大企業の経営陣に名を連ねる地位にいる事と、人間として幸せかどうかは別物であると、両親の浅はかな生き方から真也はそう思うようになった。女系とはいえ皇家の血を引く彼に、そこまで踏み入った質問は出来ない。ただ幸せであって欲しいと思った。
「では、直也君に面会していただきます」
全員が立ち上がった。普段、直也への面会は許可されていない。真也以外にも直也の状態を見る機会は少ないのだ。
「夕麿、お前は残れ」
「ですが…周さん、この状態で私だけ残るわけにはいきません」
「仕方ないな。貴之、もしもの時はお前の役目だ」
「承知しました」
このやり取りの意味がわからずに、真也はそっと首を捻った。
直也はどちらかというとおとなしい患者だと言える。隔離病棟に収容されてはいるが、主治医の許可があれば面会室での対面が可能であった。本来ならば多人数が一度に面会するのは良い事ではない。ただ今回は清方と義勝が同席し、警察官である貴之もいるという事で精神科の主任医師から許可が出た。
精神科病棟の一角にある、本来は治療の為の接見室がこの為に用意された、臨時の待合室となった。部屋には椅子も机も何も置かれてはいない。
真也はこの異様な光景に戸惑った。特別病棟のものまでは想像してはいなかったが、何もないとは思ってはいなかったのだ。
他の者は一度は経験しているので無言で立っていた。
貴之と榊は後ろに夕麿を庇うようにしていた。
そこへ看護師が直也を連れて来た。彼はどことなく虚ろな表情で入って来た。清方が彼の肩を抱いて真也の方へ連れて来た。
「直也」
名前を呼ばれて顔を上げる。直也は元々綺麗な顔立ちだったが、長い間閉じ込められている為か透けるような白い肌で、艶やかな面差しに成長していた。身長は170cmに少し届かない。1年ほど前から食欲が回復傾向にあり、内臓に問題を抱えている割には元気だ。
「直也」
真也はもう一度名前を呼んで弟の肩に手を乗せた。 すると直也は真也の顔をじっと見詰めた。
「直也君、あなたのお兄さんの真也さんですよ?」
「………兄さん?」
言葉の意味がわからないのか、それとも10数年会っていない肉親の顔が判別出来ないのか、直也は小首を傾げて呟いた。
「そうです、あなたのお兄さんです」
「兄さん…」
「直也!」
耐えかねた真也が弟を抱き締めた。無事とは言えないけれども兎に角生きていてくれた。真也にはそれが嬉しかった。
「僕…頑張ったよ…」
「ああ、よく頑張った」
もっと気の利いた言葉を口にしたいのに、胸が一杯で言葉にならない。二度と会えないと思っていた。既に生きてはいないとも思っていた。この病院に何年も入院して、治療を受けていたという事実。連絡をもらえなかった事情も説明された。
もっと早く会いたかった。想いのたけを込めて抱き締めると、直也も躊躇いがちに兄の上着を握った。
全員から安堵の溜息が漏れた。退院は無理ではあっても、直也を肉親の手に返せたのだ。
誰もがホッと胸を撫で下ろした時だった。不意に直也が兄を突き飛ばし、くるりと別な方向を見た。そこには夕麿が立っていた。
「六条さま…六条さま…」
何かに憑かれたかのように信じられない力で、止める手を振り払い夕麿に突進して行く。
「貴之、止めろ!」
義勝の声と貴之が動いたのはほぼ同時だった。夕麿に向かって伸ばされた腕を取り後ろにねじ上げる。直也はさすがに痛みに反応して絶叫する。
「嫌だぁ…六条さま…放せ…六条さま!」
夕麿は蒼褪めた顔で言葉もなく立ち尽くしていた。
「何をされるんです!? 弟を放してください」
「それは出来ません。放せば彼は夕麿さまに襲い掛かる。ここがどこであるとか、他に人がいる事を考えられなくなるのです。
雅久君、夕麿さまと外へ」
「はい」
雅久が夕麿を連れて外へ出た。ドアに施錠されたのを確認して貴之が直也を解放した。その瞬間、直也はドアに体当たりを始めた。全ての壁にクッションが入れられている為、幾らぶつかっても怪我をする事はない。それでも夕麿を呼んで体当たりを続ける光景は異様だった。
「ダメですね、清方先生。カウンセリングも投薬も、やはりサチリアジスは治療不可なのでしょうか」
「時間をかけて緩和出来た例はあります。そこに希望を持ちたいのですが」
義勝と清方の会話の内容が真也にはまるでわからない。
「どういうことですか」
二人に詰め寄る。
「サチリアジスというのは男性の色情症の事です。直也君はドン・ファン型と呼ばれるタイプだと判断出来ます」
「ドン・ファン型は特定の人間に異常な執着を持つんです。本庄…直也君は昔、夕麿が好きだった。それに縋って生きてきたんだと思う。だから…ロサンジェルスで再会した時から、彼は夕麿への執着を見せていました」
「そんな…」
「だから僕は夕麿を帰そうとしたのに」
周がうんざりした顔で言った。
「夕麿さまはそれでも、本庄君の状態をお確かめになられたかったのでしょう」
今でも夕麿を想い、異常な行動に出る。真也は弟が憐れになった。こんなにまで夕麿を想っているのに、それが叶えられれば…直也の症状も快方に向かうのではないか。そう思ってしまう。
夕麿にその気がないのは何となくわかる。それでも何とかならないのかと思ってしまう。まさか身分が高い彼に頼む事は出来ない。けれども直也がこんな状態であっても気にしてくれている。夕麿のそんな優しさに、真也は期待したくなっていた。
直也との面会を終わって解散をした後、清方は少し後悔していた。やはり夕麿と真也を会わせるべきではなかったと。彼が夕麿をじっと見ていたのが気になる。真也は弟を守れなかった事で心に傷を負っている。今のような状態の直也を見て、何とか助けたい、正常な生活が出来るようにしたいとそう思った筈だ。
夕麿に対して特別な執着を示す弟の姿を見て、その願いを叶える事が治療の早道だと思う可能性がある。
清方は夕麿に真也が面会を求めて来た時には、特別病棟の面会室を指定するように指示した。どんなに請われても絶対に、病院の外では会ってはならないと告げた。
直也との面会は夕麿がいた場合は許可しないように、精神科病棟のナースや医師に徹底させる事にした。
直也の治療は医師としての責任をかけて、全力で行うつもりである。だがその前に一番に考えなければならないのは紫霞宮夫妻の安全である。本来医療行為に身分差は持ち込んではならない建前がある。だがそれは一般的な医師にのみ要求されるべきだ。
清方は紫霞宮武王に忠誠を誓っている。臣下としても、侍医の一人としても、忠義を尽くす意味では彼らを一番にする。皇家に仕える者としての倫理観はそこにあった。
それでも真也が夕麿に関わりを求めるのは避けられないだろう。
武を怒らせないように。
二人が傷付かないように。
義勝とその辺を配慮しなければならないと、その日の遅くまで話し合った。
直也の治療をしたい。日常の当たり前の生活に戻してやりたい。願いは全員の共通のものだった。真也という肉親が見付かった事も嬉しいと思う。けれどそれと夕麿の事は別の話だ。
第一、精神疾患の治療は誰かを犠牲にして行うものじゃない。身内の都合で進めるべきものではないのだ。
サチリアジスは性嗜好障害の一種である。精神疾患に分類はされてはいるが、治療が難しい事で知られている。かつて同性愛者すら性嗜好障害症に分類されていた時代がある事でもその実情がうかがえる。古い考えの人間には未だに、治療すれば同性愛が治ると信じている者がいるのは、そのような経歴が存在するからだ。
性嗜好障害パラフィリアには様々な種類がある。SMもロリコンやショタコンもその一種ではある。当人が自身の性的嗜好に葛藤や苦痛を持たず日常生活に支障がない。当人が葛藤や苦痛を持っていても、第三者や社会秩序にとって脅威や問題がない場合。もしくは双方を含む場合は精神疾患と分類しない事になっている。
ただし当人にとって何ら問題がなくても、その性的嗜好が具体的に第三者に被害を及ぼしたり、社会秩序を混乱させるような事態は精神疾患として考えられる。
直也の状態はこれに当てはまるのだ。性嗜好障害は治療が難しいか、不可能な場合が多い。他の精神疾患と一緒になっている場合が多く、影に隠れている時もあり発見が困難な場合もある。
サチリアジスには不特定多数との性交渉を繰り返すカサノヴァ型と、特定の人間に固執するドン・ファン型とに分類される。近年問題のストーカーなどは、このドン・ファン型になる。
直也の場合は隔離病棟に収容されている為、ストーキング行為は不可能だ。それが原因か他にも要因が存在するのかは不明であるが、夕麿の姿を見ると直情的に行動してしまう。
ロサンゼルスでUCLAのメディカル・センターに収容されていた時は夕麿に縋るくらいの状態だった。皇国に連れ帰って加療を進めて、少しずつ感情を取り戻すにつれて、夕麿への執着がそれまで以上に強くなっている。周囲に目もくれず、夕麿だけを狙って突進する。
一度、その勢いに押されて夕麿が尻餅を着き、そのまま襲いかかった事があったのだ。慌てて看護師たちが引き離したが、泣き叫んで暴れまわった。夕麿もショックで完治した筈のパニック発作を起こしかけた。
命令に従ったら夕麿を与えるという、ロサンゼルスで佐久間 章雄が、直也ともう一人に与えた言葉が今も彼の中で生きているのかもしれない。
褒美として夕麿を与えられる……感情が欲望と結び付いて、夕麿をそういう意味で手に入れようとする。ゆえに安全の為、ずっと夕麿はモニター越しに観察するだけになっていた。
今回、代表者としての夕麿が真也と会わない訳には行かなかった。本来は直也との面会は避けるつもりだった。しかし夕麿の優しさや責任感がそれを許さなかったのだ。そして予想通りの行動に直也は出た。
清方にすれば頭が痛い事だった。
面会のしばらく後で直也が発作を起こしたと連絡が来た。武との違いは四肢の麻痺は起こすが、声を失う事はない…という事だった。また麻痺の状態も違っていた。本庄 直也は痛覚や触覚まで失うのだ。もっと精密な検査をしてみないとわからないが、長期間の投与による脳のダメージが、武よりも広範囲であると予想されていた。
佐久間 章雄が直也一人だけでなく、武の同級生だった板倉 正巳も利用したのは、恐らく以前から発作を起こしていたからではないか。そう考えると納得出来る部分があった。
これから何をどう進めて行くべきなのか。夕麿を守り武に過剰反応させない配慮はどうすれば良いのか。帰宅してもそれが頭から離れない。
「…ッ!」
不意に背後から抱き締められた。
「いつまで俺はお預けされなきゃダメなんだ?」
「あ…すみません」
清方にも守秘義務がある。だから何も問わない。それでも愛する者が思い悩むのを少しでも癒したい。言葉を紡げないならば身体を繋げて癒す。
今日はいつになく清方が神経質になっている。職業は違っても、そういう状態に陥る状況は見当がつく。帰宅して着替えもせずに座り込んでずっと考え込んでいる間に、雫はバスタブに湯を張り着替えまで用意した。入浴剤代わりに入れたのは、以前に武からもらったイランイランだ。
「肩のマッサージしてやるから入浴しよう」
「おや、珍しいですね?もっともあなたのマッサージとやらは、別な意味に聞こえますけど?」
「ん?俺はそんな事は言ってないぞ?だがそんな風に言われると期待に応えなきゃならんな」
清方の耳元で嬉しそうな声がする。
「困った人ですね、あなたは。どうしてそんなにエロいんです?」
「そりゃ決まってんだろ?感じてる時のお前がエロいからだ」
カッと頬が熱くなる。
「私の所為にしないでください」
俯いて言うと後ろから忍び笑いが漏れる。
本当に憎たらしい。けれどもそんなところも愛しいと感じる。清方は返事の代わりに、背後の雫に唇を重ねた。
「あッ…そ、そんなに…ン…そこ…ばっかり…」
「いやじゃないだろ?こんなに紅く色付かせて」
バスタブの中で後ろ抱きにされて、首筋や肩に口付けされながら、ずっと乳首を愛撫され続けていた。刺激を与えられ続けたそこはジンジンと痺れて、ちょっとした刺激でも痛いくらい感じる。雫はそれがわかっていて抗いを口にした罰とばかりに、一度に両方を摘まんでやや強めに引っ張った。
「ああッ!あッ!イヤぁ!」
悲鳴を上げて仰け反る。
「雫…雫…お願いです…も…ベッドへ…」
30歳半ばへ差し掛かる清方には、さすがにバスルームでの行為は体力的に無理がある。雫は清方を抱いてパウダールームへ出た。口付けを交わしながら、簡単に水気を拭ってバスローブを着た。横抱きにして寝室に入り、キングサイズのベッドに壊れ物を扱うように横たえた。
「明日、休みだろ?」
「そうですが…それが何か?」
「俺も非番だ」
雫はそう言うと意味ありげに笑った。
「今夜は覚悟するんだな」
「あなたという人は…わかりました」
ベッドに移動して少し冷静になった清方が、エロ丸出しの雫の態度に苦笑する。起き上がって自分を覗き込んでいる雫の首に腕を回して、誘うような妖艶な笑みを浮かべて告げた。
「では今夜は私がしてあげます」
「ほう…何をしてくれるんだ?」
「あなたはベッドに寝ているだけで構いませんよ?」
「それは楽しみだな」
雫は笑いながら清方の傍らに横たわった。その上に清方は跨って、バスローブの紐を解いた。よく鍛えられた身体が露になる。愛しげに目を細めて撫で回す。
「くすぐったい」
不平をもらすのが憎たらしい。
「可愛くありませんね、雫。犯しますよ?」
「おいおい、それは勘弁してくれ」
彼のギョッとした顔に満足したのか、清方が声を上げて笑った。周が夕麿への想いを終わらせたあの日、共に清方や雫との関係も終わらせた。ゆえに清方は誰かを抱く事はしていない。ひたすらに雫に抱かれる事を歓んだ。
「ふふ、冗談ですよ」
笑いながらその胸に唇を寄せた。ゆっくりずり下がり、欲望に勃っているモノに唇を寄せた。
「ああ、もう…こんなに大きい…」
手で触れながら口付けを繰り返す。
「不思議ですね。こんな大きなモノが、いつも私の中に入ってるなんて…」
口を一杯一杯に開けてソレを含んだ。
「ン…ぁふ…」
普段スーツに身を包んでクールな医師の顔をしている清方が、舌を絡めて懸命に口淫する姿は余りのも扇情的だ。けれどもどんなに淫らな姿を露にしても、彼が本来持ち合わせている気品は少しも損なわれない。
清方と離れていた10数年間、二度と逢えないと思っていた。だから胸の痛みと狂惜しいまでに求めてしまう面影を忘れたくて、誘いをかけてくる女性と手当たり次第に付き合った。 関係を持った相手も結構な数になる。
今こうして最愛の者を取り戻してみるとその誰もが、気品でも淫らさでも清方の足元にも及ばなかったと感じてしまう。
「清方、もう挿れたい」
柔らかでありながら強く締め付ける、淫らな中を早く味わいたい。抱き締めても抱き締めても、満たされながらも足りない。愛しさが強くて矛盾した想いを持ってしまう。女性と付き合っている時には、終ぞ感じた事がない感覚だった。
「もう少し…待ってくださいね…」
十分でジェルを塗り込む声が、欲望に掠れているのがたまらない。美しい面差しが紅潮して、匂わんばかりの色香を溢れさせていた。白い肌は30代半ばだというのに、再会した時から少しも衰えてはいない。艶やかで美しく妖しい。
付き合った女性の中にはかなりの美女がいた。けれど清方の美しさの方が遥かに上だと思ってしまう。ぞっこんに惚れている欲目だと言われても反論は出来ないが、それでも彼は美しいのだと言いたくなる。
「雫…」
ジェルを塗り込む行為が欲望を駆り立てたのか、唇の紅さが艶かしく輝いている。思わず喉を鳴らす雫に微笑んで、清方は蕾を自らあてがってゆっくりと腰を沈めていく。
「ぁあッ…はッ…凄い…くる…ああ…」
自らの内側を開いていくモノに陶酔するように、淫らに開いた唇から言葉が紡がれる。
「全部…入った…」
雫の胸に手を着いて、熱く乱した息を吐く。
「今日は淫らだな」
「嫌いじゃないでしょう?」
「むしろ俺の好みだ……そろそろ動いて欲しいんだがな」
そう言って軽く突き上げると、清方の中が収縮した。
「はぁッ!ダメ…今日は…私が…ああッ…雫…そ…激し…あン…」
嬌声を上げながら淫らに腰を振る。
「くッ…本当に…たちが悪いくらい今日は…締まるな。持ってイかれそうだ」
思わず呟いた雫の言葉に、我が意を得たりとでも言わんが如く妖艶に笑う。
「くそッ!」
好いように煽られて我慢が出来なくなった雫は、身を起こして抱き締めるとそのまま反転した。愛しい者の白い身体を組み敷くと更に欲望が募る。
「我慢…足らない…人…ね」
「煩い、言ってろ」
両脚を抱え挙げて繋がりを深くする。
「ああ…雫…あッああッ…」
与えられる快楽の強さに、引き千切りそうな強さで枕を掴む。
「ひぁ…あン…あッああ…ン…はぁ…」
「清方…悦いか?」
「イイ…雫…雫は…?」
「ああ、悦い…悦過ぎて…もちそうにない」
「イって…私の中に出して…」
切なげに言う清方も限界に近い様子だった。
「雫…イく…も…イくう…ああああッ!!」
「清方…!」
大きく仰け反って吐精した清方の中の収縮に、雫も引き込まれるように体内に迸らせた。
「あ…ああ…熱い…雫…」
うっとりと陶酔した面持ちで清方が呟いた。雫は覆い被さりながらそれを見て微笑む。
「雫、愛してます」
「ああ、俺も愛している」
何万回繰り返してもまだ足らない。どれほど求め合ってもまだ欲しい。二人はひとしきり見詰め合ってから、唇をどちらからともなく重ねた。
日曜日の午前10時。普通のサラリーマンの彼は自分の部屋にいる筈だ。梅雨時期のどんよりした曇り空の下、清方はマンションの入口へと歩き出した。
「あの…それで、弟の事って…どこにいるのですか?」
彼は戸惑いながらも、清方を部屋へ入れた。
本庄 真也、本庄 直也の3歳上の兄だ。
「直也君はアメリカである誘拐事件に関与して保護されました。現在は私が嘱託を勤める病院で入院しています」
「誘拐事件?入院?弟は…直也は病気なんですか?」
「順を追って説明します。直也君を最後に買い取った人間は医師でした。その医師は彼を人体実験に使用した挙げ句に、誘拐事件の手助けに利用されたのです」
真也は清方の言葉に震えた。本庄家はそれなりの家格を持った家だった。戦後の高度成長期に先代が興した企業がかなり成功し一角の資産家になっていた。直也は幼い頃から優秀で祖父のお気に入りだった事から、紫霄学院の中等部に編入させられ期待に応えて特待生になった。ところが直也の編入の数ヶ月後、祖父が倒れて寝た切りになった。もとより余り折り合いが良くなかった兄弟の父親が仕方なく企業を継いだ。そこで景気が一気に悪化した。経験もやる気もない社長の下で、会社が踏みとどまれる訳もなく倒産。先祖伝来の家屋敷から別荘などを処分したが、なおも数億円の借財が残った。
そのタイミングで多々良 正恒の事件が起こったのだ。被害者の一人である直也は、紫霄を退学して両親の元へ帰った。これまでの生活と真逆な古く狭いアパートでの暮らしに。それでも借金の取り立ては来る。お坊ちゃん育ちの父親もお嬢さん育ちの母親も貧しさに勝てなかった。佐田川の誘いに乗ってしまったのだ。
直也は競売にかけられ、その金で借金は返済された。僅かばかり残った金で、両親は山奥に古い民家を購入して、今も自ら田畑を耕して暮らしている。
真也は途中から両親と別れ、アルバイトと奨学金で高校と大学を卒業、現在は小さな商社に勤めている。
「真也君は過酷な環境に、心を蝕まれてしまっています。彼を従わせる為に投与された薬剤の影響で、現在も強い幻覚や神経系統の異常を引き起こしています」
直也が無気力、無感情から回復してから出現した症状は、どこか武の発作と似て来ていた。
「あの…それで今日は…?弟の治療費でしたら、僕にも両親にも到底用意出来ません」
真也が受けた奨学金は返済するタイプで、それと日々の生活で精一杯だった。
「いえ、入院費などは今までと同じく、ある方々が出される事になっています」
入院費や治療費はアメリカにいる麗以外の第81代生徒会のメンバーが全面的に支払っていた。帰国後、夕麿が武の許可を得て身元引受に復帰。清方が主治医として、精神疾患の治療に当たっている。直也は現在、内臓にもトラブルを抱えていた為、内科的な治療も併用されていた。だがここで限界に突き当たった。発作を起こした武の為のデータ集めにも、直也に対してもっと細かい検査が必要になり、内臓疾患の手術が必要となった。
確かに身元引受の夕麿のサインでもそれらは行える。だが直也の家族が生存している限り、法律上はその許可が必要とされるのだ。直也は治療の結果、現在、感情を取り戻しつつある。家族の誰かが面会する事で、更なる回復が考えられた。
そういった事情を真也に説明する。
「両親ではなく、私にですか?」
「申し訳ありませんがご両親は一度、直也君を金銭に変える味を知っています。現在の生活状況から判断しても、また何だかの形で金銭を得ようとされる可能性が判断されました」
全てを失って慎ましい生活をしてはいる。だが彼らはその生活を抜けて、元の生活を取り戻す幻想を捨てていなかった。それは真也がよく知っている事だった。
「両親は…直也を売った事を後悔はしています。でも有り得ない幻想も持っているのです。直也が裕福な人物の元で幸せになって、いつか自分たちを助けてくれるかもしれないと…」
夕麿たちが耳にしたら怒るだろう。実の両親に売られた直也は自分を救い出してくれる、誰かはいないと一切を諦めて生きていたのだ。だからこそかつての想い人に、夕麿に執着し幻想を抱いた。自分は彼の身代わりとして売られ、それを知った夕麿が救い出してくれる。当然ながら夕麿は雫が事件の資料などから、直也が売られた事情を知って知らせるまで、何も知らなかったし居所も知りようがなかった。
「では私は何をすればよろしいのでしょうか」
「まずは直也君の治療費を払っている、かつての同級生の方々と会っていただきます。その上で彼と面会して欲しいのです」
真也が兄として精神的な意味で弟を救いたいと望むかどうかの判断が欲しいと清方は思っていた。もし彼に肉親としての情が認められないならば、別の方法を模索しなければならない。検査の承諾ならば夕麿のサインでも構わない。しかし清方は直也を治療したいのだ、医師として。
「私は勤めを休む事は出来ません。土・日しか都合がつかないのですが、それで構わないなら…弟に会いたいです」
幾分、戸惑いながら真也は答えた。無理もない、事件から10年以上の時間が流れていた。突然に見知らぬ医師が訪ねて来て、弟の現状を知らされたのだ。当惑して当たり前だ。
「では土・日の都合が良い日をお知らせください」
考える時間を与えよう。
清方はそう考えていた。 もしこのまま彼から連絡が来なくても仕方がない事だ。 誰も責める事は出来ない。 直也の事は彼には、一つの心の傷になっている筈だ。 だから彼は両親から離れて、自力で学校を卒業して一人で生活してる。
今回の件は最初、雫と貴之が来る事を望んだ。二人は警察官としての訪問の方が、真也が受け入れると考えたからだ。しかしそれは清方が拒否した。真也を強制的に動かす事になる。それでは直也に面会する事が義務になる。真也が自分で弟の現状を理解して、決断しなければ意味はないのだ。出来れば彼に弟の治療に協力して欲しい。
それにはもう一つ理由があった。感情を取り戻しつつある直也は、性嗜好異常障害を示し始めたのだ。男性色情症と呼ばれるもので、しかも直也はドン・ファン型と呼ばれる特定の人間に異常な性衝動反応を示していた。
直也にとって特別な人間とはかつての片想いの相手である夕麿だった。小柄な直也が夕麿を犯そうとする。その事実は今のところ武にだけは秘密にしてある。知れば武が激怒して、病院から追い出す可能性もあるからだ。
サチリアジスは基本的に治療法はない。直也の場合、原因は彼が性的な事を強制され続けた結果と判断される。夕麿の身代わりとなる事で想いを貫く。恋しい人の身代わりが事実であってもなくても、直也には関係がなかった筈だ。ただそれを信じる事で、自分がおかれた境遇に耐えた。縋って耐えるしか道がなかったのだ。
精神疾患と投与された薬剤による脳障害が引き起こしたものであった。
数日後、真也から連絡が入り次の日曜日の午後に面会する予定になった。
病院の受付で清方と待ち合わせ、特別病棟の応接室へ案内した。病院の一角には似つかわしくない部屋に真也は中を見回した。部屋の中には義勝と雅久がいた。二人は真也を見て立ち上がった。それぞれが挨拶を交わし、ソファをすすめられた。
雅久が立ち上がって、お茶の用意を始めた。
「あの…まだ始めないのですか?」
「他の方々がまだこちらに来られていないです」
約束の時間が守られない。真也はその事に苛立っていた。
「申し訳ありません、本庄さん。前の予定がずれたらしく今、こちらへ向かっていると連絡が入ってますのでもう少しお待ちください」
雅久がお茶を出しながら、謝罪の言葉を口にした。余裕を持ったスケジュールを組んでおいたのに、相手方の都合で時間がずれ込んだらしい。3人は貴之の指示で、空いている道を急いでいるらしい。
雅久の携帯が鳴った。3人が到着した連絡だった。
「まもなく上がって来られます」
その言葉通りに数分後、ドアが叩かれた。雅久が立ち上がって開け、まず貴之が入室し榊が入った。全員が立ち上がるのを見て、真也もそれに従った。全員が頭を垂れる中、夕麿が入って来た。清方が席に案内し彼が座るのを待って全員が順番に座った。
真也とて身分ある一族の出身。これが何を意味するのか、わからない訳ではない。彼は夕麿の顔を知っている気がした。
「あの、間違いでしたらお許しください。六条 夕麿さまであらしゃいますか?」
直也が帰宅する度に、紫霄の同級生たちの写真を見せてくれた。その中で好きな人だと言って、夕麿の写真を特別大切にしていたのだ。あの写真の面影がある。そう思ったから尋ねてみた。『あらしゃる』などという貴族言葉も、ずっと使った事がなかった。
夕麿は真也の問いかけに微笑んだ。
「はい、六条 夕麿です。現在は御園生姓になっています」
「え?」
真也が弟から聞いたのでは、夕麿は六条家の嫡男だった筈だ。何故、姓が変わっている?
「自己紹介をお願いいたします」
見かねた清方が口を開いた。
「では、私から」
雅久が夕麿の前に紅茶を置いて顔を上げた。
「御園生 雅久と申します。現在、御園生ホールディングスで経営者ルームの秘書長をいたしております」
直也が『天から舞い降りた』と表現していた同級生、それが彼だと理解する。
「御園生 義勝です。現在、この病院で精神科の研修医として勤務しています」
白衣の理由を納得する。
「良岑 貴之です。現在、警察省に所属しております」
「天羽 榊です。御園生ホールディングスで夕麿さまの専属秘書をしてます」
確かに彼らには昔見せられた、直也の同級生の写真の面影があった。
「あともう二人特待生の同級生がおりますが、直也君の事に関わっておりません」
貴之が言った。そこへ周と保、脳神経科医が来た。彼らも武の治療に関わっている為、状態の説明や今後の計画について話に加わる。
「彼らは直也君の治療を行う医師たちです。まず、脳神経科医の呉羽都志樹副院長。その隣が外科医の慈園院 保先生。そして総合医の久我 周先生です」
呉羽医師は以前は大学病院の医局長だった人物で、現在はこの病院の副院長を務めている。有人の高校時代の友人の一人でもある。まだ新米医師である義勝と周には良い教師だった。
「副院長、説明を御願いします」
「うむ」
レントゲン写真を示しながら、現在の直也の状態を呉羽は説明していく。
次第に真也の顔から血の気が引いていく。直也は内臓にかなりの問題を抱えていた。薬剤の人体実験を行われた時の副作用と、ストレスの双方が原因だと考えられた。
「まずは肝臓の手術を行います。執刀は慈園院先生がされます。彼は若いですがUCLAで学ばれた後、メディカルセンターで研鑽を詰まれた名医です」
呉羽はここで手術の承諾書を提示した。さすがにこれには真也は素直にサインをした。
「手術と脳障害の治療の為、徹底した精密検査を行う必要があります。何分にも同じ状態の方は、世界中を探しても3人しかいません」
「弟の他にも同じ目にあった人がいるのですか!?」
それは真也を驚かせるには十分だった。
「一人は…俺たちの弟だ」
義勝が搾り出すように言った。
「ロサンジェルスで誘拐されたのはその方なのです」
貴之が言葉を継いだ。
「もう一人はアメリカで収監されています。また、使用した医師もアメリカで逮捕されましたが、裁判中に自らの生命を絶ちました」
かつての紫霄学院高等部校医 佐久間 章雄は、何も語らず記録も残さずに死んだ。薬剤の出所である研究者も行方不明になっていた。清方たちが手に入れたのは、研究者が残していたデータだけだった。しかし直也のように長時間続けて投与された例や、武のように致死量の半分以上を一度に投与された例は存在してはいない。脳障害を起こした例も存在してはいない。研究者が残した成分表と二人が投与された薬剤は、アメリカでの分析結果によると違う部分がある。
「弟の治療の為だけに私たちは御願いしている訳ではありません」
雅久が身を乗り出すようにして言った。
「俺たちにとって本庄君は大切な同級生です」
義勝が言った。
「直也は、弟は中等部に1年数ヶ月在校していただけです。あんな事件があって…いなくなった者に、何ゆえにそこまでされるのですか?私から見たら弟さんの為だけに感じるのですが?」
彼らが弟と呼ぶ人間の為に、直也が再び人体実験されるのではないのか。真也は言外にそれを匂わせていた。
「私も…あの事件の被害者の一人です。またここにいらっしゃる慈園院 保さんの弟さんも被害者でした」
搾り出すような声で言葉を吐いて夕麿は唇を噛み締めた。保も俯いて拳を握り締めた。
「弟の司は高等部卒業後に…恋人と心中しました」
確かに武を治療したい。彼らにとっては切なる願いだ。だがそれだけならば身元引き受けを今更、肉親に求めなくても良い方法は幾らでもある。実の兄と対面させて精神面の治療など考えずに、実験体扱いも出来たのだ。だが夕麿たちは直也にも普通の生活が出来るように、自分の人生を歩いて行ける様になって欲しかったのだ。
特に夕麿はそう思っていた。
「わかりました……」
あの事件の被害者にこれ以上、不幸になって欲しくない。全員の居所がわからないだけに、せめて直也を社会に出られるようにまで回復させたい。
彼らのそんな想いが真也にもヒシヒシと伝わって来た。夕麿が六条家から出たのも、あの事件が原因かもしれない。細かい事情を何も知らない彼はとっさにそう思った。
夕麿は今、幸せなのだろうか?巨大企業の経営陣に名を連ねる地位にいる事と、人間として幸せかどうかは別物であると、両親の浅はかな生き方から真也はそう思うようになった。女系とはいえ皇家の血を引く彼に、そこまで踏み入った質問は出来ない。ただ幸せであって欲しいと思った。
「では、直也君に面会していただきます」
全員が立ち上がった。普段、直也への面会は許可されていない。真也以外にも直也の状態を見る機会は少ないのだ。
「夕麿、お前は残れ」
「ですが…周さん、この状態で私だけ残るわけにはいきません」
「仕方ないな。貴之、もしもの時はお前の役目だ」
「承知しました」
このやり取りの意味がわからずに、真也はそっと首を捻った。
直也はどちらかというとおとなしい患者だと言える。隔離病棟に収容されてはいるが、主治医の許可があれば面会室での対面が可能であった。本来ならば多人数が一度に面会するのは良い事ではない。ただ今回は清方と義勝が同席し、警察官である貴之もいるという事で精神科の主任医師から許可が出た。
精神科病棟の一角にある、本来は治療の為の接見室がこの為に用意された、臨時の待合室となった。部屋には椅子も机も何も置かれてはいない。
真也はこの異様な光景に戸惑った。特別病棟のものまでは想像してはいなかったが、何もないとは思ってはいなかったのだ。
他の者は一度は経験しているので無言で立っていた。
貴之と榊は後ろに夕麿を庇うようにしていた。
そこへ看護師が直也を連れて来た。彼はどことなく虚ろな表情で入って来た。清方が彼の肩を抱いて真也の方へ連れて来た。
「直也」
名前を呼ばれて顔を上げる。直也は元々綺麗な顔立ちだったが、長い間閉じ込められている為か透けるような白い肌で、艶やかな面差しに成長していた。身長は170cmに少し届かない。1年ほど前から食欲が回復傾向にあり、内臓に問題を抱えている割には元気だ。
「直也」
真也はもう一度名前を呼んで弟の肩に手を乗せた。 すると直也は真也の顔をじっと見詰めた。
「直也君、あなたのお兄さんの真也さんですよ?」
「………兄さん?」
言葉の意味がわからないのか、それとも10数年会っていない肉親の顔が判別出来ないのか、直也は小首を傾げて呟いた。
「そうです、あなたのお兄さんです」
「兄さん…」
「直也!」
耐えかねた真也が弟を抱き締めた。無事とは言えないけれども兎に角生きていてくれた。真也にはそれが嬉しかった。
「僕…頑張ったよ…」
「ああ、よく頑張った」
もっと気の利いた言葉を口にしたいのに、胸が一杯で言葉にならない。二度と会えないと思っていた。既に生きてはいないとも思っていた。この病院に何年も入院して、治療を受けていたという事実。連絡をもらえなかった事情も説明された。
もっと早く会いたかった。想いのたけを込めて抱き締めると、直也も躊躇いがちに兄の上着を握った。
全員から安堵の溜息が漏れた。退院は無理ではあっても、直也を肉親の手に返せたのだ。
誰もがホッと胸を撫で下ろした時だった。不意に直也が兄を突き飛ばし、くるりと別な方向を見た。そこには夕麿が立っていた。
「六条さま…六条さま…」
何かに憑かれたかのように信じられない力で、止める手を振り払い夕麿に突進して行く。
「貴之、止めろ!」
義勝の声と貴之が動いたのはほぼ同時だった。夕麿に向かって伸ばされた腕を取り後ろにねじ上げる。直也はさすがに痛みに反応して絶叫する。
「嫌だぁ…六条さま…放せ…六条さま!」
夕麿は蒼褪めた顔で言葉もなく立ち尽くしていた。
「何をされるんです!? 弟を放してください」
「それは出来ません。放せば彼は夕麿さまに襲い掛かる。ここがどこであるとか、他に人がいる事を考えられなくなるのです。
雅久君、夕麿さまと外へ」
「はい」
雅久が夕麿を連れて外へ出た。ドアに施錠されたのを確認して貴之が直也を解放した。その瞬間、直也はドアに体当たりを始めた。全ての壁にクッションが入れられている為、幾らぶつかっても怪我をする事はない。それでも夕麿を呼んで体当たりを続ける光景は異様だった。
「ダメですね、清方先生。カウンセリングも投薬も、やはりサチリアジスは治療不可なのでしょうか」
「時間をかけて緩和出来た例はあります。そこに希望を持ちたいのですが」
義勝と清方の会話の内容が真也にはまるでわからない。
「どういうことですか」
二人に詰め寄る。
「サチリアジスというのは男性の色情症の事です。直也君はドン・ファン型と呼ばれるタイプだと判断出来ます」
「ドン・ファン型は特定の人間に異常な執着を持つんです。本庄…直也君は昔、夕麿が好きだった。それに縋って生きてきたんだと思う。だから…ロサンジェルスで再会した時から、彼は夕麿への執着を見せていました」
「そんな…」
「だから僕は夕麿を帰そうとしたのに」
周がうんざりした顔で言った。
「夕麿さまはそれでも、本庄君の状態をお確かめになられたかったのでしょう」
今でも夕麿を想い、異常な行動に出る。真也は弟が憐れになった。こんなにまで夕麿を想っているのに、それが叶えられれば…直也の症状も快方に向かうのではないか。そう思ってしまう。
夕麿にその気がないのは何となくわかる。それでも何とかならないのかと思ってしまう。まさか身分が高い彼に頼む事は出来ない。けれども直也がこんな状態であっても気にしてくれている。夕麿のそんな優しさに、真也は期待したくなっていた。
直也との面会を終わって解散をした後、清方は少し後悔していた。やはり夕麿と真也を会わせるべきではなかったと。彼が夕麿をじっと見ていたのが気になる。真也は弟を守れなかった事で心に傷を負っている。今のような状態の直也を見て、何とか助けたい、正常な生活が出来るようにしたいとそう思った筈だ。
夕麿に対して特別な執着を示す弟の姿を見て、その願いを叶える事が治療の早道だと思う可能性がある。
清方は夕麿に真也が面会を求めて来た時には、特別病棟の面会室を指定するように指示した。どんなに請われても絶対に、病院の外では会ってはならないと告げた。
直也との面会は夕麿がいた場合は許可しないように、精神科病棟のナースや医師に徹底させる事にした。
直也の治療は医師としての責任をかけて、全力で行うつもりである。だがその前に一番に考えなければならないのは紫霞宮夫妻の安全である。本来医療行為に身分差は持ち込んではならない建前がある。だがそれは一般的な医師にのみ要求されるべきだ。
清方は紫霞宮武王に忠誠を誓っている。臣下としても、侍医の一人としても、忠義を尽くす意味では彼らを一番にする。皇家に仕える者としての倫理観はそこにあった。
それでも真也が夕麿に関わりを求めるのは避けられないだろう。
武を怒らせないように。
二人が傷付かないように。
義勝とその辺を配慮しなければならないと、その日の遅くまで話し合った。
直也の治療をしたい。日常の当たり前の生活に戻してやりたい。願いは全員の共通のものだった。真也という肉親が見付かった事も嬉しいと思う。けれどそれと夕麿の事は別の話だ。
第一、精神疾患の治療は誰かを犠牲にして行うものじゃない。身内の都合で進めるべきものではないのだ。
サチリアジスは性嗜好障害の一種である。精神疾患に分類はされてはいるが、治療が難しい事で知られている。かつて同性愛者すら性嗜好障害症に分類されていた時代がある事でもその実情がうかがえる。古い考えの人間には未だに、治療すれば同性愛が治ると信じている者がいるのは、そのような経歴が存在するからだ。
性嗜好障害パラフィリアには様々な種類がある。SMもロリコンやショタコンもその一種ではある。当人が自身の性的嗜好に葛藤や苦痛を持たず日常生活に支障がない。当人が葛藤や苦痛を持っていても、第三者や社会秩序にとって脅威や問題がない場合。もしくは双方を含む場合は精神疾患と分類しない事になっている。
ただし当人にとって何ら問題がなくても、その性的嗜好が具体的に第三者に被害を及ぼしたり、社会秩序を混乱させるような事態は精神疾患として考えられる。
直也の状態はこれに当てはまるのだ。性嗜好障害は治療が難しいか、不可能な場合が多い。他の精神疾患と一緒になっている場合が多く、影に隠れている時もあり発見が困難な場合もある。
サチリアジスには不特定多数との性交渉を繰り返すカサノヴァ型と、特定の人間に固執するドン・ファン型とに分類される。近年問題のストーカーなどは、このドン・ファン型になる。
直也の場合は隔離病棟に収容されている為、ストーキング行為は不可能だ。それが原因か他にも要因が存在するのかは不明であるが、夕麿の姿を見ると直情的に行動してしまう。
ロサンゼルスでUCLAのメディカル・センターに収容されていた時は夕麿に縋るくらいの状態だった。皇国に連れ帰って加療を進めて、少しずつ感情を取り戻すにつれて、夕麿への執着がそれまで以上に強くなっている。周囲に目もくれず、夕麿だけを狙って突進する。
一度、その勢いに押されて夕麿が尻餅を着き、そのまま襲いかかった事があったのだ。慌てて看護師たちが引き離したが、泣き叫んで暴れまわった。夕麿もショックで完治した筈のパニック発作を起こしかけた。
命令に従ったら夕麿を与えるという、ロサンゼルスで佐久間 章雄が、直也ともう一人に与えた言葉が今も彼の中で生きているのかもしれない。
褒美として夕麿を与えられる……感情が欲望と結び付いて、夕麿をそういう意味で手に入れようとする。ゆえに安全の為、ずっと夕麿はモニター越しに観察するだけになっていた。
今回、代表者としての夕麿が真也と会わない訳には行かなかった。本来は直也との面会は避けるつもりだった。しかし夕麿の優しさや責任感がそれを許さなかったのだ。そして予想通りの行動に直也は出た。
清方にすれば頭が痛い事だった。
面会のしばらく後で直也が発作を起こしたと連絡が来た。武との違いは四肢の麻痺は起こすが、声を失う事はない…という事だった。また麻痺の状態も違っていた。本庄 直也は痛覚や触覚まで失うのだ。もっと精密な検査をしてみないとわからないが、長期間の投与による脳のダメージが、武よりも広範囲であると予想されていた。
佐久間 章雄が直也一人だけでなく、武の同級生だった板倉 正巳も利用したのは、恐らく以前から発作を起こしていたからではないか。そう考えると納得出来る部分があった。
これから何をどう進めて行くべきなのか。夕麿を守り武に過剰反応させない配慮はどうすれば良いのか。帰宅してもそれが頭から離れない。
「…ッ!」
不意に背後から抱き締められた。
「いつまで俺はお預けされなきゃダメなんだ?」
「あ…すみません」
清方にも守秘義務がある。だから何も問わない。それでも愛する者が思い悩むのを少しでも癒したい。言葉を紡げないならば身体を繋げて癒す。
今日はいつになく清方が神経質になっている。職業は違っても、そういう状態に陥る状況は見当がつく。帰宅して着替えもせずに座り込んでずっと考え込んでいる間に、雫はバスタブに湯を張り着替えまで用意した。入浴剤代わりに入れたのは、以前に武からもらったイランイランだ。
「肩のマッサージしてやるから入浴しよう」
「おや、珍しいですね?もっともあなたのマッサージとやらは、別な意味に聞こえますけど?」
「ん?俺はそんな事は言ってないぞ?だがそんな風に言われると期待に応えなきゃならんな」
清方の耳元で嬉しそうな声がする。
「困った人ですね、あなたは。どうしてそんなにエロいんです?」
「そりゃ決まってんだろ?感じてる時のお前がエロいからだ」
カッと頬が熱くなる。
「私の所為にしないでください」
俯いて言うと後ろから忍び笑いが漏れる。
本当に憎たらしい。けれどもそんなところも愛しいと感じる。清方は返事の代わりに、背後の雫に唇を重ねた。
「あッ…そ、そんなに…ン…そこ…ばっかり…」
「いやじゃないだろ?こんなに紅く色付かせて」
バスタブの中で後ろ抱きにされて、首筋や肩に口付けされながら、ずっと乳首を愛撫され続けていた。刺激を与えられ続けたそこはジンジンと痺れて、ちょっとした刺激でも痛いくらい感じる。雫はそれがわかっていて抗いを口にした罰とばかりに、一度に両方を摘まんでやや強めに引っ張った。
「ああッ!あッ!イヤぁ!」
悲鳴を上げて仰け反る。
「雫…雫…お願いです…も…ベッドへ…」
30歳半ばへ差し掛かる清方には、さすがにバスルームでの行為は体力的に無理がある。雫は清方を抱いてパウダールームへ出た。口付けを交わしながら、簡単に水気を拭ってバスローブを着た。横抱きにして寝室に入り、キングサイズのベッドに壊れ物を扱うように横たえた。
「明日、休みだろ?」
「そうですが…それが何か?」
「俺も非番だ」
雫はそう言うと意味ありげに笑った。
「今夜は覚悟するんだな」
「あなたという人は…わかりました」
ベッドに移動して少し冷静になった清方が、エロ丸出しの雫の態度に苦笑する。起き上がって自分を覗き込んでいる雫の首に腕を回して、誘うような妖艶な笑みを浮かべて告げた。
「では今夜は私がしてあげます」
「ほう…何をしてくれるんだ?」
「あなたはベッドに寝ているだけで構いませんよ?」
「それは楽しみだな」
雫は笑いながら清方の傍らに横たわった。その上に清方は跨って、バスローブの紐を解いた。よく鍛えられた身体が露になる。愛しげに目を細めて撫で回す。
「くすぐったい」
不平をもらすのが憎たらしい。
「可愛くありませんね、雫。犯しますよ?」
「おいおい、それは勘弁してくれ」
彼のギョッとした顔に満足したのか、清方が声を上げて笑った。周が夕麿への想いを終わらせたあの日、共に清方や雫との関係も終わらせた。ゆえに清方は誰かを抱く事はしていない。ひたすらに雫に抱かれる事を歓んだ。
「ふふ、冗談ですよ」
笑いながらその胸に唇を寄せた。ゆっくりずり下がり、欲望に勃っているモノに唇を寄せた。
「ああ、もう…こんなに大きい…」
手で触れながら口付けを繰り返す。
「不思議ですね。こんな大きなモノが、いつも私の中に入ってるなんて…」
口を一杯一杯に開けてソレを含んだ。
「ン…ぁふ…」
普段スーツに身を包んでクールな医師の顔をしている清方が、舌を絡めて懸命に口淫する姿は余りのも扇情的だ。けれどもどんなに淫らな姿を露にしても、彼が本来持ち合わせている気品は少しも損なわれない。
清方と離れていた10数年間、二度と逢えないと思っていた。だから胸の痛みと狂惜しいまでに求めてしまう面影を忘れたくて、誘いをかけてくる女性と手当たり次第に付き合った。 関係を持った相手も結構な数になる。
今こうして最愛の者を取り戻してみるとその誰もが、気品でも淫らさでも清方の足元にも及ばなかったと感じてしまう。
「清方、もう挿れたい」
柔らかでありながら強く締め付ける、淫らな中を早く味わいたい。抱き締めても抱き締めても、満たされながらも足りない。愛しさが強くて矛盾した想いを持ってしまう。女性と付き合っている時には、終ぞ感じた事がない感覚だった。
「もう少し…待ってくださいね…」
十分でジェルを塗り込む声が、欲望に掠れているのがたまらない。美しい面差しが紅潮して、匂わんばかりの色香を溢れさせていた。白い肌は30代半ばだというのに、再会した時から少しも衰えてはいない。艶やかで美しく妖しい。
付き合った女性の中にはかなりの美女がいた。けれど清方の美しさの方が遥かに上だと思ってしまう。ぞっこんに惚れている欲目だと言われても反論は出来ないが、それでも彼は美しいのだと言いたくなる。
「雫…」
ジェルを塗り込む行為が欲望を駆り立てたのか、唇の紅さが艶かしく輝いている。思わず喉を鳴らす雫に微笑んで、清方は蕾を自らあてがってゆっくりと腰を沈めていく。
「ぁあッ…はッ…凄い…くる…ああ…」
自らの内側を開いていくモノに陶酔するように、淫らに開いた唇から言葉が紡がれる。
「全部…入った…」
雫の胸に手を着いて、熱く乱した息を吐く。
「今日は淫らだな」
「嫌いじゃないでしょう?」
「むしろ俺の好みだ……そろそろ動いて欲しいんだがな」
そう言って軽く突き上げると、清方の中が収縮した。
「はぁッ!ダメ…今日は…私が…ああッ…雫…そ…激し…あン…」
嬌声を上げながら淫らに腰を振る。
「くッ…本当に…たちが悪いくらい今日は…締まるな。持ってイかれそうだ」
思わず呟いた雫の言葉に、我が意を得たりとでも言わんが如く妖艶に笑う。
「くそッ!」
好いように煽られて我慢が出来なくなった雫は、身を起こして抱き締めるとそのまま反転した。愛しい者の白い身体を組み敷くと更に欲望が募る。
「我慢…足らない…人…ね」
「煩い、言ってろ」
両脚を抱え挙げて繋がりを深くする。
「ああ…雫…あッああッ…」
与えられる快楽の強さに、引き千切りそうな強さで枕を掴む。
「ひぁ…あン…あッああ…ン…はぁ…」
「清方…悦いか?」
「イイ…雫…雫は…?」
「ああ、悦い…悦過ぎて…もちそうにない」
「イって…私の中に出して…」
切なげに言う清方も限界に近い様子だった。
「雫…イく…も…イくう…ああああッ!!」
「清方…!」
大きく仰け反って吐精した清方の中の収縮に、雫も引き込まれるように体内に迸らせた。
「あ…ああ…熱い…雫…」
うっとりと陶酔した面持ちで清方が呟いた。雫は覆い被さりながらそれを見て微笑む。
「雫、愛してます」
「ああ、俺も愛している」
何万回繰り返してもまだ足らない。どれほど求め合ってもまだ欲しい。二人はひとしきり見詰め合ってから、唇をどちらからともなく重ねた。
0
お気に入りに追加
20
あなたにおすすめの小説

初恋はおしまい
佐治尚実
BL
高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。
高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。
※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。
今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。


鬼上司と秘密の同居
なの
BL
恋人に裏切られ弱っていた会社員の小沢 海斗(おざわ かいと)25歳
幼馴染の悠人に助けられ馴染みのBARへ…
そのまま酔い潰れて目が覚めたら鬼上司と呼ばれている浅井 透(あさい とおる)32歳の部屋にいた…
いったい?…どうして?…こうなった?
「お前は俺のそばに居ろ。黙って愛されてればいい」
スパダリ、イケメン鬼上司×裏切られた傷心海斗は幸せを掴むことができるのか…
性描写には※を付けております。


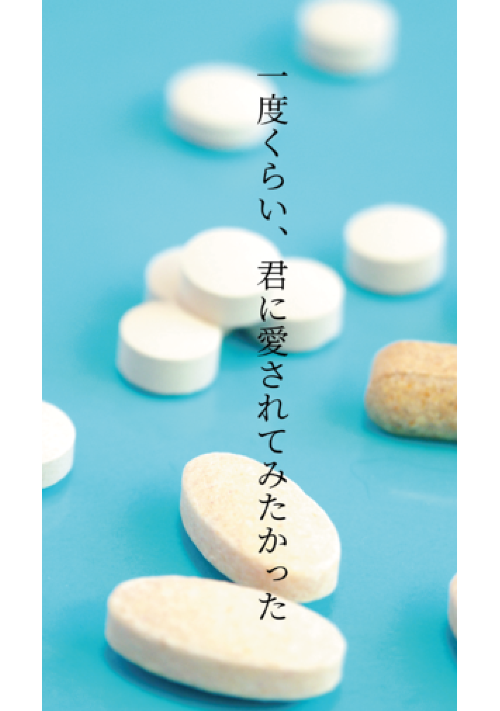

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















