お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説
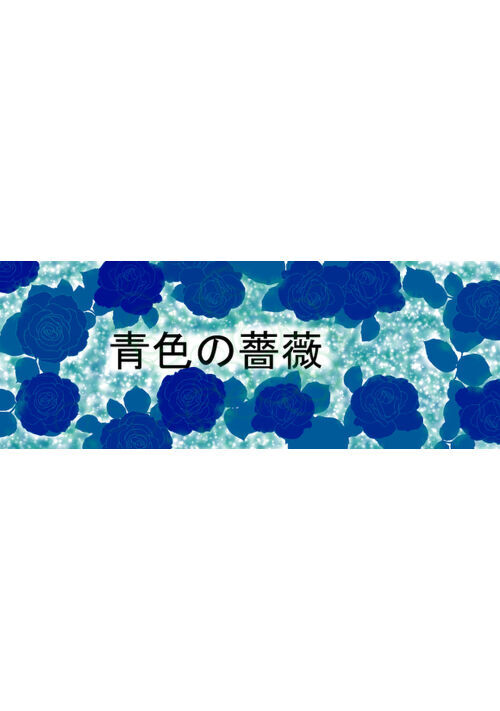
青色の薔薇
キハ
青春
栄生は小学6年生。自分の将来の夢がない。
しかし、クラスメイトは夢がある。
将来の夢をテーマにした学園物語。
6年生の始業式から始まるので、小学生時代を思い出したい方にはオススメです。
恋愛や友情も入っています!

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

隣人の女性がDVされてたから助けてみたら、なぜかその人(年下の女子大生)と同棲することになった(なんで?)
チドリ正明@不労所得発売中!!
青春
マンションの隣の部屋から女性の悲鳴と男性の怒鳴り声が聞こえた。
主人公 時田宗利(ときたむねとし)の判断は早かった。迷わず訪問し時間を稼ぎ、確証が取れた段階で警察に通報。DV男を現行犯でとっちめることに成功した。
ちっぽけな勇気と小心者が持つ単なる親切心でやった宗利は日常に戻る。
しかし、しばらくして宗時は見覚えのある女性が部屋の前にしゃがみ込んでいる姿を発見した。
その女性はDVを受けていたあの時の隣人だった。
「頼れる人がいないんです……私と一緒に暮らしてくれませんか?」
これはDVから女性を守ったことで始まる新たな恋物語。

全力でおせっかいさせていただきます。―私はツンで美形な先輩の食事係―
入海月子
青春
佐伯優は高校1年生。カメラが趣味。ある日、高校の屋上で出会った超美形の先輩、久住遥斗にモデルになってもらうかわりに、彼の昼食を用意する約束をした。
遥斗はなぜか学校に住みついていて、衣食は女生徒からもらったものでまかなっていた。その報酬とは遥斗に抱いてもらえるというもの。
本当なの?遥斗が気になって仕方ない優は――。
優が薄幸の遥斗を笑顔にしようと頑張る話です。


神代永遠とその周辺
7番目のイギー
青春
普通のJKとは色々とちょっとだけ違う、神代永遠(かみしろとわ)、17歳。それは趣味だったり洋服のセンスだったり、好みの男子だったり。だけどそれを気にすることもなく、なんとなく日常を面白おかしく過ごしている。友達や趣味の品、そして家族。大事なものを当たり前に大事にする彼女は、今日もマイペースにやりたいことを気負うことなく続けます。

放課後、理科棟にて。
禄田さつ
青春
寂れた田舎の北町にある北中学校には、都市伝説が1つ存在する。それは、「夜の理科棟に行くと、幽霊たちと楽しく話すことができる。ずっと一緒にいると、いずれ飲み込まれてしまう」という噂。
斜に構えている中学2年生の有沢和葉は、友人関係や家族関係で鬱屈した感情を抱えていた。噂を耳にし、何となく理科棟へ行くと、そこには少年少女や単眼の乳児がいたのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















