3 / 3
後編
しおりを挟むホームセンターからの帰り道は、新品の自転車とボロくなった俺の自転車を並べて押して帰った。ボロいチャリと新品のチャリが並んでいるさまは、子どもの頃のまま自転車と図体だけが大きくなったようで、なんだか面白かった。
自転車に乗る練習は車通りの少ない近所の農道でやろうということになった。農地を改良して住宅が出来たばかりの頃はまだまだ自然豊かで、田んぼから田んぼへ移動する蛙が農道を横切っていて、真琴は「蛙道」と名付けていた。子どもの残酷さで蛙を自転車で轢きながら通ったものだが、真琴はどうしても蛙が苦手で、今でも蛙を見ると猫がしっぽを踏みつけられたような、絹を裂くような黄色い悲鳴とは言い難い、なんとも言えない声をあげる。
真琴に復讐しようとしたいじめっ子が蛙を投げつけて、かばった俺の顔面に命中し、俺よりも真琴が激怒して、いじめっ子がボコボコにされたのは懐かしいような情けないような思い出だ。
今はこの辺りの自然の豊かさもずいぶん減ったのだろう。あの頃に比べたら蛙もとんぼもぐんと数を減らした気がする。道ばたに蛙やミミズの轢死体が干からびていることも少なくなった。
「なんか、こー。久しぶりにチャリに乗ったわたしがふらついて田んぼに落ちるというフラグが立っている気がするのは気のせい?」
「安心しろ。今は田んぼに水も張ってないし田おこしされているから落ちてもふかふか。濡れもしなければ、怪我もしないだろう」
「うっわー……ご親切な配慮だぁ……」
真琴がしかめっ面のまま自転車にまたがる。俺の中学時代のお下がりのぶかぶかのダッフルコートがひっかかって、それを直してから、後ろに立つ俺を振り返る。
「きちんと押さえておいてよね。転んで怪我したら尚至のせいにするからね」
「転んで怪我してもいつものように送り迎えするだけだから、いつもと変わらん」
「家事は誰がやるのよ! 腕怪我したら!」
「あー。その時は責任持って真琴様のご指導のもと、副島家の味を再現するよう頑張らせていただきます」
それを聞いて複雑な顔をしたあと、むむっと表情を改める。
「尚至に家事やらせる訳にはいかないから、転ばないようにする」
負けず嫌いは真琴の性分だ。
「じゃあね! 押さえててよ。離したらぶっ飛ばすからね!」
真琴の久しぶりのぶっ飛ばす発言を聞いて、俺は空に吸い込まれるような大声で笑った。
自転車は俺が支えるまでもなくスムーズに滑り出した。体が覚えているのだろう。真琴も笑顔で振り返って道の向こうまで行って戻ってきた。
そこからの帰りは二人とも田舎道を併走しながら家まで戻った。車通りの少ないのが本当の田舎道だ。
真琴は自宅の車庫の隅に自転車を置き、名前を付けないとねと呟いている。愛用のものになんにでも名前を付けるのは、真琴の習いの性だ。なんにでも名前を付けると愛着がわいて大事にするのだというのが、真琴の母親の教えだった。
月曜日からは一人で行くという真琴を説き伏せ、これまで通り一緒にいくということで話を付けて別れた。
夜中。隣家に耳を澄ましていると、やはり寝静まったはずの隣の家の扉が開いた音がした。新品の自転車のスタンドを跳ね上げるかすかな金属音がする。俺は急いで階段を下りて玄関の扉を開けて外に出た。今回は防寒対策もばっちりで、真琴の分の防寒用品も用意しておいた。
真琴は前と変わらず、門扉を閉めて自転車に乗って出てゆく。以前よりも増えた街灯の明かりが、真琴の新品の自転車の反射板にはねかえった。
たどり着いた先はやはりあの祠で、真琴は自転車を降りるとその祠の前にしゃがみこんだ。何かを祈っていたが、俺が自転車をとめると、真琴が振り返ってつぶやいた。
「よくわかったね」
「……長いつきあいだろ」
真琴の自転車の隣に俺の自転車を停めて、家から持ってきたベンチコートを真琴の頭からかけた。俺は以前真琴が泣いていた石に腰掛ける。
「あの時、声をかけられなかった自分を悔やむのは、もう終わりにしたいんだ」
真琴はベンチコートを羽織って俺の隣に移ってきた。
「……お母さんが入院している間、お母さんを助けてって、時間を見つけてはここで祈ってた。なんでこんなに祈っているのに助けてくれないんだって、神様は不公平だって思ってた。他の人はお母さんが生きていて、苦しい思いなんかしてないのにって」
真琴は遠い目をする。
「でも、違うんだよ。神様はわたしとお母さんの時間を出来るだけ延ばしてくれたんだよ。やっとそう思えるようになったの。だから、今日はお礼を言おうと思ってきたの」
真琴はそういって祠を見つめた。その目は澄んでいた。
真琴は神様と和解をしにきたのだ。自分でままならない運命を呪うのではなく、許し許されるために、ここに来たのだ。真琴のなかで、何かが本当に一区切りつこうとしている。俺にはそれを見届けることしか出来ない。見届けることが出来るだけでも幸せだと思わなければならないのだろう。これは真琴が解決しなければならない問題だから。
「尚至にはいろいろ気を使わせちゃったね。ありがと。ごめんね」
「俺も後悔してた。無知で子どもだった。真琴はまたもとの生活に戻れるなんて思ってた。俺たちと遊んで暮らせる生活が戻ってくるなんて思ってた。……母親が亡くなったんだ。その生活を支える重みがすべて中学生の真琴の肩にかかるなんて想像もつかなかった」
俺はゆっくりと息を吐き出した。
「ごめんな。俺たちみたいに高校生らしく遊んだりしたいって、真琴を引き戻したいって思ってた。それ、迷惑だったんだな」
「ううん。ありがたかったよ。わたしは、自分で自分を抑圧してたんだよ。わたしは遊んじゃいけないんだって。他の子と違うんだからって。でも、そうやって他人と自分を差別していたのは自分なんだ。尚至はいつもわたしを普通の高校生に戻してくれようとしてたよ」
真琴がベンチコートの前をかき抱く。
「……この前ね、お父さんが今おつき合いしている人を紹介してくれたの。三人でレストランでご飯食べた」
真琴の手がぎゅっと握られる。
「お父さんもさ、寂しかったんだと思う。お母さんを忘れたわけじゃないと思う。でもさ、前に進むんだなって。そう考えたらさ、自分だけ、前に進めてないのかなって」
真琴の声が震える。
「この前の、女装の写真を仏壇に飾ったの。お父さんがお母さんにそっくりだってびっくりしてた。お母さんが生きてたらさ、尚至のオバサンみたいに、やっぱり洋服の話で盛り上がったりしたのかな、とか。恋バナとかしてさ、友達みたいにはしゃいだりさ、やっぱり着飾らせたりしたかったのかな、とかさ。成人式には、お母さんの振り袖着なさいって言ってたなとか思い出した。タンスに着物いっぱいあったの思い出した。七五三は貸し衣装じゃなかったよ。お母さん、オシャレ好きだったよ。新品の服を買うときはいつもかっこいいの買ってくれてた」
真琴の目からすっと涙がこぼれた。真琴は拭いもせずにそのままでいる。
「ありがとう。思い出させてくれたのは川添のおうちのみんなだよ。だから、尚至が後悔することなんかないよ」
真琴は涙を流したまま笑う。今までテレビや映画で見たどんな女優の泣き顔よりきれいだった。思わず手を伸ばしてそっと抱きしめると、部活でシュートが決まったときに抱き合う部員とは違って、真琴は華奢で壊れそうに柔らかくて、そして小さかった。こんな小さい体で、一家の大黒柱のつっかえ棒だったのかと思うと、鼻の奥がむずがゆくなった。
「真琴。オシャレしてよ。そんで今度、俺と遊びに行こうよ。この前のかっこめっちゃ可愛かったよ。オバサンを安心させようよ、真琴は普通の高校生も出来るんだって」
「……前から思ってたけれど、川添一家は全員わたしに甘過ぎ」
おずおずと俺の背中に背中に手を回して、真琴は言う。そこで俺じゃなくて、川添一家なのがちょっと気に入らないけれど。
「尚至あったかい」
「そりゃそうだ。生きてるからな」
「うん。病室のお母さんは最期の方は発熱してたから、ずっと熱かったけれど、死んだら腐らないように布団にドライアイスも入れられて、すっごく冷たかった。ああ、お母さんはナマモノなんだって思った。だから、ドライアイスは今でも苦手」
真琴は鼻をすする。本当に真琴は臨終から葬儀まで余すところなく見つめていたんだ。十歳をいくつか越えたばかりの少女が、そんな場面で目をそらすことなく、全てに立ち会ったのだ。
「そんでね、保冷剤を明日の朝一番で取り替えにきますって葬儀屋さんが言うの。昔は線香は腐敗臭を隠すためにも使ってたんだって、親戚のおじさんが自慢顔で知識を披露するわけ。お母さんが死んだのに、なにその俺は物知りみたいだぜみたいな豆知識」
真琴は悲しみをどこへもやることなく、ずっと胸で凍らせてしまっていたんだ。それが解凍されたのが唯一この場所だったのだと、俺はようやく理解した。胸の中の真琴に申し訳なくて、俺は力を込めて真琴を抱きしめた。
真琴がとんとんと俺の背中を叩く。
「尚至、運動部のベアハッグは痛いって」
昔、兄貴と三人でやった格闘ゲームの技名を出して、真琴が力を緩めるように言う。離せと言われなかったことをいいことに、俺は相変わらず腕の中に真琴を囲っていた。
「焼き場でね、お母さんの骨はぼろぼろだったんだ。薬のせいで、わたしたちが、少しでも長生きさせようとしたせいで、お母さんの骨はすかすかで、焼いたら形があんまり残らなかったんだよ」
真琴の声が涙が混じる。
「それを見た遠縁のどっかのおばさんが、骨が残らないのは親不孝だって。こんなコドモ残して先立つのは迷惑だって。お母さんだって好きで病気になったわけでも、骨が残らなかったわけでもないんだよ。それをさ……」
そこから先は言葉にならず、真琴は俺の服に顔を押しつけて声を殺して泣いていた。しゃっくりが出て、真琴の肩が揺れる。俺は黙ったまま、真琴をひたすら抱きしめていた。そして再び、落ち着いてきた真琴が口を開く。
「お父さんは別に再婚するつもりはないんだって。ただ、わたしに紹介しないままじゃ、お母さんにも失礼だと思ったみたい。お母さんは「再婚しても良い」ってお父さんに言ったんだって。でも、やっぱりお父さんの一番はお母さんなんだって、わたしの女装写真見ながら教えてくれた」
話が飛んでいるが、真琴もそれだけ混乱しているんだろう。真琴は俺の胸に顔をすり付ける。なんだか甘える猫みたいだ。それが俺だけに向けられてたらいいのだけれど。
「ありがとね。女装させてもらえなかったら、こんな話もお父さんと出来なかった。……お父さんとつきあってる人も、そのことは了解してるんだって。相手もお子さんがいるんだって。中学生だったかな。思春期でいろいろあるから、落ち着いたらいつか会って欲しいって言われた。……なんか、わたしは思春期じゃないみたいだね。一応、天下のジョシコーセーなんだけれどな」
真琴はそう言ってふふふと笑って、自分で女子高生だってと再びつぶやいている。俺は片手を真琴の頭に移して髪をなでた。長いくせっ毛をゆっくりとかすように、上下に動かした。風呂上がりであろう真琴の髪は珍しく結われておらず、長い髪が指に巻き付いてはするすると逃げてゆく。
「真琴はいつだって、俺にとっての女子だよ」
「うん。ありがとう」
「意味分かってんのか?」
「……うん。たぶん」
しばらくその髪の指通りを堪能していたのだが、自然と真琴が体重を預けてくる。
「疲れたか? 眠いのか?」
「……うん。尚至あったかい。安心する」
真琴が明らかに眠そうな声で言う。
「自転車、乗るのに、けっこう……精神的に疲れた……。尚至、先帰っていい……」
そんなこと出来るわけないだろう!! と叫びたいのを我慢すると、真琴からすうと寝息が聞こえた。このまま安心されて眠られてしまう俺ってなんだと思いつつも、初めて抱きついてきた真琴は可愛いし、抱き心地が良い。しばらく、その重みと暖かさを味わってから、兄貴に電話をした。
週末なのに珍しく家にいた兄貴を呼びだして、迎えに来させた。
「とうとう切れたか……」
俺にしがみついて眠る真琴を見て、兄貴が言った。
「あれからずっと張りつめてたからな。人間、ゆるみがなきゃいつかははじける。その時そばにいた相手がお前でよかったよ」
車の後部座席を空けながら、しみじみと兄貴が言う。
「尚至、幸せにしてやれよ」
「兄貴はいいのかよ」
「真琴もお前も俺にとっちゃ家族だよ。だから、真琴は遠慮なくお前が落とせ。落とせないなら、俺がもらうけどな。真琴を嫁にもらうなら、なにせ嫁姑問題、親戚関係すべて説得する必要もなく結婚出来るしな」
「そういう問題か?」
「違うけれど、それもあるのもホント。高卒でデキ婚したやつ、今もめてるしなー。いやいや、血縁関係は恐ろしいよ」
後部座席に真琴を抱いたままの俺が収まると、扉を閉めて、兄貴はゆっくりと車を発進させる。
「真琴は小学校高学年くらいから、五年以上か? 頑張ってきたんだ。ふらついたりしても、お前が隣にしっかりいろよ」
「わかってるよ」
家までは、車では大した距離ではないので、すぐに着いた。
「どうする? 真琴は家に戻すか?」
「いや、おじさん寝てたら悪いから、うちに寝かすよ」
涙の跡までは俺たちにはどうしようもない。
「客用布団どこだったっけ?」
「俺の部屋に寝かす。俺はソファで寝る」
兄貴は一瞬だけ腹黒い笑顔を浮かべてから後部座席と家の扉を開けてくれた。真琴の靴を脱がせて、俺の部屋までついてくる。
「ベンチコートとコートは脱がさないとな~」
嬉しそうに、真琴の上着を脱がせるのを手伝い、靴下を脱がせて俺の布団をかける。ちょっとその手際の良さに腹が立ったが、俺は眠る真琴の隣に好きなぬいぐるみを並べてやった。真琴は起きる気配もせず、深く寝入っている。少し浮かんだ涙を指で拭うと、目が熱を持っていた。
コート類をハンガーにかけて俺たちは部屋を出た。
再び祠に連れて行ってもらい、兄貴の車の後部座席を倒して、無理矢理二台のチャリを詰め込んだ。
「ボックスワゴンって便利だな」
「扉が閉まらないが、安全運転でゆっくり帰れば警察もこんな時間にはいないだろ。この車を選んだお兄さまに感謝しろ」
「へいへい。ありがとうございます」
軽口を叩いて、兄貴は言葉通りゆっくりと車を発進させた。
「真琴に幸せになって欲しいのはホント。俺たちよりずっと見なくていいモンを見て、この年齢からしなくていい苦労をしてきたんだ。それを外野が勝手にカワイソウって言うのは簡単だけれど、それを言ったら真琴に失礼だ。真琴の人生は真琴のものだから、真琴の幸せも真琴が決めるべきだ」
兄貴が珍しく饒舌に語る。
「それが川添の誰かとあってくれたら俺たちは嬉しい。だけれど、そうでなくても、俺たちは真琴の幸せを祈っている。なので、真琴の幸福を邪魔するのはたとえ弟だろうと殴り飛ばすので、その点は覚悟しておくように」
「いつの間にか、兄貴は兄貴だねぇ……」
俺がつぶやくと、兄貴は肩をすくめた。
「近くにこんなに真面目に生きてる奴がいちゃ、くだらん理由で反抗期なんて馬鹿馬鹿しくてやってらんねーだろ」
家についてチャリを下ろすと、兄貴は慣れた動作で車を車庫に入れた。真琴のチャリはそっと隣の家に置いて鍵をかける。自分のチャリはいつも通り、兄貴の車の横に並べた。
家に入り、真琴の自転車の鍵と自分のチャリキーをローテーブルに投げ出すと、
「ほら、ふとん」
と、兄貴が毛布を寄越してくれる。家族がうたた寝するときに使う毛布。寝ていたら誰かがかけてくれるのがうちでは当たり前で、だけれど、真琴の家では寝てしまったら、父親が帰ってくるまでそのままなんだな、と思って、胸がざわついた。
「んじゃ、風邪引くなよ」
兄貴はそう言って自分の部屋に引き上げていった。
テレビをザッピングして、いつも通りくだらない番組しかやってないのを確認してから消す。居間では冷蔵庫のモーター音が低くうなるのが聞こえる。そして、築年数に応じた家鳴りと、外を走る車の音。
真琴が俺の部屋で寝ている。
そう思うと、心臓の音が部屋に響きわたりそうになる。寝顔をのぞきに行きたいのをぐっとこらえる。下半身に血が集まるのは健康な男子高校生として許してもらいたい。
真琴は知識としては知っていても、現実には知らないんだろうな。下世話な話題にもついていって、自分は「女子」の部類には入らないのだ、と本能的にアピールしているのを俺は気がついている。可愛い顔をして下世話な話題に乗るんだから、貞操観念もゆるいのだろうと陰で仕組まれた企みは俺がことごとく潰してきた。
真琴のアンバランスさが、これからどうなっていくのか、俺にはわからない。まあ、アンバランスなところも含めて好きなんだからしょうがない。転んだら立ち上がるための手ぐらいは差し伸べたい。そのためには近くにいたい。これからも近くにいられるだろうか。いることを、真琴は許してくれるだろうか。
そんなことを考えながら、俺はゆっくりと眠りに落ちていった。いつでも眠れるのが、なんてたって成長期の特徴だ。
起きたら、小さくテレビの音がして、台所で包丁の音と湯が沸く音がした。いつものごく当たり前の、川添家の朝の音。
ソファから起きあがると、いつも通りに朝の支度をしていた母親が声をかけてきた。
「なんか深夜番組でも見てたの? ちゃんと布団で寝ないと風邪引くわよ」
「いや、布団は真琴に譲った」
「は?」
「だから、布団は真琴が寝てる」
母親がなぜか包丁を持ったまま台所から出てくる。
「あんた、きちんと避妊したんでしょうね?」
「は? んなことしてねって」
「処女は妊娠しないとかバカな都市伝説信じてるんじゃないでしょうね。真琴ちゃんが妊娠してたら、あんた責任取って養ってく自信あるの?」
母親が包丁を片手にすごんでくる。なんか根本的な誤解がないか。
「真琴ちゃんもあんたも大人ぶったって高校生なのよ。コドモがコドモ産んで育てられるの? それとも、真琴ちゃんの中の命、殺す気なの? 生理が遅れてるって気づく頃にはお腹のコドモは心臓と肺が出来て、育っているのが確認できる頃なんですからね!」
母親の大声に、兄貴がゆっくり降りてくる。
「おはよ。なに騒いでんの?」
なぜだか笑顔が黒いのは気のせいか。
「和至……。真琴ちゃんが上で寝てるって言うのよ」
「包丁はしまおうよ、母さん。危ないから」
「そんなわけにはいかないわ。このバカ息子がやったことを思えば副島さんに申し訳がたちません!」
泣き出しそうな顔で、母親が断言する。なんかまずいことしたか、俺。
「あのー。おはようございます……。すみません……」
真琴が小さな声で挨拶をして降りてきた。
「真琴ちゃんが謝ることないのよ。全部尚至が悪いんだからね。妊娠してたらおばちゃんに言うのよ」
母親は真琴の腕をつかんで必死だ。だから危ないから包丁は放せ。
「えっと……。そういう事実はないです、多分……。どこも痛くないし……」
真琴が真っ赤になって言う。
それを見て、母親がようやくおやっという顔をする。
「だから、そんなことしてねって」
「尚至のおばさん、前から思ってたけれど、大物だよね」
真琴がしみじみと呟く。
場所は副島家の台所。
久しぶりに入るそこは、真琴の城と化していて、ただでさえ勝手がわからない俺を戸惑わせる。
「あれには、びっくりしたわ。起きたら尚至の部屋だったのもびっくりしたけれど」
キッチンスケールやら泡立て器やら、手際よく準備して、ダイニングテーブルに並べる。椅子は四脚あって、一つには大きなテディベアが置いてあった。おそらくは真琴の母親が座っていたであろう席。
二月の期末考査前だっていうのに、真琴の家で何をやろうかとしているのかというと、バレンタイン用のチョコクッキーを作るんだそうで。簡単だから尚至も手伝ってと言われて、そのままお邪魔している。
「一応、はかり、あるんじゃん……」
デジタルメモリのスイッチを入れて、俺が呟くと、
「何で買ったんだっけかなー。あ、多分、セールで500円均一とかに釣られた気がする。でも慣れたらいらないよー。計量カップで十分だもん」
と、大変主婦らしいお返事が来た。
では始めます、と真琴が宣言する。
それからはバターを練ろとか言われて練っている間に、砂糖や卵が加えられ、計量カップで小麦粉やらココアパウダーが入れられた。いつの間にか泡立て器がへらに代わっていて、俺がボケーと混ぜている間になんだか生地が出来ていた。
「ね? 簡単でしょ?」
真琴は生地を伸ばして、型抜きするだけの状態に持っていく。
そこからは懐かしの粘土遊びと同じで、二人でわいわいしながらチョコチップで模様をつけたりなんだりと童心に返って楽しく遊んだ。オーブンレンジに入れて、焼きあがる間に手早く真琴は洗い物をし、俺にコーヒーを入れてくれた。
「今年のバレンタインは尚至と作ったから、下手な人にはあげらんないかな? あ、おじさんとおばさんには持っていこうね」
香ばしい香りが漂うテーブルで、真琴はマグカップ入りのコーヒーで手を暖めている。
「生徒会室には持っていかないのか」
「ああ、それはね、ブラックサンダーでいいや。この前大袋が安売りしてた」
身も蓋もねーなと思いつつ、そんなもんでいいだろ、義理なんだからと思う心の狭い俺がいる。
「会長にはね、きちんと言ったから。遊ぶんなら尚至と遊ぶし、つきあうんなら真面目につきあってくれる人じゃないと困るので、会長はお断りですって」
湯気の向こうで、真琴が笑う。
「だからさ、春休みはどっかに遊びに行こう」
俺は頬がゆるむのを押さえきれないまま、答える。
「その前に期末なんとかしないとだ」
「そうでした。ではクッキーが焼けて冷めるまでに一つ教科を終わらせましょう」
真琴が教師ぶって言うと、俺は部屋の隅に置いた鞄からノートと問題集を取り出す。
「じゃあ、やりますか」
真琴も勉強道具を取り出すと、すぐに問題に集中しはじめる。
そんな真琴を見て、それからテディベアを見る。真琴はこうやって一人の食卓をこのぬいぐるみと過ごしてきたのだろう。そこに俺も自然に混ざれていることが嬉しくて、俺の顔がにやけるのがわかる。
そんな俺を見て、テディベアがなんだか笑った気がして、俺は目をしばたいた。
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

幼なじみとセックスごっこを始めて、10年がたった。
スタジオ.T
青春
幼なじみの鞠川春姫(まりかわはるひめ)は、学校内でも屈指の美少女だ。
そんな春姫と俺は、毎週水曜日にセックスごっこをする約束をしている。
ゆるいイチャラブ、そしてエッチなラブストーリー。

【完結】彼女はボクを狂おしいほど愛する ー超絶美少女の転校生がなぜかボクにだけぞっこんな件ー
竜竜
青春
————最後のページにたどり着いたとき、この物語の価値観は逆転する。
子どもの頃から周りと馴染めず、一人で過ごすことが多いボク。
そんなボクにも、心を許せる女の子がいた。
幼い頃に離れ離れになってしまったけど、同じ高校に転校して再開を果たした朱宮結葉。
ボクと結葉は恋人関係ではなかったけど、好き同士なことは確かだった。
再び紡がれる二人だけの幸せな日々。だけどそれは、狂おしい日常の始まりだった。

【完結】±Days
空月
青春
次々かかってくる幼馴染ズからの電話。恋愛相談?なんでそんなもの持ち込んでくるんだおまえらは…!しかも内容馬鹿らしすぎて頭痛がするっての!――自称平々凡々一般人の、平凡から遠ざかる日常のお話。初恋に右往左往な幼馴染ズにアドバイザーとして無理やり転校させられたり、その先で変人な知り合いにばったりしたり、結局転校もアドバイザーの立場も受け入れたり。
一部お題使用の変則的な小説と言えるかも疑問な代物です。基本地の文なしで進行します。逆ハーを脇から見てみようがコンセプト(多分)。
後々はシリアス色強めの話もあります。
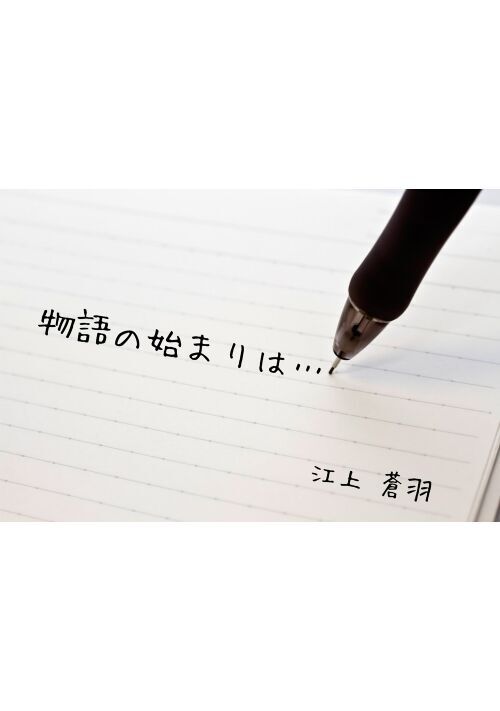
物語の始まりは…
江上蒼羽
青春
***
自他共に認める学校一のイケてる男子、清原聖慈(17)
担任教師から与えられた課題をきっかけに、物語が動き始める。
男子高校生目線の青春物語として書きました。
所々不快に思われる表現があるかと思いますが、作品の中の表現につき、ご理解願いします。
R5.7月頃〜R6.2/19執筆
R6.2/19〜公開開始
***


僕たちのトワイライトエクスプレス24時間41分
結 励琉
青春
トワイライトエクスプレス廃止から9年。懐かしの世界に戻ってみませんか。
1月24日、僕は札幌駅の4番線ホームにいる。肩からかけたカバンには、6号車のシングルツインの切符が入っている。さあ、これから24時間41分の旅が始まる。
2022年鉄道開業150年交通新聞社鉄道文芸プロジェクト「鉄文(てつぶん)」文学賞応募作
(受賞作のみ出版権は交通新聞社に帰属しています。)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















