お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

リモート刑事 笹本翔
雨垂 一滴
ミステリー
『リモート刑事 笹本翔』は、過去のトラウマと戦う一人の刑事が、リモート捜査で事件を解決していく、刑事ドラマです。
主人公の笹本翔は、かつて警察組織の中でトップクラスの捜査官でしたが、ある事件で仲間を失い、自身も重傷を負ったことで、外出恐怖症(アゴラフォビア)に陥り、現場に出ることができなくなってしまいます。
それでも、彼の卓越した分析力と冷静な判断力は衰えず、リモートで捜査指示を出しながら、次々と難事件を解決していきます。
物語の鍵を握るのは、翔の若き相棒・竹内優斗。熱血漢で行動力に満ちた優斗と、過去の傷を抱えながらも冷静に捜査を指揮する翔。二人の対照的なキャラクターが織りなすバディストーリーです。
翔は果たして過去のトラウマを克服し、再び現場に立つことができるのか?
翔と優斗が数々の難事件に挑戦します!

ファクト ~真実~
華ノ月
ミステリー
主人公、水無月 奏(みなづき かなで)はひょんな事件から警察の特殊捜査官に任命される。
そして、同じ特殊捜査班である、透(とおる)、紅蓮(ぐれん)、槙(しん)、そして、室長の冴子(さえこ)と共に、事件の「真実」を暴き出す。
その事件がなぜ起こったのか?
本当の「悪」は誰なのか?
そして、その事件と別で最終章に繋がるある真実……。
こちらは全部で第七章で構成されています。第七章が最終章となりますので、どうぞ、最後までお読みいただけると嬉しいです!
よろしくお願いいたしますm(__)m

旧校舎のフーディーニ
澤田慎梧
ミステリー
【「死体の写った写真」から始まる、人の死なないミステリー】
時は1993年。神奈川県立「比企谷(ひきがやつ)高校」一年生の藤本は、担任教師からクラス内で起こった盗難事件の解決を命じられてしまう。
困り果てた彼が頼ったのは、知る人ぞ知る「名探偵」である、奇術部の真白部長だった。
けれども、奇術部部室を訪ねてみると、そこには美少女の死体が転がっていて――。
奇術師にして名探偵、真白部長が学校の些細な謎や心霊現象を鮮やかに解決。
「タネも仕掛けもございます」
★毎週月水金の12時くらいに更新予定
※本作品は連作短編です。出来るだけ話数通りにお読みいただけると幸いです。
※本作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係ありません。
※本作品の主な舞台は1993年(平成五年)ですが、当時の知識が無くてもお楽しみいただけます。
※本作品はカクヨム様にて連載していたものを加筆修正したものとなります。

パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。
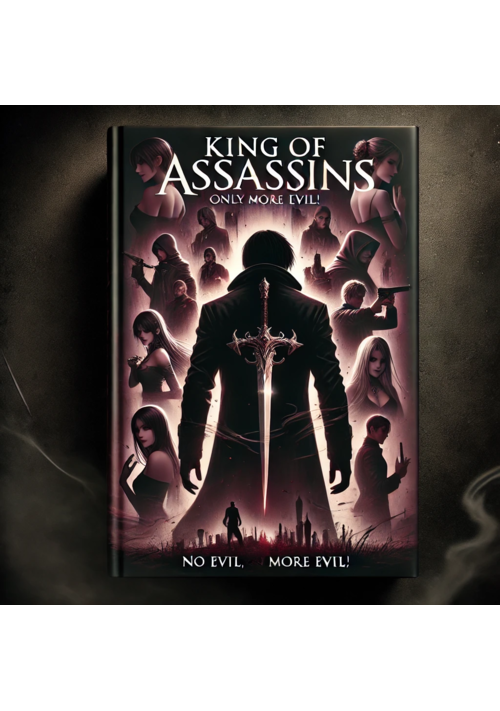

小説探偵
夕凪ヨウ
ミステリー
20XX年。日本に名を響かせている、1人の小説家がいた。
男の名は江本海里。素晴らしい作品を生み出す彼には、一部の人間しか知らない、“裏の顔”が存在した。
そして、彼の“裏の顔”を知っている者たちは、尊敬と畏怖を込めて、彼をこう呼んだ。
小説探偵、と。

実力を隠し「例え長男でも無能に家は継がせん。他家に養子に出す」と親父殿に言われたところまでは計算通りだったが、まさかハーレム生活になるとは
竹井ゴールド
ライト文芸
日本国内トップ5に入る異能力者の名家、東条院。
その宗家本流の嫡子に生まれた東条院青夜は子供の頃に実母に「16歳までに東条院の家を出ないと命を落とす事になる」と予言され、無能を演じ続け、父親や後妻、異母弟や異母妹、親族や許嫁に馬鹿にされながらも、念願適って中学卒業の春休みに東条院家から田中家に養子に出された。
青夜は4月が誕生日なのでギリギリ16歳までに家を出た訳だが。
その後がよろしくない。
青夜を引き取った田中家の義父、一狼は53歳ながら若い妻を持ち、4人の娘の父親でもあったからだ。
妻、21歳、一狼の8人目の妻、愛。
長女、25歳、皇宮警察の異能力部隊所属、弥生。
次女、22歳、田中流空手道場の師範代、葉月。
三女、19歳、離婚したフランス系アメリカ人の3人目の妻が産んだハーフ、アンジェリカ。
四女、17歳、死別した4人目の妻が産んだ中国系ハーフ、シャンリー。
この5人とも青夜は家族となり、
・・・何これ? 少し想定外なんだけど。
【2023/3/23、24hポイント26万4600pt突破】
【2023/7/11、累計ポイント550万pt突破】
【2023/6/5、お気に入り数2130突破】
【アルファポリスのみの投稿です】
【第6回ライト文芸大賞、22万7046pt、2位】
【2023/6/30、メールが来て出版申請、8/1、慰めメール】
【未完】
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















