31 / 80
あの子が欲しい
あの子が欲しい-3
しおりを挟む
で、結局行ったのは近くのイオンモール。てっきりおしゃれな店かと思っていた僕は拍子抜けしてしまった。
まあ近くの商店街とかは知らない店ばかりだし、その三分の一くらいが閉まっていたけれど。
「ごめんね、なんか用事あったとか?」
会うなり彼女はすまなさそうに口を開いた。
「いや、そうじゃないよ、大丈夫」
ちょっといろいろあって、とだけ僕は返す。
自分の親の離婚が成立したこととか、その調停をした弁護士と母親が妙に親しげだったとか、そんなこと急に話されたって、彼女だって困るだろう。
「ここに新しゅうエッグシングスが入ったんよ」
意気揚々と彼女が語るのは、どこかで聞いたことのあるような店の名前。
確か何年か前に、海外から日本初出店で原宿にできたとかってクラスの子が騒いでた。
今となってはもう、いろんなところにあるんだろうけど。
「ここ来れば涼しかしなんでんあるし、一日遊んでらるるし」
「いつもこういうところで遊んでるの?」
意外に思って僕は聞いた。
「そうだけど。東京やとなしとったと?」
どうしてたんだろう。まだ中学生だったし、あまりお店に遊びに行った記憶はない。
子供だけでそういうところに行くなって言われてたし。
かといって、じゃあどこでなにをしていたのかと言われてもあまりピンとこなかった。
そういえば、部活も入ってなかった。
「あまり、覚えてないかな」
「ふうん。じゃあ今度、一緒に東京行って遊ぼうよ」
電車の乗り換えくらいはわかるでしょ、と肩を叩かれる。それってつまり、僕と一緒に東京まで旅行に行くつもりなんだろうか。
彼女の意図がわからなくて僕はへらりと笑い返した。まあきっと、ただの社交辞令だ。
白石さんの言う通り、そのお店はできたばかりのようで、店外には行列ができていた。これに並ぶのかとうんざりする僕を尻目に、白石さんは当たり前のようにそれに並ぶ。
「どのくらい待つのかな」
「一時間くらいやなか?」と白石さんは気楽だ。
「なに、なんか急ぎの用事でもあんの?」
「そういうわけじゃないけど」
何を話したらいいのかわからなくて、僕は困っている。
「ナオって何が好きとかあんの?ほら、今回はうちに付き合わせてしもうたし」
黙りこくる僕に気づいたのだろう、白石さんが明るい声で言った。
「今度はナオの好きなん食べに行こ」
「好きなもの……」
なんだろう、改めて問われると思い出せない。そんな、僕のことなんかより、早く事件の報告をした方がいいんじゃないか。そんなことばかりが浮かんでくる。
「それよりさ、こないだの」
僕が慌てて口を開いた時だった。
「あれ、ルイじゃん」
横から掛けられたのは、少し舌っ足らずの、だらしのない声。
「あ、ケンちゃんじゃん」
その声に反応して、白石さんが視線を動かした。
その先に、髪を明るい色に染めた、同年代くらいの男の子の姿。その彼は、列に並ぶ僕らを面白そうに眺めていた。
「誰、そいつ」
ソイツが、無遠慮に僕を指さした。
「ケンはクラス違うけんわからんかも。こないだ転校してきたナオばい」
白石さんに促され、僕はおろおろと頭を下げた。それに対しケンとやらは、「うっす」と顎を軽くしゃくって相槌を打っただけだった。
「なんだよ、お前もここ来たと?なら俺とデートしてくれたっちゃよかったばい」
ニヤニヤと笑みを浮かべながら、ケンが白石さんに手を伸ばす。馴れ馴れしくその手で彼女の腰を抱いた。
「あ、ごめんね。こいつはうちん彼氏」
「そ、そうなんだ」
返す僕の声は裏返っていたかもしれない。いきなり目の前で見せつけられて、僕の口から飛び出たのはこんな言葉だった。
「なら、良かったら二人でデートしてくれば」
そうだ、その方がいい。きっと。恋人同士なら、その方が。ごめんね、僕なんかが。
「やだよ、ナオば誘うたんなうちだし。てかケンちゃんだって、なんか予定あるって言うとったばい」
不服そうに白石さんが頬を膨らませた。
そうか、彼氏と予定が合わなくて、暇を持て余してたから僕を誘ったんだ。
「ちょーめんどくせーんだけど、頼まれちまったけん仕方のうて」
ケンが、だるそうに頭を掻く。
「弟が、猫ん餌買うて来えって」
「猫?ケンちゃんち、猫飼うとったっけ?」
列が進んでいくのにも構わず話す二人に、僕はいたたまれなくなってきた。
やっぱり来なければよかった。後悔が僕を襲う。
「野良猫にあげるったいってさ、腹空かせとってかわいそうやけんって」
「ああ、あん子。もう中学生だっけ?」
「来年からばい。私立んよかとこ行かするったいって、親が張り切っとってさ」
アイツ忙しかけん俺が代わりに買い物行かんばならんの、とケンが笑った。
そこで大きく列が動いて、じゃあなとケンは去って行ってしまった。
僕はほっとしながらも、流されるままに店内に押し込められる。あまり、パンケーキなんて食べたい気分じゃなくなっていたけれど、ここまで来て何も食べないわけにいかず、仕方なしにお勧めとやらを注文する。
ようやく席につけた安堵からか、白石さんがふうと大きくため息をついた。
「ごめんね、せっかくナオとお出かけしとっとに邪魔が入って」
「邪魔だなんて、別に」
そう言いかけて、でも確かに気分が悪かったのは確かだとも思い直す。誘ってきたのはそっちなのに、僕なんかそっちのけで話して。
その一方、自分だってこちらの都合で彼女と一緒に出掛けることにしたくせに、いざそれを邪魔されて、苛立つ自分にも呆れてしまう。これじゃあまるで、嫉妬してるみたいだ。
そうだ、白石さんの彼氏に嫉妬したりするほど、そもそも僕は彼女と親しくもないのに。
「あんなんやけど、けっこう優しかたい」
僕の気持ちを知らずに、白石さんが優しく笑った。前に太陽の光を浴びて、きらきらと輝いて見えたのと同じ笑顔だった。
その顔に対し僕は何と返したらいいのかわからず、「そう」とだけ返した。
野良猫に餌をあげたい弟と、その弟のためにデートより買い物を優先させた兄。
確かに、優しいのかもしれない。その彼を鬱陶しく思ってしまった僕なんかよりは全然。
きっと彼女は、だれとでも隔てなく仲良くできるタイプなんだろう。
僕はフォークを握りながら、おいしそうにケーキを食べる彼女にそっと目をやった。
そういう純粋で優しい人間なら、神様だって好きに決まってる。まして彼女はお寺の娘で、彼女は丸藤さんやミサキとも仲が良くって。
そう思ったら、甘ったるいはずのパンケーキも、なんだか味がしなかった。
「それでさ、事件のことだけど」
あらかた皿の上を片付けたあたりで、思い出したように白石さんが僕を見た。
「結局大団円でよかったってことでおけ?」
そう言われてしまうと身も蓋もないけれど、大体は合っている。
「まあ、そうだとは思う」
だからそう返すしかなかったのだけれど、どうしても僕の歯切れは悪くなる。
それに気づいたのだろう、白石さんが不思議そうな顔をした。
「何かあったと?」
「ちょっと、気になることがあって」
僕はたっぷり残ったホイップを食べる気にもなれず、フォークを置いてあの子供のことを彼女に話し始めた。
「事件を起こした子供たちが謝りに来てくれたんだ」
それだけだったら、本当によかったんだけど。そう思いながら続ける。
「そのうちの一人があんまり悪びれた様子もなくて」
笑ってたんだ、とうつむきながら僕は呟いた。皿の上では、真っ赤ないちごジャムが飛び散っている。
「ばってん、神様たちは許したんやろ?」
白石さんが少し考えてから口を開いた。
「なら、それでよかんやなかとかなあ」
僕だってそう思いたかった。けれど人間は、きっと神様が思うより醜い。僕はそう簡単に人間を信じられない。
目の前の彼女だって、本当はどう思ってるかなんてわからない。
「ちなみにそん子、どぎゃん子やった?」
そう問われて、僕はぼんやりと思い出す。小学生の男の子。背は割と高かった気もする。銀縁のメガネをかけていて、いたずらをする側と言うよりは、それをいさめる学級委員長みたいな雰囲気で。
「ふうん、そう」
そう呟いて、白石さんが最後の一切れを口に頬張った。それと同じくらいに、僕はアイスティーを喉に流し込む。
とりあえず、これで今日の予定は終わりだ。報告も終わったし、誘われた店にも来た。さすがにあの弁護士も帰っただろう。もう十分だ。
「じゃあ、これでわたし」
そう言って席を立ちあがる。
「え、もう帰ってしまうん?」
やっぱり予定あったの?と申し訳なさそうに聞かれて、僕は少し胸が痛む。そういうわけじゃ、ないんだけど。
でも、これ以上一緒にいたって。
なんだか、疲れるだけだ。
「やっぱり、毎日バイトで疲れとるんやなか?」
うん、そうなんだ。たぶん、そう。だからもうわたし。
そう続けようとした言葉が遮られた。
「ならさ、うち来ん?」
「え?」
なんでそうなる。思わず口からそう飛び出そうになるのを押さえる。けれど彼女は本当に心配そうな顔で、
「うちでちょっと休んできなよ」
などと言ってくるので困ってしまう。
「いや、でも悪いし」
「よかって、気にせんで。それに、ほんとは丸藤さんへお礼ん準備、手伝ってほしかったんばいね」
お礼にたくさんごちそうしてあげんばだし、と彼女は唇を持ち上げる。
「ごちそう?それって、何を」
一瞬甘いパンケーキを頬張る探偵の姿が目に浮かんで、僕は慌てて頭を振った。
いや、そうじゃない。あの人が食べてたのは、きれいな石だった。それとも、本当は僕らと同じようなものの方が好きなんだろうか。
そして、彼の好物を彼女は知っているのか。
「ばってん、けっこう大変なんばい、やけん手伝ってほしゅうって。もちろん、疲れとるやろうし無理とは言わんけど」
「……手伝うって、何を?」
恐る恐る、僕は口を開いた。一体彼女は、何をするつもりなのだろう。
「丸藤さんの身体ば洗うちゃったりとか、ご飯ば食べさせてあげるんよ」
それってどういう??僕の頭の上に、たくさんのクエスチョンマークが浮かんでいる。そんな気がした。
もちろん、それが見えたわけではないだろう。けれど白石さんはにっこり笑うと僕の手を取って席を立った。
「とりあえず、来てくれればわかるけん。ね?」
まあ近くの商店街とかは知らない店ばかりだし、その三分の一くらいが閉まっていたけれど。
「ごめんね、なんか用事あったとか?」
会うなり彼女はすまなさそうに口を開いた。
「いや、そうじゃないよ、大丈夫」
ちょっといろいろあって、とだけ僕は返す。
自分の親の離婚が成立したこととか、その調停をした弁護士と母親が妙に親しげだったとか、そんなこと急に話されたって、彼女だって困るだろう。
「ここに新しゅうエッグシングスが入ったんよ」
意気揚々と彼女が語るのは、どこかで聞いたことのあるような店の名前。
確か何年か前に、海外から日本初出店で原宿にできたとかってクラスの子が騒いでた。
今となってはもう、いろんなところにあるんだろうけど。
「ここ来れば涼しかしなんでんあるし、一日遊んでらるるし」
「いつもこういうところで遊んでるの?」
意外に思って僕は聞いた。
「そうだけど。東京やとなしとったと?」
どうしてたんだろう。まだ中学生だったし、あまりお店に遊びに行った記憶はない。
子供だけでそういうところに行くなって言われてたし。
かといって、じゃあどこでなにをしていたのかと言われてもあまりピンとこなかった。
そういえば、部活も入ってなかった。
「あまり、覚えてないかな」
「ふうん。じゃあ今度、一緒に東京行って遊ぼうよ」
電車の乗り換えくらいはわかるでしょ、と肩を叩かれる。それってつまり、僕と一緒に東京まで旅行に行くつもりなんだろうか。
彼女の意図がわからなくて僕はへらりと笑い返した。まあきっと、ただの社交辞令だ。
白石さんの言う通り、そのお店はできたばかりのようで、店外には行列ができていた。これに並ぶのかとうんざりする僕を尻目に、白石さんは当たり前のようにそれに並ぶ。
「どのくらい待つのかな」
「一時間くらいやなか?」と白石さんは気楽だ。
「なに、なんか急ぎの用事でもあんの?」
「そういうわけじゃないけど」
何を話したらいいのかわからなくて、僕は困っている。
「ナオって何が好きとかあんの?ほら、今回はうちに付き合わせてしもうたし」
黙りこくる僕に気づいたのだろう、白石さんが明るい声で言った。
「今度はナオの好きなん食べに行こ」
「好きなもの……」
なんだろう、改めて問われると思い出せない。そんな、僕のことなんかより、早く事件の報告をした方がいいんじゃないか。そんなことばかりが浮かんでくる。
「それよりさ、こないだの」
僕が慌てて口を開いた時だった。
「あれ、ルイじゃん」
横から掛けられたのは、少し舌っ足らずの、だらしのない声。
「あ、ケンちゃんじゃん」
その声に反応して、白石さんが視線を動かした。
その先に、髪を明るい色に染めた、同年代くらいの男の子の姿。その彼は、列に並ぶ僕らを面白そうに眺めていた。
「誰、そいつ」
ソイツが、無遠慮に僕を指さした。
「ケンはクラス違うけんわからんかも。こないだ転校してきたナオばい」
白石さんに促され、僕はおろおろと頭を下げた。それに対しケンとやらは、「うっす」と顎を軽くしゃくって相槌を打っただけだった。
「なんだよ、お前もここ来たと?なら俺とデートしてくれたっちゃよかったばい」
ニヤニヤと笑みを浮かべながら、ケンが白石さんに手を伸ばす。馴れ馴れしくその手で彼女の腰を抱いた。
「あ、ごめんね。こいつはうちん彼氏」
「そ、そうなんだ」
返す僕の声は裏返っていたかもしれない。いきなり目の前で見せつけられて、僕の口から飛び出たのはこんな言葉だった。
「なら、良かったら二人でデートしてくれば」
そうだ、その方がいい。きっと。恋人同士なら、その方が。ごめんね、僕なんかが。
「やだよ、ナオば誘うたんなうちだし。てかケンちゃんだって、なんか予定あるって言うとったばい」
不服そうに白石さんが頬を膨らませた。
そうか、彼氏と予定が合わなくて、暇を持て余してたから僕を誘ったんだ。
「ちょーめんどくせーんだけど、頼まれちまったけん仕方のうて」
ケンが、だるそうに頭を掻く。
「弟が、猫ん餌買うて来えって」
「猫?ケンちゃんち、猫飼うとったっけ?」
列が進んでいくのにも構わず話す二人に、僕はいたたまれなくなってきた。
やっぱり来なければよかった。後悔が僕を襲う。
「野良猫にあげるったいってさ、腹空かせとってかわいそうやけんって」
「ああ、あん子。もう中学生だっけ?」
「来年からばい。私立んよかとこ行かするったいって、親が張り切っとってさ」
アイツ忙しかけん俺が代わりに買い物行かんばならんの、とケンが笑った。
そこで大きく列が動いて、じゃあなとケンは去って行ってしまった。
僕はほっとしながらも、流されるままに店内に押し込められる。あまり、パンケーキなんて食べたい気分じゃなくなっていたけれど、ここまで来て何も食べないわけにいかず、仕方なしにお勧めとやらを注文する。
ようやく席につけた安堵からか、白石さんがふうと大きくため息をついた。
「ごめんね、せっかくナオとお出かけしとっとに邪魔が入って」
「邪魔だなんて、別に」
そう言いかけて、でも確かに気分が悪かったのは確かだとも思い直す。誘ってきたのはそっちなのに、僕なんかそっちのけで話して。
その一方、自分だってこちらの都合で彼女と一緒に出掛けることにしたくせに、いざそれを邪魔されて、苛立つ自分にも呆れてしまう。これじゃあまるで、嫉妬してるみたいだ。
そうだ、白石さんの彼氏に嫉妬したりするほど、そもそも僕は彼女と親しくもないのに。
「あんなんやけど、けっこう優しかたい」
僕の気持ちを知らずに、白石さんが優しく笑った。前に太陽の光を浴びて、きらきらと輝いて見えたのと同じ笑顔だった。
その顔に対し僕は何と返したらいいのかわからず、「そう」とだけ返した。
野良猫に餌をあげたい弟と、その弟のためにデートより買い物を優先させた兄。
確かに、優しいのかもしれない。その彼を鬱陶しく思ってしまった僕なんかよりは全然。
きっと彼女は、だれとでも隔てなく仲良くできるタイプなんだろう。
僕はフォークを握りながら、おいしそうにケーキを食べる彼女にそっと目をやった。
そういう純粋で優しい人間なら、神様だって好きに決まってる。まして彼女はお寺の娘で、彼女は丸藤さんやミサキとも仲が良くって。
そう思ったら、甘ったるいはずのパンケーキも、なんだか味がしなかった。
「それでさ、事件のことだけど」
あらかた皿の上を片付けたあたりで、思い出したように白石さんが僕を見た。
「結局大団円でよかったってことでおけ?」
そう言われてしまうと身も蓋もないけれど、大体は合っている。
「まあ、そうだとは思う」
だからそう返すしかなかったのだけれど、どうしても僕の歯切れは悪くなる。
それに気づいたのだろう、白石さんが不思議そうな顔をした。
「何かあったと?」
「ちょっと、気になることがあって」
僕はたっぷり残ったホイップを食べる気にもなれず、フォークを置いてあの子供のことを彼女に話し始めた。
「事件を起こした子供たちが謝りに来てくれたんだ」
それだけだったら、本当によかったんだけど。そう思いながら続ける。
「そのうちの一人があんまり悪びれた様子もなくて」
笑ってたんだ、とうつむきながら僕は呟いた。皿の上では、真っ赤ないちごジャムが飛び散っている。
「ばってん、神様たちは許したんやろ?」
白石さんが少し考えてから口を開いた。
「なら、それでよかんやなかとかなあ」
僕だってそう思いたかった。けれど人間は、きっと神様が思うより醜い。僕はそう簡単に人間を信じられない。
目の前の彼女だって、本当はどう思ってるかなんてわからない。
「ちなみにそん子、どぎゃん子やった?」
そう問われて、僕はぼんやりと思い出す。小学生の男の子。背は割と高かった気もする。銀縁のメガネをかけていて、いたずらをする側と言うよりは、それをいさめる学級委員長みたいな雰囲気で。
「ふうん、そう」
そう呟いて、白石さんが最後の一切れを口に頬張った。それと同じくらいに、僕はアイスティーを喉に流し込む。
とりあえず、これで今日の予定は終わりだ。報告も終わったし、誘われた店にも来た。さすがにあの弁護士も帰っただろう。もう十分だ。
「じゃあ、これでわたし」
そう言って席を立ちあがる。
「え、もう帰ってしまうん?」
やっぱり予定あったの?と申し訳なさそうに聞かれて、僕は少し胸が痛む。そういうわけじゃ、ないんだけど。
でも、これ以上一緒にいたって。
なんだか、疲れるだけだ。
「やっぱり、毎日バイトで疲れとるんやなか?」
うん、そうなんだ。たぶん、そう。だからもうわたし。
そう続けようとした言葉が遮られた。
「ならさ、うち来ん?」
「え?」
なんでそうなる。思わず口からそう飛び出そうになるのを押さえる。けれど彼女は本当に心配そうな顔で、
「うちでちょっと休んできなよ」
などと言ってくるので困ってしまう。
「いや、でも悪いし」
「よかって、気にせんで。それに、ほんとは丸藤さんへお礼ん準備、手伝ってほしかったんばいね」
お礼にたくさんごちそうしてあげんばだし、と彼女は唇を持ち上げる。
「ごちそう?それって、何を」
一瞬甘いパンケーキを頬張る探偵の姿が目に浮かんで、僕は慌てて頭を振った。
いや、そうじゃない。あの人が食べてたのは、きれいな石だった。それとも、本当は僕らと同じようなものの方が好きなんだろうか。
そして、彼の好物を彼女は知っているのか。
「ばってん、けっこう大変なんばい、やけん手伝ってほしゅうって。もちろん、疲れとるやろうし無理とは言わんけど」
「……手伝うって、何を?」
恐る恐る、僕は口を開いた。一体彼女は、何をするつもりなのだろう。
「丸藤さんの身体ば洗うちゃったりとか、ご飯ば食べさせてあげるんよ」
それってどういう??僕の頭の上に、たくさんのクエスチョンマークが浮かんでいる。そんな気がした。
もちろん、それが見えたわけではないだろう。けれど白石さんはにっこり笑うと僕の手を取って席を立った。
「とりあえず、来てくれればわかるけん。ね?」
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

密室島の輪舞曲
葉羽
ミステリー
夏休み、天才高校生の神藤葉羽は幼なじみの望月彩由美とともに、離島にある古い洋館「月影館」を訪れる。その洋館で連続して起きる不可解な密室殺人事件。被害者たちは、内側から完全に施錠された部屋で首吊り死体として発見される。しかし、葉羽は死体の状況に違和感を覚えていた。
洋館には、著名な実業家や学者たち12名が宿泊しており、彼らは謎めいた「月影会」というグループに所属していた。彼らの間で次々と起こる密室殺人。不可解な現象と怪奇的な出来事が重なり、洋館は恐怖の渦に包まれていく。
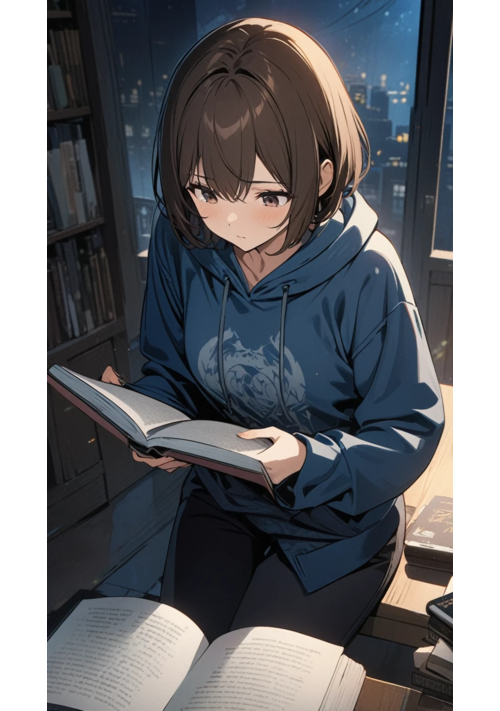
声の響く洋館
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、友人の失踪をきっかけに不気味な洋館を訪れる。そこで彼らは、過去の住人たちの声を聞き、その悲劇に導かれる。失踪した友人たちの影を追い、葉羽と彩由美は声の正体を探りながら、過去の未練に囚われた人々の思いを解放するための儀式を行うことを決意する。
彼らは古びた日記を手掛かりに、恐れや不安を乗り越えながら、解放の儀式を成功させる。過去の住人たちが解放される中で、葉羽と彩由美は自らの成長を実感し、新たな未来へと歩み出す。物語は、過去の悲劇を乗り越え、希望に満ちた未来を切り開く二人の姿を描く。

双極の鏡
葉羽
ミステリー
神藤葉羽は、高校2年生にして天才的な頭脳を持つ少年。彼は推理小説を読み漁る日々を送っていたが、ある日、幼馴染の望月彩由美からの突然の依頼を受ける。彼女の友人が密室で発見された死体となり、周囲は不可解な状況に包まれていた。葉羽は、彼女の優しさに惹かれつつも、事件の真相を解明することに心血を注ぐ。
事件の背後には、視覚的な錯覚を利用した巧妙なトリックが隠されており、密室の真実を解き明かすために葉羽は思考を巡らせる。彼と彩由美の絆が深まる中、恐怖と謎が交錯する不気味な空間で、彼は人間の心の闇にも触れることになる。果たして、葉羽は真実を見抜くことができるのか。

どんでん返し
あいうら
ミステリー
「1話完結」~最後の1行で衝撃が走る短編集~
ようやく子どもに恵まれた主人公は、家族でキャンプに来ていた。そこで偶然遭遇したのは、彼が閑職に追いやったかつての部下だった。なぜかファミリー用のテントに1人で宿泊する部下に違和感を覚えるが…
(「薪」より)

あなたの子ですが、内緒で育てます
椿蛍
恋愛
「本当にあなたの子ですか?」
突然現れた浮気相手、私の夫である国王陛下の子を身籠っているという。
夫、王妃の座、全て奪われ冷遇される日々――王宮から、追われた私のお腹には陛下の子が宿っていた。
私は強くなることを決意する。
「この子は私が育てます!」
お腹にいる子供は王の子。
王の子だけが不思議な力を持つ。
私は育った子供を連れて王宮へ戻る。
――そして、私を追い出したことを後悔してください。
※夫の後悔、浮気相手と虐げられからのざまあ
※他サイト様でも掲載しております。
※hotランキング1位&エールありがとうございます!


45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















