お気に入りに追加
24
あなたにおすすめの小説

【完】ことうの怪物いっか ~夏休みに親子で漂流したのは怪物島!? 吸血鬼と人造人間に育てられた女の子を救出せよ! ~
丹斗大巴
児童書・童話
どきどきヒヤヒヤの夏休み!小学生とその両親が流れ着いたのは、モンスターの住む孤島!?
*☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆*
夏休み、家族で出掛けた先でクルーザーが転覆し、漂流した青山親子の3人。とある島に流れ着くと、古風で顔色の悪い外国人と、大怪我を負ったという気味の悪い執事、そしてあどけない少女が住んでいた。なんと、彼らの正体は吸血鬼と、その吸血鬼に作られた人造人間! 人間の少女を救い出し、無事に島から脱出できるのか……!?
*☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆*
家族のきずなと種を超えた友情の物語。

いつか私もこの世を去るから
T
児童書・童話
母と2人で東京で生きてきた14歳の上村 糸は、母の死をきっかけに母の祖母が住む田舎の村、神坂村に引っ越す事になる。
糸の曽祖母は、巫女であり死んだ人の魂を降ろせる"カミサマ"と呼ばれる神事が出来る不思議な人だった。
そこで、糸はあるきっかけで荒木 光と言う1つ年上の村の男の子と出会う。
2人は昔から村に伝わる、願いを叶えてくれる祠を探す事になるが、そのうちに自分の本来の定めを知る事になる。

千尋の杜
深水千世
児童書・童話
千尋が祖父の家の近くにある神社で出会ったのは自分と同じ名を持つ少女チヒロだった。
束の間のやりとりで2人は心を通わせたかに見えたが……。
一夏の縁が千尋の心に残したものとは。
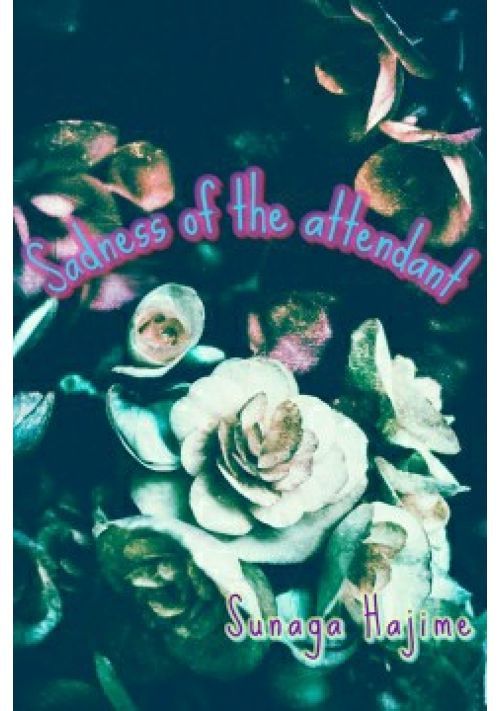
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

星座の作り方
月島鏡
児童書・童話
「君、自分で星座作ったりしてみない⁉︎」
それは、星が光る夜のお伽話。
天文学者を目指す少年シエルと、星の女神ライラの物語。
ライラと出会い、願いの意味を、大切なものを知り、シエルが自分の道を歩き出すまでのお話。
自分の願いにだけは、絶対に嘘を吐かないで


ヒョイラレ
如月芳美
児童書・童話
中学に入って関東デビューを果たした俺は、急いで帰宅しようとして階段で足を滑らせる。
階段から落下した俺が目を覚ますと、しましまのモフモフになっている!
しかも生きて歩いてる『俺』を目の当たりにすることに。
その『俺』はとんでもなく困り果てていて……。
どうやら転生した奴が俺の体を使ってる!?

花が咲く
N
児童書・童話
花の妖精は、その一生を終えるとき、つぼみに宿り花を咲かせる。
高い位置に咲く花や、鮮やかな花を咲かせる妖精は、誇り高い妖精だとされている。
そんな中、生まれつき左腕を持たない妖精がいた。
本当に大切なことは何なのか。本当に誇り高い生き方とは何なのか。幸せとは何なのか。
花を咲かせるまでの一生を通して、あらゆるものが見えてくる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















