お気に入りに追加
24
あなたにおすすめの小説

いつか私もこの世を去るから
T
児童書・童話
母と2人で東京で生きてきた14歳の上村 糸は、母の死をきっかけに母の祖母が住む田舎の村、神坂村に引っ越す事になる。
糸の曽祖母は、巫女であり死んだ人の魂を降ろせる"カミサマ"と呼ばれる神事が出来る不思議な人だった。
そこで、糸はあるきっかけで荒木 光と言う1つ年上の村の男の子と出会う。
2人は昔から村に伝わる、願いを叶えてくれる祠を探す事になるが、そのうちに自分の本来の定めを知る事になる。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。
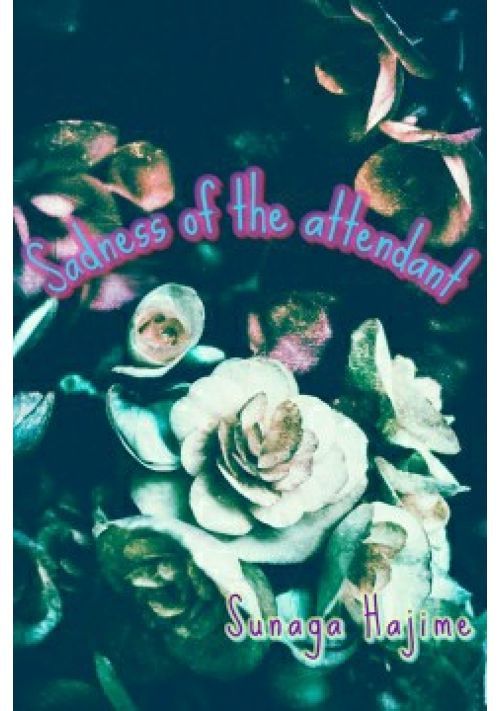
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

ヒョイラレ
如月芳美
児童書・童話
中学に入って関東デビューを果たした俺は、急いで帰宅しようとして階段で足を滑らせる。
階段から落下した俺が目を覚ますと、しましまのモフモフになっている!
しかも生きて歩いてる『俺』を目の当たりにすることに。
その『俺』はとんでもなく困り果てていて……。
どうやら転生した奴が俺の体を使ってる!?


宝石のお姫さま
近衛いさみ
児童書・童話
石の国に住むお姫さま。誰からも慕われる可愛いお姫さまです。宝石が大好きな女の子。彼女には秘密があります。石の町の裏路地にある小さな宝石屋さん。お姫さまは今日も城を抜け出し、宝石店に立ちます。
宝石の力を取り出せる不思議な力を持ったお姫さまが、様々な人たちと織りなす、心温まる物語です。

妖精コッパ
ねる
児童書・童話
妖精の国に住むコッパはフローラ姫が好きだった。
フローラ姫に会うために城に向かったが……
童話物です。
他サイトから転載しました。
2020/1/22 「妖精コッパ」を一部修正しました。
画像を追加しました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















