お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説
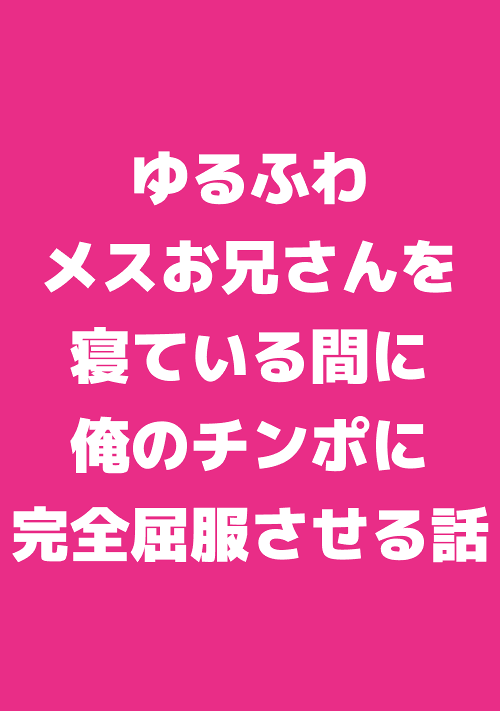
ゆるふわメスお兄さんを寝ている間に俺のチンポに完全屈服させる話
さくた
BL
攻め:浩介(こうすけ)
奏音とは大学の先輩後輩関係
受け:奏音(かなと)
同性と付き合うのは浩介が初めて
いつも以上に孕むだのなんだの言いまくってるし攻めのセリフにも♡がつく

【完結】遍く、歪んだ花たちに。
古都まとい
BL
職場の部下 和泉周(いずみしゅう)は、はっきり言って根暗でオタクっぽい。目にかかる長い前髪に、覇気のない視線を隠す黒縁眼鏡。仕事ぶりは可もなく不可もなく。そう、凡人の中の凡人である。
和泉の直属の上司である村谷(むらや)はある日、ひょんなことから繁華街のホストクラブへと連れて行かれてしまう。そこで出会ったNo.1ホスト天音(あまね)には、どこか和泉の面影があって――。
「先輩、僕のこと何も知っちゃいないくせに」
No.1ホスト部下×堅物上司の現代BL。

僕を拾ってくれたのはイケメン社長さんでした
なの
BL
社長になって1年、父の葬儀でその少年に出会った。
「あんたのせいよ。あんたさえいなかったら、あの人は死なずに済んだのに…」
高校にも通わせてもらえず、実母の恋人にいいように身体を弄ばれていたことを知った。
そんな理不尽なことがあっていいのか、人は誰でも幸せになる権利があるのに…
その少年は昔、誰よりも可愛がってた犬に似ていた。
ついその犬を思い出してしまい、その少年を幸せにしたいと思うようになった。
かわいそうな人生を送ってきた少年とイケメン社長が出会い、恋に落ちるまで…
ハッピーエンドです。
R18の場面には※をつけます。

目覚ましに先輩の声を使ってたらバレた話
ベータヴィレッジ 現実沈殿村落
BL
サッカー部の先輩・ハヤトの声が密かに大好きなミノル。
彼を誘い家に泊まってもらった翌朝、目覚ましが鳴った。
……あ。
音声アラームを先輩の声にしているのがバレた。
しかもボイスレコーダーでこっそり録音していたことも白状することに。
やばい、どうしよう。


年上が敷かれるタイプの短編集
あかさたな!
BL
年下が責める系のお話が多めです。
予告なくr18な内容に入ってしまうので、取扱注意です!
全話独立したお話です!
【開放的なところでされるがままな先輩】【弟の寝込みを襲うが返り討ちにあう兄】【浮気を疑われ恋人にタジタジにされる先輩】【幼い主人に狩られるピュアな執事】【サービスが良すぎるエステティシャン】【部室で思い出づくり】【No.1の女王様を屈服させる】【吸血鬼を拾ったら】【人間とヴァンパイアの逆転主従関係】【幼馴染の力関係って決まっている】【拗ねている弟を甘やかす兄】【ドSな執着系執事】【やはり天才には勝てない秀才】
------------------
新しい短編集を出しました。
詳しくはプロフィールをご覧いただけると幸いです。

【完結】ぎゅって抱っこして
かずえ
BL
幼児教育学科の短大に通う村瀬一太。訳あって普通の高校に通えなかったため、働いて貯めたお金で二年間だけでもと大学に入学してみたが、学費と生活費を稼ぎつつ学校に通うのは、考えていたよりも厳しい……。
でも、頼れる者は誰もいない。
自分で頑張らなきゃ。
本気なら何でもできるはず。
でも、ある日、金持ちの坊っちゃんと心の中で呼んでいた松島晃に苦手なピアノの課題で助けてもらってから、どうにも自分の心がコントロールできなくなって……。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















