お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……
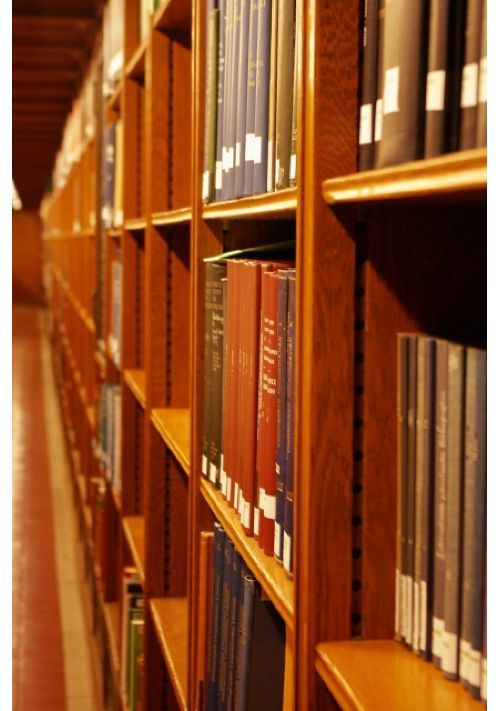
文学少女のラブレター
シャルロット(Charlotte)
ミステリー
俊介と真衣は仲良しの先輩と後輩。
読書好きな二人は、今日も高校の図書館でばったり会う。
そんなとき、同級生の真由が持ち込んだとある暗号。
俊介はその解読に取り組むが。。。
高校生たちの甘酸っぱい想いが揺れる、青春ミステリー【全3話】

朱糸
黒幕横丁
ミステリー
それは、幸福を騙った呪い(のろい)、そして、真を隠した呪い(まじない)。
Worstの探偵、弐沙(つぐさ)は依頼人から朱絆(しゅばん)神社で授与している朱糸守(しゅしまもり)についての調査を依頼される。
そのお守りは縁結びのお守りとして有名だが、お守りの中身を見たが最後呪い殺されるという噂があった。依頼人も不注意によりお守りの中身を覗いたことにより、依頼してから数日後、変死体となって発見される。
そんな変死体事件が複数発生していることを知った弐沙と弐沙に瓜二つに変装している怜(れい)は、そのお守りについて調査することになった。
これは、呪い(のろい)と呪い(まじない)の話

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

山蛭様といっしょ。
ちづ
キャラ文芸
ダーク和風ファンタジー異類婚姻譚です。
和風吸血鬼(ヒル)と虐げられた村娘の話。短編ですので、もしよかったら。
不気味な恋を目指しております。
気持ちは少女漫画ですが、
残酷描写、ヒル等の虫の描写がありますので、苦手な方又は15歳未満の方はご注意ください。
表紙はかんたん表紙メーカーさんで作らせて頂きました。https://sscard.monokakitools.net/covermaker.html

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。

この満ち足りた匣庭の中で 二章―Moon of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
それこそが、赤い満月へと至るのだろうか――
『満ち足りた暮らし』をコンセプトとして発展を遂げてきたニュータウン、満生台。
更なる発展を掲げ、電波塔計画が進められ……そして二〇一二年の八月、地図から消えた街。
鬼の伝承に浸食されていく混沌の街で、再び二週間の物語は幕を開ける。
古くより伝えられてきた、赤い満月が昇るその夜まで。
オートマティスム、鬼封じの池、『八〇二』の数字。
ムーンスパロー、周波数帯、デリンジャー現象。
ブラッドムーン、潮汐力、盈虧院……。
ほら、また頭の中に響いてくる鬼の声。
逃れられない惨劇へ向けて、私たちはただ日々を重ねていく――。
出題篇PV:https://www.youtube.com/watch?v=1mjjf9TY6Io

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















