12 / 20
2、藤の姫
八、
しおりを挟む
「坊や、可愛いねぇ」
襟を破かれる。
甘ったるいような、生臭いような臭いがする。明晴が逃げようとしても、大人の力に勝てるわけがない。衣を剥ぎ取られ、自分で触ったことのないような場所をまさぐられる。
(いやだ)
明晴がもがいても、相手は力を緩めることはなかった。
「可愛いから、いいことしてあげるの。いいでしょう」
いいわけない。なのに、相手はそれが明晴のためだとでも言うように、好き勝手に体に手や舌を這わせた。
(厭だ)
(そこに俺の意志なんてない)
(触らないで)
(誰も、俺に――)
気づくと、手には見覚えのない紙が握られていた。
(そうだ――俺は、弱くない。もう、誰にも……誰にも俺を好きになんてさせない……)
明晴は、女の喉元目がけて叫んだ。
「――斬ッ!」
◇◆◇
微睡みの中、人の気配を感じる。反射的に腕を動かしていた。
「初音どの!」
その叫び声に、明晴は目を開いた。同時に、風の刃が飛んで行った。刃は御簾を斬り裂いた。――初音の白い頬を通り抜けて。
初音は驚きのあまり、眼を皿のように丸くしながら、仙千代の胸に倒れ込んでいる。恐らく仙千代が咄嗟に庇ってくれたのだろう。そうでなければ――明晴は、間違いなく初音を――。
「明晴……」
初音の手が伸びてくる。白い指先――明晴はその指先を無意識に払いのけていた。
「触るな!」
廊下から、足音が聞こえてくる。
(ああもう――そんな騒いだら、人にも聞こえちゃうよ……隠形の意味ないじゃん)
次の瞬間、紅葉が息を切らして現れた。壊れた御簾を踏みながら、紅葉は明晴の傍に膝を突いた。――初音達から、明晴を隠すように。
「明晴」
「紅葉……俺……」
「大丈夫だ」
紅葉は明晴の肩に両手を置いた。掌の重みを感じると、明晴の目頭は熱くなった。
「お前はまだ、誰も殺していない」
そして、紅葉は、固まったまま動けない初音を振り返った。
「初音。今しばらく――席を外して」
初音はゆるゆると首を横に振った。
「いや。明晴を、置いていけない……」
「……そこに、明晴の眷属がいるのか?」
仙千代が眉間に皺を寄せる。見えないなりに、初音の様子を見て何か察したらしい。仙千代は初音の腕を掴んだ。
「初音どの、行こう」
「万見どの、でも、明晴が……」
「まだ分からないのか」
仙千代は、明晴を見ないまま言った。――その表情には軽蔑と恐れを含んだような――明晴に対する拒絶の色が含まれている。
「今の初音どのと明晴を、同じ部屋に置くことはできない」
仙千代は、立ち上がろうとしない初音の腕を無理やり引いて立たせると、部屋を出て行った。明晴のことを振り返った気配は、一度もなかった。
一方、初音は何度も明晴を振り返っているようだった。しかし、彼女の顔を見ることが怖い。足音が消えなくなるまで、明晴は顔を上げることはできなかった。
(……やってしまった)
明晴は両手で顔を覆った。
悪夢を思い出して――市井の人を殺めそうになった。それも、初音を。紅葉は「お前のせいではない」と慰めてくれたが、素直にそうだ、と言うことなどできはしない。
つん、と鼻を刺す独特の臭いがする。布団の脇には、割れた茶碗が転がっていた。どうやら初音が薬湯を運んでくれたらしい。よかれと思ってくれたのだろうに――その優しさを踏みつけにした挙句、明晴は初音の命を奪いそうになった。
「どだい無理な話だったんだ」
「明晴……?」
「俺が、人並みの幸せを、なんて」
あわよくば初音と一緒に、普通の人の暮らしをしたい、なんて。それがいかに思い上がった、図々しい発言だったのか思い出す。
(この一件が終わったら――信長さまに、お願いしよう。岐阜を出て行きたいって)
明晴は、拳を握り締めた。ずっと願っていた幸せを自分で壊してしまった。己の弱さが情けなくて、恥ずかしくて、悔しくて。その日は一晩中泣き明かした。
襟を破かれる。
甘ったるいような、生臭いような臭いがする。明晴が逃げようとしても、大人の力に勝てるわけがない。衣を剥ぎ取られ、自分で触ったことのないような場所をまさぐられる。
(いやだ)
明晴がもがいても、相手は力を緩めることはなかった。
「可愛いから、いいことしてあげるの。いいでしょう」
いいわけない。なのに、相手はそれが明晴のためだとでも言うように、好き勝手に体に手や舌を這わせた。
(厭だ)
(そこに俺の意志なんてない)
(触らないで)
(誰も、俺に――)
気づくと、手には見覚えのない紙が握られていた。
(そうだ――俺は、弱くない。もう、誰にも……誰にも俺を好きになんてさせない……)
明晴は、女の喉元目がけて叫んだ。
「――斬ッ!」
◇◆◇
微睡みの中、人の気配を感じる。反射的に腕を動かしていた。
「初音どの!」
その叫び声に、明晴は目を開いた。同時に、風の刃が飛んで行った。刃は御簾を斬り裂いた。――初音の白い頬を通り抜けて。
初音は驚きのあまり、眼を皿のように丸くしながら、仙千代の胸に倒れ込んでいる。恐らく仙千代が咄嗟に庇ってくれたのだろう。そうでなければ――明晴は、間違いなく初音を――。
「明晴……」
初音の手が伸びてくる。白い指先――明晴はその指先を無意識に払いのけていた。
「触るな!」
廊下から、足音が聞こえてくる。
(ああもう――そんな騒いだら、人にも聞こえちゃうよ……隠形の意味ないじゃん)
次の瞬間、紅葉が息を切らして現れた。壊れた御簾を踏みながら、紅葉は明晴の傍に膝を突いた。――初音達から、明晴を隠すように。
「明晴」
「紅葉……俺……」
「大丈夫だ」
紅葉は明晴の肩に両手を置いた。掌の重みを感じると、明晴の目頭は熱くなった。
「お前はまだ、誰も殺していない」
そして、紅葉は、固まったまま動けない初音を振り返った。
「初音。今しばらく――席を外して」
初音はゆるゆると首を横に振った。
「いや。明晴を、置いていけない……」
「……そこに、明晴の眷属がいるのか?」
仙千代が眉間に皺を寄せる。見えないなりに、初音の様子を見て何か察したらしい。仙千代は初音の腕を掴んだ。
「初音どの、行こう」
「万見どの、でも、明晴が……」
「まだ分からないのか」
仙千代は、明晴を見ないまま言った。――その表情には軽蔑と恐れを含んだような――明晴に対する拒絶の色が含まれている。
「今の初音どのと明晴を、同じ部屋に置くことはできない」
仙千代は、立ち上がろうとしない初音の腕を無理やり引いて立たせると、部屋を出て行った。明晴のことを振り返った気配は、一度もなかった。
一方、初音は何度も明晴を振り返っているようだった。しかし、彼女の顔を見ることが怖い。足音が消えなくなるまで、明晴は顔を上げることはできなかった。
(……やってしまった)
明晴は両手で顔を覆った。
悪夢を思い出して――市井の人を殺めそうになった。それも、初音を。紅葉は「お前のせいではない」と慰めてくれたが、素直にそうだ、と言うことなどできはしない。
つん、と鼻を刺す独特の臭いがする。布団の脇には、割れた茶碗が転がっていた。どうやら初音が薬湯を運んでくれたらしい。よかれと思ってくれたのだろうに――その優しさを踏みつけにした挙句、明晴は初音の命を奪いそうになった。
「どだい無理な話だったんだ」
「明晴……?」
「俺が、人並みの幸せを、なんて」
あわよくば初音と一緒に、普通の人の暮らしをしたい、なんて。それがいかに思い上がった、図々しい発言だったのか思い出す。
(この一件が終わったら――信長さまに、お願いしよう。岐阜を出て行きたいって)
明晴は、拳を握り締めた。ずっと願っていた幸せを自分で壊してしまった。己の弱さが情けなくて、恥ずかしくて、悔しくて。その日は一晩中泣き明かした。
1
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

暁天一縷 To keep calling your name
真道 乃ベイ
ファンタジー
命日の夏に、私たちは出会った。
妖魔・怨霊の大災害「災禍」を引き起す日本国。
政府は霊力を生業とする者を集め陰陽寮を設立するが、事態は混沌を極め大戦の時代を迎える。
災禍に傷付き、息絶える者は止まない絶望の最中。
ひとりの陰陽師が、永きに渡る大戦を終結させた。
名を、斉天大聖。
非業の死を成し遂げた聖人として扱われ、日本国は復興の兆しを歩んでいく。
それから、12年の歳月が過ぎ。
人々の平和と妖魔たちの非日常。
互いの世界が干渉しないよう、境界に線を入れる青年がいた。
職業、結界整備師。
名は、桜下。
過去の聖人に関心を持てず、今日も仕事をこなす多忙な日々を送る。
そんな、とある猛暑の日。
斉天大聖の命日である斉天祭で、彼らは巡り会う。
青い目の検非違使と、緋色の髪の舞師。
そして黒瑪瑙の陰陽師。
彼らの運命が交差し、明けない夜空に一縷の光を灯す。
※毎月16日更新中(現在本編投稿休止中、2025年6月より2章開始予定)

幼い公女様は愛されたいと願うのやめました。~態度を変えた途端、家族が溺愛してくるのはなぜですか?~
朱色の谷
ファンタジー
公爵家の末娘として生まれた6歳のティアナ
お屋敷で働いている使用人に虐げられ『公爵家の汚点』と呼ばれる始末。
お父様やお兄様は私に関心がないみたい。愛されたいと願い、愛想よく振る舞っていたが一向に興味を示してくれない…
そんな中、夢の中の本を読むと、、、
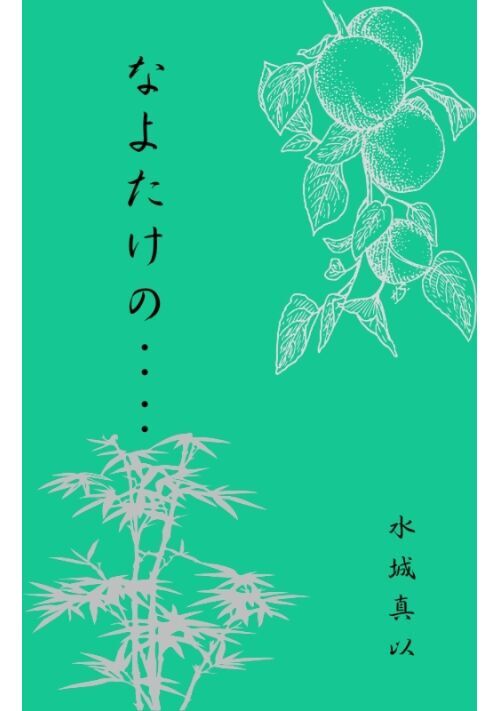


裏公務の神様事件簿 ─神様のバディはじめました─
只深
ファンタジー
20xx年、日本は謎の天変地異に悩まされていた。
相次ぐ河川の氾濫、季節を無視した気温の変化、突然大地が隆起し、建物は倒壊。
全ての基礎が壊れ、人々の生活は自給自足の時代──まるで、時代が巻き戻ってしまったかのような貧困生活を余儀なくされていた。
クビにならないと言われていた公務員をクビになり、謎の力に目覚めた主人公はある日突然神様に出会う。
「そなたといたら、何か面白いことがあるのか?」
自分への問いかけと思わず適当に答えたが、それよって依代に選ばれ、見たことも聞いたこともない陰陽師…現代の陰陽寮、秘匿された存在の【裏公務員】として仕事をする事になった。
「恋してちゅーすると言ったのは嘘か」
「勘弁してくれ」
そんな二人のバディが織りなす和風ファンタジー、陰陽師の世直し事件簿が始まる。
優しさと悲しさと、切なさと暖かさ…そして心の中に大切な何かが生まれる物語。
※BLに見える表現がありますがBLではありません。
※現在一話から改稿中。毎日近況ノートにご報告しておりますので是非また一話からご覧ください♪

戦国時代を冒険する少女 〜憧れの戦国武将と共に〜
紅夜チャンプル
ファンタジー
少女の夢は戦国武将に会うこと。それが叶う時、彼女は何を思う?
小学校低学年の綾菜(あやな)は戦国武将に会いたいという夢がある。
ある晩に目が覚めた綾菜。何と周り一面が焼け野原であった。そこに現れし馬に乗った武将。綾菜がその武将の馬に乗せてもらって、戦国時代の旅に出る。
実際の戦いを見た綾菜が思ったことは‥‥
その他にも‥‥綾菜の様々な冒険を連載していきます。優しめのファンタジー、ゆるく更新予定です。

特殊部隊の俺が転生すると、目の前で絶世の美人母娘が犯されそうで助けたら、とんでもないヤンデレ貴族だった
なるとし
ファンタジー
鷹取晴翔(たかとりはると)は陸上自衛隊のとある特殊部隊に所属している。だが、ある日、訓練の途中、不慮の事故に遭い、異世界に転生することとなる。
特殊部隊で使っていた武器や防具などを召喚できる特殊能力を謎の存在から授かり、目を開けたら、絶世の美女とも呼ばれる母娘が男たちによって犯されそうになっていた。
武装状態の鷹取晴翔は、持ち前の優秀な身体能力と武器を使い、その母娘と敷地にいる使用人たちを救う。
だけど、その母と娘二人は、
とおおおおんでもないヤンデレだった……
第3回次世代ファンタジーカップに出すために一部を修正して投稿したものです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















