11 / 28
きみの肖像
きみがいなくなった
しおりを挟む
きみがいなくなった。なにも言わずにただいなくなっていた。
気づいたらいなくなっていた。
きみの部屋の前に立ち、きみの身に何が起きたのか、しばらく途方に暮れた。
きみがいなくなった原因にまったく思い当たるところがないからだ。
そもそも、いないという事実そのものが飲み込めない。いくら考えても思いつきもしない。
逡巡したのち、ぼくはきみの部屋をノックした。
装飾もない、シンプルな白木の扉はコンコンコンッ……と乾いた音を立てるだけで、中からきみの声は返って来ない。
――からっぽな音だな。
扉のノブにそっと手をかけて回してみる。鍵が掛かっている手ごたえはなく、ノブは軽やかに回った。そのままゆっくりと引く。油が足りない軋んだ声を上げながら、扉はそろりと開いた。
一歩玄関へ足を踏み入れると、部屋の中は真っ暗だった。
ザラザラとした壁紙を撫でながら、灯りを探した。電気スイッチのつるりとした感触がある。
スイッチを押す。途端、パチンッと火花が弾けるように真っ暗だった廊下が明るくなった。奥に続く長い廊下は、その周りを取り巻く白い壁とは対照的に、行けば行くほど闇に沈んで、スイッチの灯りすらも飲み込んでしまっている。
はやる気持ちを抑えて、静かに廊下を行く。進むほどに空気が冷え冷えとして、つま先がじんじんした。突き当たりの扉の前に来る頃には、息は真っ白になっていた。
扉は取っ手までが光沢のない黒で、悪意に塗りつぶされたようで薄気味が悪い。
それでも開けなければならないという使命感とともに、かじかむ手をこすり合わせてから玄関扉を開けるときと同じようにそっと引いた。びくともしない。一切を拒絶する――そう言われている気がした。
しかし、ここを開けなければ始まらない。ふうっと息を整える。両手を添えて、腰を落とした。両足を踏ん張り、一気に力を入れて引いた。
ざりざりと錆びがはがれる嫌な音がした。ノブが氷でできているみたいに冷たくて、張りついてしまいそうだ。数センチずつしか動かない扉を何度も何度も引いて、部屋に入った。
ここも真っ暗だった。扉付近を探って電気をつける。チカチカッと蛍光灯がまたたいた。いつ消えてもおかしくない、非常に頼りない薄らぼけた光が部屋を照らした。
「えっ……」
予想もしていなかった惨状に、上ずった声が漏れた。
外部を遮断するように固く閉ざされた窓。ズタズタに切り裂かれたカーテン。一切片付けされていない散らかり放題の部屋。
真っ白い紙の書類たちが床に散乱し、いろんなメモが壁一面をびっしり埋め尽くすみたいに貼りつけてある。
卓上カレンダーの数字は三日前まで赤いペンで大きくバッテンがつけられていた。
放り出したままのペン先は乾いて使えなくなっている。
――いったいなにがあったの?
カレンダーを手に取って、バッテンがつけられている三日前を思い出す。
部屋の前にきみはいた。
「おはよう」
そうやって、いつものように声を掛けたのはたしか三日前の朝のことだ。
あのときのきみは笑っていた。いつものように普通に部屋から出てきていたはずだ。あのとき、扉はすんなり開いていたとも思う。
「おはよう」
背筋をしゃんと伸ばして笑っていたきみ。
でも、視線はどうだったか。合っていたのか、いなかったのか。どうしてハッキリ思い出せないのだろう。
「今日はいい天気だね」
「そうだね」
「最近はどう?」
「まあまあだよ」
「楽しいことはある?」
「まあまあだよ」
「そうか。今日もいい日だといいね」
「そうだね」
思えば、きみの返事はとても平板だった(心がどこかに行ってしまった……)ように思える。
だけどきみが笑っていたから(かすかだったけれど……)気に留めなかった。気に留める必要もなかったんだ。
だって、いつだってきみとは一緒だったから。
いなくなるなんてことを一度だって考えたことなんかなかったんだから。
――きみになにがあったの?
灯りがチカチカと明滅して、天井を見上げたぼくは息を飲んだ。
目じりの皮がびりびり引っ張られるくらい目を見張る。瞳孔が大きく開く。
呼吸の仕方を忘れかけた。唾が飲み込めない。
心臓に一気に火がついて、バクバクと大きな音を立てて駆け足になった。
なのに、寒くて仕方ない。
カチカチと歯が鳴り、膝はガクガクと震えている。
胸が苦しい。頭が痛い。あふれ出してくる思いを握り締めるように、ぎゅうっと胸元のシャツを掴んだ。
『たすけて』
赤いペンキで殴りつけるように書かれた文字。大きいものから小さいものまで、隙間なくびっちりと埋め尽くされた天井。天井からポトリ……と赤い文字が落ちて来た。文字はぐにゃりと溶けたかと思うと、手のひらくらいの大きさのムカデに形を変えた。
ぽと。ぽと。ぽと。ぽと……文字がどんどん剥がれ落ちてきて、それがいちいちムカデへと変わっていく。ムカデたちは群れて列を作り、ぞろぞろとぼくへ向かって這って来る。それがぼくにはきみの体から流れ出た血に見えた。きみの血が、ぼくを求めてやってくるように見えた。
『たすけて』
脳内で喉をかき切るようなきみの叫び声が聞こえた。
『たすけてたすけてたすけてたすけて……』
ムカデたちがつま先から脚へと昇ってこようとしている。払っても、踏みつけても、天井からぽとぽと、ぽとぽと雨垂れみたいに落ちてくるムカデが、ぼくを飲み込もうと追いすがって来る。
――探さなきゃ!
ぼくは転がるように部屋を飛び出した。
『たすけてたすけてたすけてたすけて……』
いなくなったきみを探さなきゃ!
気づいたらいなくなっていた。
きみの部屋の前に立ち、きみの身に何が起きたのか、しばらく途方に暮れた。
きみがいなくなった原因にまったく思い当たるところがないからだ。
そもそも、いないという事実そのものが飲み込めない。いくら考えても思いつきもしない。
逡巡したのち、ぼくはきみの部屋をノックした。
装飾もない、シンプルな白木の扉はコンコンコンッ……と乾いた音を立てるだけで、中からきみの声は返って来ない。
――からっぽな音だな。
扉のノブにそっと手をかけて回してみる。鍵が掛かっている手ごたえはなく、ノブは軽やかに回った。そのままゆっくりと引く。油が足りない軋んだ声を上げながら、扉はそろりと開いた。
一歩玄関へ足を踏み入れると、部屋の中は真っ暗だった。
ザラザラとした壁紙を撫でながら、灯りを探した。電気スイッチのつるりとした感触がある。
スイッチを押す。途端、パチンッと火花が弾けるように真っ暗だった廊下が明るくなった。奥に続く長い廊下は、その周りを取り巻く白い壁とは対照的に、行けば行くほど闇に沈んで、スイッチの灯りすらも飲み込んでしまっている。
はやる気持ちを抑えて、静かに廊下を行く。進むほどに空気が冷え冷えとして、つま先がじんじんした。突き当たりの扉の前に来る頃には、息は真っ白になっていた。
扉は取っ手までが光沢のない黒で、悪意に塗りつぶされたようで薄気味が悪い。
それでも開けなければならないという使命感とともに、かじかむ手をこすり合わせてから玄関扉を開けるときと同じようにそっと引いた。びくともしない。一切を拒絶する――そう言われている気がした。
しかし、ここを開けなければ始まらない。ふうっと息を整える。両手を添えて、腰を落とした。両足を踏ん張り、一気に力を入れて引いた。
ざりざりと錆びがはがれる嫌な音がした。ノブが氷でできているみたいに冷たくて、張りついてしまいそうだ。数センチずつしか動かない扉を何度も何度も引いて、部屋に入った。
ここも真っ暗だった。扉付近を探って電気をつける。チカチカッと蛍光灯がまたたいた。いつ消えてもおかしくない、非常に頼りない薄らぼけた光が部屋を照らした。
「えっ……」
予想もしていなかった惨状に、上ずった声が漏れた。
外部を遮断するように固く閉ざされた窓。ズタズタに切り裂かれたカーテン。一切片付けされていない散らかり放題の部屋。
真っ白い紙の書類たちが床に散乱し、いろんなメモが壁一面をびっしり埋め尽くすみたいに貼りつけてある。
卓上カレンダーの数字は三日前まで赤いペンで大きくバッテンがつけられていた。
放り出したままのペン先は乾いて使えなくなっている。
――いったいなにがあったの?
カレンダーを手に取って、バッテンがつけられている三日前を思い出す。
部屋の前にきみはいた。
「おはよう」
そうやって、いつものように声を掛けたのはたしか三日前の朝のことだ。
あのときのきみは笑っていた。いつものように普通に部屋から出てきていたはずだ。あのとき、扉はすんなり開いていたとも思う。
「おはよう」
背筋をしゃんと伸ばして笑っていたきみ。
でも、視線はどうだったか。合っていたのか、いなかったのか。どうしてハッキリ思い出せないのだろう。
「今日はいい天気だね」
「そうだね」
「最近はどう?」
「まあまあだよ」
「楽しいことはある?」
「まあまあだよ」
「そうか。今日もいい日だといいね」
「そうだね」
思えば、きみの返事はとても平板だった(心がどこかに行ってしまった……)ように思える。
だけどきみが笑っていたから(かすかだったけれど……)気に留めなかった。気に留める必要もなかったんだ。
だって、いつだってきみとは一緒だったから。
いなくなるなんてことを一度だって考えたことなんかなかったんだから。
――きみになにがあったの?
灯りがチカチカと明滅して、天井を見上げたぼくは息を飲んだ。
目じりの皮がびりびり引っ張られるくらい目を見張る。瞳孔が大きく開く。
呼吸の仕方を忘れかけた。唾が飲み込めない。
心臓に一気に火がついて、バクバクと大きな音を立てて駆け足になった。
なのに、寒くて仕方ない。
カチカチと歯が鳴り、膝はガクガクと震えている。
胸が苦しい。頭が痛い。あふれ出してくる思いを握り締めるように、ぎゅうっと胸元のシャツを掴んだ。
『たすけて』
赤いペンキで殴りつけるように書かれた文字。大きいものから小さいものまで、隙間なくびっちりと埋め尽くされた天井。天井からポトリ……と赤い文字が落ちて来た。文字はぐにゃりと溶けたかと思うと、手のひらくらいの大きさのムカデに形を変えた。
ぽと。ぽと。ぽと。ぽと……文字がどんどん剥がれ落ちてきて、それがいちいちムカデへと変わっていく。ムカデたちは群れて列を作り、ぞろぞろとぼくへ向かって這って来る。それがぼくにはきみの体から流れ出た血に見えた。きみの血が、ぼくを求めてやってくるように見えた。
『たすけて』
脳内で喉をかき切るようなきみの叫び声が聞こえた。
『たすけてたすけてたすけてたすけて……』
ムカデたちがつま先から脚へと昇ってこようとしている。払っても、踏みつけても、天井からぽとぽと、ぽとぽと雨垂れみたいに落ちてくるムカデが、ぼくを飲み込もうと追いすがって来る。
――探さなきゃ!
ぼくは転がるように部屋を飛び出した。
『たすけてたすけてたすけてたすけて……』
いなくなったきみを探さなきゃ!
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る
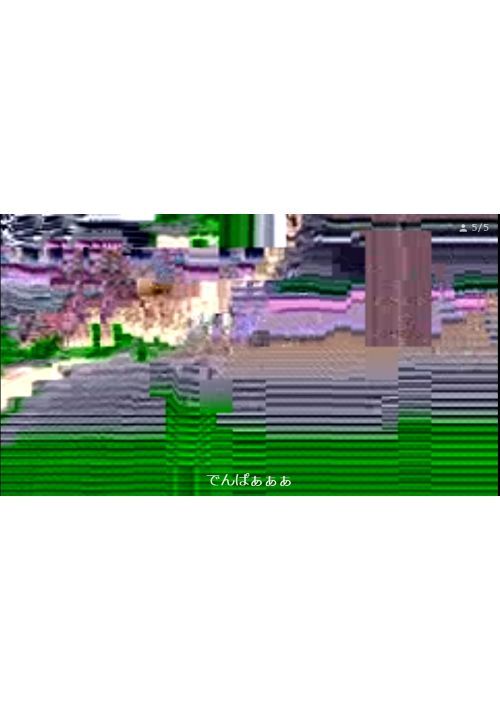

最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

花の檻
蒼琉璃
ホラー
東京で連続して起きる、通称『連続種死殺人事件』は人々を恐怖のどん底に落としていた。
それが明るみになったのは、桜井鳴海の死が白昼堂々渋谷のスクランブル交差点で公開処刑されたからだ。
唯一の身内を、心身とも殺された高階葵(たかしなあおい)による、異能復讐物語。
刑事鬼頭と犯罪心理学者佐伯との攻防の末にある、葵の未来とは………。
Illustrator がんそん様 Suico様
※ホラーミステリー大賞作品。
※グロテスク・スプラッター要素あり。
※シリアス。
※ホラーミステリー。
※犯罪描写などがありますが、それらは悪として書いています。


就職面接の感ドコロ!?
フルーツパフェ
大衆娯楽
今や十年前とは真逆の、売り手市場の就職活動。
学生達は賃金と休暇を貪欲に追い求め、いつ送られてくるかわからない採用辞退メールに怯えながら、それでも優秀な人材を発掘しようとしていた。
その業務ストレスのせいだろうか。
ある面接官は、女子学生達のリクルートスーツに興奮する性癖を備え、仕事のストレスから面接の現場を愉しむことに決めたのだった。

#彼女を探して・・・
杉 孝子
ホラー
佳苗はある日、SNSで不気味なハッシュタグ『#彼女を探して』という投稿を偶然見かける。それは、特定の人物を探していると思われたが、少し不気味な雰囲気を醸し出していた。日が経つにつれて、そのタグの投稿が急増しSNS上では都市伝説の話も出始めていた。

煩い人
星来香文子
ホラー
陽光学園高学校は、新校舎建設中の間、夜間学校・月光学園の校舎を昼の間借りることになった。
「夜七時以降、陽光学園の生徒は校舎にいてはいけない」という校則があるのにも関わらず、ある一人の女子生徒が忘れ物を取りに行ってしまう。
彼女はそこで、肌も髪も真っ白で、美しい人を見た。
それから彼女は何度も狂ったように夜の学校に出入りするようになり、いつの間にか姿を消したという。
彼女の親友だった美波は、真相を探るため一人、夜間学校に潜入するのだが……
(全7話)
※タイトルは「わずらいびと」と読みます
※カクヨムでも掲載しています
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















