お気に入りに追加
58
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

思い出を売った女
志波 連
ライト文芸
結婚して三年、あれほど愛していると言っていた夫の浮気を知った裕子。
それでもいつかは戻って来ることを信じて耐えることを決意するも、浮気相手からの執拗な嫌がらせに心が折れてしまい、離婚届を置いて姿を消した。
浮気を後悔した孝志は裕子を探すが、痕跡さえ見つけられない。
浮気相手が妊娠し、子供のために再婚したが上手くいくはずもなかった。
全てに疲弊した孝志は故郷に戻る。
ある日、子供を連れて出掛けた海辺の公園でかつての妻に再会する。
あの頃のように明るい笑顔を浮かべる裕子に、孝志は二度目の一目惚れをした。
R15は保険です
他サイトでも公開しています
表紙は写真ACより引用しました

ダブル シークレットベビー ~御曹司の献身~
菱沼あゆ
恋愛
念願のランプのショップを開いた鞠宮あかり。
だが、開店早々、植え込みに猫とおばあさんを避けた車が突っ込んでくる。
車に乗っていたイケメン、木南青葉はインテリアや雑貨などを輸入している会社の社長で、あかりの店に出入りするようになるが。
あかりには実は、年の離れた弟ということになっている息子がいて――。

その溺愛は伝わりづらい!気弱なスパダリ御曹司にノンケの僕は落とされました
海野幻創
BL
人好きのする端正な顔立ちを持ち、文武両道でなんでも無難にこなせることのできた生田雅紀(いくたまさき)は、小さい頃から多くの友人に囲まれていた。
しかし他人との付き合いは広く浅くの最小限に留めるタイプで、女性とも身体だけの付き合いしかしてこなかった。
偶然出会った久世透(くぜとおる)は、嫉妬を覚えるほどのスタイルと美貌をもち、引け目を感じるほどの高学歴で、議員の孫であり大企業役員の息子だった。
御曹司であることにふさわしく、スマートに大金を使ってみせるところがありながら、生田の前では捨てられた子犬のようにおどおどして気弱な様子を見せ、そのギャップを生田は面白がっていたのだが……。
これまで他人と深くは関わってこなかったはずなのに、会うたびに違う一面を見せる久世は、いつしか生田にとって離れがたい存在となっていく。
【7/27完結しました。読んでいただいてありがとうございました。】
【続編も8/17完結しました。】
「その溺愛は行き場を彷徨う……気弱なスパダリ御曹司は政略結婚を回避したい」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/962473946/911896785
↑この続編は、R18の過激描写がありますので、苦手な方はご注意ください。

余命宣告を受けたので私を顧みない家族と婚約者に執着するのをやめることにしました
結城芙由奈
恋愛
【余命半年―未練を残さず生きようと決めた。】
私には血の繋がらない父と母に妹、そして婚約者がいる。しかしあの人達は私の存在を無視し、空気の様に扱う。唯一の希望であるはずの婚約者も愛らしい妹と恋愛関係にあった。皆に気に入られる為に努力し続けたが、誰も私を気に掛けてはくれない。そんな時、突然下された余命宣告。全てを諦めた私は穏やかな死を迎える為に、家族と婚約者に執着するのをやめる事にした―。
2021年9月26日:小説部門、HOTランキング部門1位になりました。ありがとうございます
*「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています
※2023年8月 書籍化

野良インコと元飼主~山で高校生活送ります~
浅葱
ライト文芸
小学生の頃、不注意で逃がしてしまったオカメインコと山の中の高校で再会した少年。
男子高校生たちと生き物たちのわちゃわちゃ青春物語、ここに開幕!
オカメインコはおとなしく臆病だと言われているのに、再会したピー太は目つきも鋭く凶暴になっていた。
学校側に乞われて男子校の治安維持部隊をしているピー太。
ピー太、お前はいったいこの学校で何をやってるわけ?
頭がよすぎるのとサバイバル生活ですっかり強くなったオカメインコと、
なかなか背が伸びなくてちっちゃいとからかわれる高校生男子が織りなす物語です。
周りもなかなか個性的ですが、主人公以外にはBLっぽい内容もありますのでご注意ください。(主人公はBLになりません)
ハッピーエンドです。R15は保険です。
表紙の写真は写真ACさんからお借りしました。

運命の番?棄てたのは貴方です
ひよこ1号
恋愛
竜人族の侯爵令嬢エデュラには愛する番が居た。二人は幼い頃に出会い、婚約していたが、番である第一王子エリンギルは、新たに番と名乗り出たリリアーデと婚約する。邪魔になったエデュラとの婚約を解消し、番を引き裂いた大罪人として追放するが……。一方で幼い頃に出会った侯爵令嬢を忘れられない帝国の皇子は、男爵令息と身分を偽り竜人国へと留学していた。
番との運命の出会いと別離の物語。番でない人々の貫く愛。
※自己設定満載ですので気を付けてください。
※性描写はないですが、一線を越える個所もあります
※多少の残酷表現あります。
以上2点からセルフレイティング
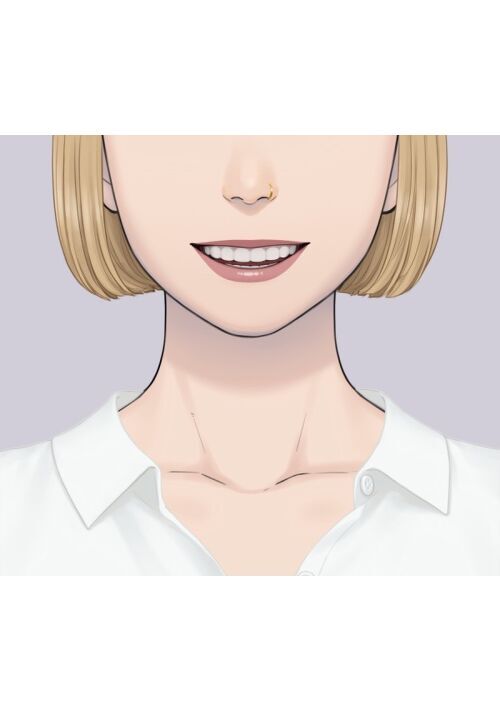
『マザーステップ』
夜神十夢(ヤガミ・トム)
ライト文芸
妊娠した百合子は直ぐに流産してしまう。友人の勧めで犬を飼うことになるが‥。
妊娠、出産は女性にとって大変な出来事です。
男性とは違った悩みを抱えたりします。
それを表現出来たらと思い筆をとりました。
まだ若輩者なので上手く描けているか不安ですが宜しくお願いします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















