4 / 21
喜志芸祭とオムライス
第四話 喜志芸祭とオムライス4
しおりを挟む
スモーキーな香りとジューシーな肉汁たっぷりのスモークチキンを堪能したあと、四人で屋台飯を食べ歩きしたり、ピアノ演奏を聞いたり、マジックショーを見たり。芸大ということもあり、レベルは高いし、何より「見てくれ!」という強い意志を持ってて、気迫もすごい。
パッと見たり、聴いたりしてその素晴らしさやすごさをお客さんにわかってもらえるのはいいなぁ……。
わたしたち文芸学科はそういう意味ではなかなか難しいといつも思う。どれだけ素敵な文章でも、読まなければわからない。内容がどうこう言う前に「文章を読むのは得意じゃないから」と一文字も読んでもらえないことだって多い。どうしたら自分の作品に触れてもらえるだろう。以前わたしが落ち込んだ、人の記憶に残るインパクトのある文章にも通じることなのかもしれないけど。
フリーマーケットコーナーで出品されたハンドメイド作品を見ても感じてしまう。小説はアクセサリーや服のように、身にまとえないもんなぁ。
「真綾、難しい顔をしているな。なにか欲しいものがあるのか」
君彦くんの声で我に返る。咲ちゃんと駿河くんは少し遠くのお店で商品を見ていて、いつの間にか二人きりになっていた。
「えっと……すごいなぁって」
「すごい?」
わたしは所狭しと並ぶお店を見渡す。
「こう、目に見えて綺麗とかかわいいとかがすぐにわかるでしょ。でも、文章はそうもいかないなぁって思っちゃった」
「ほう」
「読んでもらわないとさ、おもしろいかどうかはわからないから」
「確かにな。だが、書かれた言葉を読んで理解した者だけが面白さに気づく。一見難しそうだと思った作品でも、読んでみれば理解しやすい言い回しや文体で、気づけばのめりこんで読んでいたということはあるだろう」
「うん、あるある!」
わたしには合わないかもと思った作品が、読み進めれば進むほど目が離せなくなって、最後まで読みきった時の快感と感動は計り知れない。
「見るだけはわからない、それは文学の弱点であり、強みだ。だから、真綾も文章に悩んだりしたのだろう」
「そうだね。たぶん一生かかっても答えは見つかりそうにはないけど」
「見つからないだろうな。だからこそ、人それぞれ己の面白いと感じる言葉と言葉を合わせていく。そこに個性が出る」
「同じテーマで書いたとしても、わたしと咲ちゃん、君彦くんと駿河くん四者四様だろうね」
「そういうことだ。しかし、見ただけですべてわかることもない。さっき見たピアノ演奏やマジックにも『どう観客を魅了するか』という陰の努力はあるだろうし、服やアクセサリーも制作の過程にどれほどの工夫が隠されているだろうかと考えると奥深い」
「みんなゼロから作り上げてる……」
「簡単に完成する作品などどこにもない」
今まで創作についてこんなにお話し出来るような人がいなかった。創作のことで悩んでも自分でなんとか解決しようとあがいた。自分の解釈では限界があった。せっかく文芸学科に在籍しているんだ。君彦くん、咲ちゃん、駿河くんとももっとお話していきたい。そうすれば、嫉妬しがちで落ち込みやすい自分ももっと文章を書くこと、表現の幅が広がりそうだから。
「ごめんね。なんだか大事なこと忘れてた」
「まぁ、目で見て、または触れて、または耳で聞いて。すぐに脳を揺さぶれる表現や作品に憧れを一度も持たない物書きはいないだろう。俺もそうだ。伝わらないことのもどかしさというものを、大学に入り、読者という存在を得て初めて感じた。だが、そのもどかしさも創作の醍醐味なのかもな」
君彦くんは突然足を止めた。「服を作る際に余った布を最後の最後まで使い切るがテーマです」と書かれたポスターを張っている。
「真綾、このアクセサリー似合う気がするのだがどうだ?」
手にしていたのはバレッタだった。金の金具の上に、薄紫色の布の端切れで作ったお花が四つ並んでつけられている。
「かわいい!」
「短い髪でもバレッタなら使えると思ってな。プレゼントする」
「えっ! あ、ありがとう……!」
わたしもなにか君彦くんが使えるものはないかなと、商品の置かれた机を見ると目に入ったのは、文庫サイズのブックカバーだ。「すいません」と店員さんに声をかける。
「あの、もしかしてこれ、このバレッタと同じ布ですか?」
「そうです。同じ布で作ってあります」
わたしは君彦くんの方に向き直す。
「君彦くん、これ、わたしからプレゼントしてもいい?」
「ああ。ブックカバーはよく使用するからな」
わたしたちは早速お互いに買って、その場で渡し合う。誕生日でもなんでもない日だけど、初めてのプレゼントだ。
「ありがとう、大事にする」
「わたしも!」
咲ちゃんと駿河くんと合流し、
「じゃあ、次どうする?」
と建物の端によってパンフを広げ、次に行く場所を探す。すると、君彦くんがこめかみのあたりを押さえた。苦しそうに目を閉じ、息を吐く。
「大丈夫かと思ったのだが……少し人の波に酔ったようだ……、すまん」
持っていたペットボトルの水を差しだす。君彦くんは「助かる」と水を飲む。確かに顔が青い。
「どこか休憩できるところ……」
「そうだなぁ」と言いながら耳元で咲ちゃんが、
「そろそろ二人きりでゆっくりしたらいいんじゃね?」
と囁く。わたしがあわあわしていると、駿河くんにもなにやら耳打ちしている。
「おい、桂、さっきから二人に何をコソコソと」
「では、今日はこの辺で解散にしましょうか、佐野さん」
駿河くんもたぶんわたしたちに気を使ってくれてるんだ……。ここは二人からの気持ちを汲み取らなきゃ。
「そうだね、駿河くん」
「皆さんと一緒にまわれて楽しかったですよ」
「わたしもだよ。みんなありがとうね」
「こちらこそだ。で、神楽小路はどうだったんだよ?」
君彦くんは覚悟を決めたように、
「俺も真綾、そして駿河と桂、お前たちとまわれて楽しかった」
そう言ったあと、長い髪をかきあげて、照れくさそうにそっぽをむく。耳のふちはまた紅く色づいていた。
パッと見たり、聴いたりしてその素晴らしさやすごさをお客さんにわかってもらえるのはいいなぁ……。
わたしたち文芸学科はそういう意味ではなかなか難しいといつも思う。どれだけ素敵な文章でも、読まなければわからない。内容がどうこう言う前に「文章を読むのは得意じゃないから」と一文字も読んでもらえないことだって多い。どうしたら自分の作品に触れてもらえるだろう。以前わたしが落ち込んだ、人の記憶に残るインパクトのある文章にも通じることなのかもしれないけど。
フリーマーケットコーナーで出品されたハンドメイド作品を見ても感じてしまう。小説はアクセサリーや服のように、身にまとえないもんなぁ。
「真綾、難しい顔をしているな。なにか欲しいものがあるのか」
君彦くんの声で我に返る。咲ちゃんと駿河くんは少し遠くのお店で商品を見ていて、いつの間にか二人きりになっていた。
「えっと……すごいなぁって」
「すごい?」
わたしは所狭しと並ぶお店を見渡す。
「こう、目に見えて綺麗とかかわいいとかがすぐにわかるでしょ。でも、文章はそうもいかないなぁって思っちゃった」
「ほう」
「読んでもらわないとさ、おもしろいかどうかはわからないから」
「確かにな。だが、書かれた言葉を読んで理解した者だけが面白さに気づく。一見難しそうだと思った作品でも、読んでみれば理解しやすい言い回しや文体で、気づけばのめりこんで読んでいたということはあるだろう」
「うん、あるある!」
わたしには合わないかもと思った作品が、読み進めれば進むほど目が離せなくなって、最後まで読みきった時の快感と感動は計り知れない。
「見るだけはわからない、それは文学の弱点であり、強みだ。だから、真綾も文章に悩んだりしたのだろう」
「そうだね。たぶん一生かかっても答えは見つかりそうにはないけど」
「見つからないだろうな。だからこそ、人それぞれ己の面白いと感じる言葉と言葉を合わせていく。そこに個性が出る」
「同じテーマで書いたとしても、わたしと咲ちゃん、君彦くんと駿河くん四者四様だろうね」
「そういうことだ。しかし、見ただけですべてわかることもない。さっき見たピアノ演奏やマジックにも『どう観客を魅了するか』という陰の努力はあるだろうし、服やアクセサリーも制作の過程にどれほどの工夫が隠されているだろうかと考えると奥深い」
「みんなゼロから作り上げてる……」
「簡単に完成する作品などどこにもない」
今まで創作についてこんなにお話し出来るような人がいなかった。創作のことで悩んでも自分でなんとか解決しようとあがいた。自分の解釈では限界があった。せっかく文芸学科に在籍しているんだ。君彦くん、咲ちゃん、駿河くんとももっとお話していきたい。そうすれば、嫉妬しがちで落ち込みやすい自分ももっと文章を書くこと、表現の幅が広がりそうだから。
「ごめんね。なんだか大事なこと忘れてた」
「まぁ、目で見て、または触れて、または耳で聞いて。すぐに脳を揺さぶれる表現や作品に憧れを一度も持たない物書きはいないだろう。俺もそうだ。伝わらないことのもどかしさというものを、大学に入り、読者という存在を得て初めて感じた。だが、そのもどかしさも創作の醍醐味なのかもな」
君彦くんは突然足を止めた。「服を作る際に余った布を最後の最後まで使い切るがテーマです」と書かれたポスターを張っている。
「真綾、このアクセサリー似合う気がするのだがどうだ?」
手にしていたのはバレッタだった。金の金具の上に、薄紫色の布の端切れで作ったお花が四つ並んでつけられている。
「かわいい!」
「短い髪でもバレッタなら使えると思ってな。プレゼントする」
「えっ! あ、ありがとう……!」
わたしもなにか君彦くんが使えるものはないかなと、商品の置かれた机を見ると目に入ったのは、文庫サイズのブックカバーだ。「すいません」と店員さんに声をかける。
「あの、もしかしてこれ、このバレッタと同じ布ですか?」
「そうです。同じ布で作ってあります」
わたしは君彦くんの方に向き直す。
「君彦くん、これ、わたしからプレゼントしてもいい?」
「ああ。ブックカバーはよく使用するからな」
わたしたちは早速お互いに買って、その場で渡し合う。誕生日でもなんでもない日だけど、初めてのプレゼントだ。
「ありがとう、大事にする」
「わたしも!」
咲ちゃんと駿河くんと合流し、
「じゃあ、次どうする?」
と建物の端によってパンフを広げ、次に行く場所を探す。すると、君彦くんがこめかみのあたりを押さえた。苦しそうに目を閉じ、息を吐く。
「大丈夫かと思ったのだが……少し人の波に酔ったようだ……、すまん」
持っていたペットボトルの水を差しだす。君彦くんは「助かる」と水を飲む。確かに顔が青い。
「どこか休憩できるところ……」
「そうだなぁ」と言いながら耳元で咲ちゃんが、
「そろそろ二人きりでゆっくりしたらいいんじゃね?」
と囁く。わたしがあわあわしていると、駿河くんにもなにやら耳打ちしている。
「おい、桂、さっきから二人に何をコソコソと」
「では、今日はこの辺で解散にしましょうか、佐野さん」
駿河くんもたぶんわたしたちに気を使ってくれてるんだ……。ここは二人からの気持ちを汲み取らなきゃ。
「そうだね、駿河くん」
「皆さんと一緒にまわれて楽しかったですよ」
「わたしもだよ。みんなありがとうね」
「こちらこそだ。で、神楽小路はどうだったんだよ?」
君彦くんは覚悟を決めたように、
「俺も真綾、そして駿河と桂、お前たちとまわれて楽しかった」
そう言ったあと、長い髪をかきあげて、照れくさそうにそっぽをむく。耳のふちはまた紅く色づいていた。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

社長室の蜜月
ゆる
恋愛
内容紹介:
若き社長・西園寺蓮の秘書に抜擢された相沢結衣は、突然の異動に戸惑いながらも、彼の完璧主義に応えるため懸命に働く日々を送る。冷徹で近寄りがたい蓮のもとで奮闘する中、結衣は彼の意外な一面や、秘められた孤独を知り、次第に特別な絆を築いていく。
一方で、同期の嫉妬や社内の噂、さらには会社を揺るがす陰謀に巻き込まれる結衣。それでも、蓮との信頼関係を深めながら、二人は困難を乗り越えようとする。
仕事のパートナーから始まる二人の関係は、やがて揺るぎない愛情へと発展していく――。オフィスラブならではの緊張感と温かさ、そして心揺さぶるロマンティックな展開が詰まった、大人の純愛ストーリー。

【9】やりなおしの歌【完結】
ホズミロザスケ
ライト文芸
雑貨店で店長として働く木村は、ある日道案内した男性から、お礼として「黄色いフリージア」というバンドのライブチケットをもらう。
そのステージで、かつて思いを寄せていた同級生・金田(通称・ダダ)の姿を見つける。
終演後の楽屋で再会を果たすも、その後連絡を取り合うこともなく、それで終わりだと思っていた。しかし、突然、金田が勤務先に現れ……。
「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ9作目。(登場する人物が共通しています)。単品でも問題なく読んでいただけます。
※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。
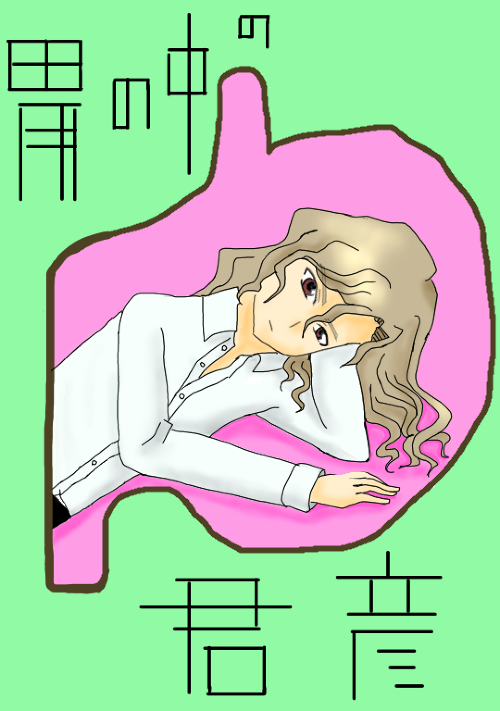
【1】胃の中の君彦【完結】
ホズミロザスケ
ライト文芸
喜志芸術大学・文芸学科一回生の神楽小路君彦は、教室に忘れた筆箱を渡されたのをきっかけに、同じ学科の同級生、佐野真綾に出会う。
ある日、人と関わることを嫌う神楽小路に、佐野は一緒に課題制作をしようと持ちかける。最初は断るも、しつこく誘ってくる佐野に折れた神楽小路は彼女と一緒に食堂のメニュー調査を始める。
佐野や同級生との交流を通じ、閉鎖的だった神楽小路の日常は少しずつ変わっていく。
「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ一作目。
※完結済。全三十六話。(トラブルがあり、完結後に編集し直しましたため、他サイトより話数は少なくなってますが、内容量は同じです)
※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。(過去に「エブリスタ」「貸し本棚」にも掲載)

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ドSでキュートな後輩においしくいただかれちゃいました!?
春音優月
恋愛
いつも失敗ばかりの美優は、少し前まで同じ部署だった四つ年下のドSな後輩のことが苦手だった。いつも辛辣なことばかり言われるし、なんだか完璧過ぎて隙がないし、後輩なのに美優よりも早く出世しそうだったから。
しかし、そんなドSな後輩が美優の仕事を手伝うために自宅にくることになり、さらにはずっと好きだったと告白されて———。
美優は彼のことを恋愛対象として見たことは一度もなかったはずなのに、意外とキュートな一面のある後輩になんだか絆されてしまって……?
2021.08.13

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


鬼上司と秘密の同居
なの
BL
恋人に裏切られ弱っていた会社員の小沢 海斗(おざわ かいと)25歳
幼馴染の悠人に助けられ馴染みのBARへ…
そのまま酔い潰れて目が覚めたら鬼上司と呼ばれている浅井 透(あさい とおる)32歳の部屋にいた…
いったい?…どうして?…こうなった?
「お前は俺のそばに居ろ。黙って愛されてればいい」
スパダリ、イケメン鬼上司×裏切られた傷心海斗は幸せを掴むことができるのか…
性描写には※を付けております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















