188 / 195
漂流する惑星『サ・ザ・ランド』
25
しおりを挟む
「……ここが動力部分か。ここを破壊すれば『マザー』も木っ端微塵に壊されちまうということだな」
修也はモニターの中に映る宇宙船の動力部分を見つめていく。映し出されていたのは宇宙船の心臓部とされる高性能のリアクター。
命よりも大事な『マザー』の動力源はホーテンス星のアンドロイドたちが扱う未知のエネルギーであることは間違いないだろう。恐らく地球の文明では想像もできないような高性能な方法で吸入されているに違いない。
というのも地球のSF小説で見られるようなリアクターならば大抵はタイヤの牽引力で用いるものの、タイヤは見当たらない。人力を用いて動かしている動きも見当たらないからだ。『マザー』はあまりにも兄弟で石炭や石油といったエネルギーで賄える量を遥かに超越している。
未知の技術とエネルギーを用いて考えなければ動力源が見えないことに説明が付かないではないか。
そんな未知のエネルギーや動力源で動く装置といっても爆弾を爆発させてしまえば破壊できるというのだから爆発が持つ衝撃や損壊力いうのはどこの宇宙に行っても信用できるものだそうだ。
修也がそんなことを考えていると、宇宙船のハッチが開く音が聞こえた。プシュという耳を研ぎ澄まさなければ聞こえないような微弱な音。それはまるで、出そうと思っても出てこない歯磨き粉のチューブからようやく歯磨き粉が出てきた時のように小さかった。
これまではハッキリと聞こえていたのに珍しいこともあるものだ。心臓部に潜入したこともあって気を遣っているのだろうか。
愚かな考えが頭に過りつつも修也が音のした方向を振り向くと、完璧な宇宙船の無機質な壁の中にそこだけ切り取られたように外の景色が見えていた。
コツコツと小さくタラップを降りる音が聞こえる。麗俐と悠介が宇宙船の外へ降りていっているのだろう。子どもたちの行動力には見習うものがある。
中年となった修也にはあまり縁がないように思えるので子どもたちが心のうちに持っている冒険心には見習うべきものがある。
修也は子どもたちに倣い恐る恐る宇宙船の外へと足を踏み出していく。未知の世界へと旅立つことは憚られたものだが、宇宙船の外に広がる景色はどこか特殊なもので地面の上に降りていく頃には恐怖心というものはすっかりと消え失せていた。
巨大なリアクターの周囲を守るように囲っているのは頑丈な鉄の柵。しかし頑丈ではあるものの侵入者を防ぐための仕様にはできていないらしい。
大きな柵の間に人が通れそうな隙間が存在しているのが、その照明であると言えるだろう。恐らくは管理者がリアクターに侵入するための通路。いくら文明が進んでいたとしても人もとい機械による細かなメンテナンスは必要なのだろう。
科学的に優れた高性能な機械も最後には人の手が欲しくなるものなのだろうか。
まだ人の手が離れることができない機械をどこか愛おしく思いつつ、修也は隙間をくぐっていく。リアクターの前には驚くほどあっさりと辿り着いた。
電流も流れていなければ地雷原も敷かれていない。番人や番犬の存在もない。
大事な心臓部であるというのにいささか無警戒過ぎるような気がする。
単なる第六感、と言われてしまえばそれまで。
だが、時に人間の中に働く本能はアンドロイドのデータや科学的に提唱されている理論を超えるような出来事を予知する力があるのだ。
修也が自身の第六感もとい単なる自身の勘に従ってコブラ男の袖を引き、彼にそのことを伝えても彼はアンドロイドらしく無表情のままだった。氷のような冷たい態度でコブラ男は質問に答えた。
「根拠はそれだけ?」
コブラ男の声は呆れているようだった。それにも関わらず修也は話を続けていく。
「えぇ、そうです。しかし伏兵の可能性もあるでしょう?」
「伏兵? そんなことを言っている間に我々はリアクターの目の前にまで到達しましたが」
コブラ男の言っていることは真実だった。修也たちはなんの妨害もないままリアクターの前へと辿り着き、コブラ男がイヤリングを外して爆弾を設置しようと準備している。ここまでなんの妨害もなかったからかゆっくりと耳からピアスを外そうとするコブラ男。そのコブラ男の背後を守るため入り口方向へと銃口を構える子どもたち。
今のところは大きな妨害もなく黙々と準備が進む。これで後は爆破予告を出して優秀な宇宙船を手に入れた後に爆発させれば全て終わり。『マザー』が破壊されたことによってホーテンス星人の面子は潰れた上、高性能なワープ機能を有した宇宙船に乗り込むことで修也たちは元の宇宙へ戻っていく。海へと旅立った鮭が最後は産卵のため川へと戻るように。
それだけ、それだけのはずだった。
しかし妙な胸騒ぎはいくら自身に言い聞かせても収まろうとしない。思えば怪奇映画などで先に異変に気がつくのは嫌な予感を覚える子どもたちだ。
映画の場合は子どもたちの進言は無視され、大人たちは危険な行動を続けていくのだ。そうした場合は大抵不幸がもたらされる。
今からでも遅くない。たとえ伝わらなかったとしても警告の言葉を発しようとした時のことだ。
突然地面から透明の液体が現れた。なんの変哲もない普通の地面だ。
どういった理屈で怪しげな液体が地面の上から現れるのかなど修也には分からない。
ただ、目の前に現れた“ソレ”が修也たちの身に危険を及ぼすものであるというのは事実だろう。名前は分からないので判明するまでの間は“ソレ”と回りくどく表することになるが、それでも構わないような気がした。
透明の液体はあっという間に人間の形に変貌した後に“ソレ”はニヤリと修也たちに向かって微笑む。原始的な機械に無理やり人間の笑顔をプログラミングさせて実行させたような不気味な笑顔だった。
笑いかけてきているはずであるのに、修也の中で嫌悪感が止まらない。無意識のうちに鼻のあたりに皺が集まっていく。ヒクヒクとさえ鳴ったかもしれない。
2人の子どもたちも同様であったようで両足を背後に下げ、逃げ出すような素振りを見せるなどの拒否反応を示していた。
目の前に立っているのが人間であれば眉を寄せるなど怒りの反応を見せたに違いないが、生憎目の前にいるのは冷徹で無情な殺戮マシーン。
『感情』という人間が持つ生きている証を全て取っ払った究極の機械。人間のように腹を立てるなどくだらない真似をするはずがない。
しばらくの間、彼はニコニコとこちらに向かって不気味な笑みを向けるだけだった。
このまま不毛な睨み合いが続くのかと息を呑んだのも束の間。彼はたった指を鳴らし、同時に彼は地球人たちが見たこともないような見事なパワードスーツに身を包んでいた。
白銀の見事な鎧であり、隅々まで磨き抜かれたボディには染みや汚れといったものは全くといっていいほど感じられなかった。
地球の偉人であれば立派な白銀の鎧の中心部には荘厳な絵画を思わせるような立派な装飾が施されているのだろうが、そこは無駄よりも利益を優先させるアンドロイド。なんの装飾も施されていない。
兜いわゆるフェイスヘルメットも同様だった。戦う相手の存在を認知する巨大な眼球を模したマゼンタのコアの他には何もない。
装飾品といえば立派なパワードスーツの腰に下げられたライトセイバーを収めたと思われる小さな鞘。そして背中に掛けているバックパップのみ。
どこか貧弱な装備だ。そう思っていたのはやはり修也自身の怠慢であったかもしれない。
“ソレ”はバックパップのジェット噴射を用いて空の上へと飛び上がり、コブラ男の目の前に到着したのだ。
「adiós junk」
正確な英語を呟いた後で“ソレ”はそのままライトセイバーを鞘から引き抜いてコブラ男の心臓を貫く。一瞬の出来事であったので修也たちも止めることができなかった。
コブラ男は正面から大きなダメージを背負ったためか、耐え切れなくなって地面の上へと倒れ込む。異常を告げる警告音が鳴り、コブラ男の内部からは火花が鳴り響く。
重度の損傷を負ったことは誰の目に見ても明らかだ。この時の修也はといえば何もできず、目の前で繰り広げられる惨劇を見物することしかできなかった。ボックス席の真上からオペラを眺めているような優雅なものではない。
短期間とはいえ危険を共に過ごした優秀なアンドロイドが目の前でなぶり殺しにされている姿を体が追い付かずに黙って見つめていることしかできない自分に不甲斐なさを覚えていた。
いや、正確にいえば怒りだろうか。何もできない怒りが修也の悲しみを大きくしていた。
だが、子どもたちは若い分、柔軟性が効いたらしい。背後に護衛として控えていたはずの2人がレーザーガンを突き付けながら叫ぶ。
「動くなッ!」
「動いたらその頭をこいつで吹き飛ばすからねッ!」
2人はいつも以上に大きな声を出しているように思えた。相手を怒鳴るように威嚇することで虚勢を張って恐怖を誤魔化そうとしている姿勢が顕著に現れている。
2人の心意気は立派なものだが、機械にはそんな見栄を張った姿勢などすぐに見抜かれてしまうことは想像に易い。
案の定、“ソレ”は虫の息となったコブラ男を放って修也たちの方へと向かってきている。
無表情のまま突撃してくる敵に耐え切れなくなったのか、麗俐は腰を抜かしていた。情けなく尻餅をつき、全身を震わせて弱みをみせるその姿は到底戦士のものとは思えない。
だが、修也は情けない態度を示した麗俐を責める気にはなれない。今の状態で悠介がレーザーガンを構え続けていられることも奇跡に近い。
修也がなんとかしようと足を踏み込んだ時のことだ。“ソレ”が地面の上を蹴り、宙の上で弧を描いたかと思うと修也の目の前へと降り立つ。目の前で丁寧な一礼を行うその姿はマジックショーが成功したに礼を述べる手品師のようだった。
思わずたじろいで見せた修也に対し、“ソレ”はフェイスヘルメットを近付け楽しげな声で言った。
「フフッ、やはりこんなものか。原始的な民族は原始的なやり方で脅すに限る」
「あ、あんた日本語を!?」
「あぁ、あんな原始的な言葉などここに入ってきた時の言葉だけで解析できたよ。実に簡単なことさ」
たったあれだけのやり取りで“ソレ”は言語を取得したらしい。優秀なのは内蔵されているコンピュータか。はたまたホーテンス星人並びにアンドロイドたちの技術か。いずれにしろ修也には及ぶこともできない領域の話。
素直に“ソレ”の言葉を受け入れた方がよしというものだろう。
それでも辻褄が合わないことはある。それは最初“にソレ”が発していた英語。
修也たちは英語を喋れない。当然会話に登ることもないのでコブラ男も英語に触れる機会はない。
そうなると、どこから英語を取得したのだろうか。修也が精一杯の大きな声を張り上げながら“ソレ”に向って問い掛けると、“ソレ”は待っていましたとばかりに嬉々とした声で話し始めていく。
「最近この辺りの星域……いいや、この宇宙全体から人間が消えつつあってね。それで我々は試しに別の宇宙の人間を狩るための計画を立てていたんだ。その第一段階として時折ワームホールから紛れ込む漂着物に我々は目を付けた」
“ソレ”の話によればホーテンス星人を名乗る宇宙人たちはワームホールから出てきた一台の宇宙船を鹵獲したのだそうだ。
その宇宙船に乗っていた人間が先ほど“ソレ”が話していた言語を口にしたというのが真相であるのは間違いない。
その話が本当であるとすれば、今ここで目の前にいる怪しげなアヤドロイドを倒さなければ修也たち自身の住む宇宙も危うくなってしまう。
一刻の猶予もない。修也は腰に下げていたビームソードを抜き、そのまま“ソレ”の頭上を目掛けて勢いよく振り下ろしていく。
頭上からの攻撃はあっさりとライトセイバーによって受け止められ、ここに光剣と熱剣による決闘が行われることになった。
修也はモニターの中に映る宇宙船の動力部分を見つめていく。映し出されていたのは宇宙船の心臓部とされる高性能のリアクター。
命よりも大事な『マザー』の動力源はホーテンス星のアンドロイドたちが扱う未知のエネルギーであることは間違いないだろう。恐らく地球の文明では想像もできないような高性能な方法で吸入されているに違いない。
というのも地球のSF小説で見られるようなリアクターならば大抵はタイヤの牽引力で用いるものの、タイヤは見当たらない。人力を用いて動かしている動きも見当たらないからだ。『マザー』はあまりにも兄弟で石炭や石油といったエネルギーで賄える量を遥かに超越している。
未知の技術とエネルギーを用いて考えなければ動力源が見えないことに説明が付かないではないか。
そんな未知のエネルギーや動力源で動く装置といっても爆弾を爆発させてしまえば破壊できるというのだから爆発が持つ衝撃や損壊力いうのはどこの宇宙に行っても信用できるものだそうだ。
修也がそんなことを考えていると、宇宙船のハッチが開く音が聞こえた。プシュという耳を研ぎ澄まさなければ聞こえないような微弱な音。それはまるで、出そうと思っても出てこない歯磨き粉のチューブからようやく歯磨き粉が出てきた時のように小さかった。
これまではハッキリと聞こえていたのに珍しいこともあるものだ。心臓部に潜入したこともあって気を遣っているのだろうか。
愚かな考えが頭に過りつつも修也が音のした方向を振り向くと、完璧な宇宙船の無機質な壁の中にそこだけ切り取られたように外の景色が見えていた。
コツコツと小さくタラップを降りる音が聞こえる。麗俐と悠介が宇宙船の外へ降りていっているのだろう。子どもたちの行動力には見習うものがある。
中年となった修也にはあまり縁がないように思えるので子どもたちが心のうちに持っている冒険心には見習うべきものがある。
修也は子どもたちに倣い恐る恐る宇宙船の外へと足を踏み出していく。未知の世界へと旅立つことは憚られたものだが、宇宙船の外に広がる景色はどこか特殊なもので地面の上に降りていく頃には恐怖心というものはすっかりと消え失せていた。
巨大なリアクターの周囲を守るように囲っているのは頑丈な鉄の柵。しかし頑丈ではあるものの侵入者を防ぐための仕様にはできていないらしい。
大きな柵の間に人が通れそうな隙間が存在しているのが、その照明であると言えるだろう。恐らくは管理者がリアクターに侵入するための通路。いくら文明が進んでいたとしても人もとい機械による細かなメンテナンスは必要なのだろう。
科学的に優れた高性能な機械も最後には人の手が欲しくなるものなのだろうか。
まだ人の手が離れることができない機械をどこか愛おしく思いつつ、修也は隙間をくぐっていく。リアクターの前には驚くほどあっさりと辿り着いた。
電流も流れていなければ地雷原も敷かれていない。番人や番犬の存在もない。
大事な心臓部であるというのにいささか無警戒過ぎるような気がする。
単なる第六感、と言われてしまえばそれまで。
だが、時に人間の中に働く本能はアンドロイドのデータや科学的に提唱されている理論を超えるような出来事を予知する力があるのだ。
修也が自身の第六感もとい単なる自身の勘に従ってコブラ男の袖を引き、彼にそのことを伝えても彼はアンドロイドらしく無表情のままだった。氷のような冷たい態度でコブラ男は質問に答えた。
「根拠はそれだけ?」
コブラ男の声は呆れているようだった。それにも関わらず修也は話を続けていく。
「えぇ、そうです。しかし伏兵の可能性もあるでしょう?」
「伏兵? そんなことを言っている間に我々はリアクターの目の前にまで到達しましたが」
コブラ男の言っていることは真実だった。修也たちはなんの妨害もないままリアクターの前へと辿り着き、コブラ男がイヤリングを外して爆弾を設置しようと準備している。ここまでなんの妨害もなかったからかゆっくりと耳からピアスを外そうとするコブラ男。そのコブラ男の背後を守るため入り口方向へと銃口を構える子どもたち。
今のところは大きな妨害もなく黙々と準備が進む。これで後は爆破予告を出して優秀な宇宙船を手に入れた後に爆発させれば全て終わり。『マザー』が破壊されたことによってホーテンス星人の面子は潰れた上、高性能なワープ機能を有した宇宙船に乗り込むことで修也たちは元の宇宙へ戻っていく。海へと旅立った鮭が最後は産卵のため川へと戻るように。
それだけ、それだけのはずだった。
しかし妙な胸騒ぎはいくら自身に言い聞かせても収まろうとしない。思えば怪奇映画などで先に異変に気がつくのは嫌な予感を覚える子どもたちだ。
映画の場合は子どもたちの進言は無視され、大人たちは危険な行動を続けていくのだ。そうした場合は大抵不幸がもたらされる。
今からでも遅くない。たとえ伝わらなかったとしても警告の言葉を発しようとした時のことだ。
突然地面から透明の液体が現れた。なんの変哲もない普通の地面だ。
どういった理屈で怪しげな液体が地面の上から現れるのかなど修也には分からない。
ただ、目の前に現れた“ソレ”が修也たちの身に危険を及ぼすものであるというのは事実だろう。名前は分からないので判明するまでの間は“ソレ”と回りくどく表することになるが、それでも構わないような気がした。
透明の液体はあっという間に人間の形に変貌した後に“ソレ”はニヤリと修也たちに向かって微笑む。原始的な機械に無理やり人間の笑顔をプログラミングさせて実行させたような不気味な笑顔だった。
笑いかけてきているはずであるのに、修也の中で嫌悪感が止まらない。無意識のうちに鼻のあたりに皺が集まっていく。ヒクヒクとさえ鳴ったかもしれない。
2人の子どもたちも同様であったようで両足を背後に下げ、逃げ出すような素振りを見せるなどの拒否反応を示していた。
目の前に立っているのが人間であれば眉を寄せるなど怒りの反応を見せたに違いないが、生憎目の前にいるのは冷徹で無情な殺戮マシーン。
『感情』という人間が持つ生きている証を全て取っ払った究極の機械。人間のように腹を立てるなどくだらない真似をするはずがない。
しばらくの間、彼はニコニコとこちらに向かって不気味な笑みを向けるだけだった。
このまま不毛な睨み合いが続くのかと息を呑んだのも束の間。彼はたった指を鳴らし、同時に彼は地球人たちが見たこともないような見事なパワードスーツに身を包んでいた。
白銀の見事な鎧であり、隅々まで磨き抜かれたボディには染みや汚れといったものは全くといっていいほど感じられなかった。
地球の偉人であれば立派な白銀の鎧の中心部には荘厳な絵画を思わせるような立派な装飾が施されているのだろうが、そこは無駄よりも利益を優先させるアンドロイド。なんの装飾も施されていない。
兜いわゆるフェイスヘルメットも同様だった。戦う相手の存在を認知する巨大な眼球を模したマゼンタのコアの他には何もない。
装飾品といえば立派なパワードスーツの腰に下げられたライトセイバーを収めたと思われる小さな鞘。そして背中に掛けているバックパップのみ。
どこか貧弱な装備だ。そう思っていたのはやはり修也自身の怠慢であったかもしれない。
“ソレ”はバックパップのジェット噴射を用いて空の上へと飛び上がり、コブラ男の目の前に到着したのだ。
「adiós junk」
正確な英語を呟いた後で“ソレ”はそのままライトセイバーを鞘から引き抜いてコブラ男の心臓を貫く。一瞬の出来事であったので修也たちも止めることができなかった。
コブラ男は正面から大きなダメージを背負ったためか、耐え切れなくなって地面の上へと倒れ込む。異常を告げる警告音が鳴り、コブラ男の内部からは火花が鳴り響く。
重度の損傷を負ったことは誰の目に見ても明らかだ。この時の修也はといえば何もできず、目の前で繰り広げられる惨劇を見物することしかできなかった。ボックス席の真上からオペラを眺めているような優雅なものではない。
短期間とはいえ危険を共に過ごした優秀なアンドロイドが目の前でなぶり殺しにされている姿を体が追い付かずに黙って見つめていることしかできない自分に不甲斐なさを覚えていた。
いや、正確にいえば怒りだろうか。何もできない怒りが修也の悲しみを大きくしていた。
だが、子どもたちは若い分、柔軟性が効いたらしい。背後に護衛として控えていたはずの2人がレーザーガンを突き付けながら叫ぶ。
「動くなッ!」
「動いたらその頭をこいつで吹き飛ばすからねッ!」
2人はいつも以上に大きな声を出しているように思えた。相手を怒鳴るように威嚇することで虚勢を張って恐怖を誤魔化そうとしている姿勢が顕著に現れている。
2人の心意気は立派なものだが、機械にはそんな見栄を張った姿勢などすぐに見抜かれてしまうことは想像に易い。
案の定、“ソレ”は虫の息となったコブラ男を放って修也たちの方へと向かってきている。
無表情のまま突撃してくる敵に耐え切れなくなったのか、麗俐は腰を抜かしていた。情けなく尻餅をつき、全身を震わせて弱みをみせるその姿は到底戦士のものとは思えない。
だが、修也は情けない態度を示した麗俐を責める気にはなれない。今の状態で悠介がレーザーガンを構え続けていられることも奇跡に近い。
修也がなんとかしようと足を踏み込んだ時のことだ。“ソレ”が地面の上を蹴り、宙の上で弧を描いたかと思うと修也の目の前へと降り立つ。目の前で丁寧な一礼を行うその姿はマジックショーが成功したに礼を述べる手品師のようだった。
思わずたじろいで見せた修也に対し、“ソレ”はフェイスヘルメットを近付け楽しげな声で言った。
「フフッ、やはりこんなものか。原始的な民族は原始的なやり方で脅すに限る」
「あ、あんた日本語を!?」
「あぁ、あんな原始的な言葉などここに入ってきた時の言葉だけで解析できたよ。実に簡単なことさ」
たったあれだけのやり取りで“ソレ”は言語を取得したらしい。優秀なのは内蔵されているコンピュータか。はたまたホーテンス星人並びにアンドロイドたちの技術か。いずれにしろ修也には及ぶこともできない領域の話。
素直に“ソレ”の言葉を受け入れた方がよしというものだろう。
それでも辻褄が合わないことはある。それは最初“にソレ”が発していた英語。
修也たちは英語を喋れない。当然会話に登ることもないのでコブラ男も英語に触れる機会はない。
そうなると、どこから英語を取得したのだろうか。修也が精一杯の大きな声を張り上げながら“ソレ”に向って問い掛けると、“ソレ”は待っていましたとばかりに嬉々とした声で話し始めていく。
「最近この辺りの星域……いいや、この宇宙全体から人間が消えつつあってね。それで我々は試しに別の宇宙の人間を狩るための計画を立てていたんだ。その第一段階として時折ワームホールから紛れ込む漂着物に我々は目を付けた」
“ソレ”の話によればホーテンス星人を名乗る宇宙人たちはワームホールから出てきた一台の宇宙船を鹵獲したのだそうだ。
その宇宙船に乗っていた人間が先ほど“ソレ”が話していた言語を口にしたというのが真相であるのは間違いない。
その話が本当であるとすれば、今ここで目の前にいる怪しげなアヤドロイドを倒さなければ修也たち自身の住む宇宙も危うくなってしまう。
一刻の猶予もない。修也は腰に下げていたビームソードを抜き、そのまま“ソレ”の頭上を目掛けて勢いよく振り下ろしていく。
頭上からの攻撃はあっさりとライトセイバーによって受け止められ、ここに光剣と熱剣による決闘が行われることになった。
0
お気に入りに追加
42
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

【新作】読切超短編集 1分で読める!!!
Grisly
現代文学
⭐︎登録お願いします。
1分で読める!読切超短編小説
新作短編小説は全てこちらに投稿。
⭐︎登録忘れずに!コメントお待ちしております。

【完結済み】VRゲームで遊んでいたら、謎の微笑み冒険者に捕獲されましたがイロイロおかしいです。<長編>
BBやっこ
SF
会社に、VRゲーム休があってゲームをしていた私。
自身の店でエンチャント付き魔道具の売れ行きもなかなか好調で。なかなか充実しているゲームライフ。
招待イベで魔術士として、冒険者の仕事を受けていた。『ミッションは王族を守れ』
同僚も招待され、大規模なイベントとなっていた。ランダムで配置された場所で敵を倒すお仕事だったのだが?
電脳神、カプセル。精神を異世界へ送るって映画の話ですか?!

法術装甲隊ダグフェロン 永遠に続く世紀末の国で 『修羅の国』での死闘
橋本 直
SF
その文明は出会うべきではなかった
その人との出会いは歓迎すべきものではなかった
これは悲しい『出会い』の物語
『特殊な部隊』と出会うことで青年にはある『宿命』がせおわされることになる
法術装甲隊ダグフェロン 第三部
遼州人の青年『神前誠(しんぜんまこと)』は法術の新たな可能性を追求する司法局の要請により『05式広域制圧砲』と言う新兵器の実験に駆り出される。その兵器は法術の特性を生かして敵を殺傷せずにその意識を奪うと言う兵器で、対ゲリラ戦等の『特殊な部隊』と呼ばれる司法局実働部隊に適した兵器だった。
一方、遼州系第二惑星の大国『甲武』では、国家の意思決定最高機関『殿上会』が開かれようとしていた。それに出席するために殿上貴族である『特殊な部隊』の部隊長、嵯峨惟基は甲武へと向かった。
その間隙を縫ったかのように『修羅の国』と呼ばれる紛争の巣窟、ベルルカン大陸のバルキスタン共和国で行われる予定だった選挙合意を反政府勢力が破棄し機動兵器を使った大規模攻勢に打って出て停戦合意が破綻したとの報が『特殊な部隊』に届く。
この停戦合意の破棄を理由に甲武とアメリカは合同で介入を企てようとしていた。その阻止のため、神前誠以下『特殊な部隊』の面々は輸送機でバルキスタン共和国へ向かった。切り札は『05式広域鎮圧砲』とそれを操る誠。『特殊な部隊』の制式シュツルム・パンツァー05式の機動性の無さが作戦を難しいものに変える。
そんな時間との戦いの中、『特殊な部隊』を見守る影があった。
『廃帝ハド』、『ビッグブラザー』、そしてネオナチ。
誠は反政府勢力の攻勢を『05式広域鎮圧砲』を使用して止めることが出来るのか?それとも……。
SFお仕事ギャグロマン小説。

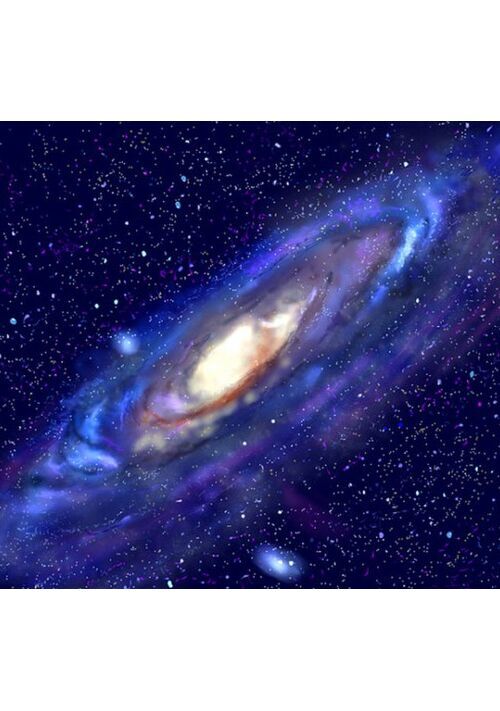
銀河文芸部伝説~UFOに攫われてアンドロメダに連れて行かれたら寝ている間に銀河最強になっていました~
まきノ助
SF
高校の文芸部が夏キャンプ中にUFOに攫われてアンドロメダ星雲の大宇宙帝国に連れて行かれてしまうが、そこは魔物が支配する星と成っていた。

夢の骨
戸禮
SF
悪魔は人間に夢を問うた。人が渇望するその欲求を夢の世界で叶えるために。昏山羊の悪魔は人に与えた。巨額の富も、万夫不当の力も、英雄を超えた名声も全てが手に入る世界を作り出した。だからこそ、力を手にした存在は現実を攻撃した。夢を求めて、或いは夢を叶えたからこそ、暴走する者の発生は必然だった。そして、それを止める者が必要になった。悪魔の僕に対抗する人類の手立て、それは夢の中で悪夢と戦う"ボイジャー"と呼ばれる改造人間たちだった。これは、夢の中で渇望を満たす人間と、世界護るために命懸けで悪夢と戦う者たちの物語−

無限回廊/多重世界の旅人シリーズIII
りゅう
SF
突然多重世界に迷い込んだリュウは、別世界で知り合った仲間と協力して元居た世界に戻ることができた。だが、いつの間にか多重世界の魅力にとらわれている自分を発見する。そして、自ら多重世界に飛び込むのだが、そこで待っていたのは予想を覆す出来事だった。
表紙イラスト:AIアニメジェネレーターにて生成。
https://perchance.org/ai-anime-generator
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















