54 / 76
54「伊藤織江について 1」
しおりを挟む
2017年、3月10日。
私にとっては、急と言えば急な話だった。
いつからその日に向けて調整されていたのかその時の私には知る由もないが、
伊藤織江が仕事を休んで一週間旅行に出かけると言う話を聞いた。
もちろんバンドメンバーも事務所のスタッフも事前に知らされており、
その事を聞いて慌てたのは私一人だった。
仕事人間と言えば聞こえはいいが、
伊藤に対しては誰もが「働きすぎ」だと感じていた。
休みを取って一週間の旅行と聞けば喜びをもって笑顔で手を振る場面のはずが、
私の胸を過ったのは心細さとも呼べる不安だった。
これまでも伊藤と一週間会わない事はいくらでもあった。
しかし「一週間会えない」と聞かされて急に不安を感じたのだ。
バンド取材に対する不安要素という意味でない事は分かっていた。
個人的な話で恐縮だが、その頃私は問題を抱えており、茫然とする事がよくあったそうだ。
そうだ、と他人事のような言い方になるのははもちろん自覚がないからで、
人に指摘されてようやく気付く程、自失している場面も多かったという。
私が伊藤の旅行を聞いたのは彼女の出発予定日の2日前、3月8日の事である。
まだ就業中で社内にいる時間帯に電話を受けられた事は運命だと言えた。
「一週間休暇で留守にします」
私はとてつもない報告を受けたような衝撃に戸惑い、
いつですか、とかなり深刻な声で返事をして電話越に笑われた。
3月10日と聞いた時、私は泣きそうになりながら、
ついて行っていいですか、と考えるより先に申し出ていた。
まだ行先も聞いていないのにだ。
私の不穏な空気を電話の向こうで感じ取ったのだろう。
考え込むような沈黙の後、伊藤は笑いもせずにいつもの優しい声で、
「お休み取れる?」
と言ってくれた。
私は心底救われたような気持になり、すぐに上司に頭を下げて一週間の休暇を願い出た。
穴を開ける事は承知の上だから、当然有給ではなく欠勤扱いで構わないと懇願した。
自慢ではないが記事を書くスピードは編集部内で誰にも負けない。
もちろん、休暇中も時間が取れれば記事を書いてメールで送ろうと思っていた。
その点においては、一週間という日数であれば取り返せるという自信も私にはあった。
すぐに伊藤へ折り返し、許可が下りた事を告げた時初めて行く先を聞くと、
「京都」
との返事。
へえ、いいですね。
「でも実家に帰るだけだよ?」
そうなんですか。
私は嬉しさのあまり深く考えらずにいたが、不思議な話だった。
伊藤織江は生まれも育ちも東京のはずだ。
例えばそれが京都旅行ならば、素晴らしい考えだと喜ぶだけで良い。
しかし彼女の口から聞いた内容からすれば、それは「帰省」と呼ぶべきものだった。
日本をしばらく離れる事が決まった時から、彼女は今回の帰省を計画していたそうだ。
聞けば伊藤の実家は今、確かに京都にあるという。
もともと父親の兄弟が京都で農家を営んでおり、10年程年前病で他界した折、
伊藤の父がその地盤を引き継ぐ形で京都へ引っ越した。
東京で生まれ育った彼女にしてみれば、実家が地方へ移動した珍しいパターンと言える。
これまで何度か帰省はしていたが、忙しさもあり纏まった時間を家族と過ごすのはとても久し振りとの事だった。
本当は神波も今回の帰省に付き添うはずだっただが、伊藤の方から遠慮したという話を聞いて、後先考えず同行を願い出た自分を思い切り恥じた。
そして当日。
東京から新幹線に揺られて京都駅へ到着するまでに2時間弱。
そこから在来線に乗り換えて鈍行列車で30分強。
目的地の駅へ到着し、ホームに降り立って真っ先に思ったのは、
「京都であって京都ではなし」といった感想だ。
伊藤の実家は観光名所ひしめく京都市内からは趣を異にした郊外都市にあり、
そこは周囲を山々に囲まれた盆地と呼ばれる地形であるらしかった。
3月に入ったとは言え降り立った地はまだまだ肌寒く、
忠告通りコートを羽織ってきて正解だった。
「風光明媚というか、田舎でしょ」
となぜか照れたように笑った伊藤と並んで立ち、私は首を横に振る。
まるでその土地の人間のような顔で笑う伊藤に、初めて訪れた土地に対して嫉妬した。
「あなたがいれば、どこだって天国です」
私がそう言うと、伊藤は目を丸くして私を見つめ、5秒後、盛大に吹き出して笑った。
ポケットに手を突っ込んだまま体をくの字にして声高らかに笑う美女に、
移動中であろう通りすがりのサラリーマンが好奇の目で私達を見た。
実は長い電車移動の最中、ずっと言おうと考えていた言葉だった。
はっきり言えば、私はこの時より随分前から伊藤織江に心酔していたのだ。
彼女が側にいるだけで、何時間でも電車に揺られていられると思った。
「何が」や「どこが」というポイントを挙げるのが嫌なくらい全てが好きだ。
あの関誠や芥川繭子をして「完璧」、「人として理想」と言わしめる女性なのだ。
知れば知るほど、のめり込んでいく自分に気づいていた。
もやは私にとって伊藤織江は、バイラル4の代表でありドーンハンマーのマネージャーという裏方の存在ではなくなっていた。
彼女の後ろをついて歩くだけで少し、自分が誇らしく思えた程だ。
改札を出て駅構内から外は、ホームから見渡せた山々とは打って変わって、
そこそこの交通量を見せる駅前繁華街だった。
どうやって移動するのか伊藤の決断を待っていた所へ、
「織江」
と彼女の名を呼ぶ声が聞こえた。
見れば60代ぐらいだろうか、背が高く質の良い衣服を身にまとった淑女が満面の笑みで立っていた。一目見て伊藤の母親だと分かった。
「久しぶり」
と伊藤は一歩を踏み出し、彼女と抱き合った。
「こちら、東京の出版社にお勤めの時枝可奈さん。うちのを御贔屓にしてもらってるの。時枝さん、母です」
私は涙が込み上げるのを必死に抑えながら、深々と頭を下げた。
しかし長すぎたせいだろう。
なかなか顔を挙げない私の頭を抱きしめて、
「恥ずかしいからやめなさい」
と言って伊藤は優しく笑った。
駅前の繁華街を抜けて車で走る事10分、
先ほど駅のホームから見えたスケールの大きな田園風景が目の前に広がる。
車を運転する伊藤織江の母は、名を冴(サエ)さんといった。
なるほど、お洒落な母の名前にして織江と乃依ありという事だ。
「遠かったでしょ」
と前を向いたまま冴さんが言う。
「まあね。でも新幹線で2時間掛からないからね、今」
伊藤がそう返すも、
「でも京都駅からここまでまた電車に乗って30分でしょ。そこからまた車に乗って家まで30分よ。はい、3時間超えました!」
と冴さんはお道化る。
つられて私達も笑い声を上げる。
「時枝さんはずーっと東京?」
「はい」
「出版社なんてお洒落よねえ」
「いえいえ、そんな」
「どう?最近の業界は」
「うーん、正直まだ底が見えないですね。やはり昨今の出版不況は…」
「いやいや、本気にしないで。この人に業界の事なんて分からないから!」
「ええ?」
「馬鹿にしてえ、もー」
久し振りの再会とは思えない二人のやり取りに、素敵な親子関係だなと眩しく思う。
お腹が痛くなるまで笑い、涙を全部拭ってようやく私は笑顔になれた。
「わざわざ織江について来てくれたの?」
バックミラー越しに私を見ながら、冴さんが言う。
「無理やり同行を願い出たんです」
「へえ、物好きねえ。こんな田舎、3日で飽きると思うわよ」
「お母さん、シティー派だもんね」
「東京が恋しいわー」
「東京でもまた是非、お会いしたいです」
「会っていきなりそんな嬉しい事言ってくれるの?やっぱりやり手のビジネスウーマンは口説き文句がシャレてるわね!」
「いちいち言葉が古いの!」
時枝、爆笑。
伊藤の実家に到着したのはお昼の12時前だった。
周囲にちらほら田畑が点在する静かな住宅地に、その家はあった。
近所の風景に溶け込んでいる為一見分からないが、とても綺麗な外観である。
聞けば数年前にフルリフォームをしたそうだ。
冴さんは口では東京が恋しいと言うし、生まれ育った街である以上本音もあるだろうが、
この場所を終の棲み家に選んだという事に間違いはない。
駐車場に車を停めて折り立ってすぐ、「お父さんは?」と伊藤が訪ねる。
「朝から田んぼ出てるけど、もうお昼だしそろそろ戻るよ」
「そっか。中入ろうか」
「はい。お邪魔します」
「なーんにもないけどね、ゆっくりして行ってね」
冴さんはそう言うと、自慢げに玄関の扉を開けてくれた。
その後、仕事場から戻って来たお父様にもご挨拶し、4人でお昼ご飯を頂いた。
久し振りに味わう種類の緊張で胸が一杯になったが、
それを上回る幸せな時間を過ごすことが出来た。
今日から始まる一週間が、とても素晴らしい思い出になる予感で胸が高鳴る。
都会の喧騒を離れて、といった表現で田舎を評する声をよく耳にするが、
そういった都市部と比較した環境面とは全く違う部分で、
この穏やかな生活に私は溶け込む事が出来たように思う。
暮しとは、人の営みの事だ。
交通事情や仕事環境や街の活気も確かに、営みを左右する要因ではある。
しかしやはり最も重要なのは人間自身だろう。
午前の仕事を終えて田んぼから戻って来た伊藤織江の父・恭平さんは、
娘の姿を見るなり鼻の下を伸ばして喜んだ。
ルックスは北大路 欣也そのままの人だ。
似てると言われませんかと初対面でも確認してしまう程雰囲気が近い。
しかし娘を見つめる眼差しの温かさと、
寡黙ながら笑顔を絶やさない人柄を見ているだけで、
ここでの暮らしがいかに穏やかで充実しているかが分かった。
「一週間、お世話になります」
と私が頭を下げた時、
「末永く娘を、よろしく見てやってください」
と言われた。
御両親ともに、深々と頭を下げていた。
私はもう涙を堪えるのを諦めた。
初日の夜。
夕飯の後お風呂をいただいて、伊藤の部屋でくつろぐ。
普段使用されていない部屋だけあって、小ぶりの机と本棚以外は何もない。
おかげで、綺麗に掃除されてはいるが殺風景と言えなくもないのだが、
並んで敷かれた布団の上で胡坐をかいて座る伊藤がそこにいるだけで、
寂しさなど微塵にも感じないのだから彼女の存在感はすごい。
「疲れた?」
戻って来た私を見るなり彼女はそう言った。
「全然です。フワフワしっぱなしです」
「それは疲れてるって事だよ」
「自覚ないです。ああ、綺麗な部屋着ですね。ジェラピケですか」
「そうみいたいだね。私のじゃないよ、お母さんの」
「そうなんですか!綺麗なピンク」
肌触りのよいタオル地で出来た、膝丈のワンピースだ。
「私下着以外は一泊分の服しか持ってこなかったの」
「荷物少ないとは思いましたけだど、郵送されたわけじゃないんですね。何故ですか?」
「仕事しないし、人と会う約束もないしね。背格好が似てるから、いつもお母さんの服を勝手に拝借してるのよ。ここへ来る時はそう決めてる。身軽だからね」
「なるほど」
「だからしばらく野暮ったい私をお見せする事になりますが」
「望む所です」
「なんでよ」
そう言うと伊藤はケラケラと笑い、布団の上に横たわった。
「カメラ回していいですか?」
「え、どうして?」
「大成さんに頼まれたので」
「ウソ? ウソだよね」
「聞いてませんか?」
「聞いてないよ、ウソでしょ」
「冗談だったのかなあ。でも私も今すっごく織江さん撮りたいです」
「おばさんを揶揄うんじゃない」
「需要と供給です。ちょっとセットしますね」
「おいー」
「…びっくりされてませんでしたか?」
伊藤の顔を見れないまま、私は尋ねた。
「…涙? んー。まあね、少しくらいは。でもうちの親も、こっちへ来るまで東京でそれこそ馬車馬みたいに働いてた人達だからね。皆それぞれ色々あるって事ぐらい、分かってるよ」
「余計な気を使わせてしまって、すみません」
「なんのなんの。私と違って、見るもの触るものに新鮮なリアクション取ってくれるって、あの二人も大喜びしてたよ」
「あはは、やはり採れたてのお野菜は美味しいですね。意識して春キャベツ食べたのなんて何年振りだろうって」
「多分気付かないだけで絶対口にはしてるんだろうけど、忙しくしてるとなかなか気づかないよね。美味しいものは東京でたくさん食べられるけど、旬の物を家で食べるって今となっては贅沢に感じるもんね」
「子供の頃は、それが当たり前だったんですけどね」
「うちにいっつも送って来てくれるから、今度からは時枝さんにもお裾分けするね」
「いえいえ、そんなご迷惑お掛けできません!」
「事務所にどーんと送られてくるんだよ。それを皆で分けっこして持って帰るの。ってもあれか、今年からは…」
「ああ。お父様たちも仕送り先が減って、寂しくなっちゃいますね」
「そうだね」
代わりに私がいただきます!
例えその場のノリでも、笑ってそう言えたら良かったのだろう。
思いついてはいた。しかし、言えなかった。
私がおどけた時に見せるであろう伊藤の微笑みが簡単に想像できて、
それがあまりに寂しすぎて、無理だった。
伊藤の言うように、やはり疲れていたのだろう。
部屋の入口脇に三脚を立てただけで、布団の上に座って伊藤と話をしているうちカメラの電源を入れる前に眠ってしまった。
朝目が覚めると既に伊藤の姿はなく、昨晩手にしていたはずの私のビデオカメラは、三脚の上に乗せられていた。
二日目の朝。
恭平さんが運営する田んぼを見せてもらった。
何年振りかも思い出せない程久し振りに畦道を歩いた。
前を行く伊藤は両手を後ろに回し、リラックスした様子でゆっくりと歩く。
東京では見る事のない、社長ではない伊藤織江の姿。
一人の女性として。一人の娘として。
そのどちらであれ、私の目に映る素顔の彼女はとても美しかった。
伊藤家所有の農地は家から歩いて5分程の所にあり、
「ここからあそこまで、全部」
と伊藤に指をさされても把握できない程広大な敷地面積だった。
「えー、ちょっと、規模が」
「あそこに林があるでしょ。その手前の畔から、端はあそこ。奥行はあの道路まで」
「本気で言ってます? リアルに東京ドーム何個分とかの世界ですね」
「そこまで特別広いってわけじゃないよ。ね?」
私達の後ろをついて来ていた恭平さんを振り返る。
「2個分」
と彼は短く答え、伊藤は目を見開いて私を見た。
「広かった」
肩をすくめて微笑む伊藤に私は照れ笑いで返す。
目の前に広がる広大な田園と、雄大な山並みに飲み込まれるような幸せな錯覚を味わう。
3月と言えば米農家にとっては一年の始まりであるらしかった。
田に植えるための種籾をある程度まで育てる「育苗」という作業が行われており、
整然と並べられた小さな緑の苗達を眺めるだけでうっとりとしてしまう。
私は特別農業に興味があるわけではない。
しかしこれから田に植えられていくであろう苗達は、
ひとつひとつが恭平さんと冴さんの手によって育てられたのだ。
ここにも人の営みの息吹を感じる。
東京で、バイラル4スタジオで、魂を削ってバンドが己を研鑽し続ける日々の反対側で、
彼らは苗を育て、米を育てて生きている。
私は今とても当たり前の話をした。
しかし正直私はこれまで、その当たり前の日常を想像せずに生きてきた。
伊藤織江と知り合い、彼女のご両親を通して見た「当たり前の風景」に、
恥ずかしながら私は震えるほどの感動を覚えた。
そこへ、私達の側を通りかかった農作業の服を来た男性が立ち止まる。
こちらも恭平さん達と同じく60代ぐらいに見えた。
その男性は立ち止まってこちらへ歩みよって来ると、それに気づいた伊藤の顔を見るなり、
「おりんちゃんか?」
と言った。
伊藤はしばらくその男性をじっと見返し、やがて両手を口に当てて、
「イバラギさん!」
と言った。
少し離れた場所にいた恭平さんがこちらへ戻って来る。その横には冴さんもいて、二人は満面の笑みだ。
伊藤は紅潮した笑顔を私に向けると、現れた男性を紹介するような仕草で言った。
「親戚のおじちゃんなの。茨木さん」
「ご親戚の方ですか!初めまして、東京から来ました時枝と申します」
茨木という男性は、被っていた帽子を取ると恥ずかしそうに頭を下げて、
「茨木ですう」
と関西訛りの口調で挨拶してくださった。
何気にこちらへ来て初めての関西弁である。
「え、偶然?」
と伊藤が両親に尋ねる。
「そんなわけないでしょう、昨日電話で話したの。会いたいって言ってくださって、こんな朝早くから」
「えー。ありがとう」
伊藤はそう言うと茨木さんに抱き着いた。
茨木さんはシャイな人らしく、顔を真っ赤にして恭平さんに助けを求めた。
「おりんちゃんは変わらんなあ。すぐ分かったわ。いくつなったん?」
「あはは、もう40」
「嘘やろ!? おりんちゃんが40! 恭平、そら俺らもガタガタなるわけやで」
恭平さんと冴さんが声に出して笑う。
圧倒されていた私を見て、冴さんが話して下さった。
「茨木さんはね。うちの人のお父さんの、弟さんの息子さんなのよ。まだ子供の頃に家族でこっちへ引っ越して、この辺りで農業を営んでいてね。うちの人の弟と仲が良かったのもあって、一緒にこの道40年以上の大ベテランってわけ」
「そうなんですか。もとは東京の方なんですね」
「もとはね。でも子供の頃から京都だし、本人はもう完全に関西人よね。乃依の事はご存じ?」
「もちろん」
「茨木さんよく東京へ遊びに来て、織江や乃依と遊んでくれたのよ。あの通り、物凄く可愛がってくれてた。いかにも関西人らしく口は達者だけど、嫌味のない本当に優しい人よ。あの人がこっちにいるのが分かってたから、私達も安心して移り住めたのよね」
「織江さんの笑顔が物語ってますよね。…おりんちゃんですって」
冴さんと話をしていた私が笑うと、伊藤は照れ笑いを浮かべた顔で振り返り、
「何年振りだろうね、そう呼ばれたの」
と冴さんに尋ねる。
「さあね。あなた、たまあに帰っては来るけどすぐにとんぼ返りするでしょ。茨木さんも寂しがってたのよ。ねえ、茨木さん」
急に話を振られた茨木さんは赤い顔で大袈裟に頷いて見せた。
「せや。タイショウは元気にしてるか?」
「元気よ」
「リュウも、ショウちゃんもか」
「皆元気よ。茨木さんも、元気そうで良かった」
伊藤の声が涙で上ずり、茨木さんの目もキラキラと滲んでいるのが分かった。
子供の頃から姉妹を可愛がっているという事は、池脇達ドーンハンマーの面子を知っているという事なのだろう。
聞き慣れない彼らの愛称を知って、私まで胸が熱くなる思いだった。
「時枝さん」
恭平さんが私の名を呼ぶ。それだけで私は嬉しい。
「はい」
私と冴さんの側まで来ると、楽しそうに話し込んでいる伊藤と茨木さんを見つめながら恭平さんは言った。
「織江はしっかりしてる子だけどね。あんまり自分の事は喋る方じゃないから、私らもずっと心配だったんだ。東京でのあの子の様子を、聞かせてくれると嬉しいんだけどね」
「是非、私でよければ」
「ありがとう。じゃあ、行ってくる」
そう言うと恭平さんは冴さんに頷いて見せ、茨木さん達の方へ歩きだした。
「いってらっしゃい」
「いってらっしゃい」
冴さんと共にそう声を掛けて背中を見送る。
伊藤は父親の肩を揉んで声を掛け、茨木さんに会釈する。
「晩飯食おな」
茨木さんはそう言うと、頷く伊藤に向かって片手を挙げ、恭平さんと共に畔道を歩いて仕事に向かった。
「あははは!びっくりしたー!」
伊藤は明るく笑って、涙を拭いた。
寒さの残る野風に吹かれて、伊藤の長い髪が地面と平行になる高さまですくい上げられる。
今更ながら、彼女が冴さんの服を着ている事に気付いた。
白と青のボーダーニットと、ベージュのフレアロングスカートだ。
確かに普段伊藤が好んで来ている服装とは印象が大分違うのだが、
不思議と、伊藤織江という女性本来の姿がそこにあるようで、
とても清らかで美しい反面、胸の奥がぎゅっと締め付けられるのを感じた。
この地へ来て度々、私は伊藤の持つ爽やかな女性らしさにハッとしては、
一抹の不安と寂しさを感じていた。
手を掴んで今すぐ東京へ連れ帰りたくなるような、そんな焦りにも似た寂しさだった。
二日目の夜。
恭平さん、冴さんでの二人暮らしが長い為か、
キッチンのそばに置かれたダイニングテーブルは少し小さめで、
大人4人が座るとお互いの距離がとても近く感じられた。
どんな料亭にも負けない、心の籠った素晴らしく美味しい晩御飯を頂いた後、
温かい緑茶で心までホカホカになりながら、静かに語られる思い出話に私は聞き入る。
伊藤姉妹の幼い頃の話。
神波達と知り合ってからの話。
学生時代の話。
成人して社会に出てからの話。
仕事の話、そして神波との結婚。
笑いの絶えない幸せな記憶であったが、
やはりそれでも乃依さんの名前が出る度に優しい空気が生まれる事が、
新参者の私には辛く感じられた。
思い切って口を開く。
「私は音楽雑誌の編集者をしておりまして、東京では織江さんをはじめバンドの皆さんに大変お世話になっています。去年の今頃から取材を開始して丁度一年が経とうとしています。その中で強く感じているのが、バンドの持つ演奏技術の高さや音楽的な才能もさる事ながら、とても人間的な魅力に溢れている方達だという事です。私がこんな事を言うと笑われるかもしれませんが、織江さんが大成さんとご結婚された時、嬉しかったのではありませんか?」
私の投げかけた問いに、冴さんはパっと明るい笑顔になってこう言った。
「綺麗に喋るわね!」
私は反射的に両手で顔を覆った。
「すみません! 仕事みたいですよね!」
「いいのいいの。よく分からないけど今、久しぶりに東京の風を感じたわ」
「お恥ずかしい」
「職業病みたいなもんだよね。時枝さんて凄いのよ。相手の本音や深い部分にある気持ちを引っ張り出す事にかけては、私の知る中でピカイチだもの」
娘の言葉に冴さんは頷き、
「そのようねえ。…もちろん、嬉しかったですよ」
と言った。
私は顔を真っ赤にしてお茶を啜る。
「私らはね」
と言葉を繋いだのは、恭平さんだ。
「全く彼らをその、所謂バンドマンとして見たことはないんだよ」
「…そうなんですか」
彼は普段言葉を多く発するタイプではないそうだ。
今朝自分から私に話を聞きたいと申し出た責任を感じていたのだろうか。
家族が驚きの表情を浮かべる程饒舌に、素直な気持ちを聞かせて下さった。
「子供の頃から皆を知ってるからね。うちにも、何度も遊びに来てくれたよ。よく覚えているのがね、皆いつも正座なんだよ。こっちはもちろん足を崩しなさいって言うんだけど、照れ笑いを浮かべたまま決して崩さない。織江に聞いてびっくりしたんだが、茶の間だけじゃなくて、この子の部屋にいる間もずっとそうだったと言うんだ。なんだか、今時の子にしては感動するくらい真面目だなあと思ったのをたまに思い出すよ。中学卒業くらいまでは、よく東京の家で見かけたもんだけど、高校に上がるとめっきり顔を見なくなってね。母さんと、どうしたのかなあって話してた。思春期だし、友達の顔ぶれだってそりゃあ変わるもんだろうとあえて織江に聞いたりはしなかったけどね。それがある時、街でタイショウを見かけてね。懐かしくて声を掛けたんだ。拍子抜けするくらい変わってなかったよ。いや、変わっていたのかな。とても精悍な顔つきをしていてね。高校生なのに、もう大人の男の顔をしていたよ。元気にやってるのかって聞くと、『元気です。いつも織江さんにお世話になってます』って頭を下げて言うわけだよ。同級生なんだよ? 相変わらずだなと思ったのと、まだ付き合いは続いてたんだなって分ると嬉しくてね。またうちへ遊びに来なさいよって言うんだけど、ありがとうございますとは言いながら、その後もしばらくは、姿を見せる事はなかったな」
「確かに、若いのに気ばっかり使う子達だった。神波さんの所も、だいぶ苦労なさったからねえ」
冴さんのしんみりとした言いように、コラ、と恭平さんは静かに窘めた。
他所様の苦労を勝手に語るもんじゃない、と言う意思が感じられた。
「大丈夫よ。時枝さんはぜーんぶ知った上で、ここにいる人だから」
伊藤がそう言うと、冴さんは湧き上がる感情を堪えるような顔で頷き、湯呑みを両手で握った。恭平さんが続ける。
「織江達が成人して、ちょくちょく雑誌やテレビなんかで彼らを見かけるようになってからは、もちろん私らも喜んではいたんだが、どうもそういう芸能人感覚は、理解出来なくてね。真面目で、いつも真剣に何かを考えていて、考え過ぎて眉間に皺の寄るような、若いくせに年寄りみたいな、そんな織江の友達であり、ボーイフレンドであり。いつ会っても言葉遣いはみんな丁寧だし、思いやりのある言葉で私らに接してくれていた」
冴さんが嬉しそうに笑って、頷く。素敵な思い出が甦って来たのだろう。
恭平さんは続ける。
「だから当然二人が結婚すると知った時、物凄く嬉しかった。私は、乃依を亡くした時の彼らの悲しみようを思い出したよ。リュウの絶望的な涙、アキやショウちゃんの叫び声が昨日の事のように蘇ってきて。…タイショウと織江が幸せになってくれて本当に良かったと、親としてこんなに嬉しい事はないと思ったし、それは今でも思ってるんだ」
微笑みを浮かべて聞いていた冴さんはギュッと目を閉じたかと思うと、
立ち上がってキッチンのシンクに向かい、緑茶のお代わりを湯呑みに注ぎ始めた。
その背中はやがてブルブルと震え、しばらくは戻って来られないように見えた。
私は自分の太ももを右手で力一杯捻り上げ、堪えろ!堪えろ!と念じていた。
私が泣いて良い場面ではない、理解したつもりになって泣いて良い場面ではない。
そうに自分に言い聞かせた。
「二人でこの京都の家に挨拶に来てくれた時、いつにもましてタイショウは無口だったな。まだリフォーム前の傷みの多い家でね、タイショウが私らの前に正座した時、恥ずかしいぐらい床が軋んだんだ。それでもあいつは押し黙ったまま笑いもせず、何も言わない。私も母さんも二人が何をしにこんな所までやって来たのか知っていたから、敢えてこちらからは何も言わずにタイショウの言葉を待ったんだ。もの凄い顔をしていたよ。緊張とかそういう事ではなかったんだろうね。色々と彼なりに思う所があったんだと思う。待ってるこちらが苦しくなるほどの沈黙があって、正直私なんかは、もう良いよって、何度もそう言いかけたんだ。気持ちは痛いぐらい伝わったし、言葉なんて、そんなに大事じゃないって思ってるような古い人間だからね。だけど、いきなりだよ。タイショウが奥歯をぐっと噛み締めたまま泣き出したんだ。それで、ボロボロと涙を流しながら言うんだ。『本当は、精一杯格好付ける気でやって来て、この有様です。私にはどうしても、あなた達に向かって、お嬢さんを下さいとは言えません。私が、伊藤になります。よろしくお願いします』。そう言って頭を下げた。きっと乃依を失った私らの気持ちを考えての言葉なんだろうね。その時までそんな事は一切考えなかったんだが、タイショウがそう言った瞬間不覚にも、私も母さんも声を上げて泣いてしまったよ。なあ、母さん」
冴さんは鼻をすすると何とか小さく笑い声を上げて、再びテーブルに戻ってきた。
私は顔を上げる事が出来ない。
先ほどから伊藤が私の背中を優しく撫でている。
この世で一番暖かい手だと感じていた。
「まあ、なんて言ったらいいか分からないけどさ」
と、娘によく似た口調で冴さんは言う。
「子の幸せを願うのが親ってもんでしょう。だから同じように、目の前のタイショウが幸せである事も願っていたし、同じように喜んでもいた。だけどあの子が伊藤になるって言い出した時、心から嬉しかったと同時に、ダメだダメだ、こんなことでは女手一つで頑張って来られた神波さんに顔向けが出来ない!って思ったよ。それに、嬉しかったのはきっと、タイショウが伊藤になるっていう可能性なんかよりも、そう思ってくれていたあの子の気持ちだよね。あの子は本当に親思いだし、友達思いのいい子だから。乃依や、亡くなられたお父様や、大切なお母様の事を思いながら泣けて仕方なかったあの子が、それでも『伊藤になる』って言った事は、あーはいそうですかありがとうとは、受け入れられないよね。こんなに優しい子が織江と一緒になってくれるんだっていう、そういう嬉しさで、胸が締め付けられる思いだった」
「ああ。その事があってから余計に、織江の事よりもタイショウやリュウが本当に幸せかどうかを考えるようになった。それに、まあリュウも酷かったが、…ショウちゃんがね。乃依の死を前に混乱してしまって、言葉にならない叫び声を上げていたのを私らは見てるからね。この子達はこの先どうやって生きていくんだろうって心配になるぐらい、嘆き、悲しんでくれた。私らにとっても、あの子達は本当に特別だから。…東京で織江はちゃんと、彼らの為にやっているか、タイショウは幸せか。皆頑張ってるか。こっちへ来て辛いのは、そういった事がすぐに分からない事なんだよ」
「織江はめったに帰ってこないし、電話もすぐに切ろうとするしね。忙しいのは分かるけど、もう少しちゃんと色々聞きたいものよね、親としては」
拗ねたように言う冴さんの言葉に恭平さんは苦笑いしながらも、頷いた。
伊藤はハンカチで涙を抑えながら笑い、
「こっちはこっちで、色々あるのよ」
と言った。
「色々ねえ。あ、誠や繭子は、いくつになったの?」
「誠は今31、繭子は29になった」
「あはは、あの子一体、いつまで20代でいる気なの!?」
冴さんの言葉に俯いていた私まで吹き出して笑った。
「長いよねえ。知り合った時はあの子達二人とも10代だもん。繭子なんて12月に29になったばかりだよ」
「二人とも元気なの?」
「なんとかね。頑張ってるよ、二人とも」
「そう」
私は自分の出番が回って来たのだと悟り、涙に濡れた顔を挙げた。
ノーメイクが幸いしたが、それでも恥ずかしい程泣いた事に変わりはない。
無かった事には出来ないと知りながら、私は努めて明るく話し始めた。
恭平さんや冴さんの期待した通りの報告が出来たかは分からない。
しかし私なりにこの一年で感じた伊藤織江という女性の勤勉さ、優しさ、温かさ、そして強さを、時に涙で声を詰まらせながら話した。
今度は伊藤が黙って立ち上がり、キッチンで湯飲みを洗い始めた。
恭平さんはそんな娘を窘めようとしたが、彼女の横顔を見て声を掛けるのをやめたようだ。
私に向かって、すまないね、とでも言いたげな苦笑いを浮かべて頷いて下さった。
三日目。
朝、お手洗いを借りて2階の部屋へあがろうと階段に足を掛けた時、
一番上の段差に腰を下ろして壁にもたれている伊藤と目が合った。
「どうされました?」
と私が声を掛けると、彼女は目をパチクリさせて、
「え?」
と言った。
「はい?」
と私が聞くと、伊藤は右耳からイヤホンを抜いた。
「ごめん、何か言った?」
「こちらこそ。何を聞いていらっしゃるんですか?」
「ネムレ」
「ん?」
「『NAMELESS RED』」
「あはは。ようやく、発売日が迫りましたね」
「二転三転したもんね。ぎりぎりになって、収録曲変えたいって言いだした時はスケジュール組む私の身になれ!って思ったけどね」
「あははは。でも、仰りはしなかったんでしょうね」
「言えないよね。遊んでるわけじゃないし」
「確かに」
私が階段の上まで辿り着くと、伊藤は立ち上がって二人で部屋に戻る。
カメラの電源を入れた。
それには伊藤も気付いている。
あまり映り込むような物がないとは言え、実家の部屋だ。
プライバシーを考慮して、伊藤が部屋の中央に座ると彼女の横顔がアップになるよう調整した。
午前中の明るい時間帯は部屋の電気を消しているため、モニターの中の伊藤は少し薄暗く映り、
却って芸術的な程白く美しい横顔のラインが浮かび上る。
「昨日、長話に付き合ってくれてありがとね」
と、伊藤は言った。
「いえいえ」
「それから、ごめんね」
「ええ? 相変わらず泣いてばかりで申し訳なかったのはこちらのほうですよ」
「ううん、そんなのは平気」
「では」
「一年前にさ、詩音社の取材を受ける事にしたのは、あなたを利用する算段もあったんだって私が言った事、覚えてる?」
「はい」
「ふふ。今回もそうよ。どうせ実家に戻ったら、お母さんからあれこれ聞かれるに決まってるだろうなあ。お父さんは聞きたいけど聞きづらそうな顔をするんだろうなあ、とか。日本を出ちゃうからさ、顔見せに来ないわけにはいかないし、もちろん私もちゃんと顔を見ておきたいっていう気持ちもあったけど、どうも私は自分の話をするのが下手なのよね。苦手なのもあるし。本当は大成も来たがったんだけど、もうちょっとギリギリにしようよって私から説得したの。久しぶりに二人で来たらきっと質問攻めにあって、あの人疲れちゃうからね。だからさ、時枝さんがついて行きたいって言った時、じゃあ私達の代わりに全部喋ってもーらおっとって。あはは、いい加減腹立つでしょ、私」
「全然立たないです」
「あなたも大概だねえ、人が良すぎるって言われない?」
伊藤は呆れたように眉根を下げて笑った。そして、
「何を言っていいか分からないのよ、ほんと言うと」
と彼女は続ける。
「聞かれた事だけ答えていれば良い気もするんだけど、それだけじゃダメな気もする。だけど私は自分から語れるような何かを持っているわけじゃないし、困るんだよね。だから昨日は本気で助かった」
「あんなの、あと10倍は喋れますよ、私」
「あはは」
「織江さんを心から尊敬しています」
「ありがとう。でも、時枝さんだから分かってもらえると思うんだけどね、例えばバンドと自分を考えた時に、虚しくなる瞬間は確かにあるのよ」
伊藤は両膝を抱えて顎を乗せ、彼女と時枝の丁度真ん中あたりを見つめながら話し始めた。
「『NAMERESS RED』の一曲目、『SUPERYEAH』を初めて聞いた時にもそれを痛感した。あの人達は他人に語って聞かせる夢もなく、したり顔で熱い言葉を話す事もせず、好きなように歌って叫んで、それでも、これでもかというくらいに私の胸を打つ。何だ、こんな事が出来ちゃう人達なら、私必要ないんじゃないのって思うの。忙しくて目が回りそうな時なんてよくそんな事考えるよ。私ホントに必要かなあって。年末にさ、翔太郎と『合図』で話した時なんて分かりやすいと思うけど、とにかく皆優しいから気を使って私を立てようとしてくれるんだけど、これって私が幼馴染じゃなくても、同じように思ってくれるのかな、とかさ。いつもじゃないよ。そういう風に思っちゃう時もある、って。そういう話」
「分かりますよ。とてもよく分かります。そういう意味ではきっと私の方が、強く抱いている感情だと思います。皆さんの側で皆さんのお話を聞いて、皆さんの努力を見て皆さんの本気を感じて。そうやって私の記事は出来上がります。だけどその記事にあるのは私自身ではなくて、皆さんのありのままの姿です。もちろん記事を書き上げた瞬間の達成感はあります。だけど私は他人の人生、他人の夢に乗っかっているだけなんじゃないかって、辛くなる事もあります」
「似たもの同志だね」
「違いますよ。織江さんは違います」
「どうして?」
「私は自分の意志で、自分がどうしても読みたくて、書籍化の企画を通す前に皆さんの伝記を書き始めました。そうでもしないと、私は自分を見失いそうになっていたからです。私は今でも『Billion』のファンですし、素敵な記事を一杯読んできましたから、大好きです。だけどいざ自分がバンドの側に立って取材を進めるうちに思ったのが、私は理想の雑誌編集者になりたいわけじゃないんだって事です。…織江さんは、これまで物凄く苦労と努力を積み重ねて来られた方です。その原動力はどこにありますか?」
「苦労と努力…。んー、どこって言われるとな」
「分からない?」
「何が苦労で、何が努力だったのか、覚えてない」
「織江さんらしいですね」
「なんで? 私のどこに苦労の痕を感じ取ってるのか分からないけど、そりゃあもちろん疲労はあるよ。でも苦労ってなんだろうなって思うと、『だって勝手に好きでやって来たじゃない』って自分で突っ込み入れちゃうもんね。例えば英語の勉強だって、会社経営の勉強だって、それは夢とか目標じゃなくて今やりたい事をやっただけだもん。必要だと思う事をやっただけで、どこかへ至るための偉大な一歩だとか、大きな目標を掲げた事が今まで一度もないんだよ」
「だからですよ」
「ん?」
「だから、私と織江さんは違うんです。織江さんは、私からすれば紛れもなく『ドーンハンマー側』の人です。ただ、やりたい事をやって来ただけ。そして今があるんです。その結果、織江さんは社長であり、大成さんの奥様なんです。竜二さんや大成さん、翔太郎さんや繭子と何も変わらない。彼らに必要とされているかを外から見て考える必要などなく、彼らの中にあなたはいます。織江さんはドーンハンマーです」
伊藤は膝の上から顔を上げると、数秒空中を見つめた。
やがて私の目をしっかりと見つめて、頷いた。
「ありがとう」
私がペコリと頭を下げて応えると、伊藤はニッコリと微笑んでこう言った。
「じゃあお礼に、良いもの見せてあげようか」
言葉の意味は分からなかったが、私はこの時既視感のようなものを感じていた。
それはどこかで見たというよりどこかで感じた事のある気持ち、と言い換えるべきものだった。実態はつかめないし、それが何なのか考えるより先に伊藤が立ち上がり、私を部屋の外へ連れ出した。
だがその『良いもの』は、隣の部屋の事だった。
扉の前に立って、伊藤はトントンとノックする。
返事はない。
「どなたの部屋ですか?」
「ノイ」
私は驚いて、扉を見つめる。
伊藤は扉の前に立ったまま、少し話をした。
「うちの親がこの家に越してきてリフォームをした時に、お母さんがこの部屋をノイの部屋にするって言いだしたの。もともと誰も使ってない部屋なんだけど、小さな部屋二つの壁を壊して8畳程の一つの部屋にしたの」
「へえ」
「もちろん、この部屋を作った時には、もうノイはいないんだけどね。なんだかとてもうちの親らしいなと思って」
「素敵だと思います、私も」
「入るね」
部屋の中に向かってそう言うと、伊藤は扉を開けた。
私は少しびっくりして半歩後退りした。
部屋の真ん中に誰かがいるような気がしたのだ。
「びっくりするよね。まあ狙ってやってるんだけど」
部屋の真ん中には、黒いベースが立てかけてあった。
「あれは」
「入って。そう、うちのタイショウのベース」
伊藤の口から聞くタイショウという呼び名がとても可愛らしくて、思わず胸がきゅんとする。
「なんか守り神みたいでしょ、真ん中にどーんと鎮座しちゃってさ」
「確かに、そう見えますね」
「これは大成が自分で置いてったの。このベース、本当は今竜二の物なんだけどね。下手くそだったけどノイはギターが好きだったから、じゃあ俺はその横でベース弾いてやるって、竜二が大成に習い始めてさ。そしたら大成が大事にしてた自分のやつを、このベースを竜二にあげたんだ。なんかそういうの嬉しいよね。はっきり言うとここにあっても邪魔なんだけど、自分がこの家にいない間は、代わりにこいつを置いておこうって大成が提案して、竜二がわざわざ東京から持って来てくれたの。だから絶対にどけたくないんだ。可笑しいのはね、この裏側見て、ここ、ここほら、全員のサインが入ってるの。アキラのもあるし、カオリのも、誠と繭子、マーとナベのもある」
「ああ、本当ですね。これは世界一レアで思いの籠ったベースですね!」
伊藤はスカートのポケットに手を入れると、白いサインペンを取り出した。
「はい。時枝さんも書いて」
「え、無理ですよ」
「嫌なんだ?」
「嫌なわけないですよ」
「じゃあ、書いて」
私はなるべく他の皆さんの邪魔にならない場所を選び、出来るだけ目立たないように自分の名前を書いた。申し訳ない気持ちを抱えたまま伊藤にサインペンを返すと、思いがけず近くに彼女の顔があって照れた。
伊藤は肩で私の体を押して、「ありがと」と言った。
こちらこそと私が言おうとする前に彼女は立ち上がり、
「お腹すいたな。畑になんか獲りに行こうか」
と言って部屋を出ていった。
私はベースに向かって深く頭を下げると、伊藤の後を追って部屋を出た。
キッチンで立ち仕事をしていた冴さんにも声を掛けて田へ向かう。
畦道を歩きながら、前を行く冴さんに聞いてみる。
「どうして翔太郎さんだけショウちゃんって、ちゃん付けなんですか?」
すると冴さんはピタリと立ち止まって、キョロキョロと周囲を確認する。
やがて私の方に近づいてくると、小声でこういった。
「お気に入りだから。これ内緒ね」
私はこの地へ来て一番の大声で笑った。冴さんは少しだけ困った顔をして、
「でもね、タイショウがやっぱり特別だからね。だから『アンタがタイショウ』のタイショウ。ここ大事よ」
「違うでしょ! タイセイだからタイショウなんでしょ。適当な事言わないの。時枝さんピュアだからそのまま記事に書いちゃうよ」
「あらま」
私はお腹を押さえて大笑いした。
遠く離れた地で聞く彼らの名前はとても新鮮に胸に響く。
しかし印象は少しも変わらない。
いつだってどこだって彼らは素敵だ。それが今、とても嬉しい。
畑で獲れた旬の野菜で贅沢な昼食をいただくと、
その日は伊藤と二人で何もせず、大の字に寝転がってだらだらと一日を過ごした。
不意に、仰向けになって天井を見上げたまま、伊藤が言った。
「今急に思い出した。カオリの話していい?」
「もちろん」
「前にさ、誰のインタビュー撮ってる時だか忘れちゃったけど、時枝さんが言ったの。『何でUP-BEAT?意外です』って、そんなような事を」
「あー、えーっと。繭子が翔太郎さんの歌を褒めた時ですね」
「ああ、そうだね。繭子はその時、そうかなーなんて曖昧な返事してたと思うけど。あれね、本当はちょっと素敵な裏話があって」
「へえ、どのような」
「知り合ってどのぐらいの頃だっかたまでは覚えてないけど、カオリにね、『お前らは普段どんな音楽聞いてるんだ?』って聞かれてさ」
「それは、織江さんがですか?」
「そうそう、私とノイね」
「ああ、はい」
「私音楽の話はそんなに得意じゃないしさ、カオリを前にしてウソでもパンクロックが好きだなんて言えないよなって観念して、UP-BEATって答えて」
「あ、え!? 織江さんが好きなんですか!」
「うん。もう子供の頃からずっとファンでさ。私東京の自分の部屋にポスター貼ってたもん。色褪せても破れちゃっても補強して、ずーっと」
「へえー。でも、織江さんならば、うん、意外ではないですね」
「あはは。ギターの岩永さんが好きでね。お母さんに言われたもん。あんたこんな男前に惚れこんじゃうと、現実と向き合えなくなるよって」
「あははは!」
「でもびっくりしたのがさ、大成と初めて会った日に『いた!岩永さんより男前いた!』ってお母さんに報告したんだって。そこは私覚えてないんだけど」
思わずエビのように丸くなってお腹を抱える。
「まあ、そこは別に良いんだけどさ。でね、カオリに白状した時、ちょっとドキドキしたの。どちらかというと王子様的な、そういう格好良さのあるバンドだったし、硬派なイメージではなかったからね。だけどカオリはニッコリ笑って、『いいね、アタシも好きだよ』って言ったの。嬉しかったし、ますますカオリが好きになったのを覚えてる。口は悪いしぶっきら棒だけど、心底優しい人だから、例え私がどんな音楽を好きだと言った所で、カオリはニッコリ笑ってくれただろうなって、そう思って」
「素敵な話ですね」
「まだ序の口」
「あはは」
「ノイが亡くなった時ね」
「…」
「皆酷かったんだ。私も含めてね。辛くて辛くて、泣いて、叫んで、暴れて、…泣いて。お葬式の時も、お父さんも言ってたけどさ、皆もう、壊れたような感じになってた。だけど唯一、カオリだけは涙を見せなかったんだ。後になってね、彼女が言うわけ。『誰か一人くらいは、しっかり立って見送ってやんないと、あの子も心配だろうと思ってさあ。…スゲー泣きたかったけど、お前ら皆バカだから』って。ありがとうって、私何度も頭を下げてお礼を言って。そしたらカオリが笑って、…あ、昔のスタジオでの話なんだけどね。カオリが笑って、アコースティックギターを抱えて、UP-BEATの夏の雨っていう曲を歌ってくれたの。私、カオリがUP-BEATを好きだって言ったのはどこかでウソなんだろうなって思ってたから、びっくりして。広石(ボーカル)さんの歌声ってハスキーでセクシーな低音が魅力なんだけど、その時歌ったカオリの力強い声は、もう、なんか、叫び声だったよ。ワンコーラス歌って、サビを歌い始めた瞬間、カオリが泣き始めて。曲自体は前向きな失恋ソングだと思うんだけどね。『サヨナラ、スイートレイディー』っていう歌詞があって。歌い始めた瞬間カオリの目から大粒の涙が溢れた。ずっと、ノイの為に我慢してくれてた涙が溢れたんだと思って、私達も大泣きして。…それまでUP-BEATなんて聞いてこなかった大成達も聞くようになって、今じゃカラオケ好きな繭子まで歌い出す始末だよ」
この時私達は寝転がって天井を見つめているので、
伊藤がどのような表情を浮かべていたのか私には分からない。
長い沈黙の後、今頃きっと、皆鬼みたいな形相で練習してるな。
とポツリと伊藤がつぶやいた。
ふり絞った声で、「そうですね」と私が言うと、彼女は呑気な声で天井に向かい、
「がんばれー」
と言った。
続く。
私にとっては、急と言えば急な話だった。
いつからその日に向けて調整されていたのかその時の私には知る由もないが、
伊藤織江が仕事を休んで一週間旅行に出かけると言う話を聞いた。
もちろんバンドメンバーも事務所のスタッフも事前に知らされており、
その事を聞いて慌てたのは私一人だった。
仕事人間と言えば聞こえはいいが、
伊藤に対しては誰もが「働きすぎ」だと感じていた。
休みを取って一週間の旅行と聞けば喜びをもって笑顔で手を振る場面のはずが、
私の胸を過ったのは心細さとも呼べる不安だった。
これまでも伊藤と一週間会わない事はいくらでもあった。
しかし「一週間会えない」と聞かされて急に不安を感じたのだ。
バンド取材に対する不安要素という意味でない事は分かっていた。
個人的な話で恐縮だが、その頃私は問題を抱えており、茫然とする事がよくあったそうだ。
そうだ、と他人事のような言い方になるのははもちろん自覚がないからで、
人に指摘されてようやく気付く程、自失している場面も多かったという。
私が伊藤の旅行を聞いたのは彼女の出発予定日の2日前、3月8日の事である。
まだ就業中で社内にいる時間帯に電話を受けられた事は運命だと言えた。
「一週間休暇で留守にします」
私はとてつもない報告を受けたような衝撃に戸惑い、
いつですか、とかなり深刻な声で返事をして電話越に笑われた。
3月10日と聞いた時、私は泣きそうになりながら、
ついて行っていいですか、と考えるより先に申し出ていた。
まだ行先も聞いていないのにだ。
私の不穏な空気を電話の向こうで感じ取ったのだろう。
考え込むような沈黙の後、伊藤は笑いもせずにいつもの優しい声で、
「お休み取れる?」
と言ってくれた。
私は心底救われたような気持になり、すぐに上司に頭を下げて一週間の休暇を願い出た。
穴を開ける事は承知の上だから、当然有給ではなく欠勤扱いで構わないと懇願した。
自慢ではないが記事を書くスピードは編集部内で誰にも負けない。
もちろん、休暇中も時間が取れれば記事を書いてメールで送ろうと思っていた。
その点においては、一週間という日数であれば取り返せるという自信も私にはあった。
すぐに伊藤へ折り返し、許可が下りた事を告げた時初めて行く先を聞くと、
「京都」
との返事。
へえ、いいですね。
「でも実家に帰るだけだよ?」
そうなんですか。
私は嬉しさのあまり深く考えらずにいたが、不思議な話だった。
伊藤織江は生まれも育ちも東京のはずだ。
例えばそれが京都旅行ならば、素晴らしい考えだと喜ぶだけで良い。
しかし彼女の口から聞いた内容からすれば、それは「帰省」と呼ぶべきものだった。
日本をしばらく離れる事が決まった時から、彼女は今回の帰省を計画していたそうだ。
聞けば伊藤の実家は今、確かに京都にあるという。
もともと父親の兄弟が京都で農家を営んでおり、10年程年前病で他界した折、
伊藤の父がその地盤を引き継ぐ形で京都へ引っ越した。
東京で生まれ育った彼女にしてみれば、実家が地方へ移動した珍しいパターンと言える。
これまで何度か帰省はしていたが、忙しさもあり纏まった時間を家族と過ごすのはとても久し振りとの事だった。
本当は神波も今回の帰省に付き添うはずだっただが、伊藤の方から遠慮したという話を聞いて、後先考えず同行を願い出た自分を思い切り恥じた。
そして当日。
東京から新幹線に揺られて京都駅へ到着するまでに2時間弱。
そこから在来線に乗り換えて鈍行列車で30分強。
目的地の駅へ到着し、ホームに降り立って真っ先に思ったのは、
「京都であって京都ではなし」といった感想だ。
伊藤の実家は観光名所ひしめく京都市内からは趣を異にした郊外都市にあり、
そこは周囲を山々に囲まれた盆地と呼ばれる地形であるらしかった。
3月に入ったとは言え降り立った地はまだまだ肌寒く、
忠告通りコートを羽織ってきて正解だった。
「風光明媚というか、田舎でしょ」
となぜか照れたように笑った伊藤と並んで立ち、私は首を横に振る。
まるでその土地の人間のような顔で笑う伊藤に、初めて訪れた土地に対して嫉妬した。
「あなたがいれば、どこだって天国です」
私がそう言うと、伊藤は目を丸くして私を見つめ、5秒後、盛大に吹き出して笑った。
ポケットに手を突っ込んだまま体をくの字にして声高らかに笑う美女に、
移動中であろう通りすがりのサラリーマンが好奇の目で私達を見た。
実は長い電車移動の最中、ずっと言おうと考えていた言葉だった。
はっきり言えば、私はこの時より随分前から伊藤織江に心酔していたのだ。
彼女が側にいるだけで、何時間でも電車に揺られていられると思った。
「何が」や「どこが」というポイントを挙げるのが嫌なくらい全てが好きだ。
あの関誠や芥川繭子をして「完璧」、「人として理想」と言わしめる女性なのだ。
知れば知るほど、のめり込んでいく自分に気づいていた。
もやは私にとって伊藤織江は、バイラル4の代表でありドーンハンマーのマネージャーという裏方の存在ではなくなっていた。
彼女の後ろをついて歩くだけで少し、自分が誇らしく思えた程だ。
改札を出て駅構内から外は、ホームから見渡せた山々とは打って変わって、
そこそこの交通量を見せる駅前繁華街だった。
どうやって移動するのか伊藤の決断を待っていた所へ、
「織江」
と彼女の名を呼ぶ声が聞こえた。
見れば60代ぐらいだろうか、背が高く質の良い衣服を身にまとった淑女が満面の笑みで立っていた。一目見て伊藤の母親だと分かった。
「久しぶり」
と伊藤は一歩を踏み出し、彼女と抱き合った。
「こちら、東京の出版社にお勤めの時枝可奈さん。うちのを御贔屓にしてもらってるの。時枝さん、母です」
私は涙が込み上げるのを必死に抑えながら、深々と頭を下げた。
しかし長すぎたせいだろう。
なかなか顔を挙げない私の頭を抱きしめて、
「恥ずかしいからやめなさい」
と言って伊藤は優しく笑った。
駅前の繁華街を抜けて車で走る事10分、
先ほど駅のホームから見えたスケールの大きな田園風景が目の前に広がる。
車を運転する伊藤織江の母は、名を冴(サエ)さんといった。
なるほど、お洒落な母の名前にして織江と乃依ありという事だ。
「遠かったでしょ」
と前を向いたまま冴さんが言う。
「まあね。でも新幹線で2時間掛からないからね、今」
伊藤がそう返すも、
「でも京都駅からここまでまた電車に乗って30分でしょ。そこからまた車に乗って家まで30分よ。はい、3時間超えました!」
と冴さんはお道化る。
つられて私達も笑い声を上げる。
「時枝さんはずーっと東京?」
「はい」
「出版社なんてお洒落よねえ」
「いえいえ、そんな」
「どう?最近の業界は」
「うーん、正直まだ底が見えないですね。やはり昨今の出版不況は…」
「いやいや、本気にしないで。この人に業界の事なんて分からないから!」
「ええ?」
「馬鹿にしてえ、もー」
久し振りの再会とは思えない二人のやり取りに、素敵な親子関係だなと眩しく思う。
お腹が痛くなるまで笑い、涙を全部拭ってようやく私は笑顔になれた。
「わざわざ織江について来てくれたの?」
バックミラー越しに私を見ながら、冴さんが言う。
「無理やり同行を願い出たんです」
「へえ、物好きねえ。こんな田舎、3日で飽きると思うわよ」
「お母さん、シティー派だもんね」
「東京が恋しいわー」
「東京でもまた是非、お会いしたいです」
「会っていきなりそんな嬉しい事言ってくれるの?やっぱりやり手のビジネスウーマンは口説き文句がシャレてるわね!」
「いちいち言葉が古いの!」
時枝、爆笑。
伊藤の実家に到着したのはお昼の12時前だった。
周囲にちらほら田畑が点在する静かな住宅地に、その家はあった。
近所の風景に溶け込んでいる為一見分からないが、とても綺麗な外観である。
聞けば数年前にフルリフォームをしたそうだ。
冴さんは口では東京が恋しいと言うし、生まれ育った街である以上本音もあるだろうが、
この場所を終の棲み家に選んだという事に間違いはない。
駐車場に車を停めて折り立ってすぐ、「お父さんは?」と伊藤が訪ねる。
「朝から田んぼ出てるけど、もうお昼だしそろそろ戻るよ」
「そっか。中入ろうか」
「はい。お邪魔します」
「なーんにもないけどね、ゆっくりして行ってね」
冴さんはそう言うと、自慢げに玄関の扉を開けてくれた。
その後、仕事場から戻って来たお父様にもご挨拶し、4人でお昼ご飯を頂いた。
久し振りに味わう種類の緊張で胸が一杯になったが、
それを上回る幸せな時間を過ごすことが出来た。
今日から始まる一週間が、とても素晴らしい思い出になる予感で胸が高鳴る。
都会の喧騒を離れて、といった表現で田舎を評する声をよく耳にするが、
そういった都市部と比較した環境面とは全く違う部分で、
この穏やかな生活に私は溶け込む事が出来たように思う。
暮しとは、人の営みの事だ。
交通事情や仕事環境や街の活気も確かに、営みを左右する要因ではある。
しかしやはり最も重要なのは人間自身だろう。
午前の仕事を終えて田んぼから戻って来た伊藤織江の父・恭平さんは、
娘の姿を見るなり鼻の下を伸ばして喜んだ。
ルックスは北大路 欣也そのままの人だ。
似てると言われませんかと初対面でも確認してしまう程雰囲気が近い。
しかし娘を見つめる眼差しの温かさと、
寡黙ながら笑顔を絶やさない人柄を見ているだけで、
ここでの暮らしがいかに穏やかで充実しているかが分かった。
「一週間、お世話になります」
と私が頭を下げた時、
「末永く娘を、よろしく見てやってください」
と言われた。
御両親ともに、深々と頭を下げていた。
私はもう涙を堪えるのを諦めた。
初日の夜。
夕飯の後お風呂をいただいて、伊藤の部屋でくつろぐ。
普段使用されていない部屋だけあって、小ぶりの机と本棚以外は何もない。
おかげで、綺麗に掃除されてはいるが殺風景と言えなくもないのだが、
並んで敷かれた布団の上で胡坐をかいて座る伊藤がそこにいるだけで、
寂しさなど微塵にも感じないのだから彼女の存在感はすごい。
「疲れた?」
戻って来た私を見るなり彼女はそう言った。
「全然です。フワフワしっぱなしです」
「それは疲れてるって事だよ」
「自覚ないです。ああ、綺麗な部屋着ですね。ジェラピケですか」
「そうみいたいだね。私のじゃないよ、お母さんの」
「そうなんですか!綺麗なピンク」
肌触りのよいタオル地で出来た、膝丈のワンピースだ。
「私下着以外は一泊分の服しか持ってこなかったの」
「荷物少ないとは思いましたけだど、郵送されたわけじゃないんですね。何故ですか?」
「仕事しないし、人と会う約束もないしね。背格好が似てるから、いつもお母さんの服を勝手に拝借してるのよ。ここへ来る時はそう決めてる。身軽だからね」
「なるほど」
「だからしばらく野暮ったい私をお見せする事になりますが」
「望む所です」
「なんでよ」
そう言うと伊藤はケラケラと笑い、布団の上に横たわった。
「カメラ回していいですか?」
「え、どうして?」
「大成さんに頼まれたので」
「ウソ? ウソだよね」
「聞いてませんか?」
「聞いてないよ、ウソでしょ」
「冗談だったのかなあ。でも私も今すっごく織江さん撮りたいです」
「おばさんを揶揄うんじゃない」
「需要と供給です。ちょっとセットしますね」
「おいー」
「…びっくりされてませんでしたか?」
伊藤の顔を見れないまま、私は尋ねた。
「…涙? んー。まあね、少しくらいは。でもうちの親も、こっちへ来るまで東京でそれこそ馬車馬みたいに働いてた人達だからね。皆それぞれ色々あるって事ぐらい、分かってるよ」
「余計な気を使わせてしまって、すみません」
「なんのなんの。私と違って、見るもの触るものに新鮮なリアクション取ってくれるって、あの二人も大喜びしてたよ」
「あはは、やはり採れたてのお野菜は美味しいですね。意識して春キャベツ食べたのなんて何年振りだろうって」
「多分気付かないだけで絶対口にはしてるんだろうけど、忙しくしてるとなかなか気づかないよね。美味しいものは東京でたくさん食べられるけど、旬の物を家で食べるって今となっては贅沢に感じるもんね」
「子供の頃は、それが当たり前だったんですけどね」
「うちにいっつも送って来てくれるから、今度からは時枝さんにもお裾分けするね」
「いえいえ、そんなご迷惑お掛けできません!」
「事務所にどーんと送られてくるんだよ。それを皆で分けっこして持って帰るの。ってもあれか、今年からは…」
「ああ。お父様たちも仕送り先が減って、寂しくなっちゃいますね」
「そうだね」
代わりに私がいただきます!
例えその場のノリでも、笑ってそう言えたら良かったのだろう。
思いついてはいた。しかし、言えなかった。
私がおどけた時に見せるであろう伊藤の微笑みが簡単に想像できて、
それがあまりに寂しすぎて、無理だった。
伊藤の言うように、やはり疲れていたのだろう。
部屋の入口脇に三脚を立てただけで、布団の上に座って伊藤と話をしているうちカメラの電源を入れる前に眠ってしまった。
朝目が覚めると既に伊藤の姿はなく、昨晩手にしていたはずの私のビデオカメラは、三脚の上に乗せられていた。
二日目の朝。
恭平さんが運営する田んぼを見せてもらった。
何年振りかも思い出せない程久し振りに畦道を歩いた。
前を行く伊藤は両手を後ろに回し、リラックスした様子でゆっくりと歩く。
東京では見る事のない、社長ではない伊藤織江の姿。
一人の女性として。一人の娘として。
そのどちらであれ、私の目に映る素顔の彼女はとても美しかった。
伊藤家所有の農地は家から歩いて5分程の所にあり、
「ここからあそこまで、全部」
と伊藤に指をさされても把握できない程広大な敷地面積だった。
「えー、ちょっと、規模が」
「あそこに林があるでしょ。その手前の畔から、端はあそこ。奥行はあの道路まで」
「本気で言ってます? リアルに東京ドーム何個分とかの世界ですね」
「そこまで特別広いってわけじゃないよ。ね?」
私達の後ろをついて来ていた恭平さんを振り返る。
「2個分」
と彼は短く答え、伊藤は目を見開いて私を見た。
「広かった」
肩をすくめて微笑む伊藤に私は照れ笑いで返す。
目の前に広がる広大な田園と、雄大な山並みに飲み込まれるような幸せな錯覚を味わう。
3月と言えば米農家にとっては一年の始まりであるらしかった。
田に植えるための種籾をある程度まで育てる「育苗」という作業が行われており、
整然と並べられた小さな緑の苗達を眺めるだけでうっとりとしてしまう。
私は特別農業に興味があるわけではない。
しかしこれから田に植えられていくであろう苗達は、
ひとつひとつが恭平さんと冴さんの手によって育てられたのだ。
ここにも人の営みの息吹を感じる。
東京で、バイラル4スタジオで、魂を削ってバンドが己を研鑽し続ける日々の反対側で、
彼らは苗を育て、米を育てて生きている。
私は今とても当たり前の話をした。
しかし正直私はこれまで、その当たり前の日常を想像せずに生きてきた。
伊藤織江と知り合い、彼女のご両親を通して見た「当たり前の風景」に、
恥ずかしながら私は震えるほどの感動を覚えた。
そこへ、私達の側を通りかかった農作業の服を来た男性が立ち止まる。
こちらも恭平さん達と同じく60代ぐらいに見えた。
その男性は立ち止まってこちらへ歩みよって来ると、それに気づいた伊藤の顔を見るなり、
「おりんちゃんか?」
と言った。
伊藤はしばらくその男性をじっと見返し、やがて両手を口に当てて、
「イバラギさん!」
と言った。
少し離れた場所にいた恭平さんがこちらへ戻って来る。その横には冴さんもいて、二人は満面の笑みだ。
伊藤は紅潮した笑顔を私に向けると、現れた男性を紹介するような仕草で言った。
「親戚のおじちゃんなの。茨木さん」
「ご親戚の方ですか!初めまして、東京から来ました時枝と申します」
茨木という男性は、被っていた帽子を取ると恥ずかしそうに頭を下げて、
「茨木ですう」
と関西訛りの口調で挨拶してくださった。
何気にこちらへ来て初めての関西弁である。
「え、偶然?」
と伊藤が両親に尋ねる。
「そんなわけないでしょう、昨日電話で話したの。会いたいって言ってくださって、こんな朝早くから」
「えー。ありがとう」
伊藤はそう言うと茨木さんに抱き着いた。
茨木さんはシャイな人らしく、顔を真っ赤にして恭平さんに助けを求めた。
「おりんちゃんは変わらんなあ。すぐ分かったわ。いくつなったん?」
「あはは、もう40」
「嘘やろ!? おりんちゃんが40! 恭平、そら俺らもガタガタなるわけやで」
恭平さんと冴さんが声に出して笑う。
圧倒されていた私を見て、冴さんが話して下さった。
「茨木さんはね。うちの人のお父さんの、弟さんの息子さんなのよ。まだ子供の頃に家族でこっちへ引っ越して、この辺りで農業を営んでいてね。うちの人の弟と仲が良かったのもあって、一緒にこの道40年以上の大ベテランってわけ」
「そうなんですか。もとは東京の方なんですね」
「もとはね。でも子供の頃から京都だし、本人はもう完全に関西人よね。乃依の事はご存じ?」
「もちろん」
「茨木さんよく東京へ遊びに来て、織江や乃依と遊んでくれたのよ。あの通り、物凄く可愛がってくれてた。いかにも関西人らしく口は達者だけど、嫌味のない本当に優しい人よ。あの人がこっちにいるのが分かってたから、私達も安心して移り住めたのよね」
「織江さんの笑顔が物語ってますよね。…おりんちゃんですって」
冴さんと話をしていた私が笑うと、伊藤は照れ笑いを浮かべた顔で振り返り、
「何年振りだろうね、そう呼ばれたの」
と冴さんに尋ねる。
「さあね。あなた、たまあに帰っては来るけどすぐにとんぼ返りするでしょ。茨木さんも寂しがってたのよ。ねえ、茨木さん」
急に話を振られた茨木さんは赤い顔で大袈裟に頷いて見せた。
「せや。タイショウは元気にしてるか?」
「元気よ」
「リュウも、ショウちゃんもか」
「皆元気よ。茨木さんも、元気そうで良かった」
伊藤の声が涙で上ずり、茨木さんの目もキラキラと滲んでいるのが分かった。
子供の頃から姉妹を可愛がっているという事は、池脇達ドーンハンマーの面子を知っているという事なのだろう。
聞き慣れない彼らの愛称を知って、私まで胸が熱くなる思いだった。
「時枝さん」
恭平さんが私の名を呼ぶ。それだけで私は嬉しい。
「はい」
私と冴さんの側まで来ると、楽しそうに話し込んでいる伊藤と茨木さんを見つめながら恭平さんは言った。
「織江はしっかりしてる子だけどね。あんまり自分の事は喋る方じゃないから、私らもずっと心配だったんだ。東京でのあの子の様子を、聞かせてくれると嬉しいんだけどね」
「是非、私でよければ」
「ありがとう。じゃあ、行ってくる」
そう言うと恭平さんは冴さんに頷いて見せ、茨木さん達の方へ歩きだした。
「いってらっしゃい」
「いってらっしゃい」
冴さんと共にそう声を掛けて背中を見送る。
伊藤は父親の肩を揉んで声を掛け、茨木さんに会釈する。
「晩飯食おな」
茨木さんはそう言うと、頷く伊藤に向かって片手を挙げ、恭平さんと共に畔道を歩いて仕事に向かった。
「あははは!びっくりしたー!」
伊藤は明るく笑って、涙を拭いた。
寒さの残る野風に吹かれて、伊藤の長い髪が地面と平行になる高さまですくい上げられる。
今更ながら、彼女が冴さんの服を着ている事に気付いた。
白と青のボーダーニットと、ベージュのフレアロングスカートだ。
確かに普段伊藤が好んで来ている服装とは印象が大分違うのだが、
不思議と、伊藤織江という女性本来の姿がそこにあるようで、
とても清らかで美しい反面、胸の奥がぎゅっと締め付けられるのを感じた。
この地へ来て度々、私は伊藤の持つ爽やかな女性らしさにハッとしては、
一抹の不安と寂しさを感じていた。
手を掴んで今すぐ東京へ連れ帰りたくなるような、そんな焦りにも似た寂しさだった。
二日目の夜。
恭平さん、冴さんでの二人暮らしが長い為か、
キッチンのそばに置かれたダイニングテーブルは少し小さめで、
大人4人が座るとお互いの距離がとても近く感じられた。
どんな料亭にも負けない、心の籠った素晴らしく美味しい晩御飯を頂いた後、
温かい緑茶で心までホカホカになりながら、静かに語られる思い出話に私は聞き入る。
伊藤姉妹の幼い頃の話。
神波達と知り合ってからの話。
学生時代の話。
成人して社会に出てからの話。
仕事の話、そして神波との結婚。
笑いの絶えない幸せな記憶であったが、
やはりそれでも乃依さんの名前が出る度に優しい空気が生まれる事が、
新参者の私には辛く感じられた。
思い切って口を開く。
「私は音楽雑誌の編集者をしておりまして、東京では織江さんをはじめバンドの皆さんに大変お世話になっています。去年の今頃から取材を開始して丁度一年が経とうとしています。その中で強く感じているのが、バンドの持つ演奏技術の高さや音楽的な才能もさる事ながら、とても人間的な魅力に溢れている方達だという事です。私がこんな事を言うと笑われるかもしれませんが、織江さんが大成さんとご結婚された時、嬉しかったのではありませんか?」
私の投げかけた問いに、冴さんはパっと明るい笑顔になってこう言った。
「綺麗に喋るわね!」
私は反射的に両手で顔を覆った。
「すみません! 仕事みたいですよね!」
「いいのいいの。よく分からないけど今、久しぶりに東京の風を感じたわ」
「お恥ずかしい」
「職業病みたいなもんだよね。時枝さんて凄いのよ。相手の本音や深い部分にある気持ちを引っ張り出す事にかけては、私の知る中でピカイチだもの」
娘の言葉に冴さんは頷き、
「そのようねえ。…もちろん、嬉しかったですよ」
と言った。
私は顔を真っ赤にしてお茶を啜る。
「私らはね」
と言葉を繋いだのは、恭平さんだ。
「全く彼らをその、所謂バンドマンとして見たことはないんだよ」
「…そうなんですか」
彼は普段言葉を多く発するタイプではないそうだ。
今朝自分から私に話を聞きたいと申し出た責任を感じていたのだろうか。
家族が驚きの表情を浮かべる程饒舌に、素直な気持ちを聞かせて下さった。
「子供の頃から皆を知ってるからね。うちにも、何度も遊びに来てくれたよ。よく覚えているのがね、皆いつも正座なんだよ。こっちはもちろん足を崩しなさいって言うんだけど、照れ笑いを浮かべたまま決して崩さない。織江に聞いてびっくりしたんだが、茶の間だけじゃなくて、この子の部屋にいる間もずっとそうだったと言うんだ。なんだか、今時の子にしては感動するくらい真面目だなあと思ったのをたまに思い出すよ。中学卒業くらいまでは、よく東京の家で見かけたもんだけど、高校に上がるとめっきり顔を見なくなってね。母さんと、どうしたのかなあって話してた。思春期だし、友達の顔ぶれだってそりゃあ変わるもんだろうとあえて織江に聞いたりはしなかったけどね。それがある時、街でタイショウを見かけてね。懐かしくて声を掛けたんだ。拍子抜けするくらい変わってなかったよ。いや、変わっていたのかな。とても精悍な顔つきをしていてね。高校生なのに、もう大人の男の顔をしていたよ。元気にやってるのかって聞くと、『元気です。いつも織江さんにお世話になってます』って頭を下げて言うわけだよ。同級生なんだよ? 相変わらずだなと思ったのと、まだ付き合いは続いてたんだなって分ると嬉しくてね。またうちへ遊びに来なさいよって言うんだけど、ありがとうございますとは言いながら、その後もしばらくは、姿を見せる事はなかったな」
「確かに、若いのに気ばっかり使う子達だった。神波さんの所も、だいぶ苦労なさったからねえ」
冴さんのしんみりとした言いように、コラ、と恭平さんは静かに窘めた。
他所様の苦労を勝手に語るもんじゃない、と言う意思が感じられた。
「大丈夫よ。時枝さんはぜーんぶ知った上で、ここにいる人だから」
伊藤がそう言うと、冴さんは湧き上がる感情を堪えるような顔で頷き、湯呑みを両手で握った。恭平さんが続ける。
「織江達が成人して、ちょくちょく雑誌やテレビなんかで彼らを見かけるようになってからは、もちろん私らも喜んではいたんだが、どうもそういう芸能人感覚は、理解出来なくてね。真面目で、いつも真剣に何かを考えていて、考え過ぎて眉間に皺の寄るような、若いくせに年寄りみたいな、そんな織江の友達であり、ボーイフレンドであり。いつ会っても言葉遣いはみんな丁寧だし、思いやりのある言葉で私らに接してくれていた」
冴さんが嬉しそうに笑って、頷く。素敵な思い出が甦って来たのだろう。
恭平さんは続ける。
「だから当然二人が結婚すると知った時、物凄く嬉しかった。私は、乃依を亡くした時の彼らの悲しみようを思い出したよ。リュウの絶望的な涙、アキやショウちゃんの叫び声が昨日の事のように蘇ってきて。…タイショウと織江が幸せになってくれて本当に良かったと、親としてこんなに嬉しい事はないと思ったし、それは今でも思ってるんだ」
微笑みを浮かべて聞いていた冴さんはギュッと目を閉じたかと思うと、
立ち上がってキッチンのシンクに向かい、緑茶のお代わりを湯呑みに注ぎ始めた。
その背中はやがてブルブルと震え、しばらくは戻って来られないように見えた。
私は自分の太ももを右手で力一杯捻り上げ、堪えろ!堪えろ!と念じていた。
私が泣いて良い場面ではない、理解したつもりになって泣いて良い場面ではない。
そうに自分に言い聞かせた。
「二人でこの京都の家に挨拶に来てくれた時、いつにもましてタイショウは無口だったな。まだリフォーム前の傷みの多い家でね、タイショウが私らの前に正座した時、恥ずかしいぐらい床が軋んだんだ。それでもあいつは押し黙ったまま笑いもせず、何も言わない。私も母さんも二人が何をしにこんな所までやって来たのか知っていたから、敢えてこちらからは何も言わずにタイショウの言葉を待ったんだ。もの凄い顔をしていたよ。緊張とかそういう事ではなかったんだろうね。色々と彼なりに思う所があったんだと思う。待ってるこちらが苦しくなるほどの沈黙があって、正直私なんかは、もう良いよって、何度もそう言いかけたんだ。気持ちは痛いぐらい伝わったし、言葉なんて、そんなに大事じゃないって思ってるような古い人間だからね。だけど、いきなりだよ。タイショウが奥歯をぐっと噛み締めたまま泣き出したんだ。それで、ボロボロと涙を流しながら言うんだ。『本当は、精一杯格好付ける気でやって来て、この有様です。私にはどうしても、あなた達に向かって、お嬢さんを下さいとは言えません。私が、伊藤になります。よろしくお願いします』。そう言って頭を下げた。きっと乃依を失った私らの気持ちを考えての言葉なんだろうね。その時までそんな事は一切考えなかったんだが、タイショウがそう言った瞬間不覚にも、私も母さんも声を上げて泣いてしまったよ。なあ、母さん」
冴さんは鼻をすすると何とか小さく笑い声を上げて、再びテーブルに戻ってきた。
私は顔を上げる事が出来ない。
先ほどから伊藤が私の背中を優しく撫でている。
この世で一番暖かい手だと感じていた。
「まあ、なんて言ったらいいか分からないけどさ」
と、娘によく似た口調で冴さんは言う。
「子の幸せを願うのが親ってもんでしょう。だから同じように、目の前のタイショウが幸せである事も願っていたし、同じように喜んでもいた。だけどあの子が伊藤になるって言い出した時、心から嬉しかったと同時に、ダメだダメだ、こんなことでは女手一つで頑張って来られた神波さんに顔向けが出来ない!って思ったよ。それに、嬉しかったのはきっと、タイショウが伊藤になるっていう可能性なんかよりも、そう思ってくれていたあの子の気持ちだよね。あの子は本当に親思いだし、友達思いのいい子だから。乃依や、亡くなられたお父様や、大切なお母様の事を思いながら泣けて仕方なかったあの子が、それでも『伊藤になる』って言った事は、あーはいそうですかありがとうとは、受け入れられないよね。こんなに優しい子が織江と一緒になってくれるんだっていう、そういう嬉しさで、胸が締め付けられる思いだった」
「ああ。その事があってから余計に、織江の事よりもタイショウやリュウが本当に幸せかどうかを考えるようになった。それに、まあリュウも酷かったが、…ショウちゃんがね。乃依の死を前に混乱してしまって、言葉にならない叫び声を上げていたのを私らは見てるからね。この子達はこの先どうやって生きていくんだろうって心配になるぐらい、嘆き、悲しんでくれた。私らにとっても、あの子達は本当に特別だから。…東京で織江はちゃんと、彼らの為にやっているか、タイショウは幸せか。皆頑張ってるか。こっちへ来て辛いのは、そういった事がすぐに分からない事なんだよ」
「織江はめったに帰ってこないし、電話もすぐに切ろうとするしね。忙しいのは分かるけど、もう少しちゃんと色々聞きたいものよね、親としては」
拗ねたように言う冴さんの言葉に恭平さんは苦笑いしながらも、頷いた。
伊藤はハンカチで涙を抑えながら笑い、
「こっちはこっちで、色々あるのよ」
と言った。
「色々ねえ。あ、誠や繭子は、いくつになったの?」
「誠は今31、繭子は29になった」
「あはは、あの子一体、いつまで20代でいる気なの!?」
冴さんの言葉に俯いていた私まで吹き出して笑った。
「長いよねえ。知り合った時はあの子達二人とも10代だもん。繭子なんて12月に29になったばかりだよ」
「二人とも元気なの?」
「なんとかね。頑張ってるよ、二人とも」
「そう」
私は自分の出番が回って来たのだと悟り、涙に濡れた顔を挙げた。
ノーメイクが幸いしたが、それでも恥ずかしい程泣いた事に変わりはない。
無かった事には出来ないと知りながら、私は努めて明るく話し始めた。
恭平さんや冴さんの期待した通りの報告が出来たかは分からない。
しかし私なりにこの一年で感じた伊藤織江という女性の勤勉さ、優しさ、温かさ、そして強さを、時に涙で声を詰まらせながら話した。
今度は伊藤が黙って立ち上がり、キッチンで湯飲みを洗い始めた。
恭平さんはそんな娘を窘めようとしたが、彼女の横顔を見て声を掛けるのをやめたようだ。
私に向かって、すまないね、とでも言いたげな苦笑いを浮かべて頷いて下さった。
三日目。
朝、お手洗いを借りて2階の部屋へあがろうと階段に足を掛けた時、
一番上の段差に腰を下ろして壁にもたれている伊藤と目が合った。
「どうされました?」
と私が声を掛けると、彼女は目をパチクリさせて、
「え?」
と言った。
「はい?」
と私が聞くと、伊藤は右耳からイヤホンを抜いた。
「ごめん、何か言った?」
「こちらこそ。何を聞いていらっしゃるんですか?」
「ネムレ」
「ん?」
「『NAMELESS RED』」
「あはは。ようやく、発売日が迫りましたね」
「二転三転したもんね。ぎりぎりになって、収録曲変えたいって言いだした時はスケジュール組む私の身になれ!って思ったけどね」
「あははは。でも、仰りはしなかったんでしょうね」
「言えないよね。遊んでるわけじゃないし」
「確かに」
私が階段の上まで辿り着くと、伊藤は立ち上がって二人で部屋に戻る。
カメラの電源を入れた。
それには伊藤も気付いている。
あまり映り込むような物がないとは言え、実家の部屋だ。
プライバシーを考慮して、伊藤が部屋の中央に座ると彼女の横顔がアップになるよう調整した。
午前中の明るい時間帯は部屋の電気を消しているため、モニターの中の伊藤は少し薄暗く映り、
却って芸術的な程白く美しい横顔のラインが浮かび上る。
「昨日、長話に付き合ってくれてありがとね」
と、伊藤は言った。
「いえいえ」
「それから、ごめんね」
「ええ? 相変わらず泣いてばかりで申し訳なかったのはこちらのほうですよ」
「ううん、そんなのは平気」
「では」
「一年前にさ、詩音社の取材を受ける事にしたのは、あなたを利用する算段もあったんだって私が言った事、覚えてる?」
「はい」
「ふふ。今回もそうよ。どうせ実家に戻ったら、お母さんからあれこれ聞かれるに決まってるだろうなあ。お父さんは聞きたいけど聞きづらそうな顔をするんだろうなあ、とか。日本を出ちゃうからさ、顔見せに来ないわけにはいかないし、もちろん私もちゃんと顔を見ておきたいっていう気持ちもあったけど、どうも私は自分の話をするのが下手なのよね。苦手なのもあるし。本当は大成も来たがったんだけど、もうちょっとギリギリにしようよって私から説得したの。久しぶりに二人で来たらきっと質問攻めにあって、あの人疲れちゃうからね。だからさ、時枝さんがついて行きたいって言った時、じゃあ私達の代わりに全部喋ってもーらおっとって。あはは、いい加減腹立つでしょ、私」
「全然立たないです」
「あなたも大概だねえ、人が良すぎるって言われない?」
伊藤は呆れたように眉根を下げて笑った。そして、
「何を言っていいか分からないのよ、ほんと言うと」
と彼女は続ける。
「聞かれた事だけ答えていれば良い気もするんだけど、それだけじゃダメな気もする。だけど私は自分から語れるような何かを持っているわけじゃないし、困るんだよね。だから昨日は本気で助かった」
「あんなの、あと10倍は喋れますよ、私」
「あはは」
「織江さんを心から尊敬しています」
「ありがとう。でも、時枝さんだから分かってもらえると思うんだけどね、例えばバンドと自分を考えた時に、虚しくなる瞬間は確かにあるのよ」
伊藤は両膝を抱えて顎を乗せ、彼女と時枝の丁度真ん中あたりを見つめながら話し始めた。
「『NAMERESS RED』の一曲目、『SUPERYEAH』を初めて聞いた時にもそれを痛感した。あの人達は他人に語って聞かせる夢もなく、したり顔で熱い言葉を話す事もせず、好きなように歌って叫んで、それでも、これでもかというくらいに私の胸を打つ。何だ、こんな事が出来ちゃう人達なら、私必要ないんじゃないのって思うの。忙しくて目が回りそうな時なんてよくそんな事考えるよ。私ホントに必要かなあって。年末にさ、翔太郎と『合図』で話した時なんて分かりやすいと思うけど、とにかく皆優しいから気を使って私を立てようとしてくれるんだけど、これって私が幼馴染じゃなくても、同じように思ってくれるのかな、とかさ。いつもじゃないよ。そういう風に思っちゃう時もある、って。そういう話」
「分かりますよ。とてもよく分かります。そういう意味ではきっと私の方が、強く抱いている感情だと思います。皆さんの側で皆さんのお話を聞いて、皆さんの努力を見て皆さんの本気を感じて。そうやって私の記事は出来上がります。だけどその記事にあるのは私自身ではなくて、皆さんのありのままの姿です。もちろん記事を書き上げた瞬間の達成感はあります。だけど私は他人の人生、他人の夢に乗っかっているだけなんじゃないかって、辛くなる事もあります」
「似たもの同志だね」
「違いますよ。織江さんは違います」
「どうして?」
「私は自分の意志で、自分がどうしても読みたくて、書籍化の企画を通す前に皆さんの伝記を書き始めました。そうでもしないと、私は自分を見失いそうになっていたからです。私は今でも『Billion』のファンですし、素敵な記事を一杯読んできましたから、大好きです。だけどいざ自分がバンドの側に立って取材を進めるうちに思ったのが、私は理想の雑誌編集者になりたいわけじゃないんだって事です。…織江さんは、これまで物凄く苦労と努力を積み重ねて来られた方です。その原動力はどこにありますか?」
「苦労と努力…。んー、どこって言われるとな」
「分からない?」
「何が苦労で、何が努力だったのか、覚えてない」
「織江さんらしいですね」
「なんで? 私のどこに苦労の痕を感じ取ってるのか分からないけど、そりゃあもちろん疲労はあるよ。でも苦労ってなんだろうなって思うと、『だって勝手に好きでやって来たじゃない』って自分で突っ込み入れちゃうもんね。例えば英語の勉強だって、会社経営の勉強だって、それは夢とか目標じゃなくて今やりたい事をやっただけだもん。必要だと思う事をやっただけで、どこかへ至るための偉大な一歩だとか、大きな目標を掲げた事が今まで一度もないんだよ」
「だからですよ」
「ん?」
「だから、私と織江さんは違うんです。織江さんは、私からすれば紛れもなく『ドーンハンマー側』の人です。ただ、やりたい事をやって来ただけ。そして今があるんです。その結果、織江さんは社長であり、大成さんの奥様なんです。竜二さんや大成さん、翔太郎さんや繭子と何も変わらない。彼らに必要とされているかを外から見て考える必要などなく、彼らの中にあなたはいます。織江さんはドーンハンマーです」
伊藤は膝の上から顔を上げると、数秒空中を見つめた。
やがて私の目をしっかりと見つめて、頷いた。
「ありがとう」
私がペコリと頭を下げて応えると、伊藤はニッコリと微笑んでこう言った。
「じゃあお礼に、良いもの見せてあげようか」
言葉の意味は分からなかったが、私はこの時既視感のようなものを感じていた。
それはどこかで見たというよりどこかで感じた事のある気持ち、と言い換えるべきものだった。実態はつかめないし、それが何なのか考えるより先に伊藤が立ち上がり、私を部屋の外へ連れ出した。
だがその『良いもの』は、隣の部屋の事だった。
扉の前に立って、伊藤はトントンとノックする。
返事はない。
「どなたの部屋ですか?」
「ノイ」
私は驚いて、扉を見つめる。
伊藤は扉の前に立ったまま、少し話をした。
「うちの親がこの家に越してきてリフォームをした時に、お母さんがこの部屋をノイの部屋にするって言いだしたの。もともと誰も使ってない部屋なんだけど、小さな部屋二つの壁を壊して8畳程の一つの部屋にしたの」
「へえ」
「もちろん、この部屋を作った時には、もうノイはいないんだけどね。なんだかとてもうちの親らしいなと思って」
「素敵だと思います、私も」
「入るね」
部屋の中に向かってそう言うと、伊藤は扉を開けた。
私は少しびっくりして半歩後退りした。
部屋の真ん中に誰かがいるような気がしたのだ。
「びっくりするよね。まあ狙ってやってるんだけど」
部屋の真ん中には、黒いベースが立てかけてあった。
「あれは」
「入って。そう、うちのタイショウのベース」
伊藤の口から聞くタイショウという呼び名がとても可愛らしくて、思わず胸がきゅんとする。
「なんか守り神みたいでしょ、真ん中にどーんと鎮座しちゃってさ」
「確かに、そう見えますね」
「これは大成が自分で置いてったの。このベース、本当は今竜二の物なんだけどね。下手くそだったけどノイはギターが好きだったから、じゃあ俺はその横でベース弾いてやるって、竜二が大成に習い始めてさ。そしたら大成が大事にしてた自分のやつを、このベースを竜二にあげたんだ。なんかそういうの嬉しいよね。はっきり言うとここにあっても邪魔なんだけど、自分がこの家にいない間は、代わりにこいつを置いておこうって大成が提案して、竜二がわざわざ東京から持って来てくれたの。だから絶対にどけたくないんだ。可笑しいのはね、この裏側見て、ここ、ここほら、全員のサインが入ってるの。アキラのもあるし、カオリのも、誠と繭子、マーとナベのもある」
「ああ、本当ですね。これは世界一レアで思いの籠ったベースですね!」
伊藤はスカートのポケットに手を入れると、白いサインペンを取り出した。
「はい。時枝さんも書いて」
「え、無理ですよ」
「嫌なんだ?」
「嫌なわけないですよ」
「じゃあ、書いて」
私はなるべく他の皆さんの邪魔にならない場所を選び、出来るだけ目立たないように自分の名前を書いた。申し訳ない気持ちを抱えたまま伊藤にサインペンを返すと、思いがけず近くに彼女の顔があって照れた。
伊藤は肩で私の体を押して、「ありがと」と言った。
こちらこそと私が言おうとする前に彼女は立ち上がり、
「お腹すいたな。畑になんか獲りに行こうか」
と言って部屋を出ていった。
私はベースに向かって深く頭を下げると、伊藤の後を追って部屋を出た。
キッチンで立ち仕事をしていた冴さんにも声を掛けて田へ向かう。
畦道を歩きながら、前を行く冴さんに聞いてみる。
「どうして翔太郎さんだけショウちゃんって、ちゃん付けなんですか?」
すると冴さんはピタリと立ち止まって、キョロキョロと周囲を確認する。
やがて私の方に近づいてくると、小声でこういった。
「お気に入りだから。これ内緒ね」
私はこの地へ来て一番の大声で笑った。冴さんは少しだけ困った顔をして、
「でもね、タイショウがやっぱり特別だからね。だから『アンタがタイショウ』のタイショウ。ここ大事よ」
「違うでしょ! タイセイだからタイショウなんでしょ。適当な事言わないの。時枝さんピュアだからそのまま記事に書いちゃうよ」
「あらま」
私はお腹を押さえて大笑いした。
遠く離れた地で聞く彼らの名前はとても新鮮に胸に響く。
しかし印象は少しも変わらない。
いつだってどこだって彼らは素敵だ。それが今、とても嬉しい。
畑で獲れた旬の野菜で贅沢な昼食をいただくと、
その日は伊藤と二人で何もせず、大の字に寝転がってだらだらと一日を過ごした。
不意に、仰向けになって天井を見上げたまま、伊藤が言った。
「今急に思い出した。カオリの話していい?」
「もちろん」
「前にさ、誰のインタビュー撮ってる時だか忘れちゃったけど、時枝さんが言ったの。『何でUP-BEAT?意外です』って、そんなような事を」
「あー、えーっと。繭子が翔太郎さんの歌を褒めた時ですね」
「ああ、そうだね。繭子はその時、そうかなーなんて曖昧な返事してたと思うけど。あれね、本当はちょっと素敵な裏話があって」
「へえ、どのような」
「知り合ってどのぐらいの頃だっかたまでは覚えてないけど、カオリにね、『お前らは普段どんな音楽聞いてるんだ?』って聞かれてさ」
「それは、織江さんがですか?」
「そうそう、私とノイね」
「ああ、はい」
「私音楽の話はそんなに得意じゃないしさ、カオリを前にしてウソでもパンクロックが好きだなんて言えないよなって観念して、UP-BEATって答えて」
「あ、え!? 織江さんが好きなんですか!」
「うん。もう子供の頃からずっとファンでさ。私東京の自分の部屋にポスター貼ってたもん。色褪せても破れちゃっても補強して、ずーっと」
「へえー。でも、織江さんならば、うん、意外ではないですね」
「あはは。ギターの岩永さんが好きでね。お母さんに言われたもん。あんたこんな男前に惚れこんじゃうと、現実と向き合えなくなるよって」
「あははは!」
「でもびっくりしたのがさ、大成と初めて会った日に『いた!岩永さんより男前いた!』ってお母さんに報告したんだって。そこは私覚えてないんだけど」
思わずエビのように丸くなってお腹を抱える。
「まあ、そこは別に良いんだけどさ。でね、カオリに白状した時、ちょっとドキドキしたの。どちらかというと王子様的な、そういう格好良さのあるバンドだったし、硬派なイメージではなかったからね。だけどカオリはニッコリ笑って、『いいね、アタシも好きだよ』って言ったの。嬉しかったし、ますますカオリが好きになったのを覚えてる。口は悪いしぶっきら棒だけど、心底優しい人だから、例え私がどんな音楽を好きだと言った所で、カオリはニッコリ笑ってくれただろうなって、そう思って」
「素敵な話ですね」
「まだ序の口」
「あはは」
「ノイが亡くなった時ね」
「…」
「皆酷かったんだ。私も含めてね。辛くて辛くて、泣いて、叫んで、暴れて、…泣いて。お葬式の時も、お父さんも言ってたけどさ、皆もう、壊れたような感じになってた。だけど唯一、カオリだけは涙を見せなかったんだ。後になってね、彼女が言うわけ。『誰か一人くらいは、しっかり立って見送ってやんないと、あの子も心配だろうと思ってさあ。…スゲー泣きたかったけど、お前ら皆バカだから』って。ありがとうって、私何度も頭を下げてお礼を言って。そしたらカオリが笑って、…あ、昔のスタジオでの話なんだけどね。カオリが笑って、アコースティックギターを抱えて、UP-BEATの夏の雨っていう曲を歌ってくれたの。私、カオリがUP-BEATを好きだって言ったのはどこかでウソなんだろうなって思ってたから、びっくりして。広石(ボーカル)さんの歌声ってハスキーでセクシーな低音が魅力なんだけど、その時歌ったカオリの力強い声は、もう、なんか、叫び声だったよ。ワンコーラス歌って、サビを歌い始めた瞬間、カオリが泣き始めて。曲自体は前向きな失恋ソングだと思うんだけどね。『サヨナラ、スイートレイディー』っていう歌詞があって。歌い始めた瞬間カオリの目から大粒の涙が溢れた。ずっと、ノイの為に我慢してくれてた涙が溢れたんだと思って、私達も大泣きして。…それまでUP-BEATなんて聞いてこなかった大成達も聞くようになって、今じゃカラオケ好きな繭子まで歌い出す始末だよ」
この時私達は寝転がって天井を見つめているので、
伊藤がどのような表情を浮かべていたのか私には分からない。
長い沈黙の後、今頃きっと、皆鬼みたいな形相で練習してるな。
とポツリと伊藤がつぶやいた。
ふり絞った声で、「そうですね」と私が言うと、彼女は呑気な声で天井に向かい、
「がんばれー」
と言った。
続く。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

My Angel -マイ・エンジェル-
甲斐てつろう
青春
逃げて、向き合って、そして始まる。
いくら頑張っても認めてもらえず全てを投げ出して現実逃避の旅に出る事を選んだ丈二。
道中で同じく現実に嫌気がさした麗奈と共に行く事になるが彼女は親に無断で家出をした未成年だった。
世間では誘拐事件と言われてしまい現実逃避の旅は過酷となって行く。
旅の果てに彼らの導く答えとは。


寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が



あの日、さようならと言って微笑んだ彼女を僕は一生忘れることはないだろう
まるまる⭐️
恋愛
僕に向かって微笑みながら「さようなら」と告げた彼女は、そのままゆっくりと自身の体重を後ろへと移動し、バルコニーから落ちていった‥
*****
僕と彼女は幼い頃からの婚約者だった。
僕は彼女がずっと、僕を支えるために努力してくれていたのを知っていたのに‥
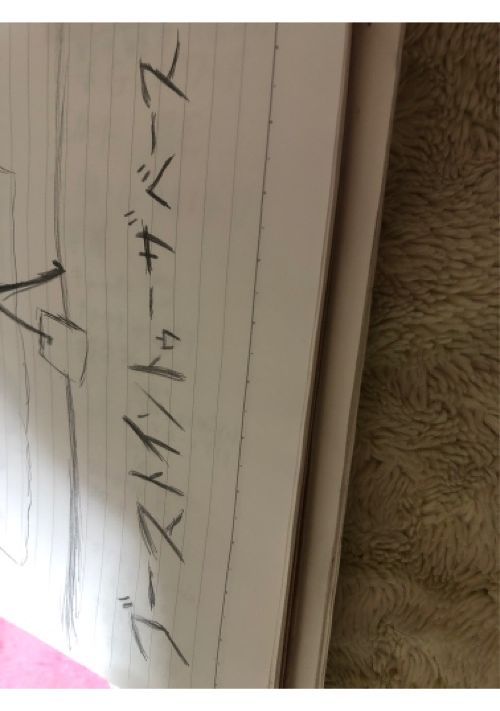
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















