11 / 71
第二章 偽りの公爵令嬢
第十一話 冷製スープ
しおりを挟む
その夜のシフトをこなす間、セナは幾度か、バーで王子を見かけてしまい、幾度か視線を逸らしてしまった。
相手に不快感を与えないように、それとなく気遣いながら。
王族関係者がこの最上階にあるバーを利用するのは、よくあることだ。
このリゾート地は帝国との国境線に近い場所にある。
帝国と王国との間を往復する際に帝都とはほぼ真反対の場所にある王都は、このホテルから数百キロは離れていて、中間地点にあるこのホテルで、旅の宿を取るのがほぼいつも通りのコースだった。
王太子ロバートは二十歳になると聞く。
自分よりも二歳しか違わないのに、彼は次期国王として権力の中枢まであと一歩といったところにいた。
対して自分はその真っ只中から、叩き出されたのだ。
十四歳という世間など右も左も分からない状況で。
そう考えると、彼の恵まれた人生のすべてが、羨ましくも憎らしいもののように思えてならなかった。
……いけない、いけない。醜い嫉妬なんて感じてる場合じゃない。今は仕事に集中しなきゃ。
セナはそう考え直し、キッチンで作るように言われたデザートの下ごしらえに入った。
今日、出すのはミントのゼラチンを使った、桃の冷製スープだ。
「桃は少々、形を崩してもかまわない。きちんと裏漉しをしてくれ。丁寧にな」
「はい、かしこまりました」
バーには厨房があるが、レストランのように料理長がいるわけではない。
二人の料理人が交互にシフトに入り、その日、客に出す日替わりのデザートはウェイトレスたちが、開店前に厨房に入り、手助けをすることになっていた。
昔は帝国の一流ホテルで働いていたという料理人は、鮮度のいいよく冷えた桃を十数個取り出すと、セナに、ミントやヨーグルトなど、他の具材の場所を教えていく。
「このスープを作った経験は?」
「先週から、何度か、やらせて頂いてます」
「よし。それなら任せたぞ。失敗はするなよ」
「はい」
料理人は配膳係やリネン部よりも厳しい。
その瞬間、その瞬間の火加減や仕込みのやり方が、如実に味に表れるからだ。
その意味ではリネン部の課長バルド。
あの嫌味な暴力男より、セナには恐ろしい相手だった。さすがに手を挙げられたりはしないが……。
「桃に、ミント。蜂蜜、ヨーグルト……漉すためのこし器に牛乳。あとはゼラチン、か」
冷蔵魔導具や棚から必要だと言われたものをメモした用紙が最初は必要だったが、いまではそうでもない。
桃の皮をむくペティナイフで手を切らないように用心しながら、まずは桃の皮をむいていく。
なかにある種を包丁の先で綺麗にとりのぞく。
十数個もあるとそれなりに時間がかかる。
ようやくペティナイフを置いたとき、ロバートの姿はキッチンから目に入る場所にはいなくなっていた。
これで余計な気を遣う相手が減った、とセナは胸をなでおろす。
ミアから話を持ちかけられて以来、殿下の花嫁探しのために開かれる舞踏会に参加していいものか、と生来の心配性が心に出てきた。
もし、話しかけられたりしたら……などと、乙女の妄想に浸っていたわけではなく。
現実的に職を失う危険性がつきまとうのが、どうしても怖かったのだ。
「ミント、ミント……葉だけを除いて」
香りの強いペパーミントの葉を茎だけちぎって容器に入れ、そこにお湯を注いで蓋をする。
香りを十分に引き出すためだ。
しばらくしてお湯が透明なグリーンになったら、蓋を除けこし器で余計な繊維などを取り除く。
まだ温かいうちに逃がさないようにしたら、ゼラチンを加え、また蓋をして氷魔法のかかった冷蔵魔導具のなかで冷やしてやる。
程よく冷えて固まったら、ミントゼリーは完成だ。
同時に桃のほうも作業をすすめていく。
手早く済ませれば、三十分もかからない作業だ。
さっさと済ませないと、ホールの接客がおろそかになる。
切った桃をすべて魔導ミキサーに入れ、牛乳と少量の塩、ヨーグルト、蜂蜜を加えてペースト状になったものを、こし器で漉してやる。
筋などが取れたものにまた牛乳を注ぎ、トマトジュースくらいの濃度に整えてやる。
滑らかなスープが完成したら、ゼリーと同じように魔導冷蔵庫で冷やしてやり、ガラスの筒のようになった深皿に、氷とミントを散らした上から、桃のスープを淵から零れない程度に注ぐ。
その上にミントゼリーを小さじ二杯ほど入れていき、上からミントの葉を飾れば、これで桃の冷製スープの完成だ。
この料理はパスタや魚料理などで油っぽさを覚えた舌を、すっきりと爽快にさせてくれるだろう。
容器の上から、同じくガラスの蓋を閉めると、セナはそれをトレイに並べて、魔導冷蔵庫のなかに四段、並べた。
一段が三十個で、百二十は出ることになる。
これは今週の定番デザートになっているから、数日は日持ちがすることを見越して、多めに作ったのだ。
とはいえ、桃のいろはすぐに悪くなるから、明後日の朝には廃棄されるのだが。
「デザート、できたわ。冷蔵庫のなかに入れて冷やしています」
「おう。お疲れさん。……どうした、嫌に機嫌がいいな?」
「え? そう見えますか?」
「豪勢にチップでも貰ったか?」
「いえ、そういうのではないですが」
時刻は十九時過ぎ。
しかし、バーはまだまだ開店したばかりで、深夜二時までは忙しい。
セナは深夜を回るまでここにいる予定だった。
「ちっ」
「どうかした?」
「嫌な奴が来てやがる……」
と料理人が漏らす方角にあるテーブルを見ると、そこにはリネン部の部長と課長……あのバルドが、もう一人の女性を囲み三人でお酒を飲んでいる姿だった。
セナはその最後の一人の後ろ姿に見覚えがある。
「カティ」
「知り合いか」
「同僚です。リネン部の。いま怪我をして休んでいるはずなのに……」
「あの事故のか?」
「……」
静かに肯くと、壮年の料理人はふん、と面白なさそうに鼻を鳴らした。
どこでもある光景だ、とぼやくように言い、三人がこちらに気づく前に、セナの手を取って厨房へと入らせる。
「あのまだなにか? デザートの用意は終わりましたけど」
「今夜はここから出なくていい」
「ええ?」
どういうこと? とセナは訝しんだ。
厨房で彼の手伝いをしろということだろうか。
もしそうだとしたらせめて服を着替えてきたい。
接客用のこの服では、油汚れがひどくなった時に、お客様の前に顔を出すことができない。
ピーク時に、周りに迷惑をかける恐れがあった。
それを伝えると、ロアッソとかかれた名札を胸につけた彼は、ほらよ、とエプロンを渡してくれる。
「二日前に酷い目にあったっていうのは噂になってる。ボケ野郎、バルドが部下の女を蹴りまくってたってな」
「……」
「誰もお前がそうだとは言ってない。お前がミスをしたとも思ってない」
「はい……」
「だがこの厨房は俺の城だ。このバーを取り仕切るのは俺に任されてる。そういうふうにオーナーと契約した。帝国の皇弟殿下とな。意味がわかるか?」
「いえ、さっぱり」
困り果てて顔を左右に振る。
ロアッソは男らしく勇ましい笑顔でそれに応えた。
「ここにいる限りは、俺の部下だ。女は殴るやつは最低だし、酒が入ったら場所を選ばない。お前に危険が及ぶ可能性もある。だから今夜はここから出るな。辛いだろうが洗い物でもして時間を過ごしてくれ。いいか?」
「はい……ありがとうございます」
「適材適所ってやつだ。お前はウェイトレスとして注文を取るのにも、料理を運ぶのにも、テーブルのサービスを行うにも有能な奴だ。そういった奴は厨房でも十分使える。だから今夜はここでいい」
料理人の温情に、思わず涙がこぼれそうになる。
今日は、いろんな人からの温情が厚い夜だった。
相手に不快感を与えないように、それとなく気遣いながら。
王族関係者がこの最上階にあるバーを利用するのは、よくあることだ。
このリゾート地は帝国との国境線に近い場所にある。
帝国と王国との間を往復する際に帝都とはほぼ真反対の場所にある王都は、このホテルから数百キロは離れていて、中間地点にあるこのホテルで、旅の宿を取るのがほぼいつも通りのコースだった。
王太子ロバートは二十歳になると聞く。
自分よりも二歳しか違わないのに、彼は次期国王として権力の中枢まであと一歩といったところにいた。
対して自分はその真っ只中から、叩き出されたのだ。
十四歳という世間など右も左も分からない状況で。
そう考えると、彼の恵まれた人生のすべてが、羨ましくも憎らしいもののように思えてならなかった。
……いけない、いけない。醜い嫉妬なんて感じてる場合じゃない。今は仕事に集中しなきゃ。
セナはそう考え直し、キッチンで作るように言われたデザートの下ごしらえに入った。
今日、出すのはミントのゼラチンを使った、桃の冷製スープだ。
「桃は少々、形を崩してもかまわない。きちんと裏漉しをしてくれ。丁寧にな」
「はい、かしこまりました」
バーには厨房があるが、レストランのように料理長がいるわけではない。
二人の料理人が交互にシフトに入り、その日、客に出す日替わりのデザートはウェイトレスたちが、開店前に厨房に入り、手助けをすることになっていた。
昔は帝国の一流ホテルで働いていたという料理人は、鮮度のいいよく冷えた桃を十数個取り出すと、セナに、ミントやヨーグルトなど、他の具材の場所を教えていく。
「このスープを作った経験は?」
「先週から、何度か、やらせて頂いてます」
「よし。それなら任せたぞ。失敗はするなよ」
「はい」
料理人は配膳係やリネン部よりも厳しい。
その瞬間、その瞬間の火加減や仕込みのやり方が、如実に味に表れるからだ。
その意味ではリネン部の課長バルド。
あの嫌味な暴力男より、セナには恐ろしい相手だった。さすがに手を挙げられたりはしないが……。
「桃に、ミント。蜂蜜、ヨーグルト……漉すためのこし器に牛乳。あとはゼラチン、か」
冷蔵魔導具や棚から必要だと言われたものをメモした用紙が最初は必要だったが、いまではそうでもない。
桃の皮をむくペティナイフで手を切らないように用心しながら、まずは桃の皮をむいていく。
なかにある種を包丁の先で綺麗にとりのぞく。
十数個もあるとそれなりに時間がかかる。
ようやくペティナイフを置いたとき、ロバートの姿はキッチンから目に入る場所にはいなくなっていた。
これで余計な気を遣う相手が減った、とセナは胸をなでおろす。
ミアから話を持ちかけられて以来、殿下の花嫁探しのために開かれる舞踏会に参加していいものか、と生来の心配性が心に出てきた。
もし、話しかけられたりしたら……などと、乙女の妄想に浸っていたわけではなく。
現実的に職を失う危険性がつきまとうのが、どうしても怖かったのだ。
「ミント、ミント……葉だけを除いて」
香りの強いペパーミントの葉を茎だけちぎって容器に入れ、そこにお湯を注いで蓋をする。
香りを十分に引き出すためだ。
しばらくしてお湯が透明なグリーンになったら、蓋を除けこし器で余計な繊維などを取り除く。
まだ温かいうちに逃がさないようにしたら、ゼラチンを加え、また蓋をして氷魔法のかかった冷蔵魔導具のなかで冷やしてやる。
程よく冷えて固まったら、ミントゼリーは完成だ。
同時に桃のほうも作業をすすめていく。
手早く済ませれば、三十分もかからない作業だ。
さっさと済ませないと、ホールの接客がおろそかになる。
切った桃をすべて魔導ミキサーに入れ、牛乳と少量の塩、ヨーグルト、蜂蜜を加えてペースト状になったものを、こし器で漉してやる。
筋などが取れたものにまた牛乳を注ぎ、トマトジュースくらいの濃度に整えてやる。
滑らかなスープが完成したら、ゼリーと同じように魔導冷蔵庫で冷やしてやり、ガラスの筒のようになった深皿に、氷とミントを散らした上から、桃のスープを淵から零れない程度に注ぐ。
その上にミントゼリーを小さじ二杯ほど入れていき、上からミントの葉を飾れば、これで桃の冷製スープの完成だ。
この料理はパスタや魚料理などで油っぽさを覚えた舌を、すっきりと爽快にさせてくれるだろう。
容器の上から、同じくガラスの蓋を閉めると、セナはそれをトレイに並べて、魔導冷蔵庫のなかに四段、並べた。
一段が三十個で、百二十は出ることになる。
これは今週の定番デザートになっているから、数日は日持ちがすることを見越して、多めに作ったのだ。
とはいえ、桃のいろはすぐに悪くなるから、明後日の朝には廃棄されるのだが。
「デザート、できたわ。冷蔵庫のなかに入れて冷やしています」
「おう。お疲れさん。……どうした、嫌に機嫌がいいな?」
「え? そう見えますか?」
「豪勢にチップでも貰ったか?」
「いえ、そういうのではないですが」
時刻は十九時過ぎ。
しかし、バーはまだまだ開店したばかりで、深夜二時までは忙しい。
セナは深夜を回るまでここにいる予定だった。
「ちっ」
「どうかした?」
「嫌な奴が来てやがる……」
と料理人が漏らす方角にあるテーブルを見ると、そこにはリネン部の部長と課長……あのバルドが、もう一人の女性を囲み三人でお酒を飲んでいる姿だった。
セナはその最後の一人の後ろ姿に見覚えがある。
「カティ」
「知り合いか」
「同僚です。リネン部の。いま怪我をして休んでいるはずなのに……」
「あの事故のか?」
「……」
静かに肯くと、壮年の料理人はふん、と面白なさそうに鼻を鳴らした。
どこでもある光景だ、とぼやくように言い、三人がこちらに気づく前に、セナの手を取って厨房へと入らせる。
「あのまだなにか? デザートの用意は終わりましたけど」
「今夜はここから出なくていい」
「ええ?」
どういうこと? とセナは訝しんだ。
厨房で彼の手伝いをしろということだろうか。
もしそうだとしたらせめて服を着替えてきたい。
接客用のこの服では、油汚れがひどくなった時に、お客様の前に顔を出すことができない。
ピーク時に、周りに迷惑をかける恐れがあった。
それを伝えると、ロアッソとかかれた名札を胸につけた彼は、ほらよ、とエプロンを渡してくれる。
「二日前に酷い目にあったっていうのは噂になってる。ボケ野郎、バルドが部下の女を蹴りまくってたってな」
「……」
「誰もお前がそうだとは言ってない。お前がミスをしたとも思ってない」
「はい……」
「だがこの厨房は俺の城だ。このバーを取り仕切るのは俺に任されてる。そういうふうにオーナーと契約した。帝国の皇弟殿下とな。意味がわかるか?」
「いえ、さっぱり」
困り果てて顔を左右に振る。
ロアッソは男らしく勇ましい笑顔でそれに応えた。
「ここにいる限りは、俺の部下だ。女は殴るやつは最低だし、酒が入ったら場所を選ばない。お前に危険が及ぶ可能性もある。だから今夜はここから出るな。辛いだろうが洗い物でもして時間を過ごしてくれ。いいか?」
「はい……ありがとうございます」
「適材適所ってやつだ。お前はウェイトレスとして注文を取るのにも、料理を運ぶのにも、テーブルのサービスを行うにも有能な奴だ。そういった奴は厨房でも十分使える。だから今夜はここでいい」
料理人の温情に、思わず涙がこぼれそうになる。
今日は、いろんな人からの温情が厚い夜だった。
45
お気に入りに追加
2,408
あなたにおすすめの小説

敗戦して嫁ぎましたが、存在を忘れ去られてしまったので自給自足で頑張ります!
桗梛葉 (たなは)
恋愛
タイトルを変更しました。
※※※※※※※※※※※※※
魔族 vs 人間。
冷戦を経ながらくすぶり続けた長い戦いは、人間側の敗戦に近い状況で、ついに終止符が打たれた。
名ばかりの王族リュシェラは、和平の証として、魔王イヴァシグスに第7王妃として嫁ぐ事になる。だけど、嫁いだ夫には魔人の妻との間に、すでに皇子も皇女も何人も居るのだ。
人間のリュシェラが、ここで王妃として求められる事は何もない。和平とは名ばかりの、敗戦国の隷妃として、リュシェラはただ静かに命が潰えていくのを待つばかり……なんて、殊勝な性格でもなく、与えられた宮でのんびり自給自足の生活を楽しんでいく。
そんなリュシェラには、実は誰にも言えない秘密があった。
※※※※※※※※※※※※※
短編は難しいな…と痛感したので、慣れた文字数、文体で書いてみました。
お付き合い頂けたら嬉しいです!

1度だけだ。これ以上、閨をともにするつもりは無いと旦那さまに告げられました。
尾道小町
恋愛
登場人物紹介
ヴィヴィアン・ジュード伯爵令嬢
17歳、長女で爵位はシェーンより低が、ジュード伯爵家には莫大な資産があった。
ドン・ジュード伯爵令息15歳姉であるヴィヴィアンが大好きだ。
シェーン・ロングベルク公爵 25歳
結婚しろと回りは五月蝿いので大富豪、伯爵令嬢と結婚した。
ユリシリーズ・グレープ補佐官23歳
優秀でシェーンに、こき使われている。
コクロイ・ルビーブル伯爵令息18歳
ヴィヴィアンの幼馴染み。
アンジェイ・ドルバン伯爵令息18歳
シェーンの元婚約者。
ルーク・ダルシュール侯爵25歳
嫁の父親が行方不明でシェーン公爵に相談する。
ミランダ・ダルシュール侯爵夫人20歳、父親が行方不明。
ダン・ドリンク侯爵37歳行方不明。
この国のデビット王太子殿下23歳、婚約者ジュリアン・スチール公爵令嬢が居るのにヴィヴィアンの従妹に興味があるようだ。
ジュリアン・スチール公爵令嬢18歳デビット王太子殿下の婚約者。
ヴィヴィアンの従兄弟ヨシアン・スプラット伯爵令息19歳
私と旦那様は婚約前1度お会いしただけで、結婚式は私と旦那様と出席者は無しで式は10分程で終わり今は2人の寝室?のベッドに座っております、旦那様が仰いました。
一度だけだ其れ以上閨を共にするつもりは無いと旦那様に宣言されました。
正直まだ愛情とか、ありませんが旦那様である、この方の言い分は最低ですよね?

身代わりの公爵家の花嫁は翌日から溺愛される。~初日を挽回し、溺愛させてくれ!~
湯川仁美
恋愛
姉の身代わりに公爵夫人になった。
「貴様と寝食を共にする気はない!俺に呼ばれるまでは、俺の前に姿を見せるな。声を聞かせるな」
夫と初対面の日、家族から男癖の悪い醜悪女と流され。
公爵である夫とから啖呵を切られたが。
翌日には誤解だと気づいた公爵は花嫁に好意を持ち、挽回活動を開始。
地獄の番人こと閻魔大王(善悪を判断する審判)と異名をもつ公爵は、影でプレゼントを贈り。話しかけるが、謝れない。
「愛しの妻。大切な妻。可愛い妻」とは言えない。
一度、言った言葉を撤回するのは難しい。
そして妻は普通の令嬢とは違い、媚びず、ビクビク怯えもせず普通に接してくれる。
徐々に距離を詰めていきましょう。
全力で真摯に接し、謝罪を行い、ラブラブに到着するコメディ。
第二章から口説きまくり。
第四章で完結です。
第五章に番外編を追加しました。

天才と呼ばれた彼女は無理矢理入れられた後宮で、怠惰な生活を極めようとする
カエデネコ
恋愛
※カクヨムの方にも載せてあります。サブストーリーなども書いていますので、よかったら、お越しくださいm(_ _)m
リアンは有名私塾に通い、天才と名高い少女であった。しかしある日突然、陛下の花嫁探しに白羽の矢が立ち、有無を言わさず後宮へ入れられてしまう。
王妃候補なんてなりたくない。やる気ゼロの彼女は後宮の部屋へ引きこもり、怠惰に暮らすためにその能力を使うことにした。

夫に離縁が切り出せません
えんどう
恋愛
初めて会った時から無口で無愛想な上に、夫婦となってからもまともな会話は無く身体を重ねてもそれは変わらない。挙げ句の果てに外に女までいるらしい。
妊娠した日にお腹の子供が産まれたら離縁して好きなことをしようと思っていたのだが──。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

転生した平凡顔な捨て子が公爵家の姫君?平民のままがいいので逃げてもいいですか
青波明来
恋愛
覚えているのは乱立するビルと車の波そして沢山の人
これってなんだろう前世の記憶・・・・・?
気が付くと赤ん坊になっていたあたし
いったいどうなったんだろ?
っていうか・・・・・あたしを抱いて息も絶え絶えに走っているこの女性は誰?
お母さんなのかな?でも今なんて言った?
「お嬢様、申し訳ありません!!もうすぐですよ」
誰かから逃れるかのように走ることを辞めない彼女は一軒の孤児院に赤ん坊を置いた
・・・・・えっ?!どうしたの?待って!!
雨も降ってるし寒いんだけど?!
こんなところに置いてかれたら赤ん坊のあたしなんて下手すると死んじゃうし!!
奇跡的に孤児院のシスターに拾われたあたし
高熱が出て一時は大変だったみたいだけどなんとか持ち直した
そんなあたしが公爵家の娘?
なんかの間違いです!!あたしはみなしごの平凡な女の子なんです
自由気ままな平民がいいのに周りが許してくれません
なので・・・・・・逃げます!!
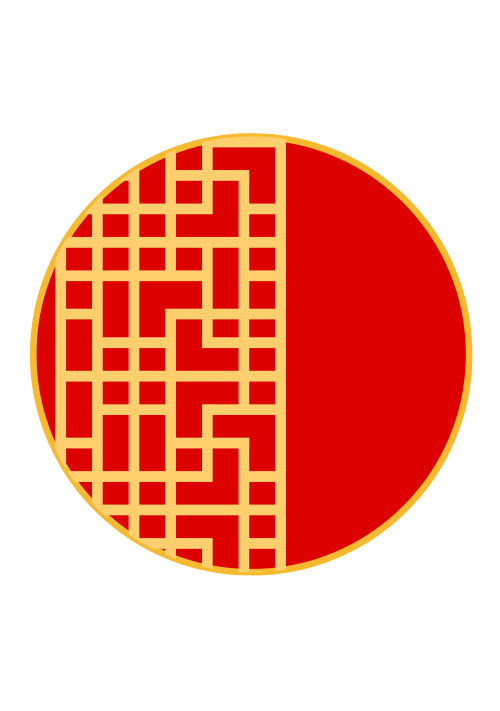
逃げるための後宮行きでしたが、なぜか奴が皇帝になっていました
吉高 花
恋愛
◆転生&ループの中華風ファンタジー◆
第15回恋愛小説大賞「中華・後宮ラブ賞」受賞しました!ありがとうございます!
かつて散々腐れ縁だったあいつが「俺たち、もし三十になってもお互いに独身だったら、結婚するか」
なんてことを言ったから、私は密かに三十になるのを待っていた。でもそんな私たちは、仲良く一緒にトラックに轢かれてしまった。
そして転生しても奴を忘れられなかった私は、ある日奴が綺麗なお嫁さんと仲良く微笑み合っている場面を見てしまう。
なにあれ! 許せん! 私も別の男と幸せになってやる!
しかしそんな決意もむなしく私はまた、今度は馬車に轢かれて逝ってしまう。
そして二度目。なんと今度は最後の人生をループした。ならば今度は前の記憶をフルに使って今度こそ幸せになってやる!
しかし私は気づいてしまった。このままでは、また奴の幸せな姿を見ることになるのでは?
それは嫌だ絶対に嫌だ。そうだ! 後宮に行ってしまえば、奴とは会わずにすむじゃない!
そうして私は意気揚々と、女官として後宮に潜り込んだのだった。
奴が、今世では皇帝になっているとも知らずに。
※タイトル試行錯誤中なのでたまに変わります。最初のタイトルは「ループの二度目は後宮で ~逃げるための後宮でしたが、なぜか奴が皇帝になっていました~」
※設定は架空なので史実には基づいて「おりません」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















