4 / 4
4 よっつ
しおりを挟む
急に訪れたひと時の静寂に、ももはは恐る恐る身を起こした。
自分を見下ろす男の目が怖い。
結果的に自分はまだ生きている。
だが、目前に立つのは、あの乱暴だった男たちを一瞬で葬り去った相手だ。できれば関わらないほうがいい気もする。
そんなももはの気持ちなどお構いなしに、冷たい金の瞳は逸らされることなくじっとももはの顔を見つめていた。
仕方なく、ももはもおずおずと見返す。
あまりにも整いすぎたその顔は、いっそ冷たく恐ろしい。
人間離れしたその容姿もそうだが、見たこともない真っ白な着物に真っ白な帯を締め、銀糸で龍の刺繍があしらわれた美しい羽織を肩に引っ掛けている。
その肩と背を滑るように広がる滑らかな白髪は、ところどころ銀色に輝き、見たこともない美しい金の瞳の奥で瞳孔が縦に伸びているのが見て取れた。
とても美しいが、見れば見るほど普通じゃない。
じっと見上げていたももはの視線を遮るように、こんな凄惨な場所にそぐわぬ優美な仕草で扇を広げた男が、その口元を隠してももはに聞いた。
「小娘、この中に家族でもおったか?」
ブンブンと首を振って否定するももは。
ももはの反応に眉を寄せ、男が再度尋ねてくる。
「じゃあなぜ泣いている」
そう指摘され、自分が泣いていることに気がついた。
ちょっと考えて、ももはが返す。
「怖いから」
「何が怖いのだ」
(何って、何だろう)
あまりに色々ありすぎて、頭が回らない。
「全部」
かろうじてそう返した途端、なにか張りつめていたものがプツリと切れた。
本当にそうだ。
すべてが怖い。
自分がどこにいるのか、ここがどこなのか、何が起きているのか、何で沢山死んでるのか、死にそうになってるのか──
「なんで、なんで私がこんな目にあうの。もうやだ、帰る」
帰る、そう口にはしたものの、帰り道なんてわかりはしない。
それでももうボロボロの今のももはには、そんなことを気にするほどの心の余裕はなかった。
「帰り道がわかるのか?」
案の定、男がももはに聞き返す。
「……わからない」
口にしたくなかった事実を口にして、またボロボロと涙があふれだした。
まるで子供のようなももはの返答に、やがて男が静かにため息をこぼす。
そんな仕草さえも、美しい顔のせいでやけに優雅に見えた。
「こちらへおいで」
まだ地面に座ったままのももはに、男はただ静かにそう告げた。
手を貸してくれるわけでもなければ、同情しているようにも見えない。
かといって、危害を加えるつもりもなさそうだ。
ももははももはで、今は自分のことで手いっぱいだった。
自分の姿を見下ろせば、見るも無残なことになっている。
引き破かれて下着が露出したシャツをかき寄せるが、ボタンが飛んでいて止められない。スカートはところどころ割けて、どこもかしこも血と泥にまみれて汚れていた。
自分の手にも、乾いた血がこびりついている。
またも恐怖で手が震えだした。
だがそんなももはを男はまだ静かに見下ろしている。
急かすことなく、かといって対して興味もなさそうな目で、ただじっと見ているだけだ。
なぜかそれがももはの心を落ち着かせてくれた。
落ち着いてよく考えれば、見た目は血だらけで酷いありさまだが、どうやら痛いところはほとんどないようだ。
さっき転んだときに擦りむいた手の甲と尻もちをついたお尻くらい。
血に濡れた手をボロボロのスカートの裾で拭いてみる。
水がないと全部は落とせそうにない。
少し綺麗になった甲で頬の涙を拭うと、やっとのことで立ち上がる気力が湧いてきた。
のっそりと立ち上がり、男の前へと歩みでる。
男は並ぶとももはよりも頭一つほど背が高い。
少し見上げるようにして前に立てば、男は無言で羽織を脱いで、ももはの肩にふわりとかけた。
「お前、名は?」
決してやさしくも、冷たくもない声で男が尋ねる。
邪心もないが、自分への興味心も感じられない。
それが今は心地よい。
ほんの少し緊張が解け、ももはは自分の名を告げようとして──
「ももは。私は、……あれ?」
──フルネームを言おうとして、はたと口が止まる。
私の名字……なんだった?
そんな当たり前のことを思い出せないことが、ももはをよりひどいパニックへと追いやっていく。
なんで、何が起きてるの?
不安と恐怖がぶり返し、またも顔がゆがんで涙が頬を伝う。
「どうした?」
「名字、私、自分の名字を思い出せない」
目前の男への畏怖よりも、自分がそんな当たり前のことを思い出せないことへの恐怖がももはの中で勝った。
思わずポロリとこぼすももはの言葉を拾って、男が目をすがめてももはを見る。
「名字とな。やはりお前は武家か公家の娘か」
「え?」
男の喋り方がおかしいのか、ももはには言っている意味が分からない。
男は男で首をかしげてももはに問い直す。
「姓があるのだろう。ならばあの村の姫か?」
「姫ってそんな。私そんな美人じゃないし」
「またわからぬことを」
どうにも二人の話がかみ合わない。
「小娘、ではお前の親はどこにおる」
そう尋ねられ、答えようとして再び頭が真っ白になった。
「うちの親……まって、お母さんとお父さんの顔、思い出せない」
思わず叫び出しそうになりながらも、ももはは懸命に自分の記憶を辿っていく。
自分にはちゃんと母と父がいることは間違いない。
それは思い出せる。
なのに、その顔や名前を辿ろうとすると、まるで記憶に靄がかかったように思い出せないのだ。
ももはが自分の記憶と悪戦苦闘する一方、男は男でももはのあやふやな答えを自分なりに解釈したようだ。
扇の向こう側でため息をついたのち、不愛想につぶやく。
「親もなく、帰り道もわからぬと」
正確には少し違うのだが、今のももはにそれをいちいち訂正する気力もない。
震える体を抱きしめながら、男を見上げ答えた。
「そうみたい」
「よかろう。大人しくしておいで」
覚束ないももはの返事を聞いた男は、全て悟ったという顔で一つ頷くと、すっと手を伸ばしてももを引き寄せる。
ももはが驚いて声をあげる間もなく、手に持っていた扇でももはの顔を覆った。
自分を見下ろす男の目が怖い。
結果的に自分はまだ生きている。
だが、目前に立つのは、あの乱暴だった男たちを一瞬で葬り去った相手だ。できれば関わらないほうがいい気もする。
そんなももはの気持ちなどお構いなしに、冷たい金の瞳は逸らされることなくじっとももはの顔を見つめていた。
仕方なく、ももはもおずおずと見返す。
あまりにも整いすぎたその顔は、いっそ冷たく恐ろしい。
人間離れしたその容姿もそうだが、見たこともない真っ白な着物に真っ白な帯を締め、銀糸で龍の刺繍があしらわれた美しい羽織を肩に引っ掛けている。
その肩と背を滑るように広がる滑らかな白髪は、ところどころ銀色に輝き、見たこともない美しい金の瞳の奥で瞳孔が縦に伸びているのが見て取れた。
とても美しいが、見れば見るほど普通じゃない。
じっと見上げていたももはの視線を遮るように、こんな凄惨な場所にそぐわぬ優美な仕草で扇を広げた男が、その口元を隠してももはに聞いた。
「小娘、この中に家族でもおったか?」
ブンブンと首を振って否定するももは。
ももはの反応に眉を寄せ、男が再度尋ねてくる。
「じゃあなぜ泣いている」
そう指摘され、自分が泣いていることに気がついた。
ちょっと考えて、ももはが返す。
「怖いから」
「何が怖いのだ」
(何って、何だろう)
あまりに色々ありすぎて、頭が回らない。
「全部」
かろうじてそう返した途端、なにか張りつめていたものがプツリと切れた。
本当にそうだ。
すべてが怖い。
自分がどこにいるのか、ここがどこなのか、何が起きているのか、何で沢山死んでるのか、死にそうになってるのか──
「なんで、なんで私がこんな目にあうの。もうやだ、帰る」
帰る、そう口にはしたものの、帰り道なんてわかりはしない。
それでももうボロボロの今のももはには、そんなことを気にするほどの心の余裕はなかった。
「帰り道がわかるのか?」
案の定、男がももはに聞き返す。
「……わからない」
口にしたくなかった事実を口にして、またボロボロと涙があふれだした。
まるで子供のようなももはの返答に、やがて男が静かにため息をこぼす。
そんな仕草さえも、美しい顔のせいでやけに優雅に見えた。
「こちらへおいで」
まだ地面に座ったままのももはに、男はただ静かにそう告げた。
手を貸してくれるわけでもなければ、同情しているようにも見えない。
かといって、危害を加えるつもりもなさそうだ。
ももははももはで、今は自分のことで手いっぱいだった。
自分の姿を見下ろせば、見るも無残なことになっている。
引き破かれて下着が露出したシャツをかき寄せるが、ボタンが飛んでいて止められない。スカートはところどころ割けて、どこもかしこも血と泥にまみれて汚れていた。
自分の手にも、乾いた血がこびりついている。
またも恐怖で手が震えだした。
だがそんなももはを男はまだ静かに見下ろしている。
急かすことなく、かといって対して興味もなさそうな目で、ただじっと見ているだけだ。
なぜかそれがももはの心を落ち着かせてくれた。
落ち着いてよく考えれば、見た目は血だらけで酷いありさまだが、どうやら痛いところはほとんどないようだ。
さっき転んだときに擦りむいた手の甲と尻もちをついたお尻くらい。
血に濡れた手をボロボロのスカートの裾で拭いてみる。
水がないと全部は落とせそうにない。
少し綺麗になった甲で頬の涙を拭うと、やっとのことで立ち上がる気力が湧いてきた。
のっそりと立ち上がり、男の前へと歩みでる。
男は並ぶとももはよりも頭一つほど背が高い。
少し見上げるようにして前に立てば、男は無言で羽織を脱いで、ももはの肩にふわりとかけた。
「お前、名は?」
決してやさしくも、冷たくもない声で男が尋ねる。
邪心もないが、自分への興味心も感じられない。
それが今は心地よい。
ほんの少し緊張が解け、ももはは自分の名を告げようとして──
「ももは。私は、……あれ?」
──フルネームを言おうとして、はたと口が止まる。
私の名字……なんだった?
そんな当たり前のことを思い出せないことが、ももはをよりひどいパニックへと追いやっていく。
なんで、何が起きてるの?
不安と恐怖がぶり返し、またも顔がゆがんで涙が頬を伝う。
「どうした?」
「名字、私、自分の名字を思い出せない」
目前の男への畏怖よりも、自分がそんな当たり前のことを思い出せないことへの恐怖がももはの中で勝った。
思わずポロリとこぼすももはの言葉を拾って、男が目をすがめてももはを見る。
「名字とな。やはりお前は武家か公家の娘か」
「え?」
男の喋り方がおかしいのか、ももはには言っている意味が分からない。
男は男で首をかしげてももはに問い直す。
「姓があるのだろう。ならばあの村の姫か?」
「姫ってそんな。私そんな美人じゃないし」
「またわからぬことを」
どうにも二人の話がかみ合わない。
「小娘、ではお前の親はどこにおる」
そう尋ねられ、答えようとして再び頭が真っ白になった。
「うちの親……まって、お母さんとお父さんの顔、思い出せない」
思わず叫び出しそうになりながらも、ももはは懸命に自分の記憶を辿っていく。
自分にはちゃんと母と父がいることは間違いない。
それは思い出せる。
なのに、その顔や名前を辿ろうとすると、まるで記憶に靄がかかったように思い出せないのだ。
ももはが自分の記憶と悪戦苦闘する一方、男は男でももはのあやふやな答えを自分なりに解釈したようだ。
扇の向こう側でため息をついたのち、不愛想につぶやく。
「親もなく、帰り道もわからぬと」
正確には少し違うのだが、今のももはにそれをいちいち訂正する気力もない。
震える体を抱きしめながら、男を見上げ答えた。
「そうみたい」
「よかろう。大人しくしておいで」
覚束ないももはの返事を聞いた男は、全て悟ったという顔で一つ頷くと、すっと手を伸ばしてももを引き寄せる。
ももはが驚いて声をあげる間もなく、手に持っていた扇でももはの顔を覆った。
5
お気に入りに追加
7
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


孤独な少年の心を癒した神社のあやかし達
フェア
キャラ文芸
小学校でいじめに遭って不登校になったショウが、中学入学後に両親が交通事故に遭ったことをきっかけに山奥の神社に預けられる。心優しい神主のタカヒロと奇妙奇天烈な妖怪達との交流で少しずつ心の傷を癒やしていく、ハートフルな物語。
*丁寧に描きすぎて、なかなか神社にたどり着いてないです。

女神の手繰る糸
ルリコ
キャラ文芸
※最終話6話を1月17日(木)の7時半に公開!!
キャラ文芸大賞エントリー、最高310位、27pt
この宇宙のどこかに存在する星。
ここをつくったのは女神。金髪で赤い瞳なのに派手さはない、港区女子くらいの年齢(見た目)の女性。
彼女の仕事は、人々の祈りを手紙にした通称ファンレターを読むことと、自分の基準で祝福を与える(ファンサ)ことだ。
そして、今日もファンレターを読む。
読み終えて自身に唯一仕える天使を呼び寄せて言う。
「祝福を与えようと思うの」
そのファンレターの内容はなんなのか。
そして、悪事に寛大な女神が「絶対に許さない」と顔を歪ませることとは?
ーーーーーー
キャラ文芸大賞用に書いた短編小説。
カクヨム様でも同時連載。
ぜひ代表作「前世で若くして病死した私は、持病を治して長生きしたいです」もお読みください!
https://www.alphapolis.co.jp/novel/266458505/518875098
[累計ポイント表]
初日:391pt /お気に入り1
2024/12/27:696pt
2025/01/05:1001pt
[大賞ポイント]
1→2→4→8→10→14→17→20→24→26

瑠菜の生活日記
白咲 神瑠
キャラ文芸
大好きで尊敬している師匠コムが急に蒸発して死んだのだと周りから言われる瑠菜。それを認めることはできず、コムは生きているんだと信じているが、見つけなければ信じ続けることもできない。
そんなことを考えていたある日、瑠菜の弟子になりたいという少女サクラが現れる。瑠菜は弟子を作ることを考えたこともなかったが、しつこいサクラを自分と重ねてしまいサクラを弟子にする。
サクラの失敗や、恋愛というより道をしながらも、コムを見つけるために瑠菜はコムがいなくなった裏側を探る。

【完結】もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

真紅の蓮華はあやかしを照らす~後宮の占術師と禁断の書~
昼から山猫
キャラ文芸
家の出身ながら、宮廷では風変わりな占術師として扱われる霧香(きりか)。彼女は天象や暦を読み解き、あやかしの動きを察知することに長けていたが、怪しげな術に頼る者と陰口を叩かれていた。後宮の妃が頻繁に悪夢を見るようになり、その解決を命じられた霧香は、占いの結果から皇族に隠された“禁断の書”の存在を示唆する。華々しい式典の裏で起きる怪奇現象、夜ごとに鳴り響く不協和音、そこには真紅の蓮華と呼ばれるあやかしを封じた古代の儀式が関係しているらしい。調査を進めるうち、霧香は禁断の書が皇宮のどこかに眠り、妃たちを蝕む悪夢と深く結びついていることを知る。しかし、やがて誰かが霧香の行動を阻むかのように、決定的な証拠が次々と失われていき――。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
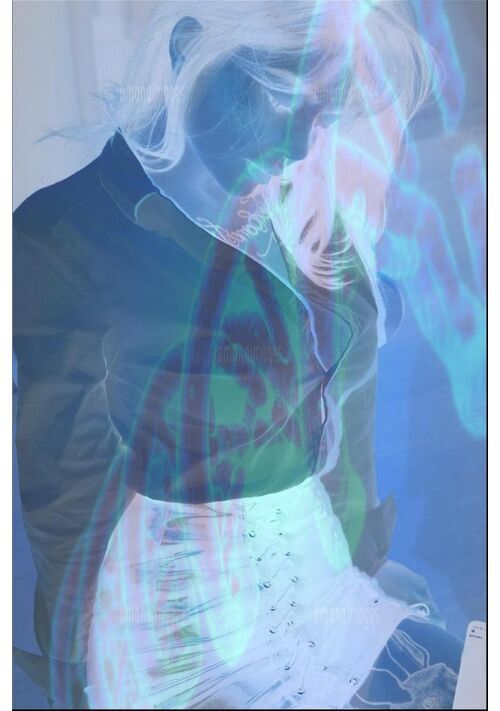
戒め
ムービーマスター
キャラ文芸
悪魔サタン=ルシファーの涙ほどの正義の意志から生まれたメイと、神が微かに抱いた悪意から生まれた天使・シンが出会う現世は、世界の滅びる時代なのか、地球上の人間や動物に次々と未知のウイルスが襲いかかり、ダークヒロイン・メイの不思議な超能力「戒め」も発動され、更なる混乱と恐怖が押し寄せる・・・
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















