50 / 60
第四Q その右手が掴むもの
7
しおりを挟む
六月十三日。全国高等学校バスケットボール選手権大会、インターハイ予選県大会一日目。
初戦、対瑞江高校戦。沢高は序盤からリードを広げ、一度もリードを奪われることなく八十一対六十で勝利を収めた。
宇佐美監督は第四クォーターでスタメンを下げ、控え選手を投入してスタメンの体力温存を図ったが、雪之丞が試合に出ることはなかった。
六月十四日、インターハイ予選県大会二日目。
沢高男子バスケ部は午前八時に学校集合予定だが、雪之丞は夏希を誘ってリングのある公園でウォーミングアップに励んでいた。
「ジョーだってもう立派にバスケ部員なんだからさー、試合前のコンディションくらい自分でしっかり整えておきなさいよね」
すでに一時間近く付き合わされている夏希は、いい加減疲れてきたのかはっきりと文句を口にした。
「もう少し付き合ってくれよ。ほら、次のパスくれ」
「てか、なんでわたしに声かけるのよ。わたし素人なんだから、バスケの練習だったらミサちゃんに声をかければ良かったじゃない」
「何言ってんだ。女バスも昨日勝ったんだから、紗綾は今日も試合に出るんだぞ? 俺が迷惑をかけるのはお前しかいない」
「……あんた……決め顔で言う台詞じゃないわよ、それ」
夏希は溜息を吐きながらも、ほんの少しだけ嬉しそうな顔で雪之丞にパスを出した。素人とはいえ、運動神経のいい夏希が出すパスはわりと正確で取りやすい。雪之丞はパスを受け取り、流れるようにレイアップシュートを決めた。
「よっしゃ。じゃあ次はもう少し前方に落とす感じで出してみてく……」
そう言いかけた雪之丞の瞳に、爽やかな朝の公園には似つかわしくない連中が映った。
雪之丞を威嚇するように睨む者や獲物を見定める獣の目で見る者もいれば、ただヘラヘラと不快な笑みを浮かべる者もいる。数にして十人程度の彼らは、ゆっくりと雪之丞と夏希を包囲した。
柄の悪い連中だと判断しても差し支えないだろう。過去に何度もこういった輩を相手に喧嘩をしてきた雪之丞は、反射的に強く睨み返した。
「……ジョー、なによこの人たち……」
気の強い夏希は、連中に屈するものかと言わんばかりに一歩も引こうとしなかった。
食ってかかりそうな夏希に下がっているように言って、雪之丞は彼らに近づいた。
「なんだお前ら? 何か用か?」
「今日の日を待っていたぜ、バスケ部の鳴海くん? この間の借り、返させてもらうぞ」
中途半端に伸びた金髪の男が一歩前に出てきて、至近距離で雪之丞を睨みつけた。
「この前? ……お前、誰だよ?」
雪之丞が顔を顰めると、男は並びの悪い歯を噛んで怒り狂ったように大声を浴びせた。
「てめえ! 俺が沢高の前で女攫おうとしたら邪魔してきただろうがよ! この俺に楯突いたくせに覚えてねえのか!?」
ようやく思い出した。迎えの車を待っていた名塚に絡んでいた三人の中の一人だ。確か、丸山といっただろうか。
よりによって試合当日を狙って復讐にくるとは、卑怯で不快な連中だと思った。
「あー、忘れてたわ。何? こんな朝から絡んでくるとか馬鹿じゃね?」
「ふん、馬鹿はてめえだよ。てめえのことは調べさせてもらった。 ……てめえが大切に思ってるモンは全部、ぶち壊してやるからな」
丸山は雪之丞が持っていたバスケットボールに唾を吐き、嗤った。それは雪之丞が激昂するには、十分過ぎる理由だった。
「……何してんだ? このボールはお前の命より価値があんだよ、ああ?」
「丸山さん、そろそろ殺っちゃっていーっすか? つか、うわ! マジだ! こいつ、マジで左手ねえじゃん!」
丸山の左にいた団子鼻の男が一歩前に出て、雪之丞の左手を指差した。
「だからなんだよ。お前らにはちょうどいいハンデだろうが」
冷静さを失いつつある雪之丞が凄むと、夏希が雪之丞の手をとってかぶりを振った。
「手を出しちゃダメ! あんた、あの日にもう喧嘩はしないって誓ったでしょ!? それに今日喧嘩なんかしたら、バスケ部がどうなるか考えて!」
夏希の言葉でチームメイトの顔が脳裏に浮かび、沸騰していた血液は温度を下げた。冷静にさせてくれた夏希には感謝だ。彼らの努力を裏切ることは絶対にしたくない。
「……わかった、好きにしろ。俺は手を出さねえから、殴りたければ殴れ。ただし、夏希とバスケ部には手を出すな」
バスケ部や夏希が危険に晒されることに比べたら、自分が怪我をして試合に出られないくらいなんてことはない。試合に出たくて必死になって練習をしてきた分悔しくないわけがないが、自分が撒いた喧嘩の種だ。責任を取るのが筋だろう。
「はっ! カーッコイイねェ! だが今の言葉、後悔することになるぜ? まあどちらにせよ、腑抜けのお前に手が出せるわけないけどなあ!」
丸山は右手にナックルダスターをはめ、雪之丞の頬を殴打した。
武器を使われたこととまったく避けなかったことが相乗して、以前よりは格段に大きなダメージを受けた。倒れこそしなかったものの打撃を受けた頬は鋭い痛みを神経に訴え、唇からは血が流れた。
高笑いをした丸山が手で合図をすると、雪之丞たちを囲っていた連中はジリジリと近づいてきた。中には鉄パイプを持っている者もいる。なかなかひどいリンチにあいそうだなと、腹のあたりに力を入れ覚悟を決めていると、
「ちょっと待ちなさいよ! 何馬鹿なこと言ってんの!? ジョー! あんたそれでいいの!? 今日まで頑張ってきたんでしょ!?」
夏希が雪之丞の手を取り、声を荒らげた。
「うるせえ、夏希は黙ってろ」
夏希の心配を無下にするより、彼女を守る方が大切だ。雪之丞はわざと突き放すようにして夏希の手を振り払った。
その様子を見ていた丸山は夏希に視線を移し、上から下まで舐め回すように見てから厭らしい笑みを浮かべた。
「……そうだ。そこの女が俺たちと遊んでくれるなら、鳴海を見逃してやるってのはどうだ? なあ、お前らはどう思う?」
同意を求めた丸山に、連れの連中も彼と同様に不快な笑みを浮かべて頷いた。
「おい、俺抜きで勝手に話を決めてんじゃねえぞ。そんなクソみてえな条件呑むわけ――」
「わかった。それでジョーが見逃してもらえるなら」
呆れた雪之丞が言い終わる前に、夏希は丸山の瞳を真っ直ぐに見据えてそう言った。
「はあ? 馬鹿か夏希! そんなこと許すわけねえだろ!?」
「はっはっは! おい鳴海! この女、てめえなんかよりよっぽど肝が据わっててイイ女じゃねえか!」
男たちの不快な笑い声に、腸が煮えくり返りそうになった。唇を真一文字に結んで強がる夏希の表情を見た雪之丞は、我慢の限界を迎えつつあった。
「……ジョー、わたしなら大丈夫。あんたの負担にだけはなりたくないって、五年前から決めてるから。早く試合に行って活躍してきてよ」
夏希はそう言って雪之丞の肩を叩き、笑顔を作った。その笑顔が無理して作ったものであることくらい雪之丞にもわかるし、触れられた指先から体が震えているのも伝わってきた。
「そうそう! 君、どうせ遊んでるんだろ? 割り切って楽しもうぜえー? 解放するときにはどうなってるのか、想像もできねえけどな!」
丸山を中心に、男たちは一斉に下品な笑い声をあげた。
――その言葉に夏希がどれだけ傷つくのか、お前らにはわかんねえだろうよ。
強がっていた夏希の表情が陰り、大きな瞳には涙が浮かんでいた。
それを見たとき、必死になって理性で押さえつけていた雪之丞の怒りが、限界点を突破した。
夏希を傷つける奴は全員、この俺が許さない。
「……もう我慢できねえ。お前ら全員、ただでは帰れないと思え」
丸山を殺す勢いで睨みつけると、雪之丞の殺気に怯えたのか数人がたじろいだ。
「おいおい、いいのかぁ? 手を出したらお前、バスケ部に迷惑かけちまうんだぜ?」
「目の前にいる大事な女すら見捨てる男に、戻る場所なんかねえよ」
怒りで我を忘れた雪之丞は、夏希の前で大胆な発言をしていることにも気づいていなかった。
「マジかー。ジョー、ちょっと熱すぎるねえ」
後方から聞こえる飄々とした声に振り向いた雪之丞は、そこにいる人物を見て目を瞬かせた。
「……お前ら、なんでここに?」
そこにはいつものように人を茶化すような笑みを浮かべる正彰と、不機嫌そうにいかつい顔でガンを飛ばしている千原の姿があった。
「ちょっとね、ジョーがやられるかもっていう悪い噂を聞いたもんだからさ」
笑っているくせにやけに迫力がある正彰が雪之丞を囲う連中を一人ひとり見定めるように視認していくと、彼らは少し怯んだようだった。
「そんで千原に声かけてみたら、目の色変えて加勢するって言ってきてさー。やー、やっぱジョーは愛されてるわ」
「うるせえぞ広尾! 俺以外の奴に鳴海をぶっ殺されたくねえだけだって言っただろうが!」
正彰にからかわれて唾を飛ばしながら反論している千原を見ていると、こんな状況にもかかわらず笑いが込み上げてきた。
怒りで沸騰していた頭がクリアになり、今自分が何をすべきなのかが明確にわかる。
「……千原、これを言うのは二回目になる。……お前のツンデレとか、誰得?」
「あ!? 少しは黙ってろボケェ! やっぱりお前から殺ってやろうか!?」
喚きながらも千原と正彰は、雪之丞と夏希を守るように前に出た。
何を言えばいいのかはわかる。そして、二人は雪之丞の言葉を待っている。
雪之丞ははっきりとした声で、彼らの背中に告げた。
「わりいな正彰、千原。……ここは頼んだ」
それを口にした瞬間、二人のスイッチが入る音が聞こえたような気がした。
「はいよー。すぐに終わらせて、試合見に行くよ」
「ここにいる奴らをぶちのめしたら、次は鳴海だからな! 首洗って待っとけ!」
正彰と千原が敵集団に切り込んでいくのと同時に、雪之丞は夏希の手を取って走り出した。
「おい待てよ! 逃がすわけねえだろ!?」
雪之丞の進行方向を塞いできた男を、千原が飛び蹴りで吹っ飛ばした。男は尻から豪快に転がっていったため、雪之丞を止めようと次々と迫り寄ってくる連中にたたらを踏ませた。その隙をつき、雪之丞は瞬足を活かしてその場を颯爽と走り抜けた。
「待てよ鳴海い! 逃げんのかよ!」
そう叫んで追いかけてくる丸山に、正彰が立ちはだかった。
「あいつはお前と違って忙しいんだってさ。さあ、暇人同士仲良くやろうぜ?」
罵声や人と人がぶつかり合う生々しい音を耳にしながらも、雪之丞は決して足を止めなかった。
「ジョー! いいの!?」
「ああ! あいつらになら任せられる!」
二人を案じて心配の声をあげる夏希にそう言って、雪之丞は一度も後ろを振り返らなかった。
正彰と千原に絶対的な信頼を置いていることは勿論、今からバスケの試合に臨むスポーツマンとして、喧嘩で流れた血など見てはいけないと思ったからである。
夏希の手を引きながら、雪之丞はただ真っ直ぐ前だけを向いて走った。
初戦、対瑞江高校戦。沢高は序盤からリードを広げ、一度もリードを奪われることなく八十一対六十で勝利を収めた。
宇佐美監督は第四クォーターでスタメンを下げ、控え選手を投入してスタメンの体力温存を図ったが、雪之丞が試合に出ることはなかった。
六月十四日、インターハイ予選県大会二日目。
沢高男子バスケ部は午前八時に学校集合予定だが、雪之丞は夏希を誘ってリングのある公園でウォーミングアップに励んでいた。
「ジョーだってもう立派にバスケ部員なんだからさー、試合前のコンディションくらい自分でしっかり整えておきなさいよね」
すでに一時間近く付き合わされている夏希は、いい加減疲れてきたのかはっきりと文句を口にした。
「もう少し付き合ってくれよ。ほら、次のパスくれ」
「てか、なんでわたしに声かけるのよ。わたし素人なんだから、バスケの練習だったらミサちゃんに声をかければ良かったじゃない」
「何言ってんだ。女バスも昨日勝ったんだから、紗綾は今日も試合に出るんだぞ? 俺が迷惑をかけるのはお前しかいない」
「……あんた……決め顔で言う台詞じゃないわよ、それ」
夏希は溜息を吐きながらも、ほんの少しだけ嬉しそうな顔で雪之丞にパスを出した。素人とはいえ、運動神経のいい夏希が出すパスはわりと正確で取りやすい。雪之丞はパスを受け取り、流れるようにレイアップシュートを決めた。
「よっしゃ。じゃあ次はもう少し前方に落とす感じで出してみてく……」
そう言いかけた雪之丞の瞳に、爽やかな朝の公園には似つかわしくない連中が映った。
雪之丞を威嚇するように睨む者や獲物を見定める獣の目で見る者もいれば、ただヘラヘラと不快な笑みを浮かべる者もいる。数にして十人程度の彼らは、ゆっくりと雪之丞と夏希を包囲した。
柄の悪い連中だと判断しても差し支えないだろう。過去に何度もこういった輩を相手に喧嘩をしてきた雪之丞は、反射的に強く睨み返した。
「……ジョー、なによこの人たち……」
気の強い夏希は、連中に屈するものかと言わんばかりに一歩も引こうとしなかった。
食ってかかりそうな夏希に下がっているように言って、雪之丞は彼らに近づいた。
「なんだお前ら? 何か用か?」
「今日の日を待っていたぜ、バスケ部の鳴海くん? この間の借り、返させてもらうぞ」
中途半端に伸びた金髪の男が一歩前に出てきて、至近距離で雪之丞を睨みつけた。
「この前? ……お前、誰だよ?」
雪之丞が顔を顰めると、男は並びの悪い歯を噛んで怒り狂ったように大声を浴びせた。
「てめえ! 俺が沢高の前で女攫おうとしたら邪魔してきただろうがよ! この俺に楯突いたくせに覚えてねえのか!?」
ようやく思い出した。迎えの車を待っていた名塚に絡んでいた三人の中の一人だ。確か、丸山といっただろうか。
よりによって試合当日を狙って復讐にくるとは、卑怯で不快な連中だと思った。
「あー、忘れてたわ。何? こんな朝から絡んでくるとか馬鹿じゃね?」
「ふん、馬鹿はてめえだよ。てめえのことは調べさせてもらった。 ……てめえが大切に思ってるモンは全部、ぶち壊してやるからな」
丸山は雪之丞が持っていたバスケットボールに唾を吐き、嗤った。それは雪之丞が激昂するには、十分過ぎる理由だった。
「……何してんだ? このボールはお前の命より価値があんだよ、ああ?」
「丸山さん、そろそろ殺っちゃっていーっすか? つか、うわ! マジだ! こいつ、マジで左手ねえじゃん!」
丸山の左にいた団子鼻の男が一歩前に出て、雪之丞の左手を指差した。
「だからなんだよ。お前らにはちょうどいいハンデだろうが」
冷静さを失いつつある雪之丞が凄むと、夏希が雪之丞の手をとってかぶりを振った。
「手を出しちゃダメ! あんた、あの日にもう喧嘩はしないって誓ったでしょ!? それに今日喧嘩なんかしたら、バスケ部がどうなるか考えて!」
夏希の言葉でチームメイトの顔が脳裏に浮かび、沸騰していた血液は温度を下げた。冷静にさせてくれた夏希には感謝だ。彼らの努力を裏切ることは絶対にしたくない。
「……わかった、好きにしろ。俺は手を出さねえから、殴りたければ殴れ。ただし、夏希とバスケ部には手を出すな」
バスケ部や夏希が危険に晒されることに比べたら、自分が怪我をして試合に出られないくらいなんてことはない。試合に出たくて必死になって練習をしてきた分悔しくないわけがないが、自分が撒いた喧嘩の種だ。責任を取るのが筋だろう。
「はっ! カーッコイイねェ! だが今の言葉、後悔することになるぜ? まあどちらにせよ、腑抜けのお前に手が出せるわけないけどなあ!」
丸山は右手にナックルダスターをはめ、雪之丞の頬を殴打した。
武器を使われたこととまったく避けなかったことが相乗して、以前よりは格段に大きなダメージを受けた。倒れこそしなかったものの打撃を受けた頬は鋭い痛みを神経に訴え、唇からは血が流れた。
高笑いをした丸山が手で合図をすると、雪之丞たちを囲っていた連中はジリジリと近づいてきた。中には鉄パイプを持っている者もいる。なかなかひどいリンチにあいそうだなと、腹のあたりに力を入れ覚悟を決めていると、
「ちょっと待ちなさいよ! 何馬鹿なこと言ってんの!? ジョー! あんたそれでいいの!? 今日まで頑張ってきたんでしょ!?」
夏希が雪之丞の手を取り、声を荒らげた。
「うるせえ、夏希は黙ってろ」
夏希の心配を無下にするより、彼女を守る方が大切だ。雪之丞はわざと突き放すようにして夏希の手を振り払った。
その様子を見ていた丸山は夏希に視線を移し、上から下まで舐め回すように見てから厭らしい笑みを浮かべた。
「……そうだ。そこの女が俺たちと遊んでくれるなら、鳴海を見逃してやるってのはどうだ? なあ、お前らはどう思う?」
同意を求めた丸山に、連れの連中も彼と同様に不快な笑みを浮かべて頷いた。
「おい、俺抜きで勝手に話を決めてんじゃねえぞ。そんなクソみてえな条件呑むわけ――」
「わかった。それでジョーが見逃してもらえるなら」
呆れた雪之丞が言い終わる前に、夏希は丸山の瞳を真っ直ぐに見据えてそう言った。
「はあ? 馬鹿か夏希! そんなこと許すわけねえだろ!?」
「はっはっは! おい鳴海! この女、てめえなんかよりよっぽど肝が据わっててイイ女じゃねえか!」
男たちの不快な笑い声に、腸が煮えくり返りそうになった。唇を真一文字に結んで強がる夏希の表情を見た雪之丞は、我慢の限界を迎えつつあった。
「……ジョー、わたしなら大丈夫。あんたの負担にだけはなりたくないって、五年前から決めてるから。早く試合に行って活躍してきてよ」
夏希はそう言って雪之丞の肩を叩き、笑顔を作った。その笑顔が無理して作ったものであることくらい雪之丞にもわかるし、触れられた指先から体が震えているのも伝わってきた。
「そうそう! 君、どうせ遊んでるんだろ? 割り切って楽しもうぜえー? 解放するときにはどうなってるのか、想像もできねえけどな!」
丸山を中心に、男たちは一斉に下品な笑い声をあげた。
――その言葉に夏希がどれだけ傷つくのか、お前らにはわかんねえだろうよ。
強がっていた夏希の表情が陰り、大きな瞳には涙が浮かんでいた。
それを見たとき、必死になって理性で押さえつけていた雪之丞の怒りが、限界点を突破した。
夏希を傷つける奴は全員、この俺が許さない。
「……もう我慢できねえ。お前ら全員、ただでは帰れないと思え」
丸山を殺す勢いで睨みつけると、雪之丞の殺気に怯えたのか数人がたじろいだ。
「おいおい、いいのかぁ? 手を出したらお前、バスケ部に迷惑かけちまうんだぜ?」
「目の前にいる大事な女すら見捨てる男に、戻る場所なんかねえよ」
怒りで我を忘れた雪之丞は、夏希の前で大胆な発言をしていることにも気づいていなかった。
「マジかー。ジョー、ちょっと熱すぎるねえ」
後方から聞こえる飄々とした声に振り向いた雪之丞は、そこにいる人物を見て目を瞬かせた。
「……お前ら、なんでここに?」
そこにはいつものように人を茶化すような笑みを浮かべる正彰と、不機嫌そうにいかつい顔でガンを飛ばしている千原の姿があった。
「ちょっとね、ジョーがやられるかもっていう悪い噂を聞いたもんだからさ」
笑っているくせにやけに迫力がある正彰が雪之丞を囲う連中を一人ひとり見定めるように視認していくと、彼らは少し怯んだようだった。
「そんで千原に声かけてみたら、目の色変えて加勢するって言ってきてさー。やー、やっぱジョーは愛されてるわ」
「うるせえぞ広尾! 俺以外の奴に鳴海をぶっ殺されたくねえだけだって言っただろうが!」
正彰にからかわれて唾を飛ばしながら反論している千原を見ていると、こんな状況にもかかわらず笑いが込み上げてきた。
怒りで沸騰していた頭がクリアになり、今自分が何をすべきなのかが明確にわかる。
「……千原、これを言うのは二回目になる。……お前のツンデレとか、誰得?」
「あ!? 少しは黙ってろボケェ! やっぱりお前から殺ってやろうか!?」
喚きながらも千原と正彰は、雪之丞と夏希を守るように前に出た。
何を言えばいいのかはわかる。そして、二人は雪之丞の言葉を待っている。
雪之丞ははっきりとした声で、彼らの背中に告げた。
「わりいな正彰、千原。……ここは頼んだ」
それを口にした瞬間、二人のスイッチが入る音が聞こえたような気がした。
「はいよー。すぐに終わらせて、試合見に行くよ」
「ここにいる奴らをぶちのめしたら、次は鳴海だからな! 首洗って待っとけ!」
正彰と千原が敵集団に切り込んでいくのと同時に、雪之丞は夏希の手を取って走り出した。
「おい待てよ! 逃がすわけねえだろ!?」
雪之丞の進行方向を塞いできた男を、千原が飛び蹴りで吹っ飛ばした。男は尻から豪快に転がっていったため、雪之丞を止めようと次々と迫り寄ってくる連中にたたらを踏ませた。その隙をつき、雪之丞は瞬足を活かしてその場を颯爽と走り抜けた。
「待てよ鳴海い! 逃げんのかよ!」
そう叫んで追いかけてくる丸山に、正彰が立ちはだかった。
「あいつはお前と違って忙しいんだってさ。さあ、暇人同士仲良くやろうぜ?」
罵声や人と人がぶつかり合う生々しい音を耳にしながらも、雪之丞は決して足を止めなかった。
「ジョー! いいの!?」
「ああ! あいつらになら任せられる!」
二人を案じて心配の声をあげる夏希にそう言って、雪之丞は一度も後ろを振り返らなかった。
正彰と千原に絶対的な信頼を置いていることは勿論、今からバスケの試合に臨むスポーツマンとして、喧嘩で流れた血など見てはいけないと思ったからである。
夏希の手を引きながら、雪之丞はただ真っ直ぐ前だけを向いて走った。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

自称未来の妻なヤンデレ転校生に振り回された挙句、最終的に責任を取らされる話
水島紗鳥
青春
成績優秀でスポーツ万能な男子高校生の黒月拓馬は、学校では常に1人だった。
そんなハイスペックぼっちな拓馬の前に未来の妻を自称する日英ハーフの美少女転校生、十六夜アリスが現れた事で平穏だった日常生活が激変する。
凄まじくヤンデレなアリスは拓馬を自分だけの物にするためにありとあらゆる手段を取り、どんどん外堀を埋めていく。
「なあ、サインと判子欲しいって渡された紙が記入済婚姻届なのは気のせいか?」
「気にしない気にしない」
「いや、気にするに決まってるだろ」
ヤンデレなアリスから完全にロックオンされてしまった拓馬の運命はいかに……?(なお、もう一生逃げられない模様)
表紙はイラストレーターの谷川犬兎様に描いていただきました。
小説投稿サイトでの利用許可を頂いております。


ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

隣人の女性がDVされてたから助けてみたら、なぜかその人(年下の女子大生)と同棲することになった(なんで?)
チドリ正明@不労所得発売中!!
青春
マンションの隣の部屋から女性の悲鳴と男性の怒鳴り声が聞こえた。
主人公 時田宗利(ときたむねとし)の判断は早かった。迷わず訪問し時間を稼ぎ、確証が取れた段階で警察に通報。DV男を現行犯でとっちめることに成功した。
ちっぽけな勇気と小心者が持つ単なる親切心でやった宗利は日常に戻る。
しかし、しばらくして宗時は見覚えのある女性が部屋の前にしゃがみ込んでいる姿を発見した。
その女性はDVを受けていたあの時の隣人だった。
「頼れる人がいないんです……私と一緒に暮らしてくれませんか?」
これはDVから女性を守ったことで始まる新たな恋物語。

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……
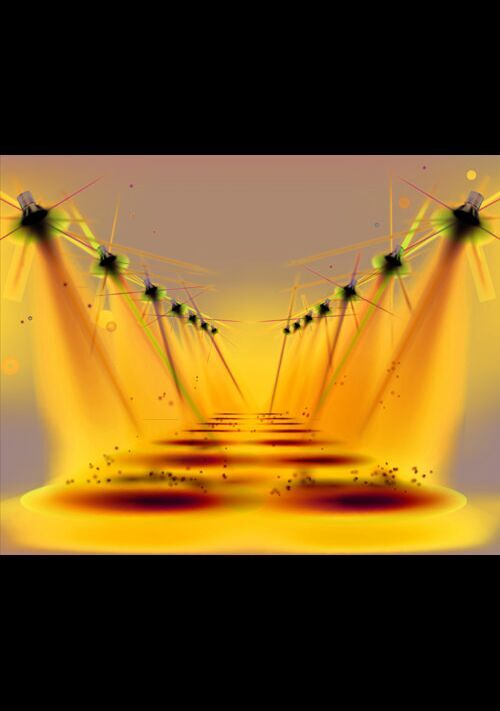
私のなかの、なにか
ちがさき紗季
青春
中学三年生の二月のある朝、川奈莉子の両親は消えた。叔母の曜子に引き取られて、大切に育てられるが、心に刻まれた深い傷は癒えない。そればかりか両親失踪事件をあざ笑う同級生によって、ネットに残酷な書きこみが連鎖し、対人恐怖症になって引きこもる。
やがて自分のなかに芽生える〝なにか〟に気づく莉子。かつては気持ちを満たす幸せの象徴だったそれが、不穏な負の象徴に変化しているのを自覚する。同時に両親が大好きだったビートルズの名曲『Something』を聴くことすらできなくなる。
春が訪れる。曜子の勧めで、独自の教育方針の私立高校に入学。修と咲南に出会い、音楽を通じてどこかに生きているはずの両親に想いを届けようと考えはじめる。
大学一年の夏、莉子は修と再会する。特別な歌声と特異の音域を持つ莉子の才能に気づいていた修の熱心な説得により、ふたたび歌うようになる。その後、修はネットの音楽配信サービスに楽曲をアップロードする。間もなく、二人の世界が動きはじめた。
大手レコード会社の新人発掘プロデューサー澤と出会い、修とともにライブに出演する。しかし、両親の失踪以来、莉子のなかに巣食う不穏な〝なにか〟が膨張し、大勢の観客を前にしてパニックに陥り、倒れてしまう。それでも奮起し、ぎりぎりのメンタルで歌いつづけるものの、さらに難題がのしかかる。音楽フェスのオープニングアクトの出演が決定した。直後、おぼろげに悟る両親の死によって希望を失いつつあった莉子は、プレッシャーからついに心が折れ、プロデビューを辞退するも、曜子から耳を疑う内容の電話を受ける。それは、両親が生きている、という信じがたい話だった。
歌えなくなった莉子は、葛藤や混乱と闘いながら――。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















