14 / 23
第三章 髪切り
.
しおりを挟む
八、
翌朝、布団に与四郎の姿は無かった。
どうやら、作業場にいるらしかった。
お沙は、よく眠れずに夜を過ごした。
――与四郎のあの言葉を信じるべきか
〝お京ちゃんを殺したのはおれなんだ〟
低い与四郎の声が、耳の中でわだかまっている。
吉原炎上のあの晩、本当に与四郎がお京を殺した犯人だったら、あの血だらけの両の手の理由も判る。
だが、信じたくない。
与四郎が人殺しだなんて思いたくない。
筆づくりに疲れ、妄言を言っているのかもしれない。
自分でも、お京を手にかけたのは与四郎かもしれないと疑ったことはあった。
それでも、与四郎を信じて疑いを持った己を責めた。
お沙は、寝間着のまま、与四郎の作業場を覗いた。
薄暗いなかで、与四郎は作業をしている。
「与四郎さん――」
背中へ、そっと声をかける。
声に反応して、与四郎は振り返った。
「どうした、お沙。そんな寝間着のままで、はしたないぞ」
穏やかに言う与四郎。
「あの、昨晩――」
訊くのが怖い。
怖いが訊く。
もし本当に与四郎が犯人だったら。
このまま知らずにいられたら。
でも、訊く。
「昨晩の話、覚えてますか」
「昨晩?」
与四郎は首を傾げる。
「なにか話したか、昨晩」
「え、覚えていないのですか」
「すまんなぁ。太助と遊んで疲れてしまったのか、すぐに寝ちまったと思うが――」
与四郎は、妻の顔を不思議そうに見つめる。
「では、なにも覚えていないと‥‥」
「あぁ――すまん」
申し訳なさそうに笑む。
どれが妄言だろう。
昨晩の話か、いまの話か。
どれを信じたらよいのか。
「どうした、お沙。おれは、なにか大事なことを言ったか?」
「あの、いえ、なんでもありません。お仕事の邪魔をしてしまって、すみませんでした」
「いや、構わん――お沙、疲れているようだからすこし休みなさい」
夫の優しい言葉。
だが、いまのお沙には、この言葉でも妄言に聴こえてしまう。
この日のお沙は、心ここにあらず、といった感じであった。
家事は業務的にこなすが、眼は常にぼんやりと宙を彷徨っていた。
すこし前の、忍のような状態――
与四郎が心配して声をかけても、
「平気です――」
と、足をふらつかせながら、家事をこなしてゆく。
昼を過ぎ、もうすぐ夕陽が射し込もうという頃、太助が夫婦の長屋を訪ねた。
「ねぇねぇ、昨日は飴を買ってくれなかったでしょ」
天秤棒を担ぎ、にこにこと言う。
「あ――そうだったか」
たまたま外に居た与四郎が太助の相手をした。
「そうだよ! 筆を見せてもらったし、お沙さんがお茶を淹れてくれたけど、おいらの飴は買ってくれなかった!」
ぷく、と両頬を膨らませる。
その様子がなんとも可愛くて与四郎は微笑する。
「そうかそうか、悪かったな。じゃあ、ひとつもらおうか」
「お沙さんの分は?」
太助が言う。
「え?」
「おじちゃんとお沙さんの分」
「まいったな」
与四郎は苦笑する。
「じゃあ、ふたつもらおう」
「ありがとう!」
「なぁ、どうせならおじちゃんじゃなくて、おれのことも名前で呼びな。与四郎ってんだ」
「おじちゃんはおじちゃんだよ」
与四郎は頬を緩ませ、太助の頭をぽんぽんと軽く叩く。
「―――」
太助の頭を叩く与四郎の手が止まる。
叩くのをやめて、掌で髪を撫でまわす。
「おじちゃん、くすぐったいよ!」
太助の髪は、髷を充分に結える長さが無いため、頭のうしろで小さく結っている。
与四郎の顔つきが真剣になる。
「おじちゃん? 飴を買ってくれるんでしょ?」
太助が与四郎の袖を引っぱる。
「あ、あぁ――そうだったな。飴な」
「おいらの頭、なにかあるの?」
「いや――」
与四郎は太助の眼を見つめ、
「太助、ちょっとおじちゃんに協力してくれないか」
静かに言った。
「ねぇ、買ってくれるんでしょ、飴」
太助は薄暗い作業場に来ていた。
なにやら刃物がたくさんある。
この作業場なら昨日も訪れているが、いま改めて見ると、どうも怖い。
与四郎は太助を適当に座らせた。
「太助、お願いがあるんだ」
「なに?」
「髪をくれないか?」
「え? なに言ってるの?」
「おじちゃんはね、髪が欲しいんだ」
「どうして?」
「どうしてだろうね」
「おいらの髪なんかどうするの? 髪を欲しがる人なんて初めて見た!」
「初めてでもなんでもいい。おれは髪が欲しい。――おじちゃんにくれるね?」
「おじちゃん、どうしたの、なんだか‥‥怖いよ」
太助の言葉と同時に、与四郎は太助の襟首をつかんだ。
「わっ! なにするの!」
暴れる太助に、与四郎は懐から錆びた鋏を取り出して、そのやわらかな頬にあてる。
鋏は、お京を刺した時のものだった。
まだ血がこびりついている。
太助は、恐怖に顔をひきつらせ、声を出せないでいる。
「おとなしくしていれば、そんなに痛くしないで済むから」
太助の耳許で囁く。
少年の眼に、涙が溜まる。
そして、頬を伝う。
鼻水が垂れ、恐怖で喰いしばった歯の間から涎が流れる。
そのうちに、歯が次第にがちがちと鳴る。
与四郎の優しい声音が、太助の恐怖を掻き立てる。
「う‥‥あ‥‥あぁ‥‥」
声にならない。
涙やら鼻水やら体液が、ぼたぼたと垂れ、太助の着物を濡らす。
「おじちゃんは困ってるんだ。君みたいに飴を売って生活できれば楽なもんだよ」
「やめ、やめてよ‥‥やめて、おじちゃ‥‥」
咽の奥から声を絞り出す。
「なあに、聴こえないなぁ」
太助は細い手足をじたばたさせて抵抗するが、当然のように大人の力には敵わない。
頬には鋏をあてられている。妙な動きをすれば、どうなるのかは、この十歳の少年でも判る。
その時、作業場の戸口からお沙が顔を覗かせた。
「履物があるけど、太助ちゃん来ているの?」
「お沙さん!」
お沙の声と同時に太助が叫ぶ。
しかし、与四郎が、鋏を持った手に力を入れた。
やわい肌に傷がつき、血が滲む。
「なにしてるの!」
眼の前の光景に、お沙は声を荒げる。
太助は両の眼を大きく見開くだけで声が出せない。涙や涎、鼻水は絶えず垂れ流れる。
「――お沙か」
与四郎がゆっくりと振り返る。
「与四郎さん。なにをしてるの、太助ちゃんになにを――」
太助の襟首をつかむ手。
頬にあてられた鋏。
小さく呻く太助。
――与四郎はなにをしようとしている?
「太助に協力してもらおうと思って」
与四郎は、据わった眼で妻を見つめる。
「協力‥‥?」
「おれはいま、髪が欲しいんだ。男の髪では使いものにならないし、女のものだって、そう簡単には手に入らない。困っているんだよ。判るだろう?」
「だからって、どうして太助ちゃんを‥‥」
「この小僧の髪は質が良い。男だが、子どもの髪は、女の髪と変わらぬ柔らかさがあるみたいでね」
「――その鋏はなんですか」
お沙は慎重に与四郎に投げかける。
なにがきっかけで、与四郎を行動させてしまうか判らない。
依然、太助の頬には鋏があてがわれたまま。
血も流れ続けている。
「髪以外の方法を見つけましょう、与四郎さん」
「おれは髪が良いんだ。確かに、吉井がいままで調達してくれていたものは素晴らしかった。だが、人間の体の一部で筆がつくられるなんてすごいと思わないか?」
まばたきをせずに、淡々と語る。
「おれがつくる髪の筆はな、生きているんだよ。生きて話しかけてくれるんだ。ほら、そこにある――」
顎で、作業台を指す。
作業台は、与四郎とお沙の間に置かれている。作業台の上には、一本の新しい筆がある。
「その筆だって、ずっと泣き叫んでいるんだ」
「泣き叫ぶ? どうして」
「お京の髪でつくったからだよ」
「―――」
お沙は驚きで声が出なかった。
やはり、昨晩の話は本当だった――
「お京はおれのことを人殺しと呼んで逃げまわったよ」
「ひと、ごろし‥‥?」
お沙は混乱する。
なにを言われているのかが判らない。
「理解できていないようだね、お沙」
与四郎は、妻の顔を見て微笑する。
「‥‥‥」
「お沙が、いま絵を入れている筆は、観月という遊女の髪で出来ている。――その遊女は火事で死んだ。おれの眼の前で死んだ。おれが殺したも同然だ」
「火事で亡くなったのでしょう? 与四郎さんのせいではないのでは――」
「おれは、あの場で観月さんを救うことができたはずだ。それをしなかった。だから、観月さんは‥‥おれが殺したも同然なんだ」
与四郎の瞳が陰る。
そして、与四郎はそのまま続ける。
「お京ちゃんは、確実におれが殺した。お京ちゃんの背中にこの鋏を突き立てたのは、おれだ」
「どうして――」
お沙は、知らずのうちに涙をこぼしていた。
「殺したくて殺したわけじゃない。お京は殺されてしまったんだ、おれのこの手にかかって」
「どうして殺されてしまったの、どうして」
「おれを人殺し呼ばわりしたからだ」
ぼそりと言った。
「おれを人殺し呼ばわりしたからだ!」
ひとつ大きく叫ぶ。
「ひっ‥‥!」
その大声に驚いて、太助が小さく啼いた。
それを聴いて、与四郎はぎろりと太助を睨む。
太助の頬にあてがっていた鋏を大きく振りあげた。
「やめて!」
お沙は咄嗟に動いて、与四郎のその手首を両の手でつかんだ。
「なぜだ?」
無機質な声で訊く。
「なぜって‥‥これ以上、殺さないで!」
「おれはもうふたりも殺しているんだ。ガキひとり手にかけるくらい、変わらないだろう」
「本気で言ってるの⁉」
与四郎の手首を両の手でつかんでいるが、やはり、男の力には敵わない。
「放せ!」
与四郎は、つかまれている腕に力を入れ、お沙の手を払う。
それでもお沙は、与四郎の手にすがり、なんとか阻止しようとする。
「だめです! もうやめて!」
「お沙! 放せ!」
このふたりのやりとりの間に、太助は恐怖で気を失ってしまった。
がくり、と太助の身体がだれ、重くなる。
与四郎は、太助の様子に気がつき、そちらに気をやっているうちにお沙が掌で鋏を払った。
鋏は宙を飛び、地に落ちる。
「あっ」
お沙はそのまま、与四郎の手をぎゅっと握った。
「やめてください」
与四郎の眼をまっすぐ見つめる。
「‥‥‥」
与四郎は呼吸を落ち着かせ、左手でつかんでいた太助の襟首を放した。
太助の身体は、ごろりと床に転げる。
「う‥‥」
太助は小さく呻いた。
お沙は、与四郎の手を放して、すぐに太助を抱き起こした。
太助の小さな頭をぎゅっと胸に抱え、
「この子は悪くありません。この子は関係ないでしょう」
涙をこぼした。
「―――」
与四郎は呆然と立ちつくす。
「そんなに髪に執着するなら、わたしの髪を差しあげます。それでよいでしょう」
「それはだめだ! それはならん!」
与四郎は声を大きくした。
「髪が欲しいのであれば、わたしのものをお使いください」
涙で声が濡れる。
「それはだめだ。絶対に許さない」
与四郎の厳しい声。
「どうして、そこまで‥‥もうやめてください」
「いやだ。髪でつくる。だが、お沙の髪は絶対に使わない」
譲らない。与四郎はひとつ息を吐き、
「おれの筆づくりは変わらん」
「わたしの髪を使わないと言うのなら、太助ちゃんのことも傷つけないと、約束してください」
お沙の心からの訴えに、与四郎は黙してその場に座り込んだ。
翌朝、布団に与四郎の姿は無かった。
どうやら、作業場にいるらしかった。
お沙は、よく眠れずに夜を過ごした。
――与四郎のあの言葉を信じるべきか
〝お京ちゃんを殺したのはおれなんだ〟
低い与四郎の声が、耳の中でわだかまっている。
吉原炎上のあの晩、本当に与四郎がお京を殺した犯人だったら、あの血だらけの両の手の理由も判る。
だが、信じたくない。
与四郎が人殺しだなんて思いたくない。
筆づくりに疲れ、妄言を言っているのかもしれない。
自分でも、お京を手にかけたのは与四郎かもしれないと疑ったことはあった。
それでも、与四郎を信じて疑いを持った己を責めた。
お沙は、寝間着のまま、与四郎の作業場を覗いた。
薄暗いなかで、与四郎は作業をしている。
「与四郎さん――」
背中へ、そっと声をかける。
声に反応して、与四郎は振り返った。
「どうした、お沙。そんな寝間着のままで、はしたないぞ」
穏やかに言う与四郎。
「あの、昨晩――」
訊くのが怖い。
怖いが訊く。
もし本当に与四郎が犯人だったら。
このまま知らずにいられたら。
でも、訊く。
「昨晩の話、覚えてますか」
「昨晩?」
与四郎は首を傾げる。
「なにか話したか、昨晩」
「え、覚えていないのですか」
「すまんなぁ。太助と遊んで疲れてしまったのか、すぐに寝ちまったと思うが――」
与四郎は、妻の顔を不思議そうに見つめる。
「では、なにも覚えていないと‥‥」
「あぁ――すまん」
申し訳なさそうに笑む。
どれが妄言だろう。
昨晩の話か、いまの話か。
どれを信じたらよいのか。
「どうした、お沙。おれは、なにか大事なことを言ったか?」
「あの、いえ、なんでもありません。お仕事の邪魔をしてしまって、すみませんでした」
「いや、構わん――お沙、疲れているようだからすこし休みなさい」
夫の優しい言葉。
だが、いまのお沙には、この言葉でも妄言に聴こえてしまう。
この日のお沙は、心ここにあらず、といった感じであった。
家事は業務的にこなすが、眼は常にぼんやりと宙を彷徨っていた。
すこし前の、忍のような状態――
与四郎が心配して声をかけても、
「平気です――」
と、足をふらつかせながら、家事をこなしてゆく。
昼を過ぎ、もうすぐ夕陽が射し込もうという頃、太助が夫婦の長屋を訪ねた。
「ねぇねぇ、昨日は飴を買ってくれなかったでしょ」
天秤棒を担ぎ、にこにこと言う。
「あ――そうだったか」
たまたま外に居た与四郎が太助の相手をした。
「そうだよ! 筆を見せてもらったし、お沙さんがお茶を淹れてくれたけど、おいらの飴は買ってくれなかった!」
ぷく、と両頬を膨らませる。
その様子がなんとも可愛くて与四郎は微笑する。
「そうかそうか、悪かったな。じゃあ、ひとつもらおうか」
「お沙さんの分は?」
太助が言う。
「え?」
「おじちゃんとお沙さんの分」
「まいったな」
与四郎は苦笑する。
「じゃあ、ふたつもらおう」
「ありがとう!」
「なぁ、どうせならおじちゃんじゃなくて、おれのことも名前で呼びな。与四郎ってんだ」
「おじちゃんはおじちゃんだよ」
与四郎は頬を緩ませ、太助の頭をぽんぽんと軽く叩く。
「―――」
太助の頭を叩く与四郎の手が止まる。
叩くのをやめて、掌で髪を撫でまわす。
「おじちゃん、くすぐったいよ!」
太助の髪は、髷を充分に結える長さが無いため、頭のうしろで小さく結っている。
与四郎の顔つきが真剣になる。
「おじちゃん? 飴を買ってくれるんでしょ?」
太助が与四郎の袖を引っぱる。
「あ、あぁ――そうだったな。飴な」
「おいらの頭、なにかあるの?」
「いや――」
与四郎は太助の眼を見つめ、
「太助、ちょっとおじちゃんに協力してくれないか」
静かに言った。
「ねぇ、買ってくれるんでしょ、飴」
太助は薄暗い作業場に来ていた。
なにやら刃物がたくさんある。
この作業場なら昨日も訪れているが、いま改めて見ると、どうも怖い。
与四郎は太助を適当に座らせた。
「太助、お願いがあるんだ」
「なに?」
「髪をくれないか?」
「え? なに言ってるの?」
「おじちゃんはね、髪が欲しいんだ」
「どうして?」
「どうしてだろうね」
「おいらの髪なんかどうするの? 髪を欲しがる人なんて初めて見た!」
「初めてでもなんでもいい。おれは髪が欲しい。――おじちゃんにくれるね?」
「おじちゃん、どうしたの、なんだか‥‥怖いよ」
太助の言葉と同時に、与四郎は太助の襟首をつかんだ。
「わっ! なにするの!」
暴れる太助に、与四郎は懐から錆びた鋏を取り出して、そのやわらかな頬にあてる。
鋏は、お京を刺した時のものだった。
まだ血がこびりついている。
太助は、恐怖に顔をひきつらせ、声を出せないでいる。
「おとなしくしていれば、そんなに痛くしないで済むから」
太助の耳許で囁く。
少年の眼に、涙が溜まる。
そして、頬を伝う。
鼻水が垂れ、恐怖で喰いしばった歯の間から涎が流れる。
そのうちに、歯が次第にがちがちと鳴る。
与四郎の優しい声音が、太助の恐怖を掻き立てる。
「う‥‥あ‥‥あぁ‥‥」
声にならない。
涙やら鼻水やら体液が、ぼたぼたと垂れ、太助の着物を濡らす。
「おじちゃんは困ってるんだ。君みたいに飴を売って生活できれば楽なもんだよ」
「やめ、やめてよ‥‥やめて、おじちゃ‥‥」
咽の奥から声を絞り出す。
「なあに、聴こえないなぁ」
太助は細い手足をじたばたさせて抵抗するが、当然のように大人の力には敵わない。
頬には鋏をあてられている。妙な動きをすれば、どうなるのかは、この十歳の少年でも判る。
その時、作業場の戸口からお沙が顔を覗かせた。
「履物があるけど、太助ちゃん来ているの?」
「お沙さん!」
お沙の声と同時に太助が叫ぶ。
しかし、与四郎が、鋏を持った手に力を入れた。
やわい肌に傷がつき、血が滲む。
「なにしてるの!」
眼の前の光景に、お沙は声を荒げる。
太助は両の眼を大きく見開くだけで声が出せない。涙や涎、鼻水は絶えず垂れ流れる。
「――お沙か」
与四郎がゆっくりと振り返る。
「与四郎さん。なにをしてるの、太助ちゃんになにを――」
太助の襟首をつかむ手。
頬にあてられた鋏。
小さく呻く太助。
――与四郎はなにをしようとしている?
「太助に協力してもらおうと思って」
与四郎は、据わった眼で妻を見つめる。
「協力‥‥?」
「おれはいま、髪が欲しいんだ。男の髪では使いものにならないし、女のものだって、そう簡単には手に入らない。困っているんだよ。判るだろう?」
「だからって、どうして太助ちゃんを‥‥」
「この小僧の髪は質が良い。男だが、子どもの髪は、女の髪と変わらぬ柔らかさがあるみたいでね」
「――その鋏はなんですか」
お沙は慎重に与四郎に投げかける。
なにがきっかけで、与四郎を行動させてしまうか判らない。
依然、太助の頬には鋏があてがわれたまま。
血も流れ続けている。
「髪以外の方法を見つけましょう、与四郎さん」
「おれは髪が良いんだ。確かに、吉井がいままで調達してくれていたものは素晴らしかった。だが、人間の体の一部で筆がつくられるなんてすごいと思わないか?」
まばたきをせずに、淡々と語る。
「おれがつくる髪の筆はな、生きているんだよ。生きて話しかけてくれるんだ。ほら、そこにある――」
顎で、作業台を指す。
作業台は、与四郎とお沙の間に置かれている。作業台の上には、一本の新しい筆がある。
「その筆だって、ずっと泣き叫んでいるんだ」
「泣き叫ぶ? どうして」
「お京の髪でつくったからだよ」
「―――」
お沙は驚きで声が出なかった。
やはり、昨晩の話は本当だった――
「お京はおれのことを人殺しと呼んで逃げまわったよ」
「ひと、ごろし‥‥?」
お沙は混乱する。
なにを言われているのかが判らない。
「理解できていないようだね、お沙」
与四郎は、妻の顔を見て微笑する。
「‥‥‥」
「お沙が、いま絵を入れている筆は、観月という遊女の髪で出来ている。――その遊女は火事で死んだ。おれの眼の前で死んだ。おれが殺したも同然だ」
「火事で亡くなったのでしょう? 与四郎さんのせいではないのでは――」
「おれは、あの場で観月さんを救うことができたはずだ。それをしなかった。だから、観月さんは‥‥おれが殺したも同然なんだ」
与四郎の瞳が陰る。
そして、与四郎はそのまま続ける。
「お京ちゃんは、確実におれが殺した。お京ちゃんの背中にこの鋏を突き立てたのは、おれだ」
「どうして――」
お沙は、知らずのうちに涙をこぼしていた。
「殺したくて殺したわけじゃない。お京は殺されてしまったんだ、おれのこの手にかかって」
「どうして殺されてしまったの、どうして」
「おれを人殺し呼ばわりしたからだ」
ぼそりと言った。
「おれを人殺し呼ばわりしたからだ!」
ひとつ大きく叫ぶ。
「ひっ‥‥!」
その大声に驚いて、太助が小さく啼いた。
それを聴いて、与四郎はぎろりと太助を睨む。
太助の頬にあてがっていた鋏を大きく振りあげた。
「やめて!」
お沙は咄嗟に動いて、与四郎のその手首を両の手でつかんだ。
「なぜだ?」
無機質な声で訊く。
「なぜって‥‥これ以上、殺さないで!」
「おれはもうふたりも殺しているんだ。ガキひとり手にかけるくらい、変わらないだろう」
「本気で言ってるの⁉」
与四郎の手首を両の手でつかんでいるが、やはり、男の力には敵わない。
「放せ!」
与四郎は、つかまれている腕に力を入れ、お沙の手を払う。
それでもお沙は、与四郎の手にすがり、なんとか阻止しようとする。
「だめです! もうやめて!」
「お沙! 放せ!」
このふたりのやりとりの間に、太助は恐怖で気を失ってしまった。
がくり、と太助の身体がだれ、重くなる。
与四郎は、太助の様子に気がつき、そちらに気をやっているうちにお沙が掌で鋏を払った。
鋏は宙を飛び、地に落ちる。
「あっ」
お沙はそのまま、与四郎の手をぎゅっと握った。
「やめてください」
与四郎の眼をまっすぐ見つめる。
「‥‥‥」
与四郎は呼吸を落ち着かせ、左手でつかんでいた太助の襟首を放した。
太助の身体は、ごろりと床に転げる。
「う‥‥」
太助は小さく呻いた。
お沙は、与四郎の手を放して、すぐに太助を抱き起こした。
太助の小さな頭をぎゅっと胸に抱え、
「この子は悪くありません。この子は関係ないでしょう」
涙をこぼした。
「―――」
与四郎は呆然と立ちつくす。
「そんなに髪に執着するなら、わたしの髪を差しあげます。それでよいでしょう」
「それはだめだ! それはならん!」
与四郎は声を大きくした。
「髪が欲しいのであれば、わたしのものをお使いください」
涙で声が濡れる。
「それはだめだ。絶対に許さない」
与四郎の厳しい声。
「どうして、そこまで‥‥もうやめてください」
「いやだ。髪でつくる。だが、お沙の髪は絶対に使わない」
譲らない。与四郎はひとつ息を吐き、
「おれの筆づくりは変わらん」
「わたしの髪を使わないと言うのなら、太助ちゃんのことも傷つけないと、約束してください」
お沙の心からの訴えに、与四郎は黙してその場に座り込んだ。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

少年少女怪奇譚 〜一位ノ毒~
しょこらあいす
ホラー
これは、「無能でも役に立ちますよ。多分」のヒロインであるジュア・ライフィンが書いたホラー物語集。
ゾッとする本格的な話から物悲しい話まで、様々なものが詰まっています。
――もしかすると、霊があなたに取り憑くかもしれませんよ。
お読みになる際はお気をつけて。
※無能役の本編とは何の関係もありません。
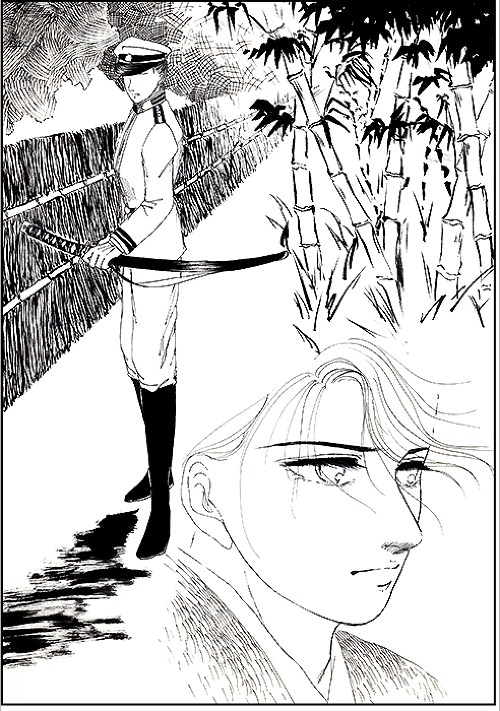
あやかしのうた
akikawa
ホラー
あやかしと人間の孤独な愛の少し不思議な物語を描いた短編集(2編)。
第1部 虚妄の家
「冷たい水底であなたの名を呼んでいた。会いたくて、哀しくて・・・」
第2部 神婚
「一族の総領以外、この儀式を誰も覗き見てはならぬ。」
好奇心おう盛な幼き弟は、その晩こっそりと神の部屋に忍び込み、美しき兄と神との秘密の儀式を覗き見たーーー。
虚空に揺れし君の袖。
汝、何故に泣く?
夢さがなく我愁うれう。
夢通わせた君憎し。
想いとどめし乙女が心の露(なみだ)。
哀しき愛の唄。

肖像
恵喜 どうこ
ホラー
とある主婦が殺害された。彼女を取り巻く被疑者たちの尋問はしかし謎ばかりが深まっていくのである。隣人の男、ママ友、夫、息子、娘。犯人はいったいだれであったのか。主婦はどうして殺されねばならなかったのか。その真相は『藪の中』のごとく、謎のヴェールで覆われていて――
様々な人の様々な人生の恐怖を描いたオムニバス短編。

葬鐘
猫町氷柱
ホラー
とある心霊番組の心霊スポット巡り企画で訪れることになったとある廃墟。
中に入るなり起こる耳鳴り、おかしくなるスタッフ、腐臭。襲いかかる怪異。明らかにまずい状況に退散を命じるAD美空だが消息不明となってしまう。
行方不明になった姉を探しに一人訪れた美海。だが、その時、館内に鐘の音が鳴り響き絶望の歯車が回りだす。襲い掛かる脅威、戦慄の廃墟に姉を見つけ出し無事出られるのか。



AstiMaitrise
椎奈ゆい
ホラー
少女が立ち向かうのは呪いか、大衆か、支配者か______
”学校の西門を通った者は祟りに遭う”
20年前の事件をきっかけに始まった祟りの噂。壇ノ浦学園では西門を通るのを固く禁じる”掟”の元、生徒会が厳しく取り締まっていた。
そんな中、転校生の平等院霊否は偶然にも掟を破ってしまう。
祟りの真相と学園の謎を解き明かすべく、霊否たちの戦いが始まる———!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















