3 / 23
生命が宿るのは、生か、死か。
押入れの秘密 第一話
しおりを挟む
押入れの秘密 第一話
16時15分
俺は人を殺してしまった。きっかけはとても馬鹿馬鹿しくてひょんなことからだった。動かなくなった肉塊は生前俺の彼女であった人物で数十分前までは意気揚々と話し、無邪気な笑顔を見せていたのに、今は白目を剥いて、口から泡を出したまま硬直し、二度と数十分前と同じ顔を見せてくれないのだと思うと後悔の念が後から一気に押し寄せる。しかし後悔して彼女が生き返るかと言われたら無理だ。俺が今しなければならないのはこの元彼女の肉塊をどう処理するか、だ。
今いるのは俺の実家、というか高校生なものだから実家なのは当たり前なのだが。一階には母と父、同階の隣には姉がいる。そして二階から降りて玄関へ向かう廊下を通る際は必ず親がくつろぐリビングを通らなければならない。ということは今俺が元彼女を担いで玄関から外に行こうとするならば親との遭遇は避けられない。二人が起きている間は下手に動くのは得策ではない。
二階にはそのリビングルートを通らなくとも裏出口というものに繋がる廊下がある。しかしそこの裏口ルートを通る際には隣にいる存在の姉の部屋の前を通過することになる。ドアも閉めてるし遭遇しない思うけど万が一遭遇することを考えると裏口ルートもあまり推奨できない。
俺はとりあえず日が暮れるのを待った。今の時間を確認すると針は十六時三十分を指していた。まだまだ時間がかかりそうなことに頭を抱えた。
15時00分
彼女は来た。
確かに来るかもと昨日の学校帰りにちらつかせるように言っていたのは覚えていたが、まさか本当に来るとは思いもしなかった。突然のことに動揺した俺にハロ~と手を振ってみせた。
「マユミさん……本当に来るなんて……」
「どーせ暇なんでしょ、なら私が来ても問題ないよね?」
有無を問わずにズカズカと入って靴を脱ぎ俺の部屋にまっすぐ進んでいく。ちなみにマユミさんは俺の一個上の先輩で出会いは確か同じ部活で話すようになった末、付き合うに至った。いまだに俺自身、さん付けで呼んでいるが彼女は上下の関係とかで区別したくないと言う理由でさん付けを嫌っている。もうそろそろこの癖も治さないと、心の隅でそう考えている。
「へぇ、結構広いんだ」
「勝手にあがんないでくださいよ……というか家どうやって知ったんですか?」
どうやら俺の友達に手当たり次第あたり聞き回ったみたいだ。最初こそ誤魔化そうとしていた彼女にしつこく聞いたらそう白状した。
「なんでそんな回りくどいことを?」
「うーん……君の驚く顔が見たかった。それじゃだめかな?」
いい加減な理由にため息をこぼした。相変わらずっていうか、先輩らしいといえばそうとも言える。
「その理由でいいなら、今回のは大成功だね。君の顔面白かったよ」
クスクスと口に手を当てながら笑いを堪える。彼女の無邪気な笑顔を見た最後の瞬間だった。
17時00分
突然インターフォンの音が一階に鳴り響くのが二階の俺の耳にも届く。びくりと心臓が跳ね上がってその場で立ち上がった。ある痛恨のミスを今思い出した。
「おい、小林くんが来てるぞ」
無視しようと耳に手を当てて声を押し込んだがあまりにも父がドアをしつこく叩くものだから堪らず応答してしまった。
「なんだ、いるじゃないか。小林くんが玄関にいるから行きなさい」
「ああ、わかったから……」
足音が遠のいていく、ひとまず安堵の息をこぼす。しかしすぐに息を呑む。そうだった今日は小林くんから借りていたとあるものを返す日だった。今からそれを玄関にいる小林くんに届けられるのならそうしたいが、この借りていた精密機械は彼しか組み立て方とバラしかたを知らない。そしてバラさないとかなりの重さがあるため階段を降りる時に苦労するだろうな。
「階段……」
階段というワードに胸が閉まる感覚になる。もしあの階段の一部分をすぐ修理していれば……。
「ダメだ、今はこの状況をどうにかしないと」
できる限りのことをしてみようと試行錯誤する。でもアニメや映画、ドラマみたいに上手く死体はいうことを聞かない。運ぼうとするだけで汗が滝のように湧き出てくる。時間をかけすぎると不審に思った親が彼を俺の部屋まで連れて来るかもしれない。
不意にとある場所に目が行く。それはどこの家にもあって使ったことのない人間がいないくらいには馴染んだ、死体を隠すのに特化した場所…………そう、押入れだ。
15時30分
そのあとは適当に時間を潰した。漫画を読んだり、勉強を教えてもらったり、雑談したり。お互い暇つぶしの神だなと感じた。
「じゃあ、私そろそろ帰るね」
「送りましょうか?」
首を横にふり、玄関までで大丈夫と言った。どうせここで突っかかっても頑なに彼女は拒否し続けることを俺は誰よりも知っていた。彼女はそういう人なんだ程度で今まで流している。
「ねえねえ、明日も暇?ならさ、どっかいこーよ」
「暇ですけど……どこか行きたいところでもあるんですか?」
首を少し傾げながら考える人みたく顎に手を当てて考えに耽っていた。案の定まだ何も考えていないようだ。いつもデートという口実を使って俺をいろんな所へ連れていく、でも行く先は唐突でいつも思いついてから向かうという無茶なものだった。俺はそんな彼女についていくのは楽しくて、いつもどこに連れて行ってくれるのだろうとワクワクさせられていた。
「あ、あそこ行きたい」
そういい彼女が俺に向きながら階段を降りようとした時、急に隣にいた彼女が俺の目線から消えた。いや消えたというよりかは、いなくなったという方が正しいか。彼女は階段から落ちたため俺の視線からいなくなったんだ。
叫び声を発することもなく、手を伸ばせば届く位置にいた俺に助けを求めることもできずに、数秒前まで思考を繰り広げていた脳と彼女も魂は、この無機質な木製の段々坂によって奪われた。
「そ、そんな……マユミさん……?」
俺は二階から下にいる彼女を見て、マユミさんは、一階の階段下から恐怖に顔を歪めた俺の哀れな顔を眺めていた。空な、その瞳にはおよそ生きた人間の生命の輝きを灯しておらず、ただひたすらに死の暗闇が広がっていた。
17時15分
「やけに遅かったじゃないですか……何かあったんですか?」
ドアを開けるなり彼は愚痴とも取れない口調だったが微かに苛立ちが混じった声でそういった。確かに彼がインターホンを押してから十五分も立たせっぱなしで外に放り出していたのだから。俺がその立場だったらインターホン連発はするだろう。
「いやあ、ごめんね。ちょっと色々あって」
頭をかきながらいつものテンションで彼に話しかけた。小林くんはここ最近仲良くなった友達だが、やけに勘が鋭くいつも話している時は心の中を見透かされている錯覚に陥る時があるから何も悟られぬようにしなければ。
「はあ、そうですか。僕は別に気にしていませんけど……」
嘘をつけ、と心の中で囁く。しかし彼はさすがというべきか早速ある異変に気がついていたみたいだ。その言葉は確実に俺の心を沈ませた。
「おっと、彼女さんが来ていたんですね。なら僕の存在は邪魔でしたか?」
「え、あ、なんで……気づいたんだ?」
まずい、確実に動揺しているのがバレた。彼はそんな俺は無視して指を刺した。
「この前に来た時にはなかった靴があったので、そしてあの靴は学校指定のレディース靴です。あなたが学校の生徒でさらに女子生徒ということは学校で噂の彼女さんかなと思ったわけです。すみません、余計な詮索をしてしまって」
冷や汗が出る。彼は俺にとっての脅威になりかねないと……そう感じた。
17時50分
彼を部屋に入れて、機械をバラしてもらった。手つきは慣れていて俺には相当手に負えるものではないと感心している心の隅には緊張で今にも跳ね上がりそうな心臓もあった。
「あの……すみません。ドライバーを貸して欲しいんですけどありますか?」
「うん?ああ、あるよ。今とってくる」
そういい、ドアノブを握った時にひとつの最悪の想定が浮かび上がった。それは俺がこの部屋から席を外した時にもしかしたら押し入れに隠した元彼女の死体が彼にバレてしまうのではということ。でも大丈夫、布団に包んで隠したんだ。バレるわけがない。
「どうしたんですか?ないのなら構いませんけど」
「いや、少し考え事を……プラスドライバーでいいかい?」
ええ、と呼吸と間違えてしまうくらい細く呟く。
大丈夫、心の中で連呼し続けながら階段を降りようとした時に一瞬足を止める。危うくマユミさんみたく落ちてしまうところだった。彼女が落ちた要因はこの階段にある。十三段あるうちの十段目にある足元の板がこの前ものを落としたせいで砕けてしまい歪んでいた。ぱっと見ではわからないが、足をそこに置いてみると沼みたいに沈む。俺は日常的なもので避けれるが彼女は今日初めてうちに来たためそんなことわかるわけもない。
そしてもっと厄介なのは、上がる時はその歪みは起きず降りる時の足にかかる重心によって軋むのだ。だから一階そこを登ってしまった人間は安全だと錯覚してしまうところにある。
第一話、終
16時15分
俺は人を殺してしまった。きっかけはとても馬鹿馬鹿しくてひょんなことからだった。動かなくなった肉塊は生前俺の彼女であった人物で数十分前までは意気揚々と話し、無邪気な笑顔を見せていたのに、今は白目を剥いて、口から泡を出したまま硬直し、二度と数十分前と同じ顔を見せてくれないのだと思うと後悔の念が後から一気に押し寄せる。しかし後悔して彼女が生き返るかと言われたら無理だ。俺が今しなければならないのはこの元彼女の肉塊をどう処理するか、だ。
今いるのは俺の実家、というか高校生なものだから実家なのは当たり前なのだが。一階には母と父、同階の隣には姉がいる。そして二階から降りて玄関へ向かう廊下を通る際は必ず親がくつろぐリビングを通らなければならない。ということは今俺が元彼女を担いで玄関から外に行こうとするならば親との遭遇は避けられない。二人が起きている間は下手に動くのは得策ではない。
二階にはそのリビングルートを通らなくとも裏出口というものに繋がる廊下がある。しかしそこの裏口ルートを通る際には隣にいる存在の姉の部屋の前を通過することになる。ドアも閉めてるし遭遇しない思うけど万が一遭遇することを考えると裏口ルートもあまり推奨できない。
俺はとりあえず日が暮れるのを待った。今の時間を確認すると針は十六時三十分を指していた。まだまだ時間がかかりそうなことに頭を抱えた。
15時00分
彼女は来た。
確かに来るかもと昨日の学校帰りにちらつかせるように言っていたのは覚えていたが、まさか本当に来るとは思いもしなかった。突然のことに動揺した俺にハロ~と手を振ってみせた。
「マユミさん……本当に来るなんて……」
「どーせ暇なんでしょ、なら私が来ても問題ないよね?」
有無を問わずにズカズカと入って靴を脱ぎ俺の部屋にまっすぐ進んでいく。ちなみにマユミさんは俺の一個上の先輩で出会いは確か同じ部活で話すようになった末、付き合うに至った。いまだに俺自身、さん付けで呼んでいるが彼女は上下の関係とかで区別したくないと言う理由でさん付けを嫌っている。もうそろそろこの癖も治さないと、心の隅でそう考えている。
「へぇ、結構広いんだ」
「勝手にあがんないでくださいよ……というか家どうやって知ったんですか?」
どうやら俺の友達に手当たり次第あたり聞き回ったみたいだ。最初こそ誤魔化そうとしていた彼女にしつこく聞いたらそう白状した。
「なんでそんな回りくどいことを?」
「うーん……君の驚く顔が見たかった。それじゃだめかな?」
いい加減な理由にため息をこぼした。相変わらずっていうか、先輩らしいといえばそうとも言える。
「その理由でいいなら、今回のは大成功だね。君の顔面白かったよ」
クスクスと口に手を当てながら笑いを堪える。彼女の無邪気な笑顔を見た最後の瞬間だった。
17時00分
突然インターフォンの音が一階に鳴り響くのが二階の俺の耳にも届く。びくりと心臓が跳ね上がってその場で立ち上がった。ある痛恨のミスを今思い出した。
「おい、小林くんが来てるぞ」
無視しようと耳に手を当てて声を押し込んだがあまりにも父がドアをしつこく叩くものだから堪らず応答してしまった。
「なんだ、いるじゃないか。小林くんが玄関にいるから行きなさい」
「ああ、わかったから……」
足音が遠のいていく、ひとまず安堵の息をこぼす。しかしすぐに息を呑む。そうだった今日は小林くんから借りていたとあるものを返す日だった。今からそれを玄関にいる小林くんに届けられるのならそうしたいが、この借りていた精密機械は彼しか組み立て方とバラしかたを知らない。そしてバラさないとかなりの重さがあるため階段を降りる時に苦労するだろうな。
「階段……」
階段というワードに胸が閉まる感覚になる。もしあの階段の一部分をすぐ修理していれば……。
「ダメだ、今はこの状況をどうにかしないと」
できる限りのことをしてみようと試行錯誤する。でもアニメや映画、ドラマみたいに上手く死体はいうことを聞かない。運ぼうとするだけで汗が滝のように湧き出てくる。時間をかけすぎると不審に思った親が彼を俺の部屋まで連れて来るかもしれない。
不意にとある場所に目が行く。それはどこの家にもあって使ったことのない人間がいないくらいには馴染んだ、死体を隠すのに特化した場所…………そう、押入れだ。
15時30分
そのあとは適当に時間を潰した。漫画を読んだり、勉強を教えてもらったり、雑談したり。お互い暇つぶしの神だなと感じた。
「じゃあ、私そろそろ帰るね」
「送りましょうか?」
首を横にふり、玄関までで大丈夫と言った。どうせここで突っかかっても頑なに彼女は拒否し続けることを俺は誰よりも知っていた。彼女はそういう人なんだ程度で今まで流している。
「ねえねえ、明日も暇?ならさ、どっかいこーよ」
「暇ですけど……どこか行きたいところでもあるんですか?」
首を少し傾げながら考える人みたく顎に手を当てて考えに耽っていた。案の定まだ何も考えていないようだ。いつもデートという口実を使って俺をいろんな所へ連れていく、でも行く先は唐突でいつも思いついてから向かうという無茶なものだった。俺はそんな彼女についていくのは楽しくて、いつもどこに連れて行ってくれるのだろうとワクワクさせられていた。
「あ、あそこ行きたい」
そういい彼女が俺に向きながら階段を降りようとした時、急に隣にいた彼女が俺の目線から消えた。いや消えたというよりかは、いなくなったという方が正しいか。彼女は階段から落ちたため俺の視線からいなくなったんだ。
叫び声を発することもなく、手を伸ばせば届く位置にいた俺に助けを求めることもできずに、数秒前まで思考を繰り広げていた脳と彼女も魂は、この無機質な木製の段々坂によって奪われた。
「そ、そんな……マユミさん……?」
俺は二階から下にいる彼女を見て、マユミさんは、一階の階段下から恐怖に顔を歪めた俺の哀れな顔を眺めていた。空な、その瞳にはおよそ生きた人間の生命の輝きを灯しておらず、ただひたすらに死の暗闇が広がっていた。
17時15分
「やけに遅かったじゃないですか……何かあったんですか?」
ドアを開けるなり彼は愚痴とも取れない口調だったが微かに苛立ちが混じった声でそういった。確かに彼がインターホンを押してから十五分も立たせっぱなしで外に放り出していたのだから。俺がその立場だったらインターホン連発はするだろう。
「いやあ、ごめんね。ちょっと色々あって」
頭をかきながらいつものテンションで彼に話しかけた。小林くんはここ最近仲良くなった友達だが、やけに勘が鋭くいつも話している時は心の中を見透かされている錯覚に陥る時があるから何も悟られぬようにしなければ。
「はあ、そうですか。僕は別に気にしていませんけど……」
嘘をつけ、と心の中で囁く。しかし彼はさすがというべきか早速ある異変に気がついていたみたいだ。その言葉は確実に俺の心を沈ませた。
「おっと、彼女さんが来ていたんですね。なら僕の存在は邪魔でしたか?」
「え、あ、なんで……気づいたんだ?」
まずい、確実に動揺しているのがバレた。彼はそんな俺は無視して指を刺した。
「この前に来た時にはなかった靴があったので、そしてあの靴は学校指定のレディース靴です。あなたが学校の生徒でさらに女子生徒ということは学校で噂の彼女さんかなと思ったわけです。すみません、余計な詮索をしてしまって」
冷や汗が出る。彼は俺にとっての脅威になりかねないと……そう感じた。
17時50分
彼を部屋に入れて、機械をバラしてもらった。手つきは慣れていて俺には相当手に負えるものではないと感心している心の隅には緊張で今にも跳ね上がりそうな心臓もあった。
「あの……すみません。ドライバーを貸して欲しいんですけどありますか?」
「うん?ああ、あるよ。今とってくる」
そういい、ドアノブを握った時にひとつの最悪の想定が浮かび上がった。それは俺がこの部屋から席を外した時にもしかしたら押し入れに隠した元彼女の死体が彼にバレてしまうのではということ。でも大丈夫、布団に包んで隠したんだ。バレるわけがない。
「どうしたんですか?ないのなら構いませんけど」
「いや、少し考え事を……プラスドライバーでいいかい?」
ええ、と呼吸と間違えてしまうくらい細く呟く。
大丈夫、心の中で連呼し続けながら階段を降りようとした時に一瞬足を止める。危うくマユミさんみたく落ちてしまうところだった。彼女が落ちた要因はこの階段にある。十三段あるうちの十段目にある足元の板がこの前ものを落としたせいで砕けてしまい歪んでいた。ぱっと見ではわからないが、足をそこに置いてみると沼みたいに沈む。俺は日常的なもので避けれるが彼女は今日初めてうちに来たためそんなことわかるわけもない。
そしてもっと厄介なのは、上がる時はその歪みは起きず降りる時の足にかかる重心によって軋むのだ。だから一階そこを登ってしまった人間は安全だと錯覚してしまうところにある。
第一話、終
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
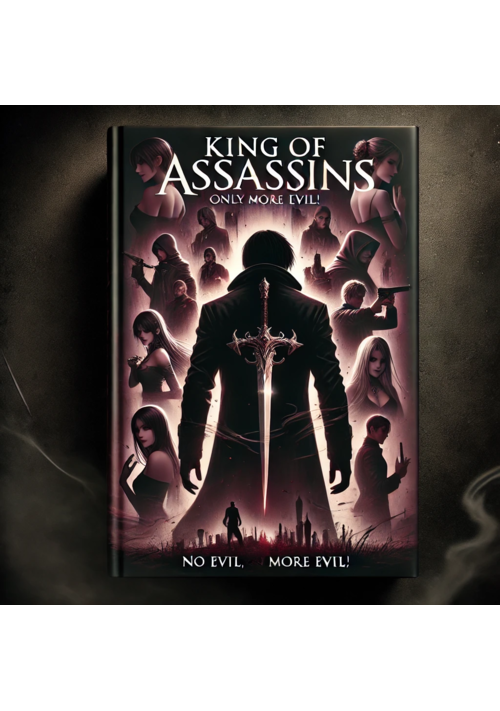


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















