19 / 46
第19話
しおりを挟む
「でもさ、こういう動き、俺たちがマックスやキャスを護りに入るのも別室は織り込み済みなんだろうな?」
「悪いけど、おそらく別室戦術コンは予測済みだろうね。そもそもいつまでマックスたちが逃げ続けられるか……体制側ならまだマシだけど連続爆破側に捕まって、それも警察官だって知られたら、それこそ拷問されて見せしめに処刑されかねないよ」
元スパイは最悪から二番目の手で生き延びてきたかのようなことばかり言い、うんざりしかけたシドは自分たちの役どころへと視点を変えた。
「テロリスト側が動きを見せてマックスたちを捕らえる、その寸前に別室はドラクロワたちの身柄を押さえるつもりなんだろ。それまでのカウンタ手段として俺たちがいる……そんなとこなんだろうな、今回は」
「そういう嵌り方でいいのかなあ?。でもマックスがあんなに出頭を拒むとは思わなかったし、何よりキャスが心配。……んっ、そんな触り方しないでよ。その気になっちゃう」
「何もしてねぇって、お前、感じやす過ぎ。……しかし、マックスがヴィクトル星系出身とか、初めて聞いたぜ。ガキの頃は結構何でも話してたのにさ」
幼馴染みだからこそ、愉しい時を一緒に過ごしている間は、出身星系の酷い有り様を口に出したくなかったのかとハイファは思う。
「何もかもを知らせ合わなきゃ、友達じゃない、なんて言えないでしょ」
「まあな、言いたくねぇほど酷かったのか。それを逆手に取った別室が何より酷いよな。実際に出たとされた二十人分の死体、心当たりは一分署と二分署の爆破被害者くらいだ。別室囮作戦に従事しただろう軍の奴らも、暫くいい夢は視られないだろうぜ」
そこでシドは『良い夢を』と言ったフォッカー=リンデマン一等特務技官を思い出す。
今回の別室が立案した作戦で自分たちがマックスたちを逃げ回らせるための護衛官という立場ならば、あのサイキ持ちこそ、その『チーム』の筆頭であるべきではないのか。なのに自分たちはチームとしての『唯一の縛り』すら破らざるを得なくなっている。
「おい、フォッカーのサイキって何なんだ?」
小声でハイファに訊いたが返事は規則正しい寝息だった。
◇◇◇◇
僅かにとろとろと眠ったかと思えばもうリモータのアラームが起動し、着替えてレストランでもそもそ朝食を摂ってから何食わぬ顔で出勤した。
本星セントラルの七分署での扱いとは違うので、朝八時半から十七時半までの間、殆どずっとデカ部屋で待機していなければならない。
ある者はTVニュースを視、ある者は書類整理をし、またある者は過去の事件記録などのファイルを読みふけって過ごす。一班十人前後が二班態勢で事件が起こりませんようにと願いながら時間が経つのをひたすら待つのだ。
こうしてヒマを持て余している間もマックスとキャスが気に掛かるシドだったが、誰に聞かれるとも限らないので口にはしない。
問題は課業終了後に歓楽街へと向かう時だろうと思っていた。
仮配属早々に始末書を提出したシドとハイファは署内で話題の人物であり、もっと話題である消えたマックスたちと親しかったことも当然知られている。
ほぼ確実につくであろう尾行を撒いた時点で、余程上手く立ち回らねば自分たちも断罪される運命だ。別にそれが怖い訳ではないが四人揃ってお縄になり一分署ごと爆破は頂けない。
ようやく昼になったが二階の簡易食堂は人数に対して小さすぎ、それぞれの部署が時間差で食べに行くよう決められていた。
指示された時間に食堂へ行きハイファと横並びでトレイに載ったものを片付けていると、他に席は空いているのにわざわざ真向かいに同じ班の男二人が陣取った。確かアリステア=ナッシュとユーイン=オライリーなる名だったと記憶している。
「せっかく偶然集った仲間が減って淋しいですよね、ワカミヤ巡査部長」
中年のアリステアがどう善意に解釈しても含みある口調で話しかけてきた。
「始末書付きでも金星、制式拳銃でもない私物銃の携帯許可、友人は手に手を取ってエスケープ。色々と貴方の周りは特別が多いようですな」
こちらもテラ標準歴で三十代中盤のユーインが続ける。
どうにも不味い飯になりそうだと思いながらもシドとハイファは澄ました顔で食事を続行した。こういう手合いにはどう返事をしても無駄、それに後ろ暗いのは事実でネタの端緒を与えかねない会話は避けるべきだった。
「あの絢爛豪華な総監賞、おまけに色男の貴方と美人のバディ、目立ってますよ」
制服の時から見られていた上にこいつらが張りつくと思うとシドはげんなりする。
粘り強い刑事というのは褒め言葉だが、こいつらのはネチこいと分類したくなる、好きになれない話しぶりだ。それが今日のシドとハイファの見張り番だと、自分たちの知らないうちに決められたらしい。
表在署の今は帰っても自宅待機だ、出掛けるだけでも余計な問題を抱える。厄介なことになりそうだった。たった一日で、もう腹を括るしかないかも知れない。
結局、「お先に」とだけ挨拶をしてシドはハイファと食堂を出た。
仮のデカ部屋に戻るとヒマもまた戻ってくる。アリステアとユーインの二人もまもなく戻ってきたが、シドはデスクで頬杖をついて寝たフリでやり過ごした。
そのうち本気で眠ってしまいカードゲームで盛り上がる声に起こされた時には二時間が経とうとしていて少々驚く。
「コーヒー飲む?」
頷くとハイファは備え付けのコーヒーメーカから注いだ紙コップふたつを持ってきた。ひとつを受け取り啜ってみたが、いずこも同じ懐かしき泥水だ。
「さっき、フォッカー特務技官からまた発信があったよ。お手洗いで返した」
「で、何だって?」
「前と同じだよ。何もないかって、それだけ。こっちも同じように返して、でもマックスとキャスが逃げて行方不明だってことは知ってたみたい。出頭させる方向で惑星警察としては動いてるって誤魔化しといたけど……いいのかな?」
「いいも何も、俺たちは実際通常勤務してるし、マックスが頷けば連れてくるしな」
「でも、じつはシドもちょっと迷ってるでしょ? フォッカー特務技官のことも」
全て計算通りなのか、大ハズレで護衛が動くべきなのか。まるで今回は分からずに、お蔭で味方の筈のフォッカーにすら事実を言えなくなってしまっている。
「何もかも別室の仕組んだ罠だとしたら」
「別室以外にあり得ねぇだろ、マックスの預金記録とかさ」
「ん、まあ、そうだよね」
「マジでこの署ごと爆破は頂けねぇし、そこんとこ別室は対策打ってるんだろうな? 大体、幾らサイキ持ちでもたった一人でそれも蚊帳の外にされてるフォッカー氏は本当に頼りになるのかよ?」
「それは勿論、折り紙付きだよ」
ここにきて表情を明るくしたハイファを見れば、余程使えるらしいことが窺えた。
「ふうん、そうか。お前がそう言うなら間違いねぇんだろうな」
「シドの名前と同じ文化言語で『鋼に青』って書いて『スチルブルーのフォッカー』って通り名までつけられてるくらい。殆ど伝説に近いサイキは最強レヴェル」
「なるほどなあ。けど別室について知らせたとはいえ、本当のえげつなさっつーか実力を実感したことのねぇ今のあいつらが第三者の介入を喜ぶとは思えねぇし、俺たちへの信頼まで失くしたら、それこそ丸腰で囮役だって思うと、な」
「まあ、そうなんだけどね……」
確かに別室と別室のサイキ持ちは味方につけたらこれ以上の心強さはない。だが問題はその別室である。これまでシドは確たる目的の達成を掲げた別室がどれだけ非情になるのかを目の当たりにし、体験させられてきた。
別室員でもない部外者目線で内情を知らされてきて、未だに呑み込みきれないことだって多いのだ。だからこそ真にマックスとキャス側についてやれるのは自分たちだけだと考えていた。喩えフォッカーという最強の駒を裏切ることになろうとも。
それから課業終了まで事務的会話以外は避け、一分署の爆破で消失した文書をドラグネットのデータベースから引き出してファイル化する作業に没頭した。深夜番のクジ引きはハイファが引いたので当たらず部屋に帰ることが許されたがここからが問題だった。
問題ではあるが、あの状態のマックスとキャスを放り出しておく訳にはいかない。
アリステアとユーインのコンビが諦めそうな深夜まで待とうかという案も検討したが、それでは相手が誰だか分からない交代要員を敵に回すだけで益は少ないと判断し署を出て二人はそのままタクシーに乗り込んだ。
途切れることのない夜を淡々と走らせた。これも途切れることなくコイルのヘッドライトが前方を照らし光の帯を作っているハイウェイを越え、歓楽街の入り口でタクシーを降りる。前方の歓楽街は相変わらず混沌と昂揚に塗れた祭りの如き空気感だ。
シドとハイファは足早に歓楽街へと紛れ込んだ。
様々な店と行き交う人々。煌めき頭上にホロを飛び出させる電子看板の群れ。
ここからマックスたちのホテルへは結構な距離がある。その間に何とか尾行を撒かなければならない。簡単ではない、向こうもプロなのだ。
「そういや買い物もしてかなきゃならねぇんだったな」
「あ、それね。今日貴方がお昼寝してる間に少し作業したんだよ」
「作業って何だよ?」
「こっそり他人様のリモータ、表層プログラムをインターラプト」
「何を盗ったんだ?」
「海賊版ソフトでマックスたちのリモータIDを一時的に上書きしようと思って。それで部屋を取り直したらルームサーヴィスだって頼めるでしょ。それくらいなら表層プログラムでもオッケー、監視カメラは誤魔化せないけどサ」
現代の監視カメラは高性能だ。喩えIR、赤外線ライトなどを照射してもハレーションを抑えて被写体は鮮明に映る。だがリモータIDの上書きは有効な手だ。こうして危険を引き連れて連日シドたちが自ら通わなくても済む。
細い路地を急に曲がりながらシドは何となく訊いてみた。
「で、誰のIDチョロまかしてきたんだ?」
「アリステア=ナッシュとユーイン=オライリーでーす」
「げっ、ときどきお前の趣味を疑いたくなるぜ。まだ後ろにいるぞ、結構やるな」
「え? ちょっと分かんないかも」
「いいから後ろは見るな。次、左な。そしたら走るぞ」
「ラジャー」
ほぼ小走りで細い径を抜け、違う通りに出た。目の前には外壁のファイバブロックがパステルカラーに塗られた建物、いわゆるラブホテルの入り口に二人は走り込む。チェックパネルに瞬間リモータを翳して前払い料金を精算したシドはそのまま薄暗い階段を駆け上った。
このまま行動確認の後ろ二名が勘違いしてくれたらいいのだが。
だからといって足は止めず確認もせずに一気に短い廊下を走り抜け、今度は階段を駆け下りて出たのはコイル駐車場だ。前方はまた違う通りになっていた。
「はあっ……ああいうホテルを、ただのトンネル代わりっていうのも勿体ないよね」
「別にカネ払ったからって、ヤラなきゃならねぇ法はねぇだろ。も少し走って、左」
「どう? 後ろ、いそう?」
「今んとこは大丈夫だ。だが行確、意外に上手かったな、あいつら」
「明日の職場が怖いなあ」
「しらを切り通すさ、どうせ出歯亀相手だ」
「あーたも『禁を犯してまでのラブホ巡り』が趣味だって噂されてもキレないでね」
「その気になれば三日でも俺は怒らず笑わずでいる自信がある」
「三日間、ずっと完全犯罪の計画練ってそうな貴方が怖い」
駄弁りながらも不審に思われないすれすれの速足でようやく辿り着いたマックスたちのホテルだったが、シドたちの苦労虚しく、またも問題が起こっていた。
キャスを置いてマックスがいなくなっていたのだった。
「悪いけど、おそらく別室戦術コンは予測済みだろうね。そもそもいつまでマックスたちが逃げ続けられるか……体制側ならまだマシだけど連続爆破側に捕まって、それも警察官だって知られたら、それこそ拷問されて見せしめに処刑されかねないよ」
元スパイは最悪から二番目の手で生き延びてきたかのようなことばかり言い、うんざりしかけたシドは自分たちの役どころへと視点を変えた。
「テロリスト側が動きを見せてマックスたちを捕らえる、その寸前に別室はドラクロワたちの身柄を押さえるつもりなんだろ。それまでのカウンタ手段として俺たちがいる……そんなとこなんだろうな、今回は」
「そういう嵌り方でいいのかなあ?。でもマックスがあんなに出頭を拒むとは思わなかったし、何よりキャスが心配。……んっ、そんな触り方しないでよ。その気になっちゃう」
「何もしてねぇって、お前、感じやす過ぎ。……しかし、マックスがヴィクトル星系出身とか、初めて聞いたぜ。ガキの頃は結構何でも話してたのにさ」
幼馴染みだからこそ、愉しい時を一緒に過ごしている間は、出身星系の酷い有り様を口に出したくなかったのかとハイファは思う。
「何もかもを知らせ合わなきゃ、友達じゃない、なんて言えないでしょ」
「まあな、言いたくねぇほど酷かったのか。それを逆手に取った別室が何より酷いよな。実際に出たとされた二十人分の死体、心当たりは一分署と二分署の爆破被害者くらいだ。別室囮作戦に従事しただろう軍の奴らも、暫くいい夢は視られないだろうぜ」
そこでシドは『良い夢を』と言ったフォッカー=リンデマン一等特務技官を思い出す。
今回の別室が立案した作戦で自分たちがマックスたちを逃げ回らせるための護衛官という立場ならば、あのサイキ持ちこそ、その『チーム』の筆頭であるべきではないのか。なのに自分たちはチームとしての『唯一の縛り』すら破らざるを得なくなっている。
「おい、フォッカーのサイキって何なんだ?」
小声でハイファに訊いたが返事は規則正しい寝息だった。
◇◇◇◇
僅かにとろとろと眠ったかと思えばもうリモータのアラームが起動し、着替えてレストランでもそもそ朝食を摂ってから何食わぬ顔で出勤した。
本星セントラルの七分署での扱いとは違うので、朝八時半から十七時半までの間、殆どずっとデカ部屋で待機していなければならない。
ある者はTVニュースを視、ある者は書類整理をし、またある者は過去の事件記録などのファイルを読みふけって過ごす。一班十人前後が二班態勢で事件が起こりませんようにと願いながら時間が経つのをひたすら待つのだ。
こうしてヒマを持て余している間もマックスとキャスが気に掛かるシドだったが、誰に聞かれるとも限らないので口にはしない。
問題は課業終了後に歓楽街へと向かう時だろうと思っていた。
仮配属早々に始末書を提出したシドとハイファは署内で話題の人物であり、もっと話題である消えたマックスたちと親しかったことも当然知られている。
ほぼ確実につくであろう尾行を撒いた時点で、余程上手く立ち回らねば自分たちも断罪される運命だ。別にそれが怖い訳ではないが四人揃ってお縄になり一分署ごと爆破は頂けない。
ようやく昼になったが二階の簡易食堂は人数に対して小さすぎ、それぞれの部署が時間差で食べに行くよう決められていた。
指示された時間に食堂へ行きハイファと横並びでトレイに載ったものを片付けていると、他に席は空いているのにわざわざ真向かいに同じ班の男二人が陣取った。確かアリステア=ナッシュとユーイン=オライリーなる名だったと記憶している。
「せっかく偶然集った仲間が減って淋しいですよね、ワカミヤ巡査部長」
中年のアリステアがどう善意に解釈しても含みある口調で話しかけてきた。
「始末書付きでも金星、制式拳銃でもない私物銃の携帯許可、友人は手に手を取ってエスケープ。色々と貴方の周りは特別が多いようですな」
こちらもテラ標準歴で三十代中盤のユーインが続ける。
どうにも不味い飯になりそうだと思いながらもシドとハイファは澄ました顔で食事を続行した。こういう手合いにはどう返事をしても無駄、それに後ろ暗いのは事実でネタの端緒を与えかねない会話は避けるべきだった。
「あの絢爛豪華な総監賞、おまけに色男の貴方と美人のバディ、目立ってますよ」
制服の時から見られていた上にこいつらが張りつくと思うとシドはげんなりする。
粘り強い刑事というのは褒め言葉だが、こいつらのはネチこいと分類したくなる、好きになれない話しぶりだ。それが今日のシドとハイファの見張り番だと、自分たちの知らないうちに決められたらしい。
表在署の今は帰っても自宅待機だ、出掛けるだけでも余計な問題を抱える。厄介なことになりそうだった。たった一日で、もう腹を括るしかないかも知れない。
結局、「お先に」とだけ挨拶をしてシドはハイファと食堂を出た。
仮のデカ部屋に戻るとヒマもまた戻ってくる。アリステアとユーインの二人もまもなく戻ってきたが、シドはデスクで頬杖をついて寝たフリでやり過ごした。
そのうち本気で眠ってしまいカードゲームで盛り上がる声に起こされた時には二時間が経とうとしていて少々驚く。
「コーヒー飲む?」
頷くとハイファは備え付けのコーヒーメーカから注いだ紙コップふたつを持ってきた。ひとつを受け取り啜ってみたが、いずこも同じ懐かしき泥水だ。
「さっき、フォッカー特務技官からまた発信があったよ。お手洗いで返した」
「で、何だって?」
「前と同じだよ。何もないかって、それだけ。こっちも同じように返して、でもマックスとキャスが逃げて行方不明だってことは知ってたみたい。出頭させる方向で惑星警察としては動いてるって誤魔化しといたけど……いいのかな?」
「いいも何も、俺たちは実際通常勤務してるし、マックスが頷けば連れてくるしな」
「でも、じつはシドもちょっと迷ってるでしょ? フォッカー特務技官のことも」
全て計算通りなのか、大ハズレで護衛が動くべきなのか。まるで今回は分からずに、お蔭で味方の筈のフォッカーにすら事実を言えなくなってしまっている。
「何もかも別室の仕組んだ罠だとしたら」
「別室以外にあり得ねぇだろ、マックスの預金記録とかさ」
「ん、まあ、そうだよね」
「マジでこの署ごと爆破は頂けねぇし、そこんとこ別室は対策打ってるんだろうな? 大体、幾らサイキ持ちでもたった一人でそれも蚊帳の外にされてるフォッカー氏は本当に頼りになるのかよ?」
「それは勿論、折り紙付きだよ」
ここにきて表情を明るくしたハイファを見れば、余程使えるらしいことが窺えた。
「ふうん、そうか。お前がそう言うなら間違いねぇんだろうな」
「シドの名前と同じ文化言語で『鋼に青』って書いて『スチルブルーのフォッカー』って通り名までつけられてるくらい。殆ど伝説に近いサイキは最強レヴェル」
「なるほどなあ。けど別室について知らせたとはいえ、本当のえげつなさっつーか実力を実感したことのねぇ今のあいつらが第三者の介入を喜ぶとは思えねぇし、俺たちへの信頼まで失くしたら、それこそ丸腰で囮役だって思うと、な」
「まあ、そうなんだけどね……」
確かに別室と別室のサイキ持ちは味方につけたらこれ以上の心強さはない。だが問題はその別室である。これまでシドは確たる目的の達成を掲げた別室がどれだけ非情になるのかを目の当たりにし、体験させられてきた。
別室員でもない部外者目線で内情を知らされてきて、未だに呑み込みきれないことだって多いのだ。だからこそ真にマックスとキャス側についてやれるのは自分たちだけだと考えていた。喩えフォッカーという最強の駒を裏切ることになろうとも。
それから課業終了まで事務的会話以外は避け、一分署の爆破で消失した文書をドラグネットのデータベースから引き出してファイル化する作業に没頭した。深夜番のクジ引きはハイファが引いたので当たらず部屋に帰ることが許されたがここからが問題だった。
問題ではあるが、あの状態のマックスとキャスを放り出しておく訳にはいかない。
アリステアとユーインのコンビが諦めそうな深夜まで待とうかという案も検討したが、それでは相手が誰だか分からない交代要員を敵に回すだけで益は少ないと判断し署を出て二人はそのままタクシーに乗り込んだ。
途切れることのない夜を淡々と走らせた。これも途切れることなくコイルのヘッドライトが前方を照らし光の帯を作っているハイウェイを越え、歓楽街の入り口でタクシーを降りる。前方の歓楽街は相変わらず混沌と昂揚に塗れた祭りの如き空気感だ。
シドとハイファは足早に歓楽街へと紛れ込んだ。
様々な店と行き交う人々。煌めき頭上にホロを飛び出させる電子看板の群れ。
ここからマックスたちのホテルへは結構な距離がある。その間に何とか尾行を撒かなければならない。簡単ではない、向こうもプロなのだ。
「そういや買い物もしてかなきゃならねぇんだったな」
「あ、それね。今日貴方がお昼寝してる間に少し作業したんだよ」
「作業って何だよ?」
「こっそり他人様のリモータ、表層プログラムをインターラプト」
「何を盗ったんだ?」
「海賊版ソフトでマックスたちのリモータIDを一時的に上書きしようと思って。それで部屋を取り直したらルームサーヴィスだって頼めるでしょ。それくらいなら表層プログラムでもオッケー、監視カメラは誤魔化せないけどサ」
現代の監視カメラは高性能だ。喩えIR、赤外線ライトなどを照射してもハレーションを抑えて被写体は鮮明に映る。だがリモータIDの上書きは有効な手だ。こうして危険を引き連れて連日シドたちが自ら通わなくても済む。
細い路地を急に曲がりながらシドは何となく訊いてみた。
「で、誰のIDチョロまかしてきたんだ?」
「アリステア=ナッシュとユーイン=オライリーでーす」
「げっ、ときどきお前の趣味を疑いたくなるぜ。まだ後ろにいるぞ、結構やるな」
「え? ちょっと分かんないかも」
「いいから後ろは見るな。次、左な。そしたら走るぞ」
「ラジャー」
ほぼ小走りで細い径を抜け、違う通りに出た。目の前には外壁のファイバブロックがパステルカラーに塗られた建物、いわゆるラブホテルの入り口に二人は走り込む。チェックパネルに瞬間リモータを翳して前払い料金を精算したシドはそのまま薄暗い階段を駆け上った。
このまま行動確認の後ろ二名が勘違いしてくれたらいいのだが。
だからといって足は止めず確認もせずに一気に短い廊下を走り抜け、今度は階段を駆け下りて出たのはコイル駐車場だ。前方はまた違う通りになっていた。
「はあっ……ああいうホテルを、ただのトンネル代わりっていうのも勿体ないよね」
「別にカネ払ったからって、ヤラなきゃならねぇ法はねぇだろ。も少し走って、左」
「どう? 後ろ、いそう?」
「今んとこは大丈夫だ。だが行確、意外に上手かったな、あいつら」
「明日の職場が怖いなあ」
「しらを切り通すさ、どうせ出歯亀相手だ」
「あーたも『禁を犯してまでのラブホ巡り』が趣味だって噂されてもキレないでね」
「その気になれば三日でも俺は怒らず笑わずでいる自信がある」
「三日間、ずっと完全犯罪の計画練ってそうな貴方が怖い」
駄弁りながらも不審に思われないすれすれの速足でようやく辿り着いたマックスたちのホテルだったが、シドたちの苦労虚しく、またも問題が起こっていた。
キャスを置いてマックスがいなくなっていたのだった。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

淫らな蜜に狂わされ
歌龍吟伶
恋愛
普段と変わらない日々は思わぬ形で終わりを迎える…突然の出会い、そして体も心も開かれた少女の人生録。
全体的に性的表現・性行為あり。
他所で知人限定公開していましたが、こちらに移しました。
全3話完結済みです。
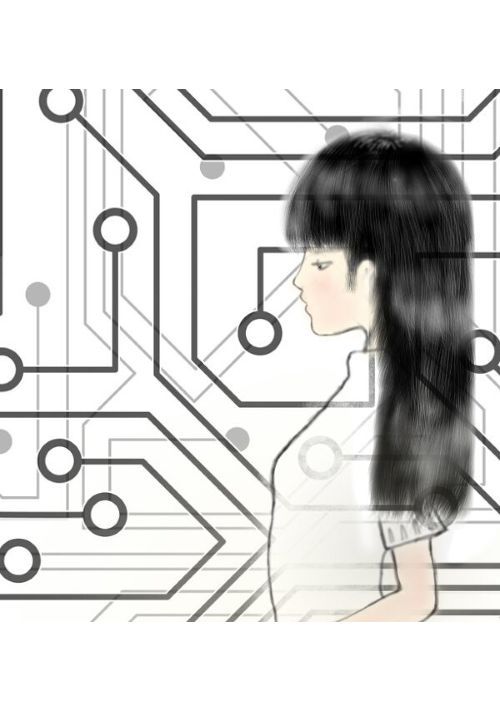

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。


イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

芙蓉は後宮で花開く
速見 沙弥
キャラ文芸
下級貴族の親をもつ5人姉弟の長女 蓮花《リェンファ》。
借金返済で苦しむ家計を助けるために後宮へと働きに出る。忙しくも穏やかな暮らしの中、出会ったのは翡翠の色の目をした青年。さらに思いもよらぬ思惑に巻き込まれてゆくーーー
カクヨムでも連載しております。

影の宦官と薄紅の后~閉ざされた宮廷、呪いの調べ~
昼から山猫
キャラ文芸
「呪われた宮廷」と呼ばれる古い離宮に、帝の寵愛を受けた后・淡雪(あわゆき)が移り住むことになった。仕える宦官の慧琉(けいりゅう)は寡黙で淡々とした物腰だが、実は過去に宮廷を脅かした呪術事件の生き残りだという。夜な夜な離宮に響く笛の音は、かつて後宮を覆った呪いの再来を告げているのか。淡雪は閉ざされた離宮で孤立し、誰も信用できなくなりかけていたが、慧琉だけは彼女を静かに守り続ける。呪われた離宮には本当に妖がいるのか、それとも人の手による策略なのか。やがて浮かび上がる淡雪の過去と宮廷の秘密が、二人をさらなる深みへと誘う。焦燥の中で繰り広げられる“呪い”の正体を突き止めるべく、静かな戦いが始まる。

今夜は帰さない~憧れの騎士団長と濃厚な一夜を
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
ラウニは騎士団で働く事務官である。
そんな彼女が仕事で第五騎士団団長であるオリベルの執務室を訪ねると、彼の姿はなかった。
だが隣の部屋からは、彼が苦しそうに呻いている声が聞こえてきた。
そんな彼を助けようと隣室へと続く扉を開けたラウニが目にしたのは――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















