12 / 64
第12話
しおりを挟む
向かった先は毎度お世話になる管内のセントラル・リドリー病院だった。天井を高く取った五階の駐機場に救急機は滑り込む。シドは先に降りるなりハイファの躰をすくい上げた。横抱きにされてハイファはさすがに抵抗する。
「ちょ、シド、降ろして。歩けるから、シドっ!」
聞く耳も持たずにシドはそのまま五階の救急救命フロアに足を踏み入れた。そこはいつもながらに戦場の様相を呈していたが、シドは目敏く馴染みの看護師を捕まえると、これも馴染みとなった医師の許に誘導して貰う。
顔を赤くしたハイファは診察台に降ろされてホッとした。患者用の回転する丸椅子に座り直し、医師に止血の結束バンドを切られると、たちまち血が溢れ出して今度こそシドが倒れるのではないかとハイファは懸念する。だがシドはしっかり処置に立ち会った。
落ち着いた様子でジャケットを脱ぐハイファに手を貸し、医師と傷を覗き込む。
「出血の割に傷は浅いな。長さ六センチ、幅一センチ、と」
「再生槽に放り込まなくていいのかよ?」
「軽く掠っただけだ、全治三日。そんなしけた顔をするんじゃない」
ハサミでドレスシャツの袖を切り取られ、まずは傷より脳に近い側にぐるりと痛覚ブロックテープを巻かれた。そして痕が残らないよう再生液で充分流してから滅菌ジェルで消毒、合成蛋白スプレーを分厚く吹き付け、人工皮膚テープを貼り付けられる。上からガーゼを貼り付けられて治療は終わり、次はシドの番だ。
四センチばかりの頬の傷を同じく処置される。こちらは痛覚ブロックテープが巻ける処でないので仕方ない。元よりシドはそれを使うのを嫌う。痺れて煙草を落とすからだ。
ついでにシドは腹のアザに消炎スプレーを吹きつけられて、ようやく釈放される。
「正式な所見はあとで署に送っておく。お大事に」
医師に軽く敬礼し、二人は救急救命フロアを出ると一階に降りてエントランスの外から無人コイルタクシーに乗る。歩いても四、五十分の慣れた道だが、ここで怪我をしたハイファを歩かせるシドではない。
モニタパネルでシドが座標指定するとタクシーは身を浮かせて走り出した。
「それにしても何だったんだ、あれは?」
「僕らが狙われるなんて……やっぱり心当たりがありすぎて分からないよ~っ!」
「だよな。過去の別室絡みか、今まで挙げたホシのお礼参りか」
「それとも、お仲間か」
「仲間なあ。お前はリカルドを疑ってるのか?」
「あのシチュエーションでタイミングだよ、疑わない訳にはいかないよ」
確かに怪しかった。怪しいと云えば昨日の射殺現場に顔を出したことからしておかしい。何故汚職や詐欺専門の捜二の刑事を演じておいて殺しに首を突っ込むのか。
「もしかしたら昨日の射殺自体にもリカルドは絡んでるかもね」
「刑事のアンダーカヴァーで殺しまでやったってか?」
「刑事を演じてるからって候補から外すなんて、シドらしくないね」
「そういう訳じゃねぇつもりなんだがな。大体、動機は何なんだよ?」
「それはホシに訊かないと。でもやっぱり怪しすぎるよ、リカルドは」
「あの情熱の下半身サンバダンサーが、なあ」
「これで警務課の婦警さんまでタラしてたら処刑モノだよね」
「嫁さん子供も傷は浅いうちかも知れねぇけどな。……ホローポイント弾か」
十分と掛からず七分署に着き、またも発生した書類を埋めていると、左隣のヤマサキの席に泥水の紙コップを手にしたマイヤー警部補が腰掛けた。
「ちょっと宜しいでしょうか?」
「何です?」
「鑑識が執念で貴方がたを撃った弾頭を二発発見しましてね。倉庫の壁に当たって砕け、ライフルマークの検出は無理でしたが、ホローポイントで間違いないということです」
ライフルマークとは発射された銃弾に刻まれた傷のことである。銃身の内側にはライフリングという螺旋状の溝が掘られているのが一般的だ。四条右転や六条左転といった溝である。銃弾に回転力を与えて真っ直ぐ飛ばす工夫だが、この溝がバレル内を通過する銃弾に傷をつけるのだ。これがライフルマークで、傷は銃によってそれぞれ違う。
故に発射後の弾により銃を特定できるのだが、今回はそれに頼れないということだった。
「そうですか、他には?」
「今のところは。それではお大事にして下さいね。……皆さん、定時ですよ!」
報告書を捜査戦術コンに食わせ、今日のシドとハイファは五階まで上がらずに、デスク端末で帳場要員たちの成果をチェックした。目撃情報もなし、キンパイにも引っ掛からず。
「あ、でもICSのリモータ解析が上がってるよ」
「どれ、『個人の手によりカスタマイズされている』って、何だ、それだけか」
「元は意外なくらいの汎用品だったんだね。あんなに電子工作の好きな人が」
「言われてみればそうだな」
マル害の寝室のデスクに精密工具や電子部品が散っていたのをシドは思い出した。
「いいや。早帰りできるときには帰ろうよ」
「そうだな、タマも待ってる……っと、ちょっと待て」
「ん、ナニ?」
答えずシドはドラグネット検索を始めていた。昨日のニュースをふいに思い出したのだ。ここ五日で二体の腕のない死体が発見され、どちらも特殊な弾が使用されていたということを。
「ネオロンドンとブラジリアシティ……ふうん、これもホローポイントとはね」
「肩の断裂面には生体反応があり、二弾で腕はちぎられている……」
「それがどうかした?」
「同じホローポイント、それも今回の死体は肩に二射浴びてた」
「もしかしてホシが同じだって言いたいの?」
切れ長の黒い目を煌めかせてシドは頷く。手探りでポケットから煙草を出して咥えた。オイルライターで火を点け紫煙を吐いてから口を開く。
「今回もホシは腕を撃ち飛ばして持ち去ろうとした。だが俺たちの現着が早すぎた」
「腕をちぎるヒマもなく逃走した?」
「ああ、それならプロが肩にぶち込んだ理由もつけられる」
「じゃあ、ちょっと待って」
自分のデスクに着くとハイファは業務課にアクセスした。端末にリモータのリードを繋ぐこともなく、得意技のハッキングなどしなくても業務管理コンの資料は閲覧可能だった。
署員の動向を示す一覧を表示し、検索して結果をシドに見せる。
「カーク=アクロイドは先週から今週初めにかけて、一週間の有休をとってるよ」
「リカルドがネオロンドンとブラジリアシティに出張ってたとでも言うのかよ?」
「可能性はあるでしょ。一応、別室戦術コンに探らせるよ」
リモータのキィを叩いて上空の軍事通信衛星MCSを介し別室コンとアクセス、ここ十日間に渡って宙港付属空港の利用者名簿をふるいに掛けるよう依頼した。当然、リカルドの別室任務には全く触れない。
一方のシドは考え込んでいた。何故ホシは腕を持ち去ったのか。
今回の射殺も腕を持ち去ろうとしたと仮定する。左腕についているのはリモータだけだ。外して持ち去ればいいものを何故腕ごとちぎろうとするのか。他人の腕に価値はない。やはり考えられるのはリモータだけしかない……。
「違う……ボディジェムだ!」
「何、今度はどうしたの?」
「ホシはボディジェムを盗ろうとしたんだ」
「ボディジェムったって、言ったと思うけど、宝石としての価値は低いんだよ?」
「だがそれしか考えられねぇだろ。それとも付属しているセス素子かも知れん」
「セス素子だってありふれてるし、大体、何も腕ごとちぎらなくたって、エグいけど、ほじくり出せばいいんじゃないの?」
言われてみればそんな気もしたが、一度湧いた疑念は晴れなかった。
「ハイファ、ネオロンドンとブラジリアシティの件、もっと深く探れるか?」
「どちらも腕にボディジェムを埋めてたかどうかだね?」
「他に何でもいい、共通点を探してくれ」
「ラジャー」
自分の席に座り直して端末にハイファは向かう。今度こそリモータからリードを引き出して端末に繋ぎ、別室戦術コンの支援を得つつ、ありとあらゆる情報を吸い上げ始めた。シドは立ち上がると煮詰まり気味の泥水を紙コップふたつに注ぎ、少し湯を足してから戻る。
「あ、ありがと。……それで二人、ううん、今回の射殺も含めて三人の共通点は、第一にハッカーとしてその分野では名の通った人間だった」
「もう出たのか、さすがだな。けどハッカーなあ」
「そう。第二に腕にボディジェムを埋めてたこと」
「やっぱりな。それだけじゃねぇんだろ?」
若草色の瞳に得意げな色を見取ってシドは期待する。
「まあね。ここで第三。先々月から先月に掛けて三人はそれぞれロニアに旅行していた。第四として、そこでボディジェムを埋め、リモータを買い換えているんだよ」
「なるほど、ロニアか」
ちょっとスリルのあるレジャーとして意外に人気のあるロニアだが、マル害三人が三人ともにロニアでボディジェムを埋め、リモータを買い換えていたのは偶然と思えない。
「じゃあ、ロニアで買ったジェムとリモータは特殊なブツってことか?」
「それは分からないけど、ここで第五。三人のリモータは、たぶん自身の手によってカスタマイズされていた。友人の証言から明らかになってる。でもリモータに何か特殊なアプリが入っていたかどうかはブツが腕ごと持ち去られてるから……」
「たったひとつ手の内にあるのはマイルズ=レインのリモータだけか」
「そういうこと。でも上のICSもマイルズのリモータに特殊アプリがあったなんて報告はしていないよ。カスタマイズしたときに消去したのかも」
チェーンスモークしてシドは首を横に振る。
「自分で消したんじゃねぇ、時限IDと同じく生体反応が消えれば自動消滅する『何か』だったかも知れねぇぞ」
「そっか、確かにね。ならボディジェムにも同じ機能があってもおかしくないかも」
そこで二人は顔を見合わせた。
「マイルズ=レインのダイイングメッセージだ!」
「ダリアネットワークだっけ?」
「ちょ、シド、降ろして。歩けるから、シドっ!」
聞く耳も持たずにシドはそのまま五階の救急救命フロアに足を踏み入れた。そこはいつもながらに戦場の様相を呈していたが、シドは目敏く馴染みの看護師を捕まえると、これも馴染みとなった医師の許に誘導して貰う。
顔を赤くしたハイファは診察台に降ろされてホッとした。患者用の回転する丸椅子に座り直し、医師に止血の結束バンドを切られると、たちまち血が溢れ出して今度こそシドが倒れるのではないかとハイファは懸念する。だがシドはしっかり処置に立ち会った。
落ち着いた様子でジャケットを脱ぐハイファに手を貸し、医師と傷を覗き込む。
「出血の割に傷は浅いな。長さ六センチ、幅一センチ、と」
「再生槽に放り込まなくていいのかよ?」
「軽く掠っただけだ、全治三日。そんなしけた顔をするんじゃない」
ハサミでドレスシャツの袖を切り取られ、まずは傷より脳に近い側にぐるりと痛覚ブロックテープを巻かれた。そして痕が残らないよう再生液で充分流してから滅菌ジェルで消毒、合成蛋白スプレーを分厚く吹き付け、人工皮膚テープを貼り付けられる。上からガーゼを貼り付けられて治療は終わり、次はシドの番だ。
四センチばかりの頬の傷を同じく処置される。こちらは痛覚ブロックテープが巻ける処でないので仕方ない。元よりシドはそれを使うのを嫌う。痺れて煙草を落とすからだ。
ついでにシドは腹のアザに消炎スプレーを吹きつけられて、ようやく釈放される。
「正式な所見はあとで署に送っておく。お大事に」
医師に軽く敬礼し、二人は救急救命フロアを出ると一階に降りてエントランスの外から無人コイルタクシーに乗る。歩いても四、五十分の慣れた道だが、ここで怪我をしたハイファを歩かせるシドではない。
モニタパネルでシドが座標指定するとタクシーは身を浮かせて走り出した。
「それにしても何だったんだ、あれは?」
「僕らが狙われるなんて……やっぱり心当たりがありすぎて分からないよ~っ!」
「だよな。過去の別室絡みか、今まで挙げたホシのお礼参りか」
「それとも、お仲間か」
「仲間なあ。お前はリカルドを疑ってるのか?」
「あのシチュエーションでタイミングだよ、疑わない訳にはいかないよ」
確かに怪しかった。怪しいと云えば昨日の射殺現場に顔を出したことからしておかしい。何故汚職や詐欺専門の捜二の刑事を演じておいて殺しに首を突っ込むのか。
「もしかしたら昨日の射殺自体にもリカルドは絡んでるかもね」
「刑事のアンダーカヴァーで殺しまでやったってか?」
「刑事を演じてるからって候補から外すなんて、シドらしくないね」
「そういう訳じゃねぇつもりなんだがな。大体、動機は何なんだよ?」
「それはホシに訊かないと。でもやっぱり怪しすぎるよ、リカルドは」
「あの情熱の下半身サンバダンサーが、なあ」
「これで警務課の婦警さんまでタラしてたら処刑モノだよね」
「嫁さん子供も傷は浅いうちかも知れねぇけどな。……ホローポイント弾か」
十分と掛からず七分署に着き、またも発生した書類を埋めていると、左隣のヤマサキの席に泥水の紙コップを手にしたマイヤー警部補が腰掛けた。
「ちょっと宜しいでしょうか?」
「何です?」
「鑑識が執念で貴方がたを撃った弾頭を二発発見しましてね。倉庫の壁に当たって砕け、ライフルマークの検出は無理でしたが、ホローポイントで間違いないということです」
ライフルマークとは発射された銃弾に刻まれた傷のことである。銃身の内側にはライフリングという螺旋状の溝が掘られているのが一般的だ。四条右転や六条左転といった溝である。銃弾に回転力を与えて真っ直ぐ飛ばす工夫だが、この溝がバレル内を通過する銃弾に傷をつけるのだ。これがライフルマークで、傷は銃によってそれぞれ違う。
故に発射後の弾により銃を特定できるのだが、今回はそれに頼れないということだった。
「そうですか、他には?」
「今のところは。それではお大事にして下さいね。……皆さん、定時ですよ!」
報告書を捜査戦術コンに食わせ、今日のシドとハイファは五階まで上がらずに、デスク端末で帳場要員たちの成果をチェックした。目撃情報もなし、キンパイにも引っ掛からず。
「あ、でもICSのリモータ解析が上がってるよ」
「どれ、『個人の手によりカスタマイズされている』って、何だ、それだけか」
「元は意外なくらいの汎用品だったんだね。あんなに電子工作の好きな人が」
「言われてみればそうだな」
マル害の寝室のデスクに精密工具や電子部品が散っていたのをシドは思い出した。
「いいや。早帰りできるときには帰ろうよ」
「そうだな、タマも待ってる……っと、ちょっと待て」
「ん、ナニ?」
答えずシドはドラグネット検索を始めていた。昨日のニュースをふいに思い出したのだ。ここ五日で二体の腕のない死体が発見され、どちらも特殊な弾が使用されていたということを。
「ネオロンドンとブラジリアシティ……ふうん、これもホローポイントとはね」
「肩の断裂面には生体反応があり、二弾で腕はちぎられている……」
「それがどうかした?」
「同じホローポイント、それも今回の死体は肩に二射浴びてた」
「もしかしてホシが同じだって言いたいの?」
切れ長の黒い目を煌めかせてシドは頷く。手探りでポケットから煙草を出して咥えた。オイルライターで火を点け紫煙を吐いてから口を開く。
「今回もホシは腕を撃ち飛ばして持ち去ろうとした。だが俺たちの現着が早すぎた」
「腕をちぎるヒマもなく逃走した?」
「ああ、それならプロが肩にぶち込んだ理由もつけられる」
「じゃあ、ちょっと待って」
自分のデスクに着くとハイファは業務課にアクセスした。端末にリモータのリードを繋ぐこともなく、得意技のハッキングなどしなくても業務管理コンの資料は閲覧可能だった。
署員の動向を示す一覧を表示し、検索して結果をシドに見せる。
「カーク=アクロイドは先週から今週初めにかけて、一週間の有休をとってるよ」
「リカルドがネオロンドンとブラジリアシティに出張ってたとでも言うのかよ?」
「可能性はあるでしょ。一応、別室戦術コンに探らせるよ」
リモータのキィを叩いて上空の軍事通信衛星MCSを介し別室コンとアクセス、ここ十日間に渡って宙港付属空港の利用者名簿をふるいに掛けるよう依頼した。当然、リカルドの別室任務には全く触れない。
一方のシドは考え込んでいた。何故ホシは腕を持ち去ったのか。
今回の射殺も腕を持ち去ろうとしたと仮定する。左腕についているのはリモータだけだ。外して持ち去ればいいものを何故腕ごとちぎろうとするのか。他人の腕に価値はない。やはり考えられるのはリモータだけしかない……。
「違う……ボディジェムだ!」
「何、今度はどうしたの?」
「ホシはボディジェムを盗ろうとしたんだ」
「ボディジェムったって、言ったと思うけど、宝石としての価値は低いんだよ?」
「だがそれしか考えられねぇだろ。それとも付属しているセス素子かも知れん」
「セス素子だってありふれてるし、大体、何も腕ごとちぎらなくたって、エグいけど、ほじくり出せばいいんじゃないの?」
言われてみればそんな気もしたが、一度湧いた疑念は晴れなかった。
「ハイファ、ネオロンドンとブラジリアシティの件、もっと深く探れるか?」
「どちらも腕にボディジェムを埋めてたかどうかだね?」
「他に何でもいい、共通点を探してくれ」
「ラジャー」
自分の席に座り直して端末にハイファは向かう。今度こそリモータからリードを引き出して端末に繋ぎ、別室戦術コンの支援を得つつ、ありとあらゆる情報を吸い上げ始めた。シドは立ち上がると煮詰まり気味の泥水を紙コップふたつに注ぎ、少し湯を足してから戻る。
「あ、ありがと。……それで二人、ううん、今回の射殺も含めて三人の共通点は、第一にハッカーとしてその分野では名の通った人間だった」
「もう出たのか、さすがだな。けどハッカーなあ」
「そう。第二に腕にボディジェムを埋めてたこと」
「やっぱりな。それだけじゃねぇんだろ?」
若草色の瞳に得意げな色を見取ってシドは期待する。
「まあね。ここで第三。先々月から先月に掛けて三人はそれぞれロニアに旅行していた。第四として、そこでボディジェムを埋め、リモータを買い換えているんだよ」
「なるほど、ロニアか」
ちょっとスリルのあるレジャーとして意外に人気のあるロニアだが、マル害三人が三人ともにロニアでボディジェムを埋め、リモータを買い換えていたのは偶然と思えない。
「じゃあ、ロニアで買ったジェムとリモータは特殊なブツってことか?」
「それは分からないけど、ここで第五。三人のリモータは、たぶん自身の手によってカスタマイズされていた。友人の証言から明らかになってる。でもリモータに何か特殊なアプリが入っていたかどうかはブツが腕ごと持ち去られてるから……」
「たったひとつ手の内にあるのはマイルズ=レインのリモータだけか」
「そういうこと。でも上のICSもマイルズのリモータに特殊アプリがあったなんて報告はしていないよ。カスタマイズしたときに消去したのかも」
チェーンスモークしてシドは首を横に振る。
「自分で消したんじゃねぇ、時限IDと同じく生体反応が消えれば自動消滅する『何か』だったかも知れねぇぞ」
「そっか、確かにね。ならボディジェムにも同じ機能があってもおかしくないかも」
そこで二人は顔を見合わせた。
「マイルズ=レインのダイイングメッセージだ!」
「ダリアネットワークだっけ?」
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

淫らな蜜に狂わされ
歌龍吟伶
恋愛
普段と変わらない日々は思わぬ形で終わりを迎える…突然の出会い、そして体も心も開かれた少女の人生録。
全体的に性的表現・性行為あり。
他所で知人限定公開していましたが、こちらに移しました。
全3話完結済みです。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
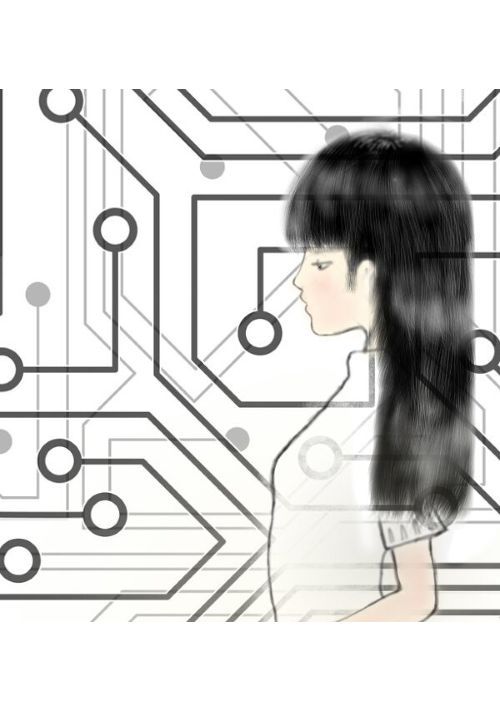

今夜は帰さない~憧れの騎士団長と濃厚な一夜を
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
ラウニは騎士団で働く事務官である。
そんな彼女が仕事で第五騎士団団長であるオリベルの執務室を訪ねると、彼の姿はなかった。
だが隣の部屋からは、彼が苦しそうに呻いている声が聞こえてきた。
そんな彼を助けようと隣室へと続く扉を開けたラウニが目にしたのは――。

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















