39 / 46
黄昏の王
4、黒髪の魔女(後編)
しおりを挟む
冬の夜は、空気は冷たい。
クリスマスが近づく季節は特にそうだ。
リアム・ディアスの運転する車はロンドンの中心部に向かっていた。
「骨董店シュレスホールド・ガーディアンってどこなんだ?」
「シュレスホールド・ガーディアンはどこにでもあってどこにもない」
「ちょっと何言ってるか分からない」
「決まった場所にはないの。当然、ナビなんかじゃ見つけられない。店への入口を見つけるには特定の条件が必要」
そう言ってミッシェルは、紙切れを取り出した。
「なんだい? それ」
紙にはリアムが見たこともない文字と奇妙な記号が規則的に書き連ねてあった。
「店主からもらった入場券みたいなもの。入口が近づくと、これに変化が起きる。これが無いと誰も店には、たどり着けない」
「要するに普通じゃないってことなんだな」
「まあね」
「君に付き合ってると自分が何も知らない子供に思えてくる」
「大丈夫よ。あなたは立派な大人の男よ。人間のね」
リアムはミッシェルを魅力的に感じていたが、それを差し引いても得体の知れない怖さを感じる事がある。それがミッシェルがヴァンパイアである事を認識させる要因でもあった。
彼女は相手をマインドコントロールする能力を持っているが、リアムにはその能力が通じない。かつて戦場で頭部に負った怪我が原因のようだが詳しい理由は分からない。
つまり、リアムがミッシェルに協力するのは、決してマインドコントロールをかけられているわけではないということだ。
リアムがミッシェルを信じるのは、かつて共に関わったある事件で彼女のとった行動を知っているというのもある。
だが、それよりも彼女の瞳の奥にある何か純粋なものを感じ取れるからだった。
人の姿を見かけない通りに入るとミッシェルは、車を止めるように指示した。
「さっきの路地裏前まで戻って」
リアムはバックギアにシフトチェンジして車を下げる。バックライトが冷たいアスファルトを照らした。
「ありがとう」
ミッシェルが、車を降りようとするとリアムが呼び止めた。
「なあ、俺も連れていってくれよ」
「えっ?」
「見てみたいんだよ。その……そっちの世界の店ってのをさ」
ミッシェルは、少し考えた後、言った。
「いいわ。ついてきて」
リアムは喜び勇んでミッシェルの後を追う。
路地裏に入るとミッシェルは呪文と記号の描かれた紙を見た。
リアムが覗き込むと記号がけがオレンジ色に光っている。まるで燃えるような色だ。リアムが驚いていると紙きれは実際に燃え尽きた。
すると目の前の壁に、いつの間にか木製の扉があった。
「ここよ」
ミッシェルは、扉を開くと中へ入っていく。
「使い切りってわけか。本当に入場券なんだな」
そう言ってリアムはミッシェルを追って中に入った。
店内は、アンティークの店そのものだ。
置かれている品もリアムが想像していた不気味なものとは違う。いたって普通の装飾品や家具だ。
奥には眼鏡をかけたおそらく店主であろう老人がいた。
「やあ、いらっしゃい。レッドアイ」
店主はミッシェルたちに気が付くとそう声をかけてきた。
「相変わらず閑古鳥ね」
「まあ、そうなんだが、上客が多くてね。売り上げはいいんだ」
「いいことね」
「あんたも、そのひとりだよ。で? 今日は何をお買い上げで?」
「そうね……?」
ミッシェルは、傍に並べてある小物に目をやると適当にいくつか掴んで店主に差し出した」
「これを包んで」
「毎度あり。そっちの連れの人は、何かお決まりで?」
店主がリアムに言う。
「いや、俺はまだ見させてもらうよ」
「ごゆっくりどうぞ」
店主はミッシェルの買う品を包む準備を始める。
「ああ、品物は別々に包んで」
「はいよ。ご注文は、それだけかい?」
ミッシェルは、ゴムバンドで巻いた札束を二つ置いた。
「黒髪の魔女と呼ばれる相手の居所を探してる。炎の魔女とも呼ばれているらしいんだけと、知ってる?」
店主は、当然といわんばかりの笑顔を見せる。
「知ってるもなにも、彼女も、うちの上客でね」
「なら話が早いわ」
「でも、お客の情報を売るというのはね。ほら、近頃は、個人情報がどうのこうのってあるから」
ミッシェルは、ポケットを探ると小袋を取り出して店主に差し出した。
「妖精の粉。貴重でしょ?」
「なんと、妖精の粉か。もちろんだよ。顧客の情報を売る価値はある」
店主は受け取った小袋と丸めた札の束ををしまいこんだ。
「さて黒髪の魔女か……タチアナ・ヴァリアントの事だね」
「本名は、もう知ってる」
「タチアナは、ユースティティア・デウスという機関に所属しているんだ」
「聞いたことのない組織だな」
横で二人のやり取りを聞いていたリアムが口をはさむ。
「ユースティティア・デウス(正義を裁く神)は、ヨーロッパで起きる魔術犯罪を取り締まる機関さ。その原型となった組織は第二次世界大戦中に遡り、かつてナチス・ドイツ内の魔術結社に対抗する為に連合国軍情報部内で組織された特別諜報チームが起源なんだ」
「それも知ってる」
そう言ってミッシェルは、口を出すなと言わんばかりにリアムの方を見た。
「OK、ごめん」
リアムは、両手を見せた後、口にチャックを閉める仕草を見せた。
タチアナ・ヴァリアントがユースティティア・デウスに所属している事も渡されていた資料で既に知っている。だからナチス・ドイツの研究機関アーネンエルベの一部だったトルッペ・シュヴェールトが敵視しているのも納得できる話でもあったのだ。
「タチアナ・ヴァリアントの居場所は?」
「タチアナが今どこにいるかなんてわからんよ」
「なら、話は終わり。お金も貴重な“妖精の粉も返して」
「話を最後まで聞けって。タチアナは、ユースティティア・デウスの本拠であるマニック・カースル城の一室を住居にしてる。まあ、社宅みたいなもんだな。要するに今どこにいるかは、知らんが、帰る場所は知ってるというわけだ」
「なるほど。それじゃ、マニック・カースル城っていうのは、何処にあるの?」
「それが問題でね。あれは、この店と同じようなものだ。知ってる者しか、辿り着けない」
「普通、そうだろ?」
我慢しきれずリアムが再び口を挟んだ。
「いや、お若いの。城が“知っている者”しか、辿り着けないって意味さ」
「城の方が? はあ? どういうこと?」
「リアム。ちょっと、黙っていてくれる?」
ミッシェルがリアムを睨む。
「だが、心配ない。城へた辿り着くヒントはある」
店主は、そう言うと店の隅を指さした。
ミッシェルとリアムが、店主が指し示した方向を見ると、メモを見ながら品物を物色しているアジア系の若い男がいた。
腰を屈めながら棚に並ぶ品を真剣に見つめている。
「誰なの?」
「タチアナ・ヴァリアントの相棒だよ。彼なら城に案内してくれる」
「ちょっと待って。彼、相棒でなんでしょ? なのに仲間を売る?」
「いや、あんたがタチアナに何をする気か知らないが……まあ、知る気もないんだが、そこは黙っていればいいさ。タチアナの知り合いだとでも言えばいい」
「……にしても」
「大丈夫さ」
そう言って店主は、にこりとする。
「彼は、度を越したお人よしだから」
クリスマスが近づく季節は特にそうだ。
リアム・ディアスの運転する車はロンドンの中心部に向かっていた。
「骨董店シュレスホールド・ガーディアンってどこなんだ?」
「シュレスホールド・ガーディアンはどこにでもあってどこにもない」
「ちょっと何言ってるか分からない」
「決まった場所にはないの。当然、ナビなんかじゃ見つけられない。店への入口を見つけるには特定の条件が必要」
そう言ってミッシェルは、紙切れを取り出した。
「なんだい? それ」
紙にはリアムが見たこともない文字と奇妙な記号が規則的に書き連ねてあった。
「店主からもらった入場券みたいなもの。入口が近づくと、これに変化が起きる。これが無いと誰も店には、たどり着けない」
「要するに普通じゃないってことなんだな」
「まあね」
「君に付き合ってると自分が何も知らない子供に思えてくる」
「大丈夫よ。あなたは立派な大人の男よ。人間のね」
リアムはミッシェルを魅力的に感じていたが、それを差し引いても得体の知れない怖さを感じる事がある。それがミッシェルがヴァンパイアである事を認識させる要因でもあった。
彼女は相手をマインドコントロールする能力を持っているが、リアムにはその能力が通じない。かつて戦場で頭部に負った怪我が原因のようだが詳しい理由は分からない。
つまり、リアムがミッシェルに協力するのは、決してマインドコントロールをかけられているわけではないということだ。
リアムがミッシェルを信じるのは、かつて共に関わったある事件で彼女のとった行動を知っているというのもある。
だが、それよりも彼女の瞳の奥にある何か純粋なものを感じ取れるからだった。
人の姿を見かけない通りに入るとミッシェルは、車を止めるように指示した。
「さっきの路地裏前まで戻って」
リアムはバックギアにシフトチェンジして車を下げる。バックライトが冷たいアスファルトを照らした。
「ありがとう」
ミッシェルが、車を降りようとするとリアムが呼び止めた。
「なあ、俺も連れていってくれよ」
「えっ?」
「見てみたいんだよ。その……そっちの世界の店ってのをさ」
ミッシェルは、少し考えた後、言った。
「いいわ。ついてきて」
リアムは喜び勇んでミッシェルの後を追う。
路地裏に入るとミッシェルは呪文と記号の描かれた紙を見た。
リアムが覗き込むと記号がけがオレンジ色に光っている。まるで燃えるような色だ。リアムが驚いていると紙きれは実際に燃え尽きた。
すると目の前の壁に、いつの間にか木製の扉があった。
「ここよ」
ミッシェルは、扉を開くと中へ入っていく。
「使い切りってわけか。本当に入場券なんだな」
そう言ってリアムはミッシェルを追って中に入った。
店内は、アンティークの店そのものだ。
置かれている品もリアムが想像していた不気味なものとは違う。いたって普通の装飾品や家具だ。
奥には眼鏡をかけたおそらく店主であろう老人がいた。
「やあ、いらっしゃい。レッドアイ」
店主はミッシェルたちに気が付くとそう声をかけてきた。
「相変わらず閑古鳥ね」
「まあ、そうなんだが、上客が多くてね。売り上げはいいんだ」
「いいことね」
「あんたも、そのひとりだよ。で? 今日は何をお買い上げで?」
「そうね……?」
ミッシェルは、傍に並べてある小物に目をやると適当にいくつか掴んで店主に差し出した」
「これを包んで」
「毎度あり。そっちの連れの人は、何かお決まりで?」
店主がリアムに言う。
「いや、俺はまだ見させてもらうよ」
「ごゆっくりどうぞ」
店主はミッシェルの買う品を包む準備を始める。
「ああ、品物は別々に包んで」
「はいよ。ご注文は、それだけかい?」
ミッシェルは、ゴムバンドで巻いた札束を二つ置いた。
「黒髪の魔女と呼ばれる相手の居所を探してる。炎の魔女とも呼ばれているらしいんだけと、知ってる?」
店主は、当然といわんばかりの笑顔を見せる。
「知ってるもなにも、彼女も、うちの上客でね」
「なら話が早いわ」
「でも、お客の情報を売るというのはね。ほら、近頃は、個人情報がどうのこうのってあるから」
ミッシェルは、ポケットを探ると小袋を取り出して店主に差し出した。
「妖精の粉。貴重でしょ?」
「なんと、妖精の粉か。もちろんだよ。顧客の情報を売る価値はある」
店主は受け取った小袋と丸めた札の束ををしまいこんだ。
「さて黒髪の魔女か……タチアナ・ヴァリアントの事だね」
「本名は、もう知ってる」
「タチアナは、ユースティティア・デウスという機関に所属しているんだ」
「聞いたことのない組織だな」
横で二人のやり取りを聞いていたリアムが口をはさむ。
「ユースティティア・デウス(正義を裁く神)は、ヨーロッパで起きる魔術犯罪を取り締まる機関さ。その原型となった組織は第二次世界大戦中に遡り、かつてナチス・ドイツ内の魔術結社に対抗する為に連合国軍情報部内で組織された特別諜報チームが起源なんだ」
「それも知ってる」
そう言ってミッシェルは、口を出すなと言わんばかりにリアムの方を見た。
「OK、ごめん」
リアムは、両手を見せた後、口にチャックを閉める仕草を見せた。
タチアナ・ヴァリアントがユースティティア・デウスに所属している事も渡されていた資料で既に知っている。だからナチス・ドイツの研究機関アーネンエルベの一部だったトルッペ・シュヴェールトが敵視しているのも納得できる話でもあったのだ。
「タチアナ・ヴァリアントの居場所は?」
「タチアナが今どこにいるかなんてわからんよ」
「なら、話は終わり。お金も貴重な“妖精の粉も返して」
「話を最後まで聞けって。タチアナは、ユースティティア・デウスの本拠であるマニック・カースル城の一室を住居にしてる。まあ、社宅みたいなもんだな。要するに今どこにいるかは、知らんが、帰る場所は知ってるというわけだ」
「なるほど。それじゃ、マニック・カースル城っていうのは、何処にあるの?」
「それが問題でね。あれは、この店と同じようなものだ。知ってる者しか、辿り着けない」
「普通、そうだろ?」
我慢しきれずリアムが再び口を挟んだ。
「いや、お若いの。城が“知っている者”しか、辿り着けないって意味さ」
「城の方が? はあ? どういうこと?」
「リアム。ちょっと、黙っていてくれる?」
ミッシェルがリアムを睨む。
「だが、心配ない。城へた辿り着くヒントはある」
店主は、そう言うと店の隅を指さした。
ミッシェルとリアムが、店主が指し示した方向を見ると、メモを見ながら品物を物色しているアジア系の若い男がいた。
腰を屈めながら棚に並ぶ品を真剣に見つめている。
「誰なの?」
「タチアナ・ヴァリアントの相棒だよ。彼なら城に案内してくれる」
「ちょっと待って。彼、相棒でなんでしょ? なのに仲間を売る?」
「いや、あんたがタチアナに何をする気か知らないが……まあ、知る気もないんだが、そこは黙っていればいいさ。タチアナの知り合いだとでも言えばいい」
「……にしても」
「大丈夫さ」
そう言って店主は、にこりとする。
「彼は、度を越したお人よしだから」
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

淫らな蜜に狂わされ
歌龍吟伶
恋愛
普段と変わらない日々は思わぬ形で終わりを迎える…突然の出会い、そして体も心も開かれた少女の人生録。
全体的に性的表現・性行為あり。
他所で知人限定公開していましたが、こちらに移しました。
全3話完結済みです。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。
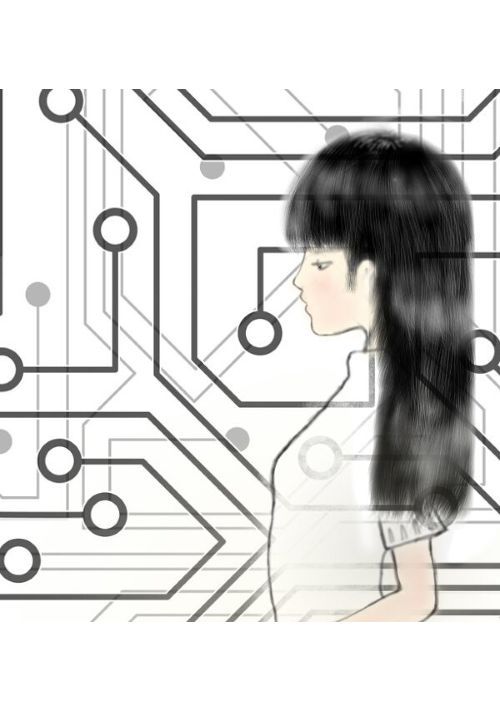

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

心に白い曼珠沙華
夜鳥すぱり
キャラ文芸
柔和な顔つきにひょろりとした体躯で、良くも悪くもあまり目立たない子供、藤原鷹雪(ふじわらのたかゆき)は十二になったばかり。
平安の都、長月半ばの早朝、都では大きな祭りが取り行われようとしていた。
鷹雪は遠くから聞こえる笛の音に誘われるように、六条の屋敷を抜けだし、お供も付けずに、徒歩で都の大通りへと向かった。あっちこっちと、もの珍しいものに足を止めては、キョロキョロ物色しながらゆっくりと大通りを歩いていると、路地裏でなにやら揉め事が。鷹雪と同い年くらいの、美しい可憐な少女が争いに巻き込まれている。助け逃げたは良いが、鷹雪は倒れてしまって……。
◆完結しました、思いの外BL色が濃くなってしまって、あれれという感じでしたが、ジャンル弾かれてない?ので、見過ごしていただいてるかな。かなり昔に他で書いてた話で手直ししつつ5万文字でした。自分でも何を書いたかすっかり忘れていた話で、読み返すのが楽しかったです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















