24 / 25
24 戯れと焦り
しおりを挟む
その日の夜、シュエシは大いに戸惑う出来事に直面していた。発端はヴァイルの「一緒に湯を使うか」という言葉で、「湯を使う」というのは「湯を使って体を綺麗にする」ということだ。それはわかっている。ただ「一緒に」という意味がわからない。
(一緒にって、どういうことだろう)
シュエシにとって体を綺麗にする行為は、布を水に浸しそれで肌を拭うことだった。両親と旅をしていたときからそうで、両親を亡くした後もそれは変わらない。さすがに冬は湯を沸かしていたが、髪の毛を洗うほどの湯を沸かすのは大変だったため昼間に水で洗うことが多かった。
身代わりの花嫁として屋敷に住むようになってからも布で拭うのは同じだった。変わったのは毎日湯を使えるようになったことと湯がたっぷりと用意されたことで、着るものをできるだけ汚さないようにと肌が赤くなるまで擦るようにもなった。旅を始めてからもそれは変わらず、宿でも屋敷にいたときと同じように体は布で拭い髪だけ湯を使って洗っていた。
それなのに「一緒に」というのはどういうことだろう。まさか布で拭い合うということだろうか。困惑したまま立ち尽くしていると「何をしている?」と声をかけられた。
目の前ではヴァイルが裸体を惜しげもなく晒している。奥には優美な形をした大きな湯船があり、たっぷりの湯があるからか湯気が立っていた。シュエシはヴァイルを見ては顔を真っ赤にし、慌てて湯船を見ては視線をさまよわせた。
「なんだ、恥ずかしいのか? 体など何度も見ているだろう」
「そう、ですけど」
「さっさと脱げ、湯が冷めてしまうぞ」
裸のヴァイルが近づいて来る。慌てて視線を逸らしながら胸元のリボンに手をかけたものの、どうしても解くことができない。
(きっとドレスというのもよくないんだ)
旅が始まってからもヴァイルが用意するのはドレスばかりで、シュエシもそれが当たり前になっていた。だが、見られながらドレスを脱ぐというのはさすがに恥ずかしい。まるで自分が少女になってしまったかのような気になる。
「湯浴みのお手伝いをいたしましょうか?」
いつの間に近づいたのか、耳元でそんなことを囁かれギョッとした。ヴァイルが執事に扮していたときに毎日のように聞いていた言葉だからか、当時のことを思い出しうろたえる。密かに想いを寄せていたことまで蘇り、咄嗟に返事をすることができなかった。
俯きながらもじもじと手を動かす様子に、ヴァイルが小さなため息をついた。
「まさか、いまだに執事のほうがよいなどと思っているわけではないだろうな?」
「そ、そんなことありません」
「その割には喜んでいるように見えるが?」
「ちっ、違います」
「まぁ、いいだろう。それよりさっさと服を脱げ」
「あっ、あのっ」
脱げと言いながら、あっという間にドレスも肌着も脱がされてしまった。全身真っ赤になったシュエシを軽々と抱き上げたヴァイルは、そのまま湯船に入り膝に座らせるように体を沈める。
湯船の湯が尻に触れた瞬間、シュエシは「ひぇっ!」と悲鳴を上げた。背中にもたれかかるように座らされたことに慌てふためき、腹や胸に湯が触れると声にならない悲鳴を上げながら手足をばたつかせる。
「おい、何をしている」
「だ、だって」
「暴れるな、湯がこぼれる」
「で、でも」
慌てふためくシュエシの様子に、ヴァイルは「まさか」とつぶやいた。
「湯に浸かるのは初めてか?」
「は、はい」
返事をするシュエシの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。
「やはり湯浴みの手伝いをするべきだったな」
ヴァイルの言葉に俯きながらブンブンと頭を横に振る。真っ赤な耳に唇を寄せたヴァイルが「おまえの好きな執事に手伝ってもらえばよかっただろう?」と囁くと、途端にシュエシが肩を震わせた。
「おまえは執事のほうが好きなのではないだろうな」
「そ、そんなことは、」
「それにしてはいちいち反応しているように見える」
「し、執事もヴァイルさまです。それにこんなこと、してもらうなんて、……っ」
ついに言葉が途切れた。混乱と羞恥に最後のほうは涙声になっている。それに気づいたヴァイルは小さくため息をつき、顔を隠している黒髪を耳にかけてやりながら優しく問いかけた。
「これまで湯浴みはどうしていた?」
「て、手桶に湯を入れて、布を浸して……」
「髪は洗っていただろう? なぜ体もそうしなかった?」
「お湯は、その、大切に使うものですから……」
答えながらもシュエシは湯船から出ようと手足を動かした。しかし腹に手を回され身動きが取れなくなる。その間も湯に触れている肌がピリピリとして落ち着かない。
「なるほどな。では、故郷に着くまでわたしが湯浴みの仕方を教えてやろう」
「え?」
「わたしはこうして湯に浸かるのを好む。おまえもきっと好きになる」
「でも、」
「それにこうして触れ合いながら湯を使うのもいいものだ」
「……っ」
ますます恥ずかしくなったシュエシは一瞬にして体を硬直させた。
その様子に背後で小さく笑ったヴァイルが湯船の脇に置いてある石鹸を手にした。それを湯船に入れ泡立て始める。もちろんシュエシも石鹸は知っているが、こうした使い方は見たことがなく目を見開いた。そのうち湯の表面に泡が浮き、心なしか湯もぬるりとした感触になる。「このくらいでいいか」とつぶやいたヴァイルが泡を手にし、シュエシの腕を撫で始めた。
「ひっ」
「おとなしくしろ」
「で、でも」
「洗うだけだ」
「あ、あの」
「ほら、次は胸だ」
「っ」
ぬるりとした手に胸を撫でられビクッと震えた。息を詰めていると、今度は胸の尖りを擦られ「んっ」と声が漏れる。
もう何度も撫でられたり摘まれたりしてきたというのに、ぬめりがあるからか何ともいえない感覚がした。はじめはくすぐったいような感じだったが、段々と違うものが混じり始める。ぬるっとした指に擦られるだけで背中がゾクッとし肌が粟立った。
「んふっ」
シュエシの口から漏れたのは明かな嬌声だった。慌てて唇を噛み締めグッと我慢するものの、どうしても吐息が漏れてしまう。体を洗ってもらっているのにいやらしく感じてしまっていることをヴァイルに知られるわけにはいかない。
(我慢、しないと)
何度もそう思ったが、すぐに限界を迎えた。このままでは大変なことになる。シュエシは動き回るヴァイルの手を止めようと両手で手首を掴んだ。
「ヴァ、ヴァイルさまっ」
「おとなしくしていろ」
そう囁かれ掴む力が弱くなる。
「いい子だ」
褒めるように耳元で囁いたヴァイルが、撫でていた手を胸から腹へと動かした。
「んぅっ」
鼻から抜けるような声が漏れた。慌てて唇を噛み締めるが、今度は下生えを撫でられ全身が震えてしまう。そのまま足の付け根や際どい部分を何度も撫でられ、シュエシは茹だったように耳や首を真っ赤にした。
「おまえは本当に敏感だな」
「あっ!」
いつの間にか緩く勃ち上がっていた性器を撫でられ顎が上がった。
「ここもすぐにこうなる」
「ヴァイルさま、だめ、です、っ」
「洗っているだけだ、これ以上のことはしない」
「でもっ」
「それとも、これ以上のことをしてほしいのか?」
囁く低い声に目の前でパチパチと星が瞬いた。薄く開いた黒目は快感の涙に濡れ、血色がよくなった唇から赤い舌先がチロチロと見え隠れする。
「果ててもいいぞ」
そう告げられた瞬間、シュエシの体がビクンと震えた。湯の表面を揺らすように二度、三度と腰が跳ねる。
「こうした戯れもたまには……おい」
これでもかと顔を真っ赤にしたシュエシの体から力が抜けた。腕の中でくたりとしているのを見たヴァイルが小さく唸る。
「湯に浸かったことがない体には酷だったか」
額に手を当てたヴァイルは、そのまま前髪をかき上げるとシュエシを抱いて湯船から出た。
「故郷が近づいているせいか、少し浮き足立っていた」
シュエシの全身を布で拭いながらヴァイルがそう告げる。それに答えられないほど湯あたりしていたシュエシは、いつもと雰囲気が違う声をぼんやりと聞いていた。手つきもいつもより優しく、というより壊れ物を扱うような雰囲気さえしている。
「同胞の中には他人の眷属に興味を持つものがいる。それだけならいいが、ちょっかいを出すものもいる。だからこそ故郷に入る前に血を……いや、焦ってはいけないとわかってはいる」
途切れ途切れに聞こえる声を聞きながら、シュエシはヴァイルの願いを叶えたいと思った。早く空腹になり、初めての牙でヴァイルの血を口にしたい。そうすればヴァイルも喜んでくれる。
(僕もきっと安心できる)
いや、それだけではない。ヴァイルの肌に牙を立てるのだと想像するだけで体が熱くなった。肌を重ねているときのような例えようがない興奮に頭がとろりととろける。
(早く……ヴァイルさまの血を……)
額に冷たい布が触れるのを心地よく感じながら、シュエシはゆっくりと目を閉じた。
(一緒にって、どういうことだろう)
シュエシにとって体を綺麗にする行為は、布を水に浸しそれで肌を拭うことだった。両親と旅をしていたときからそうで、両親を亡くした後もそれは変わらない。さすがに冬は湯を沸かしていたが、髪の毛を洗うほどの湯を沸かすのは大変だったため昼間に水で洗うことが多かった。
身代わりの花嫁として屋敷に住むようになってからも布で拭うのは同じだった。変わったのは毎日湯を使えるようになったことと湯がたっぷりと用意されたことで、着るものをできるだけ汚さないようにと肌が赤くなるまで擦るようにもなった。旅を始めてからもそれは変わらず、宿でも屋敷にいたときと同じように体は布で拭い髪だけ湯を使って洗っていた。
それなのに「一緒に」というのはどういうことだろう。まさか布で拭い合うということだろうか。困惑したまま立ち尽くしていると「何をしている?」と声をかけられた。
目の前ではヴァイルが裸体を惜しげもなく晒している。奥には優美な形をした大きな湯船があり、たっぷりの湯があるからか湯気が立っていた。シュエシはヴァイルを見ては顔を真っ赤にし、慌てて湯船を見ては視線をさまよわせた。
「なんだ、恥ずかしいのか? 体など何度も見ているだろう」
「そう、ですけど」
「さっさと脱げ、湯が冷めてしまうぞ」
裸のヴァイルが近づいて来る。慌てて視線を逸らしながら胸元のリボンに手をかけたものの、どうしても解くことができない。
(きっとドレスというのもよくないんだ)
旅が始まってからもヴァイルが用意するのはドレスばかりで、シュエシもそれが当たり前になっていた。だが、見られながらドレスを脱ぐというのはさすがに恥ずかしい。まるで自分が少女になってしまったかのような気になる。
「湯浴みのお手伝いをいたしましょうか?」
いつの間に近づいたのか、耳元でそんなことを囁かれギョッとした。ヴァイルが執事に扮していたときに毎日のように聞いていた言葉だからか、当時のことを思い出しうろたえる。密かに想いを寄せていたことまで蘇り、咄嗟に返事をすることができなかった。
俯きながらもじもじと手を動かす様子に、ヴァイルが小さなため息をついた。
「まさか、いまだに執事のほうがよいなどと思っているわけではないだろうな?」
「そ、そんなことありません」
「その割には喜んでいるように見えるが?」
「ちっ、違います」
「まぁ、いいだろう。それよりさっさと服を脱げ」
「あっ、あのっ」
脱げと言いながら、あっという間にドレスも肌着も脱がされてしまった。全身真っ赤になったシュエシを軽々と抱き上げたヴァイルは、そのまま湯船に入り膝に座らせるように体を沈める。
湯船の湯が尻に触れた瞬間、シュエシは「ひぇっ!」と悲鳴を上げた。背中にもたれかかるように座らされたことに慌てふためき、腹や胸に湯が触れると声にならない悲鳴を上げながら手足をばたつかせる。
「おい、何をしている」
「だ、だって」
「暴れるな、湯がこぼれる」
「で、でも」
慌てふためくシュエシの様子に、ヴァイルは「まさか」とつぶやいた。
「湯に浸かるのは初めてか?」
「は、はい」
返事をするシュエシの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。
「やはり湯浴みの手伝いをするべきだったな」
ヴァイルの言葉に俯きながらブンブンと頭を横に振る。真っ赤な耳に唇を寄せたヴァイルが「おまえの好きな執事に手伝ってもらえばよかっただろう?」と囁くと、途端にシュエシが肩を震わせた。
「おまえは執事のほうが好きなのではないだろうな」
「そ、そんなことは、」
「それにしてはいちいち反応しているように見える」
「し、執事もヴァイルさまです。それにこんなこと、してもらうなんて、……っ」
ついに言葉が途切れた。混乱と羞恥に最後のほうは涙声になっている。それに気づいたヴァイルは小さくため息をつき、顔を隠している黒髪を耳にかけてやりながら優しく問いかけた。
「これまで湯浴みはどうしていた?」
「て、手桶に湯を入れて、布を浸して……」
「髪は洗っていただろう? なぜ体もそうしなかった?」
「お湯は、その、大切に使うものですから……」
答えながらもシュエシは湯船から出ようと手足を動かした。しかし腹に手を回され身動きが取れなくなる。その間も湯に触れている肌がピリピリとして落ち着かない。
「なるほどな。では、故郷に着くまでわたしが湯浴みの仕方を教えてやろう」
「え?」
「わたしはこうして湯に浸かるのを好む。おまえもきっと好きになる」
「でも、」
「それにこうして触れ合いながら湯を使うのもいいものだ」
「……っ」
ますます恥ずかしくなったシュエシは一瞬にして体を硬直させた。
その様子に背後で小さく笑ったヴァイルが湯船の脇に置いてある石鹸を手にした。それを湯船に入れ泡立て始める。もちろんシュエシも石鹸は知っているが、こうした使い方は見たことがなく目を見開いた。そのうち湯の表面に泡が浮き、心なしか湯もぬるりとした感触になる。「このくらいでいいか」とつぶやいたヴァイルが泡を手にし、シュエシの腕を撫で始めた。
「ひっ」
「おとなしくしろ」
「で、でも」
「洗うだけだ」
「あ、あの」
「ほら、次は胸だ」
「っ」
ぬるりとした手に胸を撫でられビクッと震えた。息を詰めていると、今度は胸の尖りを擦られ「んっ」と声が漏れる。
もう何度も撫でられたり摘まれたりしてきたというのに、ぬめりがあるからか何ともいえない感覚がした。はじめはくすぐったいような感じだったが、段々と違うものが混じり始める。ぬるっとした指に擦られるだけで背中がゾクッとし肌が粟立った。
「んふっ」
シュエシの口から漏れたのは明かな嬌声だった。慌てて唇を噛み締めグッと我慢するものの、どうしても吐息が漏れてしまう。体を洗ってもらっているのにいやらしく感じてしまっていることをヴァイルに知られるわけにはいかない。
(我慢、しないと)
何度もそう思ったが、すぐに限界を迎えた。このままでは大変なことになる。シュエシは動き回るヴァイルの手を止めようと両手で手首を掴んだ。
「ヴァ、ヴァイルさまっ」
「おとなしくしていろ」
そう囁かれ掴む力が弱くなる。
「いい子だ」
褒めるように耳元で囁いたヴァイルが、撫でていた手を胸から腹へと動かした。
「んぅっ」
鼻から抜けるような声が漏れた。慌てて唇を噛み締めるが、今度は下生えを撫でられ全身が震えてしまう。そのまま足の付け根や際どい部分を何度も撫でられ、シュエシは茹だったように耳や首を真っ赤にした。
「おまえは本当に敏感だな」
「あっ!」
いつの間にか緩く勃ち上がっていた性器を撫でられ顎が上がった。
「ここもすぐにこうなる」
「ヴァイルさま、だめ、です、っ」
「洗っているだけだ、これ以上のことはしない」
「でもっ」
「それとも、これ以上のことをしてほしいのか?」
囁く低い声に目の前でパチパチと星が瞬いた。薄く開いた黒目は快感の涙に濡れ、血色がよくなった唇から赤い舌先がチロチロと見え隠れする。
「果ててもいいぞ」
そう告げられた瞬間、シュエシの体がビクンと震えた。湯の表面を揺らすように二度、三度と腰が跳ねる。
「こうした戯れもたまには……おい」
これでもかと顔を真っ赤にしたシュエシの体から力が抜けた。腕の中でくたりとしているのを見たヴァイルが小さく唸る。
「湯に浸かったことがない体には酷だったか」
額に手を当てたヴァイルは、そのまま前髪をかき上げるとシュエシを抱いて湯船から出た。
「故郷が近づいているせいか、少し浮き足立っていた」
シュエシの全身を布で拭いながらヴァイルがそう告げる。それに答えられないほど湯あたりしていたシュエシは、いつもと雰囲気が違う声をぼんやりと聞いていた。手つきもいつもより優しく、というより壊れ物を扱うような雰囲気さえしている。
「同胞の中には他人の眷属に興味を持つものがいる。それだけならいいが、ちょっかいを出すものもいる。だからこそ故郷に入る前に血を……いや、焦ってはいけないとわかってはいる」
途切れ途切れに聞こえる声を聞きながら、シュエシはヴァイルの願いを叶えたいと思った。早く空腹になり、初めての牙でヴァイルの血を口にしたい。そうすればヴァイルも喜んでくれる。
(僕もきっと安心できる)
いや、それだけではない。ヴァイルの肌に牙を立てるのだと想像するだけで体が熱くなった。肌を重ねているときのような例えようがない興奮に頭がとろりととろける。
(早く……ヴァイルさまの血を……)
額に冷たい布が触れるのを心地よく感じながら、シュエシはゆっくりと目を閉じた。
67
お気に入りに追加
164
あなたにおすすめの小説

追放文官、幸せなキスで旅に出る
にっきょ
BL
かつて恋人に裏切られ、追放された元文官のコーディエライト・スプリンゲンは、雪山の中で一人、写本師として暮らしていた。
ある日、ダイモンと名乗る旅の剣士を雪崩から助けたコーディエは、ダイモンにお礼として春まで家事を手伝うことを提案される。
最初はダイモンのことを邪魔に思っていたが、段々と離れがたい気持ちになっていくコーディエ。
そんなコーディエを、ダイモンは旅に誘うのだった。
春の雪解けは、すぐそこに。
夏の雰囲気を纏った青年×ツンギレ引きこもりBL
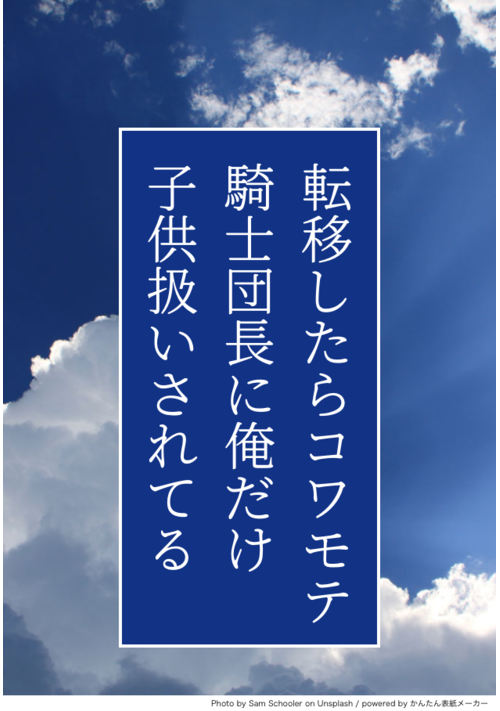
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

龍神様の神使
石動なつめ
BL
顔にある花の痣のせいで、忌み子として疎まれて育った雪花は、ある日父から龍神の生贄となるように命じられる。
しかし当の龍神は雪花を喰らおうとせず「うちで働け」と連れ帰ってくれる事となった。
そこで雪花は彼の神使である蛇の妖・立待と出会う。彼から優しく接される内に雪花の心の傷は癒えて行き、お互いにだんだんと惹かれ合うのだが――。
※少々際どいかな、という内容・描写のある話につきましては、タイトルに「*」をつけております。

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語
紅林
BL
『桜田門学院高等学校』
日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ
しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ
そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である

魔王様の胸のうち
朏猫(ミカヅキネコ)
BL
勇者は人間のために魔王と戦う――はるか昔からくり返される魔王と勇者の戦いが始まった。勇者は単独で魔王の城へ乗り込み、聖剣をもって魔王を打ち倒そうとする。一方、魔王は書物でしか読んだことのない現象――“恋”というものを確かめるべく、日々勇者を観察していた。※他サイトにも掲載
[勇者 × 魔王 / BL]

悪役令息の七日間
リラックス@ピロー
BL
唐突に前世を思い出した俺、ユリシーズ=アディンソンは自分がスマホ配信アプリ"王宮の花〜神子は7色のバラに抱かれる〜"に登場する悪役だと気付く。しかし思い出すのが遅過ぎて、断罪イベントまで7日間しか残っていない。
気づいた時にはもう遅い、それでも足掻く悪役令息の話。【お知らせ:2024年1月18日書籍発売!】

【完結】今宵、愛を飲み干すまで
夏目みよ
BL
西外れにあるウェルズ高等学園という寮制の夜間学校に通うリック。
その昔、この国では人ならざる者が住んでいたらしく、人間ではない子どもたちが夜間学校に通っていたそうだ。でもそれはあくまで昔の話。リック自身、吸血鬼や悪魔、魔法使いを見たことがない。
そんな折、リックの寮部屋に時期外れの編入生がやってくるという。
そいつは青い瞳に艷やかな濃紺の髪、透き通るような肌を持つ男で、リックから見てもゾッとするほどに美しかった。しかし、性格は最悪でリックとは馬が合わない。
とある日、リックは相性最悪な編入生のレイから、部屋を一時的に貸して欲しいとお願いされる。その間、絶対に部屋へは入るなと言われるリックだったが、その約束を破り、部屋に入ってしまって――
「馬鹿な奴だ。部屋には入るなと言っただろう?」
吸血鬼✕人間???の人外BLです。

【完結】伯爵家当主になりますので、お飾りの婚約者の僕は早く捨てて下さいね?
MEIKO
BL
【完結】そのうち番外編更新予定。伯爵家次男のマリンは、公爵家嫡男のミシェルの婚約者として一緒に過ごしているが実際はお飾りの存在だ。そんなマリンは池に落ちたショックで前世は日本人の男子で今この世界が小説の中なんだと気付いた。マズい!このままだとミシェルから婚約破棄されて路頭に迷うだけだ┉。僕はそこから前世の特技を活かしてお金を貯め、ミシェルに愛する人が現れるその日に備えだす。2年後、万全の備えと新たな朗報を得た僕は、もう婚約破棄してもらっていいんですけど?ってミシェルに告げた。なのに対象外のはずの僕に未練たらたらなの何で!?
※R対象話には『*』マーク付けますが、後半付近まで出て来ない予定です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















