19 / 28
後宮に繋がれし王子と新たな妃
6 暴漢2
しおりを挟む
「はな……っ」
離してと言いかけた口は、大きな手に塞がれて声にならなかった。あっという間の出来事で、手を避けることも逃げ出すこともできなかった。
知らない人は僕にとって不安の対象でしかない。しかも見慣れない真っ黒な軍服姿の人たちだ。慌てて部屋に戻ろうとしたけれど、一人に腕を掴まれ、声を出そうとしたら別の軍人に口を塞がれ、さらにもう一人に腰を掴まれて動けなくなった。
(この人たちは、誰なんだろう)
僕はいま、四阿に敷かれた植物製の敷物の上に体を押さえつけられている。僕を見下ろしている軍人の向こう側には、いま起きていることが現実なのか夢なのかわからなくなるくらい綺麗な青空が広がっていた。
「思った以上の上玉だぞ」
「あの軍帝が囲っているぐらいだ、よっぽどの奴だろうと思っていたが……。こりゃあ、こっちが金を積んででもやりたくなるような上玉だな」
何の話をしているのだろう。“じょうだま”というのは、もしかして僕のことだろうか。金を積んでという意味もわからない。
「もうここでヤッちまってもいいんじゃねぇか? 誰も来ないようにしてあるんなら、どこでヤッても同じだろ」
「滅んだ国の王子とは言え王子様だ、青姦なんてしたことねぇだろうなぁ。興奮してすげぇ乱れるかもしれねぇな」
「わからねぇぞ? あの軍帝のことだから、とっくに後宮のあちこちで経験済みって可能性もある」
「ははっ、違いねぇ!」
「もとは俺たちと同じ平民出身の軍人様だからな。青姦も拷問性交も調教もお手のものだろうよ」
耳障りな笑い声が聞こえる。僕を抑えつけている男たちが、笑いながら乱暴な手つきで上着をめくり上げた。
(あぁ、あのときと同じだ)
塔で衛兵に襲われたときとそっくりだと思った。あのときは衛兵一人か、従僕がいても見ているだけだった。いま僕を抑えつけているのは三人の軍人だけれど、ギラギラした目はあの人たちと変わらない。
軍人の一人が上着の下のシャツを破くように引っ張った。首が引っ張られて痛かったけれど、痛みを感じた直後に肌に触れられて気持ち悪さが上回る。
(あのときと、全部同じだ)
あのときもギラギラした目で見られた。同じようなギラギラした三人の目が僕を見下ろし、そうして胸やお腹を撫で回している。身をよじろうとしても、すぐに押さえつけられて動けなくなった。
足を押さえつけていた手がズボンに掛かるのがわかった。そうして下着ごと剥ぎ取るのもあのときと同じだ。
(祖国でも帝国でも同じなんだ)
まるで他人事のようにそう思った。
「こりゃあ、とんでもねぇ上玉だな」
「肌つやと言い白さと言い、そこら辺の高級娼婦よりよっぽど上玉だぞ」
「おいおい、こっちの毛は髪より薄い金色だ。それにやたら初心な色じゃねぇか。こりゃあたまんねぇな」
気がつけば両手を頭上に押さえつけられ、めくり上げられた上着が首に巻きついて少し苦しかった。中に着ていたシャツのボタンは飛んでいき、はだけた上半身はゴツゴツした手に執拗に撫で回されている。
何も身につけていない下半身も似たようなものだった。太ももを撫で回され、萎えたままの前を執拗にいじられた。
(気持ち、悪い)
知らない手の感触が気持ち悪くてたまらない。男たちの荒い息が体のあちこちに触れるだけで吐きそうになる。口を手で塞がれていなければ、ひどい声で叫びながら嘔吐したかもしれない。けれど、それさえも叶わない。
「おい、もういいだろ。早く突っ込ませろよ」
「待てって。ちゃんとほぐさねぇと自分も痛いぞ」
目の前で男が自分の指を舐めている。僕の後ろに入れるための準備だろう。
最後に塔で僕が襲われたときも衛兵が同じことをしていた。あのときは前日に魔石を採取した日だったからか、乱暴に指を入れられても怪我はしなかった。けれど、まったく痛みがないわけじゃない。
そこで僕の記憶は途切れたけれど、今回も入れるところまでは意識があるに違いない。もしかすると、その先も気を失わないかもしれない。だって、ここには僕を守ってくれる兄上様の魔具はないのだ。
(……嫌だ、こんなの、もう嫌だ……)
ギラギラした軍人たちの目に、塔にいたときの恐怖を思い出した。僕を撫で回す手にどんどん恐怖が蘇ってくる。
この男たちも、ただ僕を犯したいだけの獣と一緒だ。僕は昔からそんな人たちを引き寄せてきた。きっと僕が卑しい“魔血”の血筋だからだ。卑しい方法で魔石を生み出す存在だから、こうした獣たちを呼び寄せるに違いない。
(もう、大丈夫だと、思っていたのに)
軍帝に出会って、軍帝に「俺の妃だ」と言われてようやく卑しい自分じゃないと思えるようになった。兄上様に素直に感じていいのだと言われ、魔石を生み出さなくてもいいと言われ、僕は生まれ変わったような気になっていた。
けれど、本当は何も変わっていなかった。やっぱり僕は“魔血”の錆で、とりわけその力を濃く受け継いだ“魔純の御子”だ。魔石を生み出さなくても、こうして延々と卑しい行為を強要されるだけの存在であることは変わりようがない。
「さぁて、まずは一本だな」
「……っ」
男の指が後ろに入ってきた。入れるというよりも突き刺すと表現したほうがいいくらい乱暴な仕草で、ズキッとした痛みが走る。思わず眉を寄せたけれど、そんな僕のことなどお構いなしに、ただ入れる穴だと言わんばかりに乱暴に指を動かし始める。
(こうされるのも、僕が卑しいからだ)
こんなことは嫌なのに、グチグチとぬめった音が聞こえ始めた。嫌で仕方がないのに、怖くてたまらないのに、僕の体は勝手に火照ってしまう。軍帝じゃないとわかっているのに、後ろが勝手に受け入れようとほころぶのがわかった。
(全部、僕が“魔血”で卑しいせいだ)
そうだ、僕はどこにいても“魔血”だ。魔石を生み出さなくても“魔純の御子”であることからは逃れられない。僕はこの先もずっと卑しい僕のままなのだろう。そう思うと心がスッと凍えるような気がした。
段々と何も感じなくなってきた。後ろをいじられる痛みも、これからされるであろう行為への恐怖も何も感じなくなっていく。
(まるで、本当に人形になったみたいだ)
自分が魔石で動く魔具人形になったような気がした。その証拠に、僕を押さえつけている軍人の向こう側に見える青空はいつまで経っても綺麗な空のままだった。涙で滲むことなんてまったくない。口を塞いでいた手はとっくに離れているのに、悲鳴さえ漏れなかった。
グルルルルル。
不意に獣の鳴くような声が聞こえた気がした。後宮のどこかに獣がいるのだろうか。
(……違う、僕の中から聞こえるんだ)
体の深くで獣の唸り声のような響きを感じる。澱んだ魔力が暴れ出そうとしている気配がした。澱みは溜まっていないはずなのに、明らかに膨大な魔力が渦巻くような感覚がする。
(そういえば、前にもこんなことがあったような……)
あれは衛兵に襲われそうになった三度目、いや四度目だっただろうか。ちょうど魔石を採取する直前で、とくに澱みが濃くなっていたときだった。あのときは従僕が手引きをしたようで、老齢の従僕の前で若い衛兵にのし掛かられた。いまと同じように上着を剥ぎ取られ、下半身を裸にされた。
(そして、同じように後ろに指を入れられた)
あのときも痛くてたまらなかった。兄上様とはまったく違う熱と感触に恐怖を感じた。それなのにすぐに熱くなる自分の体が嫌で、そう思うだけで体の底に澱む魔力が膨らむのを感じた。
(そうだ、あのときと同じだ)
違う、あのときだけじゃない。襲われたときはいつも魔力が暴れ出そうとするのを感じていたような気がする。いまと同じように唸り声のようなものも聞こえた。
唸り声が聞こえると、僕はいつも気を失った。そうして目が覚めると傍らには必ず兄上様がいて、つらそうな目で僕を見た。「大丈夫、何もなかったからね」と言う兄上様を見るたびに、己の身一つ守れない自分を情けなく思った。
グルルルルル。
あぁ、また唸り声が聞こえている。あのときもこうして澱みが渦巻き唸るように動いていた。その澱みが段々膨らんでいくのがわかる。そうして真っ黒なそれが大きくて真っ赤な口を開き、僕の中を掻き混ぜている指に……。
「うぎゃあっ」
叫び声とともに後ろに感じていた圧迫感が消えた。
「な、なんだよ、これ……!」
「ひ、ひぃっ! 化け物……!」
また叫び声が聞こえた。それだけじゃなく、何か柔らかなものが潰れるような音も聞こえた。熟した果物がブチュッと潰れるような音がして、果汁のようなものが滴るのを感じる。
「ひぃ……!」
「や、やめろ……!」
耳障りな軍人たちの声と同時に、僕を押さえつけていた重みが消えた。
(一体どうしたんだろう)
こういう声を聞くのは初めてだ。もしかして、後宮にも兄上様の魔具が仕掛けられていて僕を守ってくれたのだろうか。
青空を見ながらそんなことを思っていると、誰かが近づいて来る足音がした。
「俺がもっとも大事にしているものに手ぇ出して、そのくらいで済んだんだ。よかったじゃねぇか」
聞こえて来た声にゆっくりと顔を動かす。そこには、会いたくないけれど一番会いたかった軍帝の姿があった。
離してと言いかけた口は、大きな手に塞がれて声にならなかった。あっという間の出来事で、手を避けることも逃げ出すこともできなかった。
知らない人は僕にとって不安の対象でしかない。しかも見慣れない真っ黒な軍服姿の人たちだ。慌てて部屋に戻ろうとしたけれど、一人に腕を掴まれ、声を出そうとしたら別の軍人に口を塞がれ、さらにもう一人に腰を掴まれて動けなくなった。
(この人たちは、誰なんだろう)
僕はいま、四阿に敷かれた植物製の敷物の上に体を押さえつけられている。僕を見下ろしている軍人の向こう側には、いま起きていることが現実なのか夢なのかわからなくなるくらい綺麗な青空が広がっていた。
「思った以上の上玉だぞ」
「あの軍帝が囲っているぐらいだ、よっぽどの奴だろうと思っていたが……。こりゃあ、こっちが金を積んででもやりたくなるような上玉だな」
何の話をしているのだろう。“じょうだま”というのは、もしかして僕のことだろうか。金を積んでという意味もわからない。
「もうここでヤッちまってもいいんじゃねぇか? 誰も来ないようにしてあるんなら、どこでヤッても同じだろ」
「滅んだ国の王子とは言え王子様だ、青姦なんてしたことねぇだろうなぁ。興奮してすげぇ乱れるかもしれねぇな」
「わからねぇぞ? あの軍帝のことだから、とっくに後宮のあちこちで経験済みって可能性もある」
「ははっ、違いねぇ!」
「もとは俺たちと同じ平民出身の軍人様だからな。青姦も拷問性交も調教もお手のものだろうよ」
耳障りな笑い声が聞こえる。僕を抑えつけている男たちが、笑いながら乱暴な手つきで上着をめくり上げた。
(あぁ、あのときと同じだ)
塔で衛兵に襲われたときとそっくりだと思った。あのときは衛兵一人か、従僕がいても見ているだけだった。いま僕を抑えつけているのは三人の軍人だけれど、ギラギラした目はあの人たちと変わらない。
軍人の一人が上着の下のシャツを破くように引っ張った。首が引っ張られて痛かったけれど、痛みを感じた直後に肌に触れられて気持ち悪さが上回る。
(あのときと、全部同じだ)
あのときもギラギラした目で見られた。同じようなギラギラした三人の目が僕を見下ろし、そうして胸やお腹を撫で回している。身をよじろうとしても、すぐに押さえつけられて動けなくなった。
足を押さえつけていた手がズボンに掛かるのがわかった。そうして下着ごと剥ぎ取るのもあのときと同じだ。
(祖国でも帝国でも同じなんだ)
まるで他人事のようにそう思った。
「こりゃあ、とんでもねぇ上玉だな」
「肌つやと言い白さと言い、そこら辺の高級娼婦よりよっぽど上玉だぞ」
「おいおい、こっちの毛は髪より薄い金色だ。それにやたら初心な色じゃねぇか。こりゃあたまんねぇな」
気がつけば両手を頭上に押さえつけられ、めくり上げられた上着が首に巻きついて少し苦しかった。中に着ていたシャツのボタンは飛んでいき、はだけた上半身はゴツゴツした手に執拗に撫で回されている。
何も身につけていない下半身も似たようなものだった。太ももを撫で回され、萎えたままの前を執拗にいじられた。
(気持ち、悪い)
知らない手の感触が気持ち悪くてたまらない。男たちの荒い息が体のあちこちに触れるだけで吐きそうになる。口を手で塞がれていなければ、ひどい声で叫びながら嘔吐したかもしれない。けれど、それさえも叶わない。
「おい、もういいだろ。早く突っ込ませろよ」
「待てって。ちゃんとほぐさねぇと自分も痛いぞ」
目の前で男が自分の指を舐めている。僕の後ろに入れるための準備だろう。
最後に塔で僕が襲われたときも衛兵が同じことをしていた。あのときは前日に魔石を採取した日だったからか、乱暴に指を入れられても怪我はしなかった。けれど、まったく痛みがないわけじゃない。
そこで僕の記憶は途切れたけれど、今回も入れるところまでは意識があるに違いない。もしかすると、その先も気を失わないかもしれない。だって、ここには僕を守ってくれる兄上様の魔具はないのだ。
(……嫌だ、こんなの、もう嫌だ……)
ギラギラした軍人たちの目に、塔にいたときの恐怖を思い出した。僕を撫で回す手にどんどん恐怖が蘇ってくる。
この男たちも、ただ僕を犯したいだけの獣と一緒だ。僕は昔からそんな人たちを引き寄せてきた。きっと僕が卑しい“魔血”の血筋だからだ。卑しい方法で魔石を生み出す存在だから、こうした獣たちを呼び寄せるに違いない。
(もう、大丈夫だと、思っていたのに)
軍帝に出会って、軍帝に「俺の妃だ」と言われてようやく卑しい自分じゃないと思えるようになった。兄上様に素直に感じていいのだと言われ、魔石を生み出さなくてもいいと言われ、僕は生まれ変わったような気になっていた。
けれど、本当は何も変わっていなかった。やっぱり僕は“魔血”の錆で、とりわけその力を濃く受け継いだ“魔純の御子”だ。魔石を生み出さなくても、こうして延々と卑しい行為を強要されるだけの存在であることは変わりようがない。
「さぁて、まずは一本だな」
「……っ」
男の指が後ろに入ってきた。入れるというよりも突き刺すと表現したほうがいいくらい乱暴な仕草で、ズキッとした痛みが走る。思わず眉を寄せたけれど、そんな僕のことなどお構いなしに、ただ入れる穴だと言わんばかりに乱暴に指を動かし始める。
(こうされるのも、僕が卑しいからだ)
こんなことは嫌なのに、グチグチとぬめった音が聞こえ始めた。嫌で仕方がないのに、怖くてたまらないのに、僕の体は勝手に火照ってしまう。軍帝じゃないとわかっているのに、後ろが勝手に受け入れようとほころぶのがわかった。
(全部、僕が“魔血”で卑しいせいだ)
そうだ、僕はどこにいても“魔血”だ。魔石を生み出さなくても“魔純の御子”であることからは逃れられない。僕はこの先もずっと卑しい僕のままなのだろう。そう思うと心がスッと凍えるような気がした。
段々と何も感じなくなってきた。後ろをいじられる痛みも、これからされるであろう行為への恐怖も何も感じなくなっていく。
(まるで、本当に人形になったみたいだ)
自分が魔石で動く魔具人形になったような気がした。その証拠に、僕を押さえつけている軍人の向こう側に見える青空はいつまで経っても綺麗な空のままだった。涙で滲むことなんてまったくない。口を塞いでいた手はとっくに離れているのに、悲鳴さえ漏れなかった。
グルルルルル。
不意に獣の鳴くような声が聞こえた気がした。後宮のどこかに獣がいるのだろうか。
(……違う、僕の中から聞こえるんだ)
体の深くで獣の唸り声のような響きを感じる。澱んだ魔力が暴れ出そうとしている気配がした。澱みは溜まっていないはずなのに、明らかに膨大な魔力が渦巻くような感覚がする。
(そういえば、前にもこんなことがあったような……)
あれは衛兵に襲われそうになった三度目、いや四度目だっただろうか。ちょうど魔石を採取する直前で、とくに澱みが濃くなっていたときだった。あのときは従僕が手引きをしたようで、老齢の従僕の前で若い衛兵にのし掛かられた。いまと同じように上着を剥ぎ取られ、下半身を裸にされた。
(そして、同じように後ろに指を入れられた)
あのときも痛くてたまらなかった。兄上様とはまったく違う熱と感触に恐怖を感じた。それなのにすぐに熱くなる自分の体が嫌で、そう思うだけで体の底に澱む魔力が膨らむのを感じた。
(そうだ、あのときと同じだ)
違う、あのときだけじゃない。襲われたときはいつも魔力が暴れ出そうとするのを感じていたような気がする。いまと同じように唸り声のようなものも聞こえた。
唸り声が聞こえると、僕はいつも気を失った。そうして目が覚めると傍らには必ず兄上様がいて、つらそうな目で僕を見た。「大丈夫、何もなかったからね」と言う兄上様を見るたびに、己の身一つ守れない自分を情けなく思った。
グルルルルル。
あぁ、また唸り声が聞こえている。あのときもこうして澱みが渦巻き唸るように動いていた。その澱みが段々膨らんでいくのがわかる。そうして真っ黒なそれが大きくて真っ赤な口を開き、僕の中を掻き混ぜている指に……。
「うぎゃあっ」
叫び声とともに後ろに感じていた圧迫感が消えた。
「な、なんだよ、これ……!」
「ひ、ひぃっ! 化け物……!」
また叫び声が聞こえた。それだけじゃなく、何か柔らかなものが潰れるような音も聞こえた。熟した果物がブチュッと潰れるような音がして、果汁のようなものが滴るのを感じる。
「ひぃ……!」
「や、やめろ……!」
耳障りな軍人たちの声と同時に、僕を押さえつけていた重みが消えた。
(一体どうしたんだろう)
こういう声を聞くのは初めてだ。もしかして、後宮にも兄上様の魔具が仕掛けられていて僕を守ってくれたのだろうか。
青空を見ながらそんなことを思っていると、誰かが近づいて来る足音がした。
「俺がもっとも大事にしているものに手ぇ出して、そのくらいで済んだんだ。よかったじゃねぇか」
聞こえて来た声にゆっくりと顔を動かす。そこには、会いたくないけれど一番会いたかった軍帝の姿があった。
6
お気に入りに追加
570
あなたにおすすめの小説

見習い薬師は臆病者を抱いて眠る
XCX
BL
見習い薬師であるティオは、同期である兵士のソルダートに叶わぬ恋心を抱いていた。だが、生きて戻れる保証のない、未知未踏の深淵の森への探索隊の一員に選ばれたティオは、玉砕を知りつつも想いを告げる。
傷心のまま探索に出発した彼は、森の中で一人はぐれてしまう。身を守る術を持たないティオは——。
人嫌いな子持ち狐獣人×見習い薬師。

悪役令息の七日間
リラックス@ピロー
BL
唐突に前世を思い出した俺、ユリシーズ=アディンソンは自分がスマホ配信アプリ"王宮の花〜神子は7色のバラに抱かれる〜"に登場する悪役だと気付く。しかし思い出すのが遅過ぎて、断罪イベントまで7日間しか残っていない。
気づいた時にはもう遅い、それでも足掻く悪役令息の話。【お知らせ:2024年1月18日書籍発売!】

釣った魚、逃した魚
円玉
BL
瘴気や魔獣の発生に対応するため定期的に行われる召喚の儀で、浄化と治癒の力を持つ神子として召喚された三倉貴史。
王の寵愛を受け後宮に迎え入れられたかに見えたが、後宮入りした後は「釣った魚」状態。
王には放置され、妃達には嫌がらせを受け、使用人達にも蔑ろにされる中、何とか穏便に後宮を去ろうとするが放置していながら縛り付けようとする王。
護衛騎士マクミランと共に逃亡計画を練る。
騎士×神子 攻目線
一見、神子が腹黒そうにみえるかもだけど、実際には全く悪くないです。
どうしても文字数が多くなってしまう癖が有るので『一話2500文字以下!』を目標にした練習作として書いてきたもの。
ムーンライト様でもアップしています。

孤独な王弟は初めての愛を救済の聖者に注がれる
葉月めいこ
BL
ラーズヘルム王国の王弟リューウェイクは親兄弟から放任され、自らの力で第三騎士団の副団長まで上り詰めた。
王家や城の中枢から軽んじられながらも、騎士や国の民と信頼を築きながら日々を過ごしている。
国王は在位11年目を迎える前に、自身の治世が加護者である女神に護られていると安心を得るため、古くから伝承のある聖女を求め、異世界からの召喚を決行した。
異世界人の召喚をずっと反対していたリューウェイクは遠征に出たあと伝令が届き、慌てて帰還するが時すでに遅く召喚が終わっていた。
召喚陣の上に現れたのは男女――兄妹2人だった。
皆、女性を聖女と崇め男性を蔑ろに扱うが、リューウェイクは女神が二人を選んだことに意味があると、聖者である雪兎を手厚く歓迎する。
威風堂々とした雪兎は為政者の風格があるものの、根っこの部分は好奇心旺盛で世話焼きでもあり、不遇なリューウェイクを気にかけいたわってくれる。
なぜ今回の召喚されし者が二人だったのか、その理由を知ったリューウェイクは苦悩の選択に迫られる。
召喚されたスパダリ×生真面目な不憫男前
全38話
こちらは個人サイトにも掲載されています。

[完結]堕とされた亡国の皇子は剣を抱く
小葉石
BL
今は亡きガザインバーグの名を継ぐ最後の亡国の皇子スロウルは実の父に幼き頃より冷遇されて育つ。
10歳を過ぎた辺りからは荒くれた男達が集まる討伐部隊に強引に入れられてしまう。
妖精姫との名高い母親の美貌を受け継ぎ、幼い頃は美少女と言われても遜色ないスロウルに容赦ない手が伸びて行く…
アクサードと出会い、思いが通じるまでを書いていきます。
※亡国の皇子は華と剣を愛でる、
のサイドストーリーになりますが、この話だけでも楽しめるようにしますので良かったらお読みください。
際どいシーンは*をつけてます。
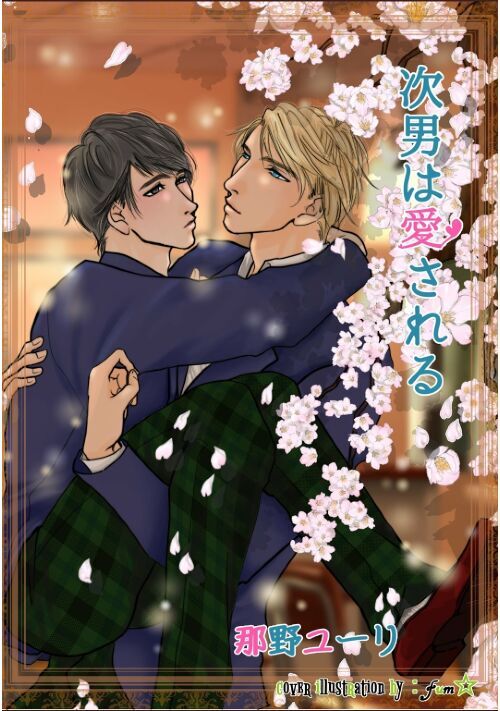
次男は愛される
那野ユーリ
BL
ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男
佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。
素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡
無断転載は厳禁です。
【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】
12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。
近況ボードをご覧下さい。

【完結】藤華の君 あかねの香
水樹風
BL
その出会いは、薄紫の花の下で……。
青龍の帝が治める大国『東の国』。
先帝の急逝で若くして即位した今上帝・孝龍。
冷血な暴君であると言われる帝は、忠誠の証として、特別な民『四族』の朱雀一族に後宮へ妃をあげることを命じた。
南の朱雀の一族に生まれながらも【賤(オメガ)】だったために、領地の外れに追放され暮らしてきた朱寧は、父親の命令で人質として孝龍に嫁ぐことになるのだが……。
◇ 世界観はあくまで創作です。
◇ この作品は、以前投稿していた同名作品の加筆改稿版です。
◇ 全27話予定。

侯爵様の愛人ですが、その息子にも愛されてます
muku
BL
魔術師フィアリスは、地底の迷宮から湧き続ける魔物を倒す使命を担っているリトスロード侯爵家に雇われている。
仕事は魔物の駆除と、侯爵家三男エヴァンの家庭教師。
成人したエヴァンから突然恋心を告げられたフィアリスは、大いに戸惑うことになる。
何故ならフィアリスは、エヴァンの父とただならぬ関係にあったのだった。
汚れた自分には愛される価値がないと思いこむ美しい魔術師の青年と、そんな師を一心に愛し続ける弟子の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















