18 / 28
後宮に繋がれし王子と新たな妃
5 暴漢1
しおりを挟む
ツアル姫が服を持って来てから三日が経った。この三日間はお茶に誘われることも何かを贈りたいと言われることもなかった。それに安堵しつつ、毎日ぼんやり過ごすだけで日課だった中庭の散歩もしていない。
お付きの人たちが用意する食事も食べたり食べなかったりしながら、軍帝が帰ってくるのをただ待っていた。待ちながら、何度もツアル姫の言葉を思い出した。
もし本当に後宮を出なくてはいけないのなら、このまま軍帝に会わないほうがいいのかもしれない。会ってしまえば離れがたくなるだろうし、後宮に残りたいと言ってしまうかもしれない。そう思ったけれど、結局後宮を出る覚悟はできないままだ。
「もし、陛下に直接後宮を去れと言われたら……」
そう思うだけで胸が痛くなる。軍帝に命じられたら出なくてはいけないけれど、果たして自分の足でちゃんと出て行けるだろうか。何より胸が痛くて動けなくなるかもしれない。
僕が原因で祖国が滅んだのだとわかったときも胸が痛んだ。けれど、あのときよりもいまのほうがずっと痛い。
「僕はなんて薄情な王子なんだろう」
僕のために、きっと大勢の人たちがひどい目に遭ったはずだ。それに胸を痛めるより軍帝のそばにいられなくなることのほうがずっとつらいなんて、さすがにひどいと僕自身も思う。
「でも、いまのほうがつらいんだ」
それに胸がツキツキするたびに体の深くで魔力が蠢くような感覚もある。これは国が滅んだときには感じなかったことだ。
澱んだ真っ黒なものが小さな渦を巻き、それが日に日に大きくなっている気がする。溜まっているはずがない澱みを感じるたびに気持ち悪くなって気鬱になる。
この感覚は食事をしても湯浴みをしても消えることはなかった。気分だけではなく体も重く感じるせいで、湯浴みをするのもおっくうになる。けれどお付きの人たちは二日に一度は湯浴みをするようにと僕のそばに立ち、湯殿に行くまで離れようとしなかった。これも軍帝の命令なのだろう。
今日も暗くなると全身真っ白なお付きの人たちが現れ、湯殿に促された。体を磨き、髪を洗い、すべてが終わると全身を柔らかな布で包まれて拭われる。同時に伸びた髪の毛を魔具で乾かし、香油をつけてから美しい細工をされた櫛で梳かれた。
軍帝が第二都市に向かった日の夜から、渡りがあるわけでもないのに毎回柑橘の香りがする香油を使われるようになった。以前はこの香りを嗅ぐだけで軍帝を思い出し体が火照っていた。けれど、いまは香油の瓶を見るだけで胸が苦しくなる。
(何も考えないようにしよう)
そうすれば胸が苦しくなることもつらくなることもない。軍帝のことを考えなければ、以前と同じように過ごせるはずだ。
何も考えず、何も感じないようにする。塔にいた頃のように、ただ毎日をくり返せばいい。
(なんだか、人形みたいだな)
ふと、そんなことを思った。そういえば、塔にいた頃は毎日がそんな感じだった。兄上様が来るときは違ったけれど、帝国に来てからのように気持ちが華やぐことはなかった気がする。
(……僕は、こんな顔だっただろうか)
手入れのときに目の前に置かれる手鏡には僕が映っている。映っているのは間違いなく僕なのに、なぜか知らない人のように見えた。
真っ白な肌に瑠璃色の眼が宝石のように冷たく光っている。いや、宝石よりも硝子玉のほうが近いかもしれない。まるで魔石で動く魔具の人形になったような気がして、鏡からそっと視線を外した。
二日後には軍帝が帰って来る。あれだけ待ちわびていたのに、いまは帰ってきてほしくないと思っている。
軍帝が帰ってきたら、僕は後宮から出ることになるのだろう。その後どこに行くのかはわからないけれど、もう二度と軍帝に会うことは叶わないに違いない。
「そうなったら、二度と触れてもらえなくなる」
それは会えないことと同じくらいつらいことだった。僕ではどうすることもできない魔力を喰らってもらえないからじゃない。あの大きな手に触れてもらえなくなる、逞しい腕に抱きしめてもらえなくなると思うだけで、息ができなくなるくらい苦しくなるのだ。
それでもここは皇帝が住む場所だから、軍帝は必ず帰ってくる。それを待つのが僕の役目……だった。
「そうか、今回が最後かもしれないんだ」
軍帝の帰りを待つのは今回が最初で最後だ。そう思うとやっぱり胸が痛むけれど、仕方がないことだと諦めの気持ちも少しだけあった。ツアル姫が言うとおり、僕が出て行くのがよいのだとどこかで悟っているからかもしれない。
「ここで過ごすのも、あとわずかということだな」
そう思うと、黄玉宮での生活が途端に得がたいもののように思えてきた。塔よりずっと広い部屋や、いつの間にか見慣れていた家具や窓から見える景色が宝物のように思えてくる。
「……そうだ、中庭を見ておこう」
黄玉宮の中でも僕が一番好きなのは中庭だ。初めて本物の花を軍帝と一緒に見たとき、僕は世界一素敵な場所だと思った。そんな思い出深い中庭を、これから先も忘れずにいた。そう思い、久しぶりに中庭の四阿に向かうことにした。
四阿にある椅子に座って中庭を眺める。青々とした木々の葉が風に揺れて、その下には色とりどりの花が咲いていて心地いい。
僕が黄玉宮に来たとき、中庭に花は咲いていなかった。塔で本物の花を見たことがなかった僕は、ここでも見られないのかと残念に思った。僕が沈んでいるのが軍帝に伝わったのだろう。理由を尋ねられ、正直に話した翌日にはたくさんの花が中庭に咲いていた。
軍帝が「おまえには花がよく似合う」と笑っていたのを思い出す。そう言われたことがうれしくて、僕のために花を咲かせてくれたことに感動して、毎日のように中庭に行くようになった。
でも、この景色が見られるのも軍帝が帰ってくるまでだ。
「そうだ、あの赤い花をもらえないかお願いしてみよう」
いろんな色の花が咲いているけれど、僕は真っ赤な花が一番好きだ。まるで軍帝の赤い眼のような鮮やかな色を見るだけでうれしくなる。
あの赤い花を一本でいいからもらえないだろうか。あれを少し前に知った押し花にすれば、この先もずっとあの赤い花を見ることができる。
色鮮やかに咲いている赤い花を見ながらそう考えていたとき、背後で土を踏むような音が聞こえた。
(足音?)
中庭にいるとき、お付きの人たちが僕に近づくことはない。軍帝の渡りを知らせに来るときは別だけれど、いま軍帝は不在だから声を掛けにやって来ることはないはずだ。ほかに考えられるのは兄上様が来るときだけれど、兄上様もいない。
じゃあ誰だろうと振り向いた先にいたのは、全身黒尽くめの見知らぬ軍人たちだった。
お付きの人たちが用意する食事も食べたり食べなかったりしながら、軍帝が帰ってくるのをただ待っていた。待ちながら、何度もツアル姫の言葉を思い出した。
もし本当に後宮を出なくてはいけないのなら、このまま軍帝に会わないほうがいいのかもしれない。会ってしまえば離れがたくなるだろうし、後宮に残りたいと言ってしまうかもしれない。そう思ったけれど、結局後宮を出る覚悟はできないままだ。
「もし、陛下に直接後宮を去れと言われたら……」
そう思うだけで胸が痛くなる。軍帝に命じられたら出なくてはいけないけれど、果たして自分の足でちゃんと出て行けるだろうか。何より胸が痛くて動けなくなるかもしれない。
僕が原因で祖国が滅んだのだとわかったときも胸が痛んだ。けれど、あのときよりもいまのほうがずっと痛い。
「僕はなんて薄情な王子なんだろう」
僕のために、きっと大勢の人たちがひどい目に遭ったはずだ。それに胸を痛めるより軍帝のそばにいられなくなることのほうがずっとつらいなんて、さすがにひどいと僕自身も思う。
「でも、いまのほうがつらいんだ」
それに胸がツキツキするたびに体の深くで魔力が蠢くような感覚もある。これは国が滅んだときには感じなかったことだ。
澱んだ真っ黒なものが小さな渦を巻き、それが日に日に大きくなっている気がする。溜まっているはずがない澱みを感じるたびに気持ち悪くなって気鬱になる。
この感覚は食事をしても湯浴みをしても消えることはなかった。気分だけではなく体も重く感じるせいで、湯浴みをするのもおっくうになる。けれどお付きの人たちは二日に一度は湯浴みをするようにと僕のそばに立ち、湯殿に行くまで離れようとしなかった。これも軍帝の命令なのだろう。
今日も暗くなると全身真っ白なお付きの人たちが現れ、湯殿に促された。体を磨き、髪を洗い、すべてが終わると全身を柔らかな布で包まれて拭われる。同時に伸びた髪の毛を魔具で乾かし、香油をつけてから美しい細工をされた櫛で梳かれた。
軍帝が第二都市に向かった日の夜から、渡りがあるわけでもないのに毎回柑橘の香りがする香油を使われるようになった。以前はこの香りを嗅ぐだけで軍帝を思い出し体が火照っていた。けれど、いまは香油の瓶を見るだけで胸が苦しくなる。
(何も考えないようにしよう)
そうすれば胸が苦しくなることもつらくなることもない。軍帝のことを考えなければ、以前と同じように過ごせるはずだ。
何も考えず、何も感じないようにする。塔にいた頃のように、ただ毎日をくり返せばいい。
(なんだか、人形みたいだな)
ふと、そんなことを思った。そういえば、塔にいた頃は毎日がそんな感じだった。兄上様が来るときは違ったけれど、帝国に来てからのように気持ちが華やぐことはなかった気がする。
(……僕は、こんな顔だっただろうか)
手入れのときに目の前に置かれる手鏡には僕が映っている。映っているのは間違いなく僕なのに、なぜか知らない人のように見えた。
真っ白な肌に瑠璃色の眼が宝石のように冷たく光っている。いや、宝石よりも硝子玉のほうが近いかもしれない。まるで魔石で動く魔具の人形になったような気がして、鏡からそっと視線を外した。
二日後には軍帝が帰って来る。あれだけ待ちわびていたのに、いまは帰ってきてほしくないと思っている。
軍帝が帰ってきたら、僕は後宮から出ることになるのだろう。その後どこに行くのかはわからないけれど、もう二度と軍帝に会うことは叶わないに違いない。
「そうなったら、二度と触れてもらえなくなる」
それは会えないことと同じくらいつらいことだった。僕ではどうすることもできない魔力を喰らってもらえないからじゃない。あの大きな手に触れてもらえなくなる、逞しい腕に抱きしめてもらえなくなると思うだけで、息ができなくなるくらい苦しくなるのだ。
それでもここは皇帝が住む場所だから、軍帝は必ず帰ってくる。それを待つのが僕の役目……だった。
「そうか、今回が最後かもしれないんだ」
軍帝の帰りを待つのは今回が最初で最後だ。そう思うとやっぱり胸が痛むけれど、仕方がないことだと諦めの気持ちも少しだけあった。ツアル姫が言うとおり、僕が出て行くのがよいのだとどこかで悟っているからかもしれない。
「ここで過ごすのも、あとわずかということだな」
そう思うと、黄玉宮での生活が途端に得がたいもののように思えてきた。塔よりずっと広い部屋や、いつの間にか見慣れていた家具や窓から見える景色が宝物のように思えてくる。
「……そうだ、中庭を見ておこう」
黄玉宮の中でも僕が一番好きなのは中庭だ。初めて本物の花を軍帝と一緒に見たとき、僕は世界一素敵な場所だと思った。そんな思い出深い中庭を、これから先も忘れずにいた。そう思い、久しぶりに中庭の四阿に向かうことにした。
四阿にある椅子に座って中庭を眺める。青々とした木々の葉が風に揺れて、その下には色とりどりの花が咲いていて心地いい。
僕が黄玉宮に来たとき、中庭に花は咲いていなかった。塔で本物の花を見たことがなかった僕は、ここでも見られないのかと残念に思った。僕が沈んでいるのが軍帝に伝わったのだろう。理由を尋ねられ、正直に話した翌日にはたくさんの花が中庭に咲いていた。
軍帝が「おまえには花がよく似合う」と笑っていたのを思い出す。そう言われたことがうれしくて、僕のために花を咲かせてくれたことに感動して、毎日のように中庭に行くようになった。
でも、この景色が見られるのも軍帝が帰ってくるまでだ。
「そうだ、あの赤い花をもらえないかお願いしてみよう」
いろんな色の花が咲いているけれど、僕は真っ赤な花が一番好きだ。まるで軍帝の赤い眼のような鮮やかな色を見るだけでうれしくなる。
あの赤い花を一本でいいからもらえないだろうか。あれを少し前に知った押し花にすれば、この先もずっとあの赤い花を見ることができる。
色鮮やかに咲いている赤い花を見ながらそう考えていたとき、背後で土を踏むような音が聞こえた。
(足音?)
中庭にいるとき、お付きの人たちが僕に近づくことはない。軍帝の渡りを知らせに来るときは別だけれど、いま軍帝は不在だから声を掛けにやって来ることはないはずだ。ほかに考えられるのは兄上様が来るときだけれど、兄上様もいない。
じゃあ誰だろうと振り向いた先にいたのは、全身黒尽くめの見知らぬ軍人たちだった。
7
お気に入りに追加
570
あなたにおすすめの小説

見習い薬師は臆病者を抱いて眠る
XCX
BL
見習い薬師であるティオは、同期である兵士のソルダートに叶わぬ恋心を抱いていた。だが、生きて戻れる保証のない、未知未踏の深淵の森への探索隊の一員に選ばれたティオは、玉砕を知りつつも想いを告げる。
傷心のまま探索に出発した彼は、森の中で一人はぐれてしまう。身を守る術を持たないティオは——。
人嫌いな子持ち狐獣人×見習い薬師。

【BL】キス魔の先輩に困ってます
筍とるぞう
BL
先輩×後輩の胸キュンコメディです。
※エブリスタでも掲載・完結している作品です。
〇あらすじ〇
今年から大学生の主人公・宮原陽斗(みやはらひなと)は、東条優馬(とうじょう ゆうま)の巻き起こす嵐(?)に嫌々ながらも巻き込まれていく。
恋愛サークルの創設者(代表)、イケメン王様スパダリ気質男子・東条優真(とうじょうゆうま)は、陽斗の1つ上の先輩で、恋愛は未経験。愛情や友情に対して感覚がずれている優馬は、自らが恋愛について学ぶためにも『恋愛サークル』を立ち上げたのだという。しかし、サークルに参加してくるのは優馬めあての女子ばかりで……。
モテることには慣れている優馬は、幼少期を海外で過ごしていたせいもあり、キスやハグは当たり前。それに加え、極度の世話焼き体質で、周りは逆に迷惑することも。恋愛でも真剣なお付き合いに発展した試しはなく、心に多少のモヤモヤを抱えている。
しかし、陽斗と接していくうちに、様々な気付きがあって……。
恋愛経験なしの天然攻め・優馬と、真面目ツンデレ陽斗が少しづつ距離を縮めていく胸きゅんラブコメ。

悪役令息の七日間
リラックス@ピロー
BL
唐突に前世を思い出した俺、ユリシーズ=アディンソンは自分がスマホ配信アプリ"王宮の花〜神子は7色のバラに抱かれる〜"に登場する悪役だと気付く。しかし思い出すのが遅過ぎて、断罪イベントまで7日間しか残っていない。
気づいた時にはもう遅い、それでも足掻く悪役令息の話。【お知らせ:2024年1月18日書籍発売!】

孤独な王弟は初めての愛を救済の聖者に注がれる
葉月めいこ
BL
ラーズヘルム王国の王弟リューウェイクは親兄弟から放任され、自らの力で第三騎士団の副団長まで上り詰めた。
王家や城の中枢から軽んじられながらも、騎士や国の民と信頼を築きながら日々を過ごしている。
国王は在位11年目を迎える前に、自身の治世が加護者である女神に護られていると安心を得るため、古くから伝承のある聖女を求め、異世界からの召喚を決行した。
異世界人の召喚をずっと反対していたリューウェイクは遠征に出たあと伝令が届き、慌てて帰還するが時すでに遅く召喚が終わっていた。
召喚陣の上に現れたのは男女――兄妹2人だった。
皆、女性を聖女と崇め男性を蔑ろに扱うが、リューウェイクは女神が二人を選んだことに意味があると、聖者である雪兎を手厚く歓迎する。
威風堂々とした雪兎は為政者の風格があるものの、根っこの部分は好奇心旺盛で世話焼きでもあり、不遇なリューウェイクを気にかけいたわってくれる。
なぜ今回の召喚されし者が二人だったのか、その理由を知ったリューウェイクは苦悩の選択に迫られる。
召喚されたスパダリ×生真面目な不憫男前
全38話
こちらは個人サイトにも掲載されています。

【完結】藤華の君 あかねの香
水樹風
BL
その出会いは、薄紫の花の下で……。
青龍の帝が治める大国『東の国』。
先帝の急逝で若くして即位した今上帝・孝龍。
冷血な暴君であると言われる帝は、忠誠の証として、特別な民『四族』の朱雀一族に後宮へ妃をあげることを命じた。
南の朱雀の一族に生まれながらも【賤(オメガ)】だったために、領地の外れに追放され暮らしてきた朱寧は、父親の命令で人質として孝龍に嫁ぐことになるのだが……。
◇ 世界観はあくまで創作です。
◇ この作品は、以前投稿していた同名作品の加筆改稿版です。
◇ 全27話予定。
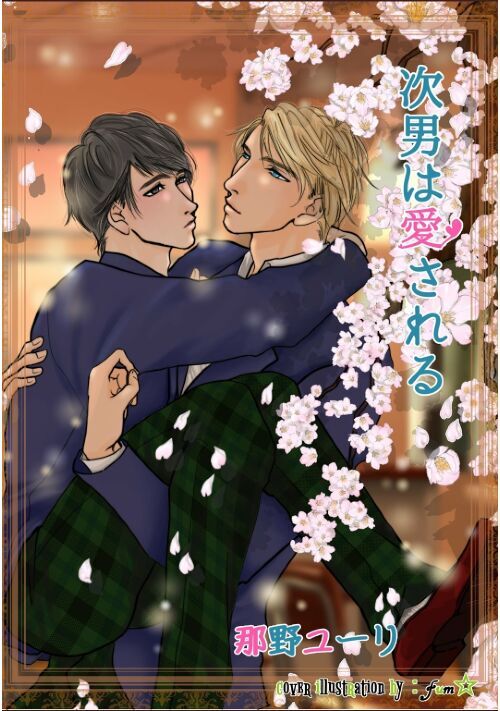
次男は愛される
那野ユーリ
BL
ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男
佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。
素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡
無断転載は厳禁です。
【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】
12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。
近況ボードをご覧下さい。

[完結]堕とされた亡国の皇子は剣を抱く
小葉石
BL
今は亡きガザインバーグの名を継ぐ最後の亡国の皇子スロウルは実の父に幼き頃より冷遇されて育つ。
10歳を過ぎた辺りからは荒くれた男達が集まる討伐部隊に強引に入れられてしまう。
妖精姫との名高い母親の美貌を受け継ぎ、幼い頃は美少女と言われても遜色ないスロウルに容赦ない手が伸びて行く…
アクサードと出会い、思いが通じるまでを書いていきます。
※亡国の皇子は華と剣を愛でる、
のサイドストーリーになりますが、この話だけでも楽しめるようにしますので良かったらお読みください。
際どいシーンは*をつけてます。

釣った魚、逃した魚
円玉
BL
瘴気や魔獣の発生に対応するため定期的に行われる召喚の儀で、浄化と治癒の力を持つ神子として召喚された三倉貴史。
王の寵愛を受け後宮に迎え入れられたかに見えたが、後宮入りした後は「釣った魚」状態。
王には放置され、妃達には嫌がらせを受け、使用人達にも蔑ろにされる中、何とか穏便に後宮を去ろうとするが放置していながら縛り付けようとする王。
護衛騎士マクミランと共に逃亡計画を練る。
騎士×神子 攻目線
一見、神子が腹黒そうにみえるかもだけど、実際には全く悪くないです。
どうしても文字数が多くなってしまう癖が有るので『一話2500文字以下!』を目標にした練習作として書いてきたもの。
ムーンライト様でもアップしています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















