94 / 101
94.糾弾に向けて
しおりを挟む
あれから暫く時間は経過しているが、ニコルは一向に戻ってくる気配がない。
私はそわそわとした態度で、先程から扉の方ばかり気にしていた。
(戻ってこない。どうして周りはニコルが出て行くのを止めなかったの?)
「あの」
我慢の限界を感じた私は、傍にいる使用人に声をかけた。
「アリーセ様、どうなさいましたか?」
「貴女はずっとこの部屋にいたのよね?」
「はい、アリーセ様が来られる前から待機しておりましたが」
「ニコルが、私の妹がどこに行ったか聞いてない?」
私が問いかけると、使用人は急に焦ったように瞳を泳がせ始めた。
そして、奥にいる従者に助けを求めるような視線を送っている。
(間違いなく何か知っていそうね。だけど、私に隠す理由なんてあるのかしら)
「居場所を知っていたら教えて」
「そ、それは……あの……」
私は厳しい口調で再度問い詰めた。
決して使用人を責めたいわけではない。
ただ早くニコルの行方が知りたくて、思わず強めの声を上げてしまった。
その様子を見ていた従者は、こちらに近づいてくる。
「アリー、そのことなんだが……」
「プラーム伯爵」
使用人が口籠もってしまったので、前に座っている父が口を開こうとすると、従者によって声は遮られた。
(何? 私には聞かれたらまずいことなの?)
「お父様、ニコルは一体どうなっているんですか?」
「……それは」
従者に鋭い視線を向けられている父は口を閉ざしてしまう。
私は何かを隠そうとしている従者を睨み付けた。
「知っていることがあるのなら、教えて。ニコルに何かあったの?」
「ヴィム殿下より、アリーセ様には伝えるなと言われております」
「は? なんで?」
「貴方様を危険に晒さないためです」
私が眉間に皺を寄せて考えていると、従者は当然のように答えた。
「それは言い換えれば、ニコルは危険な状態にいるってことよね?」
「…………」
私の問いかけに従者は表情を変えず黙ったままだ。
(否定するつもりはないのね……)
恐らくこの者達はヴィムの言葉に従っているだけだ。
私がいくら問い詰めても、何も答えてはくれないだろう。
一切顔色を変えない所から、はっきりとそれが分かった。
それならと、私は席を立ち上がり父の隣へと移動した。
「お父様、教えてください! ニコルに危険が近づいているのなら、早くなんとかしないと!」
「……いや、危険と言われたらそうかもしれないが、さすがにルシアノ殿もニコルに手を上げたりはしないはずだ」
「ちょっと待って。ニコルは、ルシの所にいるの?」
「……それは」
父は私から視線を逸らすと、俯き小さく呟いた。
その素振りを見た瞬間、間違っていないのだと気付いた。
この中にいる者達は皆それを知っていた。
知らないのは私だけだった様だ。
そう思うと、胸の奥が沸き立つように熱くなっていく。
「そう、なのね」
私は納得するように呟くと、勢い良く席を立ち上がった。
その様子に気付いた父は、慌てるように私に向けて手を伸ばした。
「アリー、待ちなさい。一体どこに行くつもり……っ!?」
私の手に触れようとした瞬間、バチッと電気が走るような音が響いた。
(また、静電気? さっきヴィムといた時は何にも無かったのに)
私は試しにもう一度父に触れようとすると、再びバチッと衝撃音が響く。
「……くっ、これは一体なんなんだ」
私には一切衝撃は伝わって来ないが、父には少なからずダメージが送られているようだった。
今までの出来事を思い返してみた。
そしてヴィムとツェーザルの意味深な会話が頭の奥に浮かんだ。
(あの握手の時、ヴィムは何か知っているようだったわ。もしかして、あの時……?)
私はペンダントに触れた。
恐らくあの時だ。
『まじないをかけた』とヴィムが言った時に、何かの魔術をかけたのだろう。
今の私はヴィム以外に触れることは出来ない。
(それなら、ニコルを助けに行けるかもしれないわ!)
「多分これはヴィムが私にかけてくれた魔術が原因だと思います。これならルシも私には触れないはず。私、ニコルを助けに行きますっ!」
「アリー、何を言っているんだ? そんなの、認めることなんて出来ない!」
「お父様は娘が危険な目に遭っているのに、何をしないでただ待っているつもりですか? ニコルに何かあっても平気なんですか?」
「そんなことはないっ! 私だって心配だ。だけどこれはニコルの願いでもあるんだ……」
父は掌をきつく握りしめ、苦しそうに表情を歪めて話始めた。
「ニコルは自分がしたことで、ルシアノ殿を破滅させてしまったと思い込んでいるようだ。それでヴィム殿下に頭を下げて頼み込んだんだ。自分がルシアノ殿を説得させて、穏便に事を済ませると。上手くいったらルシアノ殿の刑を少しでも軽くして、残りの罰は全てニコルが受けると……」
「そんな……。まさか、お父様はそれを受け入れたんですか!?」
私は驚きで声が震えてしまう。
「私だって、出来ることならそんな馬鹿げた提案は止めたかった。だけど、あんなにも必死に頼み込むニコルの姿を見せられたら、何も言えなかった……。きっとニコルは私達が思っている以上に、自分を責めているのかもしれない……」
確かにニコルは強引に自分の気持ちをルシアノに伝えたのかもしれない。
だけどそれを受け入れたのはルシアノ自身だ。
ルシアノが選んだ結果、このような状況になっているのだから、ニコルだけのせいではないはずだ。
こんなにも思ってくれるニコルの事をルシアノは簡単に切り捨てた。
今回の事は、ルシアノが勝手に人で暴走しているだけだ。
決してニコルの所為では無い。
そんな責任までニコルが負うなんて、そんなの納得なんて出来ない。
(これ以上ルシなんかのために、ニコルを傷つけさせないっ!)
このような事をヴィムが受け入れたのにも疑問が残る。
どうしてこんなにも回りくどいことばかりしているのだろう、と。
バルティス側が協力してくれているのなら、もっと簡単に対処出来る方法があったはずだ。
それをしないって事は、何かヴィムなりに考えがあるのかもしれない。
(私にかけてくれた、このおまじない。なんか出来過ぎているような気がする。もしかして、こうなることを最初から予測していた、……とか?)
さすがにそれは考え過ぎなのかもしれない。
私がこんな事を考えている間にも、ニコルは窮地に陥っているはずだ。
今はニコルを助けに行くことが最優先事項だ。
「私、ニコルを助けに行きます。お父様も来たければどうぞ。そこの従者さん達も、一緒に来てくれますよね?」
先程の動揺から一転して、私の口調は落ち着いていた。
「貴女の護衛が私達にとっては最優先ですので」
「いいのか……?」
従者達は表情を変えることなく答えていたが、父だけはまだ驚いた顔をしていた。
「お父様、私に触れない以上、止めるなんて無理です」
「…………」
私が乾いた笑みを漏らすと、父はきょとんとした顔をしていた。
(なんだかヴィムにしてやられた気分だわ。私に文句を言う機会を与えてくれたってことなのかな……)
***
私達はすぐに部屋を出ると、元いた部屋の扉を勢い良く開いた。
当然鍵なんてかけられてはいなかったので簡単に開いた。
バンッ! と激しい音と同時に、視界に室内の様子が飛び込んでくる。
私の視線の先には、驚いた顔でこちらを見ているルシアノと、目を真っ赤に腫らしているニコルの姿があった。
「……アリー?」
ルシアノは幽霊でも見るかのようにこちらを向いていた。
それも当然の事と言える。
目の前には私と同じドレスを着ている人間がいるのだから。
ルシアノの瞳には私が二人いると見えているのだろう。
(まだあの子が私だって気付いていないってことは、何もされていないってことよね。良かった……)
そう思うと少しだけ緊張が解れた。
「お姉様、どうしてこちらに……。お父様まで」
「私達はニコルを助けに来たの。そんなどうしようもない男のために、自ら犠牲になる必要なんてないわ」
私はつかつかと奥に進み、ニコルの前に立つと「もう大丈夫だから」と小さく呟いた。
その瞬間ニコルの目からは大粒の涙が零れ始めた。
私は触れることが出来なかったが、すぐに父がニコルを抱きしめていた。
「ニコル、済まなかった。こんなこと止めるべきだった。怖かったよな」
「ううっ、お父様っ……」
ニコルは父に抱きしめられながら、泣きじゃくっていた。
私はニコルの無事を確認出来てほっとすると、今度はルシアノに冷たい視線を送った。
目の前にいる男は、私の知っているルシアノではない。
優しかったあの頃の、思い出の中のルシアノはもういない。
私の前に立つ男は、妹を傷付け、自分勝手な行動を繰り返す、どうしようもないクズだ。
「一体、どうなってるんだ。アリーが二人……?」
「そこに座ってるのは私の身代わりよ。最初からルシがここに来ることは分かっていたから」
私が淡々とした口調で呟くと、ルシアノは未だにこの状況が飲み込めないまま固まっていた。
「……!?」
「その上で私達は動いてたってことよ。これは罠。ルシは見事にその罠に嵌まったの」
私はそわそわとした態度で、先程から扉の方ばかり気にしていた。
(戻ってこない。どうして周りはニコルが出て行くのを止めなかったの?)
「あの」
我慢の限界を感じた私は、傍にいる使用人に声をかけた。
「アリーセ様、どうなさいましたか?」
「貴女はずっとこの部屋にいたのよね?」
「はい、アリーセ様が来られる前から待機しておりましたが」
「ニコルが、私の妹がどこに行ったか聞いてない?」
私が問いかけると、使用人は急に焦ったように瞳を泳がせ始めた。
そして、奥にいる従者に助けを求めるような視線を送っている。
(間違いなく何か知っていそうね。だけど、私に隠す理由なんてあるのかしら)
「居場所を知っていたら教えて」
「そ、それは……あの……」
私は厳しい口調で再度問い詰めた。
決して使用人を責めたいわけではない。
ただ早くニコルの行方が知りたくて、思わず強めの声を上げてしまった。
その様子を見ていた従者は、こちらに近づいてくる。
「アリー、そのことなんだが……」
「プラーム伯爵」
使用人が口籠もってしまったので、前に座っている父が口を開こうとすると、従者によって声は遮られた。
(何? 私には聞かれたらまずいことなの?)
「お父様、ニコルは一体どうなっているんですか?」
「……それは」
従者に鋭い視線を向けられている父は口を閉ざしてしまう。
私は何かを隠そうとしている従者を睨み付けた。
「知っていることがあるのなら、教えて。ニコルに何かあったの?」
「ヴィム殿下より、アリーセ様には伝えるなと言われております」
「は? なんで?」
「貴方様を危険に晒さないためです」
私が眉間に皺を寄せて考えていると、従者は当然のように答えた。
「それは言い換えれば、ニコルは危険な状態にいるってことよね?」
「…………」
私の問いかけに従者は表情を変えず黙ったままだ。
(否定するつもりはないのね……)
恐らくこの者達はヴィムの言葉に従っているだけだ。
私がいくら問い詰めても、何も答えてはくれないだろう。
一切顔色を変えない所から、はっきりとそれが分かった。
それならと、私は席を立ち上がり父の隣へと移動した。
「お父様、教えてください! ニコルに危険が近づいているのなら、早くなんとかしないと!」
「……いや、危険と言われたらそうかもしれないが、さすがにルシアノ殿もニコルに手を上げたりはしないはずだ」
「ちょっと待って。ニコルは、ルシの所にいるの?」
「……それは」
父は私から視線を逸らすと、俯き小さく呟いた。
その素振りを見た瞬間、間違っていないのだと気付いた。
この中にいる者達は皆それを知っていた。
知らないのは私だけだった様だ。
そう思うと、胸の奥が沸き立つように熱くなっていく。
「そう、なのね」
私は納得するように呟くと、勢い良く席を立ち上がった。
その様子に気付いた父は、慌てるように私に向けて手を伸ばした。
「アリー、待ちなさい。一体どこに行くつもり……っ!?」
私の手に触れようとした瞬間、バチッと電気が走るような音が響いた。
(また、静電気? さっきヴィムといた時は何にも無かったのに)
私は試しにもう一度父に触れようとすると、再びバチッと衝撃音が響く。
「……くっ、これは一体なんなんだ」
私には一切衝撃は伝わって来ないが、父には少なからずダメージが送られているようだった。
今までの出来事を思い返してみた。
そしてヴィムとツェーザルの意味深な会話が頭の奥に浮かんだ。
(あの握手の時、ヴィムは何か知っているようだったわ。もしかして、あの時……?)
私はペンダントに触れた。
恐らくあの時だ。
『まじないをかけた』とヴィムが言った時に、何かの魔術をかけたのだろう。
今の私はヴィム以外に触れることは出来ない。
(それなら、ニコルを助けに行けるかもしれないわ!)
「多分これはヴィムが私にかけてくれた魔術が原因だと思います。これならルシも私には触れないはず。私、ニコルを助けに行きますっ!」
「アリー、何を言っているんだ? そんなの、認めることなんて出来ない!」
「お父様は娘が危険な目に遭っているのに、何をしないでただ待っているつもりですか? ニコルに何かあっても平気なんですか?」
「そんなことはないっ! 私だって心配だ。だけどこれはニコルの願いでもあるんだ……」
父は掌をきつく握りしめ、苦しそうに表情を歪めて話始めた。
「ニコルは自分がしたことで、ルシアノ殿を破滅させてしまったと思い込んでいるようだ。それでヴィム殿下に頭を下げて頼み込んだんだ。自分がルシアノ殿を説得させて、穏便に事を済ませると。上手くいったらルシアノ殿の刑を少しでも軽くして、残りの罰は全てニコルが受けると……」
「そんな……。まさか、お父様はそれを受け入れたんですか!?」
私は驚きで声が震えてしまう。
「私だって、出来ることならそんな馬鹿げた提案は止めたかった。だけど、あんなにも必死に頼み込むニコルの姿を見せられたら、何も言えなかった……。きっとニコルは私達が思っている以上に、自分を責めているのかもしれない……」
確かにニコルは強引に自分の気持ちをルシアノに伝えたのかもしれない。
だけどそれを受け入れたのはルシアノ自身だ。
ルシアノが選んだ結果、このような状況になっているのだから、ニコルだけのせいではないはずだ。
こんなにも思ってくれるニコルの事をルシアノは簡単に切り捨てた。
今回の事は、ルシアノが勝手に人で暴走しているだけだ。
決してニコルの所為では無い。
そんな責任までニコルが負うなんて、そんなの納得なんて出来ない。
(これ以上ルシなんかのために、ニコルを傷つけさせないっ!)
このような事をヴィムが受け入れたのにも疑問が残る。
どうしてこんなにも回りくどいことばかりしているのだろう、と。
バルティス側が協力してくれているのなら、もっと簡単に対処出来る方法があったはずだ。
それをしないって事は、何かヴィムなりに考えがあるのかもしれない。
(私にかけてくれた、このおまじない。なんか出来過ぎているような気がする。もしかして、こうなることを最初から予測していた、……とか?)
さすがにそれは考え過ぎなのかもしれない。
私がこんな事を考えている間にも、ニコルは窮地に陥っているはずだ。
今はニコルを助けに行くことが最優先事項だ。
「私、ニコルを助けに行きます。お父様も来たければどうぞ。そこの従者さん達も、一緒に来てくれますよね?」
先程の動揺から一転して、私の口調は落ち着いていた。
「貴女の護衛が私達にとっては最優先ですので」
「いいのか……?」
従者達は表情を変えることなく答えていたが、父だけはまだ驚いた顔をしていた。
「お父様、私に触れない以上、止めるなんて無理です」
「…………」
私が乾いた笑みを漏らすと、父はきょとんとした顔をしていた。
(なんだかヴィムにしてやられた気分だわ。私に文句を言う機会を与えてくれたってことなのかな……)
***
私達はすぐに部屋を出ると、元いた部屋の扉を勢い良く開いた。
当然鍵なんてかけられてはいなかったので簡単に開いた。
バンッ! と激しい音と同時に、視界に室内の様子が飛び込んでくる。
私の視線の先には、驚いた顔でこちらを見ているルシアノと、目を真っ赤に腫らしているニコルの姿があった。
「……アリー?」
ルシアノは幽霊でも見るかのようにこちらを向いていた。
それも当然の事と言える。
目の前には私と同じドレスを着ている人間がいるのだから。
ルシアノの瞳には私が二人いると見えているのだろう。
(まだあの子が私だって気付いていないってことは、何もされていないってことよね。良かった……)
そう思うと少しだけ緊張が解れた。
「お姉様、どうしてこちらに……。お父様まで」
「私達はニコルを助けに来たの。そんなどうしようもない男のために、自ら犠牲になる必要なんてないわ」
私はつかつかと奥に進み、ニコルの前に立つと「もう大丈夫だから」と小さく呟いた。
その瞬間ニコルの目からは大粒の涙が零れ始めた。
私は触れることが出来なかったが、すぐに父がニコルを抱きしめていた。
「ニコル、済まなかった。こんなこと止めるべきだった。怖かったよな」
「ううっ、お父様っ……」
ニコルは父に抱きしめられながら、泣きじゃくっていた。
私はニコルの無事を確認出来てほっとすると、今度はルシアノに冷たい視線を送った。
目の前にいる男は、私の知っているルシアノではない。
優しかったあの頃の、思い出の中のルシアノはもういない。
私の前に立つ男は、妹を傷付け、自分勝手な行動を繰り返す、どうしようもないクズだ。
「一体、どうなってるんだ。アリーが二人……?」
「そこに座ってるのは私の身代わりよ。最初からルシがここに来ることは分かっていたから」
私が淡々とした口調で呟くと、ルシアノは未だにこの状況が飲み込めないまま固まっていた。
「……!?」
「その上で私達は動いてたってことよ。これは罠。ルシは見事にその罠に嵌まったの」
1
お気に入りに追加
3,619
あなたにおすすめの小説
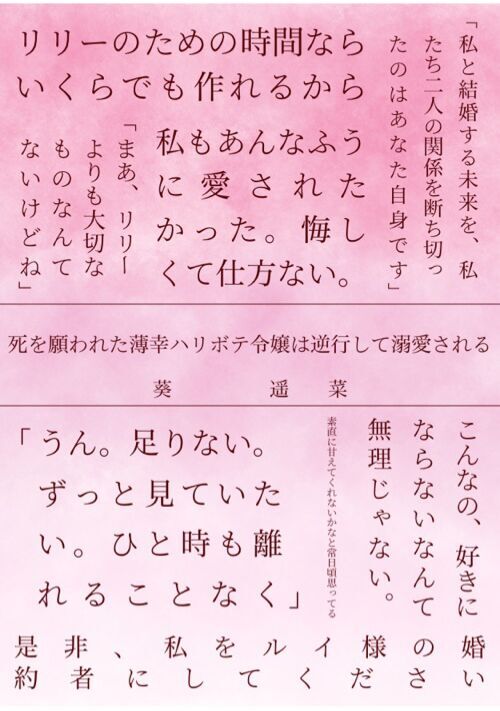
死を願われた薄幸ハリボテ令嬢は逆行して溺愛される
葵 遥菜
恋愛
「死んでくれればいいのに」
十七歳になる年。リリアーヌ・ジェセニアは大好きだった婚約者クラウス・ベリサリオ公爵令息にそう言われて見捨てられた。そうしてたぶん一度目の人生を終えた。
だから、二度目のチャンスを与えられたと気づいた時、リリアーヌが真っ先に考えたのはクラウスのことだった。
今度こそ必ず、彼のことは好きにならない。
そして必ず病気に打ち勝つ方法を見つけ、愛し愛される存在を見つけて幸せに寿命をまっとうするのだ。二度と『死んでくれればいいのに』なんて言われない人生を歩むために。
突如として始まったやり直しの人生は、何もかもが順調だった。しかし、予定よりも早く死に向かう兆候が現れ始めてーー。
リリアーヌは死の運命から逃れることができるのか? そして愛し愛される人と結ばれることはできるのか?
そもそも、一体なぜ彼女は時を遡り、人生をやり直すことができたのだろうかーー?
わけあって薄幸のハリボテ令嬢となったリリアーヌが、逆行して幸せになるまでの物語です。

余命宣告を受けたので私を顧みない家族と婚約者に執着するのをやめることにしました
結城芙由奈
恋愛
【余命半年―未練を残さず生きようと決めた。】
私には血の繋がらない父と母に妹、そして婚約者がいる。しかしあの人達は私の存在を無視し、空気の様に扱う。唯一の希望であるはずの婚約者も愛らしい妹と恋愛関係にあった。皆に気に入られる為に努力し続けたが、誰も私を気に掛けてはくれない。そんな時、突然下された余命宣告。全てを諦めた私は穏やかな死を迎える為に、家族と婚約者に執着するのをやめる事にした―。
2021年9月26日:小説部門、HOTランキング部門1位になりました。ありがとうございます
*「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています
※2023年8月 書籍化

国王陛下、私のことは忘れて幸せになって下さい。
ひかり芽衣
恋愛
同じ年で幼馴染のシュイルツとアンウェイは、小さい頃から将来は国王・王妃となり国を治め、国民の幸せを守り続ける誓いを立て教育を受けて来た。
即位後、穏やかな生活を送っていた2人だったが、婚姻5年が経っても子宝に恵まれなかった。
そこで、跡継ぎを作る為に側室を迎え入れることとなるが、この側室ができた人間だったのだ。
国の未来と皆の幸せを願い、王妃は身を引くことを決意する。
⭐︎2人の恋の行く末をどうぞ一緒に見守って下さいませ⭐︎
※初執筆&投稿で拙い点があるとは思いますが頑張ります!

三年目の離縁、「白い結婚」を申し立てます! 幼な妻のたった一度の反撃
紫月 由良
恋愛
【書籍化】5月30日発行されました。イラストは天城望先生です。
【本編】十三歳で政略のために婚姻を結んだエミリアは、夫に顧みられない日々を過ごす。夫の好みは肉感的で色香漂う大人の女性。子供のエミリアはお呼びではなかった。ある日、参加した夜会で、夫が愛人に対して、妻を襲わせた上でそれを浮気とし家から追い出すと、楽しそうに言ってるのを聞いてしまう。エミリアは孤児院への慰問や教会への寄付で培った人脈を味方に、婚姻無効を申し立て、夫の非を詳らかにする。従順(見かけだけ)妻の、夫への最初で最後の反撃に出る。

お飾りの側妃ですね?わかりました。どうぞ私のことは放っといてください!
水川サキ
恋愛
クオーツ伯爵家の長女アクアは17歳のとき、王宮に側妃として迎えられる。
シルバークリス王国の新しい王シエルは戦闘能力がずば抜けており、戦の神(野蛮な王)と呼ばれている男。
緊張しながら迎えた謁見の日。
シエルから言われた。
「俺がお前を愛することはない」
ああ、そうですか。
結構です。
白い結婚大歓迎!
私もあなたを愛するつもりなど毛頭ありません。
私はただ王宮でひっそり楽しく過ごしたいだけなのです。

最愛の側妃だけを愛する旦那様、あなたの愛は要りません
abang
恋愛
私の旦那様は七人の側妃を持つ、巷でも噂の好色王。
後宮はいつでも女の戦いが絶えない。
安心して眠ることもできない後宮に、他の妃の所にばかり通う皇帝である夫。
「どうして、この人を愛していたのかしら?」
ずっと静観していた皇后の心は冷めてしまいう。
それなのに皇帝は急に皇后に興味を向けて……!?
「あの人に興味はありません。勝手になさい!」

公爵様、契約通り、跡継ぎを身籠りました!-もう契約は満了ですわよ・・・ね?ちょっと待って、どうして契約が終わらないんでしょうかぁぁ?!-
猫まんじゅう
恋愛
そう、没落寸前の実家を助けて頂く代わりに、跡継ぎを産む事を条件にした契約結婚だったのです。
無事跡継ぎを妊娠したフィリス。夫であるバルモント公爵との契約達成は出産までの約9か月となった。
筈だったのです······が?
◆◇◆
「この結婚は契約結婚だ。貴女の実家の財の工面はする。代わりに、貴女には私の跡継ぎを産んでもらおう」
拝啓、公爵様。財政に悩んでいた私の家を助ける代わりに、跡継ぎを産むという一時的な契約結婚でございましたよね・・・?ええ、跡継ぎは産みました。なぜ、まだ契約が完了しないんでしょうか?
「ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいませええ!この契約!あと・・・、一体あと、何人子供を産めば契約が満了になるのですッ!!?」
溺愛と、悪阻(ツワリ)ルートは二人がお互いに想いを通じ合わせても終わらない?
◆◇◆
安心保障のR15設定。
描写の直接的な表現はありませんが、”匂わせ”も気になる吐き悪阻体質の方はご注意ください。
ゆるゆる設定のコメディ要素あり。
つわりに付随する嘔吐表現などが多く含まれます。
※妊娠に関する内容を含みます。
【2023/07/15/9:00〜07/17/15:00, HOTランキング1位ありがとうございます!】
こちらは小説家になろうでも完結掲載しております(詳細はあとがきにて、)

ゼラニウムの花束をあなたに
ごろごろみかん。
恋愛
リリネリア・ブライシフィックは八歳のあの日に死んだ。死んだこととされたのだ。リリネリアであった彼女はあの絶望を忘れはしない。
じわじわと壊れていったリリネリアはある日、自身の元婚約者だった王太子レジナルド・リームヴと再会した。
レジナルドは少し前に隣国の王女を娶ったと聞く。だけどもうリリネリアには何も関係の無い話だ。何もかもがどうでもいい。リリネリアは何も期待していない。誰にも、何にも。
二人は知らない。
国王夫妻と公爵夫妻が、良かれと思ってしたことがリリネリアを追い詰めたことに。レジナルドを絶望させたことを、彼らは知らない。
彼らが偶然再会したのは運命のいたずらなのか、ただ単純に偶然なのか。だけどリリネリアは何一つ望んでいなかったし、レジナルドは何一つ知らなかった。ただそれだけなのである。
※タイトル変更しました
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















