5 / 6
柊のご令嬢2
しおりを挟む
柊の離れ屋にチカの婆さんがずっと静かに暮らしていた。
姑としても婆さんとしても全く家族に無関心で、家族の中でも極力かかわりの薄い人だったらしい。
むかし、そこには見事な薔薇の棚があり、むせかえる匂いと、太い茎に這う下向きの棘は、軽い気持ちで手折る不届きものの手に傷をつけていたらしい。
「悪いな、用事を言いつけて」
と、いつにもまして顔が怖いのがぬっと屋敷の奥から顔を出してきた。
「この前言っていたの、は、あるっちゃあるが、まあ、座れ」
案内された座敷に戸惑いながら護は座った。
「まあ、その前に奥座敷で、長櫃から、これが出たわけだ。……で、俺も嫁もサイズが合わねぇ、しかも俺の知り合いも全聞いて回ってみたが、サイズが合わねえ、無理を承知で頼むが、今後の作品の資料に使わせてもらいたいので」
「…はぁ、まあ、いいですよ」
「チカちん、やっぱり長い刀とかはないよぉ」
「うむ、さて、こいつは…」
「先に写真、撮影機材はスタンバっているから」
護の頭に、『先をやられた』は、口を閉じて、ぐっとこらえた。
真っ白い長袖の制服、肩に黄金のフリンジ、見えないボタンが体を硬直させる。
日差しは、夏を超えたとはいえ、炎天下に近い。
手の角度やら、足の組み合わせやらで数枚撮っただけで汗が、ねむっていたヒノキの香りを通して洋服から出ていく。汗が蒸発して匂いでぐらつく。瞼の前に蜃気楼が見えそうだった。
「機材替えるから休憩 」
と同時に、日差しに連れていかれて、横たわりそうになってしまった。が、制服というものは、いでたちの問題なので、すぐにも崩れそうな古い衣服にシミやしわをつけるのもためらってしまう。
風が道を示したかのように護は奥の日差しの弱い場所へ歩いていった。
「おおー、ここにいたのか」
チカが、遠目で手を振った。
が、護には見えていなかった。婆さんが目の奥に光を取り戻したような顔で護を見つめて、腕を離さなかったからだ。護も婆さんの顔から目をそらすことはなかったし、柔和な顔でゆっくりと喋っているのだ。
「ああ、そうか、キヨ子って言いにくかったんですね」
「そうなのよ、あの方は、わたくしのことを、コッコとお呼びになってね、当時は流行りの名前かしらとも思いまして、わたくしも知らんぷりをしていましたの」
婆さんは記憶奥から語る。
「素敵な方ですね」護は受けて喋っている。
「あら」
「あなたも、そのお方も」
「まあ、そうですか」
「ええ、そうですよ、お互いが思いやっている」
「恥ずかしかったのですわ、お互いが」
「ですが、…重くはない」
「そうでございますね」
「東洋から西洋風にもとらえて…」
「…まるで、一陣の風のようでございました」
と、遠くを見つめながらするりと手の力が落ちていった。
「わたくしは、この窓の景色が嫌でした。ですから当時いち早く取り寄せた西洋薔薇の花を植えました。薔薇はとにかく手入れが大変で肥料もたくさん必要でした。薔薇の花を手入れすればするほど、沢山のことを忘れさせてくれましたから…そして、薔薇は儚く薄情に水やりを怠っただけで枯れるのです、そうでしたね、記憶も香りも遠い過去です」
「けれど、コッコ、この暑い日差しも、夕暮れを感じさせる爽やかな風が頬を通っています。それは今です」
どこかで通り雨もあったのか、少しアスファルトの香りのたつ風が吹いたかとおもったら、続いて夕闇に迫る少し冷たい目の大きな風が扇がれたような波でそよいだ。
どこかで部屋の空調音のスイッチが『ピッ』と鳴った。
護は静かにその場所を離れて、見えないところまで姿を隠した、ため息と共に貧血で目の前が暗くなってうずくまってしまった。
「お花屋さんの薔薇はね、こうして、一本一本棘を抜くから、高い値で売ってるんだから」
「ふん、じゃあ、棘のない薔薇を売ればいい」
「まったく、言い分も酷いなぁ。棘がなきゃ、害虫に食われるほど弱いんだから、薔薇には価値があるんだ。全く、ヴェルサイユ宮殿にお住いの姫君だってそれぐらい知っているってのに」
「ああ、うるさい子だ、ほんと、あんたは見てくれしか能がない。見てくれだけの男はほんとに嫌だ」
「あははは、婆ちゃん辛辣! 面白ぃ」
護は、別棟でシャツ一枚で寝かされていた。
湿り気のある補水液はリンゴの甘い味だった。
夕暮れの帰りに「今日はひどい目にあったね」と言われて、護はそれほどでもなかったと答えた。
「楽しかったよ、ちょっと服が重たかったけれど」
「そっか」
「でも、…服を脱がせてくれてありがとう。やっぱり、きつかった」
「ああ、あれは、そ」そうだね、あれは、着せて喜ぶのを見るのが嫌だったっていうか、「他人の服を着せられるのが嫌だった」っていうか、とか、頭と声に出すのでごっちゃになった背後で、
「くくくっ」
と、押し殺したように護の笑い声が漏れた。
「あのさ、汗臭いよ」
「うん、でも、良い」
汗と皮膚と手の感覚が交わるのを感じる長いキスをして別れた。
ぐぐぐっと、相手を押し出して、「じゃ、おやすみ」と言って自分の家に戻って行った。
これ以上はアブナイと二人は同時に感じたから。
後で聞けば音楽隊の制服だったらしい。
その後、借り物は達筆な詫び状とともに借りた。
姑としても婆さんとしても全く家族に無関心で、家族の中でも極力かかわりの薄い人だったらしい。
むかし、そこには見事な薔薇の棚があり、むせかえる匂いと、太い茎に這う下向きの棘は、軽い気持ちで手折る不届きものの手に傷をつけていたらしい。
「悪いな、用事を言いつけて」
と、いつにもまして顔が怖いのがぬっと屋敷の奥から顔を出してきた。
「この前言っていたの、は、あるっちゃあるが、まあ、座れ」
案内された座敷に戸惑いながら護は座った。
「まあ、その前に奥座敷で、長櫃から、これが出たわけだ。……で、俺も嫁もサイズが合わねぇ、しかも俺の知り合いも全聞いて回ってみたが、サイズが合わねえ、無理を承知で頼むが、今後の作品の資料に使わせてもらいたいので」
「…はぁ、まあ、いいですよ」
「チカちん、やっぱり長い刀とかはないよぉ」
「うむ、さて、こいつは…」
「先に写真、撮影機材はスタンバっているから」
護の頭に、『先をやられた』は、口を閉じて、ぐっとこらえた。
真っ白い長袖の制服、肩に黄金のフリンジ、見えないボタンが体を硬直させる。
日差しは、夏を超えたとはいえ、炎天下に近い。
手の角度やら、足の組み合わせやらで数枚撮っただけで汗が、ねむっていたヒノキの香りを通して洋服から出ていく。汗が蒸発して匂いでぐらつく。瞼の前に蜃気楼が見えそうだった。
「機材替えるから休憩 」
と同時に、日差しに連れていかれて、横たわりそうになってしまった。が、制服というものは、いでたちの問題なので、すぐにも崩れそうな古い衣服にシミやしわをつけるのもためらってしまう。
風が道を示したかのように護は奥の日差しの弱い場所へ歩いていった。
「おおー、ここにいたのか」
チカが、遠目で手を振った。
が、護には見えていなかった。婆さんが目の奥に光を取り戻したような顔で護を見つめて、腕を離さなかったからだ。護も婆さんの顔から目をそらすことはなかったし、柔和な顔でゆっくりと喋っているのだ。
「ああ、そうか、キヨ子って言いにくかったんですね」
「そうなのよ、あの方は、わたくしのことを、コッコとお呼びになってね、当時は流行りの名前かしらとも思いまして、わたくしも知らんぷりをしていましたの」
婆さんは記憶奥から語る。
「素敵な方ですね」護は受けて喋っている。
「あら」
「あなたも、そのお方も」
「まあ、そうですか」
「ええ、そうですよ、お互いが思いやっている」
「恥ずかしかったのですわ、お互いが」
「ですが、…重くはない」
「そうでございますね」
「東洋から西洋風にもとらえて…」
「…まるで、一陣の風のようでございました」
と、遠くを見つめながらするりと手の力が落ちていった。
「わたくしは、この窓の景色が嫌でした。ですから当時いち早く取り寄せた西洋薔薇の花を植えました。薔薇はとにかく手入れが大変で肥料もたくさん必要でした。薔薇の花を手入れすればするほど、沢山のことを忘れさせてくれましたから…そして、薔薇は儚く薄情に水やりを怠っただけで枯れるのです、そうでしたね、記憶も香りも遠い過去です」
「けれど、コッコ、この暑い日差しも、夕暮れを感じさせる爽やかな風が頬を通っています。それは今です」
どこかで通り雨もあったのか、少しアスファルトの香りのたつ風が吹いたかとおもったら、続いて夕闇に迫る少し冷たい目の大きな風が扇がれたような波でそよいだ。
どこかで部屋の空調音のスイッチが『ピッ』と鳴った。
護は静かにその場所を離れて、見えないところまで姿を隠した、ため息と共に貧血で目の前が暗くなってうずくまってしまった。
「お花屋さんの薔薇はね、こうして、一本一本棘を抜くから、高い値で売ってるんだから」
「ふん、じゃあ、棘のない薔薇を売ればいい」
「まったく、言い分も酷いなぁ。棘がなきゃ、害虫に食われるほど弱いんだから、薔薇には価値があるんだ。全く、ヴェルサイユ宮殿にお住いの姫君だってそれぐらい知っているってのに」
「ああ、うるさい子だ、ほんと、あんたは見てくれしか能がない。見てくれだけの男はほんとに嫌だ」
「あははは、婆ちゃん辛辣! 面白ぃ」
護は、別棟でシャツ一枚で寝かされていた。
湿り気のある補水液はリンゴの甘い味だった。
夕暮れの帰りに「今日はひどい目にあったね」と言われて、護はそれほどでもなかったと答えた。
「楽しかったよ、ちょっと服が重たかったけれど」
「そっか」
「でも、…服を脱がせてくれてありがとう。やっぱり、きつかった」
「ああ、あれは、そ」そうだね、あれは、着せて喜ぶのを見るのが嫌だったっていうか、「他人の服を着せられるのが嫌だった」っていうか、とか、頭と声に出すのでごっちゃになった背後で、
「くくくっ」
と、押し殺したように護の笑い声が漏れた。
「あのさ、汗臭いよ」
「うん、でも、良い」
汗と皮膚と手の感覚が交わるのを感じる長いキスをして別れた。
ぐぐぐっと、相手を押し出して、「じゃ、おやすみ」と言って自分の家に戻って行った。
これ以上はアブナイと二人は同時に感じたから。
後で聞けば音楽隊の制服だったらしい。
その後、借り物は達筆な詫び状とともに借りた。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説
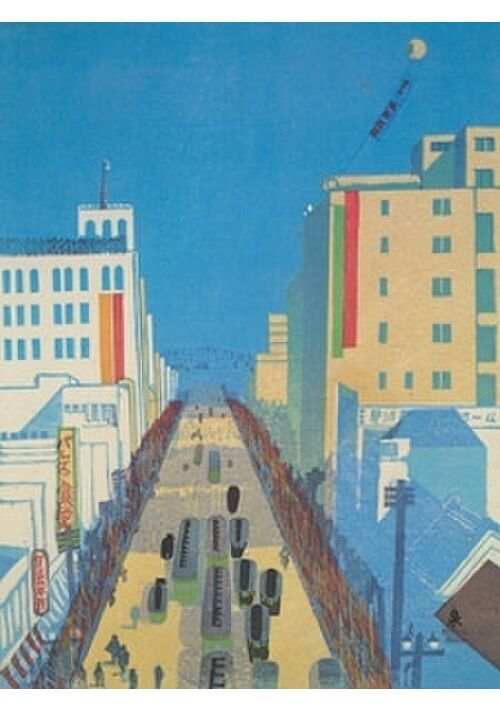
もんもんと汗
ふしきの
大衆娯楽
小町(こまちちょう)は、とても小さい町ですが、繊維工場があるため、昼夜問わず町には人がいます。女工さんもたくさん暮らしています。町には大通りが少なく、袋小路の道ばかりです。古くてエキセントリックな町ですが、駅もバスも通っています。

窓野枠 短編傑作集 6
窓野枠
大衆娯楽
日常、何処にでもありそうな、なさそうな、そんなショートショートを書き綴りました。窓野枠 オリジナル作品となります。「クスッ」と笑える作風に仕上げているつもりです。この本の作品20編をお読みになりましたら、次巻も、閲覧のほど、よろしくお願いいたします。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。



喜劇・魔切の渡し
多谷昇太
大衆娯楽
これは演劇の舞台用に書いたシナリオです。時は現代で場所はあの「矢切の渡し」で有名な葛飾・柴又となります。ヒロインは和子。チャキチャキの江戸っ子娘で、某商事会社のOLです。一方で和子はお米という名の年配の女性が起こした某新興宗教にかぶれていてその教団の熱心な信者でもあります。50年配の父・良夫と母・為子がおり和子はその一人娘です。教団の教え通りにまっすぐ生きようと常日頃から努力しているのですが、何しろ江戸っ子なものですから自分を云うのに「あちし」とか云い、どうかすると「べらんめえ」調子までもが出てしまいます。ところで、いきなりの設定で恐縮ですがこの正しいことに生一本な和子を何とか鬱屈させよう、悪の道に誘い込もうとする〝悪魔〟がなぜか登場致します。和子のような純な魂は悪魔にとっては非常に垂涎を誘われるようで、色々な仕掛けをしては何とか悪の道に誘おうと躍起になる分けです。ところが…です。この悪魔を常日頃から監視し、もし和子のような善なる、光指向の人間を悪魔がたぶらかそうとするならば、その事あるごとに〝天使〟が現れてこれを邪魔(邪天?)致します。天使、悪魔とも年齢は4、50ぐらいですがなぜか悪魔が都会風で、天使はかっぺ丸出しの田舎者という設定となります。あ、そうだ。申し遅れましたがこれは「喜劇」です。随所に笑いを誘うような趣向を凝らしており、お楽しみいただけると思いますが、しかし作者の指向としましては単なる喜劇に留まらず、現代社会における諸々の問題点とシビアなる諸相をそこに込めて、これを弾劾し、正してみようと、大それたことを考えてもいるのです。さあ、それでは「喜劇・魔切の渡し」をお楽しみください。


待ちロ旅
献残屋藤吉郎
大衆娯楽
元新聞記者の祭次郎が全国の祭り見物をしながら、その地域の人物、観光地、グルメの取材をしながら、その地域の依頼を受けて探偵調査をする社会派サスペンス、取材から人々の心に触れ、文化に触れ、取材は人情ドラマ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















