6 / 8
第一章
4
しおりを挟む
久保由香里が現場に到着したのは通報があった一時間後のことだった。既に所轄署が初動捜査を終え、遺体が解剖へと運ばれるところだった。
「警部、お疲れ様です」須藤満が規制線の手前まで迎えに来ていた。歳は四つ離れているが、久保が昇進すれば後釜を担うのはこの男だという確信を持たせるほど有能な部下だ。
「ホントにどうして、こんな朝っぱらから、こんな山奥まで来なくちゃいけないわけ」当たっても仕方がないとわかっていながら、愚痴を溢さずにはいられなかった。
「自分も警察に入ってから様々な場所に行きましたけど、こんな山奥に国立大が建っているなんて知りませんでしたね。うちの管轄って無駄に広かったりしますから」
「できることなら二度と登山は遠慮したいものね」あと何年現場で働くかわからないけど、と口の中で小さく言葉にする。
高卒で警察学校に入り、県庁に勤め始めてからと考えても八年という時間が経とうとしている。 三十路を間近にして、体力的にも現場で働いていくのに不安を感じる場面も増えてきた。
現実的な話を付け足すならば、現場で働いている女性刑事というのは相対的に少なく、中でも久保のように捜査一課で係長を務めているのは異例中の異例とも言えるが、女性進出の著しい昨今の社会情勢を省みた警察組織自体の広告塔の働きをさせられていると考えてしまうと、この地位に留まろうという気力さえも奪われてしまっていた。
結婚や出産といった女性特有の機会に恵まれていれば、とっくに家の中で専業主婦に勤しんでいただろう。しかし、そう上手くいかせてもらえないのが現状だった。
刑事という立場、不規則な生活や突然の呼び出しなど交際に発展するまでにも苦難がある上に、警察という組織の都合上生まれてしまった男勝りな性格は大方の男性へのウケが悪い。恋人と呼べる相手も、もう三年近く現れていなかった。
「で、今回のガイシャ(筆者注:被害者のこと)はこの大学の教授さんだっけ?」
「はい、奥村健一、五十二歳、この大学で教鞭をとりながら、研究者としても業界内では有名だったそうです」須藤は手帳を見ながら答えた。
「へえ、何の研究をしていた人なの?」
「犯罪心理学だそうです」
「犯罪心理学ってプロファイリングとかするやつよね」アメリカ人の丸々と太った男性が偉そうに話をしているテレビの映像を思い出した。
「それも含まれてはいますが、ガイシャの場合そうではないようです。過去に起こった凶悪犯罪などを分析するのが主にやっていたことみたいですよ」
「要はプロファイリングの基となるデータを作っていた人ってことね」
「まあ、簡単に言えばそういうことですね。現場はこの部屋になります」須藤はそう言いながら自分の背後にある部屋を指差した。「この大学の心理学分野全般の資料室のようです」
「さぞかし難しい本がたくさん置いてあるんでしょうね」少し嘲笑を含んだ言い方になった。
しかし、部屋の中を覗くと、本が並んでいる棚以上に引き出しや机の上が散乱している様子が目を引いた。ありとあらゆるものが散らかり、足の踏み場もないような状態だった。
「強盗でも入ったみたいのなっているけど、金目のものとか置いてあったわけ?」現場保存のために下手に物を動かすわけにもいかず、隙間を縫うように部屋の真ん中まで歩く。
「まだ確認が取れていないのではっきりとしたことが言えるわけではないですが、発見者である清掃員の話からすると、それは可能性として低いと思われます。資料室に金銭的なものを置いておくとは考えにくいですし、余程置いてあることを知らない限り盗むこともないでしょう」
だろうね、というのが久保の見解だった。
わざわざ山の中まで来て強盗殺人するなら、住宅街でやる方が奪えるものが多いに違いない。大体それなりの金額になる物が置いてあるかなんてことは関係者以外知ることはないだろう。
「ナイフで一突きだったっけ?」白い手袋をはめて周囲のものを動かさないように物色する。
「はい。犯人は正面からナイフで腹部を刺して、逃走したようです。刺された後もしばらくは息があったみたいですが、自力で動くことはできなかったためそのまま失血死となったみたいです。ただ、凶器に使われたナイフですが、犯人が持ち去ったみたいなので今のところ詳しい形状は明らかになっていません。おそらく解剖すればわかると思いますが、そこから犯人を特定するのは難しいでしょうね」須藤は部屋の入口から動かない。初動捜査の段階であらかた調べ終わっているのだろう。
「死亡推定時刻は?」
「検視官によれば一時から三時ごろとされています。そこから判断するに、犯行時刻は〇時から二時の間だと思われます」
死体のあった場所にはテープが人型に貼られており、その腹部と思われる部分からは薄く赤い円形の跡が残っている。テープの形からして、入り口側に頭を向けたうつ伏せの状態で倒れていたことがわかる。這って動こうとしたのだろう。少し地面に擦れた跡が残っている。
「目撃者は?」一通り物色を終えて、須藤の元へと戻る。何か目ぼしいものがあったとしても、これだけ散乱した状態の中から見つけることはできないだろう。もしかすると犯人は強盗に見せかけるのではなく、何か証拠を隠す意味があって部屋を散らかしたのかもしれない。
「いないですね。二十三時に警備員が巡回をしたのが最後ですが不審者は誰も見ていないとのことです。その時ガイシャは自分の研究室にいたそうです。直接確認はされていませんが、研究室の電気が点いていたことと死亡推定時刻から考えて、その時はまだ生きていたと考えた方が良さそうです。ちなみに、このようなケースは頻繁にあるようで、特にガイシャの場合比較的頻繁にあったようですので、警備員もさして不審に思ったことはないそうです」
久保が知りたい内容は既に聞き込みされているようだった。
部屋を出て廊下の窓から外を見る。目の前は中庭のようになっていて、ガラス越しではあるが反対側の部屋の様子も確認できた。資料室の窓も同じく特別な加工がされているわけではなく、誰かが中に居れば丸見えになってしまうだろう。
体を翻し、廊下の一望する。何の変哲もない一本道になっている。その両端はT字路になっていて、その先には各研究室が並んでいる。
「そういえば、あれは確認したの?」廊下の天井からぶら下がるものを指差しながら久保は尋ねた。
「すみません、それはこれからです。確認の用意はさせてありますが」
「じゃあ、早速行きましょうか」現場の資料室を離れていくように歩き出す。
どうやらこの事件は単調な捜査で片付きそうだ。
警備室へと向かう足取りは軽快なものになっていた。
「これって俺たちの大学だよな?」
画面から一切視線を外さないまま友一が問う。
通い慣れた大学だ。大体の場所は一目見ればわかる。
テレビにはちょうど数時間前に安伸が見ていた共同棟が正面から映されていた。アナウンサーと思しき男性が警察の規制線の前まで近づき、スタジオの女性キャスターに事件の概要などをレポートしていた。
被害者の名は奥村健一であった。安伸はこの名前と写真を見た瞬間背筋が凍り付いた。昨日安伸が目撃していたその人であるからだ。
「本当にウチの先生殺されたのか」ゼミ生の友一も驚きを隠せず、茫然としていた。
「…みたいだな」安伸はそう返すのが精一杯だった。
―もしかしたら、俺はとんでもないものを目撃したのかもしれない。
その感情が心の中を支配していた。
あの光景を目撃した瞬間から嫌な予感はしていた。
【彼】は今まで見たことのない目をしていた。そう、それこそまるで殺人をするかのような…。
その時点では現在のような展開になるとは思わなかった。いや、そう思うことを精神が否定していた。殺人が自分の身の回りで起きようなど想像したくないものだ。
しかし、受け入れるべきだったのかもしれない。あの時点で奥村の様子を確認していれば「死亡事件」という結果にはならなかったのではないか。
いくら考えても後の祭りでしかない、と自分に言い聞かせた。今こうして現実として起きてしまった事象はもう変えることができない。
安伸はスマホを取り出した。
目撃証言があれば警察はすぐにでも【彼】を検挙してくれるだろう。
そう思っているにもかかわらず、指は思うように動いてくれなかった。
自分の話を警察は信用してくれるのだろうか?
見たのはあくまで状況証拠にしかならない。犯人として示すならば証拠または凶器の隠し場所といった証拠に準ずる証言をしなければ断言できないのではないのか?
そもそも、動機という面から考えれば【彼】が犯行に及んだというのは全くもって信じがたい話になる。理由として挙がるものが何もないのだ。
無論、突発的ということや無差別であることという可能性は僅かながらも存在しているとはいる。
だが、山奥の大学の教授をわざわざ殺しに来る無差別殺人犯というのは想像に難しい部分がある。しかも、犯行時間は真夜中、普通なら人がいない時間だ。
「マモル、どうかしたのか?」友一は安伸の様子に気が付いたようだった。
俺昨日の夜この現場見てたんだぜ、という台詞が喉元から飛び出そうになった。なぜそこにいたのか、と問われれば返す言葉が見つからない。
「いや、ちょっと驚いてるだけ。こんなに身近で殺人とか起こるなんて思わないからさ」出まかせでも筋の通ったことが言えるものなんだ、と言の葉を紡ぎながら思った。
今自分から何かアクションを起こす必要はないのかもしれない。ふとそんな考えが脳裏を掠めた。
現代の警察は有能だと聞く。下手なことを何かしなくても犯人逮捕に辿り着くまでに大した時間を要さないだろう。それよりも今は…。
改めてスマホの画面を開く。
メッセージが来ていた。安祐美からだった。
『今日はよろしく』短い文に可愛らしい熊のスタンプが添えられていた。
『今朝のニュース見た?』と書いた文面はすぐに消した。
安祐美も緊張しているのかもしれない。刺激するような言葉はやめておこう。
とはいえ、どうせすぐに知られてしまうことになるだろう。
気が付けば、時刻は八時半になっていた。
「警部、お疲れ様です」須藤満が規制線の手前まで迎えに来ていた。歳は四つ離れているが、久保が昇進すれば後釜を担うのはこの男だという確信を持たせるほど有能な部下だ。
「ホントにどうして、こんな朝っぱらから、こんな山奥まで来なくちゃいけないわけ」当たっても仕方がないとわかっていながら、愚痴を溢さずにはいられなかった。
「自分も警察に入ってから様々な場所に行きましたけど、こんな山奥に国立大が建っているなんて知りませんでしたね。うちの管轄って無駄に広かったりしますから」
「できることなら二度と登山は遠慮したいものね」あと何年現場で働くかわからないけど、と口の中で小さく言葉にする。
高卒で警察学校に入り、県庁に勤め始めてからと考えても八年という時間が経とうとしている。 三十路を間近にして、体力的にも現場で働いていくのに不安を感じる場面も増えてきた。
現実的な話を付け足すならば、現場で働いている女性刑事というのは相対的に少なく、中でも久保のように捜査一課で係長を務めているのは異例中の異例とも言えるが、女性進出の著しい昨今の社会情勢を省みた警察組織自体の広告塔の働きをさせられていると考えてしまうと、この地位に留まろうという気力さえも奪われてしまっていた。
結婚や出産といった女性特有の機会に恵まれていれば、とっくに家の中で専業主婦に勤しんでいただろう。しかし、そう上手くいかせてもらえないのが現状だった。
刑事という立場、不規則な生活や突然の呼び出しなど交際に発展するまでにも苦難がある上に、警察という組織の都合上生まれてしまった男勝りな性格は大方の男性へのウケが悪い。恋人と呼べる相手も、もう三年近く現れていなかった。
「で、今回のガイシャ(筆者注:被害者のこと)はこの大学の教授さんだっけ?」
「はい、奥村健一、五十二歳、この大学で教鞭をとりながら、研究者としても業界内では有名だったそうです」須藤は手帳を見ながら答えた。
「へえ、何の研究をしていた人なの?」
「犯罪心理学だそうです」
「犯罪心理学ってプロファイリングとかするやつよね」アメリカ人の丸々と太った男性が偉そうに話をしているテレビの映像を思い出した。
「それも含まれてはいますが、ガイシャの場合そうではないようです。過去に起こった凶悪犯罪などを分析するのが主にやっていたことみたいですよ」
「要はプロファイリングの基となるデータを作っていた人ってことね」
「まあ、簡単に言えばそういうことですね。現場はこの部屋になります」須藤はそう言いながら自分の背後にある部屋を指差した。「この大学の心理学分野全般の資料室のようです」
「さぞかし難しい本がたくさん置いてあるんでしょうね」少し嘲笑を含んだ言い方になった。
しかし、部屋の中を覗くと、本が並んでいる棚以上に引き出しや机の上が散乱している様子が目を引いた。ありとあらゆるものが散らかり、足の踏み場もないような状態だった。
「強盗でも入ったみたいのなっているけど、金目のものとか置いてあったわけ?」現場保存のために下手に物を動かすわけにもいかず、隙間を縫うように部屋の真ん中まで歩く。
「まだ確認が取れていないのではっきりとしたことが言えるわけではないですが、発見者である清掃員の話からすると、それは可能性として低いと思われます。資料室に金銭的なものを置いておくとは考えにくいですし、余程置いてあることを知らない限り盗むこともないでしょう」
だろうね、というのが久保の見解だった。
わざわざ山の中まで来て強盗殺人するなら、住宅街でやる方が奪えるものが多いに違いない。大体それなりの金額になる物が置いてあるかなんてことは関係者以外知ることはないだろう。
「ナイフで一突きだったっけ?」白い手袋をはめて周囲のものを動かさないように物色する。
「はい。犯人は正面からナイフで腹部を刺して、逃走したようです。刺された後もしばらくは息があったみたいですが、自力で動くことはできなかったためそのまま失血死となったみたいです。ただ、凶器に使われたナイフですが、犯人が持ち去ったみたいなので今のところ詳しい形状は明らかになっていません。おそらく解剖すればわかると思いますが、そこから犯人を特定するのは難しいでしょうね」須藤は部屋の入口から動かない。初動捜査の段階であらかた調べ終わっているのだろう。
「死亡推定時刻は?」
「検視官によれば一時から三時ごろとされています。そこから判断するに、犯行時刻は〇時から二時の間だと思われます」
死体のあった場所にはテープが人型に貼られており、その腹部と思われる部分からは薄く赤い円形の跡が残っている。テープの形からして、入り口側に頭を向けたうつ伏せの状態で倒れていたことがわかる。這って動こうとしたのだろう。少し地面に擦れた跡が残っている。
「目撃者は?」一通り物色を終えて、須藤の元へと戻る。何か目ぼしいものがあったとしても、これだけ散乱した状態の中から見つけることはできないだろう。もしかすると犯人は強盗に見せかけるのではなく、何か証拠を隠す意味があって部屋を散らかしたのかもしれない。
「いないですね。二十三時に警備員が巡回をしたのが最後ですが不審者は誰も見ていないとのことです。その時ガイシャは自分の研究室にいたそうです。直接確認はされていませんが、研究室の電気が点いていたことと死亡推定時刻から考えて、その時はまだ生きていたと考えた方が良さそうです。ちなみに、このようなケースは頻繁にあるようで、特にガイシャの場合比較的頻繁にあったようですので、警備員もさして不審に思ったことはないそうです」
久保が知りたい内容は既に聞き込みされているようだった。
部屋を出て廊下の窓から外を見る。目の前は中庭のようになっていて、ガラス越しではあるが反対側の部屋の様子も確認できた。資料室の窓も同じく特別な加工がされているわけではなく、誰かが中に居れば丸見えになってしまうだろう。
体を翻し、廊下の一望する。何の変哲もない一本道になっている。その両端はT字路になっていて、その先には各研究室が並んでいる。
「そういえば、あれは確認したの?」廊下の天井からぶら下がるものを指差しながら久保は尋ねた。
「すみません、それはこれからです。確認の用意はさせてありますが」
「じゃあ、早速行きましょうか」現場の資料室を離れていくように歩き出す。
どうやらこの事件は単調な捜査で片付きそうだ。
警備室へと向かう足取りは軽快なものになっていた。
「これって俺たちの大学だよな?」
画面から一切視線を外さないまま友一が問う。
通い慣れた大学だ。大体の場所は一目見ればわかる。
テレビにはちょうど数時間前に安伸が見ていた共同棟が正面から映されていた。アナウンサーと思しき男性が警察の規制線の前まで近づき、スタジオの女性キャスターに事件の概要などをレポートしていた。
被害者の名は奥村健一であった。安伸はこの名前と写真を見た瞬間背筋が凍り付いた。昨日安伸が目撃していたその人であるからだ。
「本当にウチの先生殺されたのか」ゼミ生の友一も驚きを隠せず、茫然としていた。
「…みたいだな」安伸はそう返すのが精一杯だった。
―もしかしたら、俺はとんでもないものを目撃したのかもしれない。
その感情が心の中を支配していた。
あの光景を目撃した瞬間から嫌な予感はしていた。
【彼】は今まで見たことのない目をしていた。そう、それこそまるで殺人をするかのような…。
その時点では現在のような展開になるとは思わなかった。いや、そう思うことを精神が否定していた。殺人が自分の身の回りで起きようなど想像したくないものだ。
しかし、受け入れるべきだったのかもしれない。あの時点で奥村の様子を確認していれば「死亡事件」という結果にはならなかったのではないか。
いくら考えても後の祭りでしかない、と自分に言い聞かせた。今こうして現実として起きてしまった事象はもう変えることができない。
安伸はスマホを取り出した。
目撃証言があれば警察はすぐにでも【彼】を検挙してくれるだろう。
そう思っているにもかかわらず、指は思うように動いてくれなかった。
自分の話を警察は信用してくれるのだろうか?
見たのはあくまで状況証拠にしかならない。犯人として示すならば証拠または凶器の隠し場所といった証拠に準ずる証言をしなければ断言できないのではないのか?
そもそも、動機という面から考えれば【彼】が犯行に及んだというのは全くもって信じがたい話になる。理由として挙がるものが何もないのだ。
無論、突発的ということや無差別であることという可能性は僅かながらも存在しているとはいる。
だが、山奥の大学の教授をわざわざ殺しに来る無差別殺人犯というのは想像に難しい部分がある。しかも、犯行時間は真夜中、普通なら人がいない時間だ。
「マモル、どうかしたのか?」友一は安伸の様子に気が付いたようだった。
俺昨日の夜この現場見てたんだぜ、という台詞が喉元から飛び出そうになった。なぜそこにいたのか、と問われれば返す言葉が見つからない。
「いや、ちょっと驚いてるだけ。こんなに身近で殺人とか起こるなんて思わないからさ」出まかせでも筋の通ったことが言えるものなんだ、と言の葉を紡ぎながら思った。
今自分から何かアクションを起こす必要はないのかもしれない。ふとそんな考えが脳裏を掠めた。
現代の警察は有能だと聞く。下手なことを何かしなくても犯人逮捕に辿り着くまでに大した時間を要さないだろう。それよりも今は…。
改めてスマホの画面を開く。
メッセージが来ていた。安祐美からだった。
『今日はよろしく』短い文に可愛らしい熊のスタンプが添えられていた。
『今朝のニュース見た?』と書いた文面はすぐに消した。
安祐美も緊張しているのかもしれない。刺激するような言葉はやめておこう。
とはいえ、どうせすぐに知られてしまうことになるだろう。
気が付けば、時刻は八時半になっていた。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

後ろの少女だーれ
ささみ
ミステリー
2011年春俺は東京から村笹野丘村に引っ越しをした。
その村では何人も人が消える神隠しが連続して起こっていることを、引っ越しをした後俺だけに聞かされた。
真実は...
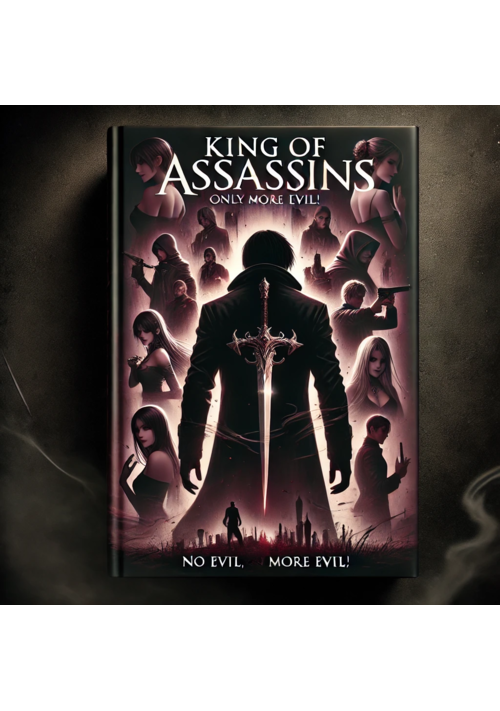

「鏡像のイデア」 難解な推理小説
葉羽
ミステリー
豪邸に一人暮らしする天才高校生、神藤葉羽(しんどう はね)。幼馴染の望月彩由美との平穏な日常は、一枚の奇妙な鏡によって破られる。鏡に映る自分は、確かに自分自身なのに、どこか異質な存在感を放っていた。やがて葉羽は、鏡像と現実が融合する禁断の現象、「鏡像融合」に巻き込まれていく。時を同じくして街では異形の存在が目撃され、空間に歪みが生じ始める。鏡像、異次元、そして幼馴染の少女。複雑に絡み合う謎を解き明かそうとする葉羽の前に、想像を絶する恐怖が待ち受けていた。
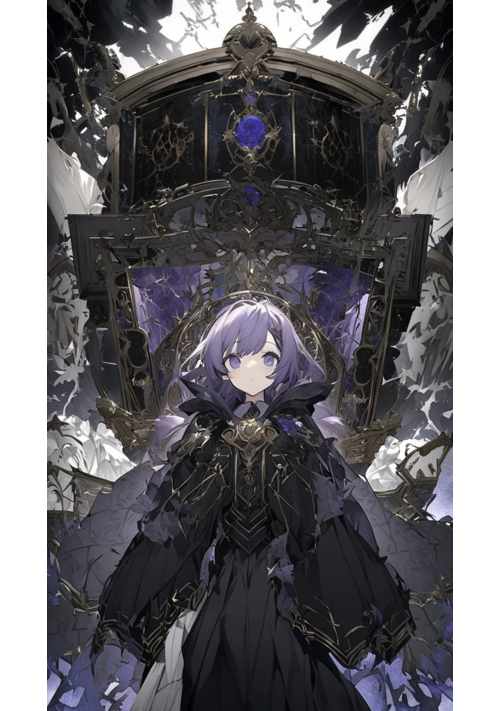
残響鎮魂歌(レクイエム)
葉羽
ミステリー
天才高校生、神藤葉羽は幼馴染の望月彩由美と共に、古びた豪邸で起きた奇妙な心臓発作死の謎に挑む。被害者には外傷がなく、現場にはただ古いレコード盤が残されていた。葉羽が調査を進めるにつれ、豪邸の過去と「時間音響学」という謎めいた技術が浮かび上がる。不可解な現象と幻聴に悩まされる中、葉羽は過去の惨劇と現代の死が共鳴していることに気づく。音に潜む恐怖と、記憶の迷宮が彼を戦慄の真実へと導く。

さよならって言っても仕方ないよね
益木 永
ミステリー
微妙に女子高生にモテない高校生、五木碧人(いつきあおと)はある日突然見知らぬ美少女な遠藤亜澄(えんどうあすみ)から一目惚れしたとされ、告白される。
そこから、彼女と交流を重ねていく碧人は、少しずつ彼女の想いに応えようという想いが強くなっていく。
しかし、彼女の本音は違うもので……?
『注意書き』
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係がありません。
※終盤、一部過激な描写が登場します。苦手な人はご注意ください。
※本作品はノベマでも掲載しています。

暗闇の中の囁き
葉羽
ミステリー
名門の作家、黒崎一郎が自らの死を予感し、最後の作品『囁く影』を執筆する。その作品には、彼の過去や周囲の人間関係が暗号のように隠されている。彼の死後、古びた洋館で起きた不可解な殺人事件。被害者は、彼の作品の熱心なファンであり、館の中で自殺したかのように見せかけられていた。しかし、その背後には、作家の遺作に仕込まれた恐ろしいトリックと、館に潜む恐怖が待ち受けていた。探偵の名探偵、青木は、暗号を解読しながら事件の真相に迫っていくが、次第に彼自身も館の恐怖に飲み込まれていく。果たして、彼は真実を見つけ出し、恐怖から逃れることができるのか?

パンドラは二度闇に眠る
しまおか
ミステリー
M県の田舎町から同じM県の若竹学園にある街へと移り住んだ和多津美樹(ワダツミキ)と、訳ありの両親を持つ若竹学園の進学コースに通う高一男子の来音心(キネシン)が中心となる物語。互いに絡む秘密を暴くと、衝撃の事実が!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















