7 / 46
6話・恩寵と呪い
しおりを挟む安藤と嵐が出て行った後、凛は制服に着替え始めた。脱いだ服をハンガーに掛け、伊達眼鏡と共にロッカーにしまい込む。普段使いの黒縁眼鏡をかけ、顔を隠すように前髪を下ろした。
学生カバンを肩に掛け、戸締りとガスの元栓を確認してから室内の照明を消す。太陽は完全に沈んでおり、カーテンのない窓からは街灯や近隣のビルの照明が射し込んでいる。
「事故物件かぁ」
安藤と話をするまで、この事務所がそういう場所だということをすっかり忘れていた。事故物件というものは本来恐れ避けるべき場所のはずなのに、凛は自宅より狭くて汚い事務所を居心地よく感じてしまう。霊感がある嵐が平然と出入りしているから安心できるのかもしれない。悪い霊がいるのなら彼がなんとかしてくれるはずなのだから。
雑居ビルから出て駅前通りを歩く。車のライトや店先の明かりが照らす歩道にはたくさんの人々が行き交っている。凛は伊達眼鏡の位置を調整し、視線を下げて誰の顔も見ない様に足を動かす。下ろした前髪が視界の半分ほどを塞いでいるが、慣れたものだ。
凛の自宅は駅からバスで十分ほどの距離にある。他人との接触をできる限り避けるため、バスは使わず徒歩で移動していた。夜とはいえ大きな道路沿いは街灯が多く、車の行き来もあるので暗くはない。
しばらく歩き続けるうちに自宅に到着した。ぼんやり辺りを照らす玄関灯を見て、凛は溜め息をもらした。憂鬱な時間の始まりだ。
「ただいま」
消え入りそうな声で帰宅を告げると、廊下の奥にあるリビングのほうからガタッと物音がした。慌てたようにバタバタ動き回る音がする。
「おかえり、凛ちゃん!」
リビングから顔を出して出迎えたのは母親だった。父親はまだ仕事から帰っていないのだろう。母親は続きの間にあるダイニングテーブルで夕食の皿を並べ始めた。凛が帰ってくるまで待っていたらしく、母親のぶんも用意されている。
「遅かったのね、どこに行ってたの」
「図書館で宿題してた」
「明るいうちに帰ってこなきゃダメよ。危ないわ、女の子なんだから」
声色は穏やかだが、有無を言わさぬ迫力があった。反論したり逆らったりしたら面倒なことになると凛は経験から知っている。
「ごめんなさい。次から気を付ける」
素直に謝れば、母親はパッと表情を明るくした。
脱いだ上着を椅子の背もたれにかけてから食卓につき、凛は小さく「いただきます」と手を合わせた。まずは湯気が立ち昇るお吸い物をひと口飲み、煮魚に箸をつける。鯖の味噌煮は凛の好物だ。特に腹身の脂が乗った部分が好きで、凛の皿にはその部位が乗っている。母親が好みを把握しているからだ。
「美味しい?」
「うん」
母親は向かいの席に座り、自分も食べながら食事をする凛の姿を眺め、時おり話しかけてくる。昼間に誰々さんが訪ねてきたとか、面白いテレビをやっていたとか、近所でこんなことがあったとか。延々と話しかけられて妙に緊張してしまう。せめてどこか視界の外に、例えばリビングのソファーに移動してくれればいいのに、頑として離れようとしない。それどころか、ぐいぐい視界に入ってこようとする。
「ごはんの時くらい前髪を退けたらどう?」
一人にしてくれたらすぐにでも前髪をピンで留めるのに、と思いつつ凛は無言で返すと、向かいに座る母親が手を伸ばしてくる。頭に触れる直前、凛はガタッと椅子を引いて距離を取った。バクバクと鳴る心臓を手で抑え込み、無理やり息を吸い込んで声を絞り出す。
「こ、このままでいい」
「そう。でも、目が悪くなっちゃうわ」
「大丈夫だから」
あからさまな拒絶の態度に気を悪くすることもなく、母親はにこりと笑みを浮かべて手を引っ込めた。鯖の味噌煮は美味しいはずなのに、妙に気を張っているせいで味がよく分からなくなった。
家族はみな凛の能力を知っている。父親と弟は凛と顔を合わさぬ様に避けているが、母親だけは積極的に関わろうとしてくる。母の愛は偉大と言うべきなのだろうが、実際は違う。確かに我が子への愛情はある。しかし、それ以上に自己愛のほうが強い。『障害を持つ娘を分け隔てなく愛する自分』が好きなのだ。
真っ当な日常生活を送れない凛の能力は、母親からすれば只の精神疾患や障害と等しい。可哀想な娘に対して変わらぬ態度で接する行為こそが正しいと心から信じており、娘を避ける夫と息子を情けないとすら思っている。彼らは凛に要らぬ負担を掛けぬように正しい対応をしているだけなのだが、母親には理解できない。どんな障害を背負っていようと普通の生活を送らせてやるのが親の勤めだと心から思っている。
だから『家族の団らん』を演じたがっている。
「ごちそうさま。美味しかった」
ジロジロと見られる中でなんとか食べ終え、空いた食器を流し台に運ぼうとする凛を母親が制した。
「片付けはお母さんがやるわ。凛ちゃんはお風呂に入ってきなさい」
「あ、ありがとう、お母さん」
椅子の背もたれに掛けてあった上着を取り、リビングから出る。階段下に置いていた学生カバンを持って二階へと上がり、自室に入った。
「また勝手に……」
朝見た時と物の配置が微妙に変わっている。
昼間、掃除のために母親が入ったようだ。だが、本棚や机の中までは関係ないはずなのに、時折いじられている形跡があった。本の並びが変わっている本棚を見て憂鬱な気持ちになる。
同級生からいじめられていないか、意地悪されていないかチェックしているのだろう。凛が同級生から仲間外れにされ、酷い扱いを受けていたのはもう何年も前の話なのに、母親の中ではまだ終わっていない。
「母の愛、かぁ」
凛に何かあれば、母親は心から嘆き悲しむ。
今日の依頼人の智代子と同じように。
「あたしにはよくわかんない」
読めば読むほど他人の心の内は理解できなくなる。
凛には自分の能力が『恩寵』などではなく『呪い』のように思えていた。
0
お気に入りに追加
32
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

特殊捜査官・天城宿禰の事件簿~乙女の告発
斑鳩陽菜
ミステリー
K県警捜査一課特殊捜査室――、そこにたった一人だけ特殊捜査官の肩書をもつ男、天城宿禰が在籍している。
遺留品や現場にある物が残留思念を読み取り、犯人を導くという。
そんな県警管轄内で、美術評論家が何者かに殺害された。
遺体の周りには、大量のガラス片が飛散。
臨場した天城は、さっそく残留思念を読み取るのだが――。

【完結】闇堕ちメモリアル
月狂 紫乃/月狂 四郎
ミステリー
とある事件を機にホスト稼業から足を洗った織田童夢は、それまでの生き方を反省して慈善事業に勤しむこととなった。
だが現実は甘くなく、副業をしないと食っていけなくなった。不本意ながらも派遣でコールセンターへ勤務しはじめた童夢は、同僚の美女たちと出会って浮かれていた。
そんな折、中年男性の同僚たちが行方不明になりはじめる。そのうちの一人が無残な他殺体で発見される。
犯人は一体どこに。そして、この裏に潜む本当の目的とは……?
月狂四郎が送るヤンデレミステリー。君はこの「ゲーム」に隠された意図を見破れるか。
※表紙はAIにて作成しました。
※全体で12万字ほど。可能であればブクマやコンテストの投票もお願いいたします。
参考文献
『ホス狂い ~歌舞伎町ネバーランドで女たちは今日も踊る~』宇都宮直子(小学館)
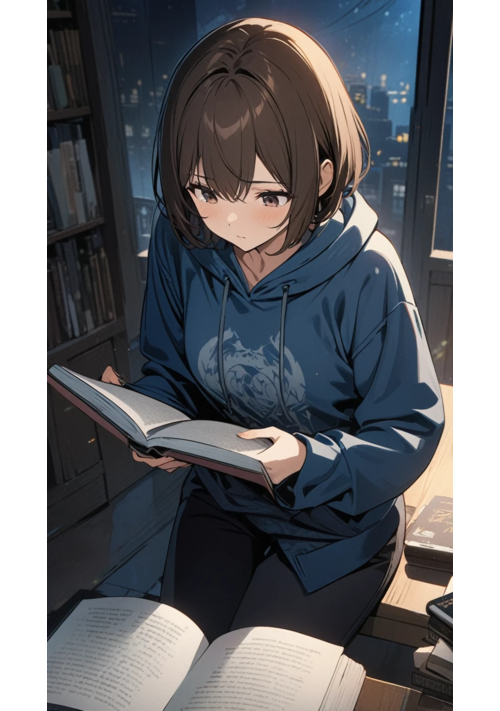
声の響く洋館
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、友人の失踪をきっかけに不気味な洋館を訪れる。そこで彼らは、過去の住人たちの声を聞き、その悲劇に導かれる。失踪した友人たちの影を追い、葉羽と彩由美は声の正体を探りながら、過去の未練に囚われた人々の思いを解放するための儀式を行うことを決意する。
彼らは古びた日記を手掛かりに、恐れや不安を乗り越えながら、解放の儀式を成功させる。過去の住人たちが解放される中で、葉羽と彩由美は自らの成長を実感し、新たな未来へと歩み出す。物語は、過去の悲劇を乗り越え、希望に満ちた未来を切り開く二人の姿を描く。

どんでん返し
あいうら
ミステリー
「1話完結」~最後の1行で衝撃が走る短編集~
ようやく子どもに恵まれた主人公は、家族でキャンプに来ていた。そこで偶然遭遇したのは、彼が閑職に追いやったかつての部下だった。なぜかファミリー用のテントに1人で宿泊する部下に違和感を覚えるが…
(「薪」より)

密室島の輪舞曲
葉羽
ミステリー
夏休み、天才高校生の神藤葉羽は幼なじみの望月彩由美とともに、離島にある古い洋館「月影館」を訪れる。その洋館で連続して起きる不可解な密室殺人事件。被害者たちは、内側から完全に施錠された部屋で首吊り死体として発見される。しかし、葉羽は死体の状況に違和感を覚えていた。
洋館には、著名な実業家や学者たち12名が宿泊しており、彼らは謎めいた「月影会」というグループに所属していた。彼らの間で次々と起こる密室殺人。不可解な現象と怪奇的な出来事が重なり、洋館は恐怖の渦に包まれていく。

双極の鏡
葉羽
ミステリー
神藤葉羽は、高校2年生にして天才的な頭脳を持つ少年。彼は推理小説を読み漁る日々を送っていたが、ある日、幼馴染の望月彩由美からの突然の依頼を受ける。彼女の友人が密室で発見された死体となり、周囲は不可解な状況に包まれていた。葉羽は、彼女の優しさに惹かれつつも、事件の真相を解明することに心血を注ぐ。
事件の背後には、視覚的な錯覚を利用した巧妙なトリックが隠されており、密室の真実を解き明かすために葉羽は思考を巡らせる。彼と彩由美の絆が深まる中、恐怖と謎が交錯する不気味な空間で、彼は人間の心の闇にも触れることになる。果たして、葉羽は真実を見抜くことができるのか。

冷凍少女 ~切なくて、会いたくて~
星野 未来
ミステリー
21歳の青年『健(タケル)』は、未来に希望を見出せず、今日死のうと決めていた。この最後の配達の仕事が終わったら、全て終わりにするはずだった。
でも、その荷物をある館に住む老人に届けると、その老人が君に必要と言って家に持ち帰るように話す。理解ができなかったが、健の住むアパートで荷物を解くと、そこには、冷凍になった16歳の少女『日和(ひより)』の姿があた。
健と日和は、どこかふたりとも淋しい者同士。いつしか一緒に生活するようになり、心が打ち解けて行く。そして、ふたりの間に淡い『恋』が生まれる。
しかし、ある日、健が出張で外泊した時に、一人留守番をしていた日和に事件が起こる。その凄まじい光景に、健は天に叫んだ……。
切なく、儚いふたりの恋と、日和の秘密と謎、そして、あの老人『西園寺』という男とは…。
このミステリーの謎は、あなたの心の中に答えがある……。
君はなぜこの世界に生まれてきたの…?
僕はなぜ君に出会ってしまったんだろう…。
この冷たい世界でしか、生きられないのに…。
切なくて……、会いたくて……。
感動のラストシーンは、あなたの胸の中に……。
表紙原画イラストは、あままつさんです。
いつもありがとうございます♪(*´◡`*)
文字入れ、装飾、アニメーションは、miraii♪ です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















