28 / 36
第27話 おはようダーリン♪
しおりを挟む
「ん…………」
「おはよ、ダーリン♪」
「あ、幽子おはよう…………ってダーリン!?」
――はうあっ!? ダ、ダダダダーリンってそういうこと!?
――俺、幽子とやったのか!? 一生の思い出になる性春18切符を切ったのか!?
――何も、何も覚えてない!
――チクショオオォォォォォッ!
寝起き直後、一郎はここ数年で一番とも言えるほどの混乱を見せた。
「あわわわ、あわわわわわわわ………………」
「……ぷっ! ……く、ふふふふ♪」
「……?」
「もうダメ! あははははは! 一郎くん反応良すぎ♪」
幽子が腹を抱えて爆笑している。
一郎は頭に?マークを浮かべながら事態を見守った。
「よく見てよ。シーツも服も乱れてないでしょ?」
「確かに……あれ? ということは……」
「何もなかったわよ。私がお風呂に入っている間に、一郎くん寝ちゃったの」
「え……俺、寝…………? マジで?」
「うん、マジよマジ。戻ったら寝ちゃってるんだもん。びっくりした」
――ぐあああああぁぁぁぁぁっ!
――お、俺は何ということを……何ということをぉぉぉぉぉぉっ!
性春18切符を切って、大人への旅路の一歩を踏み出す大事なチャンスを逃したのか。
いや、それよりも幽子だ。
彼女が勇気を出して泊まろうと言ってくれたのに、その勇気に応えることができなかっただなんて最低じゃないか!
――俺って奴は……ホント最低だ!
「幽子……その、本当にごめん! せっかく、その……」
「……いいわよ、謝らないで」
「いや、でも……」
「一郎くんから聞きたいのは謝罪の言葉じゃないわ。そんなことより昨晩、私がお風呂に行っている間に何があったのか? できるだけそのことを詳しく聞かせて。お願い」
「あ、うん……わかったよ」
「ありがとう。じゃあ話を聞く前に朝ご飯にしましょう。昨日の夕飯がまだ残ってるしね」
微笑みながらそう言うと、幽子はベッドから起き上がり台所に向かう。
お湯を沸かし、冷蔵庫に保存しておいた刺身を使ってお茶漬けを作る。
天麩羅も少し残っていたので、インスタント味噌汁を作ってその中に入れた。
味噌汁の汁気で、時間が経った天麩羅に水分が戻り、美味さが蘇る。
「へー、味噌汁に天麩羅を入れるのか。美味いの?」
「美味しいわよ。私の地元じゃ結構メジャーな食べ方なんだ」
葱や人参、牛蒡なんかの天麩羅が特に美味しいとのこと。
「お、本当だ! マジで美味い」
「でしょ?」
「味噌汁に天麩羅って合うんだなあ。カラッと食感のイメージだったけどこういうのもアリかも」
「お蕎麦やうどんに天かすとか入れるじゃない? 要はアレと同じ」
「ああ、言われてみれば確かに。天蕎麦やたぬきうどんがある時点で不味いわけがないか」
ロクの分を祭壇に上げ、二人と一匹は食事を続ける。
全てを食べ終え一服した後、ようやく幽子が話を切り出した。
「昨晩のこと、一郎くんはどこまで覚えてる?」
「えーと……」
「私がお風呂から戻ってきた時、一郎くんは寝室にはいなくて、隣のクローゼットルームで倒れていたんだけど」
「隣……あ、思い出した」
曖昧な記憶が繋がったようだ。
ゆっくりと一郎が語り始める。
「昨晩、幽子を待っている間、身だしなみがちょっと気になってさ、デカい鏡のある隣の部屋に行って直そうと思ったんだ」
「隣にいたのはそういうことね。で、それから?」
「なかなか幽子は戻ってこないし、女性の風呂は長いっていうだろ? だから今の内にって隣に行って、髪の乱れと服の乱れを直して……最後にもう一度全身を確認しようとした」
「その後は?」
「残念ながらそこで終わりだ。次の記憶は朝」
短すぎて悪いけど――と一郎。
「ふむ……なるほど。隣に行く前に何か変なことは?」
「なかった。あのさ、幽子。やっぱりここって何かいるわけ?」
「ほぼ間違いなく。でなきゃ一郎くんが気絶するわけないし」
「俺が、その……緊張しすぎて気絶したヘタレとか思わないのか?」
「思わないわよ? これっぽっちも。一郎くんがそんなヘタレなわけないじゃない」
自らの危険をかえりみず、他人を思いやれる勇気のある人が、初体験への期待と緊張で気絶するわけがない――と幽子は思っている。
迷わず否定してくれた幽子への好感度がさらに上がった一郎。
「一郎くんが気絶した後、私とロクであの部屋を含めた屋敷の敷地内を徹底的に調べたんだけど、結局何も見つからなかったの」
「それじゃあやっぱり何もいないんじゃ……?」
「それだと一郎くんの気絶が説明つかないじゃない。突発性睡眠障害の持病とか持っているなら別だけど」
当然ながらそんな持病はもっていない。
「そういえば一郎くん、体調は大丈夫?」
「ああ、問題ないけど」
「本当に? 少しでも何か変わったことがあれば教えて」
「うーん、そういうことなら少し疲労感があるかな? ほら、昨日結構釣りまくっただろ?」
全身が若干だるい。
筋肉痛とかはないし、動けないというほどでもないがだるさを感じる。
「少しだるい……昨日はぐったりしていたし、これは間違いなく気を奪われて衰弱した影響……」
屋敷の噂と一致する。
この家の住人は例外なく衰弱死しているという噂。
「でも、人が気絶するほどの生命吸収を行えるほど強い悪霊がいるなら、絶対に私とロクのどちらかが気づくはずだし、気付けないほど完璧な隠形をされていたとしたら、夜のうちに私が殺されないというのは考えにくい」
……とすると悪霊の線は極めて薄い。
悪霊以外で気絶させるほどの生命吸収を使える存在。
そう仮定した場合、どんな相手が考えられる?
「一郎くん、気絶する直前、最後に何を見たか思い出せない?」
「え? 何を見たかって言われても……身だしなみを直しに行っただけだからなあ。鏡に映った自分以外、特に何も見ていないぜ?」
「鏡に映った一郎くんだけ……あ! ということはもしかして……」
幽子が何か気付いたようだ。
「身だしなみを整えていた時間ってどのくらい? 体感でいいの」
「えーと、15分は直していたと思う」
「ちょっと直すだけなのに? どうして?」
「確か、いくら直してもなんかパッとしなくてさ。その、緊張からビビって顔色が悪くなってたっぽいんだよな、情けないことに。何度直しても決まらなくて、そのうち不安が大きくなったのか、俺の姿が昔の自分に見えちゃったんだよ。あの直前でそんな幻覚を見るなんて、自分が思っている以上にデブってた頃がコンプレックスなのかな? 俺――って、おい幽子。どこに行くんだ?」
「二階。もう一回現場を確認するの」
そう言って幽子は足早に出て行った。
一郎と傍で寝ていたロクは顔を見合わせ、ゆっくりと階段を上がる。
「この配置……天窓……そして鏡に、さっきの一郎くんの証言……うん、多分間違いないわ!」
一郎とロクが追い付くと、幽子が何かわかったらしく興奮気味に呟いていた。
「確認だけど、一郎くんがこの部屋に入ったのって何時ぐらいだった?」
「え? さすがにそんなこと分からないって」
「まあそうよね。じゃあ入った時に『電気は点けた?』」
「いや? 間接照明が自動で点いたし、天窓から明かりが入ってきてて充分明るかったから」
「了解。なら、全部繋がったわ」
幽子はそう言い部屋から出た。
一郎とロクもそれに続く。
「お昼になる前に買い出しに行かない?」
「買い出し? 今日はもう帰るんじゃ……?」
「もう一泊しましょ。せっかくの三連休だし、一泊で帰るのなんてもったいないわ」
「え? あ、うん……わかった。もう一泊、しよう」
「決まりね。今日の夜と明日の朝の分、 二回分だけ用意してお昼は外で食べよっか」
幽子の提案を受け入れた一郎は車を走らせ買い出しに向かった。
地元のスーパーで二食分の食材を購入した後、有名なカレー屋でお昼ごはんを食べる。
ここではロクは食べられないので、帰ったらソーセージを祭壇に上げるつもりだ。
「あー美味しかった。そうそう、帰る前にちょっと寄って欲しいところがあるの」
「わかった。どこに行けばいいんだ?」
「近くのホームセンター。今夜のために、ちょっと買いたいものがあって」
「へえ、何を?」
「大きな紙。それもできるだけ大きいやつを」
「おはよ、ダーリン♪」
「あ、幽子おはよう…………ってダーリン!?」
――はうあっ!? ダ、ダダダダーリンってそういうこと!?
――俺、幽子とやったのか!? 一生の思い出になる性春18切符を切ったのか!?
――何も、何も覚えてない!
――チクショオオォォォォォッ!
寝起き直後、一郎はここ数年で一番とも言えるほどの混乱を見せた。
「あわわわ、あわわわわわわわ………………」
「……ぷっ! ……く、ふふふふ♪」
「……?」
「もうダメ! あははははは! 一郎くん反応良すぎ♪」
幽子が腹を抱えて爆笑している。
一郎は頭に?マークを浮かべながら事態を見守った。
「よく見てよ。シーツも服も乱れてないでしょ?」
「確かに……あれ? ということは……」
「何もなかったわよ。私がお風呂に入っている間に、一郎くん寝ちゃったの」
「え……俺、寝…………? マジで?」
「うん、マジよマジ。戻ったら寝ちゃってるんだもん。びっくりした」
――ぐあああああぁぁぁぁぁっ!
――お、俺は何ということを……何ということをぉぉぉぉぉぉっ!
性春18切符を切って、大人への旅路の一歩を踏み出す大事なチャンスを逃したのか。
いや、それよりも幽子だ。
彼女が勇気を出して泊まろうと言ってくれたのに、その勇気に応えることができなかっただなんて最低じゃないか!
――俺って奴は……ホント最低だ!
「幽子……その、本当にごめん! せっかく、その……」
「……いいわよ、謝らないで」
「いや、でも……」
「一郎くんから聞きたいのは謝罪の言葉じゃないわ。そんなことより昨晩、私がお風呂に行っている間に何があったのか? できるだけそのことを詳しく聞かせて。お願い」
「あ、うん……わかったよ」
「ありがとう。じゃあ話を聞く前に朝ご飯にしましょう。昨日の夕飯がまだ残ってるしね」
微笑みながらそう言うと、幽子はベッドから起き上がり台所に向かう。
お湯を沸かし、冷蔵庫に保存しておいた刺身を使ってお茶漬けを作る。
天麩羅も少し残っていたので、インスタント味噌汁を作ってその中に入れた。
味噌汁の汁気で、時間が経った天麩羅に水分が戻り、美味さが蘇る。
「へー、味噌汁に天麩羅を入れるのか。美味いの?」
「美味しいわよ。私の地元じゃ結構メジャーな食べ方なんだ」
葱や人参、牛蒡なんかの天麩羅が特に美味しいとのこと。
「お、本当だ! マジで美味い」
「でしょ?」
「味噌汁に天麩羅って合うんだなあ。カラッと食感のイメージだったけどこういうのもアリかも」
「お蕎麦やうどんに天かすとか入れるじゃない? 要はアレと同じ」
「ああ、言われてみれば確かに。天蕎麦やたぬきうどんがある時点で不味いわけがないか」
ロクの分を祭壇に上げ、二人と一匹は食事を続ける。
全てを食べ終え一服した後、ようやく幽子が話を切り出した。
「昨晩のこと、一郎くんはどこまで覚えてる?」
「えーと……」
「私がお風呂から戻ってきた時、一郎くんは寝室にはいなくて、隣のクローゼットルームで倒れていたんだけど」
「隣……あ、思い出した」
曖昧な記憶が繋がったようだ。
ゆっくりと一郎が語り始める。
「昨晩、幽子を待っている間、身だしなみがちょっと気になってさ、デカい鏡のある隣の部屋に行って直そうと思ったんだ」
「隣にいたのはそういうことね。で、それから?」
「なかなか幽子は戻ってこないし、女性の風呂は長いっていうだろ? だから今の内にって隣に行って、髪の乱れと服の乱れを直して……最後にもう一度全身を確認しようとした」
「その後は?」
「残念ながらそこで終わりだ。次の記憶は朝」
短すぎて悪いけど――と一郎。
「ふむ……なるほど。隣に行く前に何か変なことは?」
「なかった。あのさ、幽子。やっぱりここって何かいるわけ?」
「ほぼ間違いなく。でなきゃ一郎くんが気絶するわけないし」
「俺が、その……緊張しすぎて気絶したヘタレとか思わないのか?」
「思わないわよ? これっぽっちも。一郎くんがそんなヘタレなわけないじゃない」
自らの危険をかえりみず、他人を思いやれる勇気のある人が、初体験への期待と緊張で気絶するわけがない――と幽子は思っている。
迷わず否定してくれた幽子への好感度がさらに上がった一郎。
「一郎くんが気絶した後、私とロクであの部屋を含めた屋敷の敷地内を徹底的に調べたんだけど、結局何も見つからなかったの」
「それじゃあやっぱり何もいないんじゃ……?」
「それだと一郎くんの気絶が説明つかないじゃない。突発性睡眠障害の持病とか持っているなら別だけど」
当然ながらそんな持病はもっていない。
「そういえば一郎くん、体調は大丈夫?」
「ああ、問題ないけど」
「本当に? 少しでも何か変わったことがあれば教えて」
「うーん、そういうことなら少し疲労感があるかな? ほら、昨日結構釣りまくっただろ?」
全身が若干だるい。
筋肉痛とかはないし、動けないというほどでもないがだるさを感じる。
「少しだるい……昨日はぐったりしていたし、これは間違いなく気を奪われて衰弱した影響……」
屋敷の噂と一致する。
この家の住人は例外なく衰弱死しているという噂。
「でも、人が気絶するほどの生命吸収を行えるほど強い悪霊がいるなら、絶対に私とロクのどちらかが気づくはずだし、気付けないほど完璧な隠形をされていたとしたら、夜のうちに私が殺されないというのは考えにくい」
……とすると悪霊の線は極めて薄い。
悪霊以外で気絶させるほどの生命吸収を使える存在。
そう仮定した場合、どんな相手が考えられる?
「一郎くん、気絶する直前、最後に何を見たか思い出せない?」
「え? 何を見たかって言われても……身だしなみを直しに行っただけだからなあ。鏡に映った自分以外、特に何も見ていないぜ?」
「鏡に映った一郎くんだけ……あ! ということはもしかして……」
幽子が何か気付いたようだ。
「身だしなみを整えていた時間ってどのくらい? 体感でいいの」
「えーと、15分は直していたと思う」
「ちょっと直すだけなのに? どうして?」
「確か、いくら直してもなんかパッとしなくてさ。その、緊張からビビって顔色が悪くなってたっぽいんだよな、情けないことに。何度直しても決まらなくて、そのうち不安が大きくなったのか、俺の姿が昔の自分に見えちゃったんだよ。あの直前でそんな幻覚を見るなんて、自分が思っている以上にデブってた頃がコンプレックスなのかな? 俺――って、おい幽子。どこに行くんだ?」
「二階。もう一回現場を確認するの」
そう言って幽子は足早に出て行った。
一郎と傍で寝ていたロクは顔を見合わせ、ゆっくりと階段を上がる。
「この配置……天窓……そして鏡に、さっきの一郎くんの証言……うん、多分間違いないわ!」
一郎とロクが追い付くと、幽子が何かわかったらしく興奮気味に呟いていた。
「確認だけど、一郎くんがこの部屋に入ったのって何時ぐらいだった?」
「え? さすがにそんなこと分からないって」
「まあそうよね。じゃあ入った時に『電気は点けた?』」
「いや? 間接照明が自動で点いたし、天窓から明かりが入ってきてて充分明るかったから」
「了解。なら、全部繋がったわ」
幽子はそう言い部屋から出た。
一郎とロクもそれに続く。
「お昼になる前に買い出しに行かない?」
「買い出し? 今日はもう帰るんじゃ……?」
「もう一泊しましょ。せっかくの三連休だし、一泊で帰るのなんてもったいないわ」
「え? あ、うん……わかった。もう一泊、しよう」
「決まりね。今日の夜と明日の朝の分、 二回分だけ用意してお昼は外で食べよっか」
幽子の提案を受け入れた一郎は車を走らせ買い出しに向かった。
地元のスーパーで二食分の食材を購入した後、有名なカレー屋でお昼ごはんを食べる。
ここではロクは食べられないので、帰ったらソーセージを祭壇に上げるつもりだ。
「あー美味しかった。そうそう、帰る前にちょっと寄って欲しいところがあるの」
「わかった。どこに行けばいいんだ?」
「近くのホームセンター。今夜のために、ちょっと買いたいものがあって」
「へえ、何を?」
「大きな紙。それもできるだけ大きいやつを」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説



サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
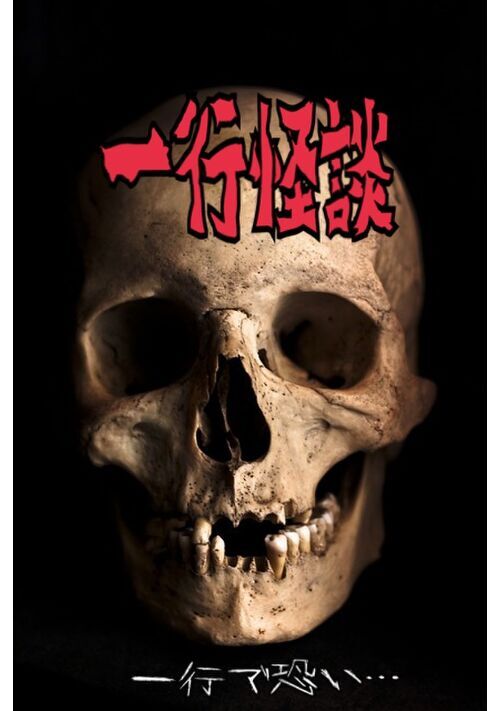


最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















