13 / 50
13
しおりを挟む
その光景をグランドに居る者達は生唾を飲み込む。
突如現れた二人の女性である夕がいきなりバットを持たされて立たされた事に話を知らない者は不思議に思うであろう。
バットを持って構える。日ごろから野球をしている人が見れば夕の構えは野球を普段していないとわかる。
そんな女性をなぜ勝負させているか分からないと言った所である。
夕の運動神経はこの世界で言えば超人とかいうレベルをはるかに超えている。
前に夕は生活に支障が出ないようにするために、朝の日課であるランニングの時に色々と確認を人目のつかない場所でしていた。
例えば大きな岩を殴れば普通に粉々になるし、本気で走れば人の目では追いつけないレベルであった。
この時にゲームと同じスキルが使えるかと試しに頭の中でスキルの名前を唱えると意識に関係なく使えた事には本人も驚いていた。
話は戻るが、そんな能力が高い人間に普通に投げた所でと言う訳である。
すでにモーションに入った相手はストライクゾーンに目掛けて思いっきり投げるが、夕の動体視力ではボールはゆっくりと回転している様に見える。プロが投げた時にボールの縫い目がわかると言うが、夕はボールに色々な文字を書かれていていようが即答で答える事が出来るほどである。
そんなボールを打つ事は余裕である。
夕はなるべくゆったりとバットを振るうが、その力はプロの力をゆうに超えている。
乾いた金属音が響く、打球は想像を超える勢いで校舎を超えてボールが飛んで見えなくなる。
何処のドームで打ってもホームランだとわかる飛距離である。これで力をセーブしているのだ。
本気で振ればどうなるかは想像もしたくない。
一発目から特大を打たれると思っていなかった対戦者はボールが飛んで行った行方をただ眺めるだけであった。
「流石、夕だな! さすがの俺もこれほどとは思ってもいなかったぞ!」
さすがの隆二もと言うかここに居る全員が思った事だろう。
対戦相手は去年甲子園でも活躍していた選手で今年ではプロでも通用する選手と世間を賑わせていた本人である。
投手としては既にプロの世界で通用すると言われ、プロの団体から目を付けられている。
そんな人物から野球を少しかじった女性に特大な打撃を打たれるとは誰も予想はしていなかっただろう。
「なっ!? なんだと……」
「おいおい、手を抜きすぎじゃないのか?」
相手チームの部員が投手に声を掛けるが、その声は微かに震えていた。
3年間、毎日一緒に泥だらけになりながら練習をしているからわかる。投手は手を抜いていないと言う事が。だが、その信じられない光景を信じたく声を掛けたのだと思う。
「すまないが、もう一回投げてもいいかな?」
投手が夕に声を掛ける。
その言葉に夕は頷く。
すると、まるで大事な試合でこの一球で勝ち負けが決まる場面を想像しながら投手は深く息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す。
相手の集中力が増した事に気がついた夕はバットを少し強く握りなおして構える。
先ほどと同じモーションで投げて来るが、先ほどより球速は遅く、ボールの回転が少なくなっている。
この時点でなんの変化球を投げたのか夕にはわかっており、ボールが落ちるタイミングを見てバットを振るう。
夕の身体能力があろうとタイミングが少しずれ、鈍い金属音が響く。だが、夕は力も化け物並みで、そのまま力のみで飛距離を伸ばして校舎の真ん中に存在する大きな時計に直撃する。
まるで祝福しているかのように時計を守っていたガラスがキラキラと太陽に照らされながら花びらの様に地面に落ちて行く。
その光景に投手は地面に項垂れる。
誰もが打ち損ねたと思っただろう。だが、その打球は嘘のように伸び始め投手が最も得意とする変化球が打たれられる事にショックを受けたのである。
「その、すまない」
「まだ負けていない!」
と言うと夕が持っていたバットを奪い取ると、打席に立つ。
その相手の目は熱血の野球漫画の様に熱く、目の奥に炎でも見えそうな勢いだった。
この勝負を受けない事には帰らしてくれないだろうと思った夕は仕方がなく構える。
柔軟な体のバネを使い。
相手が構えているキャッチャーミットに狙いをさだめて投げる。
数か月、しかもジュニアの時に少しかじった人間がコースを狙えるわけもなくただまっすぐボールを投げる。
チッと金属が擦れる音がすると、ボールはキャッチーを超えて少し後ろに落ちる。
「クッ……」
ぼそりと呟くが、既に思考はまともでは無かった。
甲子園でも稀に投げるピッチャーが居る速度だという事を。
それがバットを持っている一握りの人間だからこそ夕の異常に気が付けなかった。
外野から見ている者は夕の球が明らかにプロレベル速さだという事に気がついているようである。
「もう一回!」
夕も野球の楽しさがわかって来たのか、投げる時に少し頬を緩ましている。
先ほどより少し力を込めて投げる。
下手をすれば世界のトップレベルのストレートである。
夕から投げられた球の速さに驚く。
「ダラァァァ!」
キン!先ほどより良い音がするが、それでもボールは前に飛ぶ事は無かった。
チートの様な身体能力を持ち手加減をして投げていると言え、このボールに食らいつくのは既に化け物の域に足を踏み込もうとしている。
ボールを受け取った夕は敬意を示すかのように深く空気を吸い込み踏み込んで投げる。
この時、夕の投げる姿を見たキャッチーとバッターは同じ事を思ったであろう。夕が振りかぶった後、すぐにボールが消えて、キャチャーミットの中に納まっているボールの存在を。
「まっ…… 負けた……」
バットを落として、その場に項垂れる。
さすがに罪悪感を覚えた夕は相手の肩に手を乗せ励まそうとするが、それは逆効果である。
「やめてくれ…… もっと惨めになりそうだ」
顔を上げて夕の顔をみる。
これ程の距離で夕を見る事はなかったが、夕の美貌に初めて気がついた。
「お前…… 女だったのか?」
「そうだが? 気がついてなかったのか?」
「すごく可愛い女性を見せに来たイケメンかと思っていた」
確かに中性の男性と言われれば勘違いをしてしまいそうではあるが、少しダボっとした服を着ているが、良く見れば膨らみもあり見間違え事は無いだろうと、仲間の部員は心の中で思っていた。
まぁ言い直せばそれほど夕に敵対心を出して我を忘れていたのだろう。
すると夕の両手を握りながら立ち上がる。
「数々の無礼申し訳なかった!」
深く頭を下げる。
「えっ、いや俺は気にしてないから、そっちも気にしないでくれ」
「すまない。それと良ければ俺と付き合ってくれないか! もちろん恋人と言う意味でだ。俺は君の強さに惚れた」
「「「えぇ~~!?」」」
周囲の部員も突然の事に驚く。
「ごめんな? 今は恋愛とかに興味がないんだよ」
まぁ女性になって日が浅いので、告白されても異性と言うより同性に告白された感覚に近いのだと感じる。
「そうだよな。それに名前もまだ知らない間柄だしな。俺の名前は伊勢野(いせの) 春樹(はるき)だ。趣味は野球だけだ」
「俺は赤城 夕と言うよ。趣味は筋トレだな。まぁ付き合う事は無いが、友達としてなら喜んでだ」
「あぁ。最初は友達からだな!」
被っていた帽子を取り少し照れ臭そうに夕と話しているが、その後ろでは夕のボールを無意識に受けていたキャッチャーはどうやら腕を痛めて、手当をしてもらっている最中であった。
一言謝りに行ったが、あれほどの球を受けられた事が嬉しかったのか、すごく喜んでいた。
夕と晶はグランドを出る姿は全員が見送る。
春樹は夕の後を熱い眼差しで姿を見ていた。
その他の人は夕の能力の高さに恐怖を感じていた。特に野球部であるコーチ達である。
プロの試合、いや、バッターの飛距離は稀にあるかもしれないが、最後に投げた球の速度は明らかに人間の投げられる速度を超えていた事に恐怖していた。
もし夕が男で野球をしていたなら、一人で試合を終わらせられる潜在能力にだ。
突如現れた二人の女性である夕がいきなりバットを持たされて立たされた事に話を知らない者は不思議に思うであろう。
バットを持って構える。日ごろから野球をしている人が見れば夕の構えは野球を普段していないとわかる。
そんな女性をなぜ勝負させているか分からないと言った所である。
夕の運動神経はこの世界で言えば超人とかいうレベルをはるかに超えている。
前に夕は生活に支障が出ないようにするために、朝の日課であるランニングの時に色々と確認を人目のつかない場所でしていた。
例えば大きな岩を殴れば普通に粉々になるし、本気で走れば人の目では追いつけないレベルであった。
この時にゲームと同じスキルが使えるかと試しに頭の中でスキルの名前を唱えると意識に関係なく使えた事には本人も驚いていた。
話は戻るが、そんな能力が高い人間に普通に投げた所でと言う訳である。
すでにモーションに入った相手はストライクゾーンに目掛けて思いっきり投げるが、夕の動体視力ではボールはゆっくりと回転している様に見える。プロが投げた時にボールの縫い目がわかると言うが、夕はボールに色々な文字を書かれていていようが即答で答える事が出来るほどである。
そんなボールを打つ事は余裕である。
夕はなるべくゆったりとバットを振るうが、その力はプロの力をゆうに超えている。
乾いた金属音が響く、打球は想像を超える勢いで校舎を超えてボールが飛んで見えなくなる。
何処のドームで打ってもホームランだとわかる飛距離である。これで力をセーブしているのだ。
本気で振ればどうなるかは想像もしたくない。
一発目から特大を打たれると思っていなかった対戦者はボールが飛んで行った行方をただ眺めるだけであった。
「流石、夕だな! さすがの俺もこれほどとは思ってもいなかったぞ!」
さすがの隆二もと言うかここに居る全員が思った事だろう。
対戦相手は去年甲子園でも活躍していた選手で今年ではプロでも通用する選手と世間を賑わせていた本人である。
投手としては既にプロの世界で通用すると言われ、プロの団体から目を付けられている。
そんな人物から野球を少しかじった女性に特大な打撃を打たれるとは誰も予想はしていなかっただろう。
「なっ!? なんだと……」
「おいおい、手を抜きすぎじゃないのか?」
相手チームの部員が投手に声を掛けるが、その声は微かに震えていた。
3年間、毎日一緒に泥だらけになりながら練習をしているからわかる。投手は手を抜いていないと言う事が。だが、その信じられない光景を信じたく声を掛けたのだと思う。
「すまないが、もう一回投げてもいいかな?」
投手が夕に声を掛ける。
その言葉に夕は頷く。
すると、まるで大事な試合でこの一球で勝ち負けが決まる場面を想像しながら投手は深く息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す。
相手の集中力が増した事に気がついた夕はバットを少し強く握りなおして構える。
先ほどと同じモーションで投げて来るが、先ほどより球速は遅く、ボールの回転が少なくなっている。
この時点でなんの変化球を投げたのか夕にはわかっており、ボールが落ちるタイミングを見てバットを振るう。
夕の身体能力があろうとタイミングが少しずれ、鈍い金属音が響く。だが、夕は力も化け物並みで、そのまま力のみで飛距離を伸ばして校舎の真ん中に存在する大きな時計に直撃する。
まるで祝福しているかのように時計を守っていたガラスがキラキラと太陽に照らされながら花びらの様に地面に落ちて行く。
その光景に投手は地面に項垂れる。
誰もが打ち損ねたと思っただろう。だが、その打球は嘘のように伸び始め投手が最も得意とする変化球が打たれられる事にショックを受けたのである。
「その、すまない」
「まだ負けていない!」
と言うと夕が持っていたバットを奪い取ると、打席に立つ。
その相手の目は熱血の野球漫画の様に熱く、目の奥に炎でも見えそうな勢いだった。
この勝負を受けない事には帰らしてくれないだろうと思った夕は仕方がなく構える。
柔軟な体のバネを使い。
相手が構えているキャッチャーミットに狙いをさだめて投げる。
数か月、しかもジュニアの時に少しかじった人間がコースを狙えるわけもなくただまっすぐボールを投げる。
チッと金属が擦れる音がすると、ボールはキャッチーを超えて少し後ろに落ちる。
「クッ……」
ぼそりと呟くが、既に思考はまともでは無かった。
甲子園でも稀に投げるピッチャーが居る速度だという事を。
それがバットを持っている一握りの人間だからこそ夕の異常に気が付けなかった。
外野から見ている者は夕の球が明らかにプロレベル速さだという事に気がついているようである。
「もう一回!」
夕も野球の楽しさがわかって来たのか、投げる時に少し頬を緩ましている。
先ほどより少し力を込めて投げる。
下手をすれば世界のトップレベルのストレートである。
夕から投げられた球の速さに驚く。
「ダラァァァ!」
キン!先ほどより良い音がするが、それでもボールは前に飛ぶ事は無かった。
チートの様な身体能力を持ち手加減をして投げていると言え、このボールに食らいつくのは既に化け物の域に足を踏み込もうとしている。
ボールを受け取った夕は敬意を示すかのように深く空気を吸い込み踏み込んで投げる。
この時、夕の投げる姿を見たキャッチーとバッターは同じ事を思ったであろう。夕が振りかぶった後、すぐにボールが消えて、キャチャーミットの中に納まっているボールの存在を。
「まっ…… 負けた……」
バットを落として、その場に項垂れる。
さすがに罪悪感を覚えた夕は相手の肩に手を乗せ励まそうとするが、それは逆効果である。
「やめてくれ…… もっと惨めになりそうだ」
顔を上げて夕の顔をみる。
これ程の距離で夕を見る事はなかったが、夕の美貌に初めて気がついた。
「お前…… 女だったのか?」
「そうだが? 気がついてなかったのか?」
「すごく可愛い女性を見せに来たイケメンかと思っていた」
確かに中性の男性と言われれば勘違いをしてしまいそうではあるが、少しダボっとした服を着ているが、良く見れば膨らみもあり見間違え事は無いだろうと、仲間の部員は心の中で思っていた。
まぁ言い直せばそれほど夕に敵対心を出して我を忘れていたのだろう。
すると夕の両手を握りながら立ち上がる。
「数々の無礼申し訳なかった!」
深く頭を下げる。
「えっ、いや俺は気にしてないから、そっちも気にしないでくれ」
「すまない。それと良ければ俺と付き合ってくれないか! もちろん恋人と言う意味でだ。俺は君の強さに惚れた」
「「「えぇ~~!?」」」
周囲の部員も突然の事に驚く。
「ごめんな? 今は恋愛とかに興味がないんだよ」
まぁ女性になって日が浅いので、告白されても異性と言うより同性に告白された感覚に近いのだと感じる。
「そうだよな。それに名前もまだ知らない間柄だしな。俺の名前は伊勢野(いせの) 春樹(はるき)だ。趣味は野球だけだ」
「俺は赤城 夕と言うよ。趣味は筋トレだな。まぁ付き合う事は無いが、友達としてなら喜んでだ」
「あぁ。最初は友達からだな!」
被っていた帽子を取り少し照れ臭そうに夕と話しているが、その後ろでは夕のボールを無意識に受けていたキャッチャーはどうやら腕を痛めて、手当をしてもらっている最中であった。
一言謝りに行ったが、あれほどの球を受けられた事が嬉しかったのか、すごく喜んでいた。
夕と晶はグランドを出る姿は全員が見送る。
春樹は夕の後を熱い眼差しで姿を見ていた。
その他の人は夕の能力の高さに恐怖を感じていた。特に野球部であるコーチ達である。
プロの試合、いや、バッターの飛距離は稀にあるかもしれないが、最後に投げた球の速度は明らかに人間の投げられる速度を超えていた事に恐怖していた。
もし夕が男で野球をしていたなら、一人で試合を終わらせられる潜在能力にだ。
0
お気に入りに追加
19
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。


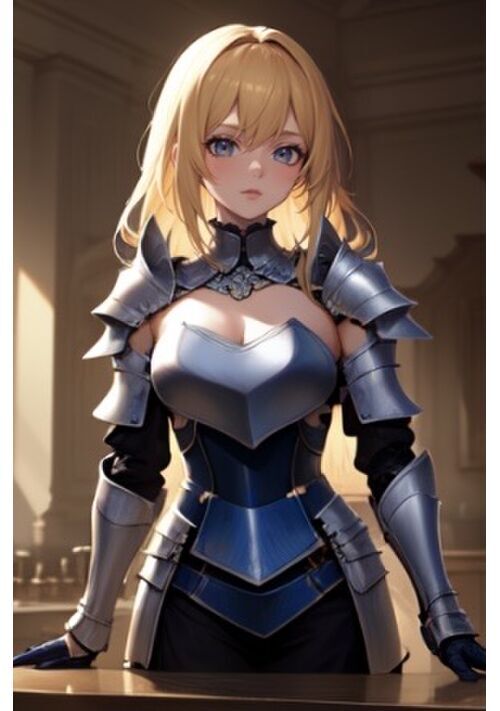
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!


蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

僕の家族は母様と母様の子供の弟妹達と使い魔達だけだよ?
闇夜の現し人(ヤミヨノウツシビト)
ファンタジー
ー 母さんは、「絶世の美女」と呼ばれるほど美しく、国の中で最も権力の強い貴族と呼ばれる公爵様の寵姫だった。
しかし、それをよく思わない正妻やその親戚たちに毒を盛られてしまった。
幸い発熱だけですんだがお腹に子が出来てしまった以上ここにいては危険だと判断し、仲の良かった侍女数名に「ここを離れる」と言い残し公爵家を後にした。
お母さん大好きっ子な主人公は、毒を盛られるという失態をおかした父親や毒を盛った親戚たちを嫌悪するがお母さんが日々、「家族で暮らしたい」と話していたため、ある出来事をきっかけに一緒に暮らし始めた。
しかし、自分が家族だと認めた者がいれば初めて見た者は跪くと言われる程の華の顔(カンバセ)を綻ばせ笑うが、家族がいなければ心底どうでもいいというような表情をしていて、人形の方がまだ表情があると言われていた。
『無能で無価値の稚拙な愚父共が僕の家族を名乗る資格なんて無いんだよ?』
さぁ、ここに超絶チートを持つ自分が認めた家族以外の生き物全てを嫌う主人公の物語が始まる。
〈念の為〉
稚拙→ちせつ
愚父→ぐふ
⚠︎注意⚠︎
不定期更新です。作者の妄想をつぎ込んだ作品です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















