お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説
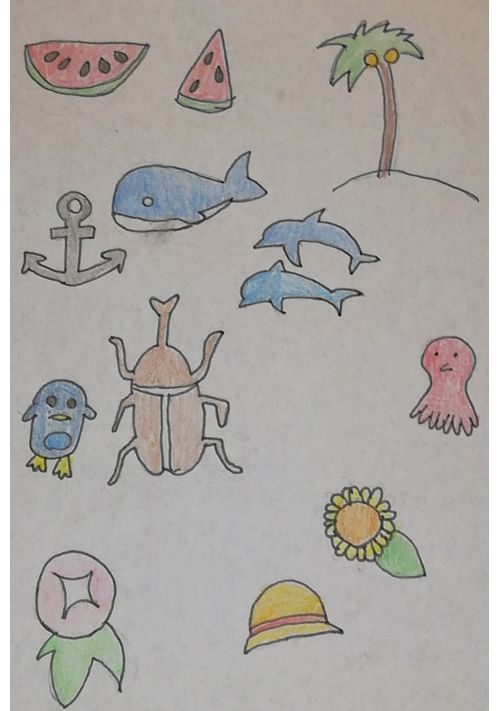
1度っきりの人生〜終わらない過去〜
黄隼
恋愛
何回でも人生は繰り広げられると思っていた・・・
ある日、病気にかかってしまった女の子。その子は一生治らない病気にかかってしまう。
友人関係も壊れてしまい…。

初恋*幼なじみ~歪に絡み合う想いの四重奏~
美和優希
恋愛
高校二年生の未夢、和人、健、真理恵の四人は、小さい頃からの幼なじみで、お互いに家族のような存在だった。
未夢は、四人の仲はいつまでも変わらないと信じていたが、ある日真理恵に和人のことが好きだと告げられる。
そこから、少しずつ四人の関係は変化し始めて──!?
四人の想いが歪に絡み合う、ほろ苦い初恋物語。
初回公開*2016.09.23(他サイト)
アルファポリスでの公開日*2020.03.29
*表紙イラストは、イラストAC(sukimasapuri様)のイラストに背景と文字入れをして使わせていただいてます。

カラダから、はじまる。
佐倉 蘭
現代文学
世の中には、どんなに願っても、どんなに努力しても、絶対に実らない恋がある……
そんなこと、能天気にしあわせに浸っている、あの二人には、一生、わからないだろう……
わたしがこの世で唯一愛した男は——妹の夫になる。
※「あなたの運命の人に逢わせてあげます」「常務の愛娘の『田中さん』を探せ!」「もう一度、愛してくれないか」「政略結婚はせつない恋の予感⁉︎」「お見合いだけど、恋することからはじめよう」のネタバレを含みます。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

【第一部・完結】七龍国物語〜冷涼な青龍さまも嫁御寮には甘く情熱的〜
四片霞彩
恋愛
七体の龍が守護する国・七龍国(しちりゅうこく)。
その内の一体である青龍の伴侶に選ばれた和華(わか)の身代わりとして、青龍の元に嫁ぐことになった海音(みおん)だったが、輿入れの道中に嫁入り道具を持ち逃げされた挙句、青龍が住まう山中に置き去りにされてしまう。
日が暮れても輿入れ先に到着しない海音は、とうとう山に住まう獣たちの餌食になることを覚悟する。しかしそんな海音を心配して迎えに来てくれたのは、和華を伴侶に望んだ青龍にして、巷では「人嫌いな冷涼者」として有名な蛍流(ほたる)であった。
冷酷無慈悲の噂まである蛍流だったが、怪我を負っていた海音を心配すると、自ら背負って輿入れ先まで運んでくれる。
身代わりがバレないまま話は進んでいき、身代わりの花嫁として役目を達成するという時、喉元に突き付けられたのは海音と和華の入れ替わりを見破った蛍流の刃であった。
「和華ではないな。お前、何者だ?」
疑いの眼差しを向ける蛍流。そんな蛍流に海音は正直に身の内を打ち明けるのだった。
「信じてもらえないかもしれませんが、私は今から三日前、こことは違う世界――『日本』からやって来ました……」
現代日本から転移したという海音を信じる蛍流の誘いでしばらく身を寄せることになるが、生活を共にする中で知るのは、蛍流と先代青龍との師弟関係、蛍流と兄弟同然に育った兄の存在。
そして、蛍流自身の誰にも打ち明けられない秘められた過去と噂の真相。
その過去を知った海音は決意する。
たとえ伴侶になれなくても、蛍流の心を救いたいと。
その結果、この身がどうなったとしても――。
転移先で身代わりの花嫁となった少女ד青龍”に選ばれて国を守護する人嫌い青年。
これは、遠い過去に願い事を分かち合った2人の「再会」から始まる「約束」された恋の物語。
「人嫌い」と噂の国の守護龍に嫁いだ身代わり娘に、冷涼な青龍さまは甘雨よりも甘く熱い愛を注ぐ。
┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁┈┈┈┈┈┈┈┈
第一部完結しました。最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。
第二部開始まで今しばらくお待ちください。
┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁┈┈┈┈┈┈┈┈

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

最後の恋って、なに?~Happy wedding?~
氷萌
恋愛
彼との未来を本気で考えていた―――
ブライダルプランナーとして日々仕事に追われていた“棗 瑠歌”は、2年という年月を共に過ごしてきた相手“鷹松 凪”から、ある日突然フラれてしまう。
それは同棲の話が出ていた矢先だった。
凪が傍にいて当たり前の生活になっていた結果、結婚の機を完全に逃してしまい更に彼は、同じ職場の年下と付き合った事を知りショックと動揺が大きくなった。
ヤケ酒に1人酔い潰れていたところ、偶然居合わせた上司で支配人“桐葉李月”に介抱されるのだが。
実は彼、厄介な事に大の女嫌いで――
元彼を忘れたいアラサー女と、女嫌いを克服したい35歳の拗らせ男が織りなす、恋か戦いの物語―――――――

紫の桜
れぐまき
恋愛
紫の源氏物語の世界に紫の上として転移した大学講師の前世はやっぱり紫の上…?
前世に戻ってきた彼女はいったいどんな道を歩むのか
物語と前世に悩みながらも今世こそは幸せになろうともがく女性の物語
注)昔個人サイトに掲載していました
番外編も別に投稿してるので良ければそちらもどうぞ
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















