10 / 19
誕生日
しおりを挟む
店長室を覗くと、店長の最上が下唇を突きだし、パソコンの画面に顔を近づけていた。店長の手元を見ると右手人差し指だけでキーボードをポツポツと頼りなく叩いている。キーボードを叩いているというより、ボタンを押していると言った方が正しい。
「店長、お先に失礼します」
幸仁が声をかけると、店長は人差し指の動きを止めて幸仁の方に顔を向けた。
「おお、佐山か」
店長の目は真っ赤になっていた。今日は、店長の姿が見えないと思ったら、一日中、店長室にこもり、パソコンと向き合っていたようだ。
「お疲れ様です」
幸仁はペコリと頭を下げた。
「お疲れさん。今日は早いんだな」
店長はそう言ってから、立ち上がり短い両手を突き上げ「ウーン」と声を上げて背筋を伸ばした。
「はい、店長が忙しい時にすいません」
店長の充血した目を見ると、先に帰ることが申し訳なくなった。
「いいよ、いいよ、そんなこと気にすんな。閉店業務をやって遅くなる日もあるんだから、早く帰れる日は帰ればいいんだ」
「でも、店長、大変そうですね」
「そうなんだー、こいつが厄介なんだよな。みんなは便利って言うけど、俺にとっちゃ全然便利じゃないよ」
店長がそう言って、パソコンを顎で差した。
「パソコンですか」
「そう。明日、会議だからさ、報告書を作成中なんだよ」
「そう言えば、明日は本社で店長会議があるって言ってましたね」
「そっ。また会議で絞られるわけだけど、その前に会議に出す報告書を作らないといけないんだ。それが今月からは手書きの報告書がダメになってさ、パソコンに打ち込んで、今日中にメールで送信しないといけないんだ。手書きだとすぐにできるんだけど、パソコンだと、これがなかなか進まんのよ。ここに先月の売上と利益率を入力しろとか、ここには自慢の売場画像を貼り付けろとか、全くわけわかんねえよ。文字を打ち込むのに時間がかかるし、ほんと歳とるとやっぱりダメだわ」
店長はそう言って頭をボリボリと掻いた。店長は自分は歳だと言うが、まだ五十歳くらいのはずだ。まだまだ元気で若い。売場で力仕事とかバリバリとこなしているので、歳だというよりデスクワーク、特にパソコンが苦手なだけだ。
「店長の仕事って、いろんなことやらなきゃいけなくて大変なんですね」
「まあな。けど、お前んとこの親父さんに比べたら屁みたいなもんだけどな。俺なんて雇われの身だから、毎月給料はちゃんともらえるし、忙しいといったって仕事離れりゃ自由の身だしな。親父さんは社長だからプライベートなんてないと思うぞ。家族のためだけじゃなく、従業員のことまで考えないといけないからな。なのに、いつも新しいことにチャレンジしてすごいよ」
幸仁は親父の話題になったので、逃げ出したくなって、「店長、頑張ってください」と逃げるようにして店長室を出た。
店長は幸仁との会話の合間に親父の話題をしらじらしく挟んでくる。幸仁と親父を仲直りさせようとしているためのようだが、それが無駄だということが、店長は全くわかっていない。店長はいい人で、すごくお世話になっているが、幸仁と親父の問題に他人である店長が口を挟んでくることだけは鬱陶しい。
店長は幸仁がここで働く前から親父と知り合いだ。店長はなぜか親父のことを尊敬している。親父みたいな人間を尊敬する店長の感覚もよくわからない。幸仁の親父は、この地域では有名なスーパーミウラの社長だ。幸仁の祖父三浦奏輔が営む果物店を継いでスーパーミウラとしてオープンさせてから順調に売上を伸ばし店舗数を増やしていったようだが、幸仁にとってはそれが凄いとは思わない。
幸仁と親父との関係が壊れたのは一年以上前のことだ。幸仁が付き合っていた向日葵のお腹に子どもができたことがきっかけだった。向日葵は両親がいなくて親戚もいないので頼れるのは幸仁しかいなかった。しかし、幸仁も大学生だったので、子どもを堕ろすしかないと向日葵は言ってきた。幸仁は向日葵が子ども生んで育てるために、大学をやめて、向日葵と結婚し、バイト先のホームセンターショーマンで社員として働くと決めた。そのことを親父に話すと猛反対され口論となり、最後に幸仁は勘当されて家を飛び出した。それ以来、幸仁は親父とおふくろには会っていない。幸仁は勘当された時の親父の言葉が今でも許せない。三浦孝士という男は血も涙もない人間だ。今でもあの日の親父の言葉を思い出すと怒りで体が熱くなる。
ベビーベッドを覗くと、斗真はスヤスヤと気持ちよさそうに寝息をたてていた。首を横に傾け、半開きの口からよだれが垂れる。幸仁はそれを見ているだけで、一日の疲れがふっ飛ぶ。
「それじゃあ、今から誕生パーティーの準備するね」
向日葵が斗真を起こさないように、幸仁の耳元で小声で言った。今日早く帰ってきた理由は幸仁と向日葵の誕生日だからだ。
「斗真は?」
「夜寝なくなるかもしれないけど、もう少し寝かせておくわ」
向日葵は台所へと向かった。
「それにしても、斗真はよく寝るよな」
幸仁は居間で胡座をかいてテレビのリモコンをつけた。
「寝る子は、元気に育ってくれるかな」
台所から向日葵の声がした。
テレビの画面からは、さほどおもしろくもないお笑いタレントが焼肉を食べている映像が流れていた。
そのお笑いタレントが、「この肉の脂はしつこくなくて本当に甘いですね。これまで食べた焼肉の中で一番美味しいです」と目を大きく見開いてコメントしていた。確かに旨そうな焼肉だったが、『これまで食べた中で一番美味しい』というコメントは大袈裟じゃないか。このお笑いタレントが今までに食べに行った焼肉屋の店員が聞いたらどう思うのだろうかといらぬ心配をした。そんなことを思いながら、焼肉の映像を見て生唾を飲みこんだ。
「はーい、おまたせー」
向日葵が大きな白い皿を両手で持ってきた。その皿を幸仁の前に置いてニコッと笑った。幸仁も笑みを返してから、向日葵が置いた大きな白い皿に視線を落とした。
「えっー、す、すげえ」
幸仁の目に飛び込んできたのは皿の上にどっしり載ったステーキ肉だった。幸仁の掌くらいの大きさで厚さが一センチ以上あった。焼きたてで金色に輝く脂が白い皿に滴っている。脂のいい匂いが部屋中に立ち込めた。さっきテレビに映っていた焼肉よりこっちの方が断然旨そうだった。
「こ、この肉、す、すごいね」
幸仁の口の中は唾液が止まらない。
「そう、二人の誕生日だし奮発しちゃった」
嬉しそうに話す向日葵の手にはワインがあった。
「えっ、ワインまであるの?」
「そう、記念日だからね」
こんな上等な肉とワインを買って、家計の方は大丈夫なのかという言葉は飲み込んだ。今のこの雰囲気をぶち壊すわけにはいかないし、今の稼ぎは向日葵の方が幸仁より多いからだ。
「俺、こんな大きくて旨そうなステーキ食べるのはじめてかも」
「あたしも、こんなステーキ食べるのはじめて。A5ランクの肉だって言ってたよ。感謝、感謝ねー」
A5ランクの肉? 肉のランクは、よくわからないが、たぶん高級なんだろう。それに、向日葵は何に感謝なんだろうか。
これも今日のために向日葵が買ってきたのか、これまでに見たことのないキラキラしたワイングラスで乾杯してから、ワインを口に含んだ。この赤い液体の味の旨いまずいはよくわからないが、気分は盛り上がった。
ステーキにナイフを入れると、柔らかくて簡単に切れた。肉の焼き加減もよくわからないが、ミディアムに丁度よく焼けているんだろうと思った。向日葵は料理なら何でも上手だ。料理は祖母から教えてもらったということだが、さすがに肉の焼き方なんかは教えてもらってないと思う。元々向日葵自身に料理のセンスがあるのだろうか。肉を口に入れると、とろけるように簡単に噛みきれて、肉汁が口の中に広がった。脂がしつこくなくて甘い。旨すぎる。こんな旨い肉、生まれてはじめてだ。さっきのお笑いタレントとは違い、幸仁の場合は間違いなくこれまで食べた肉の中で一番旨い肉だった。
「旨すぎ」
思わず声が出た。
「うん、すんごく、美味しい」
向日葵も興奮気味に声を上げた。
贅沢な気分だった。せっかくの二人の誕生日だ。これくらいの贅沢をしてもバチはあたらないだろうと幸仁は思った。
「ありがとう。美味しかった。ごちそうさま」
「うん、美味しかったね。ごちそうさま」
二人で顔を見合わせ、手を合わせた。そこで、隣の部屋から斗真の泣き声が聞こえてきた。
「斗真が起きたみたいだな」
「ほんとだ。ちょうどだね」
向日葵が斗真の寝ている隣の部屋に視線を向けた。
「斗真は、俺たちが食べ終わるのを待っててくれたのかな」
「斗真って、赤ちゃんなのにすごいね」
「ちょっと見てくるよ」
幸仁は立ち上がり隣の部屋に向かった。
「うん、お願い」
向日葵がそう言ってから、洗い物をキッチンへと運んで行った。
幸仁は斗真を隣の部屋から連れてきて膝の上に置いた。斗真もご機嫌そうだ。向日葵がキッチンから、またお皿をもってきた。
「ユキくん、お待たせ。はい、次は食後のデザート」
向日葵がそう言ってお皿をテーブルの上に置いた。
「おっ」幸仁はお皿を覗きこんだ。
「ついに桃を買いましたー」
お皿の上には一口サイズに切った桃が並べられていた。
「おー、す、すげえな」
「ケーキを買おうと思ったんだけど、ユキくんは桃が大好物だからね」
向日葵はニコニコしながら幸仁の顔を覗きこんだ。
向日葵はなぜ、幸仁が桃が大好物だと知っているのだろうか。幸仁が桃が好きだったのは、子どもの頃に行った桃農園の記憶があるからだ。桃農園で過ごした楽しい時間と食べた桃の美味しさが忘れられなかったからだ。しかし、今は違う。だから、向日葵に桃が大好物だと話した記憶はない。
「向日葵、俺が桃が好きだったことよく知ってたな」
「当たり前よ。ユキくんのことは何でも知ってるんだからね」
幸仁は不思議に思ったが、これ以上桃について話したくなかったので、そのまま終わらせた。
爪楊枝に刺した桃を一切れ持ち上げた。部屋の灯りに反射してみずみずしくキラキラと輝いている。そのまま口に放り込むと口の中が冷んやりとした。噛むと甘い果汁が口いっぱいに広がった。子供のころに食べたあの桃と同じくらいに、向日葵の出したこの桃は美味しかった。これまで食べた桃の中で一番旨いとは言えないが、あの時に食べた桃に匹敵するくらいの旨さだった。あの旨い桃を食べた日のことを思い出したが、幸仁は頭を振って、記憶を振り払った。あれは遠い過去のことで、自分は子どもだったから勘違いしていただけなんだ。
「斗真の分はこっちね」
斗真用に、火を通して細かく砕いた桃がプラスチックの皿にのせてある。
「斗真の方も旨そうだな」
向日葵が幸仁の隣に座り斗真に桃を食べさせていた。
「はい、あーん」
斗真が大きく口を開けた。つられて幸仁も大きく口を開けていた。向日葵がスプーンにのせた桃を斗真の口に入れると、斗真はモグモグと口を動かして笑っている。それをゆっくり何度か繰り返していた。すぐに皿のなかの桃は空っぽになった。やっぱり斗真は食いしん坊だな。
「マーマ」
斗真がしゃべった。少し前から斗真がしゃべりはじめていた。最初の言葉は今と同じ『マーマ』だった。
それから『パーパ』と言ってもらえるようにと、幸仁は何度も「斗真、パーパだよ」と斗真に向かって言い続けたが、未だに『パーパ』とは言ってもらえていない。
今日も斗真に顔を近づけて「斗真、パーパだよ」と言ってみたが、斗真は幸仁の顔を見て笑ってるだけだった。
今日もダメだなと諦めかけた時に、斗真が「じーじ」と言った。幸仁は慌てて斗真の顔を見た。
「斗真、『じーじ』じゃないよ。俺は『パーパ』だよ。言ってみな」
幸仁は斗真の顔を覗きこんだ。
「ばーば」
今度もパーパではなく、濁音になっていた。
「『ばーば』じゃないよ、『パーパ』だよ。ほら、斗真言ってみな」
「じーじ」
「ばーば」
「マーマ」
斗真は『じーじ』と『ばーば』と『マーマ』を繰り返した。幸仁は首を傾げた。
「なんで、『じーじ』と『ばーば』と『マーマ』なんだよ」
幸仁はふてくされるように言った。
「お隣の三橋のおじいちゃんとおばあちゃんにも可愛がってもらってるからかな」
向日葵は困ったような表情を浮かべた。
「そっか、斗真は俺より三橋のおじいちゃんとおばあちゃんと過ごしてる時間の方が長いもんな」
この町内にはお年寄りが多くて幸仁と向日葵のような若い夫婦はめずらしい。だから斗真は、この町内に住むお年寄りの人気者になっているのは、向日葵から聞いていた。前の公園で遊んでもらったり、家に呼んでもらったりしているらしい。
斗真が可愛がってもらえていることはすごく嬉しい。向日葵も小さい頃からここで育っているから、顔見知りも多くて向日葵のことを娘のように思い、斗真のことを孫のように可愛がってくれている。
しかし、斗真と長い時間過ごせるお年寄りたちを羨ましく思うことがある。幸仁も斗真ともっと長い時間一緒に過ごして、もっともっと遊びたいと思う。しかし、仕事をしっかり頑張らないと向日葵と斗真を養っていけない。仕事に行ってる間はもちろん斗真に会えない。朝早く出勤する日は斗真はまだ寝ているし、遅く帰る日は斗真はすでに寝ている。
小さなホームセンターだ。大企業とは違い残業もそこそこ多い。週休二日といっても休日出勤も時々ある。
仕事で疲れていても斗真や向日葵の顔を見ると元気になることは間違いないが、やはり肉体的、精神的な疲れが積もり積もっていくと、正直、休みの日は体を休めたくて斗真と遊ぶ気力がない時もある。
休みは一人で、ボーっとしていたい、ゆっくりと眠りたいと思ってしまう。会社の先輩たちは昔に比べたら、残業も休日出勤もマシになったと言っていた。自分たちの若い頃は一ヶ月間休み無しだったとか、一日の睡眠時間が二、三時間しかなかったとか、一ヶ月の残業時間が二百時間を超えていたとか、武勇伝のように話している。昔の人は本当に働き者なんだなと思う。
昔、親父が仕事から帰ってきて、グッタリとリビングに座りこんでいるのを、何度も目にしたことがあった。親父から生気が感じられなかった。おふくろと幸仁に対して一言も口をきかずに、目を閉じてソファに静かに座っていた。おふくろはそんな親父のことがわかっていたのか、文句も言わず黙って夕食の支度をしていた。
幸仁はそのドンよりした空間にいるのが耐えられなかったので、すぐに自分の部屋に引っ込んだ。親父のせいで家が暗くなるのが嫌だった。
今思えば、親父は社長だから今の幸仁なんかとは比べ物にならないくらいに肉体的、精神的に追い込まれていたのかもしれない。今の幸仁の職場で武勇伝のように話している人たちよりもっと大変だったのかもしれない。それでも頑張り続けていたのは、家族を養っていくため、従業員を守るためだったのだろうか。本当は今の幸仁と同じように、幼ない息子とゆっくりと長い時間を共に過ごしたかったのだろうか。
今日の帰り際の最上店長の言葉が頭を過る。
『お前んとこの親父さんに比べたら屁みたいなもんだわ』
幸仁が疲れた表情で帰ってきても、斗真と向日葵はいつもニコニコと笑ってくれる。斗真と向日葵の笑顔に幸仁は助けられている。子どもの頃の幸仁は、今の斗真や向日葵のような笑顔を親父に向けたことはなく、どちらかと言えば避けていた。疲れて帰ってきた親父に挨拶もしなかった。
今、斗真や向日葵があの頃の幸仁のような態度だったら、自分は頑張れるだろうか。あの時の親父は、どんな気持ちでいたのだろうか。
「斗真はいつも笑ってくれるな。お母さん譲りなのかな。ありがとうな。父さん、斗真の笑顔のお陰で仕事も元気に頑張れるよ」
そう言って斗真の頭を撫でた。『パーパ』はまた今度聞かせてもらうことにしよう。
「店長、お先に失礼します」
幸仁が声をかけると、店長は人差し指の動きを止めて幸仁の方に顔を向けた。
「おお、佐山か」
店長の目は真っ赤になっていた。今日は、店長の姿が見えないと思ったら、一日中、店長室にこもり、パソコンと向き合っていたようだ。
「お疲れ様です」
幸仁はペコリと頭を下げた。
「お疲れさん。今日は早いんだな」
店長はそう言ってから、立ち上がり短い両手を突き上げ「ウーン」と声を上げて背筋を伸ばした。
「はい、店長が忙しい時にすいません」
店長の充血した目を見ると、先に帰ることが申し訳なくなった。
「いいよ、いいよ、そんなこと気にすんな。閉店業務をやって遅くなる日もあるんだから、早く帰れる日は帰ればいいんだ」
「でも、店長、大変そうですね」
「そうなんだー、こいつが厄介なんだよな。みんなは便利って言うけど、俺にとっちゃ全然便利じゃないよ」
店長がそう言って、パソコンを顎で差した。
「パソコンですか」
「そう。明日、会議だからさ、報告書を作成中なんだよ」
「そう言えば、明日は本社で店長会議があるって言ってましたね」
「そっ。また会議で絞られるわけだけど、その前に会議に出す報告書を作らないといけないんだ。それが今月からは手書きの報告書がダメになってさ、パソコンに打ち込んで、今日中にメールで送信しないといけないんだ。手書きだとすぐにできるんだけど、パソコンだと、これがなかなか進まんのよ。ここに先月の売上と利益率を入力しろとか、ここには自慢の売場画像を貼り付けろとか、全くわけわかんねえよ。文字を打ち込むのに時間がかかるし、ほんと歳とるとやっぱりダメだわ」
店長はそう言って頭をボリボリと掻いた。店長は自分は歳だと言うが、まだ五十歳くらいのはずだ。まだまだ元気で若い。売場で力仕事とかバリバリとこなしているので、歳だというよりデスクワーク、特にパソコンが苦手なだけだ。
「店長の仕事って、いろんなことやらなきゃいけなくて大変なんですね」
「まあな。けど、お前んとこの親父さんに比べたら屁みたいなもんだけどな。俺なんて雇われの身だから、毎月給料はちゃんともらえるし、忙しいといったって仕事離れりゃ自由の身だしな。親父さんは社長だからプライベートなんてないと思うぞ。家族のためだけじゃなく、従業員のことまで考えないといけないからな。なのに、いつも新しいことにチャレンジしてすごいよ」
幸仁は親父の話題になったので、逃げ出したくなって、「店長、頑張ってください」と逃げるようにして店長室を出た。
店長は幸仁との会話の合間に親父の話題をしらじらしく挟んでくる。幸仁と親父を仲直りさせようとしているためのようだが、それが無駄だということが、店長は全くわかっていない。店長はいい人で、すごくお世話になっているが、幸仁と親父の問題に他人である店長が口を挟んでくることだけは鬱陶しい。
店長は幸仁がここで働く前から親父と知り合いだ。店長はなぜか親父のことを尊敬している。親父みたいな人間を尊敬する店長の感覚もよくわからない。幸仁の親父は、この地域では有名なスーパーミウラの社長だ。幸仁の祖父三浦奏輔が営む果物店を継いでスーパーミウラとしてオープンさせてから順調に売上を伸ばし店舗数を増やしていったようだが、幸仁にとってはそれが凄いとは思わない。
幸仁と親父との関係が壊れたのは一年以上前のことだ。幸仁が付き合っていた向日葵のお腹に子どもができたことがきっかけだった。向日葵は両親がいなくて親戚もいないので頼れるのは幸仁しかいなかった。しかし、幸仁も大学生だったので、子どもを堕ろすしかないと向日葵は言ってきた。幸仁は向日葵が子ども生んで育てるために、大学をやめて、向日葵と結婚し、バイト先のホームセンターショーマンで社員として働くと決めた。そのことを親父に話すと猛反対され口論となり、最後に幸仁は勘当されて家を飛び出した。それ以来、幸仁は親父とおふくろには会っていない。幸仁は勘当された時の親父の言葉が今でも許せない。三浦孝士という男は血も涙もない人間だ。今でもあの日の親父の言葉を思い出すと怒りで体が熱くなる。
ベビーベッドを覗くと、斗真はスヤスヤと気持ちよさそうに寝息をたてていた。首を横に傾け、半開きの口からよだれが垂れる。幸仁はそれを見ているだけで、一日の疲れがふっ飛ぶ。
「それじゃあ、今から誕生パーティーの準備するね」
向日葵が斗真を起こさないように、幸仁の耳元で小声で言った。今日早く帰ってきた理由は幸仁と向日葵の誕生日だからだ。
「斗真は?」
「夜寝なくなるかもしれないけど、もう少し寝かせておくわ」
向日葵は台所へと向かった。
「それにしても、斗真はよく寝るよな」
幸仁は居間で胡座をかいてテレビのリモコンをつけた。
「寝る子は、元気に育ってくれるかな」
台所から向日葵の声がした。
テレビの画面からは、さほどおもしろくもないお笑いタレントが焼肉を食べている映像が流れていた。
そのお笑いタレントが、「この肉の脂はしつこくなくて本当に甘いですね。これまで食べた焼肉の中で一番美味しいです」と目を大きく見開いてコメントしていた。確かに旨そうな焼肉だったが、『これまで食べた中で一番美味しい』というコメントは大袈裟じゃないか。このお笑いタレントが今までに食べに行った焼肉屋の店員が聞いたらどう思うのだろうかといらぬ心配をした。そんなことを思いながら、焼肉の映像を見て生唾を飲みこんだ。
「はーい、おまたせー」
向日葵が大きな白い皿を両手で持ってきた。その皿を幸仁の前に置いてニコッと笑った。幸仁も笑みを返してから、向日葵が置いた大きな白い皿に視線を落とした。
「えっー、す、すげえ」
幸仁の目に飛び込んできたのは皿の上にどっしり載ったステーキ肉だった。幸仁の掌くらいの大きさで厚さが一センチ以上あった。焼きたてで金色に輝く脂が白い皿に滴っている。脂のいい匂いが部屋中に立ち込めた。さっきテレビに映っていた焼肉よりこっちの方が断然旨そうだった。
「こ、この肉、す、すごいね」
幸仁の口の中は唾液が止まらない。
「そう、二人の誕生日だし奮発しちゃった」
嬉しそうに話す向日葵の手にはワインがあった。
「えっ、ワインまであるの?」
「そう、記念日だからね」
こんな上等な肉とワインを買って、家計の方は大丈夫なのかという言葉は飲み込んだ。今のこの雰囲気をぶち壊すわけにはいかないし、今の稼ぎは向日葵の方が幸仁より多いからだ。
「俺、こんな大きくて旨そうなステーキ食べるのはじめてかも」
「あたしも、こんなステーキ食べるのはじめて。A5ランクの肉だって言ってたよ。感謝、感謝ねー」
A5ランクの肉? 肉のランクは、よくわからないが、たぶん高級なんだろう。それに、向日葵は何に感謝なんだろうか。
これも今日のために向日葵が買ってきたのか、これまでに見たことのないキラキラしたワイングラスで乾杯してから、ワインを口に含んだ。この赤い液体の味の旨いまずいはよくわからないが、気分は盛り上がった。
ステーキにナイフを入れると、柔らかくて簡単に切れた。肉の焼き加減もよくわからないが、ミディアムに丁度よく焼けているんだろうと思った。向日葵は料理なら何でも上手だ。料理は祖母から教えてもらったということだが、さすがに肉の焼き方なんかは教えてもらってないと思う。元々向日葵自身に料理のセンスがあるのだろうか。肉を口に入れると、とろけるように簡単に噛みきれて、肉汁が口の中に広がった。脂がしつこくなくて甘い。旨すぎる。こんな旨い肉、生まれてはじめてだ。さっきのお笑いタレントとは違い、幸仁の場合は間違いなくこれまで食べた肉の中で一番旨い肉だった。
「旨すぎ」
思わず声が出た。
「うん、すんごく、美味しい」
向日葵も興奮気味に声を上げた。
贅沢な気分だった。せっかくの二人の誕生日だ。これくらいの贅沢をしてもバチはあたらないだろうと幸仁は思った。
「ありがとう。美味しかった。ごちそうさま」
「うん、美味しかったね。ごちそうさま」
二人で顔を見合わせ、手を合わせた。そこで、隣の部屋から斗真の泣き声が聞こえてきた。
「斗真が起きたみたいだな」
「ほんとだ。ちょうどだね」
向日葵が斗真の寝ている隣の部屋に視線を向けた。
「斗真は、俺たちが食べ終わるのを待っててくれたのかな」
「斗真って、赤ちゃんなのにすごいね」
「ちょっと見てくるよ」
幸仁は立ち上がり隣の部屋に向かった。
「うん、お願い」
向日葵がそう言ってから、洗い物をキッチンへと運んで行った。
幸仁は斗真を隣の部屋から連れてきて膝の上に置いた。斗真もご機嫌そうだ。向日葵がキッチンから、またお皿をもってきた。
「ユキくん、お待たせ。はい、次は食後のデザート」
向日葵がそう言ってお皿をテーブルの上に置いた。
「おっ」幸仁はお皿を覗きこんだ。
「ついに桃を買いましたー」
お皿の上には一口サイズに切った桃が並べられていた。
「おー、す、すげえな」
「ケーキを買おうと思ったんだけど、ユキくんは桃が大好物だからね」
向日葵はニコニコしながら幸仁の顔を覗きこんだ。
向日葵はなぜ、幸仁が桃が大好物だと知っているのだろうか。幸仁が桃が好きだったのは、子どもの頃に行った桃農園の記憶があるからだ。桃農園で過ごした楽しい時間と食べた桃の美味しさが忘れられなかったからだ。しかし、今は違う。だから、向日葵に桃が大好物だと話した記憶はない。
「向日葵、俺が桃が好きだったことよく知ってたな」
「当たり前よ。ユキくんのことは何でも知ってるんだからね」
幸仁は不思議に思ったが、これ以上桃について話したくなかったので、そのまま終わらせた。
爪楊枝に刺した桃を一切れ持ち上げた。部屋の灯りに反射してみずみずしくキラキラと輝いている。そのまま口に放り込むと口の中が冷んやりとした。噛むと甘い果汁が口いっぱいに広がった。子供のころに食べたあの桃と同じくらいに、向日葵の出したこの桃は美味しかった。これまで食べた桃の中で一番旨いとは言えないが、あの時に食べた桃に匹敵するくらいの旨さだった。あの旨い桃を食べた日のことを思い出したが、幸仁は頭を振って、記憶を振り払った。あれは遠い過去のことで、自分は子どもだったから勘違いしていただけなんだ。
「斗真の分はこっちね」
斗真用に、火を通して細かく砕いた桃がプラスチックの皿にのせてある。
「斗真の方も旨そうだな」
向日葵が幸仁の隣に座り斗真に桃を食べさせていた。
「はい、あーん」
斗真が大きく口を開けた。つられて幸仁も大きく口を開けていた。向日葵がスプーンにのせた桃を斗真の口に入れると、斗真はモグモグと口を動かして笑っている。それをゆっくり何度か繰り返していた。すぐに皿のなかの桃は空っぽになった。やっぱり斗真は食いしん坊だな。
「マーマ」
斗真がしゃべった。少し前から斗真がしゃべりはじめていた。最初の言葉は今と同じ『マーマ』だった。
それから『パーパ』と言ってもらえるようにと、幸仁は何度も「斗真、パーパだよ」と斗真に向かって言い続けたが、未だに『パーパ』とは言ってもらえていない。
今日も斗真に顔を近づけて「斗真、パーパだよ」と言ってみたが、斗真は幸仁の顔を見て笑ってるだけだった。
今日もダメだなと諦めかけた時に、斗真が「じーじ」と言った。幸仁は慌てて斗真の顔を見た。
「斗真、『じーじ』じゃないよ。俺は『パーパ』だよ。言ってみな」
幸仁は斗真の顔を覗きこんだ。
「ばーば」
今度もパーパではなく、濁音になっていた。
「『ばーば』じゃないよ、『パーパ』だよ。ほら、斗真言ってみな」
「じーじ」
「ばーば」
「マーマ」
斗真は『じーじ』と『ばーば』と『マーマ』を繰り返した。幸仁は首を傾げた。
「なんで、『じーじ』と『ばーば』と『マーマ』なんだよ」
幸仁はふてくされるように言った。
「お隣の三橋のおじいちゃんとおばあちゃんにも可愛がってもらってるからかな」
向日葵は困ったような表情を浮かべた。
「そっか、斗真は俺より三橋のおじいちゃんとおばあちゃんと過ごしてる時間の方が長いもんな」
この町内にはお年寄りが多くて幸仁と向日葵のような若い夫婦はめずらしい。だから斗真は、この町内に住むお年寄りの人気者になっているのは、向日葵から聞いていた。前の公園で遊んでもらったり、家に呼んでもらったりしているらしい。
斗真が可愛がってもらえていることはすごく嬉しい。向日葵も小さい頃からここで育っているから、顔見知りも多くて向日葵のことを娘のように思い、斗真のことを孫のように可愛がってくれている。
しかし、斗真と長い時間過ごせるお年寄りたちを羨ましく思うことがある。幸仁も斗真ともっと長い時間一緒に過ごして、もっともっと遊びたいと思う。しかし、仕事をしっかり頑張らないと向日葵と斗真を養っていけない。仕事に行ってる間はもちろん斗真に会えない。朝早く出勤する日は斗真はまだ寝ているし、遅く帰る日は斗真はすでに寝ている。
小さなホームセンターだ。大企業とは違い残業もそこそこ多い。週休二日といっても休日出勤も時々ある。
仕事で疲れていても斗真や向日葵の顔を見ると元気になることは間違いないが、やはり肉体的、精神的な疲れが積もり積もっていくと、正直、休みの日は体を休めたくて斗真と遊ぶ気力がない時もある。
休みは一人で、ボーっとしていたい、ゆっくりと眠りたいと思ってしまう。会社の先輩たちは昔に比べたら、残業も休日出勤もマシになったと言っていた。自分たちの若い頃は一ヶ月間休み無しだったとか、一日の睡眠時間が二、三時間しかなかったとか、一ヶ月の残業時間が二百時間を超えていたとか、武勇伝のように話している。昔の人は本当に働き者なんだなと思う。
昔、親父が仕事から帰ってきて、グッタリとリビングに座りこんでいるのを、何度も目にしたことがあった。親父から生気が感じられなかった。おふくろと幸仁に対して一言も口をきかずに、目を閉じてソファに静かに座っていた。おふくろはそんな親父のことがわかっていたのか、文句も言わず黙って夕食の支度をしていた。
幸仁はそのドンよりした空間にいるのが耐えられなかったので、すぐに自分の部屋に引っ込んだ。親父のせいで家が暗くなるのが嫌だった。
今思えば、親父は社長だから今の幸仁なんかとは比べ物にならないくらいに肉体的、精神的に追い込まれていたのかもしれない。今の幸仁の職場で武勇伝のように話している人たちよりもっと大変だったのかもしれない。それでも頑張り続けていたのは、家族を養っていくため、従業員を守るためだったのだろうか。本当は今の幸仁と同じように、幼ない息子とゆっくりと長い時間を共に過ごしたかったのだろうか。
今日の帰り際の最上店長の言葉が頭を過る。
『お前んとこの親父さんに比べたら屁みたいなもんだわ』
幸仁が疲れた表情で帰ってきても、斗真と向日葵はいつもニコニコと笑ってくれる。斗真と向日葵の笑顔に幸仁は助けられている。子どもの頃の幸仁は、今の斗真や向日葵のような笑顔を親父に向けたことはなく、どちらかと言えば避けていた。疲れて帰ってきた親父に挨拶もしなかった。
今、斗真や向日葵があの頃の幸仁のような態度だったら、自分は頑張れるだろうか。あの時の親父は、どんな気持ちでいたのだろうか。
「斗真はいつも笑ってくれるな。お母さん譲りなのかな。ありがとうな。父さん、斗真の笑顔のお陰で仕事も元気に頑張れるよ」
そう言って斗真の頭を撫でた。『パーパ』はまた今度聞かせてもらうことにしよう。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が
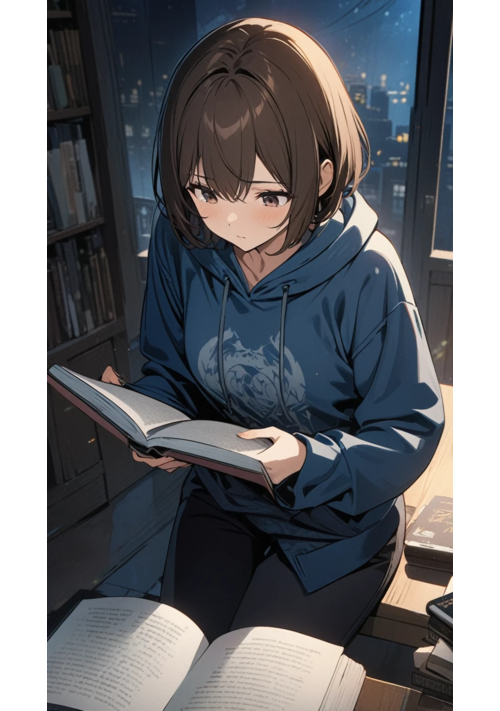
声の響く洋館
葉羽
ミステリー
神藤葉羽と望月彩由美は、友人の失踪をきっかけに不気味な洋館を訪れる。そこで彼らは、過去の住人たちの声を聞き、その悲劇に導かれる。失踪した友人たちの影を追い、葉羽と彩由美は声の正体を探りながら、過去の未練に囚われた人々の思いを解放するための儀式を行うことを決意する。
彼らは古びた日記を手掛かりに、恐れや不安を乗り越えながら、解放の儀式を成功させる。過去の住人たちが解放される中で、葉羽と彩由美は自らの成長を実感し、新たな未来へと歩み出す。物語は、過去の悲劇を乗り越え、希望に満ちた未来を切り開く二人の姿を描く。


密室島の輪舞曲
葉羽
ミステリー
夏休み、天才高校生の神藤葉羽は幼なじみの望月彩由美とともに、離島にある古い洋館「月影館」を訪れる。その洋館で連続して起きる不可解な密室殺人事件。被害者たちは、内側から完全に施錠された部屋で首吊り死体として発見される。しかし、葉羽は死体の状況に違和感を覚えていた。
洋館には、著名な実業家や学者たち12名が宿泊しており、彼らは謎めいた「月影会」というグループに所属していた。彼らの間で次々と起こる密室殺人。不可解な現象と怪奇的な出来事が重なり、洋館は恐怖の渦に包まれていく。


深淵の迷宮
葉羽
ミステリー
東京の豪邸に住む高校2年生の神藤葉羽は、天才的な頭脳を持ちながらも、推理小説の世界に没頭する日々を送っていた。彼の心の中には、幼馴染であり、恋愛漫画の大ファンである望月彩由美への淡い想いが秘められている。しかし、ある日、葉羽は謎のメッセージを受け取る。メッセージには、彼が憧れる推理小説のような事件が待ち受けていることが示唆されていた。
葉羽と彩由美は、廃墟と化した名家を訪れることに決めるが、そこには人間の心理を巧みに操る恐怖が潜んでいた。次々と襲いかかる心理的トラップ、そして、二人の間に生まれる不穏な空気。果たして彼らは真実に辿り着くことができるのか?葉羽は、自らの推理力を駆使しながら、恐怖の迷宮から脱出することを試みる。

密室の継承 ~黒川家の遺産~
山瀬滝吉
ミステリー
百年の歴史と格式を誇る老舗旅館、黒川旅館。四季折々の風情が漂う古都の一角に位置し、訪れる者に静かな安らぎと畏敬の念を抱かせるこの場所で、ある日、悲劇が起こる。旅館の当主・黒川源一郎が自室で亡くなっているのが発見され、現場は密室。しかも彼の死因は毒殺によるものだった。事件の背後には、黒川家の長年にわたる複雑な家族関係と、当主の隠された秘密が暗い影を落としている。探偵・神楽坂奏は、地元警察からの依頼を受け、黒川家と黒川旅館に潜む謎に挑むことになる。
若き探偵の神楽坂が調査を進めるにつれ、事件に関わる人物たちの思惑や過去の葛藤が少しずつ明らかになる。野心家の長女・薫は、父親から愛されるため、そして黒川旅館の継承者として認められるためにあらゆる手段を厭わない。一方、穏やかな長男・圭吾は、父からの愛情を感じられないまま育ち、家族に対しても心の距離を保っている。さらに、長年旅館に勤める従業員・佐藤の胸にも、かつての当主との秘密が潜んでいる。事件は、黒川家の隠し子の存在をほのめかし、神楽坂の捜査は次第に家族間の裏切り、葛藤、愛憎の渦に引き込まれていく。
本作は、古都の美しい風景と、登場人物たちの心の闇が対比的に描かれ、読む者に独特の緊張感を抱かせる。神楽坂が少しずつ真相に迫り、密室トリックの解明を通して浮かび上がる真実は、黒川家にとってあまりにも過酷で、残酷なものであった。最後に明かされる「家族の絆」や「愛憎の果て」は、ただの殺人事件に留まらない深いテーマを含み、読者の心に余韻を残す。
事件の謎が解けた後、残された家族たちはそれぞれの想いを抱えながら、旅館の新たな未来に向かう決意を固める。旅館の格式を守りながらも、時代に合わせて新しい形で再生する道を模索する姿は、物語全体に深みを与えている。
愛と憎しみ、裏切りと許し、家族とは何かを問いかける本作は、読者にとって心に残るミステリー小説となるだろう。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















