1 / 3
ざまみろ、お前は俺が好き
しおりを挟む
声がやんだ。
ディベートが終わる。テーブルの向こうで、奴が健闘を称えるようににっこりと微笑んでくる。
顔のいい男にしか似合いそうにない、センターパートの髪型。すっと通った鼻筋。そろった歯並び。
人をこてんぱんにしておいて。
(うわあ。嫌味)
井の中の蛙は顔をしかめた。大海がまるっと嫌になっていた。
この蛙、名を青田秀(あおた しゅう)という。つまり俺である。
地元では蛙の自覚はなく、むしろ龍か何かだと思っていた。たぶんまわりもそう思っていたと思う。
世の中にはいろんな種類のオタクがいるが、俺の場合は勉強オタクだった。同級生たちと青春ごっこに興じるよりは、未知の世界を攻略していく方が面白かった。ただし物理。お前はダメだ。
夢というほどのものは持っていなかったが、もっと広い世界に行きたいとふんわり思っていた。海外なんていいかもしれない、ぐらいに。何せ、自己定義が龍だったので。
留学制度が充実しているのが魅力だった。難関の外国語大学を目指し、あの悪名高い英語の試験を突破して、ちゃんと合格した。
思えばそれが間違いのもとだった。
(あれ、俺、浮いてね?)
生まれからしてグローバルな奴らがうようよしている。それになんだか育ちがいい。外交官のご子息ご令嬢がまったく珍しくない。そして思ったより女子が多い。
(……ま、いいか)
浮いているだけなら別に大きな問題はなかった。
勉強さえできればいい。俺がナンバーワンならもっといい。
だが現実は厳しかった。
まず語学の問題だ。
一般的基準なら特上だった俺の語学力が、よくて並。ネイティブスピーカーレベルの人間に太刀打ちできるわけがなかった。せめて流ちょうに鳴ける蛙になろう。ゲコ。
いちばん詰まったのがディベートだった。もっと人と話す訓練を積んでおけば楽だったかもしれない。自分の思考を言語化するのは母語でも面倒なのに、それが英語だのフランス語だの。自説の補強? 説得力?
(一通り話してわかんない奴なんて、放っておけばよくね?)
トピックの問題もある。
法学はそれなりに興味が持てたから、相応に口が回った。が、社会学はどうにも喋れない。統計というものに根本的疑念を持っているせいである。言いたいことのために、証拠を後付けする感じが気持ち悪い。
不信感はモチベーションの低下を招き、当然のように低成績をもたらした。まことに遺憾である。
ああ、ディベートが憎い。対抗戦だと、いつも俺がはっきりと足を引っ張る。
対抗チームに奴がいると、状況はさらに悪くなる。
鳥見瑛人(とりみ えいと)。
この男、たいていの成績が優秀なうえに、議論が憎たらしいほど強い。するっと弱点を突いてきたかと思うと、勝手に持論の補強に使い、自分に都合の良い議論を始めてしまう。
こうなるともう、俺では手も足も出なくなる。ちゃんとこちらの言い分も聞いているポーズをとるのがまた、抜け目がない。
先生が熱心に奴を称える様子をぼんやりと眺める。ひとしきり褒め終わった先生は俺たちの方もざっと見渡し、「君たちも頑張った」という旨の英語を口にした。熱の一切こもっていないグレーの目。温度差は明らかである。
(俺と何が違うんだ)
何もかも、か。
これだけできるのに努力の匂いがしないのも、癪にさわる男だ。
この大学に来るためだけに、俺はあんなに時間と労力を費やした。なのにこの男とは同じ土俵にも立てない。
どうせこいつも、お育ちが違うんだろう。階段の数が少なくて、楽に頂上についたタイプだ。
どうでもいい。あいつを嫌ったところで俺のディベート力が上がるわけでもない。どうせダメ、考えるだけ無駄。
そういうわけで、蛙は世界が嫌になった。
ところで、東京は誘惑の多い街である。
「何やってんの」
きらきらしたネオンを背景に、嫌味なぐらい整った顔が俺を覗き込んでくる。鳥見の顔だとわかると俺は呻いて、バス停のベンチに座りなおした。
うわ、最悪。腕組みをしつつ目を閉じ、白い顔を視界から追い出す。
「なんでまた寝んの」
男は半笑いしている。
「ふて寝」
「酒は二十歳からだよ」
「飲んでねえ」
「飲んでないのにこんなところに寝てたの?」
まるきり信じていない声だ。
「お前には関係ないだろ」
俺は片目だけ開け、唸った。
郊外にある大学からはるばる遊びに来たのに、ひとり焼肉とひとりカラオケは思ったより面白くなかった。散財したのにこれでは割に合わない。
元をとろうと座り込んでぐずぐずしていたところ、どうやら寝落ちしていたらしい。
「もしかして昼のあれ、根に持ってる?」
「うぜえ。ほっとけ」
「ベタなこと言っていい? 風邪ひくぞ」
「お前さ、俺のことみじめにしようとしてねえか?」
男は面白そうな顔をした。
「かもね」
「なんでお前がこんなとこにいるんだよ」
「たまたま?」
あきらかにはぐらかすように、鳥見は言った。
「たまたまこんな治安の悪いところに?」
「それ以上はプライベートなので」
鳥見は指を唇の前に立てた。
俺はふたたび呻いた。勘がいいせいで気づいてしまった。
なんだ。女とホテルか。
(その顔面ならさぞや困らないだろうな)
女の子なんて面倒くささのかたまりで、別にうらやましいわけでもない。が、鳥見のスペックがさらに補強された点は面白くない。
あ、でも。俺は周りを見回した。
(今ひとりってことは、振られたわけか)
さすがに女の子をひとりで帰らせるはずないだろうし。
俺は急に機嫌がよくなった。
「何にやついてるんだよ」
「別に?」
そうかそうか、こいつも人間だったか。ああ、よかった。これで焼肉の元がとれたというものだ。
「まあ、人生いろいろあるわな。気にすんな」
俺が笑いかけると、奴は冷たい顔をした。
「なんのことか知らないけど、君になぐさめられるほど落ちぶれてはいないな」
「あー、はいはい。そうだよねー」
鳥見はへらへらする俺をじっと眺めた。
「くそうざいけど、この際、こいつでもいいか……」
「何が」
鳥見は口元だけで微笑んだ。どうしてこいつの笑みは常に打算的なんだろう。
「ルームシェアしない? いっしょに住んでた奴が出てって、新しい同居人を探してるんだ」
俺はきょとんとした。
「お前、金ないの?」
金欠と鳥見はいちばん遠い気がしていた。特に根拠があったわけではないが。
鳥見はまた氷のように冷たい顔をした。
「留学資金に余裕を持たせておきたいのが恥ずかしいことか?」
「ああ……いや、そういうわけじゃ」
俺は口ごもった。
なるほど、すっかり忘れていた。今度バイトを始めないと間に合わないかもしれない。
少し間があって、俺は膝を打った。
「その話、乗った」
俺にとってはうまい話だということに気づいたのである。
「だろ」
鳥見はスマートフォンを取り出した。画面をいじったかと思うと、地面にジーンズの膝をついて俺の隣にぐいと頭を近づけてくる。男性用香水のいい匂いが鼻を直撃した。
なんだなんだ、と思っていると、フラッシュが光った。
「いきなり何」
「新しいルームメイトの紹介。ふつうするから」
涼しい顔で言って、鳥見は画面を操作する。
あ、そういうことをするものなんですね。俺には興味のない世界である。
「投稿するけど、いいよね?」
「ああ、うん」
鳥見がおざなりに画面を見せてくる。
(なるほど。あの無理やりな角度だと夜景がきれいに撮れると)
俺は感心した。これが映えというやつか。
サイケデリックな光に包まれ、鳥見が画面の中央で笑っている。
俺は半分見切れている。ぽかんと間抜けに鳥見を見つめている顔は、なんとも特徴が薄い。
まるでカスミソウのように鳥見を引き立てるだけの存在。カスミソウに失礼か。
「……お前、友だち多いんだろ? なんで俺なの」
鳥見は答えないで、スマートフォンの中の住人になっている。
(鳥見って思ったよりつまんない奴だな)
あくびをしながらスマートフォンを取り出した。
(こいつとルームシェアするのか。意識高くて面倒そう)
そう思うのは、鳥見に対するひがみのせいなんだろうが。
(小せえ俺)
こいつが頂上にいるから悪いんだよ、と俺は内心毒づいた。俺と同じ階層にいてくれたら、妙な偏見をもたずに付き合えただろうに。
ヘッドライトを大げさに光らせ、バスがやってくる。
(鳥見って思ったより面白い奴だな)
そう思うようになったのは、しばらく一緒に暮らしはじめてからだ。
ぽんと袋を開け、薄く軽い物体を指先でかき混ぜる。つまんで口に放り、ばりりと噛みしめる。
俺はソファにうずくまり、映画を見ながらひたすらポテトチップを音高く食べている。
むろん、わざとである。
うしろで鳥見が苛立っている気配がする。
「静かにしてくれないかな」
「ヘッドホンしてるだろ」
「オーディオじゃない。咀嚼音がうるさいって言ってるんだ」
俺はひそかににんまりと笑った。
この男、からかうととても面白い。
ぼくは無駄なことはしない、というのが鳥見の口癖だった。
自己管理だと言いながら、鳥見は家では野菜とタンパク質ばかりの食事をする。嗜好品ひとつ食わない。金と健康と時間の無駄だからだ。少なくとも鳥見はそう主張する。
俺は奴が無駄だと思うすべてを実践している。
塩と油が味蕾に刺さる。こんがりと揚がったじゃがいもの香りが口をいっぱいにする。
なんの役にも立たないB級ホラー映画を半笑いで見ながら食べるポテトチップスは、やはりいい。
鳥見は苦々しそうにため息をついた。
「ぼくのソファだからな。汚すなよ。人を呼んだときに困る」
「はーい」
たしかに高そうなソファだった。鳥見はインテリアにも凝っている。どこを切り取っても素敵な写真になりそうな2DKの部屋だ。
だが、ルームシェアをしないと家賃が厳しい。
(金持ちなのかそうじゃないのか、わかんねえ)
画面の中で、安っぽい作り物のゾンビが上から垂れ下がっている。
面白いと思う点はほかにもあった。
俺が読んでいる本をこっそりチェックして、同じものを読んでいるらしいのだ。
たとえば俺が読書を中断して部屋を出る。トイレにでも行ったふりをして部屋の様子を覗く。
すると鳥見はちゃんと罠に引っかかる。
スマートフォンを片手に表紙を確認しているのは、タイトルを検索しているのだろう。
(変な奴)
何らかのプライドにかかわるらしく、けっして正面からは尋ねてこない。別にこっそりチェックしなくても、聞かれたら題名や著者名ぐらいは答えてやるのに。
理由なら見当はついている。
会話のとき、俺だけが知っていて自分が知らないことがあるのが、許せないらしいのである。
蛙ごときが知っていることは、ぼくだって当然知っているべきだ。そう思っているのが透けて見えている。
そして次の瞬間、
「え、あれをそう読んだの? 本気? だってこの著者……」
このように解釈バトルを吹っ掛けてくる。厄介だ。これが始まると、残念ながら俺に勝ち目はない。
さて俺も蛙ではあるが、まるきり馬鹿というわけではない。このパターンに気づいたので、俺も対抗策をとることにした。
本はなるべく電子書籍で読むようにしたのである。これでもう、俺が読んでいる本の表紙は物理的に覗けない。
それでもって知識をひけらかすと、鳥見は実に面白い表情をする。
「あ、初耳だった? 鳥見なら知ってるかと思った」
鳥見の眉間に深々としわが寄っていくのを、俺は嬉々として眺める。
(気持ちいいー)
いつもは負ける一方なんだ。俺だって少しぐらい勝利の快感を味わいたい。性格が悪いとは思いつつ、こたえられない。
楽しかった。躍起になって本を読んだ。本さえ読めば、あいつの知らないことが増える。蛙でもあいつに勝てる。
俺はふたたび勉強が苦にならなくなっていた。知識さえ潤沢なら、あの憎きディベートも多少は形になることにも気づいた。要は物量作戦である。
そしてついに、いくつかの科目で期末の成績が鳥見に肉薄するまでになった。もちろんうれしかったが、同時にあと一歩足りなかったのが猛烈に悔しかった。ちなみに社会学は相変わらずだ。
そう、俺はやりすぎた。
「ええ、またうちに人を呼ぶのか」
俺は顔を思い切りしかめた。
「ああ。今週末」
鳥見はときどき、社会人の知り合いを家に招く。いったいどこで知り合ってくるんだか。そのたびに邪険にされる俺の身にもなってほしい。
仕方がない、チェーンのコーヒー屋にでも避難するか。進捗状況が23パーセントの電子書籍をさっさと消化してしまおう。見てろ、また賢くなって戻ってくるぞ、俺は。
俺の目論見をよそに、鳥見は冷ややかに微笑んだ。
「コネクションづくりは大事だよ。時間のある今のうちにつながりを作っておかないと」
「そんなもんかねぇ?」
俺はつい純粋に首をかしげてしまった。有望とはいえただの大学生を、数年先の遠い未来まで覚えていてくれる人っているんだろうか。
「その時間、勉強したらいいんじゃね? だから最近、俺に負けそうなんじゃ」
鳥見の顔から笑みが急速に消えていく。
さすがに口が滑ったな、と俺はちらりと後悔した。鳥見の努力を全否定するつもりはなかったのだ。
ばん。硬い音が空気を震わせた。
鳥見が机に手のひらを伏せ、俺をにらんでいる。
「プレッシャーのない君に何がわかるんだ」
地雷を踏んだのだと俺は直感した。
「ぼくだってそんな風に気楽にしてたかった」
奇妙に抑えた、這うような声だ。
「無駄なこと。楽しいこと。ぼくは全部あきらめて、ようやくこの位置にいるんだ。それを君が、君なんかが」
さすがの俺もすくんでしまった。
「……ごめん。お前もいろいろあったんだ」
俺が示した理解はかえって逆効果だった。
「憐れむなよ!」
きれいな瞳がぎらぎらと光っている。俺は蛇ににらまれた蛙のように動けなくなる。
少し間があって、鳥見は暗く笑った。
「謝るなら、君が楽しいことをぼくに教えてよ」
「えっ」
俺は面食らった。鳥見はテーブル越しに、俺の胸倉をつかんだ。
鳥見の目が脅すようにすっと細くなる。
「たぶんぼく、男の方がいいんだ。前の同居人はそのせいで逃げていった」
鳥見がルームシェアを持ちかけてきたとき、ホテル街のそばだったことを、俺は急に思い出した。
(あのときこいつが振られたのは女の子じゃなくて……)
同居人の男だった、ということなのか。
鳥見の笑い声が自虐的に響く。
「はは、気持ち悪いだろ。君もそうしなよ」
俺はごくっと唾を飲んだ。何それ。
「でないと食べちゃうよ」
こいつ、おかしい。ストイックに生きすぎて、行きつくところまで行ってしまった感じ。
「ねえ。青田。聞いてる?」
子どもみたいな喋り方だ。
生温かい呼気が近づいてくる。俺を覗き込む瞳は、少し泣きそうに見えた。
(これが、こいつの、本性……?)
この男は、必死になってこれを隠していたわけか。
(……あれ?)
こんな絶体絶命の状態だというのに、俺はふいにおかしくなった。
(こいつ、こっちの方が断然いいじゃん)
いつもの仮面じみた完璧さより、このぐちゃぐちゃな自我の方がよっぽど人間らしい。
「ふふっ」
思わず笑いがこみ上げて、抑えられなかった。
「何がおかしいんだ」
至近距離で、鳥見はひどく傷ついた顔をしている。
「お前、俺なんかのこと好きだったんだ。へえ」
鳥見はぽかんと口を開けた。
「な、なんでそうなる」
「まあ今のお前なら? 友だちから始めるんなら、考えてやらんでもないかな」
鳥見は口をぱくぱくさせた。
「なんで君がそんなに偉そうなんだ!? ふだんは卑屈なくせにその自己肯定感はどこから来たんだ」
「自分でもわからん」
だが妙に気分がいい。この感情はなんだろう。しいて言えば、ざまみろ、だろうか。
あんなに見下していたくせに、俺なんかが好きだなんて。
「別に君が好きでルームシェアを持ちかけたわけじゃない! 君ならぼくの邪魔にならないと思っただけで」
「いっしょにいると優越感に浸れると思った? 俺がはるか下の方で足掻いてるのが面白かった?」
鳥見は口をつぐんだ。顔に罪悪感が浮かんでいる。
「いいんだよ。俺はうそつきより正直者の方が好きだ。覚えておけ」
とんと胸を押し、鳥見を軽く突き離す。
鳥見は苦々しい顔をして、セットした頭をぐしゃぐしゃにかき乱している。
俺は奴を一瞥して、部屋を出た。
からかって面白いだけの奴だった鳥見は俺の中で、はっきりと興味深い存在に格上げされた。
こんなことがあったくせに、鳥見との関係はたいして変わらなかった。
鳥見はまるでこの事件が存在しなかったかのように振舞った。俺が好きだとどうしても認めたくないのかもしれない。
(素直じゃねえ奴)
あるいは、自分があんな風に取り乱したこと自体が許せないのか。
俺も積極的に奴とどうにかなりたいわけでもなかった。あの件については忘れたふりをしてやりながら、俺はこっそりと奴の観察を続けることにした。
互いにぐちゃぐちゃな中身を隠し持ったまま、表面上は何もかも元通りになった。
週末、鳥見は意識の高いままに知人を家に招いた。俺はその間カフェで時間をつぶした。鳥見が帰ってくると、新たに仕入れた知識で鳥見をからかった。
「……君って奴は」
冷静を装っているのだろうが、口元はひくひくしているし、顔は苛立ちで赤くなっている。楽しい。
「ああ、そうそう。忘れてた」
寝る前のコーラをラッパ飲みしながら、俺は鳥見を振り返った。
「明日からの冬休み、俺、実家に帰るから。そのつもりで。あれ、そういえば、荷物詰めなきゃ」
鳥見は何か言いたげにしたが、やがて吐き捨てた。
「勝手にしなよ」
ディベートが終わる。テーブルの向こうで、奴が健闘を称えるようににっこりと微笑んでくる。
顔のいい男にしか似合いそうにない、センターパートの髪型。すっと通った鼻筋。そろった歯並び。
人をこてんぱんにしておいて。
(うわあ。嫌味)
井の中の蛙は顔をしかめた。大海がまるっと嫌になっていた。
この蛙、名を青田秀(あおた しゅう)という。つまり俺である。
地元では蛙の自覚はなく、むしろ龍か何かだと思っていた。たぶんまわりもそう思っていたと思う。
世の中にはいろんな種類のオタクがいるが、俺の場合は勉強オタクだった。同級生たちと青春ごっこに興じるよりは、未知の世界を攻略していく方が面白かった。ただし物理。お前はダメだ。
夢というほどのものは持っていなかったが、もっと広い世界に行きたいとふんわり思っていた。海外なんていいかもしれない、ぐらいに。何せ、自己定義が龍だったので。
留学制度が充実しているのが魅力だった。難関の外国語大学を目指し、あの悪名高い英語の試験を突破して、ちゃんと合格した。
思えばそれが間違いのもとだった。
(あれ、俺、浮いてね?)
生まれからしてグローバルな奴らがうようよしている。それになんだか育ちがいい。外交官のご子息ご令嬢がまったく珍しくない。そして思ったより女子が多い。
(……ま、いいか)
浮いているだけなら別に大きな問題はなかった。
勉強さえできればいい。俺がナンバーワンならもっといい。
だが現実は厳しかった。
まず語学の問題だ。
一般的基準なら特上だった俺の語学力が、よくて並。ネイティブスピーカーレベルの人間に太刀打ちできるわけがなかった。せめて流ちょうに鳴ける蛙になろう。ゲコ。
いちばん詰まったのがディベートだった。もっと人と話す訓練を積んでおけば楽だったかもしれない。自分の思考を言語化するのは母語でも面倒なのに、それが英語だのフランス語だの。自説の補強? 説得力?
(一通り話してわかんない奴なんて、放っておけばよくね?)
トピックの問題もある。
法学はそれなりに興味が持てたから、相応に口が回った。が、社会学はどうにも喋れない。統計というものに根本的疑念を持っているせいである。言いたいことのために、証拠を後付けする感じが気持ち悪い。
不信感はモチベーションの低下を招き、当然のように低成績をもたらした。まことに遺憾である。
ああ、ディベートが憎い。対抗戦だと、いつも俺がはっきりと足を引っ張る。
対抗チームに奴がいると、状況はさらに悪くなる。
鳥見瑛人(とりみ えいと)。
この男、たいていの成績が優秀なうえに、議論が憎たらしいほど強い。するっと弱点を突いてきたかと思うと、勝手に持論の補強に使い、自分に都合の良い議論を始めてしまう。
こうなるともう、俺では手も足も出なくなる。ちゃんとこちらの言い分も聞いているポーズをとるのがまた、抜け目がない。
先生が熱心に奴を称える様子をぼんやりと眺める。ひとしきり褒め終わった先生は俺たちの方もざっと見渡し、「君たちも頑張った」という旨の英語を口にした。熱の一切こもっていないグレーの目。温度差は明らかである。
(俺と何が違うんだ)
何もかも、か。
これだけできるのに努力の匂いがしないのも、癪にさわる男だ。
この大学に来るためだけに、俺はあんなに時間と労力を費やした。なのにこの男とは同じ土俵にも立てない。
どうせこいつも、お育ちが違うんだろう。階段の数が少なくて、楽に頂上についたタイプだ。
どうでもいい。あいつを嫌ったところで俺のディベート力が上がるわけでもない。どうせダメ、考えるだけ無駄。
そういうわけで、蛙は世界が嫌になった。
ところで、東京は誘惑の多い街である。
「何やってんの」
きらきらしたネオンを背景に、嫌味なぐらい整った顔が俺を覗き込んでくる。鳥見の顔だとわかると俺は呻いて、バス停のベンチに座りなおした。
うわ、最悪。腕組みをしつつ目を閉じ、白い顔を視界から追い出す。
「なんでまた寝んの」
男は半笑いしている。
「ふて寝」
「酒は二十歳からだよ」
「飲んでねえ」
「飲んでないのにこんなところに寝てたの?」
まるきり信じていない声だ。
「お前には関係ないだろ」
俺は片目だけ開け、唸った。
郊外にある大学からはるばる遊びに来たのに、ひとり焼肉とひとりカラオケは思ったより面白くなかった。散財したのにこれでは割に合わない。
元をとろうと座り込んでぐずぐずしていたところ、どうやら寝落ちしていたらしい。
「もしかして昼のあれ、根に持ってる?」
「うぜえ。ほっとけ」
「ベタなこと言っていい? 風邪ひくぞ」
「お前さ、俺のことみじめにしようとしてねえか?」
男は面白そうな顔をした。
「かもね」
「なんでお前がこんなとこにいるんだよ」
「たまたま?」
あきらかにはぐらかすように、鳥見は言った。
「たまたまこんな治安の悪いところに?」
「それ以上はプライベートなので」
鳥見は指を唇の前に立てた。
俺はふたたび呻いた。勘がいいせいで気づいてしまった。
なんだ。女とホテルか。
(その顔面ならさぞや困らないだろうな)
女の子なんて面倒くささのかたまりで、別にうらやましいわけでもない。が、鳥見のスペックがさらに補強された点は面白くない。
あ、でも。俺は周りを見回した。
(今ひとりってことは、振られたわけか)
さすがに女の子をひとりで帰らせるはずないだろうし。
俺は急に機嫌がよくなった。
「何にやついてるんだよ」
「別に?」
そうかそうか、こいつも人間だったか。ああ、よかった。これで焼肉の元がとれたというものだ。
「まあ、人生いろいろあるわな。気にすんな」
俺が笑いかけると、奴は冷たい顔をした。
「なんのことか知らないけど、君になぐさめられるほど落ちぶれてはいないな」
「あー、はいはい。そうだよねー」
鳥見はへらへらする俺をじっと眺めた。
「くそうざいけど、この際、こいつでもいいか……」
「何が」
鳥見は口元だけで微笑んだ。どうしてこいつの笑みは常に打算的なんだろう。
「ルームシェアしない? いっしょに住んでた奴が出てって、新しい同居人を探してるんだ」
俺はきょとんとした。
「お前、金ないの?」
金欠と鳥見はいちばん遠い気がしていた。特に根拠があったわけではないが。
鳥見はまた氷のように冷たい顔をした。
「留学資金に余裕を持たせておきたいのが恥ずかしいことか?」
「ああ……いや、そういうわけじゃ」
俺は口ごもった。
なるほど、すっかり忘れていた。今度バイトを始めないと間に合わないかもしれない。
少し間があって、俺は膝を打った。
「その話、乗った」
俺にとってはうまい話だということに気づいたのである。
「だろ」
鳥見はスマートフォンを取り出した。画面をいじったかと思うと、地面にジーンズの膝をついて俺の隣にぐいと頭を近づけてくる。男性用香水のいい匂いが鼻を直撃した。
なんだなんだ、と思っていると、フラッシュが光った。
「いきなり何」
「新しいルームメイトの紹介。ふつうするから」
涼しい顔で言って、鳥見は画面を操作する。
あ、そういうことをするものなんですね。俺には興味のない世界である。
「投稿するけど、いいよね?」
「ああ、うん」
鳥見がおざなりに画面を見せてくる。
(なるほど。あの無理やりな角度だと夜景がきれいに撮れると)
俺は感心した。これが映えというやつか。
サイケデリックな光に包まれ、鳥見が画面の中央で笑っている。
俺は半分見切れている。ぽかんと間抜けに鳥見を見つめている顔は、なんとも特徴が薄い。
まるでカスミソウのように鳥見を引き立てるだけの存在。カスミソウに失礼か。
「……お前、友だち多いんだろ? なんで俺なの」
鳥見は答えないで、スマートフォンの中の住人になっている。
(鳥見って思ったよりつまんない奴だな)
あくびをしながらスマートフォンを取り出した。
(こいつとルームシェアするのか。意識高くて面倒そう)
そう思うのは、鳥見に対するひがみのせいなんだろうが。
(小せえ俺)
こいつが頂上にいるから悪いんだよ、と俺は内心毒づいた。俺と同じ階層にいてくれたら、妙な偏見をもたずに付き合えただろうに。
ヘッドライトを大げさに光らせ、バスがやってくる。
(鳥見って思ったより面白い奴だな)
そう思うようになったのは、しばらく一緒に暮らしはじめてからだ。
ぽんと袋を開け、薄く軽い物体を指先でかき混ぜる。つまんで口に放り、ばりりと噛みしめる。
俺はソファにうずくまり、映画を見ながらひたすらポテトチップを音高く食べている。
むろん、わざとである。
うしろで鳥見が苛立っている気配がする。
「静かにしてくれないかな」
「ヘッドホンしてるだろ」
「オーディオじゃない。咀嚼音がうるさいって言ってるんだ」
俺はひそかににんまりと笑った。
この男、からかうととても面白い。
ぼくは無駄なことはしない、というのが鳥見の口癖だった。
自己管理だと言いながら、鳥見は家では野菜とタンパク質ばかりの食事をする。嗜好品ひとつ食わない。金と健康と時間の無駄だからだ。少なくとも鳥見はそう主張する。
俺は奴が無駄だと思うすべてを実践している。
塩と油が味蕾に刺さる。こんがりと揚がったじゃがいもの香りが口をいっぱいにする。
なんの役にも立たないB級ホラー映画を半笑いで見ながら食べるポテトチップスは、やはりいい。
鳥見は苦々しそうにため息をついた。
「ぼくのソファだからな。汚すなよ。人を呼んだときに困る」
「はーい」
たしかに高そうなソファだった。鳥見はインテリアにも凝っている。どこを切り取っても素敵な写真になりそうな2DKの部屋だ。
だが、ルームシェアをしないと家賃が厳しい。
(金持ちなのかそうじゃないのか、わかんねえ)
画面の中で、安っぽい作り物のゾンビが上から垂れ下がっている。
面白いと思う点はほかにもあった。
俺が読んでいる本をこっそりチェックして、同じものを読んでいるらしいのだ。
たとえば俺が読書を中断して部屋を出る。トイレにでも行ったふりをして部屋の様子を覗く。
すると鳥見はちゃんと罠に引っかかる。
スマートフォンを片手に表紙を確認しているのは、タイトルを検索しているのだろう。
(変な奴)
何らかのプライドにかかわるらしく、けっして正面からは尋ねてこない。別にこっそりチェックしなくても、聞かれたら題名や著者名ぐらいは答えてやるのに。
理由なら見当はついている。
会話のとき、俺だけが知っていて自分が知らないことがあるのが、許せないらしいのである。
蛙ごときが知っていることは、ぼくだって当然知っているべきだ。そう思っているのが透けて見えている。
そして次の瞬間、
「え、あれをそう読んだの? 本気? だってこの著者……」
このように解釈バトルを吹っ掛けてくる。厄介だ。これが始まると、残念ながら俺に勝ち目はない。
さて俺も蛙ではあるが、まるきり馬鹿というわけではない。このパターンに気づいたので、俺も対抗策をとることにした。
本はなるべく電子書籍で読むようにしたのである。これでもう、俺が読んでいる本の表紙は物理的に覗けない。
それでもって知識をひけらかすと、鳥見は実に面白い表情をする。
「あ、初耳だった? 鳥見なら知ってるかと思った」
鳥見の眉間に深々としわが寄っていくのを、俺は嬉々として眺める。
(気持ちいいー)
いつもは負ける一方なんだ。俺だって少しぐらい勝利の快感を味わいたい。性格が悪いとは思いつつ、こたえられない。
楽しかった。躍起になって本を読んだ。本さえ読めば、あいつの知らないことが増える。蛙でもあいつに勝てる。
俺はふたたび勉強が苦にならなくなっていた。知識さえ潤沢なら、あの憎きディベートも多少は形になることにも気づいた。要は物量作戦である。
そしてついに、いくつかの科目で期末の成績が鳥見に肉薄するまでになった。もちろんうれしかったが、同時にあと一歩足りなかったのが猛烈に悔しかった。ちなみに社会学は相変わらずだ。
そう、俺はやりすぎた。
「ええ、またうちに人を呼ぶのか」
俺は顔を思い切りしかめた。
「ああ。今週末」
鳥見はときどき、社会人の知り合いを家に招く。いったいどこで知り合ってくるんだか。そのたびに邪険にされる俺の身にもなってほしい。
仕方がない、チェーンのコーヒー屋にでも避難するか。進捗状況が23パーセントの電子書籍をさっさと消化してしまおう。見てろ、また賢くなって戻ってくるぞ、俺は。
俺の目論見をよそに、鳥見は冷ややかに微笑んだ。
「コネクションづくりは大事だよ。時間のある今のうちにつながりを作っておかないと」
「そんなもんかねぇ?」
俺はつい純粋に首をかしげてしまった。有望とはいえただの大学生を、数年先の遠い未来まで覚えていてくれる人っているんだろうか。
「その時間、勉強したらいいんじゃね? だから最近、俺に負けそうなんじゃ」
鳥見の顔から笑みが急速に消えていく。
さすがに口が滑ったな、と俺はちらりと後悔した。鳥見の努力を全否定するつもりはなかったのだ。
ばん。硬い音が空気を震わせた。
鳥見が机に手のひらを伏せ、俺をにらんでいる。
「プレッシャーのない君に何がわかるんだ」
地雷を踏んだのだと俺は直感した。
「ぼくだってそんな風に気楽にしてたかった」
奇妙に抑えた、這うような声だ。
「無駄なこと。楽しいこと。ぼくは全部あきらめて、ようやくこの位置にいるんだ。それを君が、君なんかが」
さすがの俺もすくんでしまった。
「……ごめん。お前もいろいろあったんだ」
俺が示した理解はかえって逆効果だった。
「憐れむなよ!」
きれいな瞳がぎらぎらと光っている。俺は蛇ににらまれた蛙のように動けなくなる。
少し間があって、鳥見は暗く笑った。
「謝るなら、君が楽しいことをぼくに教えてよ」
「えっ」
俺は面食らった。鳥見はテーブル越しに、俺の胸倉をつかんだ。
鳥見の目が脅すようにすっと細くなる。
「たぶんぼく、男の方がいいんだ。前の同居人はそのせいで逃げていった」
鳥見がルームシェアを持ちかけてきたとき、ホテル街のそばだったことを、俺は急に思い出した。
(あのときこいつが振られたのは女の子じゃなくて……)
同居人の男だった、ということなのか。
鳥見の笑い声が自虐的に響く。
「はは、気持ち悪いだろ。君もそうしなよ」
俺はごくっと唾を飲んだ。何それ。
「でないと食べちゃうよ」
こいつ、おかしい。ストイックに生きすぎて、行きつくところまで行ってしまった感じ。
「ねえ。青田。聞いてる?」
子どもみたいな喋り方だ。
生温かい呼気が近づいてくる。俺を覗き込む瞳は、少し泣きそうに見えた。
(これが、こいつの、本性……?)
この男は、必死になってこれを隠していたわけか。
(……あれ?)
こんな絶体絶命の状態だというのに、俺はふいにおかしくなった。
(こいつ、こっちの方が断然いいじゃん)
いつもの仮面じみた完璧さより、このぐちゃぐちゃな自我の方がよっぽど人間らしい。
「ふふっ」
思わず笑いがこみ上げて、抑えられなかった。
「何がおかしいんだ」
至近距離で、鳥見はひどく傷ついた顔をしている。
「お前、俺なんかのこと好きだったんだ。へえ」
鳥見はぽかんと口を開けた。
「な、なんでそうなる」
「まあ今のお前なら? 友だちから始めるんなら、考えてやらんでもないかな」
鳥見は口をぱくぱくさせた。
「なんで君がそんなに偉そうなんだ!? ふだんは卑屈なくせにその自己肯定感はどこから来たんだ」
「自分でもわからん」
だが妙に気分がいい。この感情はなんだろう。しいて言えば、ざまみろ、だろうか。
あんなに見下していたくせに、俺なんかが好きだなんて。
「別に君が好きでルームシェアを持ちかけたわけじゃない! 君ならぼくの邪魔にならないと思っただけで」
「いっしょにいると優越感に浸れると思った? 俺がはるか下の方で足掻いてるのが面白かった?」
鳥見は口をつぐんだ。顔に罪悪感が浮かんでいる。
「いいんだよ。俺はうそつきより正直者の方が好きだ。覚えておけ」
とんと胸を押し、鳥見を軽く突き離す。
鳥見は苦々しい顔をして、セットした頭をぐしゃぐしゃにかき乱している。
俺は奴を一瞥して、部屋を出た。
からかって面白いだけの奴だった鳥見は俺の中で、はっきりと興味深い存在に格上げされた。
こんなことがあったくせに、鳥見との関係はたいして変わらなかった。
鳥見はまるでこの事件が存在しなかったかのように振舞った。俺が好きだとどうしても認めたくないのかもしれない。
(素直じゃねえ奴)
あるいは、自分があんな風に取り乱したこと自体が許せないのか。
俺も積極的に奴とどうにかなりたいわけでもなかった。あの件については忘れたふりをしてやりながら、俺はこっそりと奴の観察を続けることにした。
互いにぐちゃぐちゃな中身を隠し持ったまま、表面上は何もかも元通りになった。
週末、鳥見は意識の高いままに知人を家に招いた。俺はその間カフェで時間をつぶした。鳥見が帰ってくると、新たに仕入れた知識で鳥見をからかった。
「……君って奴は」
冷静を装っているのだろうが、口元はひくひくしているし、顔は苛立ちで赤くなっている。楽しい。
「ああ、そうそう。忘れてた」
寝る前のコーラをラッパ飲みしながら、俺は鳥見を振り返った。
「明日からの冬休み、俺、実家に帰るから。そのつもりで。あれ、そういえば、荷物詰めなきゃ」
鳥見は何か言いたげにしたが、やがて吐き捨てた。
「勝手にしなよ」
6
お気に入りに追加
21
あなたにおすすめの小説

執着男に勤務先を特定された上に、なんなら後輩として入社して来られちゃった
パイ生地製作委員会
BL
【登場人物】
陰原 月夜(カゲハラ ツキヤ):受け
社会人として気丈に頑張っているが、恋愛面に関しては後ろ暗い過去を持つ。晴陽とは過去に高校で出会い、恋に落ちて付き合っていた。しかし、晴陽からの度重なる縛り付けが苦しくなり、大学入学を機に逃げ、遠距離を理由に自然消滅で晴陽と別れた。
太陽 晴陽(タイヨウ ハルヒ):攻め
明るく元気な性格で、周囲からの人気が高い。しかしその実、月夜との関係を大切にするあまり、執着してしまう面もある。大学卒業後、月夜と同じ会社に入社した。
【あらすじ】
晴陽と月夜は、高校時代に出会い、互いに深い愛情を育んだ。しかし、海が大学進学のため遠くに引っ越すことになり、二人の間には別れが訪れた。遠距離恋愛は困難を伴い、やがて二人は別れることを決断した。
それから数年後、月夜は大学を卒業し、有名企業に就職した。ある日、偶然の再会があった。晴陽が新入社員として月夜の勤務先を訪れ、再び二人の心は交わる。時間が経ち、お互いが成長し変わったことを認識しながらも、彼らの愛は再燃する。しかし、遠距離恋愛の過去の痛みが未だに彼らの心に影を落としていた。
更新報告用のX(Twitter)をフォローすると作品更新に早く気づけて便利です
X(旧Twitter): https://twitter.com/piedough_bl
制作秘話ブログ: https://piedough.fanbox.cc/
メッセージもらえると泣いて喜びます:https://marshmallow-qa.com/8wk9xo87onpix02?t=dlOeZc&utm_medium=url_text&utm_source=promotion

息子よ……。父を性的な目で見るのはやめなさい
チョロケロ
BL
《息子×父》拾った子供が成長したらおかしくなってしまった。どうしたらいいものか……。
ムーンライトノベルズ様でも投稿しています。
宜しくお願いします。


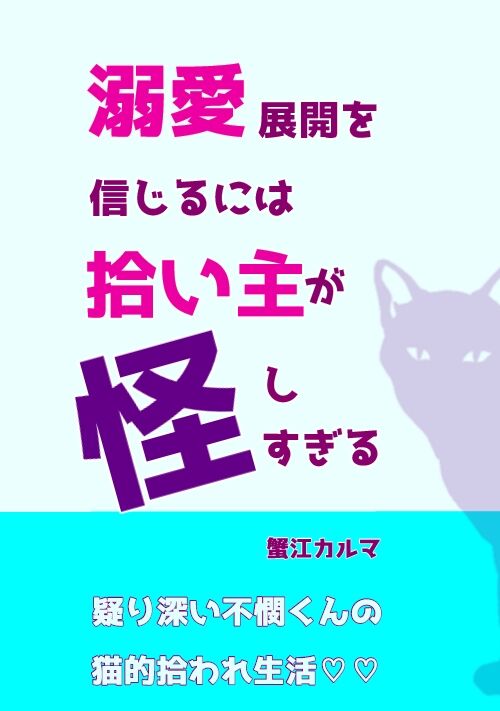
溺愛展開を信じるには拾い主が怪しすぎる
蟹江カルマ
BL
ちょっと胡散臭い美形猫飼いお兄さんが、優しさ耐性ゼロのやさぐれ元工員を拾いました。
あるもの
・怪しいけどほんとは優しい金持ち美形攻め
・疑り深いけど次第に懐く不憫受け
・すれ違いからのハピエン
・えろ
・猫ハーレム
性描写は※つき。

同室者の怖い彼と、僕は恋人同士になりました
すいかちゃん
BL
高校に入学した有村浩也は、強面の猪熊健吾と寮の同室になる。見た目の怖さにビクビクしていた浩也だが、健吾の意外な一面を知る。
だが、いきなり健吾にキスをされ・・・?


隠れヤンデレは自制しながら、鈍感幼なじみを溺愛する
知世
BL
大輝は悩んでいた。
完璧な幼なじみ―聖にとって、自分の存在は負担なんじゃないか。
自分に優しい…むしろ甘い聖は、俺のせいで、色んなことを我慢しているのでは?
自分は聖の邪魔なのでは?
ネガティブな思考に陥った大輝は、ある日、決断する。
幼なじみ離れをしよう、と。
一方で、聖もまた、悩んでいた。
彼は狂おしいまでの愛情を抑え込み、大輝の隣にいる。
自制しがたい恋情を、暴走してしまいそうな心身を、理性でひたすら耐えていた。
心から愛する人を、大切にしたい、慈しみたい、その一心で。
大輝が望むなら、ずっと親友でいるよ。頼りになって、甘えられる、そんな幼なじみのままでいい。
だから、せめて、隣にいたい。一生。死ぬまで共にいよう、大輝。
それが叶わないなら、俺は…。俺は、大輝の望む、幼なじみで親友の聖、ではいられなくなるかもしれない。
小説未満、小ネタ以上、な短編です(スランプの時、思い付いたので書きました)
受けと攻め、交互に視点が変わります。
受けは現在、攻めは過去から現在の話です。
拙い文章ですが、少しでも楽しんで頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















