お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


Dark Night Princess
べるんご
ホラー
古より、闇の隣人は常に在る
かつての神話、現代の都市伝説、彼らは時に人々へ牙をむき、時には人々によって滅ぶ
突如現れた怪異、鬼によって瀕死の重傷を負わされた少女は、ふらりと現れた美しい吸血鬼によって救われた末に、治癒不能な傷の苦しみから解放され、同じ吸血鬼として蘇生する
ヒトであったころの繋がりを全て失い、怪異の世界で生きることとなった少女は、その未知の世界に何を見るのか
現代を舞台に繰り広げられる、吸血鬼や人狼を始めとする、古今東西様々な怪異と人間の恐ろしく、血生臭くも美しい物語
ホラー大賞エントリー作品です

ナオキと十の心霊部屋
木岡(もくおか)
ホラー
日本のどこかに十の幽霊が住む洋館があった……。
山中にあるその洋館には誰も立ち入ることはなく存在を知る者すらもほとんどいなかったが、大企業の代表で億万長者の男が洋館の存在を知った。
男は洋館を買い取り、娯楽目的で洋館内にいる幽霊の調査に対し100億円の謝礼を払うと宣言して挑戦者を募る……。
仕事をやめて生きる上での目標もない平凡な青年のナオキが100億円の魅力に踊らされて挑戦者に応募して……。

【完結】大量焼死体遺棄事件まとめサイト/裏サイド
まみ夜
ホラー
ここは、2008年2月09日朝に報道された、全国十ケ所総数六十体以上の「大量焼死体遺棄事件」のまとめサイトです。
事件の上澄みでしかない、ニュース報道とネット情報が序章であり終章。
一年以上も前に、偶然「写本」のネット検索から、オカルトな事件に巻き込まれた女性のブログ。
その家族が、彼女を探すことで、日常を踏み越える恐怖を、誰かに相談したかったブログまでが第一章。
そして、事件の、悪意の裏側が第二章です。
ホラーもミステリーと同じで、ラストがないと評価しづらいため、短編集でない長編はweb掲載には向かないジャンルです。
そのため、第一章にて、表向きのラストを用意しました。
第二章では、その裏側が明らかになり、予想を裏切れれば、とも思いますので、お付き合いください。
表紙イラストは、lllust ACより、乾大和様の「お嬢さん」を使用させていただいております。


理科準備室のお狐様
石澄 藍
ホラー
高校1年生の駒井竜次はある日、友だちと夜の学校で肝試しをする計画を立てていた。しかし、それを同級生の孤塚灼に止められる。
「夜の学校には近寄らないほうがいい。この学校、本当に出るから」
嫌な予感がしつつも、竜次はその忠告を無視して肝試しを決行してしまう。そこで出会ったのは、不気味な同級生と可愛らしい真っ白な少女のふたり組。
この出会いは、果たして何をもたらすのかーー。
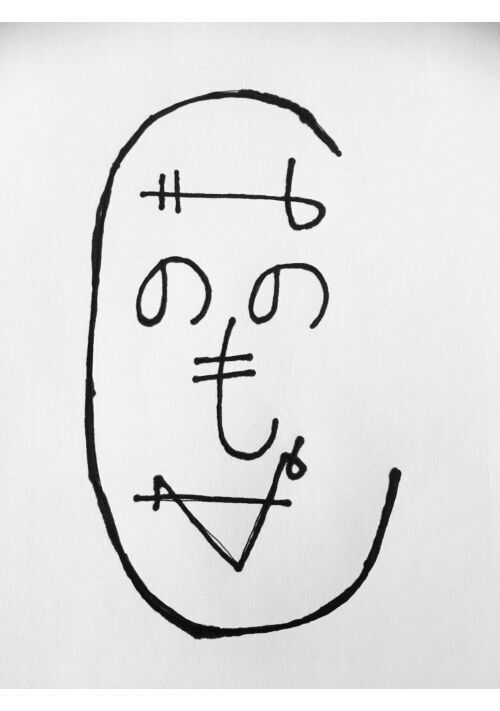
ものまね
TATSUYA HIROSHIMA
ホラー
お笑い界の底辺に位置する芸人の奥村は、ある日、‘‘モノマネ’’に活路を見出す。
大御所芸人のモノマネでブレイクを果たした奥村だったが、みるみるうちに自分自身を見失っていく。
彼の行きつく末路とは?

矛盾のAI話
月歌(ツキウタ)
ホラー
500文字以内のAIが作った矛盾話です。AIが作ったので、矛盾の意図は分かりませんw
☆月歌ってどんな人?こんな人↓↓☆
『嫌われ悪役令息は王子のベッドで前世を思い出す』が、アルファポリスの第9回BL小説大賞にて奨励賞を受賞(#^.^#)
その後、幸運な事に書籍化の話が進み、2023年3月13日に無事に刊行される運びとなりました。49歳で商業BL作家としてデビューさせていただく機会を得ました。
☆表紙絵、挿絵は全てAIイラスです
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















