44 / 91
負けたくない (カウンタークルー 古木理緒)
しおりを挟む
自分は他人が思っているよりも根に持つタイプだと古木理緒は思った。
今日も宮本遥マネージャーに注意を受ける。やり直しをさせられたことも何度もあった。たいてい目を見て素直に「わかりました」とか「すみません」とか言って流すことにしている。いちいち反抗的な態度をとるのも飽きてしまったからだ。ほかのクルーたちがやっているように、適当に言うことを聞いておけば、台風が過ぎ去るのも時間の問題だった。
しかしひとりになると、一日の出来事がまざまざと蘇ってくる。とくに叱られた光景はいちいち理緒の胸を刺し、嘔気を催すほどの痛みをもたらした。こういう時は思い切り泣いた方が早く気持ちが楽になる。あるいはゲーセンのもぐらたたき。
ふだんは殆ど感情を表に出さない。付き合いの浅い人にはポーカーフェイスと言われる。しかし、長い付き合いの家族だとか、五年も一緒にいる級友などには、感情の起伏が激しいタイプだと思われている。溜めても一気に爆発させてすっとする、だからあとに残らないさっぱりとした性格、そう誤解されている。しかしそれは間違いだ。
悔しいと思った経験だけはどうしても忘れられなかった。いつまでもいつまでも心の奥底どこかに残っていて、ときどき思い出したように湧き上がってくる。やはり根に持つタイプだと理緒は思った。
高校では生徒会活動をしている。広報担当だ。中学部の時には剣道部に籍を置いたこともあったが、二年ほどで辞めてしまった。中途半端に筋が良かったものだから期待され、扱かれて耐えられなくなったからだ。人は自分を負けず嫌いと言うが、所詮そんなものだと自己卑下に陥り、人と接触するのも面倒になってしまった。
生徒会活動の時は、広報という仮面を被って、それらしく振舞っている。女優になれるかしらと思ったこともある。
棲む世界を変えたくて、アルバイトをしようと思いつき、クイーンズサンドのアルバイト募集の広告を目にした。それがここへ来るきっかけだった。
面接を担当した二人の男が、あとで江尻マネージャーと松原チーフだとわかったが、自分の全身を上から下まで舐めまわすように見て、開き直ったように背筋を伸ばして坐っている様子を度胸があると勘違いしたのか、その場で採用を言い渡してくれた。
今のクルーの中には、あとから採用を通達されたものもいるらしい。それを聞くと少し優越感に浸ることが出来る。あるいはただ通っている高校の名前に価値を見い出されたのかもしれない。
立志大付属高校には中学部から通っていた。六年制の学校になる。そのまま立志大へ進学する道もあるが、多くの生徒はさらに上とされる帝都大や東都大、私立では明鏡大や叡智大を受験するという。理緒も今は、よそへ出て行きたいと思うようになった。本来ならアルバイトどころではないはずだ。
立志大付属は第一志望ではなかった。第一志望は栴檀女学院。母親の母校だ。女子校としては都内でトップクラスの進学校である。しかし不幸なことに理緒は母親から明晰な頭脳を受け継ぐことが出来なかった。塾に通うのが遅れたせいもあるが、どんなに頑張っても栴檀の合格ラインには届かず、強引に受験したらやはり不合格になった。同じ塾の友人たちが何人か栴檀に合格するのを見て羨ましくて涙が出た。その中の一人が高見澤神那である。
このQS明葉ビル店において、五年ぶりくらいで再会した高見澤神那は、驚くほど美しい少女に成長していた。清楚で可憐な花。そういう表現は虫唾が走るが、彼女に対して形容するにはふさわしいことばだった。所作まですっかりお嬢様になっている。
「まあ、理緒さん、お久し振りですね」
しとやかにお辞儀をする様子を見て、理緒はただ呆然とした。自分も栴檀に入っていたら、こういう風になれたのだろうか。
立志大付属で過ごした理緒は、否応なくその校風に染まっていった。もともと体育会系の大学で、進学校に転換を図ってからも、その精神は変わらなかった。極端なまでの競争主義。試験の順位と点数はこれ見よがしに張り出される。一位、二位、三位には金、銀、銅のメダルに見立てた賞状が送られた。まだ何にも染まっていなかった理緒は、常に全力を注ぐこと、スピードをアップさせること、とにかく他人に勝つことを教えられた。今考えれば当時の担任団の戦略にまんまとのせられただけである。賢い生徒は、周囲に惑わされることなくマイペースを維持していた。
しかし長年培った性分はすぐには変えられそうになかった。同じ年頃の女の子を見ると競争したくなる。特にスピードでは負けたくなかった。
QS明葉ビル店には、高校二年生の女子が理緒以外に二人いた。高見澤神那ともうひとり、瀧本あづさである。
アメリカ人の祖母を持つクォーターのあづさは、髪を金髪にしていて、仕事中は薄く化粧を施すなど、そのフランクな態度といい、自由人に見えた。理緒にとっては、こういう風になってみたいという憧れる存在である。別にあづさ個人に憧れているわけではない。彼女の生き方だ。
あづさの通う公立高校は、その学区では比較的上位にあったので、校風は自由だったようだ。髪型や格好にそれほどチェックが入らないらしい。彼女はその校風を十分に利用して楽しんでいるように見えた。バンドをしている彼氏がいるという噂も、彼女には箔だった。
自分には彼氏がいて欲しいとは思わないが、あづさにはそういうものがアクセサリーとして必要に感じられた。
いずれにせよ、高見澤神那、瀧本あづさとも、全く異なるタイプだが、理緒にとって負けたくない相手だった。いざアルバイトが始まると、まもなくこの二人目当ての客がやってくることに気づいた。それも腹立たしい。理緒は余計な雑談に惑わされないよう、とにかくレジに集中した。
スピードは誰にも負けなかった。しかしその代償として、小さなミスが積み重なり、理緒はつねに常勤スタッフの叱責を受けた。
ああ、またか、という気がする。またやってしまった。いつまでも進歩のない自分。情けなくて、ひとりになると涙が出る。
そのままただ時間だけが過ぎていったとしたら、自分はどうにもならないところまで流されていっただろう。しかし救う神もあった。
蒲田美香は、笑うと八重歯とえくぼが特徴的な、人懐こい女の子だった。童顔のため当初理緒は自分と同じかあるいは年下だと思って、それなりの対応をしてきたが、あとで大学三年生と知らされ、たちまち態度を改めた。またやってしまったと頭をかく。
「いいのよ、いつものことだから」と美香は全く気にしていない。それよりも美香は、ひとりでいる理緒を気にしているようだった。
二階の書店で雑誌を見ていると、いつの間にか横に並んでいたり、地下のゲーセンでもぐらを叩いていると、傍らで声援を送っていた。彼女は無意識に自分が発するSOSのサインを感知していたのかもしれないと理緒は思った。
「ねえ、もうちょっと力を抜こうよ」
それがいつもの美香の台詞だった。
美香の弟は立志大付属中学にいるという。その弟から美香を通じて自分に関する噂を知らされた。サッカー部の主将に肘鉄を食らわした女。納得できないことがあると教師にまで食ってかかる女。噂とは恐ろしいものだ。
サッカー部のキャプテンに声をかけられたのは事実だ。こんながさつな人間に声をかける男など信用できない。「俺と遊びに行かない?」とかいう言い方も気に入らなかった。
「結構です」といってもしつこく付きまとうので振り払ったら肘があたり、キャプテンは吹っ飛ばされたような形になった。一瞬まずいと思って助け起こそうとしたら、すでに取り巻きに肩をかしてもらっていたので、何も言わず逃げるようにその場を去った。それが尾鰭つきディナーとなってみんなの食卓にのぼったのだろう。
その話をすると美香はけらけらと笑った。
「いかにも理緒ちゃんらしいわ」と言うのである。
まあそうかもしれないと理緒は思った。
「でも男の人にナンパされるのは、それだけあなたに魅力があるからよ」
「え、あれってナンパなんですか? もっと真摯な誘い方があるでしょう」
「理緒ちゃんは真面目なタイプが好みなのね」
好みの話などしていないと言ったが、美香は聞いてくれなかった。人が真っ赤になっているのを見るのも楽しいらしい。子供みたいに素直な笑い方をした。
バイトをしてみて、クイーンズサンドでの人間関係は理緒に新鮮な驚きを与えた。学校では同い年の男女が一つどころに押し込められ、競争を強いている。だが、ここでは少しずつ微妙に年の異なる若者が、一つの目標に向かって働いていた。クラブ活動をやめてしまった理緒に仲間意識というものを教えてくれた。
驚いたことに、年下の、ミスして叱られてばかりいた泊留美佳が、驚くほど成長し、理緒を気遣って、友達になってと言い出したのだ。これにはさすがの理緒も言葉を失った。
「お友達になってもらえません?」
そんな言葉は久しく聞いたことがなかった。まるで幼稚園児が発するような言葉。
しかし何だか胸が焼け付くような感覚に襲われる。これはひょっとして自分は嬉しがっているのか。その感情の正体を知って理緒は愕然とした。
理緒はこれまで、競争することをあまりに即物的にストレートに受け取ってしまったために、友達をつくるという発想が全くなくなっていた。まわりはすべて競争相手だ。自分が栴檀女学院に入れなかったのは、友達などという甘さがあったからだと思っていた。
しかしここでは競争は全く意味がなかった。相手は同僚のスタッフではなく、お客様だったのだから。
理緒は、だから、留美佳の勧めに素直に応じることにしている。今度スタッフの希望者で海へレクリエーションに行くという。蒲田美香も参加すると聞いていた。泊留美佳に誘われ、理緒はレクに参加することを決めた。
海へ行くなんて何年ぶりだろう。水着は学校用のものしか持っていないが、新たに購入しなければならないか。あれこれ考えると、どうしようと思うことが多すぎる。しかしこれは新鮮な感覚だと理緒は思った。
今日も宮本遥マネージャーに注意を受ける。やり直しをさせられたことも何度もあった。たいてい目を見て素直に「わかりました」とか「すみません」とか言って流すことにしている。いちいち反抗的な態度をとるのも飽きてしまったからだ。ほかのクルーたちがやっているように、適当に言うことを聞いておけば、台風が過ぎ去るのも時間の問題だった。
しかしひとりになると、一日の出来事がまざまざと蘇ってくる。とくに叱られた光景はいちいち理緒の胸を刺し、嘔気を催すほどの痛みをもたらした。こういう時は思い切り泣いた方が早く気持ちが楽になる。あるいはゲーセンのもぐらたたき。
ふだんは殆ど感情を表に出さない。付き合いの浅い人にはポーカーフェイスと言われる。しかし、長い付き合いの家族だとか、五年も一緒にいる級友などには、感情の起伏が激しいタイプだと思われている。溜めても一気に爆発させてすっとする、だからあとに残らないさっぱりとした性格、そう誤解されている。しかしそれは間違いだ。
悔しいと思った経験だけはどうしても忘れられなかった。いつまでもいつまでも心の奥底どこかに残っていて、ときどき思い出したように湧き上がってくる。やはり根に持つタイプだと理緒は思った。
高校では生徒会活動をしている。広報担当だ。中学部の時には剣道部に籍を置いたこともあったが、二年ほどで辞めてしまった。中途半端に筋が良かったものだから期待され、扱かれて耐えられなくなったからだ。人は自分を負けず嫌いと言うが、所詮そんなものだと自己卑下に陥り、人と接触するのも面倒になってしまった。
生徒会活動の時は、広報という仮面を被って、それらしく振舞っている。女優になれるかしらと思ったこともある。
棲む世界を変えたくて、アルバイトをしようと思いつき、クイーンズサンドのアルバイト募集の広告を目にした。それがここへ来るきっかけだった。
面接を担当した二人の男が、あとで江尻マネージャーと松原チーフだとわかったが、自分の全身を上から下まで舐めまわすように見て、開き直ったように背筋を伸ばして坐っている様子を度胸があると勘違いしたのか、その場で採用を言い渡してくれた。
今のクルーの中には、あとから採用を通達されたものもいるらしい。それを聞くと少し優越感に浸ることが出来る。あるいはただ通っている高校の名前に価値を見い出されたのかもしれない。
立志大付属高校には中学部から通っていた。六年制の学校になる。そのまま立志大へ進学する道もあるが、多くの生徒はさらに上とされる帝都大や東都大、私立では明鏡大や叡智大を受験するという。理緒も今は、よそへ出て行きたいと思うようになった。本来ならアルバイトどころではないはずだ。
立志大付属は第一志望ではなかった。第一志望は栴檀女学院。母親の母校だ。女子校としては都内でトップクラスの進学校である。しかし不幸なことに理緒は母親から明晰な頭脳を受け継ぐことが出来なかった。塾に通うのが遅れたせいもあるが、どんなに頑張っても栴檀の合格ラインには届かず、強引に受験したらやはり不合格になった。同じ塾の友人たちが何人か栴檀に合格するのを見て羨ましくて涙が出た。その中の一人が高見澤神那である。
このQS明葉ビル店において、五年ぶりくらいで再会した高見澤神那は、驚くほど美しい少女に成長していた。清楚で可憐な花。そういう表現は虫唾が走るが、彼女に対して形容するにはふさわしいことばだった。所作まですっかりお嬢様になっている。
「まあ、理緒さん、お久し振りですね」
しとやかにお辞儀をする様子を見て、理緒はただ呆然とした。自分も栴檀に入っていたら、こういう風になれたのだろうか。
立志大付属で過ごした理緒は、否応なくその校風に染まっていった。もともと体育会系の大学で、進学校に転換を図ってからも、その精神は変わらなかった。極端なまでの競争主義。試験の順位と点数はこれ見よがしに張り出される。一位、二位、三位には金、銀、銅のメダルに見立てた賞状が送られた。まだ何にも染まっていなかった理緒は、常に全力を注ぐこと、スピードをアップさせること、とにかく他人に勝つことを教えられた。今考えれば当時の担任団の戦略にまんまとのせられただけである。賢い生徒は、周囲に惑わされることなくマイペースを維持していた。
しかし長年培った性分はすぐには変えられそうになかった。同じ年頃の女の子を見ると競争したくなる。特にスピードでは負けたくなかった。
QS明葉ビル店には、高校二年生の女子が理緒以外に二人いた。高見澤神那ともうひとり、瀧本あづさである。
アメリカ人の祖母を持つクォーターのあづさは、髪を金髪にしていて、仕事中は薄く化粧を施すなど、そのフランクな態度といい、自由人に見えた。理緒にとっては、こういう風になってみたいという憧れる存在である。別にあづさ個人に憧れているわけではない。彼女の生き方だ。
あづさの通う公立高校は、その学区では比較的上位にあったので、校風は自由だったようだ。髪型や格好にそれほどチェックが入らないらしい。彼女はその校風を十分に利用して楽しんでいるように見えた。バンドをしている彼氏がいるという噂も、彼女には箔だった。
自分には彼氏がいて欲しいとは思わないが、あづさにはそういうものがアクセサリーとして必要に感じられた。
いずれにせよ、高見澤神那、瀧本あづさとも、全く異なるタイプだが、理緒にとって負けたくない相手だった。いざアルバイトが始まると、まもなくこの二人目当ての客がやってくることに気づいた。それも腹立たしい。理緒は余計な雑談に惑わされないよう、とにかくレジに集中した。
スピードは誰にも負けなかった。しかしその代償として、小さなミスが積み重なり、理緒はつねに常勤スタッフの叱責を受けた。
ああ、またか、という気がする。またやってしまった。いつまでも進歩のない自分。情けなくて、ひとりになると涙が出る。
そのままただ時間だけが過ぎていったとしたら、自分はどうにもならないところまで流されていっただろう。しかし救う神もあった。
蒲田美香は、笑うと八重歯とえくぼが特徴的な、人懐こい女の子だった。童顔のため当初理緒は自分と同じかあるいは年下だと思って、それなりの対応をしてきたが、あとで大学三年生と知らされ、たちまち態度を改めた。またやってしまったと頭をかく。
「いいのよ、いつものことだから」と美香は全く気にしていない。それよりも美香は、ひとりでいる理緒を気にしているようだった。
二階の書店で雑誌を見ていると、いつの間にか横に並んでいたり、地下のゲーセンでもぐらを叩いていると、傍らで声援を送っていた。彼女は無意識に自分が発するSOSのサインを感知していたのかもしれないと理緒は思った。
「ねえ、もうちょっと力を抜こうよ」
それがいつもの美香の台詞だった。
美香の弟は立志大付属中学にいるという。その弟から美香を通じて自分に関する噂を知らされた。サッカー部の主将に肘鉄を食らわした女。納得できないことがあると教師にまで食ってかかる女。噂とは恐ろしいものだ。
サッカー部のキャプテンに声をかけられたのは事実だ。こんながさつな人間に声をかける男など信用できない。「俺と遊びに行かない?」とかいう言い方も気に入らなかった。
「結構です」といってもしつこく付きまとうので振り払ったら肘があたり、キャプテンは吹っ飛ばされたような形になった。一瞬まずいと思って助け起こそうとしたら、すでに取り巻きに肩をかしてもらっていたので、何も言わず逃げるようにその場を去った。それが尾鰭つきディナーとなってみんなの食卓にのぼったのだろう。
その話をすると美香はけらけらと笑った。
「いかにも理緒ちゃんらしいわ」と言うのである。
まあそうかもしれないと理緒は思った。
「でも男の人にナンパされるのは、それだけあなたに魅力があるからよ」
「え、あれってナンパなんですか? もっと真摯な誘い方があるでしょう」
「理緒ちゃんは真面目なタイプが好みなのね」
好みの話などしていないと言ったが、美香は聞いてくれなかった。人が真っ赤になっているのを見るのも楽しいらしい。子供みたいに素直な笑い方をした。
バイトをしてみて、クイーンズサンドでの人間関係は理緒に新鮮な驚きを与えた。学校では同い年の男女が一つどころに押し込められ、競争を強いている。だが、ここでは少しずつ微妙に年の異なる若者が、一つの目標に向かって働いていた。クラブ活動をやめてしまった理緒に仲間意識というものを教えてくれた。
驚いたことに、年下の、ミスして叱られてばかりいた泊留美佳が、驚くほど成長し、理緒を気遣って、友達になってと言い出したのだ。これにはさすがの理緒も言葉を失った。
「お友達になってもらえません?」
そんな言葉は久しく聞いたことがなかった。まるで幼稚園児が発するような言葉。
しかし何だか胸が焼け付くような感覚に襲われる。これはひょっとして自分は嬉しがっているのか。その感情の正体を知って理緒は愕然とした。
理緒はこれまで、競争することをあまりに即物的にストレートに受け取ってしまったために、友達をつくるという発想が全くなくなっていた。まわりはすべて競争相手だ。自分が栴檀女学院に入れなかったのは、友達などという甘さがあったからだと思っていた。
しかしここでは競争は全く意味がなかった。相手は同僚のスタッフではなく、お客様だったのだから。
理緒は、だから、留美佳の勧めに素直に応じることにしている。今度スタッフの希望者で海へレクリエーションに行くという。蒲田美香も参加すると聞いていた。泊留美佳に誘われ、理緒はレクに参加することを決めた。
海へ行くなんて何年ぶりだろう。水着は学校用のものしか持っていないが、新たに購入しなければならないか。あれこれ考えると、どうしようと思うことが多すぎる。しかしこれは新鮮な感覚だと理緒は思った。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

ツイン・ボーカル
hakusuya
現代文学
芸能事務所の雇われ社長を務める八波龍介は、かつての仲間から伝説のボーカル、レイの再来というべき逸材を見つけたと報告を受ける。しかしその逸材との顔合わせが実現することなく、その仲間は急逝した。ほんとうに伝説の声の持ち主はいたのか。仲間が残したノートパソコンの中にそれらしき音源を見つけた八波は、その声を求めてオーディション番組を利用することを思い立つ。
これは奇蹟の声を追い求める者たちの物語。


サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
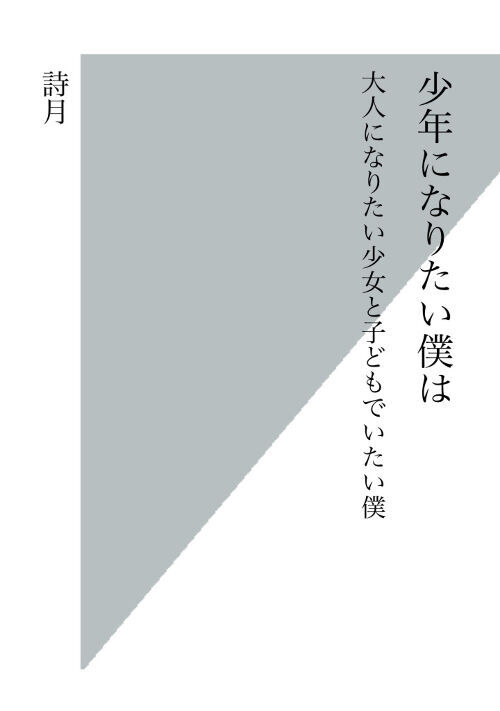
少年になりたい僕は-大人になりたい君と子どもでいたい僕の青春ストーリー-
詩月
現代文学
高校生1年生である的羽暁人は、少年の頃都会で出会った少女を絵に描きたいと思っていた。その少女の言葉は幼く、芯をついているとは到底言えない。だが彼女の言葉には無知だからこそ私たちに共感を得られるものがあったのかもしれない。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活
XD
恋愛
誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。

いいんだよ
歌華
現代文学
どこにでも居る高校生の琉生。思春期の悩みも沢山あるが、それなりに生活していた、しかしある日を境に精神的にどんどんボロボロになっていく。
そして自分を見失いかけ、沢山の良い思い出すら忘れかけてしまう。
精神疾患者に理解を傾けそのままでも生きていて良いと支え合う心暖まるストーリー
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















