お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

巡る季節に育つ葦 ー夏の高鳴りー
瀬戸口 大河
青春
季節に彩られたそれぞれの恋。同じ女性に恋した者たちの成長と純真の話。
五部作の第一弾
高校最後の夏、夏木海斗の青春が向かう先は…
季節を巡りながら変わりゆく主人公
桜庭春斗、夏木海斗、月島秋平、雪井冬華
四人が恋心を抱く由依
過ぎゆく季節の中で由依を中心に4人は自分の殻を破り大人へと変わってゆく
連載物に挑戦しようと考えています。更新頻度は最低でも一週間に一回です。四人の主人公が同一の女性に恋をして、成長していく話しようと考えています。主人公の四人はそれぞれ季節ごとに一人。今回は夏ということで夏木海斗です。章立ては二十四節気にしようと思っていますが、なかなか多く文章を書かないためpart で分けようと思っています。
暇つぶしに読んでいただけると幸いです。
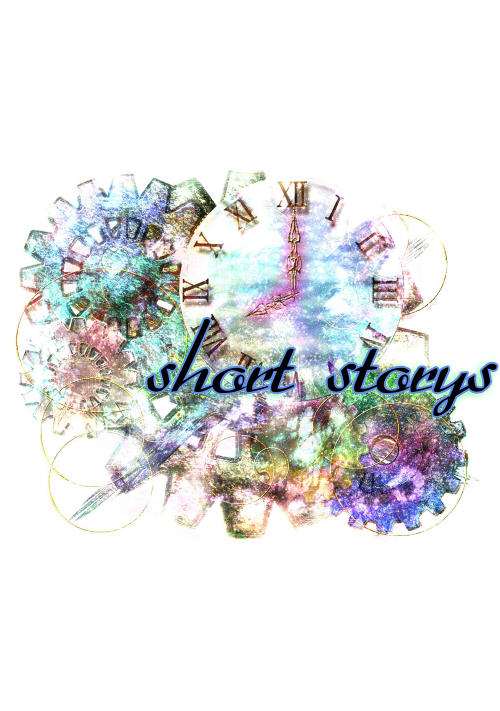
紺坂紫乃短編集-short storys-
紺坂紫乃
大衆娯楽
2014年から2018年のSS、短編作品を纏めました。
「東京狂乱JOKERS」や「BROTHERFOOD」など、完結済み長編の登場人物が初出した作品及び未公開作品も収録。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

Last Recrudescence
睡眠者
現代文学
1998年、核兵器への対処法が発明された以来、その故に起こった第三次世界大戦は既に5年も渡った。庶民から大富豪まで、素人か玄人であっても誰もが皆苦しめている中、各国が戦争進行に。平和を自分の手で掴めて届けようとする理想家である村山誠志郎は、辿り着くためのチャンスを得たり失ったりその後、ある事件の仮面をつけた「奇跡」に訪れられた。同時に災厄も生まれ、その以来化け物達と怪獣達が人類を強襲し始めた。それに対して、誠志郎を含めて、「英雄」達が生れて人々を守っている。犠牲が急増しているその惨劇の戦いは人間に「災慝(さいとく)」と呼ばれている。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

ARIA(アリア)
残念パパいのっち
ミステリー
山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















