2 / 4
深雪 ~みゆき~
①
しおりを挟む
その翁が訪ねて来たのは、旦那様が亡くなられて、間もなくの事だった。
「突然、訪ねてしまってすまないね。」
「いいえ。こちらは一人暮らしですから、返って誰かが来て下さると嬉しいんです。」
ずっと真木家にお仕えして、結婚もせず独り身でいた私は、近くに借家を借りて、住んでいた。
「それで……お話を伺いたいと言うのは……」
「ああ、実はご主人との話を、お聞かせ願いたい。」
「旦那様との?」
お茶を出す私の手が、止まった。
そっと、翁の目を見てみる。
このお方は、なぜそのような事を申されるのか。
「……ご主人の、真木伸太郎さんの、姉君のようなお方だったと、お聞きしています。」
「……姉君ですか。」
私は隣の部屋にある、テーブルと椅子を眺めた。
珍しい洋式のテーブルと椅子で、私と旦那様は、いつもここに座りながら、お酒を飲んでいた。
「そうですね……少しだけ思い出話に、付き合って頂けますか?」
私があの方と、初めてお会いしたのは、まだ私が16歳の頃でした。
先代から続く大きな病院の家で、数人の奉公人を雇っていた真木家に働くようになって、1年目のこと。
優しかった奥様が亡くなり、そのお葬式での事だったんです。
当時まだ 紳太郎さんは11歳。
母親が亡くなった悲しさに、じっと耐えながら、8歳の妹の面倒を見ている、そんなお方でした。
私が、お葬式に来た方達のお世話をするのに、パタパタと廊下を、小走りで歩いていると、庭の片隅で、腕で顔を覆いながら、泣いているあのお方を見かけました。
その前には、奥様が植えたという花畑があって、紳太郎さんは、亡くなったお母様を思い出して、泣いておられたのでしょう。
その時私は、まだ奉公人の中でも下の方で、お子様達に、声を掛けることもできない身分でしたが、私も15歳で親元を離れてきたので、母が恋しいと泣く気持ちも理解でき、一緒に涙を流していたのを、よく覚えています。
それから2年後の事。
私は奉公も三年目になり、旦那さまにも顔を知って頂くようになって、そのついでに、お子様達とも話すようになっていました。
割と年齢も近いこともあって、話が弾んでは、上の人に怒られる事も度々でした。
そんな18歳の夏、旦那さまに呼ばれ、部屋にお伺いした時のことでした。
「旦那様、深雪(ミユキ)です。」
扉の外で自分の名を名乗ると、「入りなさい。」と、旦那さまの声が聞こえました。
「失礼します。」
私が部屋に入ると、旦那さまのお側には、二人のお子様が、座ってらっしゃいました。
向かって右側、旦那様の横には長男の倫太郎様。
左側には、ご次男の紳太郎様がいらっしゃいました。
「深雪、今日呼んだのは他でもない。おまえに頼みごとがあるんだ。」
「はい。」
「おまえも知っての通り、妻が亡くなってもう2年になる。息子達も大きくなって、身の回りの世話をするものが必要だ。」
「はい。」
「そこでどうだろう。おまえに、息子の世話を頼みたいんだが……」
私は驚いて、返事もできずにいました。
「いいだろう。息子達はおまえに、よく懐いているようだし。」
「はい。」
懐いていると言っても、時々お話をさせて頂くだけ。
とんでもない事になったわ。
そう思いながら顔を上げて、ちらっとお子様たちを見ると、16歳になった倫太郎様と13歳になった紳太郎様が、顔を見合せて、笑っていらっしゃいました。
お二人とも、私がお世話係になったのが、とても嬉しいと言うような、表情をしてらしたんです。
「お前の申し出が通ってよかったな、紳太郎。」
「はい、兄さん。」
何のことか分からずに、目をパチクリさせていると、倫太郎さんが教えてくれました。
「世話係りに、深雪を推薦したのは、紳太郎なんだよ。」
「紳太郎さんが?」
そう言うと、紳太郎さんは無邪気な笑顔を、私に見せて下さったのです。
そうなると、私もお断りする事もできず、その次の日から、倫太郎さんと紳太郎さんの、身の回りの世話が始まったのです。
ですが二人はまだ、16歳と13歳。
幼さが少しだけ、残っていらっしゃって。
朝、起きてお二人の元へ行くと、倫太郎様はもう起きていて、ご自分が寝ていらしゃった布団をたたんでいたりするのですが、紳太郎様は決まって、布団の中。
学校に遅れますよと、起こして差し上げると、眠い目をこすって、ゆっくり起き上がるのが、私達の日課でしたね。
ところで真木家というのは、倫太郎様と紳太郎様の、お爺様の代から医者の家系なんです。
経営なさっている病院も、地元では有名で大きなところだったんです。
当然の如く、お二人とも医者になるように、言い聞かされておりました。
ですから、学校も周りの方々が通っている普通の学校ではなく、医者や政治家、実業家、そんな人を多く輩出している学校に、通っていらっしゃいました。
ああ、お勉強の方ですか?
ええ。
倫太郎様も紳太郎様も、勉強に関しては何の不満も言わずに、一生懸命、頑張っていらしゃいましたよ。
お二人とも、旦那様の後を継いで、立派な医者になるのだと、仰っていましたから。
ところでお二人には、妹さまが一人いらっしゃって、名前を風音(カザネ)様と言いました。
お二人とも、特に紳太郎様は、この風音様を可愛がっていらしたんです。
ただ風音様は、生まれつき身体が弱い方で、いつも床に臥せっているようなお子様でした。
こんな事言うのもあれなんですがね。
とにかく、お金は持っている家でしたから、風音様には専属の医者、何人かの家政婦もつき、24時間お世話している状態でした。
甘やかしている?
傍から見れば、そう見えるのでしょうけど、当の風音様は重い心臓の病気で、いつ心臓が止まってもおかしくない状態だったんです。
その中で紳太郎様は、時々本を読んであげたり、一緒に双六をしたり。
珍しいお菓子をもらってきたと言っては、風音様へ持って行ってあげる、そんなおお優しいお兄様でしたね。
ああ、お二人に妹様がいらっしゃったのを、初めて聞きましたか?
あまり知られていないことですからね。
特別な事情というほどでもないのですが、妹の風音様は看病の甲斐もなく、幼い頃にお亡くなりになってしまったんです。
それはある雪の日、いつものように、紳太郎様が帰ってらっしゃった時でした。
「ただいま帰ったよ、深雪。」
「お帰りなさいませ。」
「何か変わった事は?」
鞄を置きながら、そう私に聞くのが、紳太郎様の口癖でした。
「特に変わったことは……」
私がそう言おうとした時でした。
「失礼します!」
風音様についている家政婦の一人が、急いでやってきたんです。
「どうしたのです?」
私が尋ねると、その家政婦の体は、震えていました。
「紳太郎様、早く……早く、風音様の元へ……」
只事ではない表情に、私と紳太郎様は、急いで風音様の部屋へ、向かったのですが………
「紳太郎…」
既に倫太郎様はいらっしゃっていて、風音様の小さな手を握っておいででした。
「たった今…逝ってしまった……」
紳太郎様は、その場に崩れ落ちてしまって、這いながら風音様の枕元へ。
「風音……風音!!」
何度も風音様の身体を揺らして、終いには、その亡骸にすがっておいででした。
そして、その後。
部屋に戻った紳太郎様が一言。
「深雪。」
「はい。」
「俺は、医者になりたくない。」
あんなに立派な医者になると、仰っていた紳太郎様が、そんな言葉を口にされるなんて。
「紳太郎様?」
「風音は結局、死んでしまったじゃないか。」
生きとし生ける者、全て死ぬ時が来る。
風音様は、人よりもその時が早かっただけ。
そう分かっていても、紳太郎様にかけて差し上げる言葉も見つからず、私はただ俯いて、あの方のお側にいるだけでした。
「突然、訪ねてしまってすまないね。」
「いいえ。こちらは一人暮らしですから、返って誰かが来て下さると嬉しいんです。」
ずっと真木家にお仕えして、結婚もせず独り身でいた私は、近くに借家を借りて、住んでいた。
「それで……お話を伺いたいと言うのは……」
「ああ、実はご主人との話を、お聞かせ願いたい。」
「旦那様との?」
お茶を出す私の手が、止まった。
そっと、翁の目を見てみる。
このお方は、なぜそのような事を申されるのか。
「……ご主人の、真木伸太郎さんの、姉君のようなお方だったと、お聞きしています。」
「……姉君ですか。」
私は隣の部屋にある、テーブルと椅子を眺めた。
珍しい洋式のテーブルと椅子で、私と旦那様は、いつもここに座りながら、お酒を飲んでいた。
「そうですね……少しだけ思い出話に、付き合って頂けますか?」
私があの方と、初めてお会いしたのは、まだ私が16歳の頃でした。
先代から続く大きな病院の家で、数人の奉公人を雇っていた真木家に働くようになって、1年目のこと。
優しかった奥様が亡くなり、そのお葬式での事だったんです。
当時まだ 紳太郎さんは11歳。
母親が亡くなった悲しさに、じっと耐えながら、8歳の妹の面倒を見ている、そんなお方でした。
私が、お葬式に来た方達のお世話をするのに、パタパタと廊下を、小走りで歩いていると、庭の片隅で、腕で顔を覆いながら、泣いているあのお方を見かけました。
その前には、奥様が植えたという花畑があって、紳太郎さんは、亡くなったお母様を思い出して、泣いておられたのでしょう。
その時私は、まだ奉公人の中でも下の方で、お子様達に、声を掛けることもできない身分でしたが、私も15歳で親元を離れてきたので、母が恋しいと泣く気持ちも理解でき、一緒に涙を流していたのを、よく覚えています。
それから2年後の事。
私は奉公も三年目になり、旦那さまにも顔を知って頂くようになって、そのついでに、お子様達とも話すようになっていました。
割と年齢も近いこともあって、話が弾んでは、上の人に怒られる事も度々でした。
そんな18歳の夏、旦那さまに呼ばれ、部屋にお伺いした時のことでした。
「旦那様、深雪(ミユキ)です。」
扉の外で自分の名を名乗ると、「入りなさい。」と、旦那さまの声が聞こえました。
「失礼します。」
私が部屋に入ると、旦那さまのお側には、二人のお子様が、座ってらっしゃいました。
向かって右側、旦那様の横には長男の倫太郎様。
左側には、ご次男の紳太郎様がいらっしゃいました。
「深雪、今日呼んだのは他でもない。おまえに頼みごとがあるんだ。」
「はい。」
「おまえも知っての通り、妻が亡くなってもう2年になる。息子達も大きくなって、身の回りの世話をするものが必要だ。」
「はい。」
「そこでどうだろう。おまえに、息子の世話を頼みたいんだが……」
私は驚いて、返事もできずにいました。
「いいだろう。息子達はおまえに、よく懐いているようだし。」
「はい。」
懐いていると言っても、時々お話をさせて頂くだけ。
とんでもない事になったわ。
そう思いながら顔を上げて、ちらっとお子様たちを見ると、16歳になった倫太郎様と13歳になった紳太郎様が、顔を見合せて、笑っていらっしゃいました。
お二人とも、私がお世話係になったのが、とても嬉しいと言うような、表情をしてらしたんです。
「お前の申し出が通ってよかったな、紳太郎。」
「はい、兄さん。」
何のことか分からずに、目をパチクリさせていると、倫太郎さんが教えてくれました。
「世話係りに、深雪を推薦したのは、紳太郎なんだよ。」
「紳太郎さんが?」
そう言うと、紳太郎さんは無邪気な笑顔を、私に見せて下さったのです。
そうなると、私もお断りする事もできず、その次の日から、倫太郎さんと紳太郎さんの、身の回りの世話が始まったのです。
ですが二人はまだ、16歳と13歳。
幼さが少しだけ、残っていらっしゃって。
朝、起きてお二人の元へ行くと、倫太郎様はもう起きていて、ご自分が寝ていらしゃった布団をたたんでいたりするのですが、紳太郎様は決まって、布団の中。
学校に遅れますよと、起こして差し上げると、眠い目をこすって、ゆっくり起き上がるのが、私達の日課でしたね。
ところで真木家というのは、倫太郎様と紳太郎様の、お爺様の代から医者の家系なんです。
経営なさっている病院も、地元では有名で大きなところだったんです。
当然の如く、お二人とも医者になるように、言い聞かされておりました。
ですから、学校も周りの方々が通っている普通の学校ではなく、医者や政治家、実業家、そんな人を多く輩出している学校に、通っていらっしゃいました。
ああ、お勉強の方ですか?
ええ。
倫太郎様も紳太郎様も、勉強に関しては何の不満も言わずに、一生懸命、頑張っていらしゃいましたよ。
お二人とも、旦那様の後を継いで、立派な医者になるのだと、仰っていましたから。
ところでお二人には、妹さまが一人いらっしゃって、名前を風音(カザネ)様と言いました。
お二人とも、特に紳太郎様は、この風音様を可愛がっていらしたんです。
ただ風音様は、生まれつき身体が弱い方で、いつも床に臥せっているようなお子様でした。
こんな事言うのもあれなんですがね。
とにかく、お金は持っている家でしたから、風音様には専属の医者、何人かの家政婦もつき、24時間お世話している状態でした。
甘やかしている?
傍から見れば、そう見えるのでしょうけど、当の風音様は重い心臓の病気で、いつ心臓が止まってもおかしくない状態だったんです。
その中で紳太郎様は、時々本を読んであげたり、一緒に双六をしたり。
珍しいお菓子をもらってきたと言っては、風音様へ持って行ってあげる、そんなおお優しいお兄様でしたね。
ああ、お二人に妹様がいらっしゃったのを、初めて聞きましたか?
あまり知られていないことですからね。
特別な事情というほどでもないのですが、妹の風音様は看病の甲斐もなく、幼い頃にお亡くなりになってしまったんです。
それはある雪の日、いつものように、紳太郎様が帰ってらっしゃった時でした。
「ただいま帰ったよ、深雪。」
「お帰りなさいませ。」
「何か変わった事は?」
鞄を置きながら、そう私に聞くのが、紳太郎様の口癖でした。
「特に変わったことは……」
私がそう言おうとした時でした。
「失礼します!」
風音様についている家政婦の一人が、急いでやってきたんです。
「どうしたのです?」
私が尋ねると、その家政婦の体は、震えていました。
「紳太郎様、早く……早く、風音様の元へ……」
只事ではない表情に、私と紳太郎様は、急いで風音様の部屋へ、向かったのですが………
「紳太郎…」
既に倫太郎様はいらっしゃっていて、風音様の小さな手を握っておいででした。
「たった今…逝ってしまった……」
紳太郎様は、その場に崩れ落ちてしまって、這いながら風音様の枕元へ。
「風音……風音!!」
何度も風音様の身体を揺らして、終いには、その亡骸にすがっておいででした。
そして、その後。
部屋に戻った紳太郎様が一言。
「深雪。」
「はい。」
「俺は、医者になりたくない。」
あんなに立派な医者になると、仰っていた紳太郎様が、そんな言葉を口にされるなんて。
「紳太郎様?」
「風音は結局、死んでしまったじゃないか。」
生きとし生ける者、全て死ぬ時が来る。
風音様は、人よりもその時が早かっただけ。
そう分かっていても、紳太郎様にかけて差し上げる言葉も見つからず、私はただ俯いて、あの方のお側にいるだけでした。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

粗暴で優しい幼馴染彼氏はおっとり系彼女を好きすぎる
春音優月
恋愛
おっとりふわふわ大学生の一色のどかは、中学生の時から付き合っている幼馴染彼氏の黒瀬逸希と同棲中。態度や口は荒っぽい逸希だけど、のどかへの愛は大きすぎるほど。
幸せいっぱいなはずなのに、逸希から一度も「好き」と言われてないことに気がついてしまって……?
幼馴染大学生の糖度高めなショートストーリー。
2024.03.06
イラスト:雪緒さま

マッサージ
えぼりゅういち
恋愛
いつからか疎遠になっていた女友達が、ある日突然僕の家にやってきた。
背中のマッサージをするように言われ、大人しく従うものの、しばらく見ないうちにすっかり成長していたからだに触れて、興奮が止まらなくなってしまう。
僕たちはただの友達……。そう思いながらも、彼女の身体の感触が、冷静になることを許さない。
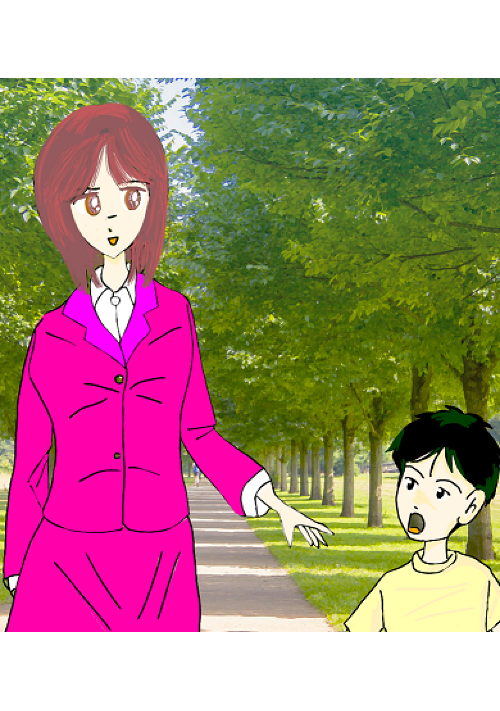
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















