97 / 127
狼と名もなき墓標
30
しおりを挟む
庭の散歩から戻ると、心配顔のクラウスが出迎えてくれた。
エミールが屋敷に閉じこもっている間、クラウスもまた、ほとんど出かけることはなかった。彼の騎士団の制服姿を、エミールはこの三か月一度も見ていない。
エミールから離れられないからだ。
エミールが、いつ正気を失って暴れるかわからないから。
だからいつもエミールの様子を伺って、極力目を離さないようにしているのだと、そう思っていた。
だけど、もしかしたらそれだけが理由ではないのかもしれない。
今回の件で、クラウスにも傷が残ったのだとしたら。
エミールが、クラウス不在の折りに死ぬほどの怪我を負ってしまったこと、それがクラウスの傷になってしまったのだとしたら。
クラウス自身が、エミールから離れることを恐れているのかもしれない、と、そう思えた。
伸びてきた腕に抱き寄せられ、クラウスの腕の中でつがいの匂いを鼻腔に吸い込みながら、このままじゃいけない、とエミールは思った。
自分も、クラウスも。このままじゃいけない。
ではどうすればいいのだろう。
傷を抱えたまま前に進むのに、必要なものは、なんだろう。
「エル、大丈夫か。散歩に行っていたのか」
「うん……」
「疲れてないか」
「大丈夫」
抱きあげられ、男の首に腕を回す。かなしみの匂いはクラウス自身の香りと混ざり合っていて、もはやひとつの香りになってしまっている。
「オレ、今日は大丈夫なんだ……」
エミールはそう繰り返した。
頑張るから、とスヴェンに言ったときの、あの胸の奥に灯った熱はまだそこにしっかりと根付いていた。
「ラス……ラス、聞いて」
「どうした」
エミールを抱いたまま寝室へ連れて行こうとしていたクラウスが、足を止めた。エミールは彼の頬に両手を当てた。
元々狼のように端整で鋭かった顔立ち。その輪郭は以前に比べると痩せていて、彼の苦しみを如実に表しているようだった。
「ごめんね。ずっとひとりで頑張らせて」
エミールはひたいをコツリと当てて、クラウスへと謝った。蒼い瞳が見開かれた。
「エル、おまえはなにも悪くない」
「うん。でも、オレ、弱くて……全部夢なら良かったのにって思って、逃げて……」
「私も弱い。これはすべて悪い夢で、目覚めたらいつものようにおまえが笑ってる。そんな妄想を幾度もした」
「でもラスは、ちゃんと踏ん張って、オレを支えてくれた。……オレが先におかしくなったから、ラスがしっかりするしかなかったんだよね」
「そんなふうに考えたことはない」
合わさったひたいをこするようにして、クラウスが首を横に振った。
おまえは悪くない。そう言い続けてくれたクラウス。
エミールは悪くない。
エミールは誰も殺していない、と。
エミールの負った傷をすべてかき集めて、ぜんぶ自分で背負おうとしてくるエミールのアルファ。
彼の愛情はいつも、大きくて、あたたかで、一途で、真摯だ。
だけどそれを、エミールの目から隠す。エミールの知らないところで、エミールのためにとファルケンと契約をして、オシュトロークではエミールの母親を探して、護衛に『狼』をつけて……ぜんぶ、エミールの見えないところで、エミールのために。
では、いま、エミールがクラウスのためにできることはなんだろう。
この男のために。なにをしてあげられるだろうか。
「オレ、オレね、頑張りたい」
「……エミール」
「頑張るよ。ちゃんと立ち直れるように頑張る。だから、前を向けるように、ラスにお願いがあるんだ」
「……おまえは充分頑張っている。だが、おまえが望むなら私はそれをなんでも叶えたい」
返ってきた生真面目な言葉に、思わず小さな笑みがこぼれた。
唇を啄むと、相手からも触れるだけのキスが返ってくる。
エミールはクラウスと視線を合わせたまま、ささやきの音で願いごとを伝えた。
「お墓に行きたいんだ」
クラウスが絶句した。
あるよね、とエミールは続けた。
「あるよね。オレとラスの、赤ちゃんのお墓」
「…………」
沈黙は、肯定でも否定でもなかった。
想像妊娠だと言われた。お腹に子どもは居なかった。クラウスからもベルンハルトからもそう説明された。シモンがまとめたという報告書も読んだ。想像妊娠というものが実際に起こり得る症状だということもわかった。
それでもエミールは、自身のお腹に子が居たという事実を、なかったことにはできなかった。
赤ちゃんは、居た。
想像妊娠は、エミールに子どものいのちを背負わせないための、クラウスのついたやさしい嘘なのだ。
「ラス、お願い。オレが前を向く、きっかけにしたいんだ。オレたちの子の、お墓に連れて行って」
クラウスの眉が苦しげに寄せられた。
唇の端がひくりと動いた。彼は迷うように、幾度も口を開きかけ……やがてしずかに一度、頷いた。
「明日でいいか」
「……うん」
「一緒に行こう」
「うん」
自分で言い出したことなのに、体が震えだした。
その日の夜は、いつものようにクラウスに抱き締められて眠った。
今日の出来事を忘れてしまわないように、なんども頭の中で反芻させたからか、眠りは浅かった。
翌朝、スヴェンに起こされて目を覚ましたエミールは、朝食の後、久しぶりに外出着に着替えた。
クラウスはすでに身支度を済ませており、朝摘みの花で作った花束をエミールに差し出してきた。
「行くか」
花束を左手に持ち、右手はクラウスに引かれて屋敷を出る。
遠いの? と尋ねたら、すぐ近くだと言われた。
屋敷の裏手には小さな池がある。そこをぐるりと回った木陰に、ひっそりと立つ石碑があった。
膝の高さにも満たない石碑だ。
赤子は、お腹の中に居る時点ではまだ王族とは認められない。生まれてきて初めて、王家の一員となるのだ。だからエミールの子どもは、王家の墓には入れない。その代わりに、いつでも会えるよう屋敷のそば近くに墓を作った。そんなクラウスの説明を聞きながら、エミールは頽れるようにして膝をついた。
両手で、木の根元の土を掻き分ける。
横からクラウスの手が伸びてきた。クラウスは、エミールを制止しようとはしなかった。エミールと一緒に土を掘ってくれた。
やがて、白い陶器の壺が見えた。片手で包めてしまうほどの小さな小さな壺だった。
エミールは肩で息をしながら、その壺を土中からそうっと取り上げた。
蓋を外そうとして、おのれの手が土で汚れていることに気づいた。ごしごしと太ももの辺りに手をこすりつけ、土を落とす。
クラウスがハンカチを出してきて、エミールの手をくるんだ。
蓋を開いた。壺を傾けて、ハンカチの上に中身を出した。
白い白い骨の欠片が、数個、転がり落ちてきた。
エミールは泣いた。泣きながら、その欠片をそっと胸に押し抱いた。
これはなんの骨なのだろう。
エミールのお腹に居た赤ちゃんのものなのか。
それとも本当に赤ちゃんなどは居なくて、エミールを納得させるためにクラウスが仕込んだ、小動物の骨なのか。
本当のところはわからない。
赤ちゃんは居たのか、居なかったのか。
それでもエミールのかなしみと、胸の痛みは現実のもので。
エミールの肩を抱くクラウスの苦しみと傷もまた、現実のものなのだ。
「……ラス、ラス、お墓を、ありがとう……」
「礼など、言わないでくれ。私はこんなことしかできなかった」
「こんなことじゃ、ないよ……ここからは、オレたちのお屋敷が良く見える。さびしくないね」
泣きながらエミールは、つがいと抱き合った。
生まれる前に消えたいのち。名前のない、墓標。小さな骨の欠片たち。
一生忘れない。
一生、忘れない。
エミールはクラウスの作った花束を墓標の前に置いて、声を上げて思う存分泣いた。
エミールが屋敷に閉じこもっている間、クラウスもまた、ほとんど出かけることはなかった。彼の騎士団の制服姿を、エミールはこの三か月一度も見ていない。
エミールから離れられないからだ。
エミールが、いつ正気を失って暴れるかわからないから。
だからいつもエミールの様子を伺って、極力目を離さないようにしているのだと、そう思っていた。
だけど、もしかしたらそれだけが理由ではないのかもしれない。
今回の件で、クラウスにも傷が残ったのだとしたら。
エミールが、クラウス不在の折りに死ぬほどの怪我を負ってしまったこと、それがクラウスの傷になってしまったのだとしたら。
クラウス自身が、エミールから離れることを恐れているのかもしれない、と、そう思えた。
伸びてきた腕に抱き寄せられ、クラウスの腕の中でつがいの匂いを鼻腔に吸い込みながら、このままじゃいけない、とエミールは思った。
自分も、クラウスも。このままじゃいけない。
ではどうすればいいのだろう。
傷を抱えたまま前に進むのに、必要なものは、なんだろう。
「エル、大丈夫か。散歩に行っていたのか」
「うん……」
「疲れてないか」
「大丈夫」
抱きあげられ、男の首に腕を回す。かなしみの匂いはクラウス自身の香りと混ざり合っていて、もはやひとつの香りになってしまっている。
「オレ、今日は大丈夫なんだ……」
エミールはそう繰り返した。
頑張るから、とスヴェンに言ったときの、あの胸の奥に灯った熱はまだそこにしっかりと根付いていた。
「ラス……ラス、聞いて」
「どうした」
エミールを抱いたまま寝室へ連れて行こうとしていたクラウスが、足を止めた。エミールは彼の頬に両手を当てた。
元々狼のように端整で鋭かった顔立ち。その輪郭は以前に比べると痩せていて、彼の苦しみを如実に表しているようだった。
「ごめんね。ずっとひとりで頑張らせて」
エミールはひたいをコツリと当てて、クラウスへと謝った。蒼い瞳が見開かれた。
「エル、おまえはなにも悪くない」
「うん。でも、オレ、弱くて……全部夢なら良かったのにって思って、逃げて……」
「私も弱い。これはすべて悪い夢で、目覚めたらいつものようにおまえが笑ってる。そんな妄想を幾度もした」
「でもラスは、ちゃんと踏ん張って、オレを支えてくれた。……オレが先におかしくなったから、ラスがしっかりするしかなかったんだよね」
「そんなふうに考えたことはない」
合わさったひたいをこするようにして、クラウスが首を横に振った。
おまえは悪くない。そう言い続けてくれたクラウス。
エミールは悪くない。
エミールは誰も殺していない、と。
エミールの負った傷をすべてかき集めて、ぜんぶ自分で背負おうとしてくるエミールのアルファ。
彼の愛情はいつも、大きくて、あたたかで、一途で、真摯だ。
だけどそれを、エミールの目から隠す。エミールの知らないところで、エミールのためにとファルケンと契約をして、オシュトロークではエミールの母親を探して、護衛に『狼』をつけて……ぜんぶ、エミールの見えないところで、エミールのために。
では、いま、エミールがクラウスのためにできることはなんだろう。
この男のために。なにをしてあげられるだろうか。
「オレ、オレね、頑張りたい」
「……エミール」
「頑張るよ。ちゃんと立ち直れるように頑張る。だから、前を向けるように、ラスにお願いがあるんだ」
「……おまえは充分頑張っている。だが、おまえが望むなら私はそれをなんでも叶えたい」
返ってきた生真面目な言葉に、思わず小さな笑みがこぼれた。
唇を啄むと、相手からも触れるだけのキスが返ってくる。
エミールはクラウスと視線を合わせたまま、ささやきの音で願いごとを伝えた。
「お墓に行きたいんだ」
クラウスが絶句した。
あるよね、とエミールは続けた。
「あるよね。オレとラスの、赤ちゃんのお墓」
「…………」
沈黙は、肯定でも否定でもなかった。
想像妊娠だと言われた。お腹に子どもは居なかった。クラウスからもベルンハルトからもそう説明された。シモンがまとめたという報告書も読んだ。想像妊娠というものが実際に起こり得る症状だということもわかった。
それでもエミールは、自身のお腹に子が居たという事実を、なかったことにはできなかった。
赤ちゃんは、居た。
想像妊娠は、エミールに子どものいのちを背負わせないための、クラウスのついたやさしい嘘なのだ。
「ラス、お願い。オレが前を向く、きっかけにしたいんだ。オレたちの子の、お墓に連れて行って」
クラウスの眉が苦しげに寄せられた。
唇の端がひくりと動いた。彼は迷うように、幾度も口を開きかけ……やがてしずかに一度、頷いた。
「明日でいいか」
「……うん」
「一緒に行こう」
「うん」
自分で言い出したことなのに、体が震えだした。
その日の夜は、いつものようにクラウスに抱き締められて眠った。
今日の出来事を忘れてしまわないように、なんども頭の中で反芻させたからか、眠りは浅かった。
翌朝、スヴェンに起こされて目を覚ましたエミールは、朝食の後、久しぶりに外出着に着替えた。
クラウスはすでに身支度を済ませており、朝摘みの花で作った花束をエミールに差し出してきた。
「行くか」
花束を左手に持ち、右手はクラウスに引かれて屋敷を出る。
遠いの? と尋ねたら、すぐ近くだと言われた。
屋敷の裏手には小さな池がある。そこをぐるりと回った木陰に、ひっそりと立つ石碑があった。
膝の高さにも満たない石碑だ。
赤子は、お腹の中に居る時点ではまだ王族とは認められない。生まれてきて初めて、王家の一員となるのだ。だからエミールの子どもは、王家の墓には入れない。その代わりに、いつでも会えるよう屋敷のそば近くに墓を作った。そんなクラウスの説明を聞きながら、エミールは頽れるようにして膝をついた。
両手で、木の根元の土を掻き分ける。
横からクラウスの手が伸びてきた。クラウスは、エミールを制止しようとはしなかった。エミールと一緒に土を掘ってくれた。
やがて、白い陶器の壺が見えた。片手で包めてしまうほどの小さな小さな壺だった。
エミールは肩で息をしながら、その壺を土中からそうっと取り上げた。
蓋を外そうとして、おのれの手が土で汚れていることに気づいた。ごしごしと太ももの辺りに手をこすりつけ、土を落とす。
クラウスがハンカチを出してきて、エミールの手をくるんだ。
蓋を開いた。壺を傾けて、ハンカチの上に中身を出した。
白い白い骨の欠片が、数個、転がり落ちてきた。
エミールは泣いた。泣きながら、その欠片をそっと胸に押し抱いた。
これはなんの骨なのだろう。
エミールのお腹に居た赤ちゃんのものなのか。
それとも本当に赤ちゃんなどは居なくて、エミールを納得させるためにクラウスが仕込んだ、小動物の骨なのか。
本当のところはわからない。
赤ちゃんは居たのか、居なかったのか。
それでもエミールのかなしみと、胸の痛みは現実のもので。
エミールの肩を抱くクラウスの苦しみと傷もまた、現実のものなのだ。
「……ラス、ラス、お墓を、ありがとう……」
「礼など、言わないでくれ。私はこんなことしかできなかった」
「こんなことじゃ、ないよ……ここからは、オレたちのお屋敷が良く見える。さびしくないね」
泣きながらエミールは、つがいと抱き合った。
生まれる前に消えたいのち。名前のない、墓標。小さな骨の欠片たち。
一生忘れない。
一生、忘れない。
エミールはクラウスの作った花束を墓標の前に置いて、声を上げて思う存分泣いた。
434
お気に入りに追加
784
あなたにおすすめの小説
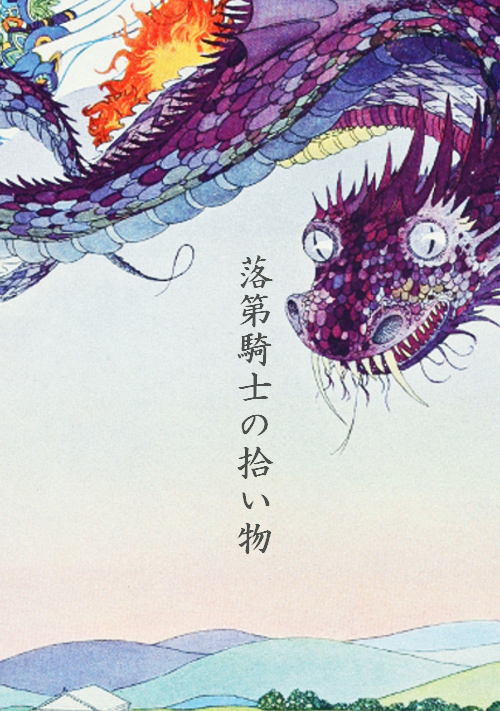
落第騎士の拾い物
深山恐竜
BL
「オメガでございます」
ひと月前、セレガは医者から第三の性別を告知された。将来は勇猛な騎士になることを夢見ていたセレガは、この診断に絶望した。
セレガは絶望の末に”ドラゴンの巣”へ向かう。そこで彼は騎士見習いとして最期の戦いをするつもりであった。しかし、巣にはドラゴンに育てられたという男がいた。男は純粋で、無垢で、彼と交流するうちに、セレガは未来への希望を取り戻す。
ところがある日、発情したセレガは男と関係を持ってしまって……?
オメガバースの設定をお借りしています。
ムーンライトノベルズにも掲載中

こじらせΩのふつうの婚活
深山恐竜
BL
宮間裕貴はΩとして生まれたが、Ωとしての生き方を受け入れられずにいた。
彼はヒートがないのをいいことに、ふつうのβと同じように大学へ行き、就職もした。
しかし、ある日ヒートがやってきてしまい、ふつうの生活がままならなくなってしまう。
裕貴は平穏な生活を取り戻すために婚活を始めるのだが、こじらせてる彼はなかなかうまくいかなくて…。

【完結】幼馴染から離れたい。
June
BL
隣に立つのは運命の番なんだ。
βの谷口優希にはαである幼馴染の伊賀崎朔がいる。だが、ある日の出来事をきっかけに、幼馴染以上に大切な存在だったのだと気づいてしまう。
番外編 伊賀崎朔視点もあります。
(12月:改正版)

初心者オメガは執着アルファの腕のなか
深嶋
BL
自分がベータであることを信じて疑わずに生きてきた圭人は、見知らぬアルファに声をかけられたことがきっかけとなり、二次性の再検査をすることに。その結果、自身が本当はオメガであったと知り、愕然とする。
オメガだと判明したことで否応なく変化していく日常に圭人は戸惑い、悩み、葛藤する日々。そんな圭人の前に、「運命の番」を自称するアルファの男が再び現れて……。
オメガとして未成熟な大学生の圭人と、圭人を番にしたい社会人アルファの男が、ゆっくりと愛を深めていきます。
穏やかさに滲む執着愛。望まぬ幸運に恵まれた主人公が、悩みながらも運命の出会いに向き合っていくお話です。本編、攻め編ともに完結済。

花婿候補は冴えないαでした
一
BL
バース性がわからないまま育った凪咲は、20歳の年に待ちに待った判定を受けた。会社を経営する父の一人息子として育てられるなか結果はΩ。 父親を困らせることになってしまう。このまま親に従って、政略結婚を進めて行こうとするが、それでいいのかと自分の今後を考え始める。そして、偶然同じ部署にいた25歳の秘書の孝景と出会った。
本番なしなのもたまにはと思って書いてみました!
※pixivに同様の作品を掲載しています

僕の番
結城れい
BL
白石湊(しらいし みなと)は、大学生のΩだ。αの番がいて同棲までしている。最近湊は、番である森颯真(もり そうま)の衣服を集めることがやめられない。気づかれないように少しずつ集めていくが――
※他サイトにも掲載


既成事実さえあれば大丈夫
ふじの
BL
名家出身のオメガであるサミュエルは、第三王子に婚約を一方的に破棄された。名家とはいえ貧乏な家のためにも新しく誰かと番う必要がある。だがサミュエルは行き遅れなので、もはや選んでいる立場ではない。そうだ、既成事実さえあればどこかに嫁げるだろう。そう考えたサミュエルは、ヒート誘発薬を持って夜会に乗り込んだ。そこで出会った美丈夫のアルファ、ハリムと意気投合したが───。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















