57 / 127
二人の王子
4
しおりを挟む
あのアダムの事件のとき、スヴェンは機敏に動き、ファルケンにも劣らない体術を披露していた。エミールと体型は変わらないのに、だ。
筋肉のつきにくいエミールと違ってスヴェンは華奢ながらもしっかりと鍛えているため、まったく同じように動くことはできないだろうけど、身長も体格もほぼ同じなのだから、エミールだってスヴェンを真似すればそれなりになるのではないか。
そう考え、スヴェンに簡単な武術を教わってもいいだろうかとクラウスに相談したところ、彼は非常に渋い顔を見せた。
なにがそんなに嫌なのか、と問いただし、
「あなたはヒョロヒョロのオレが好きなんですね。筋肉ムキムキになったら嫌いになるんですね!」
と腹立たしく詰ったら、そんなわけないだろうとヒシと抱きしめられた。
「どんなおまえでも私の愛が変わることはない」
「じゃあ、」
「だが、武術を習うのは反対だ」
「なんでですか!」
「武術や剣術には型がある。護身術にもだ。決まった動きをせねばならない」
それのなにが問題なのか、とエミールが胡乱な目で男を見ると、クラウスは至極真面目な顔で続けた。
「動きを教える過程で、おまえの体に触れることになるだろう」
「…………」
「私以外の者が、おまえの体に触れるんだ」
「…………」
エミールはひたいを押さえた。
「ただの訓練でしょう。あなただって、そうやって剣術を覚えてきたんだし」
「私の場合はおまえと出会う前のことだ」
「でも、スヴェンですよ? スヴェンのことはラスだって信頼してるんでしょう?」
スヴェンはクラウスの私兵のひとりだ。そう言ったのはクラウス本人である。
信頼しているからこそエミールの侍従に付けたわけだし、エミールの護衛も任せていたはずだ。
「信頼しているからと言って、おまえに触れていいことにはならない」
「……子どもですかあなたは」
「わかった。私が教える。それでいいな?」
「却下します」
「なぜだ」
自分よりもスヴェンがいいのか、とクラウスが目を剥いた。
その蒼い宝石のような瞳を見つめ返し、エミールは男の金髪を撫でた。
「ラスは忙しいから、オレの稽古の相手なんてする暇ないだろ」
そう。クラウスは多忙だ。それは年々ひどくなっている気がする。
騎士団の任務や訓練、王族としての公務、それに革命派の旗印という役割も加わった。
彼が寝食を惜しんで動き回っていることは、エミールにもよくわかっている。
だからエミールの稽古の相手などする暇はないはずだ。
しかしクラウスは首を横に振った。
「時間は作る」
「いいよ。ラスとは稽古よりも、こうやってくっついてたい」
胸元に抱き寄せたクラウスの頭にすり……と頬ずりをして囁いたエミールは、
「だからスヴェンに習っても、」
いいよね、と言葉を続けかけたが、
「ダメだ」
と強い声が被さってきて掻き消されてしまった。
なんて頑固なつがいだろう。
エミールは両手でクラウスの頬を挟み、ぐっと顔を近づけて「わかりました」と頷いた。
「わかりました。スヴェンに触られるのはダメで、オレが暴漢に襲われたときに碌な抵抗もできず体を撫でまわされるのはいいってことですね」
「そんなことは言ってない。そもそもおまえが襲われることなどない」
「そんなのわからないでしょう。スヴェンだってオレにずっと張り付いてるわけじゃないんだし、不測の事態ってのはどんなときも起こる可能性があるんですよ」
「む……だが」
「万が一オレが襲われる事態になったとき、武術を習わせておけば良かったって後悔しませんか? 絶対に? オレが暴漢にベタベタ触れてても? 暴漢よりはスヴェンとの稽古でスヴェンに触られる方が良かったって思いませんか?」
矢継ぎ早に問いかけると、クラウスが「ぐ……」と怯んだのがわかった。
揺れている。あと一押しだ。
「オレだって暴漢なんかに触られるのは嫌です。だからいざというときに動けるようになりたいんです。だって、オレが襲われたら一番かなしむのは、ラス、あなたなんですから」
「……エル……」
「ラス、オレにあなたをまもらせて」
「……エル!」
クラウスがぎゅうっとエミールを抱きしめた。息が止まりそうなほどに強い抱擁だ。
よし、落ちた。エミールの感じたその手ごたえは、本物の結果に繋がった。
クラウスは渋々……本当に渋々エミールがスヴェンに護身術を教わることを認めてくれたのだ。
この顛末をスヴェンに話したところ、彼は呆れたように吐息して、
「つがいバカってのはクラウス様のことを言うんでしょうね」
と侍従にあるまじき発言をしていた。
思えばロンバードもファルケンも、第二王子相手に言いたい放題だ。そういう、あまり畏まらない人間を私兵として採用しているのかもしれなかった。
ともかく、そういう流れを経て最近のエミールの日課には、スヴェンとの稽古が追加になったのである。
「まぁ護身術ぐらいは身に着けておくべきだな」
と言ったのはファルケンだ。
いつもの異国風の黒い包衣姿の彼は、娼館の自室でゆったりと煙管を咥えていた。
エミールがここを訪れるのはいつも日中で女たちが寝ている時間であったため、ファルケン以外と顔を合わせる機会は少ない。
それでも数年にわたり頻繁に通ってくるエミールのことを、娼婦たちは『ファルケンの恋人』と認識しているようだった。
「ファルケン、ファルケン、今日も来たわよ」
「あなたのイイひとが」
小鳥のように囀る女たちを、
「うるさい。さっさと部屋で休んでろ」
ファルケンがぞんざいに手を振って追い返している場面に遭遇したこともあった。
王都で認可を得て経営しているこの娼館には、俗に言う高級娼婦が所属している。建物は清潔で豪奢だし、客層もいいから用心棒としてのファルケンの仕事はあまりないようで、そのぶん女たちの世話役のようなこともしていると聞く。
うつくしく豊満な体つきの娼婦たちにファルケンが囲まれていると、エミールはなんだかモヤモヤしてしまう。
自分がクラウスと結婚したように、ファルケンもいずれは誰かと添い遂げるのだろうか。それはあまり楽しくない想像だった。
「ルーは恋人は居るの?」
それとなく尋ねてみたが、
「そんな暇ねぇよ」
と一蹴されて終わった。
本当だろうか、とエミールは疑いの目を向ける。
幼馴染の欲目を抜いても、ファルケンは男らしくてとても格好いい。顔の半分をクラウスから貰った黒い眼帯で覆っているせいで、近寄りがたく怖い印象もあるが、それがまた彼の魅力にもなっていた。
上背もあり体格もいい。クラウスといい、アルファとは皆、神に愛されたような外見をしているのだろうか。
「恋人ができたら、教えてくれる?」
「なんでだよ」
「だって、オレはルーの家族なわけだし」
正式にはなんの繋がりもない。戸籍局に届け出たわけでもない。家族であることを証明できる書類さえない。それでも、エミールにとってファルケンは家族だった。
ファルケンが金茶の瞳を細めた。彼の左手が、エミールの頭を軽く撫でた。
「おまえやチビたちで手一杯なのに、恋人なんかできるわけないだろ」
『国防壁の向こう側から落とされた子どもたち』についてはまだ調査が続いていた。
昨年クラウスら騎士団が成し遂げたオメガ解放。その際にオシュトロークより保護したオメガたちの中に、孤児たちの母親が居るのではないかという指摘があり、親子関係の鑑定にも時間を要している。
ファルケンはそちらの調査にも駆り出されているとのことだった。
自分や子どもたちがファルケンを縛り付けている。
その自覚はエミールの中にあったが、もうすこしだけ、ファルケンを留めておきたかった。
だって、さびしい。
ファルケンが誰かのものになって、エミールよりもその誰かが優先されるようになってしまうのは、さびしい。
先に結婚した自分が言うことではなかったが、クラウスとはまたべつの意味でファルケンはエミールにとって特別だったから。
ファルケンにとってもエミールも、特別な場所に置いておいてほしかった。
それが身勝手な願望だと、よくわかっていたけれど。
筋肉のつきにくいエミールと違ってスヴェンは華奢ながらもしっかりと鍛えているため、まったく同じように動くことはできないだろうけど、身長も体格もほぼ同じなのだから、エミールだってスヴェンを真似すればそれなりになるのではないか。
そう考え、スヴェンに簡単な武術を教わってもいいだろうかとクラウスに相談したところ、彼は非常に渋い顔を見せた。
なにがそんなに嫌なのか、と問いただし、
「あなたはヒョロヒョロのオレが好きなんですね。筋肉ムキムキになったら嫌いになるんですね!」
と腹立たしく詰ったら、そんなわけないだろうとヒシと抱きしめられた。
「どんなおまえでも私の愛が変わることはない」
「じゃあ、」
「だが、武術を習うのは反対だ」
「なんでですか!」
「武術や剣術には型がある。護身術にもだ。決まった動きをせねばならない」
それのなにが問題なのか、とエミールが胡乱な目で男を見ると、クラウスは至極真面目な顔で続けた。
「動きを教える過程で、おまえの体に触れることになるだろう」
「…………」
「私以外の者が、おまえの体に触れるんだ」
「…………」
エミールはひたいを押さえた。
「ただの訓練でしょう。あなただって、そうやって剣術を覚えてきたんだし」
「私の場合はおまえと出会う前のことだ」
「でも、スヴェンですよ? スヴェンのことはラスだって信頼してるんでしょう?」
スヴェンはクラウスの私兵のひとりだ。そう言ったのはクラウス本人である。
信頼しているからこそエミールの侍従に付けたわけだし、エミールの護衛も任せていたはずだ。
「信頼しているからと言って、おまえに触れていいことにはならない」
「……子どもですかあなたは」
「わかった。私が教える。それでいいな?」
「却下します」
「なぜだ」
自分よりもスヴェンがいいのか、とクラウスが目を剥いた。
その蒼い宝石のような瞳を見つめ返し、エミールは男の金髪を撫でた。
「ラスは忙しいから、オレの稽古の相手なんてする暇ないだろ」
そう。クラウスは多忙だ。それは年々ひどくなっている気がする。
騎士団の任務や訓練、王族としての公務、それに革命派の旗印という役割も加わった。
彼が寝食を惜しんで動き回っていることは、エミールにもよくわかっている。
だからエミールの稽古の相手などする暇はないはずだ。
しかしクラウスは首を横に振った。
「時間は作る」
「いいよ。ラスとは稽古よりも、こうやってくっついてたい」
胸元に抱き寄せたクラウスの頭にすり……と頬ずりをして囁いたエミールは、
「だからスヴェンに習っても、」
いいよね、と言葉を続けかけたが、
「ダメだ」
と強い声が被さってきて掻き消されてしまった。
なんて頑固なつがいだろう。
エミールは両手でクラウスの頬を挟み、ぐっと顔を近づけて「わかりました」と頷いた。
「わかりました。スヴェンに触られるのはダメで、オレが暴漢に襲われたときに碌な抵抗もできず体を撫でまわされるのはいいってことですね」
「そんなことは言ってない。そもそもおまえが襲われることなどない」
「そんなのわからないでしょう。スヴェンだってオレにずっと張り付いてるわけじゃないんだし、不測の事態ってのはどんなときも起こる可能性があるんですよ」
「む……だが」
「万が一オレが襲われる事態になったとき、武術を習わせておけば良かったって後悔しませんか? 絶対に? オレが暴漢にベタベタ触れてても? 暴漢よりはスヴェンとの稽古でスヴェンに触られる方が良かったって思いませんか?」
矢継ぎ早に問いかけると、クラウスが「ぐ……」と怯んだのがわかった。
揺れている。あと一押しだ。
「オレだって暴漢なんかに触られるのは嫌です。だからいざというときに動けるようになりたいんです。だって、オレが襲われたら一番かなしむのは、ラス、あなたなんですから」
「……エル……」
「ラス、オレにあなたをまもらせて」
「……エル!」
クラウスがぎゅうっとエミールを抱きしめた。息が止まりそうなほどに強い抱擁だ。
よし、落ちた。エミールの感じたその手ごたえは、本物の結果に繋がった。
クラウスは渋々……本当に渋々エミールがスヴェンに護身術を教わることを認めてくれたのだ。
この顛末をスヴェンに話したところ、彼は呆れたように吐息して、
「つがいバカってのはクラウス様のことを言うんでしょうね」
と侍従にあるまじき発言をしていた。
思えばロンバードもファルケンも、第二王子相手に言いたい放題だ。そういう、あまり畏まらない人間を私兵として採用しているのかもしれなかった。
ともかく、そういう流れを経て最近のエミールの日課には、スヴェンとの稽古が追加になったのである。
「まぁ護身術ぐらいは身に着けておくべきだな」
と言ったのはファルケンだ。
いつもの異国風の黒い包衣姿の彼は、娼館の自室でゆったりと煙管を咥えていた。
エミールがここを訪れるのはいつも日中で女たちが寝ている時間であったため、ファルケン以外と顔を合わせる機会は少ない。
それでも数年にわたり頻繁に通ってくるエミールのことを、娼婦たちは『ファルケンの恋人』と認識しているようだった。
「ファルケン、ファルケン、今日も来たわよ」
「あなたのイイひとが」
小鳥のように囀る女たちを、
「うるさい。さっさと部屋で休んでろ」
ファルケンがぞんざいに手を振って追い返している場面に遭遇したこともあった。
王都で認可を得て経営しているこの娼館には、俗に言う高級娼婦が所属している。建物は清潔で豪奢だし、客層もいいから用心棒としてのファルケンの仕事はあまりないようで、そのぶん女たちの世話役のようなこともしていると聞く。
うつくしく豊満な体つきの娼婦たちにファルケンが囲まれていると、エミールはなんだかモヤモヤしてしまう。
自分がクラウスと結婚したように、ファルケンもいずれは誰かと添い遂げるのだろうか。それはあまり楽しくない想像だった。
「ルーは恋人は居るの?」
それとなく尋ねてみたが、
「そんな暇ねぇよ」
と一蹴されて終わった。
本当だろうか、とエミールは疑いの目を向ける。
幼馴染の欲目を抜いても、ファルケンは男らしくてとても格好いい。顔の半分をクラウスから貰った黒い眼帯で覆っているせいで、近寄りがたく怖い印象もあるが、それがまた彼の魅力にもなっていた。
上背もあり体格もいい。クラウスといい、アルファとは皆、神に愛されたような外見をしているのだろうか。
「恋人ができたら、教えてくれる?」
「なんでだよ」
「だって、オレはルーの家族なわけだし」
正式にはなんの繋がりもない。戸籍局に届け出たわけでもない。家族であることを証明できる書類さえない。それでも、エミールにとってファルケンは家族だった。
ファルケンが金茶の瞳を細めた。彼の左手が、エミールの頭を軽く撫でた。
「おまえやチビたちで手一杯なのに、恋人なんかできるわけないだろ」
『国防壁の向こう側から落とされた子どもたち』についてはまだ調査が続いていた。
昨年クラウスら騎士団が成し遂げたオメガ解放。その際にオシュトロークより保護したオメガたちの中に、孤児たちの母親が居るのではないかという指摘があり、親子関係の鑑定にも時間を要している。
ファルケンはそちらの調査にも駆り出されているとのことだった。
自分や子どもたちがファルケンを縛り付けている。
その自覚はエミールの中にあったが、もうすこしだけ、ファルケンを留めておきたかった。
だって、さびしい。
ファルケンが誰かのものになって、エミールよりもその誰かが優先されるようになってしまうのは、さびしい。
先に結婚した自分が言うことではなかったが、クラウスとはまたべつの意味でファルケンはエミールにとって特別だったから。
ファルケンにとってもエミールも、特別な場所に置いておいてほしかった。
それが身勝手な願望だと、よくわかっていたけれど。
339
お気に入りに追加
784
あなたにおすすめの小説
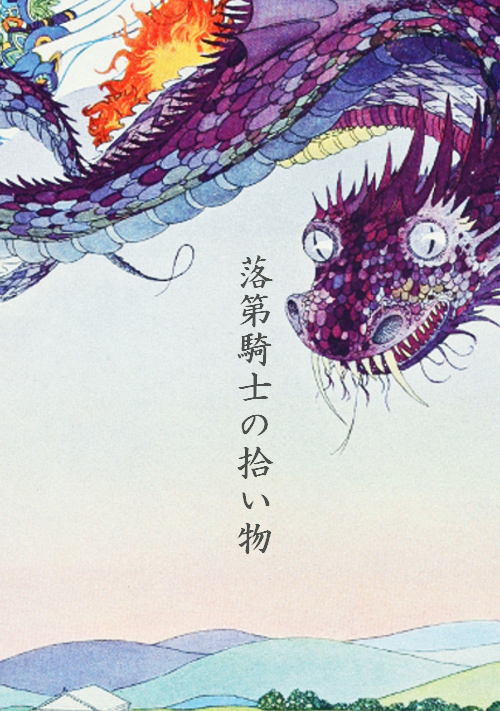
落第騎士の拾い物
深山恐竜
BL
「オメガでございます」
ひと月前、セレガは医者から第三の性別を告知された。将来は勇猛な騎士になることを夢見ていたセレガは、この診断に絶望した。
セレガは絶望の末に”ドラゴンの巣”へ向かう。そこで彼は騎士見習いとして最期の戦いをするつもりであった。しかし、巣にはドラゴンに育てられたという男がいた。男は純粋で、無垢で、彼と交流するうちに、セレガは未来への希望を取り戻す。
ところがある日、発情したセレガは男と関係を持ってしまって……?
オメガバースの設定をお借りしています。
ムーンライトノベルズにも掲載中

こじらせΩのふつうの婚活
深山恐竜
BL
宮間裕貴はΩとして生まれたが、Ωとしての生き方を受け入れられずにいた。
彼はヒートがないのをいいことに、ふつうのβと同じように大学へ行き、就職もした。
しかし、ある日ヒートがやってきてしまい、ふつうの生活がままならなくなってしまう。
裕貴は平穏な生活を取り戻すために婚活を始めるのだが、こじらせてる彼はなかなかうまくいかなくて…。

【完結】幼馴染から離れたい。
June
BL
隣に立つのは運命の番なんだ。
βの谷口優希にはαである幼馴染の伊賀崎朔がいる。だが、ある日の出来事をきっかけに、幼馴染以上に大切な存在だったのだと気づいてしまう。
番外編 伊賀崎朔視点もあります。
(12月:改正版)

初心者オメガは執着アルファの腕のなか
深嶋
BL
自分がベータであることを信じて疑わずに生きてきた圭人は、見知らぬアルファに声をかけられたことがきっかけとなり、二次性の再検査をすることに。その結果、自身が本当はオメガであったと知り、愕然とする。
オメガだと判明したことで否応なく変化していく日常に圭人は戸惑い、悩み、葛藤する日々。そんな圭人の前に、「運命の番」を自称するアルファの男が再び現れて……。
オメガとして未成熟な大学生の圭人と、圭人を番にしたい社会人アルファの男が、ゆっくりと愛を深めていきます。
穏やかさに滲む執着愛。望まぬ幸運に恵まれた主人公が、悩みながらも運命の出会いに向き合っていくお話です。本編、攻め編ともに完結済。

花婿候補は冴えないαでした
一
BL
バース性がわからないまま育った凪咲は、20歳の年に待ちに待った判定を受けた。会社を経営する父の一人息子として育てられるなか結果はΩ。 父親を困らせることになってしまう。このまま親に従って、政略結婚を進めて行こうとするが、それでいいのかと自分の今後を考え始める。そして、偶然同じ部署にいた25歳の秘書の孝景と出会った。
本番なしなのもたまにはと思って書いてみました!
※pixivに同様の作品を掲載しています

僕の番
結城れい
BL
白石湊(しらいし みなと)は、大学生のΩだ。αの番がいて同棲までしている。最近湊は、番である森颯真(もり そうま)の衣服を集めることがやめられない。気づかれないように少しずつ集めていくが――
※他サイトにも掲載


既成事実さえあれば大丈夫
ふじの
BL
名家出身のオメガであるサミュエルは、第三王子に婚約を一方的に破棄された。名家とはいえ貧乏な家のためにも新しく誰かと番う必要がある。だがサミュエルは行き遅れなので、もはや選んでいる立場ではない。そうだ、既成事実さえあればどこかに嫁げるだろう。そう考えたサミュエルは、ヒート誘発薬を持って夜会に乗り込んだ。そこで出会った美丈夫のアルファ、ハリムと意気投合したが───。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















