13 / 18
第五章
再来 ……2
しおりを挟む
映画の後はふだんと変わりなく会話して、食事して雑多な店が並ぶ街をぶらついた。翌日の予定も考えて早めに切り上げることにし、電車で地元まで戻ってきた。
結局、梶山は水沢遙香について多くを語らなかった。彼女を責める言葉はひとつも漏らさない。
反射神経が鈍ったのかな、と梶山は苦笑した。まさか真っ昼間に歩きながら居眠りでもしてたわけでもあるまいし、あんな無様な落ちかたをするなんてな。
「俺の不注意だったんだ」
梶山は言った。「彼女には迷惑をかけたよ」
無理に訊き出すのはよくない気がして、あえて修哉も梶山が話す事情だけを黙って聞いていた。
改札を出たところで梶山が立ち止まる。スマートフォンの通知を確認している。
見慣れた駅の風景はどこか安心する。同時に帰宅するだけとなり、早くも一日の終わりを実感して名残惜しい気持ちも入り混じる。
最近は日も短くなって、暗くなる時刻も早まっている。日中は日差しも強く、いまだに酷暑が続く。それでもすこしずつ季節は移り変わる。どこか遠くでヒグラシの声が繰り返すのが聞こえる。晩夏の夕暮れ時のもの悲しさが漂う。
日が傾いて夕焼け空が広がる。
「慎がこの辺車転がしてるから、迎えに来るってさ。おまえも乗ってくか?」
過保護だな、と笑いつつ返答する。「いや、ちょっと寄りたいところがあるから遠慮するよ」
そうか、と梶山はあっさり引き下がる。
駅前のロータリーにやってきた慎の車に梶山が乗り込むのを見届け、修哉は自宅方向と逆の商店街へと足を向けた。在庫を切らしていた印刷用紙を購入し、店を出たところで背後から声をかけられた。
「お兄さん、ちょっと時間ある?」
聞き覚えのある声だった。振り返ると、そこには水沢遙香――いや、マサキがいた。
暮色に染まりはじめた街の風景と雑踏を背景に、マサキは人懐こく魅力的な笑顔を向けてくる。
周囲から浮かび上がるような印象を受けた。どことなく浮世離れした雰囲気を漂わせる。
駅前なのに、こちら側の公道はほぼ歩行者専用と化していて、帰宅する人通りで混雑している。なかなか下がりきらない日中からの気温に疲労し、汗を拭きながらうんざりした顔をして歩く人々。
一方でマサキはひとり、気温の違う世界に立っているように見えた。髪をひとつにくくり、いまから就活に行くかのような真っ白なシャツを二の腕までまくり、黒のスラックスと底の低い革靴の姿。髪からか服からなのか、爽やかな芳香が匂う。
修哉は返す言葉を見失い、詰まった。
「……」
なんと返せばいいかわからなかった。
「昼間に妹と会ったでしょ。たぶんもう会う機会もないだろうから、ストーカーみたいな真似しちゃいました」
えへへ、とばつが悪そうにマサキが笑う。
「もしかして、あれからずっと後をつけてた……んですか」
「一度、探偵のアルバイトってのをやってみたくて」
彼女は顔をやや横に倒し、こめかみのあたりを掻いてなんとかごまかそうとしている。「面白そうでしょ、バレずに追跡するってやつ」
修哉は小さく肩をすくめた。
「まったく気づかなかった」
だれかが後をついてくるなんて考えもしなかった。この暑いなか、ずっと尾行してたのだとすれば、よほど用事があるのか単にヒマなのか。
修哉は疑問に思った。だけど、梶山に声をかけるならまだしも――
「なんでオレに?」
「梶山さんには会いたくないって言うもんだから。顔合わせづらいでしょ」
不可思議な言い回しをする。修哉は目をしばたいた。
「……?」
「私、お兄さんとちょっと話がしてみたいと思ったんですよ」
あたし、ではなく、わたし、と意図的にはっきりと発音した。
来て、と半袖の端をつままれる。小さな子どもの力ほどでしかなく、引っ張られてもこの身長差では微塵も動かせない。
「どこ行くんだよ」
マサキは、ぱっと振り向いた。「実はここらの土地勘、ないんですよね」
うーん、と考える。目尻を下げ、輝くような笑顔を向けてくる。
「どっか、いいとこあります? おごります」
あ、でも、とちょっと顔を曇らせる。「手持ちが少ないんで、できるかぎりあんまり高くないとこで。ごめんね」
表情がくるくると変わる。顔を見なければ、少年にも聞こえる中性的な声。
「オレもきみに訊きたいことがあるんだ。なんか訳ありっぽいし」
よかった、と安堵の笑顔を向けられる。「梶山さんの話題によく出てきたひとって、お兄さんだよね」
梶山が、オレのことをマサキに話した? いったいどういう経緯でそんな話題になるんだろう。
「ってか、お兄さんはやめてくれないかな。きみは梶山と同学年だろ?」
うん、と頷く。楽しそうに笑う。「背が高いから、てっきり年上かと思った」
なんだよそれ、と内心で思った。老けてるとでもいいたいのかな、と少しばかり不満が込み上げる。
「梶山と同じなら、オレともタメだろ」
そこまで言って、まだ名乗ってなかったことに気づいた。「オレの名は碓氷」
「碓氷……さん」
ちょっと間が空く。「碓氷さん、下の名前は?」
下の名まで、わざわざ確かめられるとは思っていなかった。不思議に思いながらも答える。
「修哉」
そう、とマサキが記憶に刻む目になる。
「僕は水沢マサキ。真っ直ぐに咲くと書いて、真咲」
よろしくね、と人懐こい笑みとともに、真咲は言った。
結局、梶山は水沢遙香について多くを語らなかった。彼女を責める言葉はひとつも漏らさない。
反射神経が鈍ったのかな、と梶山は苦笑した。まさか真っ昼間に歩きながら居眠りでもしてたわけでもあるまいし、あんな無様な落ちかたをするなんてな。
「俺の不注意だったんだ」
梶山は言った。「彼女には迷惑をかけたよ」
無理に訊き出すのはよくない気がして、あえて修哉も梶山が話す事情だけを黙って聞いていた。
改札を出たところで梶山が立ち止まる。スマートフォンの通知を確認している。
見慣れた駅の風景はどこか安心する。同時に帰宅するだけとなり、早くも一日の終わりを実感して名残惜しい気持ちも入り混じる。
最近は日も短くなって、暗くなる時刻も早まっている。日中は日差しも強く、いまだに酷暑が続く。それでもすこしずつ季節は移り変わる。どこか遠くでヒグラシの声が繰り返すのが聞こえる。晩夏の夕暮れ時のもの悲しさが漂う。
日が傾いて夕焼け空が広がる。
「慎がこの辺車転がしてるから、迎えに来るってさ。おまえも乗ってくか?」
過保護だな、と笑いつつ返答する。「いや、ちょっと寄りたいところがあるから遠慮するよ」
そうか、と梶山はあっさり引き下がる。
駅前のロータリーにやってきた慎の車に梶山が乗り込むのを見届け、修哉は自宅方向と逆の商店街へと足を向けた。在庫を切らしていた印刷用紙を購入し、店を出たところで背後から声をかけられた。
「お兄さん、ちょっと時間ある?」
聞き覚えのある声だった。振り返ると、そこには水沢遙香――いや、マサキがいた。
暮色に染まりはじめた街の風景と雑踏を背景に、マサキは人懐こく魅力的な笑顔を向けてくる。
周囲から浮かび上がるような印象を受けた。どことなく浮世離れした雰囲気を漂わせる。
駅前なのに、こちら側の公道はほぼ歩行者専用と化していて、帰宅する人通りで混雑している。なかなか下がりきらない日中からの気温に疲労し、汗を拭きながらうんざりした顔をして歩く人々。
一方でマサキはひとり、気温の違う世界に立っているように見えた。髪をひとつにくくり、いまから就活に行くかのような真っ白なシャツを二の腕までまくり、黒のスラックスと底の低い革靴の姿。髪からか服からなのか、爽やかな芳香が匂う。
修哉は返す言葉を見失い、詰まった。
「……」
なんと返せばいいかわからなかった。
「昼間に妹と会ったでしょ。たぶんもう会う機会もないだろうから、ストーカーみたいな真似しちゃいました」
えへへ、とばつが悪そうにマサキが笑う。
「もしかして、あれからずっと後をつけてた……んですか」
「一度、探偵のアルバイトってのをやってみたくて」
彼女は顔をやや横に倒し、こめかみのあたりを掻いてなんとかごまかそうとしている。「面白そうでしょ、バレずに追跡するってやつ」
修哉は小さく肩をすくめた。
「まったく気づかなかった」
だれかが後をついてくるなんて考えもしなかった。この暑いなか、ずっと尾行してたのだとすれば、よほど用事があるのか単にヒマなのか。
修哉は疑問に思った。だけど、梶山に声をかけるならまだしも――
「なんでオレに?」
「梶山さんには会いたくないって言うもんだから。顔合わせづらいでしょ」
不可思議な言い回しをする。修哉は目をしばたいた。
「……?」
「私、お兄さんとちょっと話がしてみたいと思ったんですよ」
あたし、ではなく、わたし、と意図的にはっきりと発音した。
来て、と半袖の端をつままれる。小さな子どもの力ほどでしかなく、引っ張られてもこの身長差では微塵も動かせない。
「どこ行くんだよ」
マサキは、ぱっと振り向いた。「実はここらの土地勘、ないんですよね」
うーん、と考える。目尻を下げ、輝くような笑顔を向けてくる。
「どっか、いいとこあります? おごります」
あ、でも、とちょっと顔を曇らせる。「手持ちが少ないんで、できるかぎりあんまり高くないとこで。ごめんね」
表情がくるくると変わる。顔を見なければ、少年にも聞こえる中性的な声。
「オレもきみに訊きたいことがあるんだ。なんか訳ありっぽいし」
よかった、と安堵の笑顔を向けられる。「梶山さんの話題によく出てきたひとって、お兄さんだよね」
梶山が、オレのことをマサキに話した? いったいどういう経緯でそんな話題になるんだろう。
「ってか、お兄さんはやめてくれないかな。きみは梶山と同学年だろ?」
うん、と頷く。楽しそうに笑う。「背が高いから、てっきり年上かと思った」
なんだよそれ、と内心で思った。老けてるとでもいいたいのかな、と少しばかり不満が込み上げる。
「梶山と同じなら、オレともタメだろ」
そこまで言って、まだ名乗ってなかったことに気づいた。「オレの名は碓氷」
「碓氷……さん」
ちょっと間が空く。「碓氷さん、下の名前は?」
下の名まで、わざわざ確かめられるとは思っていなかった。不思議に思いながらも答える。
「修哉」
そう、とマサキが記憶に刻む目になる。
「僕は水沢マサキ。真っ直ぐに咲くと書いて、真咲」
よろしくね、と人懐こい笑みとともに、真咲は言った。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が


就職面接の感ドコロ!?
フルーツパフェ
大衆娯楽
今や十年前とは真逆の、売り手市場の就職活動。
学生達は賃金と休暇を貪欲に追い求め、いつ送られてくるかわからない採用辞退メールに怯えながら、それでも優秀な人材を発掘しようとしていた。
その業務ストレスのせいだろうか。
ある面接官は、女子学生達のリクルートスーツに興奮する性癖を備え、仕事のストレスから面接の現場を愉しむことに決めたのだった。

カゲムシ
倉澤 環(タマッキン)
ホラー
幼いころ、陰口を言う母の口から不気味な蟲が這い出てくるのを見た男。
それから男はその蟲におびえながら生きていく。
そんな中、偶然出会った女性は、男が唯一心を許せる「蟲を吐かない女性」だった。
徐々に親しくなり、心を奪われていく男。
しかし、清らかな女性にも蟲は襲いかかる。

【短編】親子のバトン
吉岡有隆
ホラー
ー母親は俺に小説を書いて欲しいと言ったー
「俺の母親は昔、小説家になりたかったらしい」この言葉から始まる、小説書きの苦悩を書き綴った物語。
※この作品は犯罪描写を含みますが、犯罪を助長する物ではございません。
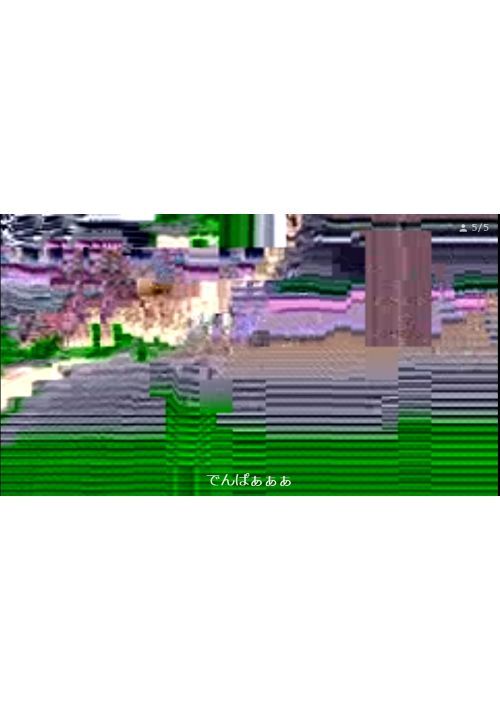

COME COME CAME
昔懐かし怖いハナシ
ホラー
ある部屋へと引っ越した、大学生。しかし、数ヶ月前失踪した女が住んでいた部屋の隣だった。
何故か赤い壁。何があるのだろうか。
そして、笑い声は誰のだろうか。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















